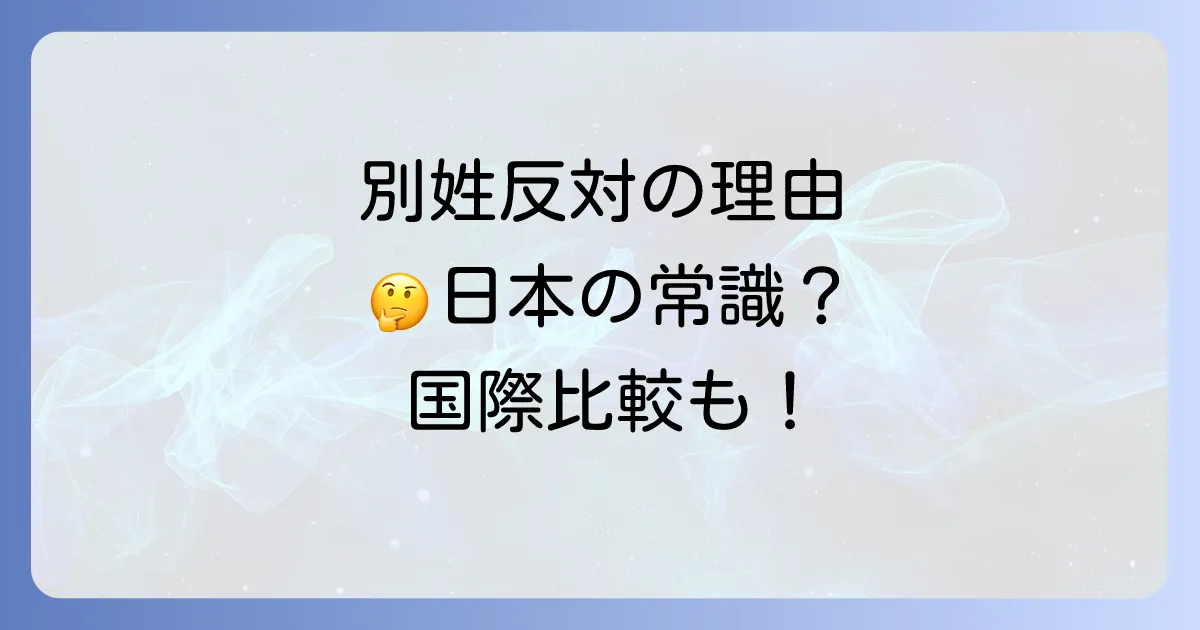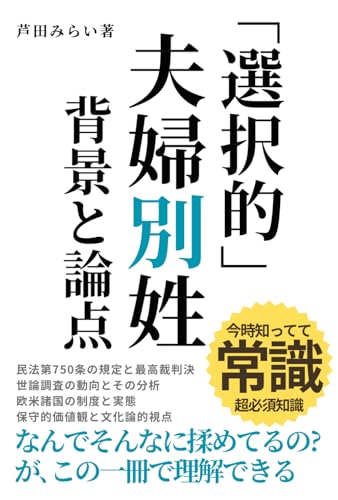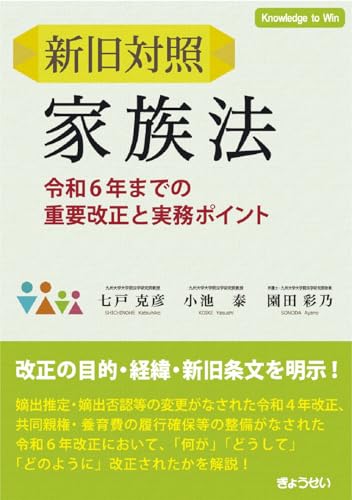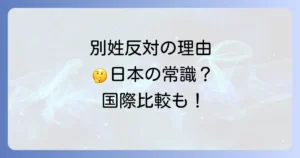結婚という人生の大きな節目において、夫婦の姓をどうするかは、多くの人にとって重要な問題です。日本では現在、夫婦のどちらかが姓を変える「夫婦同姓」が原則とされていますが、近年では「選択的夫婦別姓」の導入を求める声が高まっています。しかし、その一方で、制度導入に反対する意見も根強く存在し、特に外国人との関連性において、その議論はさらに複雑さを増しています。
本記事では、選択的夫婦別姓制度に反対する主な理由を深掘りし、国際結婚における姓の扱いや、外国人から見た日本の制度に対する視点についても詳しく解説します。この問題について多角的に理解を深めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
選択的夫婦別姓とは?制度の基本を理解する
選択的夫婦別姓制度は、夫婦が結婚後もそれぞれが結婚前の姓を名乗ることを選択できる制度です。現在の日本では、民法第750条により、結婚する夫婦は夫または妻のどちらかの姓を選び、同じ姓を称することが義務付けられています。この制度は、個人の尊厳や多様な家族のあり方を尊重する観点から、その導入が長年議論されてきました。
選択的夫婦別姓の定義と現状
「選択的夫婦別姓制度」とは、夫婦が希望すれば、結婚後もそれぞれが結婚前の姓(氏)を名乗ることを認める制度を指します。これはあくまで「選択的」な制度であり、夫婦が同じ姓を名乗ることを望む場合は、これまで通りどちらかの姓で婚姻することも可能です。
現行の民法では、婚姻に際して夫婦のいずれか一方の氏を選び、同じ氏を称することが義務付けられています。これにより、結婚を機にどちらかが必ず改姓しなければならず、実際には多くのケースで女性が男性の姓に改めることが大半を占めているのが現状です。
選択的夫婦別姓制度が導入されれば、夫婦で同じ姓にすることも、希望する場合にはお互いが自分の旧姓をそのまま使い続けることもできるようになります。これは、多様な価値観や生き方を法制度に反映させ、家族観の多様化や社会のニーズに即した法制度へと進化させるものと考えられています。
夫婦同姓原則の背景と歴史
日本における夫婦同姓の原則は、1898年に施行された明治民法にその起源があります。この法律では、結婚した夫婦は必ず同じ姓を名乗ることが定められました。この制度は、当時の「家制度」に基づいており、妻は夫の家に入り、その家の姓を名乗ることが求められたのです。
しかし、夫婦が同姓を名乗ることは、はたして本当に「伝統」なのでしょうか。実は、一人ひとりに姓が必要だと国が気づき、姓を名乗ることを義務付けたのは、ここ100年ちょっとの話に過ぎません。明治民法によって夫婦同姓のベースとなる「夫婦同氏」の原則が定められ、妻が婚姻によって夫の「家」に入ること、妻が夫の姓になるというルールができたのです。
この制度は、戦後の民法改正で家制度が廃止された後も、夫婦同姓の原則として維持されてきました。しかし、世界的に見ると、夫婦同姓を義務付けている国は日本だけという状況であり、国際社会からは「女性差別」として見直しの勧告を受けています。
選択的夫婦別姓に反対する主な理由
選択的夫婦別姓制度の導入には、さまざまな反対意見が存在します。これらの意見は、主に家族のあり方、子供への影響、伝統の尊重、そして制度運用上の懸念に集約されます。反対派は、制度導入が社会に大きな負の影響をもたらすと考えているのです。
家族の一体感の喪失への懸念
選択的夫婦別姓に反対する理由として、最も多く挙げられるのが「家族の一体感が失われる」という懸念です。同じ姓を名乗ることで、家族としての絆やまとまりが強まると考えられており、姓が異なることでその一体感が損なわれるのではないかという不安があります。
特に、男性から発せられるこの主張には、「妻が同じ姓であることで、自分のものになったように感じられる」といった心理が含まれていると指摘する声もあります。名字を共有することで、「一家の長としての立場」や「家庭を統べる存在としての自己イメージ」が保たれるという感覚が無意識のうちにあるのかもしれません。
しかし、家族の絆や一体感は、姓が同じであることだけで決まるものでしょうか。夫婦別姓の家庭で育った人の中には、「同じ空間で生活し、家族の一体感があった。幸せな人生」と語る人もいます。
子供の姓と教育への影響
子供の姓に関する問題も、反対理由として強く主張されています。選択的夫婦別姓が導入された場合、子供の姓をどうするのかという新たな課題が生じます。親と異なる姓を名乗ることで、子供がいじめの対象になったり、精神的な混乱を招いたりするのではないかという懸念が示されています。
しかし、再婚や国際結婚、事実婚など、すでに親子別姓で暮らしている家族は少なくありません。そうした子供たちを全て「別姓親子だからかわいそう」と決めつけるのは偏見ではないかという反論もあります。親と姓が同じかどうかで、子供の幸せが決まるものではないという意見も多く聞かれます。
また、選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも、子供の姓は夫婦の協議によって決めることになります。これは、子供の下の名前を決めるのと同様に、夫婦で話し合って決定するものであり、いつまでも決まらないという事態は想定しにくいと考えられています。
伝統的な家族観と文化の尊重
「伝統的な家族のあり方を守るべきだ」「別姓を許せば日本古来の家族のあり方が失われる」という意見も、選択的夫婦別姓に反対する大きな理由の一つです。夫婦同姓は日本の伝統であり、これを維持することが日本の文化や社会の安定に繋がるという考え方です。
しかし、夫婦同姓が日本の「伝統」であるかについては、歴史的な議論があります。明治民法以前の庶民には姓を持つことが許されていなかった時代もあり、夫婦同姓が一般化したのは近代以降のことです。
また、反対派は、選択的夫婦別姓の導入が、戸籍制度の解体や、ひいては皇室のあり方、社会のあり方までも変えてしまうのではないかという漠然とした不安を抱いているとも指摘されています。
戸籍制度の混乱と行政コストの増大
選択的夫婦別姓制度の導入は、戸籍制度に混乱をもたらし、行政コストを増大させるという懸念も示されています。姓が異なる夫婦が増えることで、行政手続きが煩雑になったり、個人を特定するシステムに支障が生じたりするのではないかという意見です。
しかし、日本弁護士連合会の渕上玲子会長は、「選択的夫婦別姓制度ができても、戸籍制度は問題なく維持される」と指摘しています。 制度設計によっては、混乱を最小限に抑えることが可能であると考えられます。
また、現在の夫婦同姓制度においても、改姓に伴う運転免許証、パスポート、銀行口座、国家資格などの名義変更手続きは、個人にとっても行政にとっても大きな負担となっています。選択的夫婦別姓が導入されれば、これらの手続きが不要となり、むしろ行政コストの軽減に繋がる可能性もあります。
旧姓通称使用で十分という意見
選択的夫婦別姓に反対する意見の中には、「結婚後も旧姓を通称使用することで、実質的な不利益は解消されるため、新たな制度は不要である」という主張もあります。
確かに、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できる制度はありますが、これはあくまで「通称使用」であり、法的な姓は変更されたままです。
旧姓通称使用では、公的な書類や契約など、重要な場面で戸籍上の姓と通称の姓が異なることによる不便や混乱が生じる可能性があります。例えば、外国政府や企業との間で審査や取引を行う際、パスポートの名前とその他の書類の名前が食い違うケースが多発し、信用を失うことにもつながりかねないという指摘もあります。
外国人から見た選択的夫婦別姓問題と反対理由の関連性
選択的夫婦別姓の議論は、日本人同士の結婚だけでなく、国際結婚においても重要な意味を持ちます。多くの国で夫婦別姓が一般的である中、日本の夫婦同姓原則は、外国人から見るとどのように映るのでしょうか。ここでは、国際結婚における姓の選択肢や、外国人から見た日本の制度、そして反対理由との関連性について掘り下げます。
国際結婚における姓の選択肢と現状
日本人同士の結婚では夫婦同姓が義務付けられている一方で、国際結婚の場合、原則として夫婦別姓を選択することが可能です。これは、外国人には日本の戸籍が作られないことに起因します。
国際結婚では、日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更することも、自分の姓を維持することも、あるいは複合姓を選択することもできます。婚姻届を提出後、特に手続きを行わなければ夫婦別姓の状態となりますが、結婚から6ヶ月以内であれば市町村役場に「氏の変更届」を提出することで、外国人配偶者の姓に変更することも可能です。6ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。
この柔軟な選択肢は、日本人同士の結婚における姓の選択の自由がない現状と対照的であり、選択的夫婦別姓制度の必要性を訴える根拠の一つにもなっています。
外国籍配偶者の姓の扱いと日本の制度
外国籍の配偶者は日本の戸籍に登録されないため、その姓は日本の夫婦同姓原則の対象外となります。日本人の配偶者が外国人配偶者の姓を名乗る場合、その姓は日本の戸籍には反映されず、あくまで「通称」として扱われることがあります。
この状況は、外国人配偶者から見ると、日本の制度が自国の文化や慣習と大きく異なるため、困惑や不便を感じる原因となることがあります。例えば、自国では夫婦別姓が当たり前であるにもかかわらず、日本で生活する上で日本人配偶者との姓の統一を求められる場面に遭遇する可能性もゼロではありません。
また、外国人配偶者が日本に帰化して日本国籍を取得した場合、日本の戸籍に入ることになり、その際に夫婦同姓の原則が適用されます。この場合、日本人配偶者と同じ姓にするか、あるいは日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更するかを選択することになります。
諸外国の夫婦別姓制度と日本の比較
世界的に見ると、夫婦同姓を法律で強制している国は、把握する限り日本だけです。多くの国では、夫婦別姓が原則であったり、夫婦が同姓・別姓・複合姓を自由に選択できる制度が導入されています。
例えば、ドイツでは1991年の法改正により、夫婦が共通の姓を使用するか旧姓を保持するかを選択できるようになりました。別姓のままの夫婦も一般的な家族の形として受け入れられています。アメリカやイギリスでも、社会的な慣習や州ごとの手続きの違いはあるものの、夫婦が自由に姓を選べる制度が整っています。
韓国や中国、ベトナムなど、歴史的に血縁を重んじる傾向が強い国では、伝統的に夫婦別姓が原則です。 このように、国際的な視点から見ると、日本の夫婦同姓強制は特異な制度であり、国連の女性差別撤廃委員会からも見直しを求める勧告が繰り返し出されています。
外国人の視点から見た反対理由への疑問
選択的夫婦別姓に反対する理由として挙げられる「家族の一体感の喪失」や「子供への悪影響」といった意見は、夫婦別姓が一般的な国の人々から見ると、疑問に感じられることがあります。
例えば、ドイツでは親同士も親子も姓が違うのが普通であり、家族の絆が壊れるといった問題は生じていません。 また、父親が外国人であり、父母の姓が異なる家庭で育った人の中には、「家族に絆を感じるし、別姓が理由で何か悪影響があったとは全く感じていない」と語る人もいます。
このように、海外の事例や当事者の声は、日本の反対派が抱く懸念が必ずしも現実的ではないことを示唆しています。多様な家族のあり方が存在する現代において、姓の選択が家族の絆を左右するという考え方は、国際的な視点から見ると時代遅れと捉えられる可能性もあるでしょう。
選択的夫婦別姓の導入を求める賛成派の主な意見
選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、個人の尊厳、ジェンダー平等、そして現代社会における多様な生き方を尊重する観点から高まっています。反対意見がある一方で、制度導入には多くのメリットがあると考えられています。
個人の尊厳とジェンダー平等の実現
賛成派が最も重視する理由の一つは、個人の尊厳とジェンダー平等の実現です。現在の夫婦同姓制度では、結婚する際に夫婦のどちらかが必ず姓を変えなければならず、その多くは女性が男性の姓に改めることになります。
これにより、「長年使ってきた自分の姓を失うことへの自己喪失感」や「姓を選べないことによる不自由さ」を感じる人が少なくありません。 選択的夫婦別姓制度は、このような個人の意思を尊重し、性別に関わらず自分の姓を維持する自由を保障することで、より平等な社会の実現に貢献すると考えられています。
国連の女性差別撤廃委員会も、日本の夫婦同姓規定を「差別的規定」であるとして、見直しを求める勧告を繰り返し出しています。 選択的夫婦別姓の導入は、国際的な人権基準にも合致する動きと言えるでしょう。
キャリア上の不利益解消と社会活動の円滑化
結婚による改姓は、特に女性のキャリア形成において大きな不利益をもたらすことがあります。旧姓で築き上げてきた実績や信用が、改姓によって途切れてしまうという問題です。
例えば、医師や弁護士、研究者など、専門職として活動してきた女性にとって、姓が変わることは、これまでの実績が認識されにくくなったり、名義変更の手続きに多大な時間と労力がかかったりする原因となります。 企業経営者の中にも、選択的夫婦別姓の導入が女性活躍推進のために不可欠であると訴える声が多く聞かれます。
選択的夫婦別姓が導入されれば、改姓に伴う煩雑な手続きが不要となり、キャリア上の不利益が解消されます。これにより、女性が結婚後も安心して社会活動を続けられるようになり、社会全体の生産性向上にも繋がると期待されています。
よくある質問
- 選択的夫婦別姓とは何ですか?
- 選択的夫婦別姓のメリットは何ですか?
- 選択的夫婦別姓のデメリットは何ですか?
- 夫婦別姓は世界でどれくらい導入されていますか?
- 選択的夫婦別姓が導入されない理由は何ですか?
- 選択的夫婦別姓で子供の姓はどうなりますか?
- 外国人と結婚した場合、姓はどうなりますか?
選択的夫婦別姓とは何ですか?
選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が結婚後もそれぞれが結婚前の姓を名乗ることを選択できる制度です。現在の日本では、夫婦は結婚時にどちらかの姓を選んで統一することが義務付けられています。この制度が導入されれば、夫婦で同じ姓を選ぶことも、別々の姓を名乗り続けることも、自由に選択できるようになります。
選択的夫婦別姓のメリットは何ですか?
選択的夫婦別姓のメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。個人の自由と尊厳が尊重され、結婚によって姓を変えることによる自己喪失感が解消されます。また、改姓に伴う運転免許証や銀行口座などの名義変更手続きの負担が軽減され、特に女性のキャリア形成における不利益が解消されることで、社会活動が円滑になります。さらに、多様な家族の形に対応できるようになり、国際社会との調和も図られます。
選択的夫婦別姓のデメリットは何ですか?
選択的夫婦別姓のデメリットとしては、反対派から「家族の一体感が薄れる」「子供の姓をどうするかで混乱が生じる」「伝統的な家族観が失われる」といった点が指摘されています。また、制度導入による戸籍制度の混乱や行政コストの増大を懸念する声もあります。しかし、これらのデメリットについては、制度設計や社会の理解によって解消できるという反論も多くあります。
夫婦別姓は世界でどれくらい導入されていますか?
夫婦同姓を法律で強制している国は、把握する限り日本だけです。世界中の多くの国では、夫婦別姓が原則であったり、夫婦が同姓・別姓・複合姓を自由に選択できる制度が導入されています。例えば、ドイツ、アメリカ、イギリス、スウェーデン、韓国、中国など、多くの国で夫婦別姓が認められています。
選択的夫婦別姓が導入されない理由は何ですか?
選択的夫婦別姓が導入されない主な理由としては、伝統的な家族観を重視する保守派の根強い反対意見、家族の一体感が失われることへの懸念、子供への影響を心配する声などが挙げられます。また、政治的な要因や、制度導入に対する国民の幅広いコンセンサスが得られていないという意見も背景にあります。
選択的夫婦別姓で子供の姓はどうなりますか?
選択的夫婦別姓制度が導入された場合、子供の姓については、夫婦が結婚時に協議して定めることが提案されています。例えば、法務省の案では、別姓を選択する夫婦は結婚時に子供の姓を定め、兄弟姉妹の姓は一致することになります。また、出生時に父母の協議で決める案もあり、この場合は兄弟姉妹で姓が異なる可能性もあります。
外国人と結婚した場合、姓はどうなりますか?
日本人が外国人と結婚した場合、原則として夫婦別姓を選択することが可能です。婚姻届を提出後、特に手続きを行わなければ夫婦別姓のままとなります。日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更することも、自分の姓を維持することも、あるいは複合姓を選択することもできます。結婚から6ヶ月以内であれば市町村役場に「氏の変更届」を提出することで、外国人配偶者の姓に変更することも可能です。
まとめ
- 選択的夫婦別姓は結婚後も各自の姓を名乗れる制度。
- 現行法では夫婦同姓が義務付けられている。
- 反対理由には家族の一体感喪失への懸念がある。
- 子供の姓や教育への影響も反対理由の一つ。
- 伝統的な家族観の尊重を求める声も根強い。
- 戸籍制度の混乱や行政コスト増大を懸念する意見もある。
- 旧姓通称使用で十分という主張もある。
- 国際結婚では原則として夫婦別姓が選択可能。
- 外国籍配偶者の姓の扱いは日本の制度と異なる。
- 多くの国では夫婦別姓が一般的または選択可能。
- 外国人の視点から反対理由への疑問も呈されている。
- 賛成派は個人の尊厳とジェンダー平等を重視。
- キャリア上の不利益解消も賛成の大きな理由。
- 国連は日本の夫婦同姓規定を見直すよう勧告。
- 多様な家族のあり方に対応する社会の実現が求められる。
新着記事