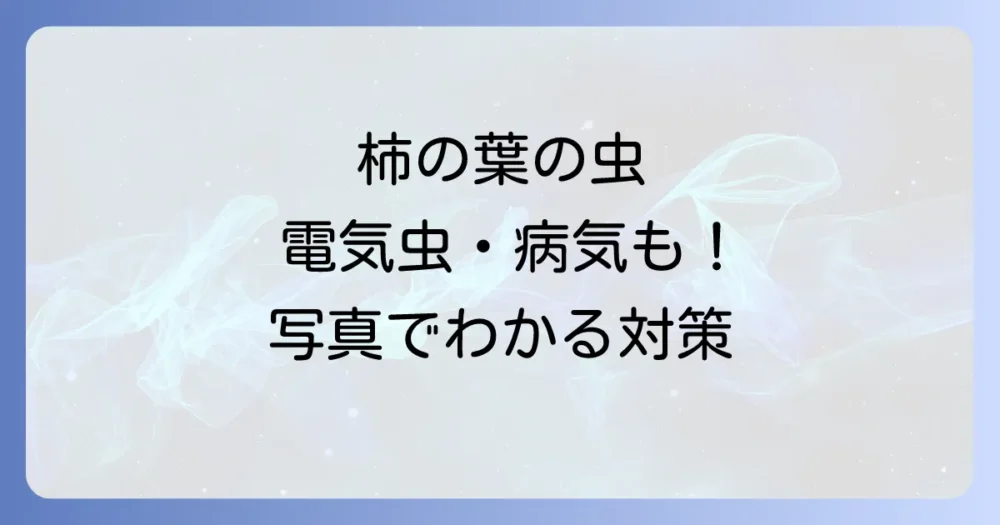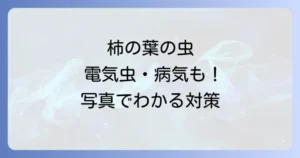大切に育てている柿の木。ふと見ると、葉に見慣れない虫がついていたり、黒い斑点ができていたりして、不安になった経験はありませんか?「この虫は何だろう?」「どうやって駆除すればいいの?」「柿の実は無事に育つの?」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。柿の木を健やかに保ち、美味しい実を収穫するためには、害虫や病気への早期発見と適切な対処が欠かせません。本記事では、柿の葉によくつく代表的な害虫の種類から、それぞれの駆除・予防法、そして虫の被害と間違いやすい病気の症状まで、写真付きで詳しく解説します。この記事を読めば、あなたも柿の木のトラブルに的確に対処できるようになるはずです。
【要注意】柿の葉によくつく代表的な害虫5選と駆除方法
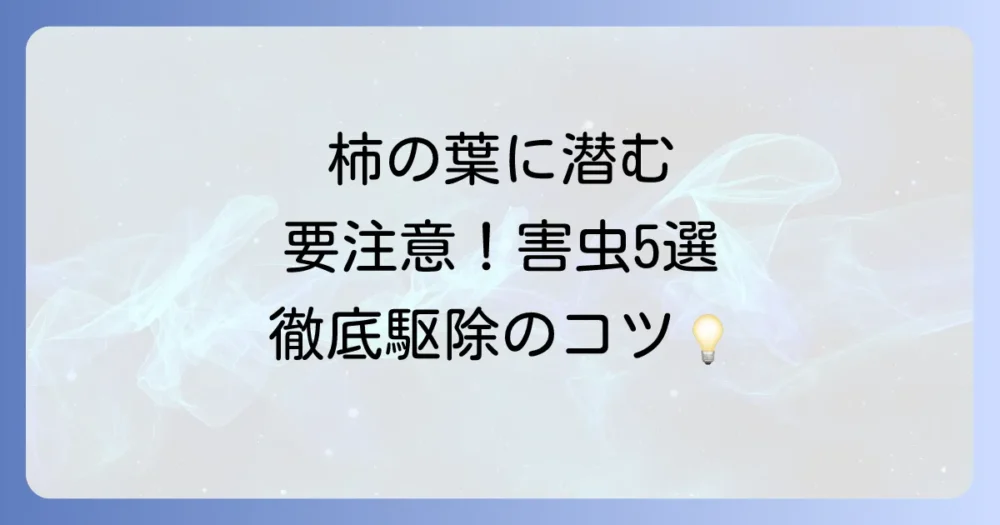
柿の木には様々な虫がつきますが、特に被害が大きく、注意が必要な代表的な害虫がいます。まずは、よく見かける5種類の害虫の特徴と、それぞれの対策をしっかりと把握しましょう。早期発見が、被害を最小限に食い止めるための第一歩です。
- イラガ(電気虫)
- カキノヘタムシガ(ヘタムシ)
- カイガラムシ類
- ハマキムシ類
- ハダニ類
イラガ(電気虫)
柿の葉の裏に、鮮やかな緑色で奇妙な形の毛虫がびっしり…それはイラガの幼虫かもしれません。見た目のインパクトもさることながら、その毒針による被害は強烈で、庭仕事をする際には最も注意したい害虫の一つです。
特徴と被害
イラガの幼虫は、体中に毒のあるトゲ(毒針毛)を持っています。 このトゲに触れると、電気が走ったような激しい痛みに襲われることから、「電気虫」とも呼ばれています。 痛みは数時間から、場合によっては翌日まで続くこともあり、アレルギー反応を引き起こす可能性もあるため、絶対に素手で触ってはいけません。 幼虫は集団で発生し、葉の裏側から葉脈を残してレース状に食害するのが特徴です。 放置すると、あっという間に葉を食べ尽くされてしまい、木の生育に大きな影響を与えます。
発生時期
イラгаは種類によって異なりますが、主に年に1〜2回発生します。 幼虫は6月~7月と8月~9月頃によく見られます。 成虫のガは毒を持っていませんが、夜間に飛来して葉の裏に卵を産み付けます。 冬は枝や幹に硬くて丸い繭を作って越冬します。
駆除と対策
イラガの幼虫を見つけたら、すぐに駆除しましょう。幼虫がまだ小さく、集団で固まっている場合は、その葉ごと枝を切り取って処分するのが最も安全で確実な方法です。 駆除作業の際は、長袖、長ズボン、手袋、帽子、ゴーグルを着用し、肌の露出を避けてください。 広範囲に発生してしまった場合は、殺虫剤の使用が効果的です。イラガに適用のある園芸用殺虫剤を、説明書に従って散布しましょう。 冬の剪定時に、枝についている卵形の繭を見つけたら、ヘラなどで削ぎ落として駆除しておくことで、翌年の発生を抑えることができます。
カキノヘタムシガ(ヘタムシ)
柿の収穫を心待ちにしていたのに、実が大きくならずにポタポタと落ちてしまう…その原因は、カキノヘタムシガ、通称「ヘタムシ」の仕業かもしれません。この虫は柿の実に直接的な被害を与える、非常に厄介な害虫です。
特徴と被害
カキノヘタムシガは、その名の通り、幼虫が柿のヘタの部分から果実に食い入る害虫です。 食入された若い果実は、成長が止まってしまい、やがて落果してしまいます。 幼虫は一つの果実を食べ終えると、次の果実へと移動して加害を続けるため、被害が拡大しやすいのが特徴です。 収穫間近の果実が被害にあうと、早期に着色して軟化し、商品価値がなくなってしまいます。 柿だけを専門に加害する害虫で、成虫は体長8mmほどの小さな蛾です。
発生時期
カキノヘタムシガは年に2回発生します。 1回目の成虫は5月下旬~6月上旬、2回目の成虫は7月下旬~8月上旬に現れます。 幼虫が実に食い込むのは、孵化してから少し成長した3齢幼虫になってからです。 そのため、薬剤散布は幼虫が実に潜り込む前に行う必要があります。
駆除と対策
カキノヘタムシガの防除で最も重要なのは、冬の間の「粗皮削り」です。 幼虫は木の幹や枝の古い皮(粗皮)の下で繭を作って越冬するため、冬の休眠期にこの粗皮を削り落とすことで、越冬する幼虫の数を大幅に減らすことができます。 薬剤を使用する場合は、散布のタイミングが非常に重要です。幼虫が果実に侵入してしまうと効果がなくなるため、成虫の発生最盛期の約10日後を目安に散布します。 地域の病害虫防除所の発生予察情報などを参考に、適切な時期に防除を行いましょう。被害を受けて落果した実は、放置せずに集めて土に埋めるなどして処分することも、翌年の発生源を減らす上で効果的です。
カイガラムシ類
柿の枝や葉、果実の表面に、白や茶色の小さな貝殻のようなものが付着していたら、それはカイガラムシです。一見すると虫には見えませんが、れっきとした植物の汁を吸う害虫で、大量に発生すると木を弱らせるだけでなく、見た目にも大きな被害をもたらします。
特徴と被害
カイガラムシは、硬い殻やロウ物質で体を覆っているため、薬剤が効きにくいのが特徴です。 柿にはフジコナカイガラムシやクワシロカイガラムシなどが発生します。 これらの虫は植物の樹液を吸って生育を阻害するだけでなく、排泄物が「すす病」という病気を誘発します。 すす病になると、葉や果実が黒いすすで覆われたようになり、光合成が妨げられたり、果実の商品価値が著しく低下したりします。
発生時期
カイガラムシの種類によって発生サイクルは異なりますが、多くは年に複数回発生します。 例えばフジコナカイガラムシは年に3回発生し、幼虫や成虫の姿で木の皮の隙間などで越冬します。 幼虫が多く発生する6月下旬~7月上旬が、薬剤散布による防除の重要な時期となります。
駆除と対策
カイガラムシ対策でも、冬の「粗皮削り」が非常に有効です。 越冬している個体を物理的に取り除くことで、春先の発生密度を大きく下げることができます。発生してしまった場合は、幼虫の時期が最も薬剤が効きやすいため、このタイミングを狙って薬剤を散布します。 ただし、成虫になると薬剤が効きにくくなるため、歯ブラシやヘラなどで物理的にこすり落とす方法も有効です。この作業は、木を傷つけないように丁寧に行いましょう。カイガラムシは一度発生すると根絶が難しい害虫なので、地道な対策を続けることが大切です。
ハマキムシ類
柿の葉が不自然に巻かれていたり、糸で綴り合わされていたりしたら、それはハマキムシ類の幼虫の仕業です。葉を隠れ家にして内部から食害するため、見つけにくいのが特徴です。
特徴と被害
ハマキムシ類の幼虫は、その名の通り、葉を巻いたり、数枚の葉を糸で綴り合わせたりして巣を作ります。 幼虫はその巣の中に隠れながら、葉やヘタ、果実の表面を食害します。 被害を受けた果実は表面に食害の跡が残り、見た目が悪くなってしまいます。柿にはコカクモンハマキやチャハマキなど、複数の種類が発生します。
発生時期
ハマキムシ類は年に数回発生します。 例えばチャハマキは5月下旬、7月中旬、9月下旬に成虫が発生し、その後幼虫による被害が見られます。 幼虫は葉を巻いているため薬剤がかかりにくいという厄介な性質を持っています。
駆除と対策
ハマキムシの被害を見つけたら、巻いている葉ごと捕殺するのが最も確実な方法です。数が少ないうちは、この手作業での駆除をこまめに行いましょう。薬剤を散布する場合は、幼虫が葉の中に隠れていることを考慮し、薬剤が内部まで届くように丁寧に散布する必要があります。 発生初期に防除することが、被害を広げないためのポイントです。
ハダニ類
葉の色がなんとなく悪くなり、カスリ状に白っぽくなっている…そんな時は葉の裏をよく観察してみてください。非常に小さな赤い点のような虫が動いていたら、それはハダニかもしれません。
特徴と被害
ハダニは0.5mm程度の非常に小さな虫で、肉眼では確認しにくい害虫です。 葉の裏に寄生して汁を吸うため、被害を受けた葉は葉緑素が抜けて白いカスリ状の斑点ができ、やがて葉全体が白っぽくなります。 大量に発生すると光合成が阻害されて生育が悪くなり、ひどい場合には落葉することもあります。 高温で乾燥した環境を好むため、梅雨明けから夏にかけて特に発生が多くなります。
発生時期
ハダニは気温が上がる春から秋にかけて活動し、特に梅雨明け後の高温乾燥期(7月~9月)に繁殖がピークを迎えます。 世代交代が非常に早く、短期間で爆発的に増殖することがあるため注意が必要です。
駆除と対策
ハダニは水に弱いという性質があります。 そのため、発生初期であれば、ホースなどで葉の裏に勢いよく水をかける「葉水」をこまめに行うことで、数を減らすことができます。 また、ハダニは雑草で増殖してから柿の木に移動してくることもあるため、園内の除草を適切に行うことも予防につながります。 大量に発生してしまった場合は、ハダニに効果のある殺ダニ剤を散布します。薬剤抵抗性がつきやすい害虫なので、同じ系統の薬剤を連続して使用するのは避け、ローテーション散布を心がけましょう。
まだいる!柿の葉や実を狙うその他の害虫
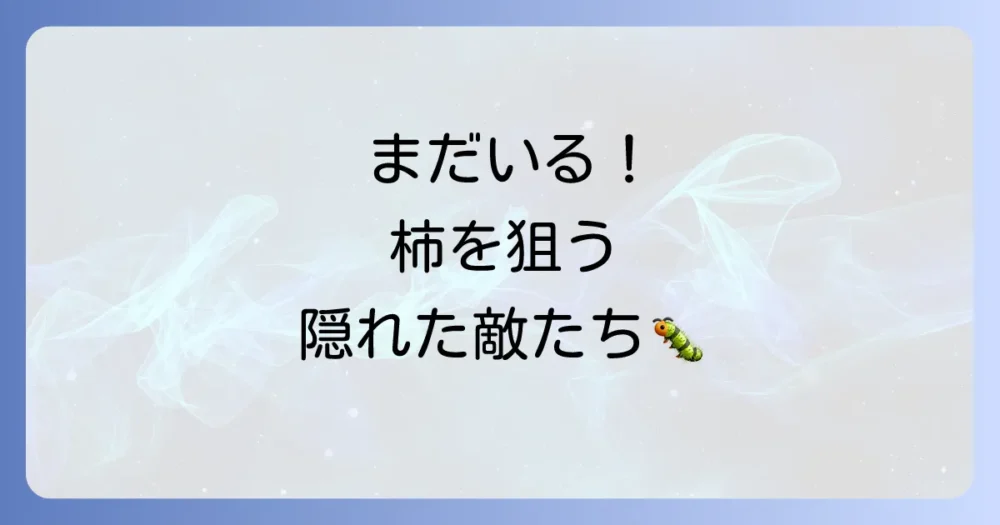
これまで紹介した5種類の他にも、柿には注意すべき害虫がいます。被害は局所的かもしれませんが、発生すると厄介なものばかりです。知識として知っておくことで、いざという時に落ち着いて対処できます。
- アブラムシ類
- カメムシ類
- ミノガ類(チャミノガなど)
- マイマイガ
アブラムシ類
新芽や若い葉に、緑色や黒色の小さな虫が群がっているのを見つけたら、それはアブラムシです。アブラムシは植物の汁を吸って生育を妨げるだけでなく、その排泄物がカイガラムシと同様に「すす病」の原因となります。 また、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第、早めに駆除することが大切です。数が少ないうちは粘着テープなどで取り除いたり、牛乳を薄めたスプレーを吹きかけたりする方法も有効です。大量に発生した場合は、アブラムシに適用のある殺虫剤を使用しましょう。
カメムシ類
カメムシは、柿の果実から汁を吸う害虫です。 被害を受けた果実は、吸われた部分がスポンジ状に変質したり、奇形になったり、早期に落果したりしてしまいます。特にチャバネアオカメムシやツヤアオカメムシなどが問題となります。 カメムシは周辺の山林や雑草地で繁殖し、柿園に飛来してくるため、園内だけでなく周辺の環境管理も重要になります。飛来してくるため、袋がけも有効な対策の一つです。薬剤散布は、カメムシが活発に活動する日暮れ前が効果的です。
ミノガ類(チャミノガなど)
葉や小枝で作った「蓑(みの)」をかぶって移動する姿でおなじみのミノムシも、柿の葉を食害します。 特にチャミノガは、柿の葉や果実を食害することがあります。 蓑をかぶっているため薬剤が効きにくいのが難点です。見つけ次第、手で取り除いて捕殺するのが最も確実な駆除方法です。 冬の間も枝にぶら下がって越冬しているので、剪定の際に一緒に取り除いておくと良いでしょう。
マイマイガ
マイマイガの幼虫(毛虫)は、非常に食欲旺盛で、柿の葉をはじめ様々な樹木の葉を食べ尽くしてしまいます。 大発生すると、木が丸裸にされてしまうほどの被害が出ることもあります。幼虫は春先(4月~5月)に卵からかえり、葉を食害します。 幼虫が小さいうちは集団で行動するので、その時期に葉ごと取り除いて駆除するのが効果的です。大きくなると分散してしまうため、見つけ次第捕殺するか、薬剤を散布して駆除します。
害虫対策の基本!効果的な駆除と予防法
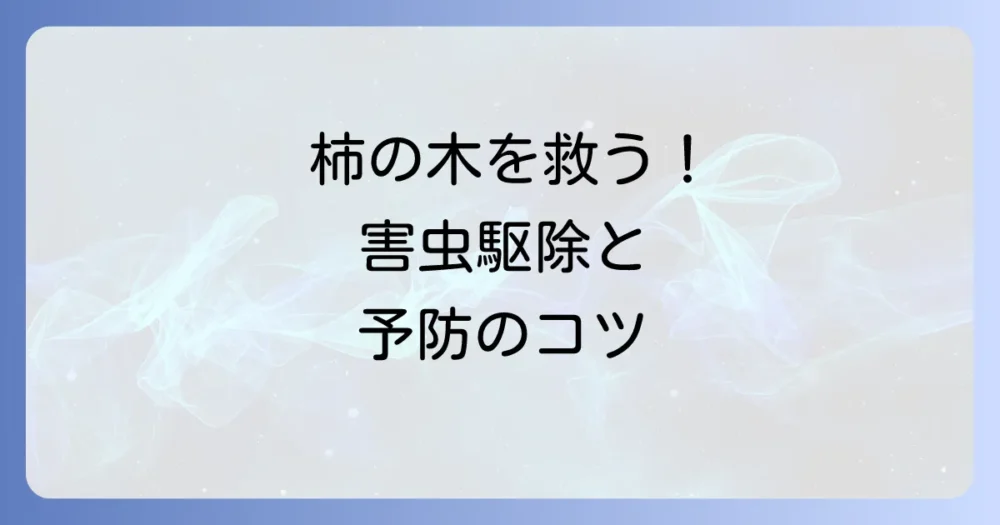
柿の木を害虫から守るためには、発生してからの駆除はもちろん、日頃からの予防が何よりも大切です。ここでは、薬剤を使った方法から、できるだけ農薬に頼らない方法、そして冬の間にできる重要な作業まで、害虫対策の基本を解説します。
- 薬剤(農薬)を使った駆除方法
- 農薬を使わない!無農薬での駆除・予防法
- 冬の間にできる重要な予防作業「粗皮削り」
薬剤(農薬)を使った駆除方法
害虫が大量に発生してしまった場合や、被害を確実に抑えたい場合には、薬剤(農薬)の使用が有効な手段となります。しかし、使い方を間違えると効果がなかったり、環境に影響を与えたりすることもあるため、正しく使うことが重要です。
薬剤選びのポイント
まず大切なのは、対象の害虫と、使用する作物(この場合は柿)に登録がある薬剤を選ぶことです。 農薬のラベルには、対象となる病害虫名や作物名、使用時期、希釈倍率などが詳しく記載されているので、必ず確認しましょう。 例えば、イラガには効果があってもカキノヘタムシガには効かない、といった薬剤もあります。自分の柿の木で発生している害虫に合ったものを選びましょう。
おすすめの薬剤
柿の害虫に広く使われる代表的な薬剤には、「スミチオン」などの有機リン系殺虫剤や、「ベニカベジフル乳剤」のような速効性と持続性を兼ね備えた薬剤などがあります。 最近では、天敵への影響が少ない薬剤や、自然由来成分の薬剤も増えています。ホームセンターやJAなどで相談し、自分の栽培スタイルに合った薬剤を選ぶと良いでしょう。
散布の時期と注意点
薬剤散布で最も重要なのはタイミングです。多くの害虫は、卵や成虫よりも幼虫の時期が薬剤が効きやすいです。 例えばカキノヘタムシガは、幼虫が果実に潜り込む前に散布しないと効果がありません。 地域の防除暦やJAの指導などを参考に、適切な時期に散布しましょう。 散布する際は、風のない穏やかな日を選び、マスクやゴーグル、手袋などを着用して、薬剤を吸い込んだり皮膚に付着したりしないよう十分に注意してください。 また、葉の裏など、害虫が潜んでいる場所にもしっかりと薬剤がかかるように丁寧に散布することが大切です。
農薬を使わない!無農薬での駆除・予防法
「家庭菜園なので、できるだけ農薬は使いたくない」と考える方も多いでしょう。無農薬で害虫を防ぐには、手間はかかりますが、いくつかの有効な方法があります。根気強く続けることが、健康な柿の木を育てる鍵となります。
物理的に取り除く
最も基本的で効果的なのが、害虫を見つけ次第、手で取り除くことです。イラガの幼虫が集まっている葉を切り取ったり、ハマキムシが巻いた葉を潰したり、ミノガを手で捕まえたりします。 この方法は、発生初期で数が少ない場合に特に有効です。こまめに木を観察する習慣をつけ、被害が広がる前に対応しましょう。
天敵を利用する
テントウムシがアブラムシを食べるように、害虫には天敵となる虫がいます。農薬、特に効果の強い合成ピレスロイド剤などを多用すると、害虫だけでなくこれらの天敵まで殺してしまい、かえって特定の害虫(カイガラムシやハダニなど)が異常発生することがあります。 薬剤の使用を最小限に抑え、多様な生き物が生息できる環境を保つことが、結果的に害虫の発生を抑制することにつながります。
木酢液など自然由来のものを活用する
木酢液や竹酢液を薄めて散布すると、その独特の匂いで害虫を寄せ付けにくくする効果が期待できます。また、土壌の微生物を活性化させる効果もあると言われています。ただし、これらは殺虫剤ではないため、直接的な駆除効果は限定的です。あくまで予防的な手段として、定期的に散布すると良いでしょう。使用する際は、規定の濃度に正しく薄めて使うことが大切です。
冬の間にできる重要な予防作業「粗皮削り」
冬の寒い時期、柿の木が葉を落として休眠している間に行う「粗皮削り」は、翌年の害虫発生を抑えるために非常に重要な作業です。一見地味な作業ですが、その効果は絶大です。
カキノヘタムシガやカイガラムシ類、その他の多くの害虫は、木の幹や太い枝のゴツゴツとした古い樹皮(粗皮)の下や隙間で冬を越します。 そこで、冬の間にヘラやワイヤーブラシなどを使ってこの粗皮を削り落とすことで、越冬中の害虫を物理的に駆除することができます。 これにより、春になって暖かくなった時に活動を始める害虫の数を大幅に減らすことができ、年間の薬剤散布の回数を減らすことにも繋がります。作業は、木が休眠している12月~2月頃に行うのが適期です。削り取った樹皮は、そのままにせず、集めて処分しましょう。
これって虫のせい?柿の葉に現れる病気のサイン
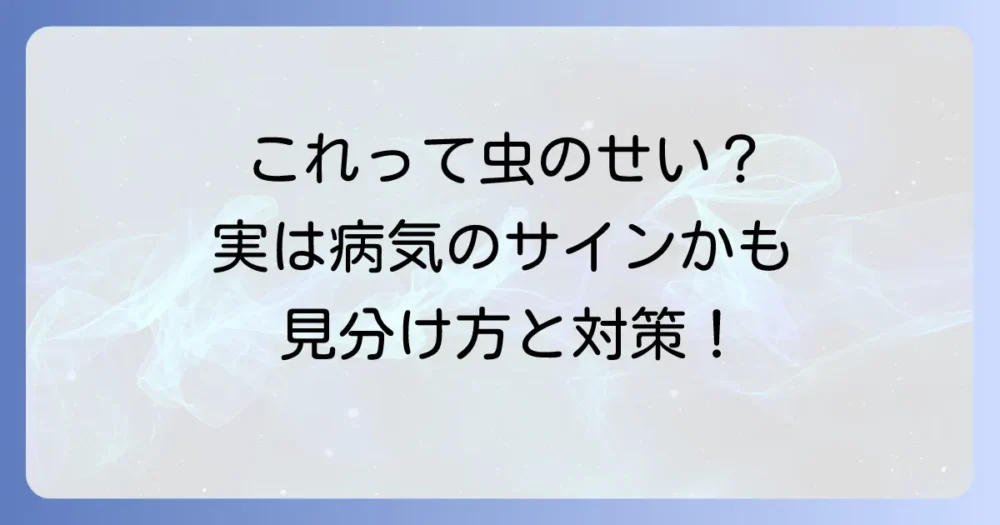
柿の葉の異変は、必ずしも虫が原因とは限りません。カビなどが原因で起こる「病気」の可能性もあります。害虫の被害と症状が似ていることもあるため、見分け方を知っておくことが適切な対処につながります。ここでは、柿によく見られる代表的な病気を紹介します。
- 葉に黒い斑点ができる「炭疽病」「落葉病」
- 葉が白い粉を吹いたようになる「うどんこ病」
- 果実がすすで汚れたようになる「すす病」
葉に黒い斑点ができる「炭疽病」「落葉病」
葉に黒や褐色の斑点が現れたら、「炭疽病(たんそびょう)」や「落葉病(らくようびょう)」の可能性があります。これらの病気は、見た目が悪くなるだけでなく、ひどくなると葉を早期に落としてしまい、木の成長や果実の品質に深刻な影響を与えます。
炭疽病は、葉だけでなく枝や果実にも発生します。 特に湿度が高い梅雨時期に発生しやすく、黒い小さな斑点が次第に大きくなり、中央がへこんでくるのが特徴です。 落葉病には「円星落葉病」と「角斑落葉病」があり、どちらも葉に斑点を生じさせ、最終的に落葉を引き起こします。 これらの病気の病原菌は、被害を受けた枝や落ち葉で冬を越し、翌年の伝染源となるため、病気にかかった枝や葉は剪定・除去し、落ち葉は集めて処分することが非常に重要です。 予防のためには、風通しを良くするための適切な剪定や、登録のある殺菌剤の散布が有効です。
葉が白い粉を吹いたようになる「うどんこ病」
葉の表面が、まるでうどんの粉をまぶしたように白くなるのが「うどんこ病」です。 この白い粉はカビの一種で、光合成を妨げるため、発生すると木の生育が悪くなります。 うどんこ病は、特に風通しが悪く、日当たりの良くない場所で発生しやすいです。窒素肥料の与えすぎも発生の一因となります。 予防としては、剪定によって風通しと日当たりを改善することが基本です。発生初期であれば、被害の出た葉を取り除くことで拡大を防げる場合もあります。症状が広がるようであれば、うどんこ病に効果のある殺菌剤を散布して対処しましょう。
果実がすすで汚れたようになる「すす病」
葉や枝、果実の表面が黒いすすで覆われたようになる症状は、「すす病」です。 この病気は、病原菌が直接植物に感染するのではなく、カイガラムシやアブラムシなどの害虫の排泄物(甘露)を栄養源として繁殖することで発生します。 つまり、すす病が発生しているということは、その原因となる害虫がどこかにいる証拠です。すす病自体が木を枯らすことは少ないですが、光合成を妨げたり、果実の見た目を著しく損なったりします。 対策としては、原因となっているカイガラムシやアブラムシを駆除することが最も重要です。原因害虫がいなくなれば、すす病も自然と発生しなくなります。
よくある質問
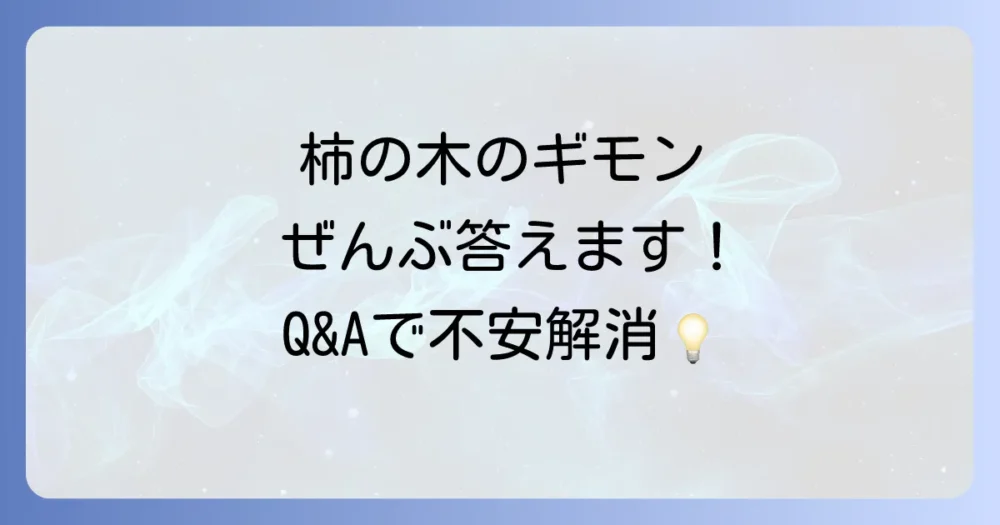
柿の木の消毒に最適な時期はいつですか?
柿の木の消毒は、目的とする病害虫によって最適な時期が異なります。 一般的に、多くの病害虫が活動を始める前の冬(休眠期)に行う石灰硫黄合剤の散布や、害虫の活動が活発になる5月~7月頃が重要な防除時期となります。 特にカキノヘタムシガやカイガラムシの幼虫が発生する6月頃は、重要な消毒タイミングの一つです。 地域のJAなどが発行する防除暦を参考にすると、より的確なタイミングで消毒を行うことができます。
虫がついた柿の実は食べられますか?
虫の種類や被害の程度によります。カキノヘタムシガの被害にあった実は、内部が食い荒らされて食べられない状態になっていることが多いです。 カメムシに吸われた部分はスポンジ状になって食感が悪くなります。表面だけを少し食べられたような場合は、その部分だけを取り除けば食べられることもありますが、内部に虫が侵入している可能性も考え、よく確認してから判断してください。
柿の葉の裏にびっしりついている虫は何ですか?
柿の葉の裏にびっしりと集団でついている虫は、イラガの若い幼虫である可能性が高いです。 孵化したばかりの幼虫は一か所に固まって葉を食べる習性があります。 他にはアブラムシが群生している場合もあります。いずれにしても、集団でいるうちに葉ごと取り除いて駆除するのが最も効果的です。
毛虫に刺されたらどうすればいいですか?
イラガなどの毒毛虫に刺された場合は、まず刺された場所をこすらず、セロハンテープやガムテープなどをそっと貼り付けて剥がし、皮膚に残った毒針を取り除きます。 その後、流水でよく洗い流してください。 痛みやかゆみが強い場合は、抗ヒスタミン成分を含むステロイド軟膏などを塗布し、氷などで冷やすと症状が和らぎます。症状がひどい場合や、アレルギー反応(じんましん、息苦しさなど)が出た場合は、速やかに皮膚科を受診してください。
まとめ
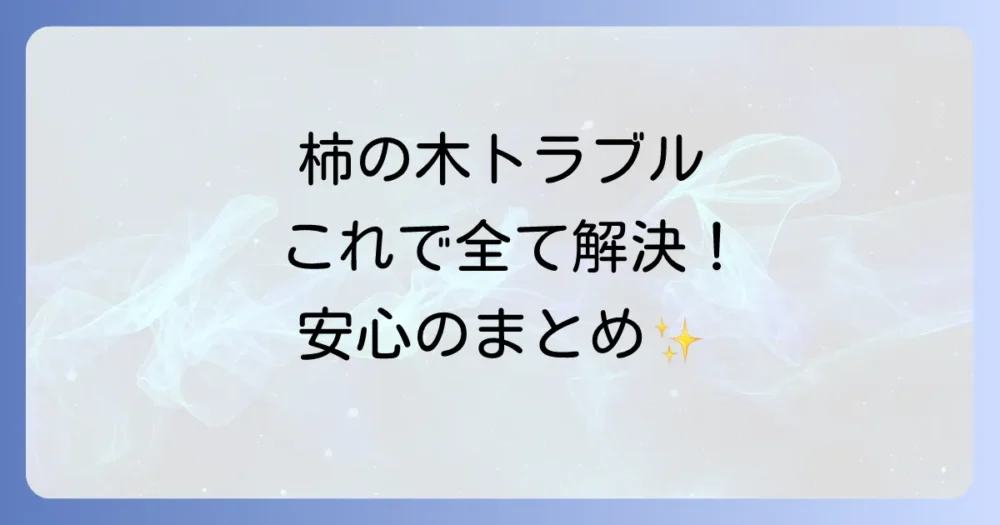
- 柿の葉にはイラガやカキノヘタムシガなど多様な害虫がつく。
- イラガは毒針を持ち、触れると激しい痛みを伴う。
- カキノヘタムシガは実に食入し、落果の原因となる。
- カイガラムシはすす病を誘発し、見た目と生育に悪影響を与える。
- 害虫駆除は、発生初期に物理的に取り除くのが基本。
- 大量発生時は、対象害虫に合った薬剤を適切に使用する。
- 冬の「粗皮削り」は越冬害虫を減らすのに非常に効果的。
- 農薬を使わない対策として、天敵の保護や木酢液の利用がある。
- 葉の黒い斑点は炭疽病や落葉病の可能性がある。
- 白い粉はうどんこ病のサインで、風通しの改善が重要。
- すす病はカイガラムシなどの害虫の排泄物が原因。
- 病気の対策は、原因菌の伝染源となる落ち葉や枝の処理が大切。
- 消毒は病害虫の活動時期に合わせて行うのが効果的。
- 毛虫に刺されたら、こすらず毒針を取り除き、流水で洗う。
- 日頃から柿の木をよく観察し、異常の早期発見に努めることが重要。
新着記事