「あれ、額田王(ぬかたのおおきみ)って百人一首にいたっけ?」
歴史や和歌に興味のある方なら、一度はそう思ったことがあるかもしれません。飛鳥時代を代表する情熱的な歌人、額田王。彼女の詠んだ歌は、千年以上の時を超えて私たちの心を打ちます。しかし、意外なことに、彼女の歌は小倉百人一首には一首も選ばれていないのです。
本記事では、なぜ額田王が百人一首に選ばれなかったのか、その理由を深く掘り下げて解説します。さらに、天智天皇・天武天皇とのドラマチックな関係や、彼女が残した有名な和歌の魅力にも迫ります。この記事を読めば、額田王と百人一首にまつわる全ての疑問が解決するでしょう。
結論:額田王の歌は百人一首に選ばれていません
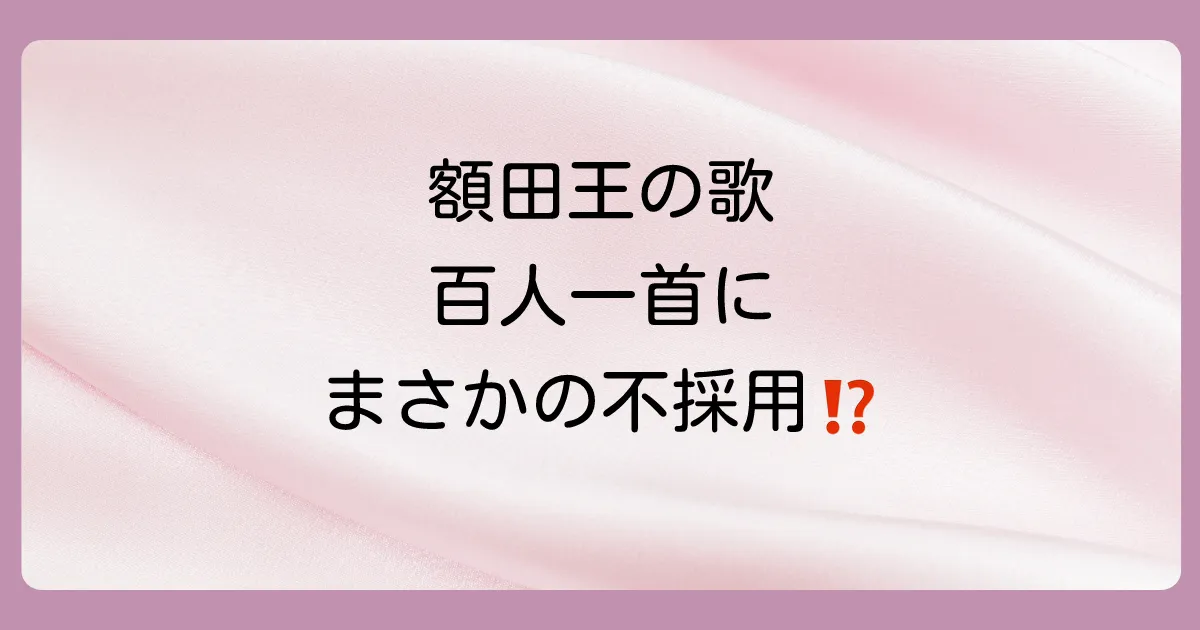
まず結論からお伝えすると、額田王の歌は小倉百人一首には一首も選ばれていません。
「え、あんなに有名な歌人なのに?」と驚かれる方も多いのではないでしょうか。事実、額田王は『万葉集』を代表する歌人の一人であり、その知名度は非常に高いです。 特に、天智天皇と弟の天武天皇という二人の天皇から愛されたというドラマチックな生涯は、多くの歴史ファンを魅了してやみません。
では、なぜこれほど有名な額田王の歌が、後世に編まれた代表的な和歌集である百人一首に選ばれなかったのでしょうか。それには、いくつかの理由が考えられます。次の章で詳しく見ていきましょう。
なぜ額田王は百人一首に選ばれなかったのか?考えられる3つの理由
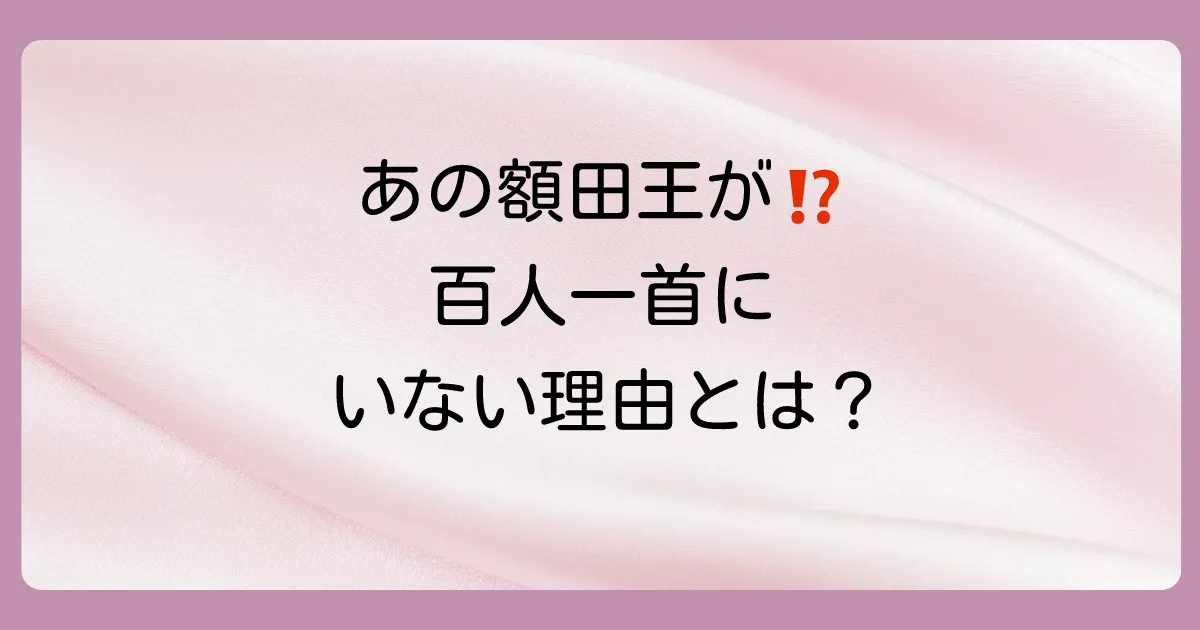
額田王が百人一首に選ばれなかった理由は一つだけではありません。時代の隔たりや、選者である藤原定家の好みなど、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。ここでは、主な理由として考えられる3つのポイントを解説します。
- 理由①:活躍した時代が古すぎた
- 理由②:選者・藤原定家の好みではなかった?
- 理由③:『万葉集』と『古今和歌集』以降の歌風の違い
理由①:活躍した時代が古すぎた
最も大きな理由として考えられるのが、活躍した時代の違いです。
額田王が活躍したのは7世紀後半の飛鳥時代です。 一方、小倉百人一首が選ばれたのは鎌倉時代初期、13世紀前半のこと。 選者である藤原定家(ふじわらのさだいえ/ていか)が生きた時代から見ると、額田王の時代は550年以上も昔ということになります。
百人一首には、天智天皇(1番)や持統天皇(2番)など、額田王と同じ飛鳥時代の歌人も選ばれてはいます。 しかし、全体を見ると、選ばれている歌の多くは平安時代の『古今和歌集』や『新古今和歌集』から採られています。定家にとって、あまりにも古い時代の万葉歌人である額田王は、選考の対象として少し遠い存在だったのかもしれません。
理由②:選者・藤原定家の好みではなかった?
選者である藤原定家の個人的な好みも、選歌に大きく影響したと考えられます。
定家は、優雅で洗練された、技巧的な歌を好んだことで知られています。彼の美意識は「幽玄・有心(うしん)」といった言葉で表現され、言葉の裏に深い余情や情趣が感じられる歌を高く評価しました。 例えば、定家が愛したとされる式子内親王の歌(89番)などは、その典型と言えるでしょう。
一方、額田王の歌は、おおらかで素朴、そして感情をストレートに表現する力強さが魅力です。 これは『万葉集』全体の歌風(ますらおぶり)にも通じる特徴ですが、定家が理想とする繊細で技巧的な歌の世界とは少し趣が異なっていた可能性があります。定家自身の美学に照らし合わせた結果、残念ながら額田王の歌は選ばれなかった、という見方もできるのです。
理由③:『万葉集』と『古今和歌集』以降の歌風の違い
額田王の歌が収録されている『万葉集』と、百人一首の主な選定元である『古今和歌集』以降の勅撰和歌集とでは、歌のスタイル(歌風)に大きな違いがあります。
『万葉集』の歌は、天皇から農民まで様々な身分の人々の歌が収められており、表現も素朴で力強いのが特徴です。 これに対し、平安時代に編纂された『古今和歌集』以降は、貴族社会が中心となり、知的で洗練された、いわゆる「みやび」な歌が主流となっていきます。
藤原定家は、この『古今和歌集』以降の流れを汲む歌人です。 そのため、百人一首を選ぶ際にも、自然と自身が慣れ親しんだ優美な歌風のものを中心に選んだと考えられます。万葉集の素朴で雄大な歌風は、定家の選歌基準からすると、少し異質に感じられたのかもしれませんね。
謎多き歌人・額田王とはどんな人物?
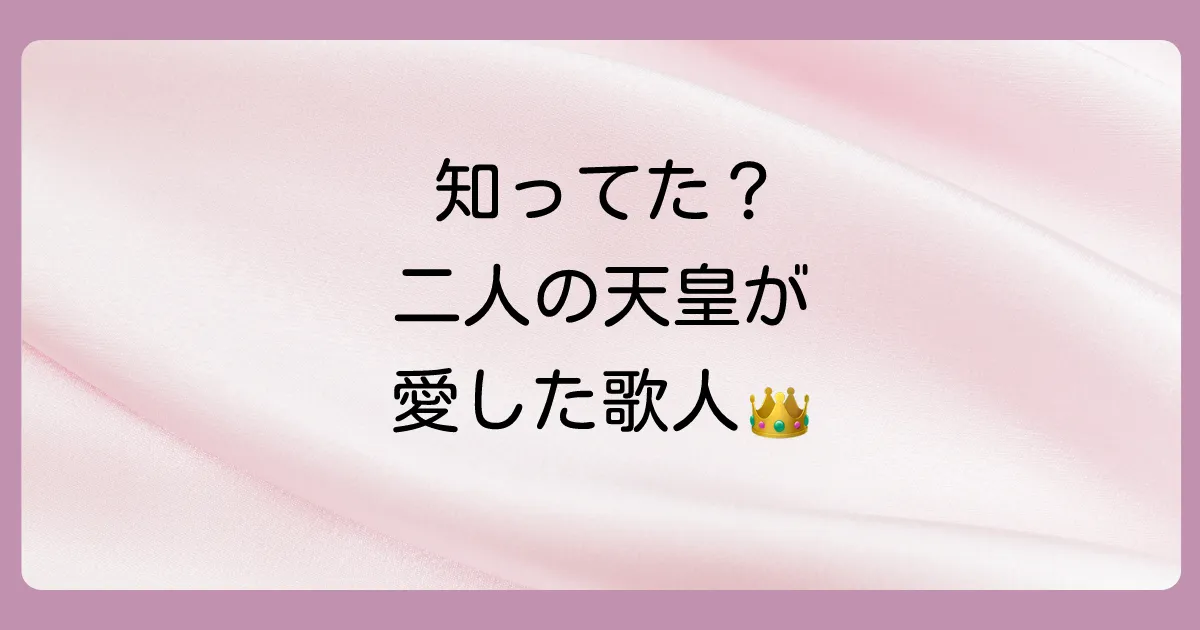
百人一首には選ばれなかったものの、額田王が日本文学史上に残る偉大な歌人であることは間違いありません。彼女の生涯は謎に包まれた部分も多いですが、残された歌からは情熱的で才能あふれる女性像が浮かび上がってきます。 ここでは、額田王の人物像に迫ってみましょう。
- 天智天皇と天武天皇、二人の天皇に愛された女性
- 巫女的な存在だったという説も
- 額田王の生涯と人物像
天智天皇と天武天皇、二人の天皇に愛された女性
額田王の人生を語る上で欠かせないのが、天智天皇(中大兄皇子)と天武天皇(大海人皇子)という兄弟との関係です。
『日本書紀』によれば、額田王ははじめ弟である大海人皇子(後の天武天皇)に嫁ぎ、十市皇女(とおちのひめみこ)という娘をもうけました。 しかしその後、兄である中大兄皇子(後の天智天皇)に見初められ、その寵愛を受けることになります。 現在の価値観からすると驚くべき関係ですが、当時の大らかな風習の中、彼女は二人の偉大な天皇から愛されるという数奇な運命をたどったのです。 このドラマチックな三角関係は、彼女の歌作にも大きな影響を与えたと言われています。
巫女的な存在だったという説も
額田王は、単なる天皇の妃というだけでなく、神意を伺い、それを歌の形で伝える巫女的な役割も担っていたのではないか、という説があります。
彼女の歌には、個人の恋心を詠んだものだけでなく、国の安泰や戦の勝利を祈るような、公的な性格を持つ歌も残されています。 例えば、斉明天皇が百済救援のために九州へ向かう船出の際に詠んだ「熟田津(にきたつ)に…」の歌は、軍の士気を高めるための儀式歌であったと考えられています。 類まれな和歌の才能を持つ彼女は、神と人とをつなぐ特別な存在として、宮廷で重んじられていたのかもしれません。
額田王の生涯と人物像
額田王の生没年や出自については、詳しい記録が残っておらず、謎に包まれています。 『日本書紀』に「鏡王の娘」と記されていることから、皇族の一員であったと推測されていますが、その父である鏡王もまた謎の多い人物です。
しかし、残された12首の和歌からは、情熱的で、知性と感性に溢れ、そして強い意志を持った女性像が浮かび上がってきます。 天皇の前で堂々と元夫と恋の歌を詠み交わす大胆さ。 遠征に向かう船団を力強く鼓舞するリーダーシップ。そして、去りゆく都を惜しむ繊細な感受性。彼女の歌は、飛鳥という激動の時代を生き抜いた一人の女性の、力強い息吹を今に伝えてくれるのです。
心を揺さぶる額田王の有名な和歌3選【現代語訳付き】
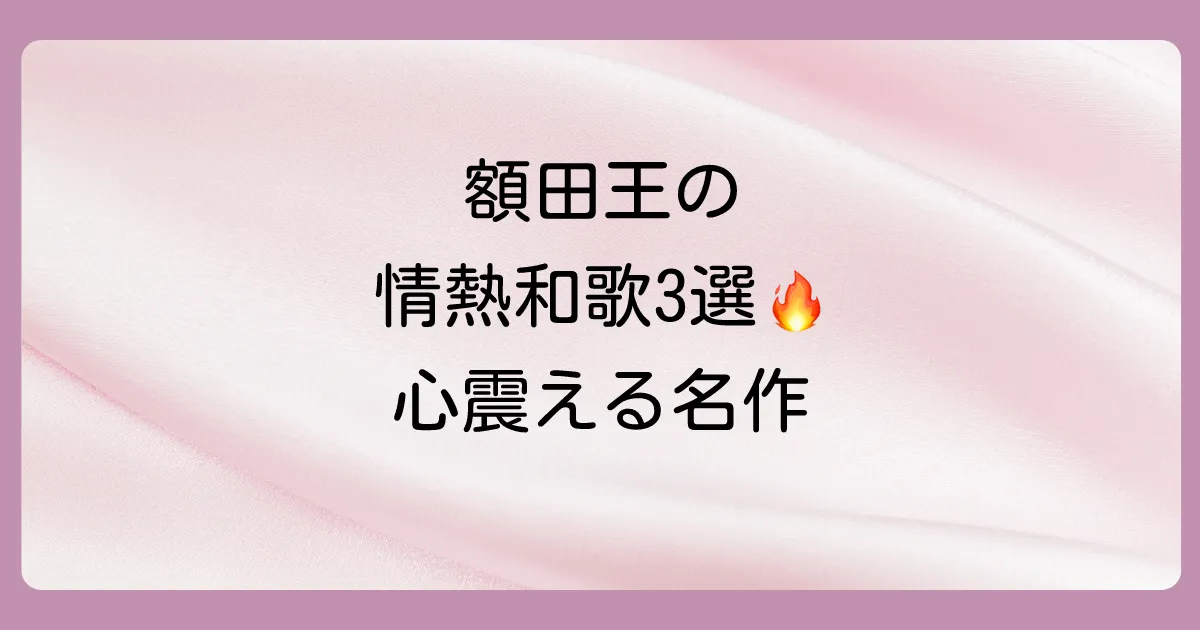
額田王の魅力は、何と言ってもその情熱的な和歌にあります。彼女が残した歌は決して多くはありませんが、いずれも傑作として語り継がれています。 ここでは、特に有名な3首を現代語訳とともにご紹介します。
- ①あかねさす紫野行き標野行き…【天武天皇への恋の歌】
- ②君待つと我が恋ひをれば…【切ない恋心を詠んだ歌】
- ③熟田津に船乗りせむと…【斉明天皇の船出を詠んだ歌】
①あかねさす紫野行き標野行き…【天武天皇への恋の歌】
あかねさす 紫野(むらさきの)行き 標野(しめの)行き 野守(のもり)は見ずや 君が袖振る
この歌は、額田王の代表作として最も有名な一首です。 天智天皇の御前で、元夫である大海人皇子(天武天皇)に向けて詠まれました。
【現代語訳】
(茜色に輝く)紫草の生えている野、天皇の御料地であるこの野を行きながら、あなたはそんなに袖を振って私への想いを示して…。野の番人が見てしまうではありませんか。
現在の夫である天智天皇の前で、昔の夫である大海人皇子からアプローチされ、それをやんわりと、しかし情熱的にたしなめる。なんとも大胆でドラマチックな一場面が目に浮かぶようです。この歌に対し、大海人皇子も情熱的な返歌を詠んでおり、二人のやり取りは万葉集屈指の名場面として知られています。
②君待つと我が恋ひをれば…【切ない恋心を詠んだ歌】
君待つと 我が恋ひをれば 我が宿の 簾(すだれ)動かし 秋の風吹く
この歌は、恋しい人を待つ女性の切ない心情を詠んだ歌です。 誰を待っているのかは明らかにされていませんが、一説には天智天皇を待って詠んだ歌とも言われています。
【現代語訳】
あなたがいらっしゃるのを恋しく思いながら待っていると、我が家の簾を動かして、秋の風が吹いてきましたよ。
「カサ…」と音を立てて揺れる簾。「もしや、あの人が来たのでは?」という期待と、それがただの風の音だったと知った時の寂しさや落胆。その一瞬の心の揺れを見事に捉えた、非常に繊細で美しい一首です。 期待と失望が入り混じる恋の切なさが、時を超えてひしひしと伝わってきますね。
③熟田津に船乗りせむと…【斉明天皇の船出を詠んだ歌】
熟田津(にきたつ)に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
この歌は、恋の歌とは趣が異なり、公的な場面で詠まれたとされる勇壮な一首です。 661年、斉明天皇が百済救援のために大船団を率いて九州へ向かう途中、伊予の熟田津(現在の愛媛県松山あたり)に立ち寄った際に詠まれました。
【現代語訳】
熟田津で船出しようと月の出を待っていると、ちょうど良い潮時にもなった。さあ、今こそ船を漕ぎ出そう!
これから始まる困難な戦を前に、全軍の士気を鼓舞する力強い号令のような歌です。天皇に代わって、あるいは天皇の思いを代弁して、このような重要な歌を詠む役割を担っていたことからも、額田王が宮廷でいかに重要な存在であったかがうかがえます。 個人的な恋情だけでなく、公的な場面でもその才能を遺憾なく発揮した、彼女のスケールの大きさを感じさせる名歌です。
【豆知識】百人一首と万葉集の違いとは?
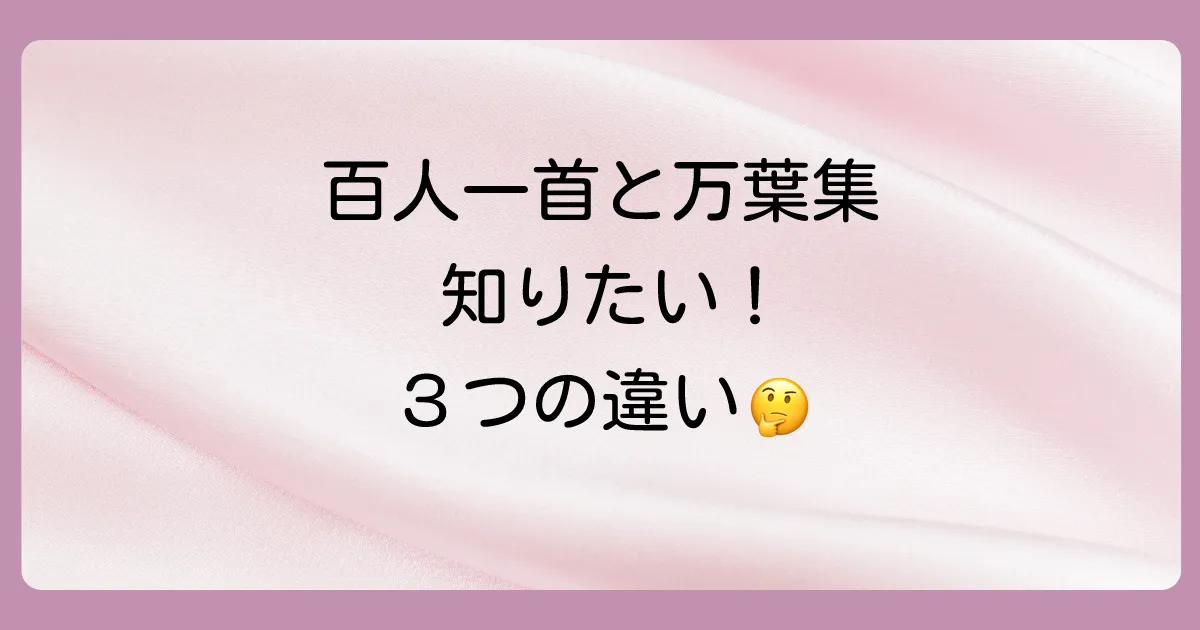
「額田王は万葉集の歌人だけど、百人一首とは何が違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。どちらも有名な和歌集ですが、その成り立ちや特徴には大きな違いがあります。 ここで、その違いを簡単に整理しておきましょう。
- 成立した時代
- 撰者(編纂者)
- 収録されている歌の数と歌風
成立した時代
まず、成立した時代が大きく異なります。
- 万葉集:奈良時代(8世紀後半)に成立した、現存する日本最古の歌集です。
- 小倉百人一首:鎌倉時代初期(13世紀前半)に、歌人の藤原定家によって選ばれた私的な和歌集(秀歌撰)です。
このように、万葉集の成立から百人一首の選定までには、約450年もの時間の隔たりがあるのです。
撰者(編纂者)
誰が作ったか、という点も異なります。
- 万葉集:中心的な編纂者は大伴家持(おおとものやかもち)とされていますが、複数の人物が長年にわたって関わったと考えられており、最終的な編纂者は不明な部分も多いです。
- 小倉百人一首:鎌倉時代の代表的な歌人である藤原定家が一人で選んだとされています。 ただし、近年の研究では異説も唱えられています。
万葉集が国家的な事業に近い形で編纂されたのに対し、百人一首は定家個人の美意識が強く反映されたコレクションと言えるでしょう。
収録されている歌の数と歌風
内容にも大きな違いが見られます。
- 万葉集:約4500首もの歌が収められており、天皇から兵士、農民まで、様々な身分の人々の歌が含まれています。歌風は素朴で力強く、感情をストレートに表現したものが多いのが特徴です(ますらおぶり)。
- 小倉百人一首:その名の通り、100人の歌人の歌を1首ずつ、合計100首集めたものです。 主に平安時代以降の貴族の歌が中心で、洗練された優雅な歌風(たおやめぶり)のものが多く選ばれています。
このように、二つは全く性格の異なる歌集なのです。額田王の歌に触れたい場合は『万葉集』を、様々な時代の名歌を少しずつ楽しみたい場合は『百人一首』を手に取ってみるのがおすすめです。
よくある質問
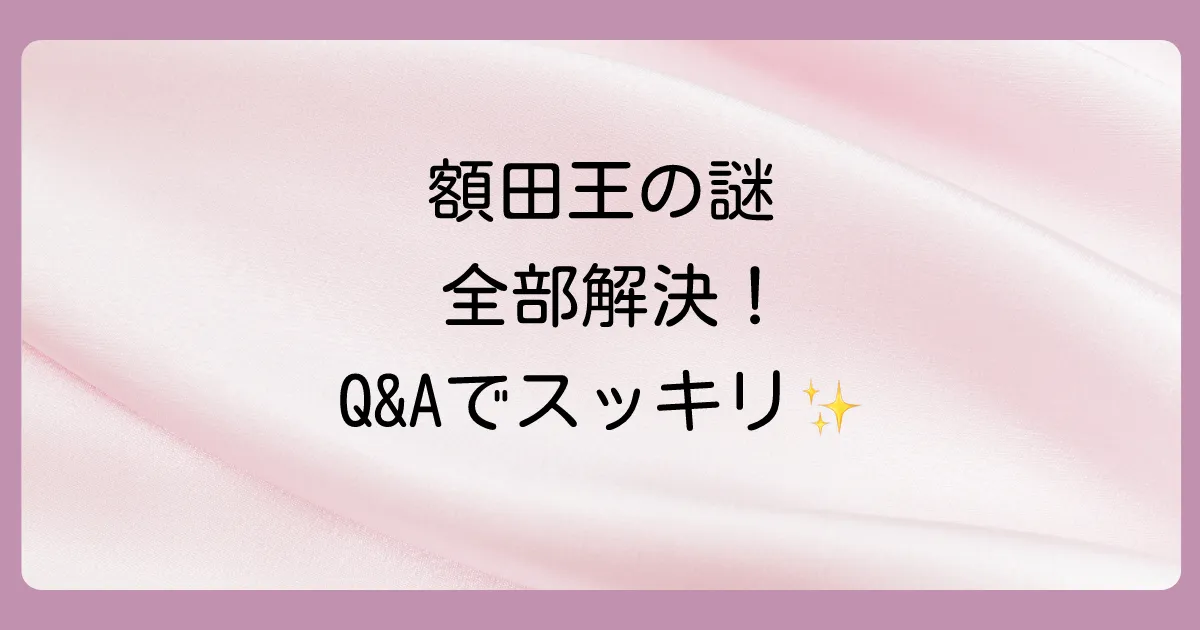
額田王の代表作は何ですか?
額田王の代表作として最も有名なのは、「あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」です。 この歌は、天智天皇の御前で元夫の大海人皇子(天武天皇)に詠んだ情熱的な一首で、万葉集の中でも特に人気の高い歌の一つです。 その他にも、「君待つと我が恋ひをれば我が宿の簾動かし秋の風吹く」や「熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな」なども有名です。
額田王と天智天皇、天武天皇はどのような関係だったのですか?
額田王は、はじめ弟である大海人皇子(後の天武天皇)の妻となり、十市皇女をもうけました。 その後、兄である中大兄皇子(後の天智天皇)に見初められ、その寵愛を受けることになりました。 兄弟である二人の天皇から愛されたという、非常にドラマチックな関係にありました。 この三角関係は、彼女の和歌にも大きな影響を与えたとされています。
百人一首の選者は誰ですか?
小倉百人一首の選者は、鎌倉時代初期の公家であり、当代きっての歌人であった藤原定家(ふじわらのさだいえ、または「ていか」)であると広く信じられています。 彼は『新古今和歌集』の撰者の一人でもあり、歌壇に絶大な影響力を持っていました。 百人一首は、定家が京都・嵯峨の小倉山にある山荘で、襖に貼る色紙のために選んだ和歌が元になったと言われています。
百人一首で一番有名な歌はなんですか?
「一番」を決めるのは非常に難しいですが、一般的に知名度が高い歌としては、蝉丸の「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」や、小野小町の「花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに」などが挙げられます。 また、競技かるたの影響で、決まり字が短い「むすめふさほせ(村雨の〜、めぐりあひて〜、ふくからに〜、さびしさに〜、ほととぎす〜、せをはやみ〜)」の歌もよく知られています。
まとめ
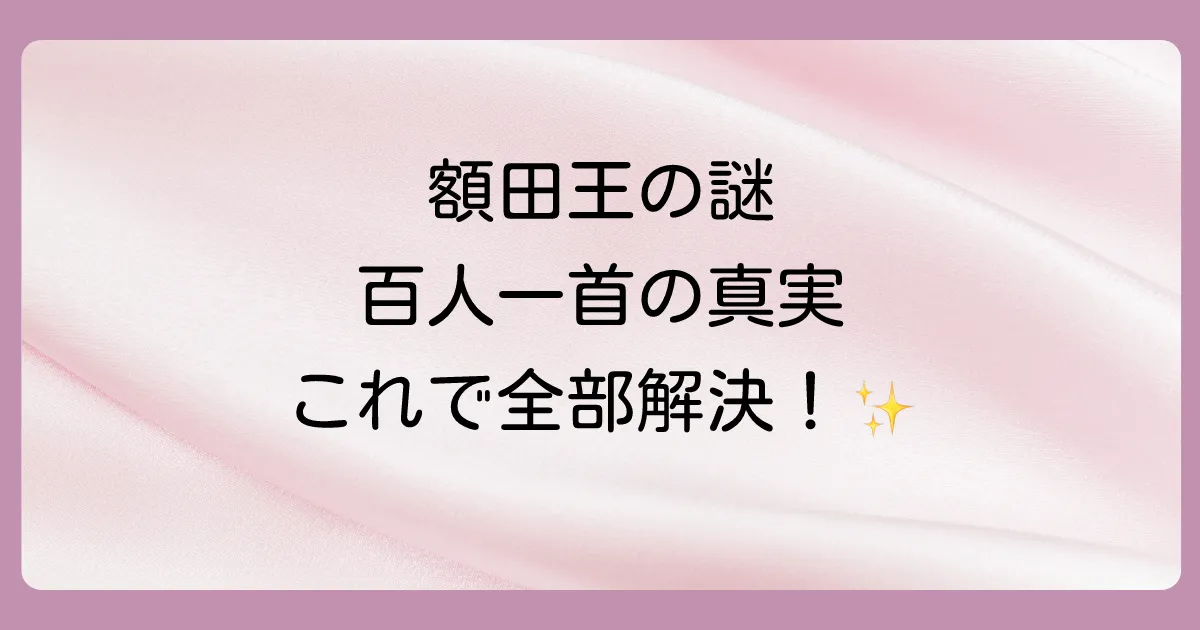
- 額田王の歌は小倉百人一首には選ばれていない。
- 選ばれなかった理由は、活躍した時代が古すぎたこと。
- 選者である藤原定家の好みと合わなかった可能性。
- 万葉集と古今和歌集以降の歌風の違いも一因。
- 額田王は飛鳥時代を代表する情熱的な女流歌人。
- 天智天皇と天武天皇の兄弟二人に愛された。
- 巫女的な役割も担っていたとされる公的な歌も詠んだ。
- 代表作は「あかねさす紫野行き標野行き…」。
- 元夫の天武天皇へ詠んだ大胆な恋の歌である。
- 「君待つと…」は恋人を待つ切ない心情を詠んだ名歌。
- 「熟田津に…」は船団の士気を高める勇壮な歌。
- 額田王の歌は『万葉集』に収録されている。
- 万葉集は日本最古の歌集で、約4500首を収録。
- 百人一首は鎌倉時代に藤原定家が選んだ秀歌撰。
- 百人一首は主に平安時代の優美な歌が中心である。




