韓国の歴史ドラマを見ていると、頻繁に登場する「奴婢(ヌヒ)」という存在。主人公が奴婢の身分に落とされたり、奴婢との許されない恋に悩んだり…物語の重要な要素として描かれることが多いですよね。「奴婢って、具体的にどんな人たちなの?」「日本の武士や農民とは違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?
本記事では、韓国史における奴婢とは何か、その壮絶な歴史と生活の実態、そしてよく混同される「白丁(ペクチョン)」との違いについて、誰にでも分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、韓国の歴史ドラマがもっと深く、もっと面白くなること間違いなしです。
韓国の歴史に登場する「奴婢(ヌヒ)」とは?
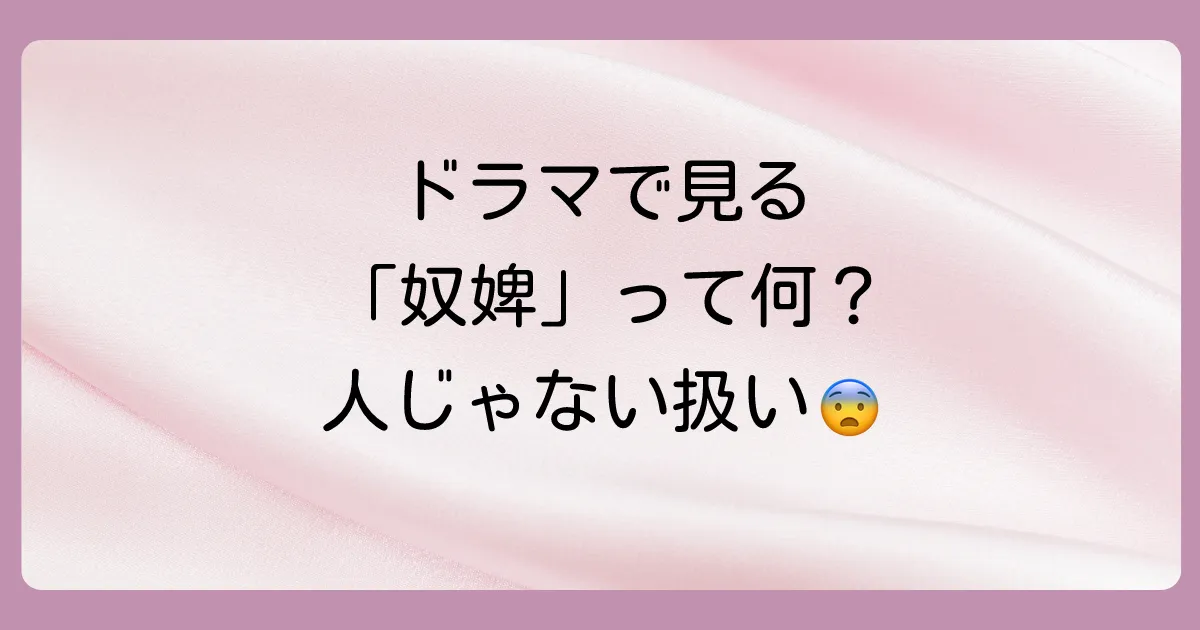
韓国の歴史を語る上で欠かせないのが、厳しい身分制度です。その中でも最下層に位置づけられたのが「奴婢」でした。彼らがどのような存在だったのか、基本的な意味から日本の身分制度との違いまで、詳しく見ていきましょう。
この章では、以下の点について解説します。
- 奴婢の基本的な意味 – 人として扱われなかった最下層の賤民
- 奴婢の起源と歴史的背景
- 日本の「下人」や欧米の「奴隷」との違い
奴婢の基本的な意味 – 人として扱われなかった最下層の賤民
奴婢(ヌヒ)とは、高麗時代から李氏朝鮮時代にかけて存在した、社会の最下層に置かれた賤民(せんみん)のことです。 「奴」は男性、「婢」は女性を指す言葉で、彼らは人間としての尊厳を認められず、主人の「所有物」として扱われました。 そのため、まるで牛や馬のような家畜と同じように、売買、相続、贈与の対象とされていたのです。
奴婢は、主に戦争捕虜や犯罪者、借金を返せなくなった人々、そして反逆者の家族などがその身分に落とされました。 一度奴婢になると、そこから抜け出すことは極めて困難であり、その身分は子孫にまで受け継がれるという、非常に過酷な運命を背負っていました。 彼らは、居住移転の自由や職業選択の自由もなく、主人の命令に絶対服従の生活を強いられていたのです。
奴婢の起源と歴史的背景
奴婢制度の起源は古く、朝鮮の歴史においては古代の古朝鮮時代からその存在が確認されています。 しかし、この制度が国家の法として確立され、社会に深く根付いたのは、高麗時代から李氏朝鮮時代にかけてでした。
特に、儒教を国家の統治理念とした李氏朝鮮時代には、身分制度がより厳格化され、奴婢の数は爆発的に増加しました。 ある記録によれば、15世紀頃には全人口の約40%を奴婢が占めていたという推計もあるほどです。 これは、支配階級である両班(ヤンバン)が、自らの経済的基盤を維持・拡大するために、労働力として奴婢を大量に必要としたためです。国家としても、奴婢を管理するための専門機関「掌隷院(チャンネウォン)」を設置するなど、制度的に奴婢を社会の底辺に固定化していました。
日本の「下人」や欧米の「奴隷」との違い
「奴婢」と聞くと、日本の歴史における「下人(げにん)」や、欧米の歴史における「奴隷」を思い浮かべるかもしれません。確かに、主人のために働き、自由が制限されるという点では共通しています。しかし、いくつかの重要な違いがあります。
日本の「下人」も主家に仕える身分でしたが、奴婢のように人格を完全に否定され、売買の対象となることは比較的少なかったとされています。また、時代と共にそのあり方は変化し、律令制の崩壊とともに公的な身分としての奴婢は10世紀初頭には姿を消しました。
一方、欧米のプランテーションなどで働かされた「奴隷」は、出身地から遠く離れた土地へ強制的に連れてこられ、家族やコミュニティから完全に引き離されるという点で、奴婢とは異なる過酷さがありました。朝鮮の奴婢は、主人の家の近くに住み、限定的ながらも家族を形成することが許される場合もありました。 しかし、その身分が法的に固定され、親から子へと世襲される「一身賤則」という原則が徹底されていた点は、朝鮮の奴婢制度の最も大きな特徴と言えるでしょう。
想像を絶する奴婢の生活実態
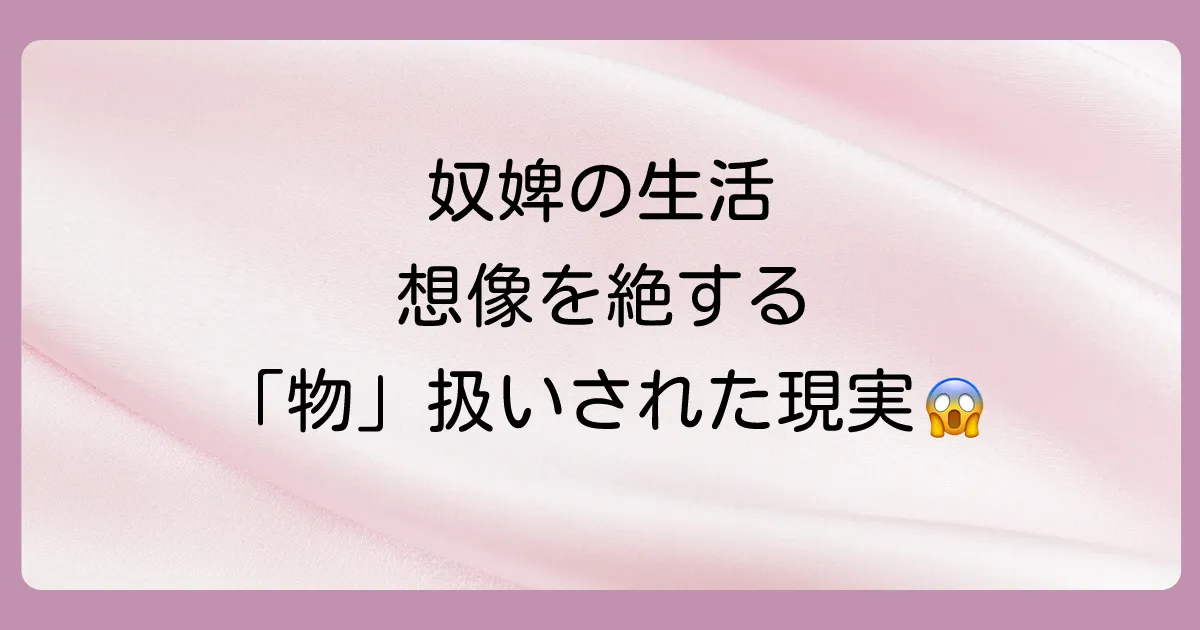
奴婢の生活は、現代の私たちからは想像もつかないほど過酷なものでした。法律上「物」として扱われた彼らは、どのような日常を送っていたのでしょうか。その壮絶な実態に迫ります。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 主人からの逃亡は許されない過酷な労働
- 財産として扱われた奴婢 – 売買・相続の対象
- 奴婢の結婚と「一身賤則」の悲劇
主人からの逃亡は許されない過酷な労働
奴婢の最も基本的な役割は、主人のために働くことでした。その労働内容は、農業、家事、雑用など多岐にわたり、夜明けから日没まで、休みなく働き続けるのが日常でした。彼らに職業選択の自由はなく、主人の命令は絶対でした。
もし、この過酷な労働から逃れようと逃亡しても、待っているのは厳しい現実でした。「推奴(チュノ)」と呼ばれる、逃亡した奴婢を捕まえる専門の追跡者が存在し、捕まれば厳しい罰が待っていました。 実際に、朝鮮前期の有名な宰相が「逃亡奴婢は100万人にのぼる」と述べた記録も残っており、いかに多くの奴婢が逃亡を試み、そして捕らえられていたかがうかがえます。 このように、奴婢にとって逃亡は死をも覚悟するほどの危険な賭けだったのです。
財産として扱われた奴婢 – 売買・相続の対象
奴婢が「人」ではなく「物」として扱われていたことを最も象徴するのが、売買や相続の対象であったという事実です。 主人は自らが所有する奴婢を、市場で自由に売り買いすることができました。また、奴婢は主人の財産の一部と見なされたため、主人が亡くなると、土地や家屋と同じように子孫へと相続されました。
時には、借金の担保として奴婢が利用されることもありました。 親から引き離され、見知らぬ土地の新しい主人へと売られていく子どもの奴婢も少なくありませんでした。家族という概念さえ、主人の都合によって簡単に引き裂かれてしまう、非常に不安定で非人間的な状況に置かれていたのです。
奴婢の結婚と「一身賤則」の悲劇
奴婢は結婚し、家族を持つことが許される場合もありました。 しかし、その結婚も自由なものではありませんでした。多くの場合、主人の許可が必要であり、同じ奴婢同士の結婚が基本でした。
そして、奴婢の家族制度において最も悲劇的だったのが、「一身賤則(イルチョンチョクチョン)」または「賤者隨母法(せんじゃずいぼほう)」と呼ばれる原則です。 これは、父母のどちらか一方が奴婢であれば、その間に生まれた子どもも奴婢の身分になるという法律でした。 特に、母親が奴婢である場合、その子どもは例外なく奴婢とされました。
この法律は、支配階級である両班が奴婢の数を確保し続けるために非常に好都合なものでした。 例えば、両班の男性が女性の奴婢を妾にし、子どもを産ませた場合、その子どもは父親の身分ではなく、母親の身分を引き継いで奴婢となりました。 このようにして、奴婢の身分は世代を超えて再生産され、多くの人々が生まれながらにして自由を奪われるという悲劇が繰り返されたのです。
奴婢にも種類があった?公奴婢と私奴婢の違い
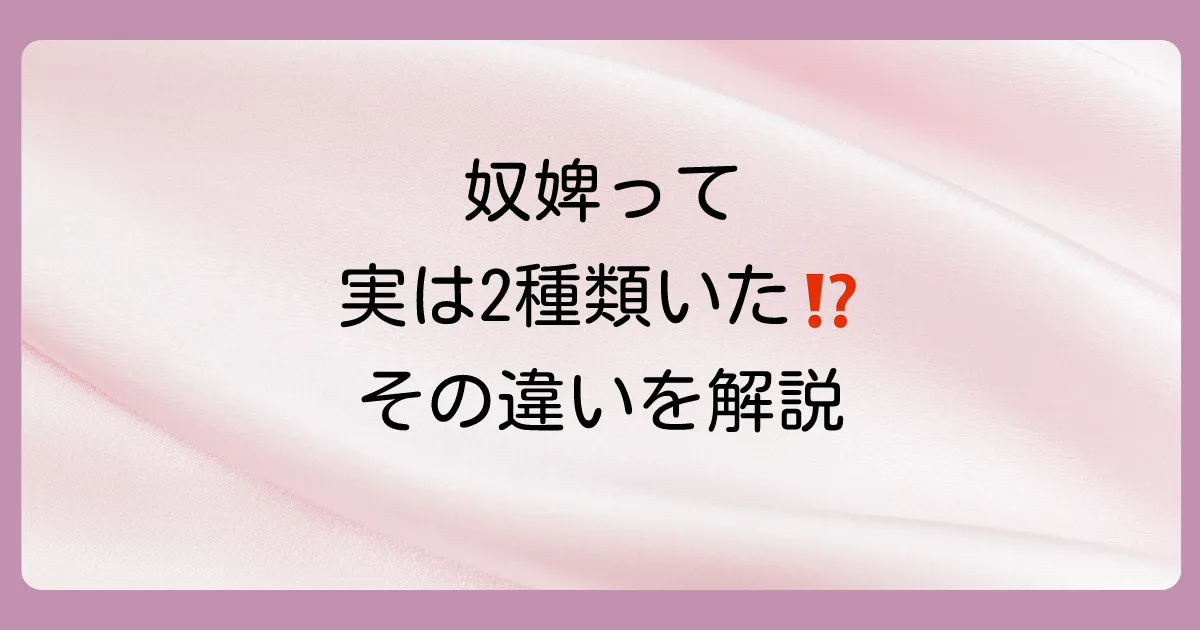
一口に「奴婢」と言っても、その所属先によっていくつかの種類に分けられていました。最も大きな区分が、国に所属する「公奴婢(コンノビ)」と、個人に所有される「私奴婢(サノビ)」です。それぞれの役割や立場にはどのような違いがあったのでしょうか。
この章では、以下の点について詳しく見ていきます。
- 国家に隷属する「公奴婢(コンノビ)」
- 個人に所有された「私奴婢(サノビ)」
国家に隷属する「公奴婢(コンノビ)」
公奴婢(コンノビ)とは、国や官庁に所有された奴婢のことです。 彼らは、宮殿や中央の役所、地方の官衙(かんが)などで様々な業務に従事しました。例えば、宮殿の清掃や雑務、官庁での下働き、さらには駅の管理や狼煙(のろし)台の番人といった仕事も公奴婢の役割でした。
公奴婢は、国から給料(俸給)が支払われることもあり、私奴婢に比べると比較的安定した生活を送ることができたと言われています。 しかし、彼らもまた国の財産であり、自由な身分ではありませんでした。反逆者の家族などは、罪を問われて公奴婢の身分に落とされることもありました。 韓国ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』などで描かれる宮廷の下働きなども、この公奴婢にあたります。
個人に所有された「私奴婢(サノビ)」
私奴婢(サノビ)は、両班などの個人に所有された奴婢です。 韓国の歴史ドラマで描かれる、主人の家で働く使用人の多くはこの私奴婢にあたります。 彼らは主人の私有財産として扱われ、売買や相続の対象となりました。 その生活は完全に主人の裁量に委ねられており、公奴婢よりも過酷な状況に置かれることが多かったとされています。
この私奴婢は、さらに働き方によって2つのタイプに分けられました。
主人と同居する「率居奴婢(ソルゴノビ)」
率居奴婢(ソルゴノビ)は、主人の家に住み込みで働く奴婢です。 主人の身の回りの世話から家事全般、農作業まで、あらゆる労働を担いました。常に主人の監視下にあり、自由な時間はほとんどありませんでした。ドラマなどで描かれる、屋敷内で働く奴婢の多くがこのタイプです。
独立して生活する「外居奴婢(ウェゴノビ)」
一方、外居奴婢(ウェゴノビ)は、主人の家の外に独立した住居を構え、生活していた奴婢です。 彼らは、主人から土地を与えられて農業を営み、その収穫物の一部を「身貢(シングン)」として主人に納める義務がありました。この身貢を納めていれば、ある程度の自由な生活が認められていました。中には、自らの財産を蓄え、さらに別の奴婢を所有する外居奴婢も存在したと言われています。 しかし、彼らも身分上は奴婢であり、主人の命令があればいつでも呼び出され、労働に従事しなければなりませんでした。
奴婢制度はいつまで続いた?解放への長い道のり
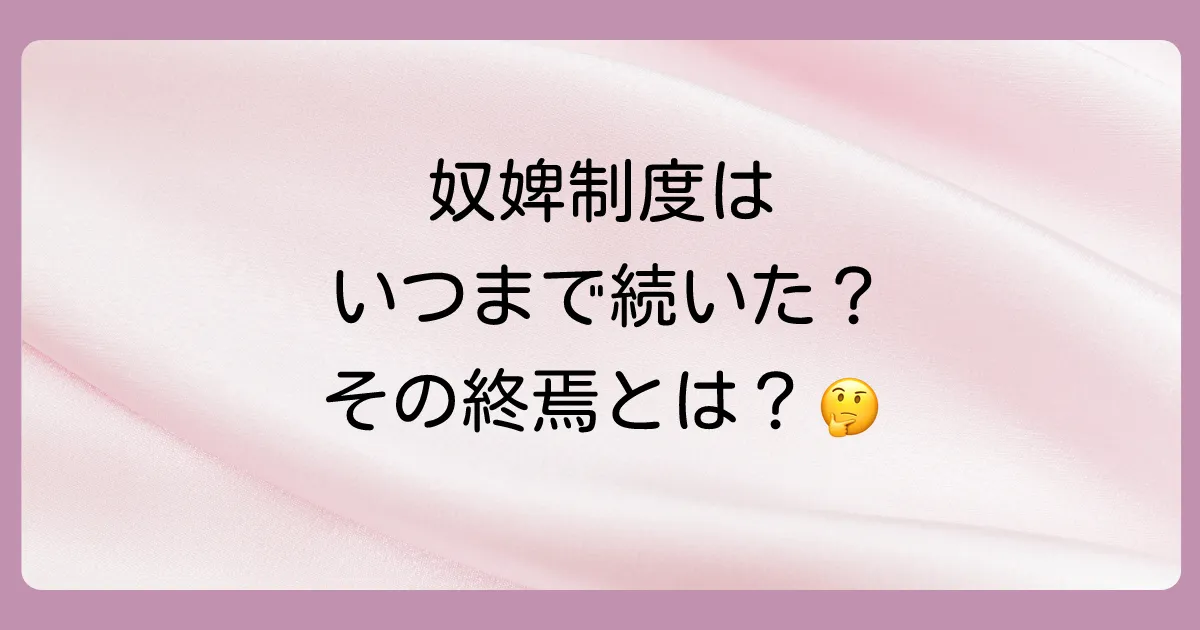
何世紀にもわたって朝鮮社会に存在し続けた奴婢制度。多くの人々を苦しめたこの制度は、いつ、どのようにして終わりを迎えたのでしょうか。その廃止に至るまでの歴史的な経緯と、制度がなくなった後も残った課題について解説します。
この章では、以下のポイントに焦点を当てます。
- 李氏朝鮮時代に最も固定化された身分制度
- 奴婢解放のきっかけとなった「甲午改革」
- 制度廃止後も残った社会的差別
李氏朝鮮時代に最も固定化された身分制度
奴婢制度は朝鮮の長い歴史の中で存在していましたが、特に李氏朝鮮時代(1392年~1910年)に最も強固な社会制度として確立されました。 支配階級である両班は、儒教的な秩序を社会の隅々まで浸透させ、自らの特権的な地位を維持するために、厳格な身分制度を必要としました。その結果、奴婢は人口の大きな割合を占めるようになり、社会の最下層に完全に固定化されてしまったのです。
もちろん、奴婢の数を減らそうとする王もいました。例えば、太宗や英祖は、奴婢の身分から解放される道を一部開く政策を行いました。 しかし、労働力を失うことを恐れた両班たちの強い反対に遭い、抜本的な改革には至りませんでした。 奴婢制度は、李氏朝鮮の社会と経済を根底で支える、不可欠な仕組みとなってしまっていたのです。
奴婢解放のきっかけとなった「甲午改革」
この長きにわたる奴婢制度に、ついに終止符が打たれるきっかけとなったのが、1894年の「甲午改革(こうごかいかく)」です。 甲午改革は、日清戦争を契機に、日本の影響下で進められた朝鮮の近代化改革運動です。
この改革の中で、旧来の封建的な身分制度の撤廃が宣言され、法的に奴婢制度は廃止されました。 これにより、奴婢は「所有物」としての身分から解放され、理論上は良民(平民)と同じ権利を持つことになったのです。これは、朝鮮の歴史における非常に大きな転換点であり、多くの人々が長年の隷属から解放される道が開かれた瞬間でした。
制度廃止後も残った社会的差別
法的に奴婢制度が廃止されたからといって、すぐに社会から差別がなくなったわけではありませんでした。何百年にもわたって人々の意識に深く根付いた差別観は、制度廃止後も根強く残り続けたのです。
奴婢出身であるというだけで、結婚や就職で差別を受けるといった問題は、その後も長く続きました。 1910年の日韓併合後、朝鮮総督府が旧来の身分を明記した戸籍を廃止し、新しい戸籍制度を導入したことで、ようやく法的な身分差別は完全に撤廃されました。 しかし、社会的な偏見や差別意識が完全に払拭されるまでには、さらに長い時間が必要でした。現代の韓国社会においても、その名残が全くないとは言い切れない、非常に根深い問題なのです。
よく混同される「奴婢」と「白丁」の決定的な違い
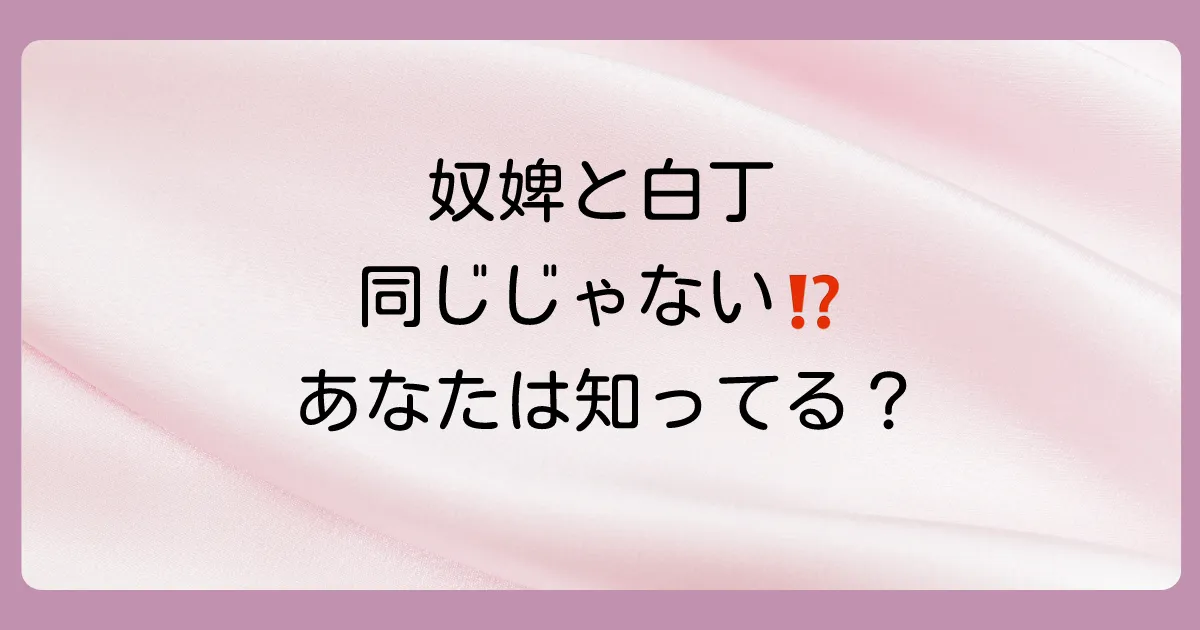
韓国の歴史における賤民を語る上で、奴婢とともによく名前が挙がるのが「白丁(ペクチョン)」です。両者はともに社会の最下層に置かれた人々ですが、その性質は大きく異なります。この違いを理解することで、朝鮮時代の社会構造をより深く知ることができます。
この章では、以下の2つの観点から違いを明確にします。
- 身分制度における位置づけの違い
- 従事する仕事内容の違い
身分制度における位置づけの違い
奴婢と白丁の最も決定的な違いは、「所有物」であったかどうかという点です。
前述の通り、奴婢は国や個人の「所有物」であり、財産として売買や相続の対象とされていました。 彼らは法的に奴隷身分であり、主人の支配下にありました。
一方、白丁は誰かの所有物ではありませんでした。 彼らは賤民という身分ではありましたが、法的には自由民に分類されることもありました。しかし、奴婢以上に厳しい社会的差別と蔑視を受けており、人間以下の存在と見なされることも少なくありませんでした。 例えば、白丁を殺害しても罪に問われないことさえあったと言われています。 つまり、奴婢は「法的な奴隷」、白丁は「法的には自由民だが、社会的には奴隷以下の扱いを受ける被差別民」という違いがあったのです。
従事する仕事内容の違い
両者は、従事する職業においても明確な違いがありました。
奴婢は、農業や家事など、主人の命令に応じてあらゆる種類の労働に従事しました。特定の職業に限定されていたわけではありません。
それに対して、白丁は特定の不浄(ふじょう)と見なされる職業に限定されていました。 その代表的なものが、動物の屠殺や皮革製品の加工、柳細工などです。 当時の儒教や仏教の価値観では、生き物を殺すことは穢(けが)れた行為とされており、そうした仕事に従事する白丁は社会から極度に疎外され、住む場所や服装、言葉遣いまで厳しく制限されていました。
| 奴婢(ヌヒ) | 白丁(ペクチョン) | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 法的な奴隷(国や個人の所有物) | 被差別民(所有物ではないが、強い社会的差別を受けた) |
| 主な仕事 | 農業、家事、雑用など全般 | 屠殺、皮革加工など特定の不浄視された職業 |
| 特徴 | 売買・相続の対象。身分は世襲。 | 居住地や服装、職業などが厳しく制限された。 |
よくある質問
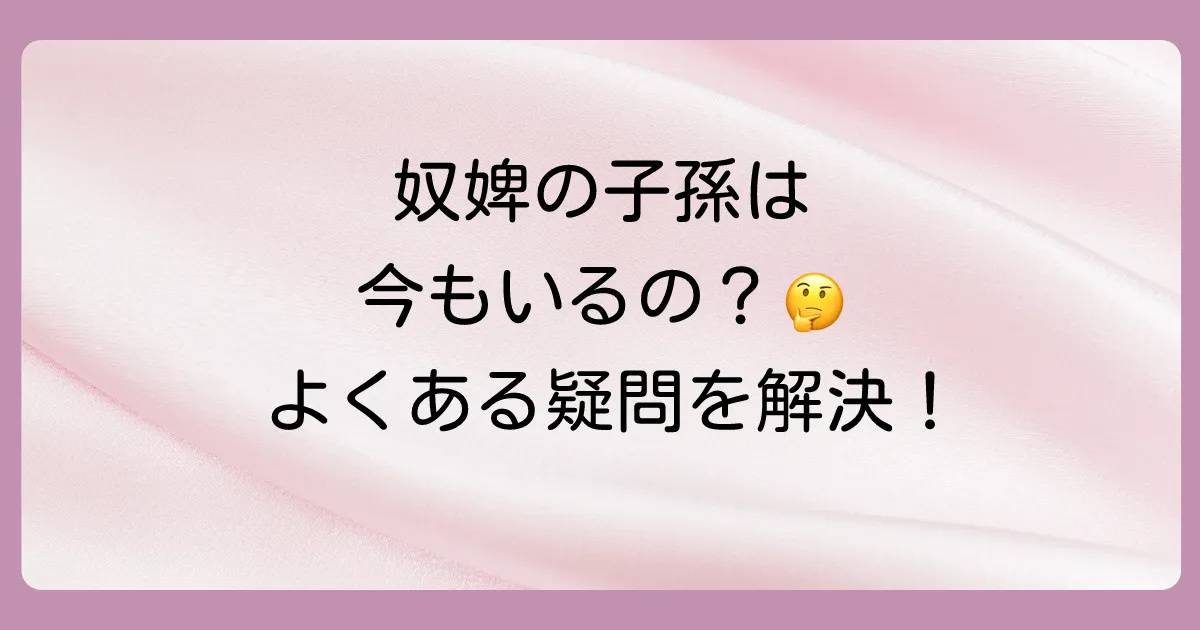
奴婢の子孫は現代の韓国にいますか?
法的な身分制度としての奴婢は1894年の甲午改革で廃止され、1910年の戸籍制度改革で完全に消滅しました。 そのため、現代の韓国に「奴婢」という身分は存在しません。しかし、歴史的に奴婢であった人々の家系が続いていることは事実です。朝鮮時代には人口の大きな割合を奴婢が占めていたため、多くの韓国人のルーツをたどれば、奴婢であった先祖に行き着く可能性は十分に考えられます。ただし、戸籍制度の変更や長い年月を経ているため、個人の家系を正確にさかのぼって奴婢であったかどうかを特定することは非常に困難です。
奴婢から両班になることは可能でしたか?
原則として、奴婢が支配階級である両班になることは不可能でした。身分は基本的に世襲であり、一度奴婢となれば、その子どもも孫も奴婢として生きるのが定めでした。 しかし、全く例外がなかったわけではありません。国の戦争などで大きな功績を立てた場合や、大金を国に納めることで、稀に賤民の身分から解放され、良民(常民)になることが許されるケースはありました。 それでも、そこからさらに科挙(官吏登用試験)に合格し、両班の地位にまで上り詰めるのは、天文学的な確率と言えるほど困難な道でした。
韓国ドラマで描かれる奴婢の姿は史実に基づいていますか?
多くの韓国歴史ドラマは、史実をベースにしながらも、ドラマティックな演出やフィクションが加えられています。 例えば、奴婢が経験した過酷な労働、売買の対象とされた悲劇、身分違いの恋の苦悩といった描写は、史実に基づいている部分が多いと言えます。 ドラマ『推奴(チュノ)』で描かれた逃亡奴婢を追う追跡者の存在も、当時の社会状況を反映したものです。 しかし、主人公が驚くべき能力を発揮したり、王族と深く関わったりする展開は、物語を面白くするための創作であることがほとんどです。ドラマはあくまでエンターテインメントとして楽しみつつ、その背景にある歴史的事実を知ることで、より深い理解が得られるでしょう。
奴婢の人口はどのくらいでしたか?
奴婢の人口割合は、時代や地域によって変動がありますが、特に李氏朝鮮時代にその数が増加しました。研究者によって見解は異なりますが、李氏朝鮮前期から中期にかけては、全人口の30%~40%を奴婢が占めていたという推計があります。 例えば、1690年の大邱地域の記録では、人口の約41%が奴婢であったとされています。 このように、奴婢は決して特殊な存在ではなく、朝鮮社会を構成する非常に大きな集団だったことがわかります。
まとめ
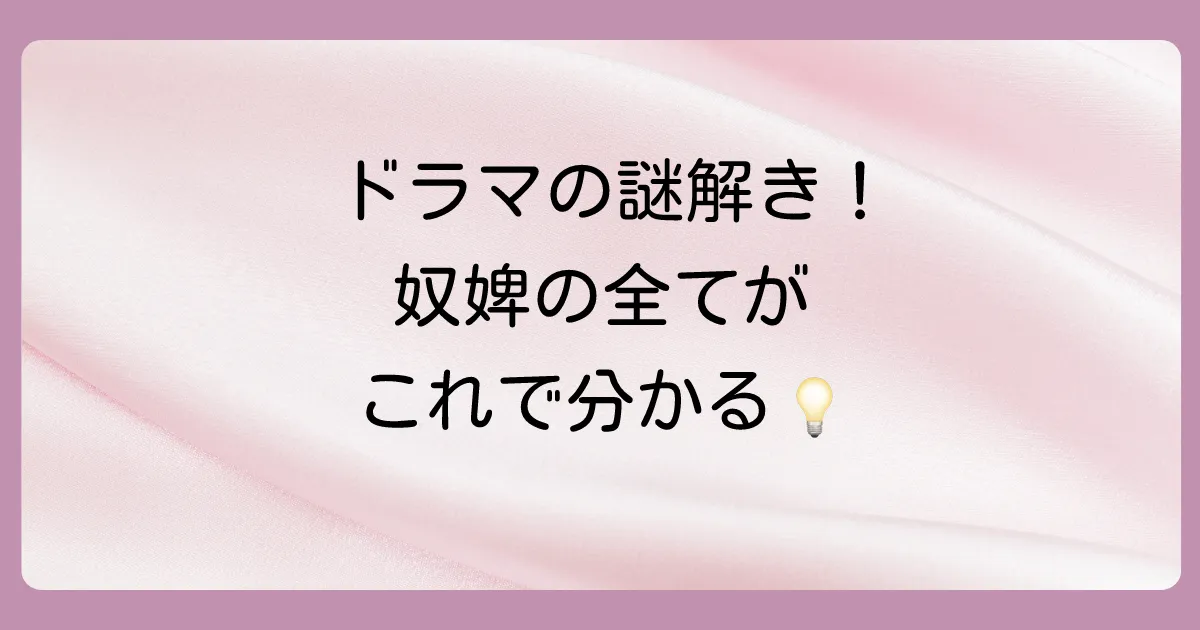
- 奴婢は韓国の歴史上の最下層の賤民でした。
- 彼らは人間ではなく主人の「所有物」と見なされました。
- 奴婢の身分は売買・相続の対象となりました。
- 奴婢制度は李氏朝鮮時代に最も固定化されました。
- 全人口の3~4割を奴婢が占めた時期もありました。
- 奴婢の身分は子孫に世襲されるのが原則でした。
- 過酷な労働を強いられ、逃亡は厳しく罰せられました。
- 国に属する「公奴婢」と個人所有の「私奴婢」がいました。
- 私奴婢には住み込みの「率居奴婢」と独立した「外居奴婢」がいました。
- 1894年の甲午改革によって法的に廃止されました。
- 制度廃止後も社会的な差別は根強く残りました。
- 「白丁」は所有物ではなく、職業が限定された被差別民でした。
- 奴婢と白丁は賤民の中でも異なる存在でした。
- 現代の韓国に奴婢という身分は存在しません。
- 韓国ドラマは史実を基にしたフィクションとして楽しむのがおすすめです。




