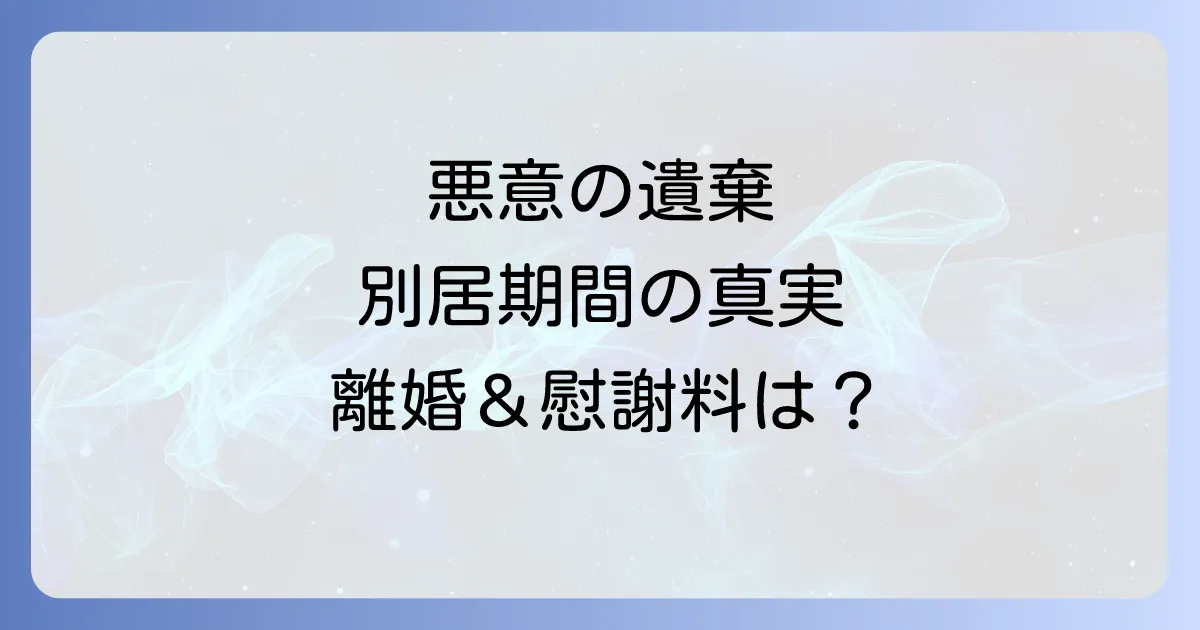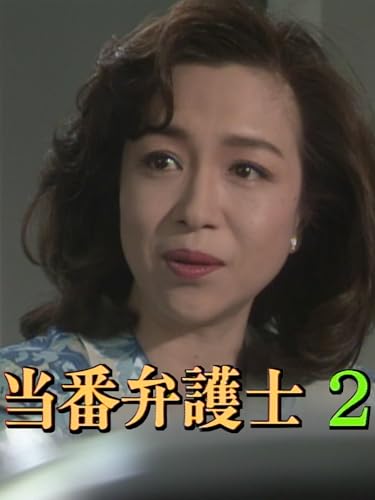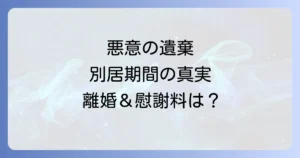夫婦関係の破綻は、誰にとってもつらい経験です。特に、配偶者から一方的に家を捨てられたり、生活費を打ち切られたりする「悪意の遺棄」に直面した場合、その精神的な苦痛は計り知れません。さらに、別居期間が長引く中で、「これは悪意の遺棄に当たるのだろうか」「離婚はできるのか」「慰謝料は請求できるのか」といった疑問や不安が募る方も多いでしょう。本記事では、悪意の遺棄と別居期間の関係に焦点を当て、その法的定義から具体的なケース、離婚や慰謝料請求のポイントまで、あなたの抱える疑問を解消するための情報をお届けします。一人で悩まず、正しい知識を得て、これからの人生を前向きに進むための一歩を踏み出しましょう。
悪意の遺棄とは?夫婦の義務と「悪意」の定義
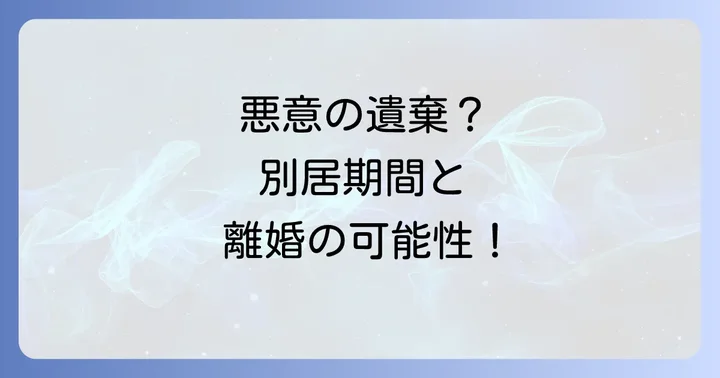
悪意の遺棄とは、民法で定められた夫婦の義務を、正当な理由なく意図的に果たさない行為を指します。これは、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」の一つであり、その成立にはいくつかの重要な要素があります。まず、夫婦には法律上、「同居」「協力」「扶助」という三大義務が課せられています。これらの義務は、単なる道徳的なものではなく、婚姻生活を維持するための基本的な責任として民法第752条に明記されています。もし、これらの義務が正当な理由なく履行されず、かつその行為に「悪意」が認められる場合、悪意の遺棄が成立する可能性があります。この「悪意」の有無が、悪意の遺棄を判断する上で非常に重要なポイントとなります。
夫婦に課される「同居」「協力」「扶助」の三大義務
夫婦が婚姻生活を送る上で、民法第752条によって定められているのが、以下の三つの義務です。これらの義務は、夫婦が共同生活を円満に営むための基盤となります。
- 同居義務:夫婦は同じ場所に住み、共同生活を送る義務があります。単に同じ屋根の下にいるだけでなく、夫婦としての実質的な生活を共にすることが求められます。
- 協力義務:夫婦は互いに協力し、家事や育児、家庭運営など、共同生活における様々な事柄を分担する義務があります。
- 扶助義務:夫婦は互いに経済的・精神的に支え合う義務があります。これには、衣食住の費用や医療費、子どもの養育費など、婚姻生活に必要な費用(婚姻費用)を分担することも含まれます。
これらの義務は、夫婦が互いに尊重し、助け合いながら生活していくための基本的なルールです。もし、これらの義務が一方的に、かつ正当な理由なく果たされない場合、悪意の遺棄と判断される可能性があります。
「悪意」とは夫婦関係の破綻を意図する気持ち
悪意の遺棄における「悪意」とは、単に義務を果たさないこと以上の意味を持ちます。ここでいう「悪意」とは、夫婦としての共同生活が破綻しても構わない、あるいは積極的に破綻させようという意図を指します。 例えば、単に仕事が忙しくて家事を手伝えなかったり、病気で一時的に生活費を支払えなかったりするだけでは、「悪意」があるとは認められません。しかし、配偶者が困窮していることを知りながら意図的に生活費を送らなかったり、夫婦関係の修復を求める相手の連絡を無視し続けたりする行為は、「悪意」があると判断される可能性が高まります。裁判所は、悪意の有無を判断する際に、その行為に至った経緯、夫婦の関係性、別居後の生活状況、子どもの有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。 この「悪意」の立証が、悪意の遺棄を主張する上で最も難しい点の一つと言えるでしょう。
別居期間は悪意の遺棄にどう影響する?期間の目安と判断基準
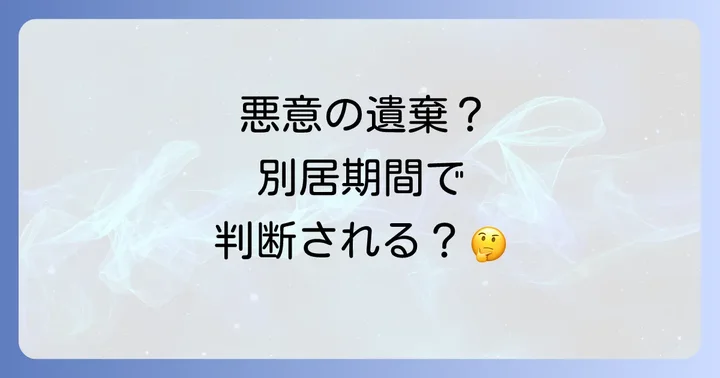
悪意の遺棄を考える上で、「どのくらいの別居期間があれば悪意の遺棄と認められるのか」という疑問は多くの方が抱くものです。しかし、結論から言えば、悪意の遺棄の成立に法律で明確な別居期間の定めはありません。 重要なのは、別居の期間そのものよりも、その別居が「正当な理由なく」「悪意を持って」行われたかどうかという点です。ただし、義務違反の状態が「一定期間継続していること」も要件の一つとされており、期間が全く考慮されないわけではありません。裁判例では、個別の事情に応じて判断が分かれるため、一概に「〇ヶ月以上」と言い切ることは難しいのが実情です。
悪意の遺棄に明確な別居期間の定めはない
民法には、悪意の遺棄が成立するための具体的な別居期間は明記されていません。これは、夫婦関係の状況が多岐にわたるため、一律の期間を設けることが現実的ではないからです。例えば、一方的な別居であっても、その背後にDVやモラハラといった正当な理由があれば、悪意の遺棄とは認められません。逆に、別居期間が短くても、配偶者が不倫相手と同棲するために家を出た場合など、悪意が明確であれば悪意の遺棄と判断されることもあります。 裁判所は、別居の経緯、期間中の夫婦のやり取り、生活費の支払い状況、子どもの養育状況など、あらゆる事情を総合的に評価して、悪意の遺棄の有無を判断します。そのため、期間の長さだけにとらわれず、別居に至った背景やその後の行動が重要になります。
短期間の別居が悪意の遺棄と認められないケース
一時的な別居や、夫婦関係の冷却期間を目的とした別居は、通常、悪意の遺棄とは認められません。例えば、夫婦喧嘩がエスカレートし、一時的に実家に身を寄せた場合や、夫婦関係を見つめ直すために話し合いの上で一定期間距離を置く場合などがこれに該当します。 また、単身赴任や病気療養、親の介護など、やむを得ない事情による別居も、正当な理由があるため悪意の遺棄には当たりません。 悪意の遺棄が成立するためには、義務違反が「一定期間継続していること」が必要とされており、一時的な状況ではこの要件を満たさないと考えられています。 重要なのは、その別居が夫婦共同生活を破綻させる意図を持って行われたものではない、という点です。
長期間の別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」となる場合
悪意の遺棄が認められない場合でも、長期間の別居は離婚の理由となることがあります。民法第770条1項5号には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という法定離婚事由が定められており、夫婦関係が完全に破綻していると判断されるほどの長期間の別居がこれに該当する場合があります。一般的に、裁判で「婚姻関係が破綻している」と認められるには、3年から5年程度の別居期間が目安とされています。 この場合、悪意の遺棄のように「悪意」の立証は不要ですが、夫婦関係が修復不可能な状態にあることを客観的に示す必要があります。悪意の遺棄と「婚姻を継続し難い重大な事由」は異なる離婚事由であり、それぞれ立証すべき内容が異なります。
悪意の遺棄が認められる具体的なケース
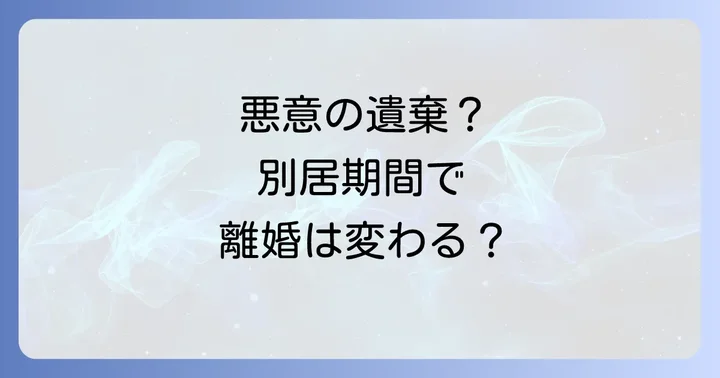
悪意の遺棄は、夫婦の同居・協力・扶助義務のいずれか、または複数を正当な理由なく果たさない場合に成立します。具体的な状況は多岐にわたりますが、ここでは特に悪意の遺棄と認められやすい典型的なケースを解説します。これらの事例は、あなたが直面している状況が法的にどのように評価されるかの参考になるでしょう。ただし、個々のケースは複雑であり、最終的な判断は裁判所が行うため、あくまで目安として捉えることが大切です。
正当な理由なく家を出て同居を拒否する
配偶者が正当な理由もなく一方的に家を出て、同居を拒否し続ける行為は、同居義務違反として悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。例えば、何の相談もなく突然家を出て行き、連絡も取れなくなるケースや、夫婦関係の修復を求めても頑なに同居を拒否し続けるケースなどがこれに当たります。 特に、不倫相手と同棲するために家を出た場合などは、夫婦共同生活を破綻させる明確な「悪意」があると判断されやすいでしょう。 ただし、DVやモラハラから逃れるための別居や、夫婦間で合意した上での冷却期間としての別居は、正当な理由があるため悪意の遺棄には当たりません。別居の理由や経緯が、悪意の有無を判断する上で非常に重要となります。
生活費を支払わない「扶助義務違反」
夫婦には互いに扶助する義務があり、経済的に支え合うことも含まれます。そのため、健康で働く能力があるにもかかわらず、正当な理由なく配偶者や子どもに生活費(婚姻費用)を支払わない行為は、扶助義務違反として悪意の遺棄に該当します。 例えば、収入があるにもかかわらず、一方的に生活費の送金を停止したり、婚姻費用分担調停で定められた金額を支払わなかったりするケースがこれに当たります。 特に、遺棄された側が経済的に困窮し、生活に支障をきたしている状況であれば、悪意の遺棄と認められる可能性はさらに高まります。 ただし、病気や失業など、やむを得ない事情で一時的に生活費を支払えない場合は、悪意の遺棄とは判断されないことがあります。重要なのは、「正当な理由なく」「悪意を持って」支払いを拒否しているかどうかです。
家事や育児を放棄する「協力義務違反」
夫婦は互いに協力し、共同生活を営む義務があります。そのため、健康であるにもかかわらず、正当な理由なく家事や育児を全く行わない、あるいは一方的に配偶者に押し付ける行為は、協力義務違反として悪意の遺棄に該当する可能性があります。 例えば、共働きであるにもかかわらず、家事や育児の全てを配偶者に任せきりにし、自分は一切関わろうとしないケースなどが考えられます。また、子どもが病気であるにもかかわらず、看病や世話を拒否するような行為も、悪意の遺棄と判断されることがあります。 ただし、病気や怪我で一時的に家事や育児ができない場合や、夫婦間で役割分担について合意がある場合は、悪意の遺棄には当たりません。ここでも、「正当な理由」と「悪意」の有無が重要な判断要素となります。
配偶者を家から追い出す行為
自らが家を出るだけでなく、配偶者を家から追い出す行為も、悪意の遺棄に該当します。これは、同居義務の積極的な違反とみなされます。例えば、暴力や暴言によって配偶者を精神的に追い詰め、家にいられない状況にしたり、物理的に鍵を交換して家に入れないようにしたりする行為などがこれに当たります。 このような行為は、夫婦共同生活を意図的に破壊しようとする「悪意」が非常に強く認められるため、悪意の遺棄として離婚や慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。特に、子どもがいる家庭でこのような行為が行われた場合、その悪質性はさらに高く評価される傾向にあります。
悪意の遺棄と判断されない「正当な理由」がある別居
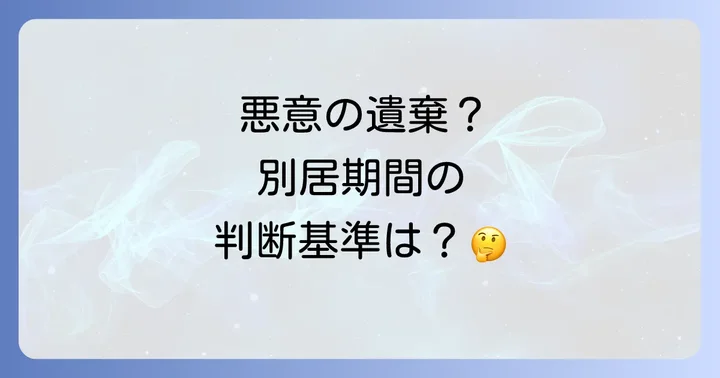
別居しているからといって、全てが悪意の遺棄と判断されるわけではありません。夫婦の同居・協力・扶助義務を一時的に果たせない状況であっても、そこに「正当な理由」があれば、悪意の遺棄には該当しません。この「正当な理由」の有無が、悪意の遺棄の成立を左右する重要なポイントとなります。ここでは、どのような場合に正当な理由があると認められるのか、具体的なケースを挙げて解説します。あなたの別居がこれらのケースに当てはまるかどうか、確認してみましょう。
仕事上の都合による単身赴任や転勤
夫婦の一方が仕事の都合で単身赴任や転勤となり、一時的に別居を余儀なくされるケースは、悪意の遺棄とは認められません。 これは、夫婦の意思に反して生じた状況であり、夫婦共同生活を破綻させる意図がないためです。単身赴任中も、定期的に連絡を取り合ったり、帰省したり、生活費を送ったりしていれば、夫婦としての協力・扶助義務を果たしていると見なされます。ただし、単身赴任を口実に不倫相手と同棲を開始したり、一切連絡を絶って生活費も送らなくなったりした場合は、その状況が悪意の遺棄と判断される可能性が出てきます。あくまで、仕事上の必要性に基づく誠実な別居であることが前提となります。
DVやモラハラから避難するための別居
配偶者からのDV(家庭内暴力)やモラハラ(精神的暴力)に耐えかねて、身の安全を守るために別居を開始するケースは、正当な理由がある別居として悪意の遺棄には当たりません。 むしろ、DVやモラハラを行った配偶者側に、婚姻関係を破綻させた責任があると判断される可能性が高いでしょう。このような状況での別居は、自己防衛のためのやむを得ない行動であり、夫婦共同生活を破綻させる「悪意」があるとは言えません。むしろ、被害者側が悪意の遺棄を主張できる立場になることもあります。証拠として、診断書や警察への相談記録、DV相談機関の記録などを残しておくことが重要です。
夫婦間の合意に基づく別居や冷却期間
夫婦がお互いの合意の上で別居を開始したり、関係修復のための冷却期間として一時的に距離を置いたりするケースも、悪意の遺棄には該当しません。 この場合、夫婦双方に共同生活を破綻させる意図がないため、「悪意」の要件を満たさないからです。例えば、夫婦喧嘩が頻繁になり、冷静に話し合うために一時的に別居する、あるいは子どもの教育環境のために別居婚を選択するなどが考えられます。重要なのは、別居の目的が夫婦関係の破綻ではなく、関係の改善や特定の目的達成にあること、そして夫婦双方の合意があることです。合意の証拠として、別居期間や生活費の分担などについて書面で取り交わしておくことが望ましいでしょう。
病気療養や親の介護のための別居
夫婦の一方または双方が病気の療養のために実家に戻ったり、高齢の親の介護のために別居したりするケースも、正当な理由がある別居として悪意の遺棄には当たりません。 これらの状況は、夫婦の意思とは関係なく生じるやむを得ない事情であり、夫婦共同生活を破綻させる意図がないためです。このような場合でも、夫婦としての連絡を取り合ったり、可能な範囲で扶助し合ったりすることが期待されます。例えば、介護のために別居していても、定期的に相手の元を訪れたり、経済的な支援を続けたりしていれば、夫婦としての義務を果たしていると見なされるでしょう。重要なのは、その別居が真にやむを得ない事情に基づくものであることです。
悪意の遺棄で離婚は可能?慰謝料請求と婚姻費用
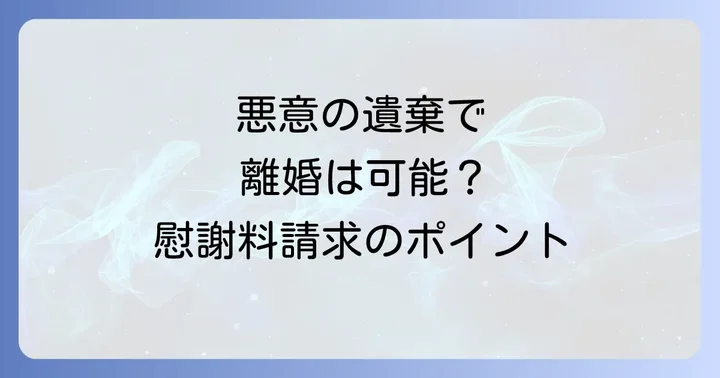
もし配偶者の行為が悪意の遺棄と認められた場合、あなたは法的にどのような権利を行使できるのでしょうか。悪意の遺棄は、離婚の理由となるだけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。また、別居中の生活を支えるための婚姻費用についても知っておく必要があります。ここでは、悪意の遺棄が認められた場合の具体的な法的措置と、その際に知っておくべき重要なポイントについて詳しく解説します。
悪意の遺棄は法定離婚事由の一つ
悪意の遺棄は、民法第770条1項2号に定められた法定離婚事由の一つです。 これは、配偶者が離婚に同意しない場合でも、裁判所に悪意の遺棄があったと認められれば、裁判官の判決によって強制的に離婚が成立することを意味します。協議離婚や調停離婚では離婚理由を問われませんが、裁判離婚では法定離婚事由の存在を立証する必要があります。悪意の遺棄を理由に離婚を請求する場合、その事実を裏付ける証拠を十分に集めることが不可欠です。また、悪意の遺棄は、婚姻関係を破綻させた原因として、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めないという原則にも影響します。 つまり、悪意の遺棄をした側からの離婚請求は、非常に難しいのが実情です。
悪意の遺棄による慰謝料の相場と増額要素
悪意の遺棄は、配偶者に精神的苦痛を与える不法行為であるため、その損害賠償として慰謝料を請求することができます。 悪意の遺棄による慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度とされています。 しかし、この金額はあくまで目安であり、個別の事情によって大きく変動します。慰謝料の金額を決定する際には、以下のような要素が考慮され、増額される可能性があります。
- 悪意の遺棄の期間が長期間にわたる場合
- 悪意の遺棄の態様が著しく悪質である場合
- 夫婦間に未成熟の子どもがいる場合
- 婚姻期間が長い場合
- 悪意の遺棄をした配偶者に反省の態度が見られない場合
- 悪意の遺棄に加えて、不貞行為など他の離婚原因がある場合
これらの要素を具体的に立証することで、より高額な慰謝料が認められる可能性が高まります。慰謝料請求には時効があるため、注意が必要です。
別居中の生活を支える婚姻費用の重要性
夫婦は、離婚が成立するまで、互いに生活費を分担する「扶助義務」を負っています。この生活費を「婚姻費用」と呼びます。たとえ別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が継続しているため、収入の少ない側は収入の多い側に対して婚姻費用を請求することができます。 配偶者が正当な理由なく婚姻費用を支払わない場合、それは扶助義務違反となり、悪意の遺棄と判断される可能性があります。 婚姻費用は、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費や教育費など、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な一切の費用を指します。婚姻費用の請求は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで行えます。別居中の生活を安定させるためにも、婚姻費用の請求は非常に重要です。
悪意の遺棄をした側(有責配偶者)からの離婚請求
悪意の遺棄を行った配偶者は、「有責配偶者」とみなされます。日本の裁判実務では、婚姻関係を破綻させた原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないとされています。 これは、自らの責任で夫婦関係を破綻させた者が、一方的に離婚を求めることを許さないという考え方に基づいています。ただし、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。それは、相当長期の別居期間が経過しており、未成熟の子どもがいない、かつ相手方配偶者が離婚によって精神的・経済的に過酷な状況に置かれないなど、特別な事情がある場合に限られます。 このように、悪意の遺棄をした側からの離婚は非常にハードルが高いことを理解しておく必要があります。
悪意の遺棄を証明するために必要な証拠
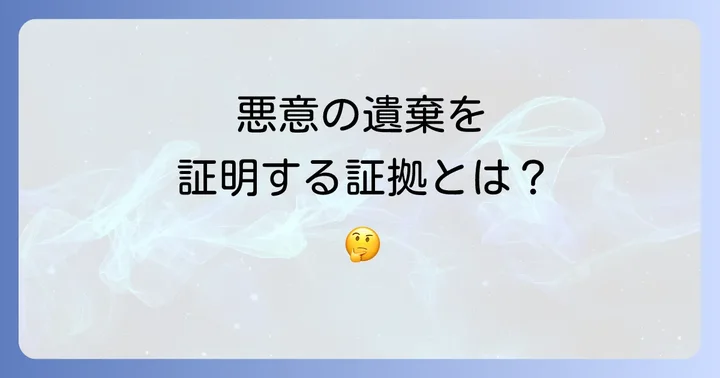
悪意の遺棄を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、その事実を客観的に証明するための証拠が不可欠です。口頭での主張だけでは、裁判所に悪意の遺棄があったと認めてもらうことは困難です。どのような証拠が有効となるのか、具体的に解説します。証拠は、「同居義務違反」「協力義務違反」「扶助義務違反」のいずれか、または複数を裏付けるものである必要があります。 証拠集めは精神的に負担が大きい作業ですが、あなたの権利を守るために非常に重要です。
別居の事実を裏付ける証拠
配偶者の一方的な別居が悪意の遺棄に当たることを証明するためには、まず別居の事実そのものを客観的に示す証拠が必要です。具体的には、以下のようなものが有効です。
- 住民票の写し:別居している住所が異なることを示します。
- 賃貸借契約書や光熱費の領収書:別居先の住居に関する契約書や、光熱費の支払い状況から、別居の事実を裏付けられます。
- 郵便物:別居先に届いた郵便物も証拠となり得ます。
- 日記や家計簿:別居開始日や、その後の生活状況を記録したものは、状況を把握する上で役立ちます。
これらの証拠は、配偶者が正当な理由なく同居義務を怠っていることを示すために重要です。特に、一方的な別居の経緯がわかるメールやLINEのやり取りがあれば、悪意の有無を判断する上で強力な証拠となります。
生活費の不払いを証明する証拠
扶助義務違反、特に生活費の不払いを証明するためには、以下のような経済的な証拠が有効です。
- 銀行の通帳や取引明細:生活費が振り込まれなくなった、あるいは不足している状況を客観的に示します。
- 家計簿:生活費の不足により、家計が困窮している状況を具体的に記録したものです。
- 給与明細や源泉徴収票:配偶者の収入があるにもかかわらず、生活費が支払われていないことを示すために必要となる場合があります。
- 婚姻費用分担調停の記録:調停で決定した婚姻費用が支払われていないことを証明します。
これらの証拠は、配偶者が経済的な扶助義務を怠っていることを明確に示し、悪意の遺棄の成立を裏付ける重要な要素となります。特に、配偶者に収入があるにもかかわらず、意図的に生活費を支払わない状況を証明することが重要です。
同居・協力・扶助義務違反を示す客観的な証拠
別居の事実や生活費の不払い以外にも、同居・協力・扶助義務違反を示す様々な証拠があります。これらは、配偶者の「悪意」を立証するために役立ちます。
- メールやLINEの履歴:夫婦関係の修復を求めたのに拒否されたやり取り、別居の理由を尋ねても返事がないやり取り、不倫相手とのやり取りなどが有効です。
- 話し合いの録音:同居や生活費の支払いについて話し合った際の録音は、配偶者の態度や意図を示す重要な証拠となり得ます。
- 日記やメモ:配偶者の義務違反行為(家事・育児の放棄、暴言など)や、それによって受けた精神的苦痛を詳細に記録したものです。
- 健康診断の結果や診断書:働ける能力があるにもかかわらず働かないケースで、就労能力があることを示すために利用できます。
- 第三者の証言:友人や親族など、夫婦の状況を知る第三者の証言も、証拠の一つとなり得ます。
これらの証拠を多角的に集めることで、悪意の遺棄の事実をより強固に立証し、あなたの主張を裁判所に認めてもらう可能性を高めることができます。
悪意の遺棄に関するよくある質問
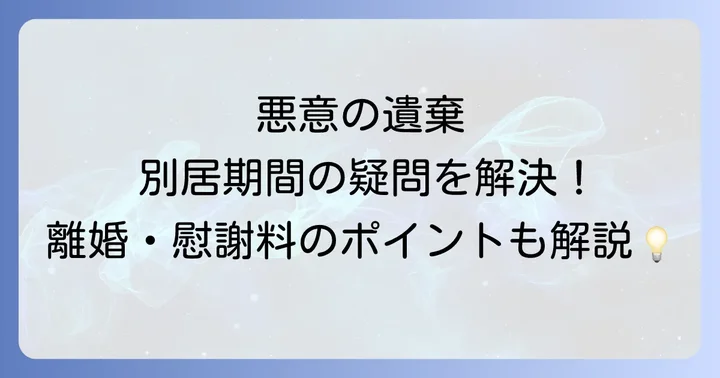
悪意の遺棄と別居期間について、多くの方が抱える疑問にお答えします。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問をまとめました。あなたの疑問解決の一助となれば幸いです。
- 悪意の遺棄はどのくらいの期間で成立しますか?
- 悪意の遺棄で離婚すると慰謝料はいくらですか?
- 悪意の遺棄の証拠は何ですか?
- 悪意の遺棄に該当しないケースは?
- 別居期間が長いと悪意の遺棄になりますか?
- 生活費を払わないと悪意の遺棄になりますか?
悪意の遺棄はどのくらいの期間で成立しますか?
悪意の遺棄の成立に、法律で明確な別居期間の定めはありません。重要なのは、正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を意図的に果たさない「悪意」があるかどうかです。ただし、義務違反の状態が「一定期間継続していること」も要件の一つとされており、一時的な別居では認められにくい傾向にあります。学説では、少なくとも6ヶ月以上の別居期間が必要であるとする見解もありますが、個別の事情によって判断は異なります。
悪意の遺棄で離婚すると慰謝料はいくらですか?
悪意の遺棄による慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度です。 金額は、悪意の遺棄の期間、悪質性、夫婦の婚姻期間、未成熟の子どもの有無、遺棄した側の反省の態度など、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。悪質性が高い場合や、他の離婚原因(不貞行為など)が重なる場合は、増額される可能性があります。
悪意の遺棄の証拠は何ですか?
悪意の遺棄の証拠としては、以下のようなものが有効です。
- 別居の事実を示すもの:住民票、賃貸借契約書、光熱費の領収書など。
- 生活費の不払いを証明するもの:銀行の通帳、取引明細、家計簿など。
- 義務違反や悪意を示すもの:メールやLINEのやり取り(同居拒否、連絡無視、不倫相手とのやり取りなど)、話し合いの録音、日記、第三者の証言など。
これらの証拠をできるだけ多く集めることが、悪意の遺棄を立証する上で重要です。
悪意の遺棄に該当しないケースは?
以下のような場合は、正当な理由があるため悪意の遺棄には該当しません。
- 仕事上の都合による単身赴任や転勤。
- DVやモラハラから避難するための別居。
- 夫婦間の合意に基づく別居や冷却期間。
- 病気療養や親の介護のための別居。
- 病気や失業など、やむを得ない事情で一時的に生活費を支払えない場合。
- 婚姻関係がすでに破綻した後に別居した場合。
重要なのは、夫婦共同生活を破綻させる「悪意」がないことです。
別居期間が長いと悪意の遺棄になりますか?
別居期間が長いこと自体が悪意の遺棄に直結するわけではありません。悪意の遺棄の成立には「悪意」が不可欠です。しかし、正当な理由なく長期間別居し、かつ生活費を支払わないなどの義務違反が継続している場合は、悪意の遺棄と判断される可能性が高まります。また、悪意の遺棄と認められなくても、3年から5年程度の長期間の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」として、別の離婚原因となることがあります。
生活費を払わないと悪意の遺棄になりますか?
はい、健康で働く能力があるにもかかわらず、正当な理由なく配偶者や子どもに生活費(婚姻費用)を支払わない行為は、扶助義務違反として悪意の遺棄に該当する可能性が非常に高いです。 特に、遺棄された側が経済的に困窮している状況であれば、悪意の遺棄と認められる可能性はさらに高まります。ただし、病気や失業など、やむを得ない事情で一時的に支払えない場合は、悪意の遺棄とは判断されないことがあります。
まとめ
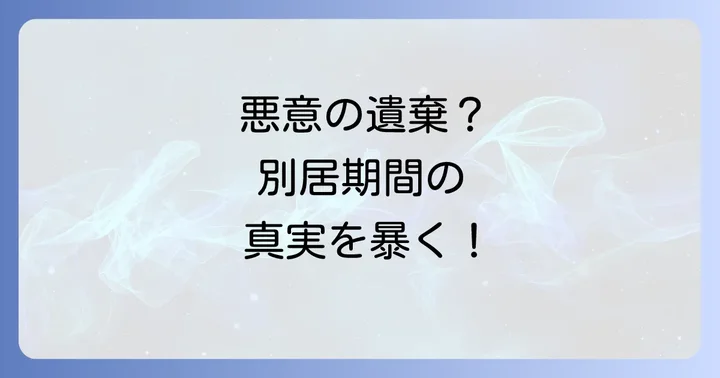
悪意の遺棄と別居期間に関する重要なポイントをまとめました。
- 悪意の遺棄は民法上の法定離婚事由の一つです。
- 夫婦には同居・協力・扶助の三大義務があります。
- 「悪意」とは夫婦関係を破綻させる意図を指します。
- 悪意の遺棄に明確な別居期間の定めはありません。
- 期間より「悪意」と「正当な理由」の有無が重要です。
- 短期間の別居は悪意の遺棄と認められにくいです。
- 長期間の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」となり得ます。
- 正当な理由のない一方的な別居は悪意の遺棄です。
- 生活費の不払いは扶助義務違反として悪意の遺棄です。
- 家事や育児の放棄も協力義務違反となり得ます。
- DVやモラハラからの避難は正当な理由です。
- 合意に基づく別居も正当な理由とされます。
- 悪意の遺棄で離婚と慰謝料請求が可能です。
- 慰謝料相場は50万円から300万円程度です。
- 別居中でも婚姻費用を請求する権利があります。