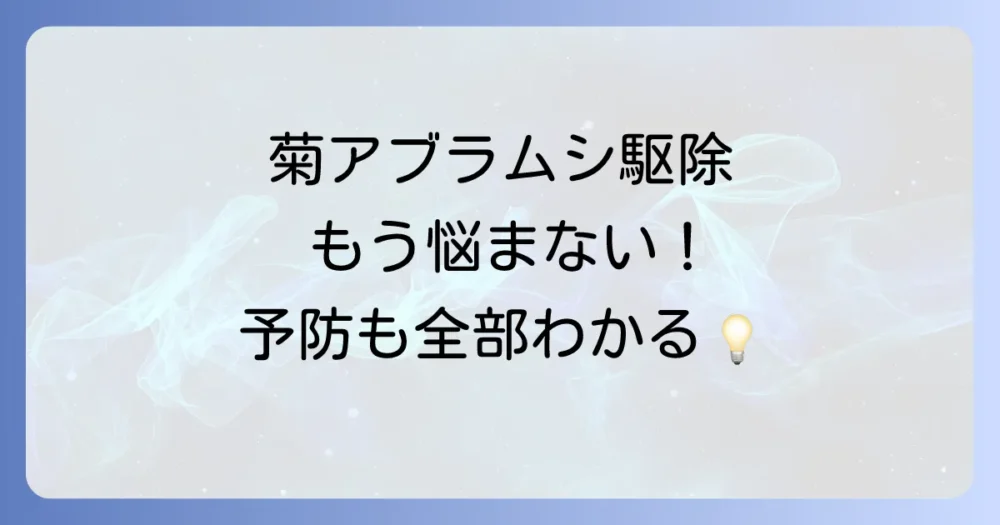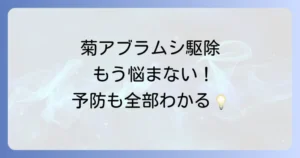大切に育てている菊に、緑や黒の小さな粒がびっしり…。その正体は、植物の汁を吸って弱らせてしまうアブラムシです。見た目の不快感はもちろん、病気の原因にもなるため、見つけたらすぐに対処したいですよね。本記事では、菊をアブラムシの被害から守るための具体的な駆除方法から、厄介なアブラムシを二度と寄せ付けないための予防策まで、詳しく解説していきます。
今すぐできる!菊のアブラムシ駆除方法
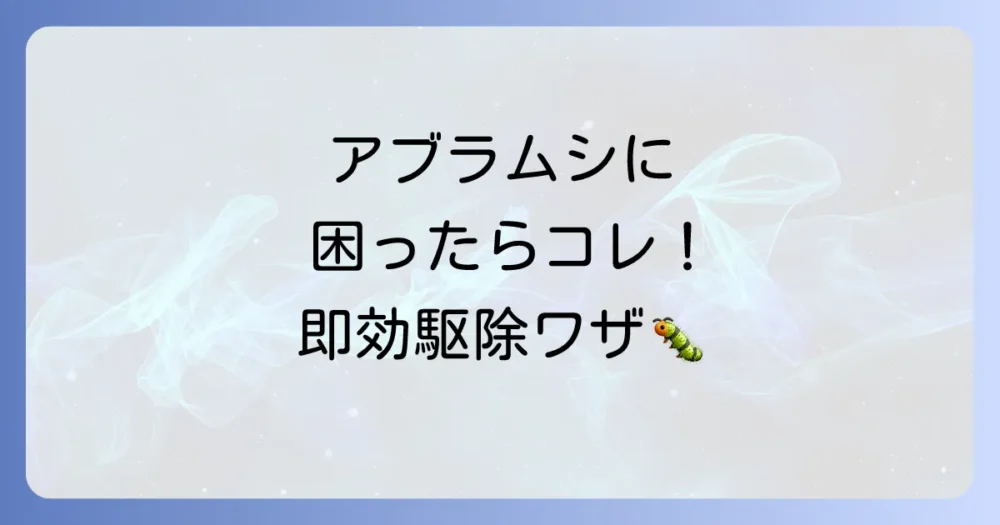
菊にアブラムシを見つけたら、とにかく早めの対処が肝心です。アブラムシは驚異的な繁殖力であっという間に増えてしまいます。ここでは、状況に合わせて選べる駆除方法を「薬剤を使わない手軽な方法」と「薬剤を使った確実な方法」に分けてご紹介します。
- 【薬剤を使わない】手軽にできる駆除方法
- 【薬剤を使う】確実&効果的な駆除方法
【薬剤を使わない】手軽にできる駆除方法
「できるだけ薬剤は使いたくない」「食べる予定の菊だから安全な方法がいい」という方におすすめの方法です。ご家庭にあるもので手軽に試せるのが魅力ですが、効果が穏やかなため、こまめなチェックと繰り返し行うことが大切です。
牛乳スプレー
牛乳を水で1:1の割合で薄めたものをスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接吹きかけます。牛乳が乾くときに膜を作り、アブラムシの気門(呼吸するための穴)を塞いで窒息させる効果が期待できます。 よく晴れた日の午前中に行うのがおすすめです。ただし、散布後に牛乳をそのままにしておくと、臭いやカビの原因になるため、牛乳が乾いたら必ず水でしっかりと洗い流しましょう。
木酢液・食酢スプレー
木酢液や食酢を水で薄めてスプレーする方法も有効です。木酢液は独特の燻製のような香りでアブラムシを寄せ付けにくくします。 食酢にも同様の効果が期待できます。希釈倍率は製品によって異なりますが、一般的に木酢液は100~500倍、食酢は25~50倍程度が目安です。 濃度が濃すぎると菊自体を傷めてしまう可能性があるので注意してください。
粘着テープで取り除く
アブラムシの数が少ない初期段階であれば、ガムテープやセロハンテープなどの粘着テープでペタペタと貼り付けて取り除く物理的な方法も簡単で効果的です。 菊の葉や茎を傷つけないように、粘着力が強すぎないテープを選ぶのがコツです。
水で洗い流す
ホースやシャワーで勢いよく水をかけて、アブラムシを物理的に洗い流す方法です。 特に新芽や葉の裏など、アブラムシが密集しやすい場所を狙って行いましょう。ただし、水の勢いが強すぎると植物を傷める原因になるため、力加減には注意が必要です。
【薬剤を使う】確実&効果的な駆除方法
アブラムシが大量発生してしまった場合や、手軽に、そして確実に駆除したい場合には、市販の殺虫剤の使用がおすすめです。園芸用の薬剤は様々な種類がありますので、用途に合ったものを選びましょう。
スプレータイプ(速効性)
見つけたアブラムシに直接吹きかけて駆除するタイプです。速効性が高く、すぐに効果を実感したい方におすすめです。商品によっては、病気の予防も同時にできるものもあります。
- 住友化学園芸 ベニカXファインスプレー: 害虫への速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)が特長です。 病気の予防効果も兼ね備えています。
- フマキラー カダンプラスDX: 害虫と病気を1本で対策でき、予防効果も期待できます。 浸透移行性で葉の裏に隠れた虫にも効果があります。
- アース製薬 ロハピ: 食品原料99.9%でできているため、安心して使いやすい殺虫殺菌剤です。 収穫前日まで使用できる野菜も多いのが特徴です。
粒剤タイプ(持続性)
植物の株元にまくことで、有効成分が根から吸収され、植物全体に行き渡るタイプです。効果が長期間持続するのが最大のメリットで、アブラムシの予防にも繋がります。
- 住友化学園芸 GFオルトラン粒剤: 土に混ぜたりばらまくだけで効果が持続する浸透移行性の殺虫剤です。 幅広い植物に使え、アブラムシには約2~3週間の効果が期待できます。
薬剤を使用する際は、必ず製品のラベルに記載されている使用方法や回数、対象植物などをよく読んでから正しく使用してください。特に、食用菊の場合は、収穫時期や使用できる薬剤が限られている場合があるので注意が必要です。
なぜ菊にアブラムシが?発生の3大原因
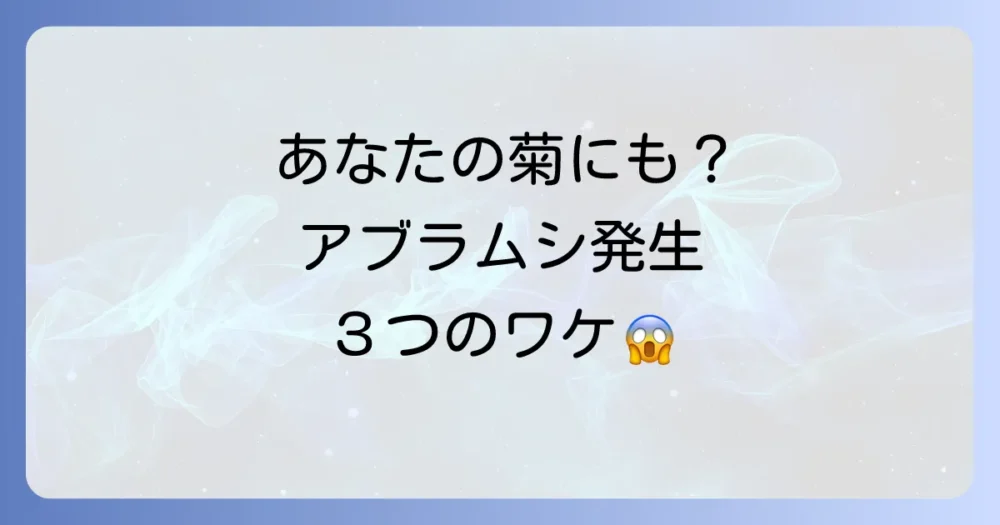
駆除と同時に、なぜアブラムシが発生したのか原因を知ることが、再発防止への第一歩です。アブラムシが好む環境を作ってしまっていないか、チェックしてみましょう。
- 原因1:窒素(チッソ)肥料の与えすぎ
- 原因2:日当たりや風通しの悪さ
- 原因3:どこからか飛んでくる
原因1:窒素(チッソ)肥料の与えすぎ
植物の葉や茎を大きくするために必要な窒素ですが、与えすぎは禁物です。窒素成分が過剰になると、植物体内のアミノ酸が増加します。このアミノ酸はアブラムシの大好物であるため、結果的にアブラムシを呼び寄せてしまうのです。 元気な菊を育てたいという思いが、かえって害虫の発生原因になることもあるので、肥料は適量を守ることが重要です。
原因2:日当たりや風通しの悪さ
葉が密集して茂りすぎている場所は、日当たりが悪く、風通しも滞りがちになります。このようなジメジメした環境は、アブラムシにとって格好の隠れ家となり、繁殖を促してしまいます。 また、風通しが悪いと薬剤を散布しても隅々まで行き渡りにくく、駆除しきれない原因にもなります。定期的な剪定などで、株全体の風通しを良く保つことが大切です。
原因3:どこからか飛んでくる
アブラムシは、ある程度数が増えると、羽の生えた「有翅虫(ゆうしちゅう)」が現れます。 この有翅虫が風に乗って飛んできて、新しい住処としてあなたの菊に住み着き、そこでまた繁殖を始めます。どんなに庭を綺麗にしていても、外部からの飛来によってアブラムシが発生する可能性は常にあります。そのため、日頃からの予防策が非常に重要になってくるのです。
もう寄せ付けない!菊のアブラムシ徹底予防策
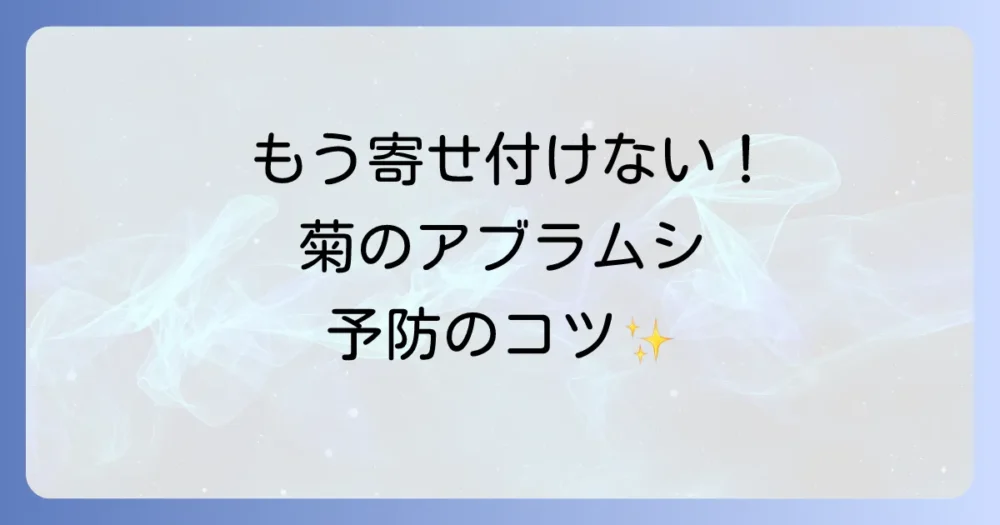
一度アブラムシを駆除しても、再発しては意味がありません。ここでは、アブラムシが寄り付きにくい環境を作るための予防策をご紹介します。日々のちょっとした心がけで、大切な菊を害虫から守りましょう。
- 栽培環境を見直す
- 天敵を味方につける
- コンパニオンプランツを活用する
栽培環境を見直す
アブラムシの発生を抑える基本は、菊が健康に育つ環境を整えることです。
適切な肥料管理
前述の通り、窒素肥料の与えすぎはアブラムシを呼び寄せます。 菊の肥料を選ぶ際は、花付きを良くする「リン酸」が多く含まれているものを選ぶと良いでしょう。 肥料の袋に記載されている「N(窒素)-P(リン酸)-K(カリ)」の比率を確認し、Pの割合が高いものを選ぶのがおすすめです。
物理的な防御
アブラムシはキラキラした光を嫌う性質があります。株元にアルミホイルやシルバーマルチを敷くことで、光が乱反射し、アブラムシが寄り付きにくくなる効果が期待できます。 また、プランターや鉢植えの場合は、目の細かい防虫ネットで覆うことで、外部からのアブラムシの飛来を物理的に防ぐことができます。
風通しを良くする
混み合った枝や葉を定期的に剪定し、株全体の風通しを良く保ちましょう。風通しが良いと、アブラムシが好む湿った環境ができにくくなるだけでなく、病気の予防にも繋がります。
天敵を味方につける
自然界には、アブラムシを食べてくれる頼もしい益虫が存在します。その代表格がテントウムシです。テントウムシは、成虫も幼虫もアブラムシを大好物としており、1匹の成虫が1日に100匹ものアブラムシを食べるとも言われています。 薬剤を使わずにアブラムシを駆除する「天敵農法」でも活用されています。 庭でテントウムシを見かけたら、殺虫剤で殺してしまわないように注意し、アブラムシ退治のパートナーとして大切にしましょう。他にも、ヒラタアブやカゲロウの幼虫もアブラムシの天敵です。
コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いによい影響を与え合う植物のことです。アブラムシは特定の植物の香りを嫌うため、菊の近くに植えることで、天然の忌避剤としての効果が期待できます。
アブラムシが嫌う代表的な植物には、マリーゴールド、ミント、カモミール、セージ、ヨモギなどがあります。 これらのハーブ類は、菊と一緒に植えることで、ガーデンの彩りも豊かになり、一石二鳥の効果が期待できます。
駆除前に知っておきたいアブラムシの生態と被害
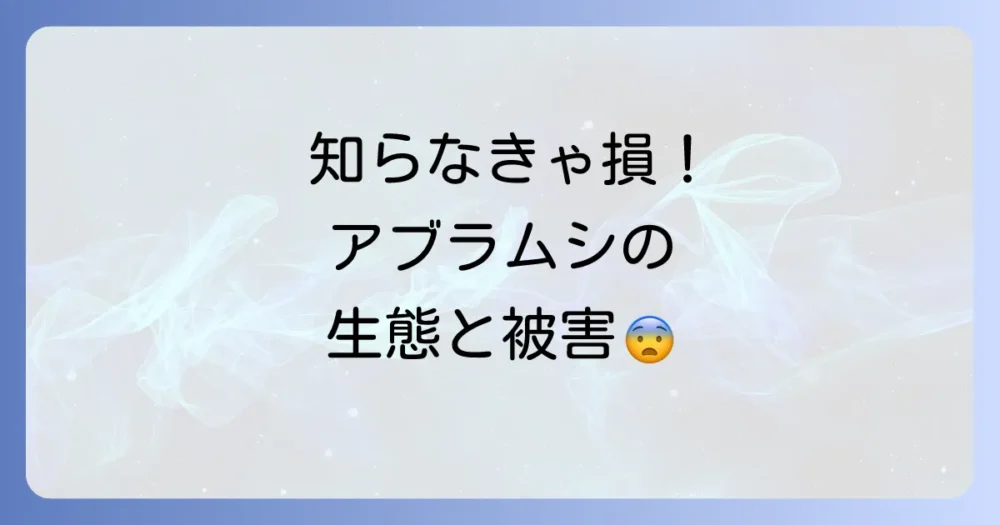
敵を知ることは、効果的な対策に繋がります。アブラムシがどのような虫で、放置するとどんな被害があるのかを理解しておきましょう。
- 驚異的な繁殖力
- 放置が招く二次被害「すす病」と「ウイルス病」
- アリがいたら要注意!共生関係のサイン
驚異的な繁殖力
アブラムシの最も厄介な特徴は、その驚異的な繁殖力です。春から秋にかけての暖かい時期、アブラムシはオスなしでメスだけで子どもを産む「単為生殖」を行います。 しかも卵ではなく、直接幼虫を産むため、爆発的に増殖します。1匹見つけたら、すでにたくさんの仲間が隠れていると考え、すぐに対処することが被害を最小限に食い止める鍵となります。
放置が招く二次被害「すす病」と「ウイルス病」
アブラムシの被害は、植物の汁を吸われるだけではありません。アブラムシの排泄物(甘露)は糖分を多く含んでおり、これを栄養源として黒いカビが発生する「すす病」を引き起こします。 すす病になると葉が黒く覆われ、光合成が妨げられて生育が悪くなります。
さらに深刻なのが、ウイルス病の媒介です。アブラムシは、ウイルスに感染した植物の汁を吸った後、健康な植物に移動して汁を吸うことで、病気を次々と広めてしまいます。 一度ウイルス病に感染すると治療法はなく、株ごと処分するしかなくなる場合もあるため、アブラムシの発生は早期に食い止める必要があります。
アリがいたら要注意!共生関係のサイン
菊の周りでアリを頻繁に見かけるようになったら、それはアブラムシがいるサインかもしれません。アリは、アブラムシが出す甘い排泄物(甘露)をもらう代わりに、アブラムシの天敵であるテントウムシなどを追い払って守るという「共生関係」にあります。 そのため、アリの行列はアブラムシの存在を示す重要な手がかりとなるのです。
よくある質問
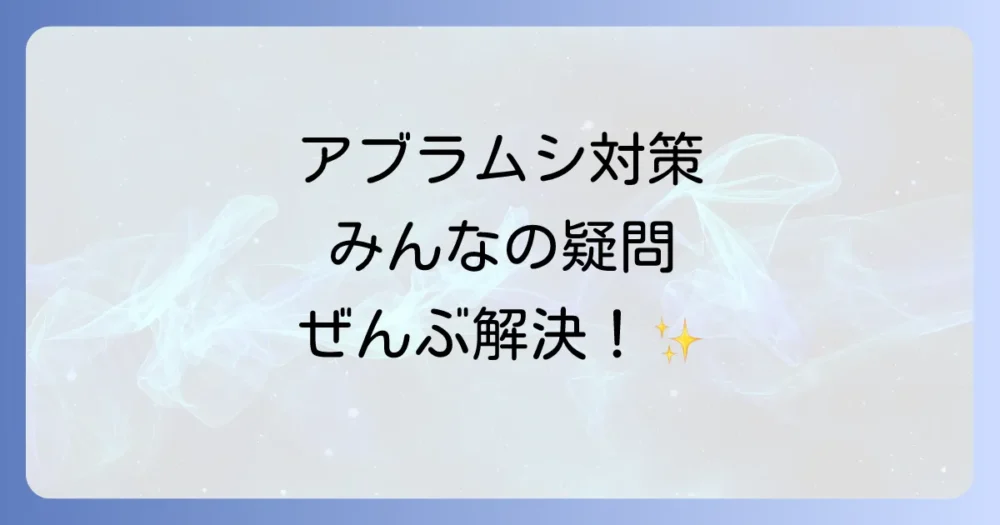
牛乳スプレーは本当に効きますか?後始末はどうすればいいですか?
はい、効果が期待できます。牛乳が乾燥する際の膜がアブラムシの気門を塞ぎ、窒息させる仕組みです。 ただし、使用後は必ず水で洗い流してください。放置すると牛乳が腐敗し、悪臭やカビの原因となります。
木酢液や食酢の正しい希釈倍率と使用頻度は?
製品によって異なりますが、一般的に木酢液は100~500倍、食酢は25~50倍程度に水で薄めて使用します。 効果を持続させるためには、週に1~2回程度の散布がおすすめです。ただし、濃度が濃すぎたり、頻度が多すぎたりすると植物を傷める可能性があるので、様子を見ながら調整してください。
薬剤を使いたくないのですが、天敵のテントウムシはどこで手に入りますか?
自然に庭にやってくるのを待つのが基本ですが、農産物直売所やインターネット通販などで、天敵製剤として販売されていることもあります。 「ナミテントウ」などの名前で探してみてください。
薬剤はどんな時間帯に散布するのが効果的ですか?
薬剤散布は、風のない穏やかな日の早朝か夕方に行うのが最適です。日中の高温時に散布すると、薬剤がすぐに蒸発してしまったり、薬害(植物へのダメージ)が出やすくなったりすることがあります。
アブラムシはなぜ黄色に集まるのですか?
アブラムシには黄色に引き寄せられる習性があります。 この性質を利用して、市販の黄色い粘着シートを菊の近くに設置することで、飛来する有翅アブラムシを捕獲し、発生を予防する効果が期待できます。
まとめ
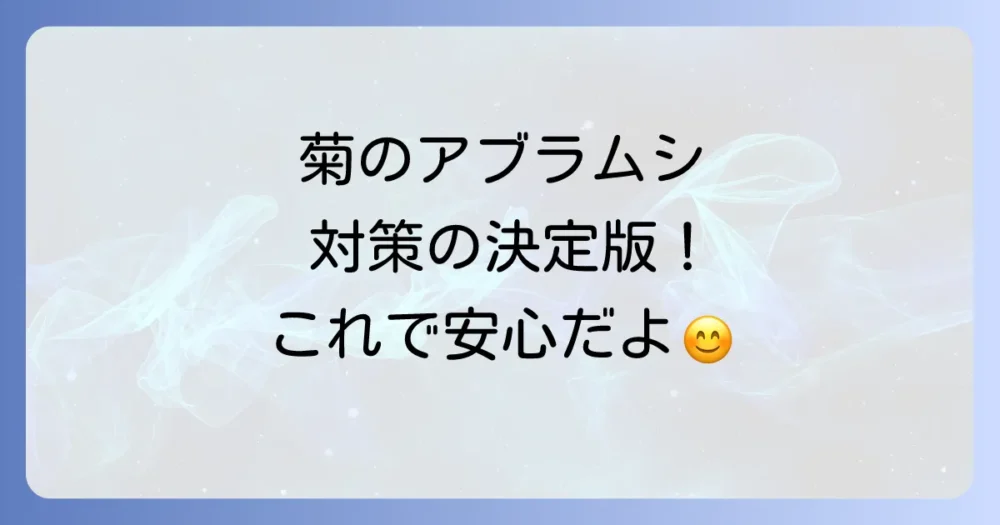
- 菊のアブラムシは発見したらすぐに対処する。
- 駆除方法は薬剤不使用と使用の2種類がある。
- 牛乳や木酢液は手軽だが後処理や濃度に注意。
- 薬剤は速効性と持続性でタイプを選ぶ。
- アブラムシ発生の原因は窒素肥料の過多。
- 風通しが悪いとアブラムシの温床になる。
- 羽の生えたアブラムシが外部から飛来する。
- 予防には適切な肥料管理が不可欠。
- リン酸が多めの肥料で花付きを良くする。
- シルバーマルチや防虫ネットで物理的に防ぐ。
- 天敵のテントウムシはアブラムシ退治の味方。
- マリーゴールドなどのコンパニオンプランツも有効。
- アブラムシは繁殖力が非常に強い害虫。
- 放置すると「すす病」や「ウイルス病」を招く。
- アリの存在はアブラムシがいるサイン。