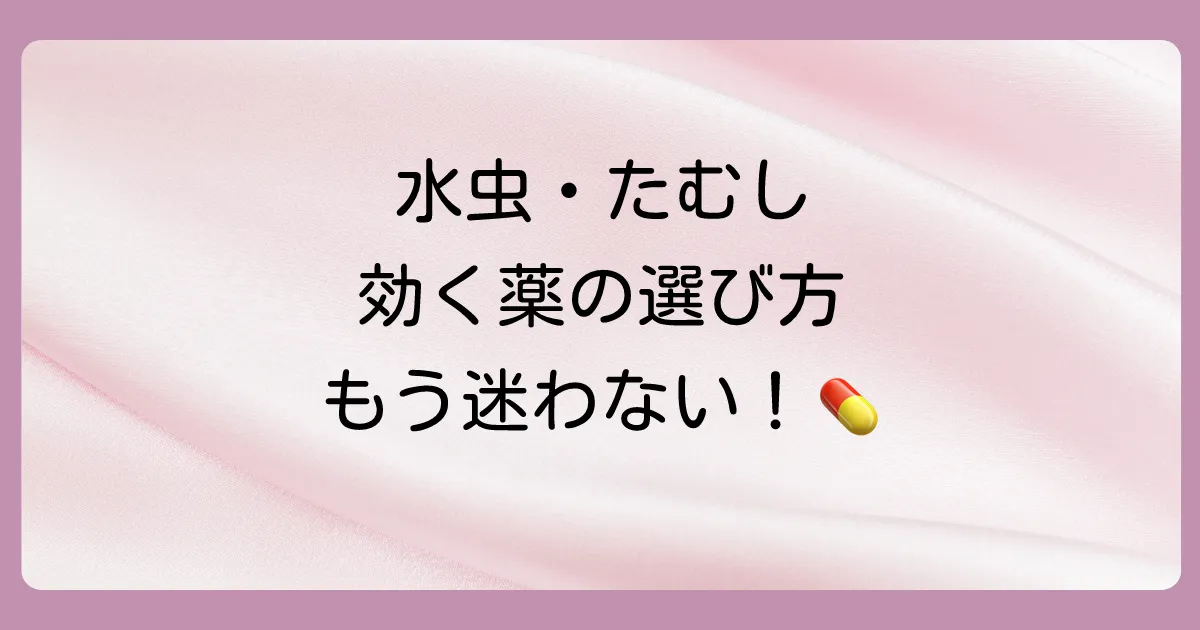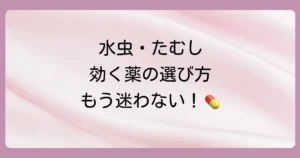足の指の間がジュクジュクする、皮がむける、デリケートゾーンに猛烈なかゆみがある…。もしかして、水虫やいんきんたむしかもしれないと悩んでいませんか?病院に行くのは恥ずかしいし、時間もない。そんな時、頼りになるのがドラッグストアなどで手軽に購入できる市販の抗真菌薬(塗り薬)です。
しかし、いざ薬局に行ってみると、たくさんの種類があってどれを選べば良いのか迷ってしまいますよね。本記事では、そんなお悩みを解決するために、市販の抗真菌薬の選び方から、症状別のおすすめ商品、そして効果を最大限に引き出す正しい使い方まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたにぴったりの薬が見つかり、つらい症状を改善する一歩を踏み出せるはずです。
まず確認!その症状、市販の抗真菌薬で本当に大丈夫?
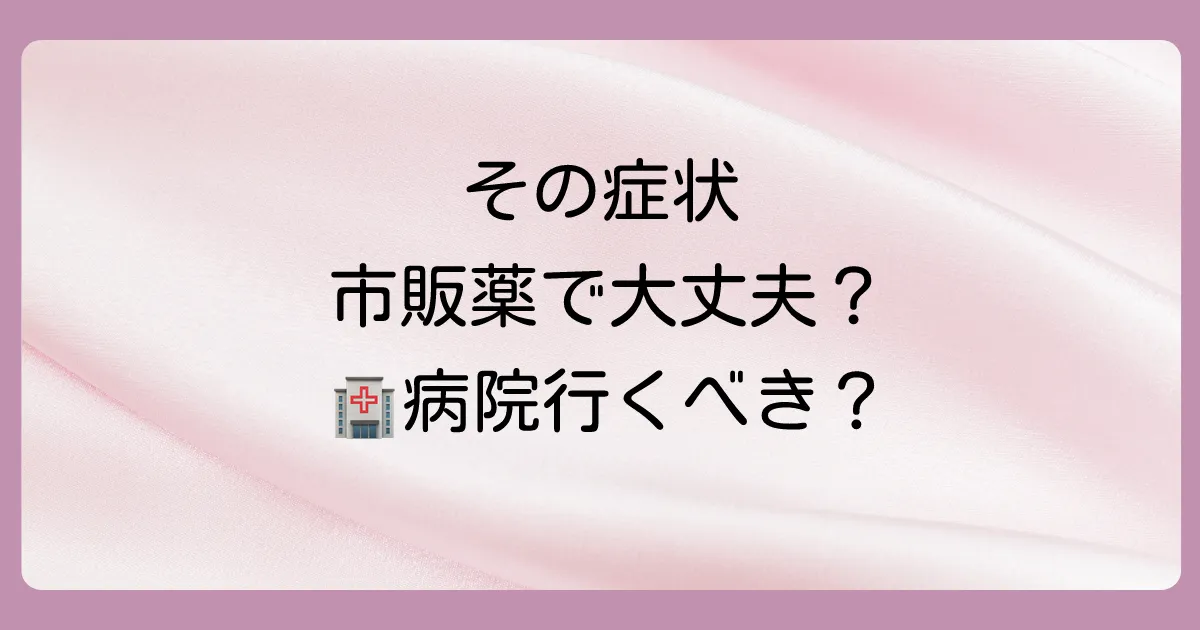
市販の抗真菌薬はとても便利ですが、使用する前に、その症状が本当に市販薬で対応できるものなのかを確認することが非常に重要です。自己判断で誤った薬を使ってしまうと、症状が悪化したり、治療が長引いたりする可能性があります。まずは、ご自身の症状をよく観察してみましょう。
この章では、市販の抗真菌薬で対処できる症状と、すぐに皮膚科などの医療機関を受診すべき症状について解説します。
市販薬が使える症状セルフチェック
市販の抗真菌薬が有効なのは、主に白癬菌(はくせんきん)というカビ(真菌)の一種が原因で起こる皮膚の感染症です。具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 水虫(足白癬): 足の指の間が赤くなり皮がむける、ジュクジュクする(趾間型)、足の裏に小さな水ぶくれができる(小水疱型)、足の裏やかかとがカサカサして硬くなる(角質増殖型)といった症状です。
- いんきんたむし(股部白癬): 太ももの付け根(股部)に、円形または半円形の赤い発疹ができ、強いかゆみを伴います。
- ぜにたむし(体部白癬): 顔、首、腕、お腹など、体のどこにでもできる可能性があり、円形の赤い発疹が特徴です。
これらの症状に当てはまり、以前に医師から同様の症状で「白癬菌が原因」と診断されたことがある場合は、市販の抗真菌薬を試してみる価値があります。 しかし、初めてこれらの症状が出た場合は、自己判断せず、一度皮膚科を受診して正確な診断を受けることを強くおすすめします。
これは危険!すぐに病院へ行くべき症状
一方で、以下のような症状が見られる場合は、市販薬での対応は困難、あるいは危険な場合があります。速やかに皮膚科を受診してください。
爪が白や黄色に濁る、厚くなる(爪水虫の疑い)
爪水虫(爪白癬)は、市販の塗り薬では有効成分が爪の内部まで浸透しにくいため、治療が困難です。 飲み薬による治療が基本となるため、必ず医師の診断が必要です。頭皮のかゆみ、フケ、脱毛(頭部白癬の疑い)
頭部にできる白癬は「しらくも」とも呼ばれ、市販薬では治療できません。放置すると脱毛が広がる可能性があるため、専門医による治療が不可欠です。デリケートゾーンのおりもの異常、強いかゆみ(カンジダ症の疑い)
女性のデリケートゾーンのかゆみで、ヨーグルト状やカッテージチーズ状のおりものを伴う場合、カンジダ症の可能性があります。 市販薬は再発した場合のみ使用可能で、初めて症状が出た場合は必ず婦人科などを受診してください。 また、男性の陰部のかゆみも、カンジダ症や他の病気の可能性があるため、自己判断は禁物です。症状が広範囲に及んでいる、化膿している
患部が広範囲に広がっている場合や、ジュクジュクして黄色い膿が出ている場合は、細菌による二次感染を起こしている可能性があります。 このような場合も、市販薬だけでの対応は難しいため、医療機関を受診しましょう。市販薬を2週間使用しても改善しない
市販薬を2週間ほど使用しても症状が全く良くならない、あるいは悪化する場合は、そもそも原因が白癬菌ではない可能性があります。 湿疹やかぶれなど、他の皮膚疾患との見分けは専門家でないと難しいことも多いため、使用を中止して医師に相談してください。
自分の症状を正しく見極め、適切な対処をすることが、つらい症状から早く解放されるための最も大切な第一歩です。
【症状・部位別】市販の抗真菌薬(塗り薬)おすすめ12選
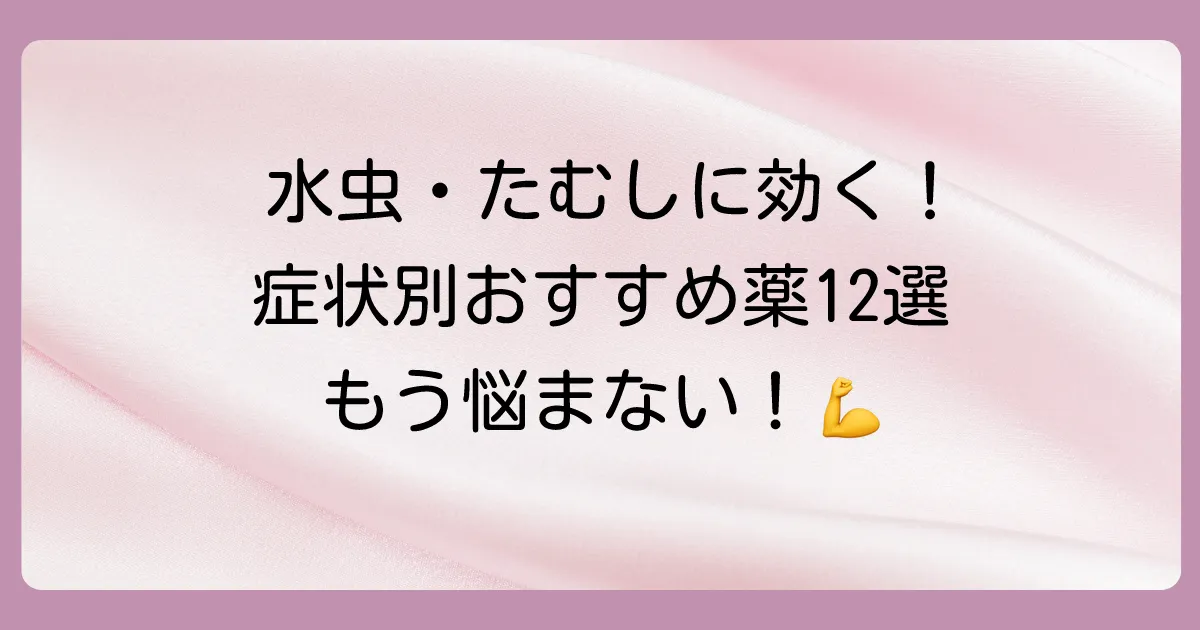
ここでは、数ある市販の抗真菌薬の中から、症状や部位に合わせて選んだおすすめの商品を12種類ご紹介します。それぞれの薬の特徴や有効成分、剤形などを比較し、あなたに最適な一品を見つける手助けになれば幸いです。ぜひ、薬選びの参考にしてください。
この章で紹介する内容は以下の通りです。
足水虫(趾間型・小水疱型)におすすめの塗り薬
足の指の間がジュクジュクしたり、小さな水ぶくれができたりするタイプの水虫には、べたつきが少なく、さらっとした使用感のクリームタイプや液体タイプがおすすめです。
| 商品名 | 特徴 | 有効成分 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| ラミシールATクリーム (グラクソ・スミスクライン) | 殺真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」が角質層に浸透し、1日1回の使用で効果を発揮します。 有効成分が抗真菌成分のみのシンプル処方で、かぶれが心配な方にもおすすめです。 | テルビナフィン塩酸塩 | クリーム |
| ブテナロックVαクリーム (久光製薬) | 優れた殺菌力を持つ「ブテナフィン塩酸塩」に加え、かゆみ止め成分や抗炎症成分など7種類の有効成分を配合。 スーッとした使用感も特徴です。 | ブテナフィン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン、グリチルレチン酸、l-メントールなど | クリーム |
| ダマリングランデX液 (大正製薬) | 殺真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」に、かゆみと炎症を抑える成分を配合。 サラッとした液体タイプで、患部に直接触れずに塗布できます。 | テルビナフィン塩酸塩、リドカイン、グリチルレチン酸、l-メントール | 液体 |
足水虫(角質増殖型)におすすめの塗り薬
かかとなどがカサカサ、ゴワゴワと硬くなる角質増殖型の水虫には、硬くなった角質を柔らかくする「尿素」が配合されたクリームが効果的です。抗真菌成分が浸透しやすくなります。
| 商品名 | 特徴 | 有効成分 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| メンソレータム エクシブWディープ10クリーム (ロート製薬) | 抗真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」に加え、尿素を10%配合。 硬くなった角質を柔らかくし、有効成分の浸透を助けます。かゆみ止め成分や殺菌成分も配合されています。 | テルビナフィン塩酸塩、尿素、リドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、グリチルレチン酸など | クリーム |
| ラミシールプラスクリーム (グラクソ・スミスクライン) | 殺真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」に、角質を柔らかくする尿素を5%配合。 さらに、かゆみや炎症を抑える成分もプラスされています。 | テルビナフィン塩酸塩、尿素、クロタミトン、グリチルレチン酸、l-メントール | クリーム |
| ヒフールV8 水虫クリーム (万協製薬) | 8種類の有効成分を配合し、水虫の諸症状に幅広く対応。 殺菌力のある「ブテナフィン塩酸塩」が角質層の奥まで浸透します。ジュクジュクタイプにもカサカサタイプにも使えます。 | ブテナフィン塩酸塩、リドカイン、グリチルレチン酸、クロタミトン、dl-カンフルなど | クリーム |
いんきんたむし・ぜにたむしにおすすめの塗り薬
股部などデリケートな部分に発症するいんきんたむしや、体の様々な部位にできるぜにたむしには、刺激が少なく、広範囲に塗りやすいクリームタイプが基本です。蒸れやすい部位なので、軟膏よりクリームや液体、スプレーがおすすめです。
| 商品名 | 特徴 | 有効成分 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| ピロエースZクリーム (第一三共ヘルスケア) | 殺真菌成分「ラノコナゾール」を配合し、1日1回の使用で効果が持続します。 患部に長くとどまり、しつこいかゆみや炎症をしっかり抑えます。 | ラノコナゾール、クロタミトン、グリチルレチン酸、l-メントール、イソプロピルメチルフェノール | クリーム |
| タムチンキパウダースプレーZ (小林製薬) | 手を汚さずに広範囲に塗布できるスプレータイプ。ジュクジュクした患部をサラサラに乾燥させます。かゆみを鎮める成分も配合。 | ブテナフィン塩酸塩、リドカイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、酸化亜鉛など | スプレー |
| ラミシールDX (グラクソ・スミスクライン) | 殺真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」が角質層に長くとどまり、1日1回の塗布で効果を発揮。 かゆみ止め成分や清涼感成分も配合されています。 | テルビナフィン塩酸塩、クロタミトン、グリチルレチン酸、l-メントール | クリーム |
かゆみが特に強い時におすすめの塗り薬
水虫やいんきんたむしに伴うかゆみが我慢できない時には、かゆみ止め成分が複数配合されている薬や、スーッとした清涼感のある薬がおすすめです。
| 商品名 | 特徴 | 有効成分 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| メンソレータム エクシブEX液 (ロート製薬) | 抗真菌成分に加え、3種類のかゆみ止め成分を配合。 しつこいかゆみをしっかり鎮めます。直接患部に触れずに塗れる液体タイプです。 | テルビナフィン塩酸塩、リドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、グリチルレチン酸など | 液体 |
| ブテナロックVα液 (久光製薬) | 殺菌力に優れた「ブテナフィン塩酸塩」と、3種類のかゆみ止め成分を配合。 l-メントール配合で、強い清涼感が得られます。 | ブテナフィン塩酸塩、ジブカイン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、クロタミトンなど | 液体 |
| メンソレータム エクシブWきわケアジェル (ロート製薬) | 爪のきわなど、細かい部分にも塗りやすいジェルタイプ。 浸透殺菌する抗真菌成分と、かゆみ止め成分を配合しています。 | テルビナフィン塩酸塩、リドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、グリチルレチン酸など | ジェル |
後悔しない!市販の抗真菌薬(塗り薬)の選び方 3つのポイント
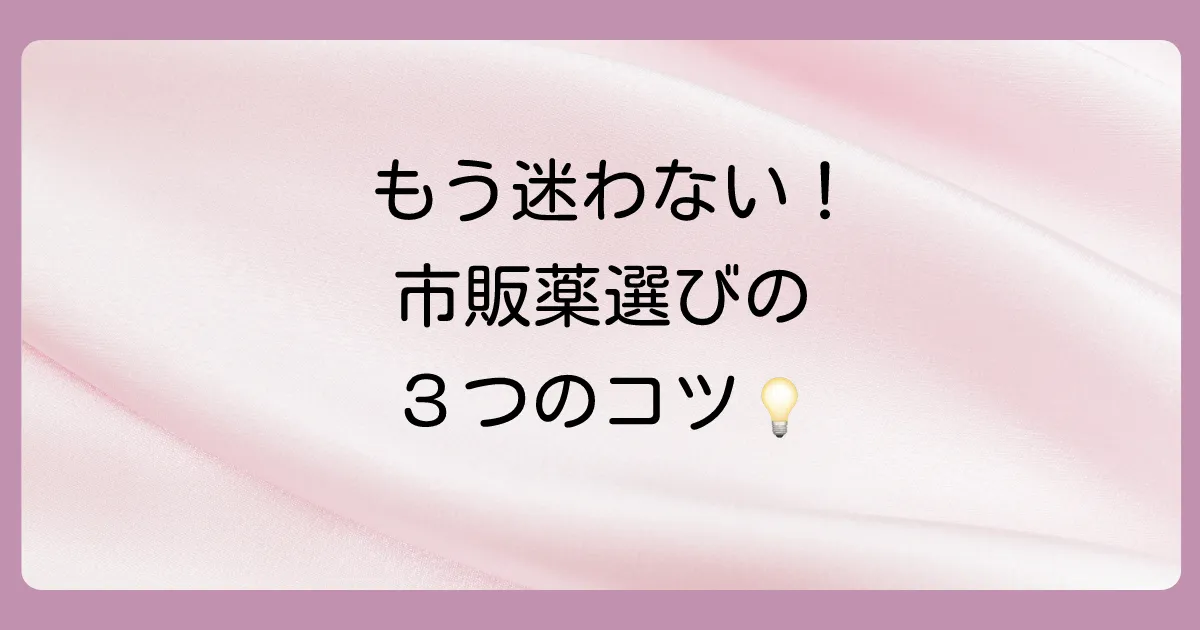
自分に合った市販の抗真菌薬を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、薬選びで後悔しないための3つの重要なポイントを解説します。成分、剤形、そして付随する症状に注目して、最適な一品を選びましょう。
この章では、以下の3つのポイントについて詳しく見ていきます。
ポイント1:原因菌に効く「抗真菌成分」で選ぶ
市販の抗真菌薬の主役は、もちろん「抗真菌成分」です。この成分が白癬菌の増殖を抑えたり、殺菌したりすることで効果を発揮します。 市販薬に含まれる主な抗真菌成分にはいくつかの系統があり、それぞれに特徴があります。
アリルアミン系(テルビナフィン塩酸塩など)
殺菌作用が特徴で、白癬菌を直接殺す力が強いとされています。角質層への浸透性も高く、1日1回の使用で効果が持続する製品が多いです。 代表的な商品に「ラミシール」シリーズや「エクシブ」シリーズがあります。ベンジルアミン系(ブテナフィン塩酸塩など)
アリルアミン系と同様に優れた殺菌作用を持ちます。皮膚に長くとどまる性質があるため、こちらも1日1回の使用で効果が期待できます。 代表的な商品に「ブテナロック」シリーズがあります。イミダゾール系(ラノコナゾール、ミコナゾール硝酸塩など)
白癬菌だけでなく、カンジダ菌など幅広い真菌に対して効果を示す抗菌スペクトルが広いのが特徴です。 白癬菌の増殖を抑える静菌作用が中心ですが、殺菌的に働く成分もあります。代表的な商品に「ピロエース」シリーズや、カンジダ再発治療薬の「メディトリート」などがあります。チオカルバミン酸系(リラナフタートなど)
比較的新しい成分で、殺菌的に作用します。皮膚の角質層への移行性が良いとされています。
どの成分も白癬菌に有効ですが、殺菌力を重視するならアリルアミン系やベンジルアミン系、原因菌がはっきりしない場合や幅広い菌への効果を期待するならイミダゾール系、といった視点で選ぶのも一つの方法です。
ポイント2:症状に合わせた「剤形」で選ぶ
抗真菌薬には、クリーム、軟膏、液体、スプレーなど、様々な剤形(ざいけい)があります。 患部の状態や使用する部位、使い心地の好みによって最適な剤形は異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解して選びましょう。
| 剤形 | メリット | デメリット | おすすめの症状 |
|---|---|---|---|
| クリーム | 伸びが良く、べたつかない。ほとんどの症状に使える。 | 液体に比べると浸透性がやや劣る場合がある。 | ジュクジュク、カサカサ両方のタイプ、広範囲の患部 |
| 軟膏 | 刺激が少なく、患部を保護する効果が高い。 | べたつきが気になることがある。 | ジュクジュクして、ひび割れがある患部 |
| 液体(リキッド) | 浸透性が高く、さらっとした使用感。 | アルコールを含むものが多く、傷にしみることがある。 | カサカサ乾燥している患部 |
| スプレー | 手を汚さずに広範囲に塗布できる。 | 患部にピンポイントで塗りにくい。 | 背中や広範囲の患部、手が届きにくい場所 |
例えば、ジュクジュクした水虫にはクリームや軟膏、カサカサした水虫にはクリームや液体が適しています。 自分の症状とライフスタイルに合った剤形を選ぶことが、治療を継続するコツです。
ポイント3:かゆみなどの「付随症状」で選ぶ
水虫やいんきんたむしは、白癬菌の感染だけでなく、つらいかゆみや炎症、赤みなどを伴うことが多くあります。 そのような不快な症状を和らげるために、抗真菌成分に加えて、以下のような成分が配合されている薬を選ぶのも良い方法です。
- かゆみ止め成分(鎮痒成分): クロタミトン、リドカイン、ジフェンヒドラミン塩酸塩など。我慢できないかゆみを素早く鎮めてくれます。
- 抗炎症成分: グリチルレチン酸など。患部の赤みや炎症を抑えます。
- 殺菌成分(抗菌成分): イソプロピルメチルフェノールなど。雑菌の繁殖を防ぎ、二次感染の予防や足の臭いを抑える効果が期待できます。
- 清涼感成分: l-メントール、dl-カンフルなど。スーッとした使用感で、かゆみを一時的に紛らわしてくれます。
特にかゆみが強い場合は、かゆみ止め成分が複数配合されている製品を選ぶと効果的です。 ただし、薬の成分にかぶれやすい方は、有効成分が抗真菌成分のみのシンプルな処方の製品から試してみるのが安心です。 自分の症状をよく観察し、必要な成分が配合された薬を選びましょう。
効果なしは塗り方が原因?抗真菌薬の効果的な使い方と注意点
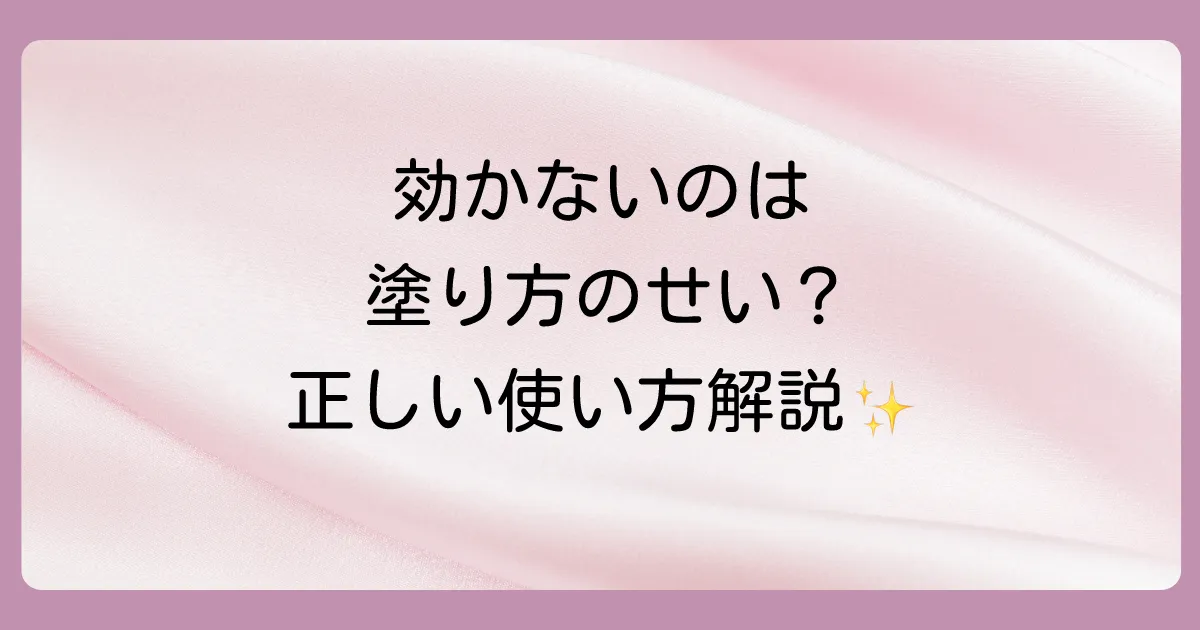
せっかく自分に合った薬を選んでも、使い方が間違っていては十分な効果は得られません。「市販薬を試したけど効果がなかった」という方の中には、実は塗り方に問題があったというケースも少なくありません。ここでは、抗真菌薬の効果を最大限に引き出すための正しい使い方と、知っておくべき注意点を解説します。
この章で解説するポイントは以下の通りです。
塗る前の準備:患部を清潔に
薬を塗る前の準備は、治療効果を左右する重要なステップです。まず、入浴時などに石鹸をよく泡立て、患部とその周りを優しく丁寧に洗いましょう。このとき、ゴシゴシと強くこすって皮膚を傷つけないように注意してください。皮膚に傷がつくと、そこから雑菌が入り込み、症状が悪化する原因になりかねません。
洗い終わったら、清潔なタオルで水分をしっかりと拭き取ります。特に足の指の間は水分が残りやすいので、念入りに拭いてください。患部を清潔で乾燥した状態に保つことが、薬の浸透を助け、白癬菌の増殖を抑えるための基本です。
正しい塗り方:広めに、優しく
薬の塗り方には、いくつかの大切なコツがあります。自己流で塗るのではなく、正しい方法を実践しましょう。
- 塗る範囲は「広めに」
白癬菌は、症状が出ている部分だけでなく、その周囲にも潜んでいます。 そのため、薬を塗るときは、赤みやかゆみがある部分だけでなく、その周囲も含めて広範囲に塗ることが重要です。足の裏に症状がある場合は、足の裏全体と指の間、足の側面まで、広めに塗るように心がけましょう。 - 塗る量は「適量を」
薬を塗る量は、多すぎても少なすぎてもいけません。目安として、患部を覆うくらいの量を指に取り、薄くすり込むように塗ります。べたつくほど大量に塗る必要はありません。 - 塗り方は「優しく」
患部に薬をすり込む際は、力を入れすぎず、優しく塗り広げてください。特にジュクジュクしている部分や水ぶくれがある部分は、潰さないように注意が必要です。 - 塗るタイミング
入浴後の皮膚が清潔で柔らかくなっている時が、薬の浸透が良くなるため最も効果的です。1日1回タイプの薬なら、このタイミングで塗るのがベストです。
塗る期間の目安:症状が消えても1ヶ月は継続
これが最も重要なポイントと言っても過言ではありません。多くの人が、かゆみや皮むけなどの自覚症状がなくなると、「治った」と勘違いして薬の使用をやめてしまいます。しかし、見た目がきれいになっても、皮膚の角質層の奥には白癬菌がまだ生き残っている可能性が高いのです。
ここで治療をやめてしまうと、残った菌が再び増殖し、夏場などに再発を繰り返す原因となります。 症状が改善した後も、最低でも1ヶ月は根気強く薬を塗り続けることが、完治を目指すための最大のコツです。 製品によっては、より長い期間の使用を推奨している場合もあるので、説明書をよく確認しましょう。
副作用と対処法
市販の抗真菌薬は比較的安全性の高い薬ですが、人によっては副作用が起こる可能性もあります。主な副作用としては、塗った部分のかぶれ(接触皮膚炎)、赤み、かゆみ、刺激感などが報告されています。
もし、薬を使用してこれらの症状が現れたり、元の症状が悪化したりした場合は、すぐに使用を中止してください。 そして、薬のパッケージや説明書を持参して、医師または薬剤師に相談しましょう。自己判断で別の薬を重ねて塗ることは、症状をさらに悪化させる可能性があるため絶対にやめてください。
よくある質問
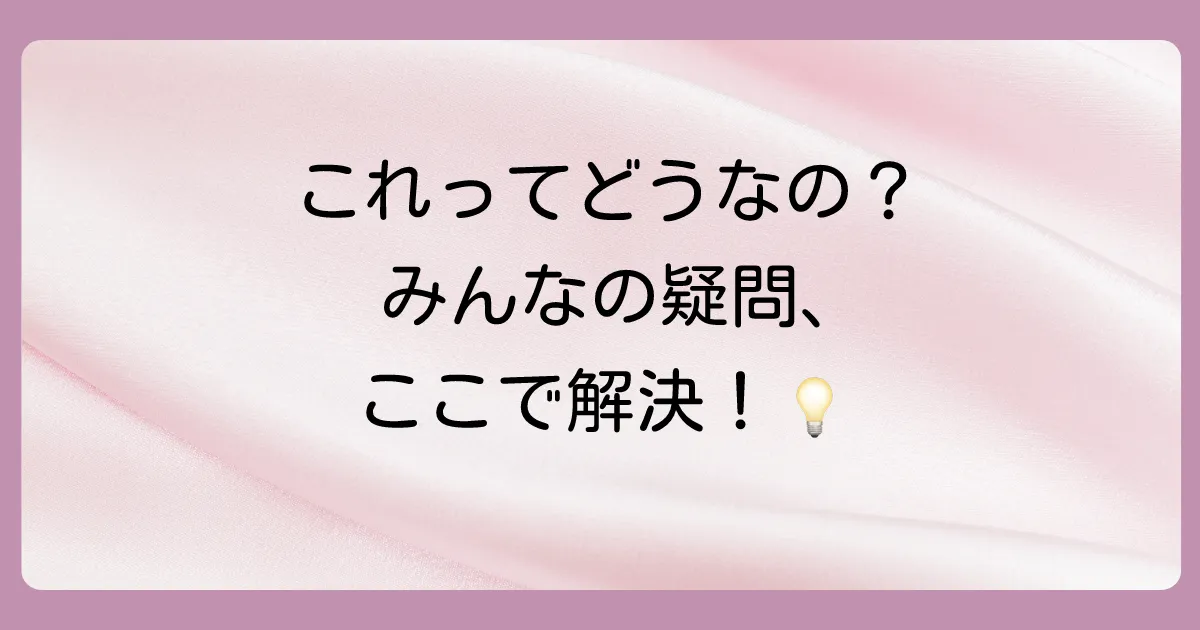
市販の抗真菌薬について、多くの方が抱く疑問にお答えします。デリケートな悩みだからこそ、正しい知識を持って対処することが大切です。
デリケートゾーン(陰部)のかゆみに市販の抗真菌薬は使えますか?
デリケートゾーンのかゆみの原因は様々で、自己判断は危険です。
女性の場合:
おりものに異常(ヨーグルト状、カッテージチーズ状など)があり、以前に医師から「膣カンジダ症」と診断されたことがある場合に限り、再発治療薬として市販の抗真菌薬(カンジダ用)を使用できます。 ただし、初めての症状の場合や、原因がはっきりしない場合は、必ず婦人科を受診してください。 水虫用の抗真菌薬は使用できません。
男性の場合:
股間のかゆみで、円形の発疹がある場合は「いんきんたむし(股部白癬)」の可能性があり、水虫・たむし用の市販薬が使用できます。 しかし、カンジダ症や他の皮膚炎の可能性もあるため、症状が改善しない場合や、初めての場合は皮膚科や泌尿器科の受診をおすすめします。
カンジダ症は市販薬で治せますか?
膣カンジダ症の場合、過去に医師の診断・治療を受けたことがある方の「再発」に限り、市販薬(第1類医薬品)で治療が可能です。 市販薬には、膣内に直接挿入する「膣錠」と、外陰部のかゆみを抑える「クリーム」があります。 膣症状(おりもの異常)がある場合は、クリームだけでなく膣錠の併用が必要です。
初めて症状が出た方や、60歳以上の方、糖尿病の方、再発の頻度が高い方は、市販薬を使用せず、必ず医療機関を受診してください。 自己判断は、症状の悪化や他の病気の見逃しにつながる危険性があります。
ステロイド入りの薬との違いは何ですか?
抗真菌薬は、水虫やカンジダの原因である「真菌(カビ)」を殺菌したり、増殖を抑えたりする薬です。 一方、ステロイド薬は、炎症やアレルギー反応を強力に抑える薬で、湿疹やかぶれ、虫刺されなどに使われます。
水虫などの真菌感染症にステロイド薬だけを使用すると、菌に対する抵抗力を弱めてしまい、かえって症状を悪化させてしまう危険性があります。 これを「菌交代現象」と呼びます。かゆみが強いからといって、自己判断でステロイド薬を使うのは絶対にやめてください。ただし、市販の水虫薬の中には、炎症を抑える目的で弱いステロイド成分が少量配合されているものもあります。
薬はどのくらいの期間で効果が出ますか?
正しく使用すれば、通常1~2週間程度でかゆみや赤みなどの症状は改善してくることが多いです。 しかし、これはあくまで自覚症状が和らいだだけで、原因菌である白癬菌が完全にいなくなったわけではありません。
ここで薬をやめてしまうと、生き残った菌が再び増殖し、再発の原因となります。 症状がきれいになっても、最低1ヶ月は根気よく治療を続けることが完治への鍵です。 爪水虫の治療期間はさらに長く、爪が生え変わるのに約1年~1年半かかります。
子供や赤ちゃんにも使えますか?
市販の抗真菌薬の多くは、乳幼児への使用を想定していません。子供の皮膚は大人に比べてデリケートで、副作用が出やすい可能性があります。また、子供の皮膚トラブルは、水虫と似た他の病気である可能性も高いです。自己判断で市販薬を使用せず、必ず小児科や皮膚科を受診して、医師の指示に従ってください。
妊娠中や授乳中でも使えますか?
妊娠中や授乳中は、薬の使用に特に注意が必要です。塗り薬は飲み薬に比べて体への吸収は少ないですが、胎児や母乳に影響を与える可能性がゼロではありません。市販の抗真菌薬を使用する前に、必ずかかりつけの産婦人科医や薬剤師に相談し、使用の可否や安全な薬について指示を受けてください。自己判断での使用は絶対に避けてください。
市販薬で治らない場合はどうすればいいですか?
市販薬を2週間程度使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、以下の可能性が考えられます。
- そもそも水虫ではない(湿疹、かぶれなど他の皮膚疾患)
- 原因菌が市販薬の成分に抵抗性を持っている
- 爪水虫など、市販薬では治療困難な状態になっている
- 使い方が間違っている
このような場合は、市販薬の使用を中止し、速やかに皮膚科を受診してください。 専門医による正確な診断と、適切な処方薬による治療が必要です。
まとめ
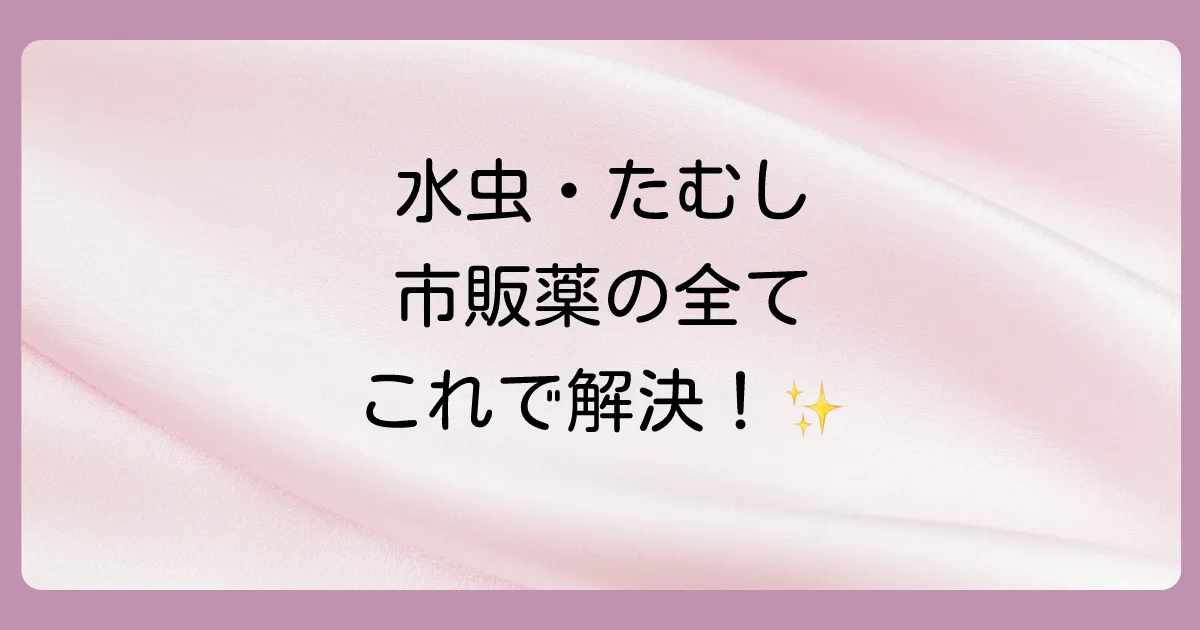
- 市販の抗真菌薬は水虫やいんきんたむしに有効です。
- 爪水虫やカンジダの初回は市販薬では治療できません。
- 薬を選ぶ際は「抗真菌成分」「剤形」「付随症状」がポイントです。
- 殺菌力重視ならアリルアミン系やベンジルアミン系がおすすめです。
- ジュクジュクした症状にはクリームや軟膏が適しています。
- カサカサした症状にはクリームや液体が向いています。
- かゆみが強い場合は、かゆみ止め成分配合の薬を選びましょう。
- 薬を塗る前には患部を清潔にし、よく乾かすことが大切です。
- 薬は症状のある部分より広めに塗るのがコツです。
- 症状が消えても最低1ヶ月は薬を塗り続ける必要があります。
- 再発を防ぐためには、根気強い治療が不可欠です。
- 副作用が出たらすぐに使用を中止し、専門家に相談してください。
- デリケートゾーンへの使用は、特に慎重な判断が必要です。
- カンジダの市販薬は再発時にのみ使用可能です。
- 2週間使っても改善しない場合は、皮膚科を受診しましょう。
新着記事