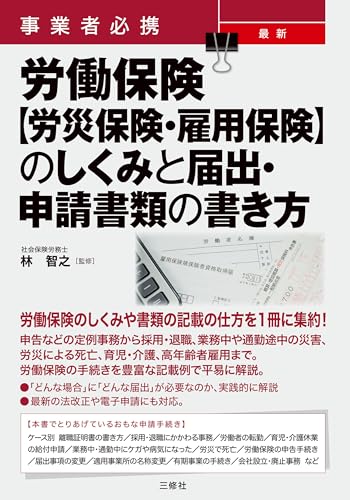仕事中に怪我をしたり、病気になったりした場合、労災保険から給付金が支払われることがあります。しかし、会社側から示談を提案されるケースも少なくありません。示談は早期解決のメリットがある一方、内容をよく確認せずに合意してしまうと、後々後悔する可能性も。本記事では、労災の示談における注意点を中心に、示談金の相場や交渉のポイントなどを分かりやすく解説します。この記事を読めば、不利な条件で示談してしまうリスクを避け、納得のいく解決を目指せるでしょう。
労災における示談とは?
労災における示談とは、労働災害によって被った損害について、被災労働者と会社側が話し合い、合意によって解決することを指します。 労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる場合に、示談交渉が行われることがあります。 この交渉で合意に至った金額が示談金として支払われます。 示談が成立すると、原則として、それ以上の金銭的な請求はできなくなるため、内容を慎重に検討する必要があります。
具体的には、以下のような項目について話し合われます。
- 示談金の金額
- 支払方法
- 今後の処遇(退職しない場合など)
示談金と損害賠償金・慰謝料の違い
示談金、損害賠償金、慰謝料は、それぞれ意味合いが異なります。
損害賠償金は、労災事故によって被った損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)の総称です。 法律や過去の判例に基づいて算定されます。 一方、示談金は、この損害賠償金について当事者間の話し合いによって合意した金額を指します。 つまり、示談金は損害賠償金の一部であり、交渉によって金額が決まるという違いがあります。
慰謝料は、労災によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金であり、損害賠償金の一部です。 労災保険からは慰謝料は支払われないため、会社に対して別途請求する必要があります。
労災保険給付と示談金の関係
労災保険から給付を受けた場合、その金額は会社に対する損害賠償請求額(示談金)から差し引かれます(控除)。 これは、同じ損害に対して二重に補償を受けることを防ぐためです。 ただし、労災保険の特別支給金は損害賠償額から控除されません。
労災保険の給付だけでは、慰謝料や逸失利益の全額がカバーされないケースも多くあります。 そのような場合に、不足分を会社に請求するために示談交渉が行われます。
労災で示談交渉を行うメリット・デメリット
労災で会社と示談交渉を行うことには、メリットとデメリットの両方があります。安易に判断せず、それぞれの側面を理解した上で慎重に検討することが重要です。
この章では、労災における示談交渉の主なメリットとデメリットについて解説します。
- 労災で示談交渉を行うメリット
- 労災で示談交渉を行うデメリット
労災で示談交渉を行うメリット
労災の示談交渉には、いくつかのメリットがあります。主なメリットは以下の通りです。
- 早期解決が期待できる
裁判手続きを経ずに当事者間の話し合いで解決するため、紛争が長期化するのを避け、早期に解決できる可能性があります。 これにより、精神的な負担から早く解放されるというメリットがあります。 - 労災保険では補償されない損害も請求できる可能性がある
労災保険からは、慰謝料や逸失利益の一部など、全ての損害が補償されるわけではありません。 示談交渉では、これらの労災保険ではカバーされない損害についても会社に請求できる可能性があります。 - 柔軟な解決が期待できる
裁判のように厳格な法的手続きに縛られず、当事者双方の事情を考慮した柔軟な解決が期待できます。例えば、今後の雇用条件などについても話し合うことができます。
これらのメリットを考慮し、示談交渉が自分にとって有利な解決方法となるかを見極めることが大切です。
労災で示談交渉を行うデメリット
一方で、労災の示談交渉にはデメリットも存在します。主なデメリットは以下の通りです。
- 一度示談すると原則として追加請求できない
示談書には通常「清算条項」が盛り込まれ、示談成立後は、示談書に記載された内容以外の請求は原則としてできなくなります。 後から新たな後遺障害が判明したり、症状が悪化したりしても、追加の賠償請求は非常に困難になります。 - 会社側の提示額が低い可能性がある
会社側は、支払う示談金額を抑えようとして、適正な金額よりも低い金額を提示してくることがあります。 専門知識がないと、提示された金額が妥当かどうか判断するのが難しい場合があります。 - 交渉がまとまらない可能性がある
示談交渉はあくまで話し合いなので、双方が合意に至らなければ成立しません。 会社側が誠意ある対応をしない場合や、提示額に大きな隔たりがある場合は、交渉が難航し、解決に至らないこともあります。
これらのデメリットを十分に理解し、安易に示談に応じないように注意が必要です。
労災の示談金、相場はいくら?内訳と計算方法
労災の示談金は、個別の事案によって金額が大きく異なります。しかし、一般的にどのような損害項目が含まれ、どのように計算されるのかを知っておくことは、適正な金額で示談するために非常に重要です。労災保険ではカバーされない損害についても、会社に請求できる可能性があります。
この章では、労災の示談金に含まれる主な損害項目とその計算方法の概要について解説します。
- 治療費
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料
- その他の損害
治療費
労災事故による怪我や病気の治療にかかった費用です。労災保険から療養(補償)給付として支払われるため、基本的には全額カバーされます。 ただし、労災保険の範囲を超える治療が必要な場合や、労災指定病院以外で治療を受けた場合などは、自己負担分を会社に請求できる可能性があります。
具体的には、診察費、入院費、手術費、薬剤費、リハビリ費用、通院交通費などが含まれます。 領収書などの証拠書類をきちんと保管しておくことが重要です。
休業損害
労災による怪我や病気のために仕事を休んだことで得られなかった収入のことです。労災保険からは休業(補償)給付として、休業4日目から給付基礎日額の80%(休業特別支給金を含む)が支給されます。
しかし、労災保険の給付だけでは休業前の収入の全額をカバーできない場合があります。 その差額分について、会社に請求できる可能性があります。休業損害の計算は、事故前の収入額や休業日数を基に行われます。
逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたはずの収入のことです。 後遺障害が残った場合や死亡した場合に問題となります。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されるのが一般的です。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入:原則として事故前年の年収
- 労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて定められた割合
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に換算するための係数
死亡逸失利益も同様の考え方で計算されますが、生活費控除が行われます。
労災保険からも障害(補償)給付や遺族(補償)給付が支払われますが、逸失利益の全額をカバーするものではありません。 そのため、不足分を会社に請求することになります。
慰謝料
慰謝料は、労災によって被った精神的な苦痛に対する賠償金です。 労災保険からは慰謝料は支払われません。 そのため、会社に対して別途請求する必要があります。
慰謝料には、主に以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料:入院や通院の期間に応じて算定されます。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害の等級に応じて算定されます。等級が高いほど高額になる傾向があります。
- 死亡慰謝料:被災労働者が死亡した場合に、遺族に対して支払われます。一家の支柱であったかなど、家庭内の立場によって金額の目安が変わります。
慰謝料の金額は、過去の裁判例などを参考に、個別の事情を考慮して決定されます。
その他の損害
上記の他にも、労災事故に関連して発生した様々な損害が賠償の対象となる可能性があります。
例えば、以下のようなものが考えられます。
- 通院交通費:労災保険でカバーされない範囲の交通費
- 付添看護費:入院中の付き添いや自宅療養中の介護にかかった費用
- 将来の介護費用:重度の後遺障害により将来にわたって介護が必要となる場合の費用
- 葬儀費用:被災労働者が死亡した場合の葬儀関係費用
- 弁護士費用:示談交渉や訴訟のために弁護士に依頼した場合の費用の一部
- 物損に関する費用:事故によって破損した衣服や所持品などの損害
これらの損害についても、必要性や相当性が認められれば、示談金に含まれる可能性があります。
労災の示談交渉、いつ始める?適切なタイミングとは
労災の示談交渉を開始するタイミングは、非常に重要です。早すぎても遅すぎても、被災労働者にとって不利な結果を招く可能性があります。適切なタイミングを見極めることが、納得のいく解決への第一歩となります。
この章では、労災の示談交渉を開始する適切なタイミングについて、特に重要なポイントを解説します。
- 症状固定(治癒)の診断を受けてから
- 後遺障害等級が確定してから
- 焦らず慎重に判断する
症状固定(治癒)の診断を受けてから
労災の示談交渉を開始する最も基本的なタイミングは、医師から「症状固定」または「治癒」の診断を受けた後です。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態を指します。 完治していなくても、症状が安定し、後遺障害の有無や程度が確定できる状態になった時点と考えられます。
症状固定前に示談してしまうと、以下のようなリスクがあります。
- 後から症状が悪化したり、新たな後遺障害が判明したりしても、追加の賠償請求が困難になる。
- 適正な後遺障害慰謝料や逸失利益を算定できない。
そのため、まずは治療に専念し、医師の判断を待つことが重要です。会社側から早期の示談を迫られた場合でも、安易に応じず、症状固定の診断を待つべきです。
後遺障害等級が確定してから
労災事故によって後遺障害が残った場合は、症状固定後に労働基準監督署に障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級の認定を受けることになります。 この後遺障害等級が確定してから示談交渉を開始するのが一般的です。
後遺障害等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益を算定する上で非常に重要な要素となります。 等級が確定していなければ、これらの損害額を正確に計算することができません。
会社によっては、後遺障害等級の認定前に示談を提案してくることもありますが、等級が確定するまでは具体的な金額交渉に入るべきではありません。 認定された等級に不服がある場合は、審査請求などの不服申し立て手続きも検討する必要があります。
焦らず慎重に判断する
会社側から示談の提案があった場合でも、すぐに返事をする必要はありません。提示された内容を十分に検討し、必要であれば専門家である弁護士に相談するなど、時間をかけて慎重に判断することが大切です。
特に、以下のような場合は注意が必要です。
- 会社側が提示する示談金の額が、自分で計算した損害額や一般的な相場よりも著しく低い場合。
- 示談書の内容に、自分にとって不利な条項が含まれている場合(例:将来一切の請求を放棄する旨の条項など)。
- 会社側が、示談に応じなければ解雇するなどと圧力をかけてくる場合。
示談は一度成立すると、原則として覆すことはできません。 焦って不利な条件で合意してしまい、後で後悔することのないよう、納得できるまで交渉し、慎重に判断するようにしましょう。
労災の示談交渉、会社側の提示を鵜呑みにしない!注意すべき5つのポイント
会社から労災に関する示談の提案があった場合、その内容を鵜呑みにして安易に合意してしまうのは非常に危険です。会社側は、できるだけ支払う示談金を低く抑えようとするのが一般的だからです。 被災労働者自身が注意点を理解し、慎重に対応することが、適正な補償を得るために不可欠です。
この章では、会社からの示談提示に対して特に注意すべき5つのポイントを解説します。
- 提示された示談金の金額は妥当か
- 示談書の内容を隅々まで確認する
- 安易に「治癒」「症状固定」と認めない
- 労災保険の給付内容を正確に把握する
- 不用意な念書や同意書にサインしない
提示された示談金の金額は妥当か
会社から提示される示談金の額が、必ずしも適正な金額であるとは限りません。 むしろ、会社側の都合で低く見積もられている可能性が高いと考え、慎重に検討する必要があります。
提示された金額が妥当かどうかを判断するためには、以下の点を確認しましょう。
- 治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など、全ての損害項目が網羅されているか。
- 各損害項目の算定根拠は明確か。特に慰謝料や逸失利益の計算方法が適切か。
- 労災保険から給付される金額が正しく控除されているか。特別支給金まで控除されていないか。
- 過去の裁判例や一般的な相場と比較して、著しく低い金額ではないか。
自分で判断するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談し、提示額の妥当性についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。
示談書の内容を隅々まで確認する
示談が成立すると、通常、示談書(合意書、和解契約書など名称は様々)を作成します。 この示談書は法的な拘束力を持つ重要な書類であり、一度署名・捺印してしまうと、原則としてその内容を覆すことはできません。
示談書にサインする前には、内容を隅々まで確認し、不明な点や納得できない点があれば、必ず会社側に説明を求め、必要であれば修正を要求しましょう。
特に注意すべきは「清算条項」です。 これは、「本示談書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する」といった内容の条項で、これが記載されていると、示談成立後に新たな損害が判明しても、追加の請求ができなくなる可能性があります。
その他、支払いの時期や方法、遅延した場合の損害金など、細かい条件についてもきちんと確認しておく必要があります。
安易に「治癒」「症状固定」と認めない
会社側から「もう症状は固定したでしょう」「これ以上治療しても良くならないのでは」などと言われ、早期の示談を促されることがあります。しかし、「治癒」や「症状固定」の判断は、医学的な知見に基づいて医師が行うものです。 会社側の言葉を鵜呑みにして、安易に認めてはいけません。
症状固定前に示談してしまうと、
- その後も治療が必要になった場合の治療費が自己負担になる。
- 後遺障害が残った場合に、適正な後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れない。
といった不利益が生じる可能性があります。必ず主治医とよく相談し、医学的な判断に基づいて症状固定の時期を見極めるようにしましょう。
労災保険の給付内容を正確に把握する
示談交渉を行う前提として、自身が労災保険からどのような給付を、いくら受けられるのかを正確に把握しておくことが重要です。労災保険からの給付額は、会社に対する損害賠償請求額(示談金)から控除されるためです。
労災保険には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付など、様々な種類の給付があります。 また、これらの本給付とは別に、社会復帰促進等事業として特別支給金が支払われる場合もあります。
特に、特別支給金は損害賠償額から控除されないため、この点を会社側が誤解していたり、意図的に含めて控除計算していたりするケースもあるので注意が必要です。 労働基準監督署に確認するなどして、給付内容を正確に理解しておきましょう。
不用意な念書や同意書にサインしない
示談交渉の過程や、労災申請の手続きなどで、会社から念書や同意書への署名・捺印を求められることがあります。 これらの書類の内容をよく確認せずに安易にサインしてしまうと、後々不利な状況に陥る可能性があります。
例えば、以下のような内容の書類には特に注意が必要です。
- 「本件事故に関し、会社に対し一切の請求を放棄します」といった包括的な権利放棄の文言。
- 「会社の指示に従い、速やかに示談解決に協力します」といった、交渉の自由を制限するような文言。
- 事実と異なる内容や、自分に不利な内容が記載されている書類。
書類の内容がよく分からない場合や、少しでも疑問を感じる場合は、その場でサインせず、持ち帰って専門家である弁護士に相談するなど、慎重に対応しましょう。 一度サインしてしまうと、その内容に同意したとみなされる可能性が高いです。
労災の示談交渉、弁護士に相談するメリットとタイミング
労災の示談交渉は、法律や医学的な知識が必要となる場面が多く、被災労働者自身で対応するには限界があります。そのような場合に頼りになるのが弁護士です。弁護士に相談・依頼することで、より有利な条件で示談をまとめられる可能性が高まります。
この章では、労災の示談交渉を弁護士に相談するメリットと、相談する適切なタイミングについて解説します。
- 弁護士に相談・依頼するメリット
- 弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談・依頼するメリット
労災の示談交渉を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
- 適正な損害賠償額を算定してくれる
弁護士は、過去の裁判例や専門知識に基づいて、個別の事案に応じた適正な損害賠償額を算定してくれます。 会社側の提示額が妥当かどうかを客観的に判断し、不当に低い場合は増額交渉を行ってくれます。 - 会社との交渉を代行してくれる
会社との交渉は精神的な負担が大きいものですが、弁護士に依頼すれば、交渉の窓口となってもらえます。 法律の専門家である弁護士が交渉することで、会社側も誠実に対応せざるを得なくなり、有利な条件を引き出しやすくなります。 - 法的な手続きを任せられる
示談書の作成や内容確認、後遺障害等級認定の手続きなど、煩雑な法的手続きを代行またはサポートしてくれます。 これにより、被災労働者は治療やリハビリに専念できます。 - 精神的な支えになる
労災事故に遭い、心身ともに辛い状況にある被災労働者にとって、専門家である弁護士の存在は大きな精神的な支えとなります。 不安なことや疑問点を気軽に相談できる相手がいることは、非常に心強いでしょう。 - 裁判になった場合も安心
示談交渉がまとまらず、やむを得ず裁判になった場合でも、引き続き弁護士に代理人として対応してもらうことができます。
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いと言えます。具体的には、以下のようなタイミングで相談を検討しましょう。
- 労災事故が発生した直後
事故直後から弁護士に相談することで、証拠収集や会社との初期対応について適切なアドバイスを受けることができます。 - 会社から示談の提案があったとき
会社から示談金や示談書の内容が提示されたら、すぐにサインせず、まずは弁護士に相談して内容の妥当性を確認してもらいましょう。 - 症状固定の診断を受けたとき
症状固定の診断を受け、後遺障害が残りそうな場合は、後遺障害等級認定の手続きや、その後の示談交渉について弁護士に相談するのが良いでしょう。 - 会社との交渉がうまくいかないとき
自分で会社と交渉してみたものの、話が進まない、会社側の対応に不満があるといった場合も、弁護士に相談することで状況が打開できる可能性があります。 - その他、少しでも不安や疑問を感じたとき
示談交渉の進め方、損害賠償額の計算方法、法的な手続きなど、少しでも分からないことや不安なことがあれば、遠慮なく弁護士に相談してみましょう。
多くの法律事務所では、労災に関する初回相談を無料で行っています。 まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
労災で示談しないという選択肢と、その場合に起こり得ること
労災に関して会社と示談交渉を行ったものの、提示された条件に納得できない場合や、そもそも会社側が交渉に応じない場合など、示談が成立しないケースもあります。そのような場合、被災労働者にはどのような選択肢が残されているのでしょうか。また、示談しないことによってどのような事態が起こり得るのでしょうか。
この章では、労災で示談しないという選択肢と、その場合に考えられる展開について解説します。
- 示談しない場合の選択肢:労働審判や訴訟
- 示談しない場合に起こり得ること
示談しない場合の選択肢:労働審判や訴訟
会社との示談交渉が不成立に終わった場合、被災労働者が会社に対して損害賠償を請求するためには、法的な手続きを利用することになります。主な選択肢としては、労働審判や民事訴訟があります。
- 労働審判
労働審判は、労働者と事業主との間の個別労働紛争を、迅速かつ適正に解決することを目的とした手続きです。原則として3回以内の期日で審理が行われ、調停による解決を目指します。調停が成立しない場合は、裁判官と労働審判員が事案の実情に応じた解決案(労働審判)を示します。 - 民事訴訟(裁判)
労働審判でも解決しない場合や、より慎重な審理を求める場合は、地方裁判所に民事訴訟を提起することになります。 訴訟では、当事者双方が証拠を提出し、主張・立証を尽くした上で、最終的に裁判所が判決を下します。判決には法的な拘束力があり、相手方が支払いに応じない場合は強制執行も可能です。ただし、解決までに時間がかかる傾向があります。
どちらの手続きを選択するかは、事案の内容や求める解決のスピード、費用などを考慮して慎重に判断する必要があります。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
示談しない場合に起こり得ること
労災に関して会社と示談しない場合、以下のような事態が起こり得ます。
- 損害賠償請求権の消滅時効
会社に対する損害賠償請求権には、消滅時効があります。 具体的には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(人の生命または身体の侵害による損害賠償の場合は20年)で時効により消滅します。不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)、または不法行為の時から20年で時効となります。示談交渉が長引いている間に時効期間が経過してしまうと、たとえ正当な請求であっても、会社から時効を主張されて支払いを拒否される可能性があります。 - 解決までの長期化と費用の増加
労働審判や訴訟といった法的手続きを利用する場合、示談交渉で解決するよりも時間がかかるのが一般的です。 また、弁護士費用や裁判所に納める印紙代、郵券代などの費用も高額になる可能性があります。 - 精神的な負担の継続
紛争が長引けば長引くほど、精神的な負担も大きくなります。 早く解決して次のステップに進みたいと考えるのであれば、ある程度の譲歩も視野に入れつつ、早期の示談成立を目指すという考え方もあります。 - 会社との関係悪化
示談交渉が決裂し、法的手続きに移行すると、会社との関係がさらに悪化する可能性があります。特に、労災後もその会社で働き続けたいと考えている場合は、慎重な判断が必要です。
示談しないという選択をする場合は、これらの点を十分に考慮し、専門家である弁護士とよく相談した上で、最善の方法を検討するようにしましょう。
よくある質問
労災の示談に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
労災で示談金はいつもらえる?
労災で示談金が支払われるタイミングは、会社との示談が成立し、示談書を取り交わした後になります。 具体的な支払時期は示談書の中で定めることになりますが、一般的には示談成立から1ヶ月以内など、比較的速やかに支払われるケースが多いようです。ただし、これはあくまで目安であり、個別の交渉によって変わってきます。支払いが遅れる場合の遅延損害金についても、示談書に明記しておくことが望ましいでしょう。
労災の示談金に税金はかかる?
原則として、労災の示談金(損害賠償金)のうち、慰謝料や治療費、逸失利益といった損害の補填にあたる部分については、所得税はかかりません。これは、損害賠償金が利益ではなく、あくまで被った損害を元に戻すためのものと考えられるためです。ただし、休業損害に対する見舞金や、解決金といった名目で、損害の補填を超える部分が支払われたとみなされる場合には、一時所得として課税対象となる可能性もあります。不安な場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
労災の示談交渉は会社側から拒否されることもある?
はい、会社側が労災の示談交渉を拒否するケースもあります。 例えば、会社が「労災事故について会社に責任はない」と主張している場合や、被災労働者側の要求する金額があまりにも高額で折り合いがつかないと判断した場合などです。また、そもそも話し合いに応じないという不誠実な対応を取る会社も残念ながら存在します。そのような場合は、労働審判や民事訴訟といった法的手続きを検討する必要が出てきます。
労災の示談書にサインしたら、もう労災保険はもらえない?
原則として、示談が成立し、その示談の内容が労災保険給付でカバーされるべき損害の全額を填補するものであれば、その後の労災保険給付は行われないか、調整されることになります。 特に、示談書の中に「今後一切の請求権を放棄する」といった清算条項が含まれている場合、労災保険の請求も難しくなる可能性があります。 ただし、示談の内容や労災保険給付の種類によっては、引き続き給付を受けられるケースもあります。例えば、示談が一部の損害(慰謝料のみなど)についてのみ行われ、労災保険でカバーされるべき治療費や休業補償については別途請求する場合などです。不用意な示談は、労災保険の受給権に影響を与える可能性があるため、サインする前に必ず専門家(弁護士や労働基準監督署)に相談することが重要です。
労災の示談を弁護士に依頼した場合の費用は?
労災の示談交渉を弁護士に依頼した場合の費用は、法律事務所や依頼する弁護士、事案の複雑さなどによって異なります。一般的には、相談料、着手金、成功報酬、実費などがかかります。
- 相談料:法律相談をする際にかかる費用です。初回相談は無料としている事務所も多くあります。
- 着手金:弁護士に正式に依頼する際に支払う費用です。示談交渉の結果にかかわらず返金されないのが一般的です。
- 成功報酬:示談が成立し、経済的な利益が得られた場合に、その利益の一定割合を支払う費用です。
- 実費:交通費、郵便費、印紙代など、手続きを進める上で実際にかかった費用です。
弁護士費用については、依頼する前に必ず詳細な説明を受け、契約書の内容をよく確認するようにしましょう。最近では、着手金無料で完全成功報酬制を採用している事務所もあります。
会社が労災を認めてくれない場合はどうすればいい?
会社が労災であることを認めてくれない(労災隠しなど)場合でも、労働者自身が労働基準監督署に労災申請を行うことができます。 労災認定の判断は、最終的に労働基準監督署が行います。会社が協力してくれない場合でも、諦めずに申請手続きを進めましょう。申請方法が分からない場合や、会社からの妨害があるような場合は、弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。労災申請は労働者の正当な権利です。
労災の示談で後遺障害が残った場合の注意点は?
労災で後遺障害が残った場合の示談では、特に慎重な対応が必要です。 まず、必ず後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉に臨むようにしましょう。 後遺障害等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益を算定する上で最も重要な基準となります。 等級が確定する前に示談してしまうと、適正な賠償額を受け取れない可能性があります。また、示談書にサインする際には、将来的に症状が悪化した場合や、新たな後遺障害が判明した場合の取り扱いについても確認しておくことが望ましいですが、通常、清算条項により追加請求は困難です。 弁護士に相談し、将来的なリスクも考慮した上で、慎重に示談を進めることが重要です。
まとめ
- 労災の示談は、会社との合意で損害賠償問題を解決する方法。
- 示談金には治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などが含まれる。
- 労災保険からの給付額は、示談金から控除される。
- 示談のメリットは早期解決、デメリットは追加請求不可など。
- 示談交渉は症状固定・後遺障害等級確定後が基本。
- 会社提示の示談金額は鵜呑みにせず、妥当性を確認する。
- 示談書の内容、特に清算条項は入念にチェックする。
- 不用意な念書や同意書にはサインしない。
- 弁護士に依頼すると、適正額の算定や交渉代行のメリットがある。
- 示談しない場合は労働審判や訴訟も選択肢だが、時効に注意。
- 示談金には原則として所得税はかからない。
- 会社が示談を拒否する場合もある。
- 不用意な示談は労災保険の受給権に影響する可能性あり。
- 後遺障害が残った場合は、等級認定後の示談が鉄則。
- 労災の悩みは、まず弁護士などの専門家に相談することが大切。