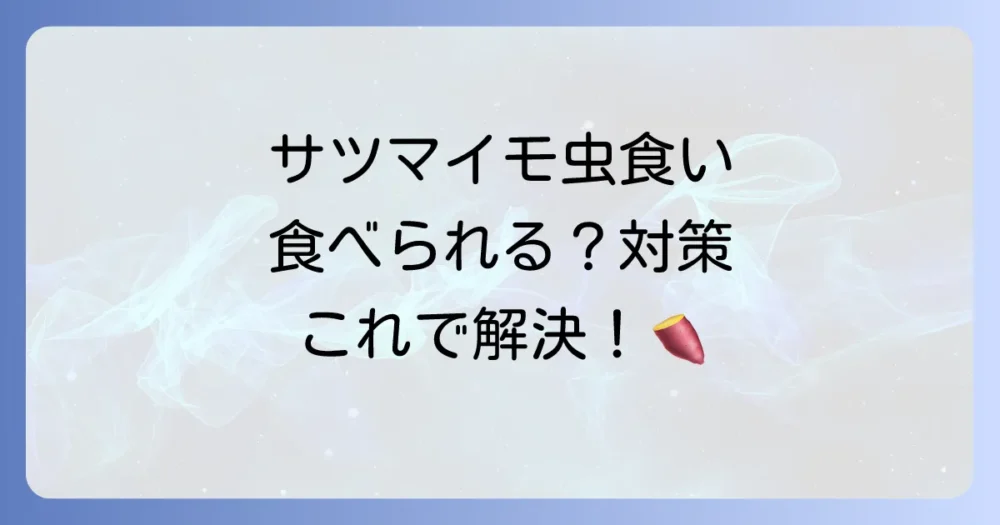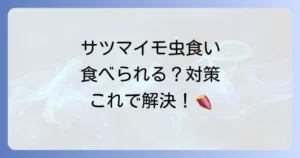大切に育てているサツマイモに虫がついてしまい、がっかりした経験はありませんか?「葉が穴だらけになっている…」「収穫した芋に黒い穴が…」そんな時、どう対処すれば良いのか、そもそもこのサツマイモは食べられるのか、不安になりますよね。家庭菜園でサツマイモを育てる多くの方が、同じ悩みを抱えています。でも、安心してください。この記事を読めば、サツマイモを悩ませる虫の正体から、今日からできる具体的な対策、そして気になる虫食い芋の食べ方まで、全ての疑問が解決します。虫の被害を最小限に抑え、美味しいサツマイモを収穫するための知識を身につけましょう。
大丈夫?サツマイモの虫食い、実は食べられます!
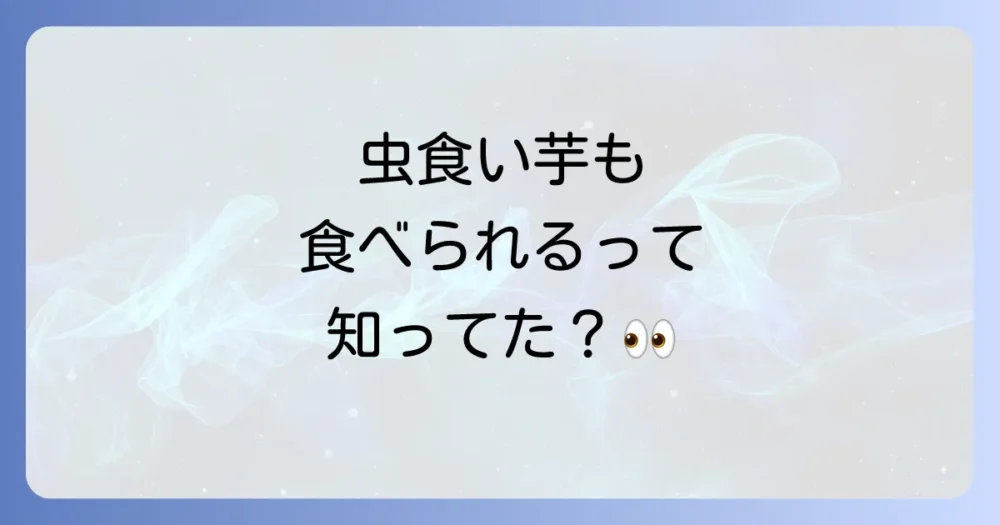
収穫したサツマイモに虫食いの穴を見つけると、食べるのをためらってしまいますよね。しかし、結論から言うと、虫食いの部分をしっかり取り除けば食べても問題ありません。 虫が食べた部分は、味や食感が悪くなっている可能性があるため、穴の周りを少し広めに包丁で削り取りましょう。
虫食いの原因となる虫自体に毒があるわけではなく、加熱調理すれば万が一虫のフンなどが残っていても衛生的には心配ないことがほとんどです。 ただし、穴から雑菌が入り、腐敗やカビが発生している場合は注意が必要です。異臭がしたり、明らかに傷んでいる部分は無理に食べず、思い切って処分しましょう。
無農薬で育てたサツマイモは、虫がつきやすい反面、安全性の高い証拠とも言えます。 虫食いは、いわば自然の中でたくましく育った勲章のようなもの。適切な処理をすれば、美味しくいただくことができますので、安心してくださいね。
【被害別】サツマイモを襲う主な害虫10選と見分け方
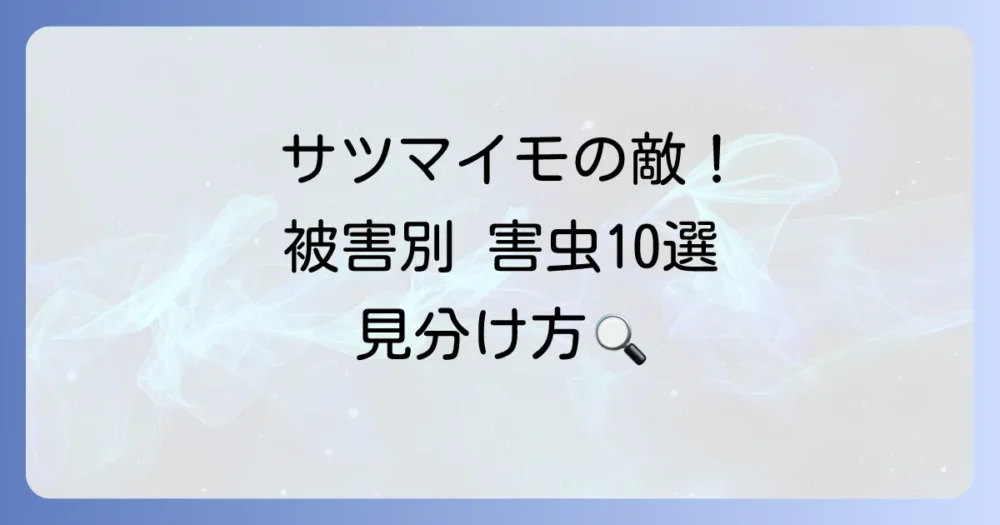
サツマイモに害を及ぼす虫は、葉を食べるものから、土の中で芋を直接食害するものまで様々です。被害の状況から原因となる虫を特定することが、効果的な対策への第一歩となります。ここでは、サツマイモに発生しやすい代表的な害虫を、被害を受ける場所ごとに分けて詳しく解説します。
- 葉を食べる虫
- 芋(塊根)を食べる虫
- 茎や苗を食べる虫
葉を食べる虫
葉は光合成を行い、芋を大きくするための栄養を作る大切な部分です。葉が虫に食べられてしまうと、生育不良につながり、収穫量の減少に直結します。葉に異変を見つけたら、早めに犯人を見つけ出しましょう。
ヨトウムシ
ヨトウムシは「夜盗虫」という名前の通り、夜間に活動して葉を食い荒らす厄介な害虫です。 昼間は土の中に隠れているため、姿が見えないのに葉だけが食べられている場合は、ヨトウムシの仕業を疑いましょう。 若い幼虫は緑色ですが、成長すると褐色や黒色になります。 葉の裏に卵を産み付け、ふ化した幼虫が集団で葉の表皮を残して食べるため、葉が白っぽく見えることもあります。
ナカジロシタバ
ナカジロシタバも蛾の一種で、その幼虫がサツマイモの葉を好んで食べます。 大発生すると、短期間で葉脈だけを残して葉を食べ尽くしてしまうほどの食欲旺盛な害虫です。 幼虫はシャクトリムシのような動き方をし、体長は4〜5cmほどになります。 葉の裏にいることが多いので、定期的にチェックすることが大切です。
エビガラスズメ
エビガラスズメはスズメガ科の蛾で、その幼虫は尻尾に一本のツノがあるのが特徴的な、大型のイモムシです。 緑色や褐色の大きな体で、サツマイモの葉をムシャムシャと食べ進めます。フンが大きく黒いので、葉の上や株元に黒いコロコロとしたものを見つけたら、近くに潜んでいる可能性が高いです。
アブラムシ
アブラムシは体長1〜3mmほどの小さな虫で、新芽や葉の裏にびっしりと群がって汁を吸います。 汁を吸われると株が弱るだけでなく、アブラムシの排泄物が原因ですす病などの病気を引き起こしたり、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第早急な対策が必要です。 光るものを嫌う性質があるため、シルバーマルチを敷くことで飛来をある程度防ぐことができます。
ヨツモンカメノコハムシ
成虫は亀の甲羅のような形をした茶褐色の面白い見た目の虫ですが、葉に楕円形の穴を開ける食害をもたらします。 幼虫は自分のフンや脱皮殻を背負うという変わった習性があります。発生数が多くなると、葉が網目状にされてしまい、光合成を妨げ生育不良の原因となるため注意が必要です。
芋(塊根)を食べる虫
土の中で育つ芋を直接食べる害虫は、収穫するまで被害に気づきにくいのが特徴です。収穫の喜びが一転、がっかりということにならないよう、土の中に潜む敵についても知っておきましょう。
コガネムシの幼虫
収穫したサツマイモの表面に、かじられたような傷や穴があったら、その犯人はコガネムシの幼虫である可能性が高いです。 カブトムシの幼虫に似た乳白色の体を丸めた姿で、土の中に潜んでいます。 未熟な堆肥などを畑に入れると、それを目当てに成虫が卵を産み付けやすくなるため、土作りには注意が必要です。
センチュウ
センチュウは肉眼ではほとんど見えない非常に小さな土壌生物ですが、サツマイモの根や芋に侵入して被害をもたらします。 芋の表面にひび割れができたり、奇形になったり、黒いシミのような斑点ができることがあります。連作をすると土壌中の密度が高まり、被害が大きくなる傾向があるため、同じ場所でサツマイモを続けて栽培するのは避けましょう。
ハリガネムシ
ハリガネムシはコメツキムシの幼虫で、その名の通り針金のように細長く硬い体をしています。土の中を移動しながら芋に侵入し、内部を食害します。 芋の表面には小さな穴が開き、中を掘ると細いトンネル状の食害痕が見られます。
ケラ
ケラはモグラのような前足を持ち、土中を掘り進む昆虫です。主に植物の根を食べますが、サツマイモの芋も食害することがあります。 芋の表面がえぐられるように、不規則な形でかじられるのが特徴です。
茎や苗を食べる虫
植え付けたばかりの苗や、成長途中の茎が被害にあうこともあります。生育の初期段階での被害は、その後の成長に大きく影響するため、特に注意が必要です。
イモキバガ
イモキバガは「イモコガ」とも呼ばれる小さな蛾で、その幼虫がサツマイモの茎や葉の付け根に潜り込んで内部を食害します。 被害を受けた部分は生育が止まったり、枯れてしまったりします。特に苗の時期に被害にあうと、株全体の成長が著しく悪くなるため注意が必要です。
もう悩まない!サツマイモの虫対策【予防から駆除まで】
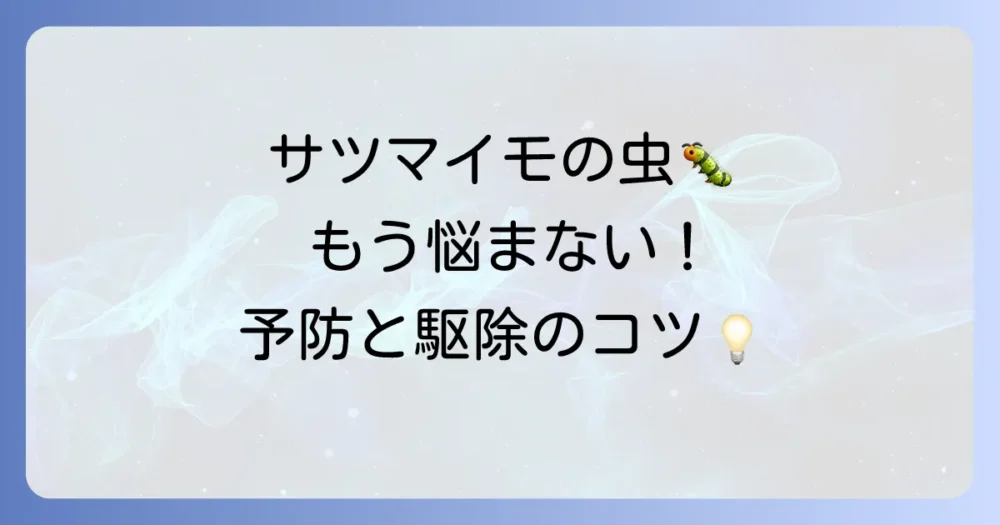
害虫の被害を防ぐためには、虫が発生してから対処するだけでなく、そもそも虫を寄せ付けない環境を作ることが重要です。ここでは、栽培前の準備から、万が一虫が発生してしまった場合の駆除方法まで、具体的な対策を段階的にご紹介します。
- 栽培前にできる!虫を寄せ付けない予防策
- 発生してしまった虫の駆除方法
栽培前にできる!虫を寄せ付けない予防策
美味しいサツマイモ作りは、植え付け前の準備から始まっています。少しの手間で害虫のリスクを大きく減らすことができるので、ぜひ実践してみてください。
土作りと畑の準備
コガネムシの幼虫は、未熟な堆肥などの有機物を好みます。 堆肥を使う場合は、必ず完熟したものを選びましょう。 また、センチュウ対策として、マリーゴールドやエンバクなどを植え付け前に育て、土にすき込む「緑肥」も効果的です。 これらの植物は、センチュウの増殖を抑える働きがあります。
無病の苗を選ぶ
病害虫に侵されていない、健康な苗を選ぶことは基本中の基本です。ウイルス病などはアブラムシによって媒介されるため、最初から病気にかかっていない苗を選ぶことが、その後のアブラムシ被害のリスクを減らすことにも繋がります。 葉の色が良く、茎がしっかりとした元気な苗を選びましょう。
コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いによい影響を与え合う植物のことです。 サツマイモの場合、赤シソを近くに植えると、コガネムシがその赤い色を嫌って寄り付きにくくなると言われています。 また、マリーゴールドはセンチュウを、ネギ類は様々な害虫を遠ざける効果が期待できます。
マルチングで飛来を防ぐ
畑の畝をビニールシート(マルチ)で覆う「マルチング」は、地温の確保や雑草防止だけでなく、害虫対策にも有効です。 特に、銀色のシルバーマルチは光を反射するため、アブラムシの飛来を防ぐ効果が高いです。 また、マルチで土の表面を覆うことで、コガネムシの成虫が土の中に産卵するのを物理的に防ぐこともできます。
発生してしまった虫の駆除方法
予防策を講じていても、虫が発生してしまうことはあります。被害が広がる前に、迅速に対処しましょう。駆除方法には、農薬を使わない手軽なものから、薬剤を使用する方法まで様々です。
農薬を使わない!手軽にできる駆除方法
家庭菜園では、できるだけ農薬を使いたくないと考える方も多いでしょう。
- 手で取り除く: ヨトウムシやエビガラスズメの幼虫など、目に見える大きな虫は、見つけ次第、手で捕まえて駆除するのが最も確実で手っ取り早い方法です。
- 牛乳スプレー: アブラムシには、牛乳を水で少し薄めてスプレーするのが効果的です。牛乳が乾くときに膜を作り、アブラムシを窒息させます。 使用後は水で洗い流しましょう。
- 木酢液: ヨトウムシは木酢液の匂いを嫌います。 規定の倍率に薄めた木酢液を散布することで、寄り付きにくくする効果が期待できます。
- 粘着テープ: アブラムシは黄色に集まる習性があります。 黄色の粘着テープを近くに吊るしておくと、飛来したアブラムシを捕獲できます。
効果的な農薬の選び方と使い方
害虫が大量発生してしまい、手作業での駆除が追いつかない場合は、農薬の使用も検討しましょう。サツマイモに使える農薬は、害虫の種類によって異なります。
例えば、コガネムシの幼虫には「ダイアジノン粒剤」などを植え付け時に土に混ぜ込むのが効果的です。 ヨトウムシやナカジロシタバなど葉を食べる虫には、散布用の殺虫剤が各種販売されています。
農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている適用作物、対象害虫、使用時期、希釈倍率などをよく確認し、正しく使用することが非常に重要です。 特に収穫前使用日数には注意し、安全なサツマイモを収穫しましょう。
【収穫後も油断禁物】サツマイモの保存と虫対策
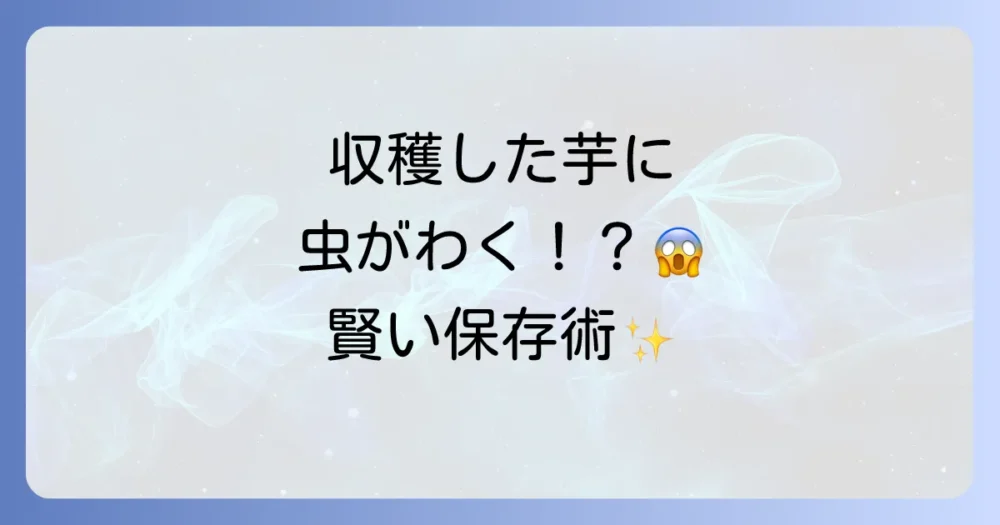
無事に収穫できたからといって、まだ安心はできません。収穫後のサツマイモも、保存状態によっては虫の被害にあう可能性があります。特に、収穫時に芋についていた小さな虫や卵が、保存中にふ化して食害を始めるケースです。
サツマイモを長期保存する際の基本は、「低温すぎず、湿度を保つ」ことです。最適な温度は13〜15℃と言われており、冷蔵庫に入れると低温障害を起こして傷みやすくなります。新聞紙で一本ずつ包み、段ボール箱などに入れて、暖房の影響を受けない涼しい場所で保存しましょう。
収穫した芋は、土を軽く落とす程度にし、水洗いはしないでください。表面が濡れていると腐りやすくなります。また、収穫時にできた傷口から虫が侵入したり、腐敗の原因になったりするため、傷のある芋は長期保存せず、早めに食べるようにしましょう。
よくある質問
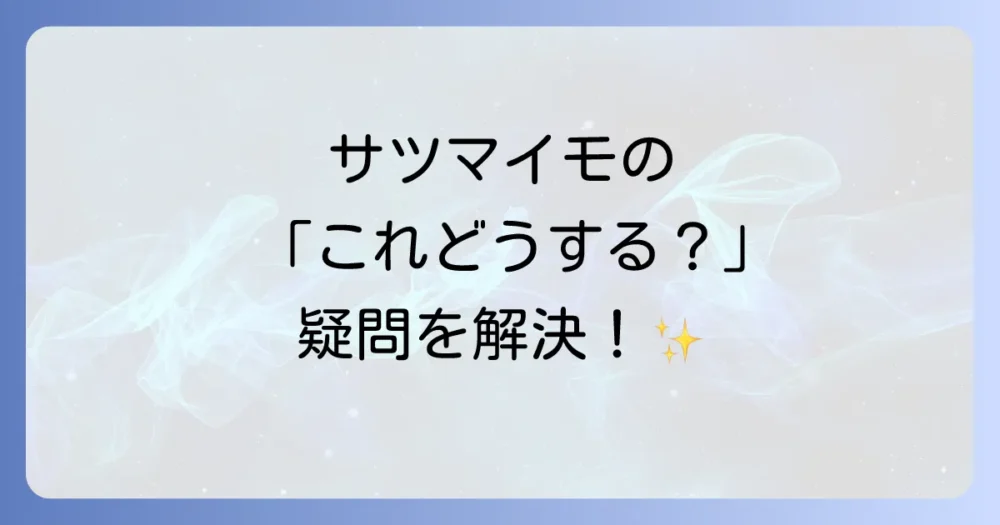
サツマイモの黒い点は虫ですか?
サツマイモの皮や断面に見られる黒い点は、必ずしも虫が原因とは限りません。切り口から出るヤラピンという白い液体が空気に触れて黒く変色した場合や、センチュウなどの害虫被害の痕、あるいは「黒斑病」などの病気の可能性が考えられます。 虫食いの場合は小さな穴や食害された跡が見られますが、単なる変色であれば、その部分を取り除けば問題なく食べられます。
サツマイモの葉が食べられて穴だらけなのはなぜですか?
サツマイモの葉に穴が開いている場合、ヨトウムシ、ナカジロシタバ、エビガラスズメ、ヨツモンカメノコハムシといった害虫による食害の可能性が高いです。 特に夜間に被害が進行しているようであればヨトウムシ、葉脈だけを残してレース状に食べられている場合はナカジロシタバの幼虫などが考えられます。 葉の裏や周辺の土をよく観察し、虫の姿やフンがないか確認してみましょう。
無農薬でサツマイモを育てると虫はつきますか?
はい、無農薬で栽培すると、農薬を使用した場合に比べて虫がつきやすくなるのは事実です。 しかし、本記事で紹介したようなコンパニオンプランツの活用、マルチング、こまめな見回りによる早期発見・手作業での駆除など、農薬に頼らない方法でも害虫の被害を抑えることは十分に可能です。 無農薬栽培は、虫にとって居心地が良い、つまり自然に近い環境である証拠とも言えます。
サツマイモの収穫時期の目安は?
サツマイモの収穫時期は、苗を植え付けてから120日〜150日後が一般的です。地上部の葉や茎が黄色く枯れ始めたら収穫のサインです。試し掘りをしてみて、十分な大きさに育っているか確認すると良いでしょう。収穫が遅れると、芋が大きくなりすぎたり、害虫の被害にあうリスクが高まったりすることがあります。
サツマイモのつる返しは必要ですか?
「つる返し」とは、伸びたつるの途中から出てくる根(不定根)を地面から剥がす作業のことです。この不定根からも小さな芋ができてしまい、本来大きくしたい株元の芋に栄養が集中しなくなるのを防ぐために行います。必ずしも必要な作業ではありませんが、つる返しを行うことで、大きくて形の良い芋が収穫しやすくなる傾向があります。
まとめ
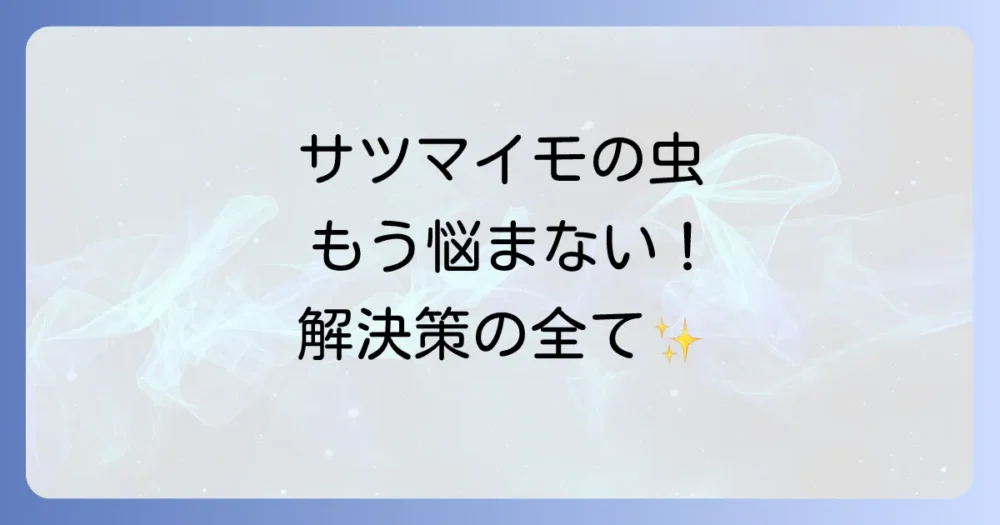
- 虫食いのサツマイモは、被害部分を取り除けば食べられる。
- 葉を食べる主な害虫はヨトウムシやナカジロシタバ。
- 芋を食べる主な害虫はコガネムシの幼虫やセンチュウ。
- 害虫対策は、予防と駆除の両面から行うことが重要。
- 完熟堆肥の使用やマルチングは効果的な予防策。
- コンパニオンプランツとして赤シソやマリーゴールドが有効。
- 発生した虫は、手で取り除くか、天敵を利用する。
- アブラムシには牛乳スプレーが手軽で効果的。
- 農薬を使う際は、必ずラベルの指示に従う。
- コガネムシ幼虫には土壌混和タイプの薬剤が有効。
- センチュウ対策には連作を避けることが基本。
- 収穫後の保存中も虫が発生することがある。
- 保存は新聞紙に包み、涼しい場所で行う。
- 傷のある芋は長期保存に向かないため早めに消費する。
- 虫の被害を正しく理解し、適切な対処で美味しいサツマイモを守ろう。
新着記事