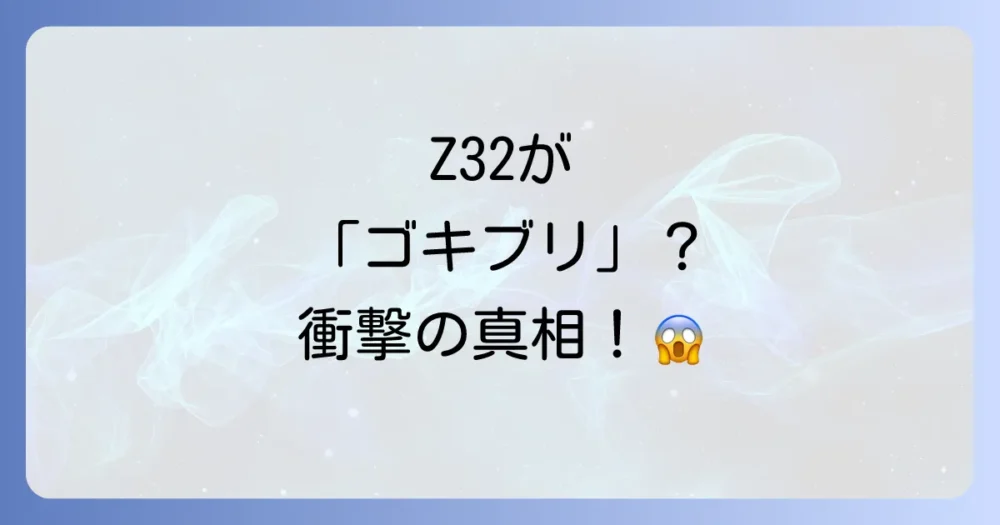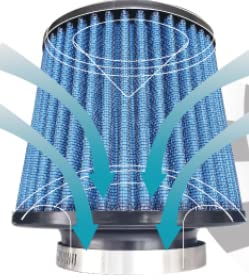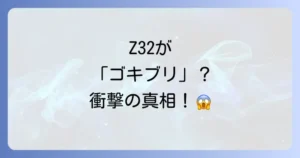「Z32がゴキブリって呼ばれてるの?ひどい…」なんて、愛車のフェアレディZ Z32がそんな風に呼ばれていると知ったら、ショックを受けてしまいますよね。でも、安心してください。実はその呼び名、必ずしも悪口として使われているわけではないのです。本記事では、Z32が「ゴキブリ」と呼ばれるようになった衝撃的な理由から、その呼び名に対するオーナーたちの本音、そしてZ32が今なお多くのファンを魅了し続ける不朽の名車である実像まで、余すところなく徹底的に解説していきます。この記事を読めば、Z32への愛がさらに深まること間違いなしです。
Z32が「ゴキブリ」と呼ばれる衝撃の理由
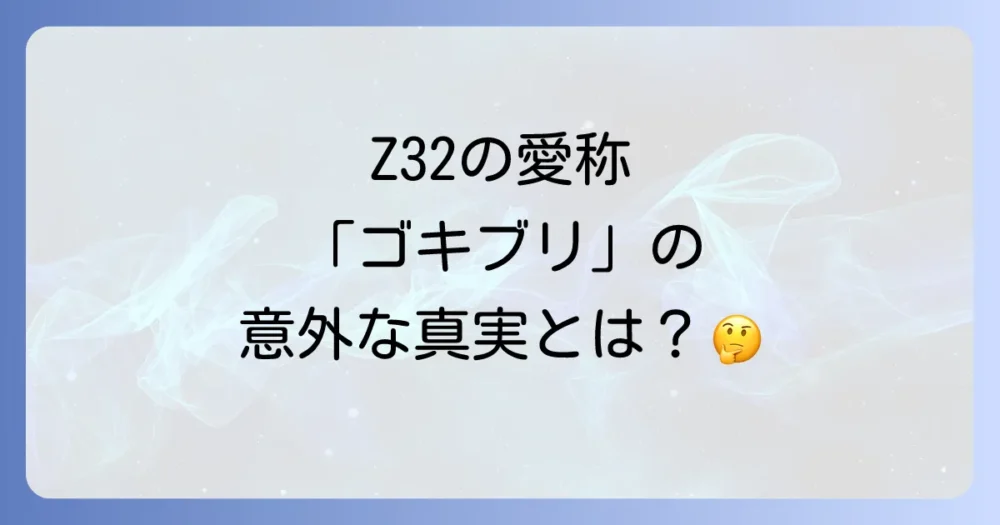
日産が誇るスポーツカー、フェアレディZの4代目モデルとして1989年に登場したZ32。その斬新なデザインと高い性能で一世を風靡しましたが、一部では「ゴキブリ」という、お世辞にも良いとは言えない愛称で呼ばれることがあります。なぜ、これほどの名車がそのような名前で呼ばれるのでしょうか。その背景には、Z32ならではの特徴が深く関係していました。ここでは、その主な理由を3つのポイントから探っていきます。
- 理由1:唯一無二のワイド&ローなフォルム
- 理由2:当時の流行色だったブラック系のボディカラー
- 理由3:俊敏でパワフルな走行性能
- これは悪口?それとも愛称?オーナーたちの本音
理由1:唯一無二のワイド&ローなフォルム
Z32が「ゴキブリ」と呼ばれる最大の理由は、その独特のスタイリングにあります。 全高が低く、全幅が広い、いわゆる「ワイド&ロー」なデザインは、地面に張り付くように走る姿を連想させます。 特に、フロントからリアにかけて流れるように一体化したボディラインと、低く構えたそのフォルムが、見る角度によっては黒光りするあの虫の姿と重なって見えてしまったのです。
しかし、このデザインこそがZ32の最大の魅力でもあります。当時の国産車としては類を見ない先進的で美しいスタイリングは、多くの人々を魅了しました。 実際、そのデザイン性の高さは海外でも評価され、ランボルギーニ・ディアブロのヘッドライトにZ32のものが流用されたという逸話は有名です。 つまり、「ゴキブリ」という呼び名は、その唯一無二のデザインが生んだ、ある種の宿命だったのかもしれません。
理由2:当時の流行色だったブラック系のボディカラー
Z32が販売されていた1990年代は、車のボディカラーとしてブラックが非常に人気でした。Z32も例外ではなく、市場には多くのブラック系の個体が出回っていました。 ワイド&ローのフォルムに、光沢のあるブラックの塗装が施されると、その姿はまさに「黒い塊」。夜の街灯の下などを俊敏に走り抜ける様子が、より一層「ゴキブリ」のイメージを強くしたと考えられます。
もちろん、Z32にはイエローやシルバーなど、他の魅力的なカラーも存在します。 しかし、当時の流行とZ32のデザインが見事にマッチした結果、ブラックのイメージが定着し、「ゴキブリ」という愛称に繋がった側面は否定できないでしょう。
理由3:俊敏でパワフルな走行性能
見た目だけでなく、Z32の走行性能も「ゴキブリ」という呼び名に関係している可能性があります。ツインターボモデル「VG30DETT」は、国産車で初めて最高出力280馬力を達成したエンジンとして知られています。 そのパワフルなエンジンが生み出す俊敏な加速性能は、まさに獲物を見つけた虫が素早く動き出す様を彷彿とさせます。
アクセルを踏み込んだ瞬間に地面を蹴って猛然とダッシュする感覚は、オーナーでしか味わえない快感です。その圧倒的な速さが、畏敬の念を込めて「ゴキブリ」という、ある意味で生命力の強さを感じさせる呼び名に繋がったのかもしれません。
これは悪口?それとも愛称?オーナーたちの本音
では、「ゴキブリ」という呼び名は、悪口として使われているのでしょうか。実は、一概にそうとは言えません。もちろん、Z32のデザインを好まない人が揶揄して使う場合もあります。 しかし、オーナーやファンの間では、むしろ親しみを込めた愛称として使われることが多いのです。
「ゴキブリみたいに速い」「地面に張り付くような走りがたまらない」といったように、その独特のフォルムや性能を肯定的に捉え、愛情表現の一つとして使っているケースが少なくありません。 ネット上のコミュニティやオーナーズクラブなどでは、自ら「ゴキブリZ」と称して楽しんでいる様子も見受けられます。 結局のところ、この呼び名が悪口か愛称かは、発言者の意図や文脈によって変わる、非常にユニークな存在だと言えるでしょう。
「ゴキブリ」だけじゃない!Z32の多彩な愛称
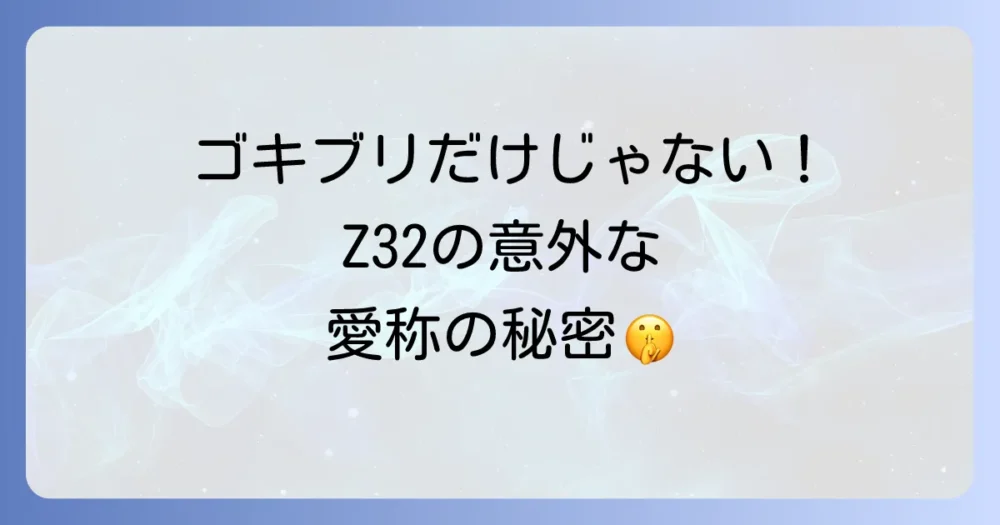
Z32には「ゴキブリ」以外にも、様々な愛称が存在します。その多くは、Z32が持つ魅力や特徴を捉えたものであり、いかに多くの人々から注目され、愛されてきたかの証と言えるでしょう。ここでは、Z32のポジティブな愛称と、少しネガティブな愛称、それぞれの背景を探っていきます。
- ポジティブな愛称の数々
- ネガティブな愛称とその背景
ポジティブな愛称の数々
Z32は、その型式名からシンプルに「サンニー」や「ゼットサンニー」と呼ばれることが最も一般的です。これは、スカイラインGT-RのR32が「サンニー」と呼ばれるのと同様で、車好きの間ではごく自然な呼び方です。
また、その美しいデザインから「スーパーモデル」や「平成の名車」と称されることもあります。 バブル期に開発されたZ32は、コストを度外視したかのような贅沢な設計が随所に見られます。 その流麗なスタイリングと、国産初の280馬力というパワフルな性能は、まさに時代の寵児。今見ても色褪せないその魅力は、多くのファンにとって特別な存在であり続けています。
ネガティブな愛称とその背景
一方で、ネガティブな意味合いで使われる愛称も存在します。「壊れやすい」「金食い虫」といった呼び名は、Z32が抱える弱点に由来するものです。
特にエンジンルームの狭さは有名で、整備性の悪さにつながっています。 ちょっとした部品交換でも、多くのパーツを外さなければならず、工賃が高額になりがちです。また、年式的に経年劣化による故障は避けられず、エアコンやパワートランジスタ、燃料ポンプなどは定番の故障箇所として知られています。 これらの維持に関する難しさが、「やめとけ」と言われる所以であり、ネガティブな愛称を生む原因となっているのです。
専門家が語る!Z32のデザイン哲学と革新性
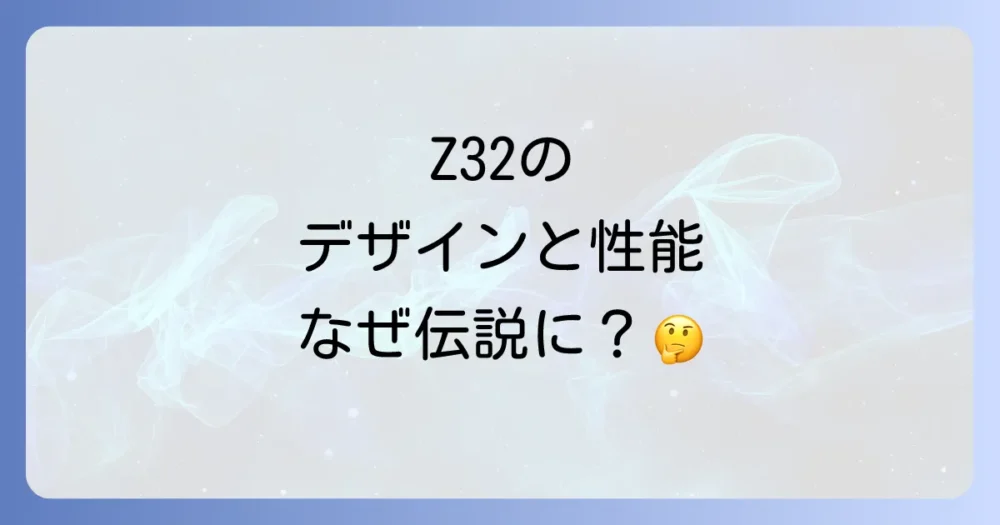
Z32のデザインは、なぜこれほどまでに人々を惹きつけ、そして「ゴキブリ」とまで呼ばれるほどのインパクトを与えたのでしょうか。その答えは、開発当時のデザイン哲学と、時代を先取りした革新性にあります。ここでは、専門的な視点からZ32のデザインと性能の凄さを掘り下げていきます。
- 時代を先取りした先進的なデザイン
- 日本車離れしたパワフルなエンジン
- 当時のライバル車との比較
時代を先取りした先進的なデザイン
Z32のデザインを手がけたのは、日産の名デザイナーとして知られる山下敏男氏です。 彼は、従来のフェアレディZが持っていたロングノーズ・ショートデッキという伝統的なスタイルをあえて覆し、キャビンフォワードのモダンなフォルムを採用しました。
特に印象的なのが、60度という極端な角度で傾斜したヘッドライトです。 当時の技術では実現不可能とまで言われたこのデザインは、Z32の先進性を象徴しています。 また、凹凸の少ない滑らかなボディラインは、シンプルでありながら力強さと美しさを両立させており、今なお多くのデザイナーに影響を与えています。 この時代を超越した普遍的なデザインこそが、Z32が「名車」と呼ばれる最大の理由なのです。
日本車離れしたパワフルなエンジン
Z32の魅力はデザインだけではありません。搭載されたエンジンもまた、革新的なものでした。V型6気筒3リッターの「VG30DE」と、それにツインターボを装着した「VG30DETT」の2種類が用意されました。
特筆すべきは、ツインターボモデルの「VG30DETT」です。当時の自主規制値いっぱいの280馬力を発生させ、国産スポーツカーのパワー競争の火付け役となりました。 このパワフルなエンジンと、4輪マルチリンクサスペンションやスーパーHICASといった最新技術が組み合わさることで、Z32は欧州の高級スポーツカーに匹敵する走行性能を手に入れたのです。
当時のライバル車との比較
Z32が登場した1989年は、日本の自動車史における「ヴィンテージイヤー」と呼ばれています。 同年には、トヨタからスープラ(A70型)、マツダからユーノス・ロードスター(NA型)、そして同じ日産からはスカイラインGT-R(R32型)といった、今なお語り継がれる名車たちが次々と誕生しました。
その中でもZ32は、エレガントなGTカー(グランドツーリングカー)としての性格が強いモデルでした。ライバルたちが走行性能の高さを前面に押し出す中、Z32は美しいデザインと快適な居住性、そして余裕のあるパワーを兼ね備え、独自のポジションを築いていました。 速さだけでなく、所有する喜びや長距離を快適に移動する楽しさを提供してくれる、大人のためのスポーツカー。それがZ32だったのです。
Z32オーナーが直面する現実!維持する上での注意点
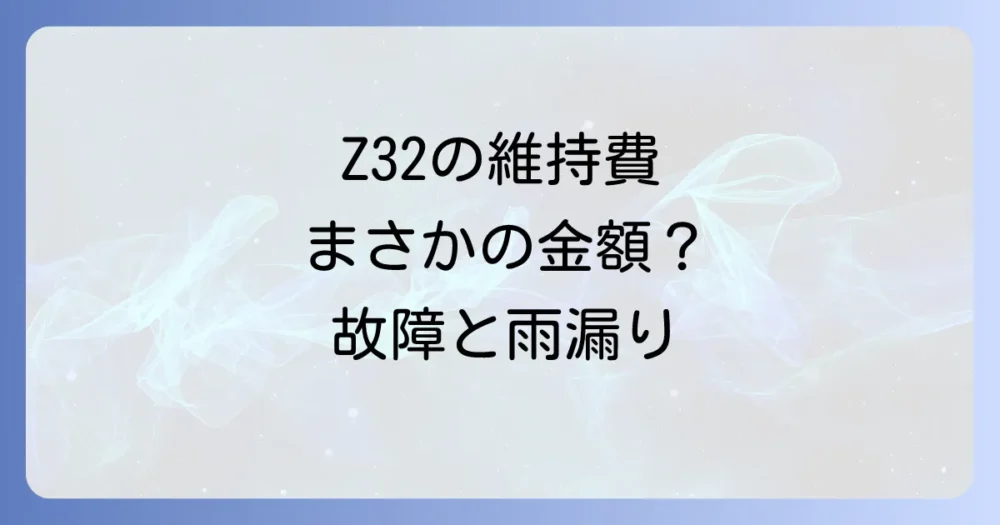
Z32の魅力に惹かれ、購入を検討している方も多いでしょう。しかし、生産終了から20年以上が経過した旧車であるため、維持していくには相応の覚悟と知識が必要です。ここでは、Z32オーナーが直面する現実的な問題点と、その対策について解説します。
- 避けては通れない故障リスク
- 気になる維持費はどのくらい?
- Tバールーフの雨漏りは宿命か?
避けては通れない故障リスク
Z32を維持する上で最大の課題は、やはり故障との闘いです。特に電装系のトラブルは多く、パワートランジスタの故障によるエンジン不調や、エアコンのコンプレッサー故障は定番中の定番と言えるでしょう。 また、エンジンルームが高温になりやすいため、ゴムや樹脂パーツの劣化が早く、ホース類からのオイル漏れや水漏れにも注意が必要です。
これらの故障は、ある日突然やってきます。信頼できる整備工場を見つけておくことはもちろん、日頃から車の状態をよく観察し、異変を感じたらすぐに対処することが重要です。また、純正部品の供給が少なくなってきているため、リビルト品や社外品をうまく活用する知識も必要になります。
気になる維持費はどのくらい?
Z32の年間維持費は、車の状態や乗り方によって大きく変わりますが、最低でも年間50万円以上は見込んでおいた方が良いでしょう。 内訳としては、自動車税(重課ありで58,600円)、車検費用、任意保険料、ガソリン代、そして突発的な故障に備えるための修理費用です。
燃費は、街乗りでリッター5〜7km程度、高速道路で10km/L前後というのが現実的な数値です。 もちろん、ツインターボ車で走りを楽しめば、さらに悪化します。 燃料はハイオク指定なので、ガソリン代も決して安くはありません。購入費用だけでなく、こうしたランニングコストもしっかりと計算に入れておくことが、Z32と長く付き合っていくための秘訣です。
Tバールーフの雨漏りは宿命か?
Z32の象徴的な装備の一つであるTバールーフ。開放感あふれるドライブを楽しめる一方で、多くのオーナーを悩ませるのが雨漏りです。 主な原因は、ルーフとボディの境目にあるゴム製ウェザーストリップの経年劣化です。このゴムが硬化したり、ひび割れたりすることで隙間ができ、そこから雨水が侵入してしまいます。
ウェザーストリップを新品に交換すれば改善されますが、部品代と工賃で10万円以上かかることも珍しくありません。また、交換しても完全に雨漏りが止まらないケースもあり、オーナーにとっては悩みの種です。雨漏りを防ぐためには、定期的なゴムのメンテナンスや、屋根付き駐車場での保管が効果的です。
今、Z32に乗るということ!中古車選びのコツ
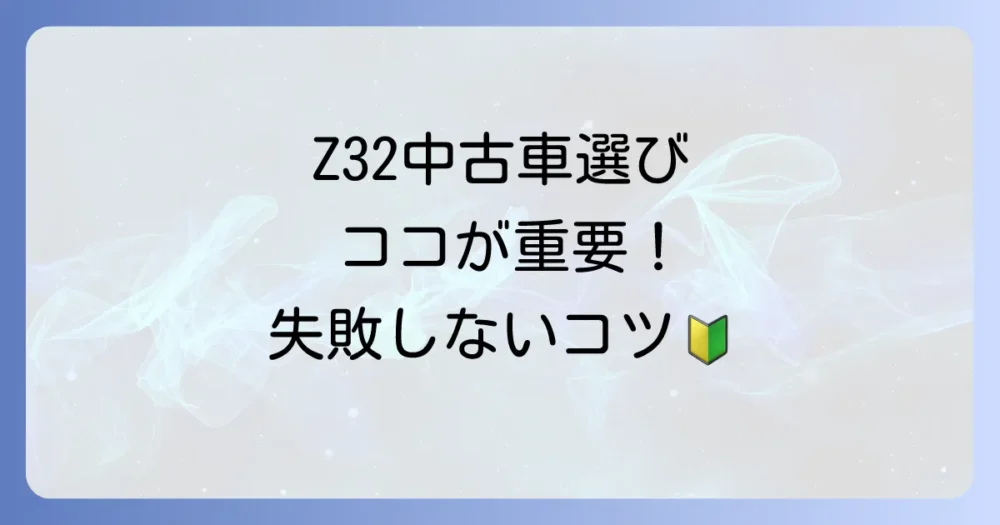
様々な困難がありながらも、Z32は今なお多くの人々を惹きつけてやまない魅力的な車です。状態の良い個体は減ってきていますが、ポイントを押さえれば、まだまだ良いZ32に巡り会うことは可能です。ここでは、中古車選びで失敗しないためのコツをご紹介します。
- 中古車市場でのZ32の現状と価格相場
- 失敗しない中古車選びのチェックポイント
- 前期型と後期型の違いと選び方
中古車市場でのZ32の現状と価格相場
Z32の中古車価格は、近年高騰傾向にあります。特に、スポーツカー人気やネオクラシックカーブームの影響で、状態の良い個体は驚くような価格で取引されています。
価格相場は非常に幅広く、安いものでは100万円台から見つかりますが、これらは走行距離が多かったり、修復歴があったりするものがほとんどです。 状態の良いノーマルに近い個体や、最終型のバージョンRといった希少グレードになると、300万円から500万円以上、場合によっては1000万円を超えるプライスがつくこともあります。 予算と車の状態のバランスをよく見極めることが重要です。
失敗しない中古車選びのチェックポイント
Z32の中古車選びで最も重要なのは、内外装の状態よりも機関系のコンディションです。特に以下の点は、必ずチェックしましょう。
- エンジン:アイドリングは安定しているか、異音や白煙はないか。オイル漏れの痕跡も要チェック。
- ミッション:AT、MTともにスムーズに変速できるか。MTの場合はクラッチの滑りにも注意。
- 電装系:エアコン、パワーウィンドウ、メーター類など、全ての電装品が正常に作動するか確認する。
- 修復歴:修復歴の有無は必ず確認。特にフロント周りの修復歴は、走行に影響を与える可能性があるため注意が必要。
- 整備記録簿:過去の整備履歴がわかる記録簿があれば、車の状態を把握する上で非常に役立ちます。
可能であれば、Z32に詳しい専門ショップや、信頼できる整備士と一緒に現車確認をすることをおすすめします。
前期型と後期型の違いと選び方
Z32は11年という長い生産期間の中で、複数回のマイナーチェンジが行われています。 大きく分けると、1989年〜1993年頃までの前期型、1993年〜1998年頃までの中期型、そして1998年〜2000年までの後期型(最終型)に分類できます。
主な違いは以下の通りです。
- 外装:後期型ではフロントバンパーやリアスポイラーのデザインが変更され、より洗練された印象になりました。
- 内装:エアバッグの標準装備化やシート生地の変更など、年々改良が加えられています。
- 機関:ブレーキキャリパーの材質がアルミから鉄製に変更されたり(中期以降)、ボディ剛性が向上したり(後期)と、走行性能に関わる部分も進化しています。
一般的に、年式が新しくなるほど熟成され、信頼性も高まるため、予算が許すのであれば後期型がおすすめです。しかし、初期型のシンプルなデザインに魅力を感じるファンも多く、最終的には個人の好みと予算で決めることになるでしょう。
よくある質問
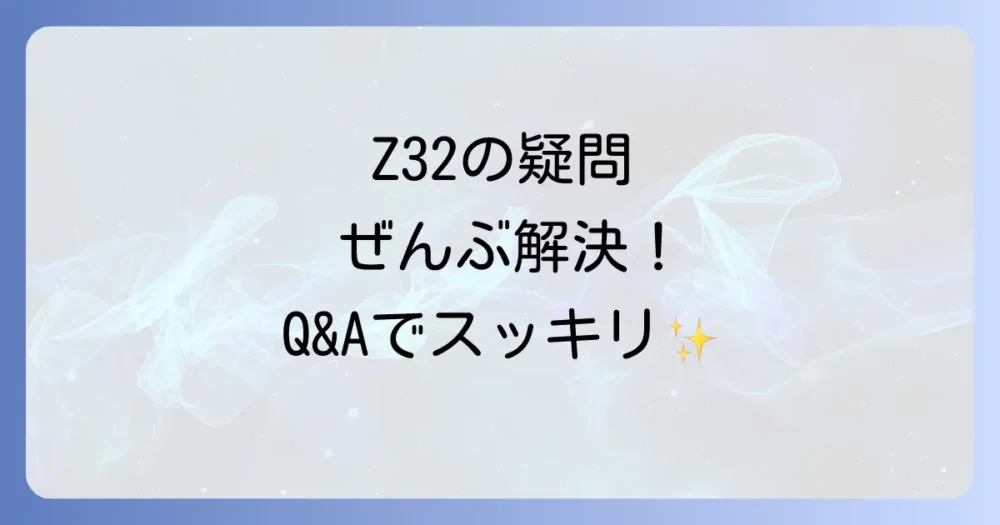
Z32のデザイナーは誰ですか?
Z32のデザインは、当時日産自動車に在籍していたデザイナーの山下敏男氏と、そのチームによって手掛けられました。 彼はZ32の他にも、セドリック430などをデザインしたことで知られています。 彼の先進的なデザインアプローチが、Z32という不朽の名車を生み出したのです。
Z32の弱点は何ですか?
Z32の主な弱点としては、エンジンルームの狭さからくる整備性の悪さ、電装系の故障(特にパワートランジスタやエアコン)、エンジンルームの熱によるゴム・樹脂パーツの劣化、Tバールーフからの雨漏りなどが挙げられます。 これらは経年劣化によるものが多く、旧車を維持する上である程度は覚悟が必要です。
フェアレディZで一番人気なのは何代目ですか?
どの世代も根強い人気がありますが、各種の人気投票などを見ると、初代S30型と4代目Z32型が特に高い人気を誇っています。 S30型は「悪魔のZ」として漫画にも登場し、そのヒストリーとクラシックなスタイルで多くのファンを魅了しています。一方、Z32型はバブル期ならではの先進的なデザインと高性能で、今なお多くの人々から支持を集めています。
Z32の燃費はどのくらいですか?
Z32の燃費は、モデルや運転状況によって大きく異なりますが、カタログ燃費(10・15モード)ではリッターあたり7.6km/Lから8.0km/L程度です。 実燃費としては、街乗りでリッター5〜7km、高速道路を大人しく走って10km/L前後というのが一般的なようです。 ツインターボ車でスポーティーな走行をすれば、リッター5kmを下回ることも珍しくありません。
まとめ
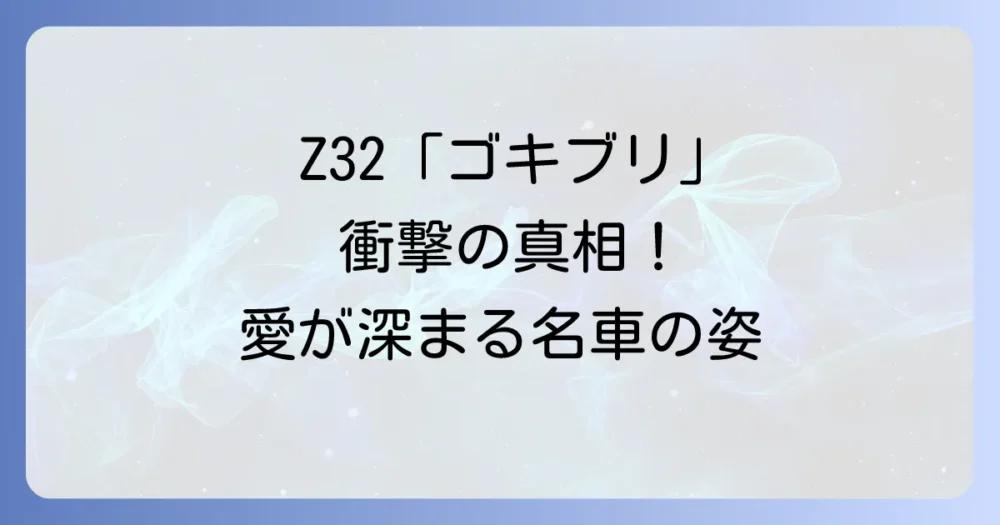
- Z32が「ゴキブリ」と呼ばれるのは、そのワイド&ローなフォルムが主な理由。
- 黒いボディカラーと俊敏な走りも「ゴキブリ」のイメージを補強した。
- オーナーの間では「ゴキブリ」は愛情を込めたニックネームとして使われることも多い。
- Z32のデザインは山下敏男氏が手掛け、海外でも高く評価されている。
- 国産車で初めて280馬力を達成し、パワー競争の先駆けとなった。
- 当時のライバル車と比べ、GTカーとしての性格が強いモデルだった。
- 弱点は整備性の悪さと電装系の故障、そして雨漏り。
- 維持費は年間50万円以上を見込む必要があり、覚悟が必要。
- 中古車価格は高騰しており、状態の良い個体は300万円を超える。
- 中古車選びは機関系のコンディションを最優先にチェックすることが重要。
- Z32は前期・中期・後期に分かれ、後期型ほど熟成されている。
- 「ゴキブリ」という呼び名は、Z32の強烈な個性の裏返しである。
- 今なお多くのファンを魅了する、平成を代表する名車の一つ。
- その魅力は、時代を超越した美しいデザインと高い性能にある。
- Z32と付き合うには、愛情と知識、そして経済的な余裕が不可欠。
新着記事