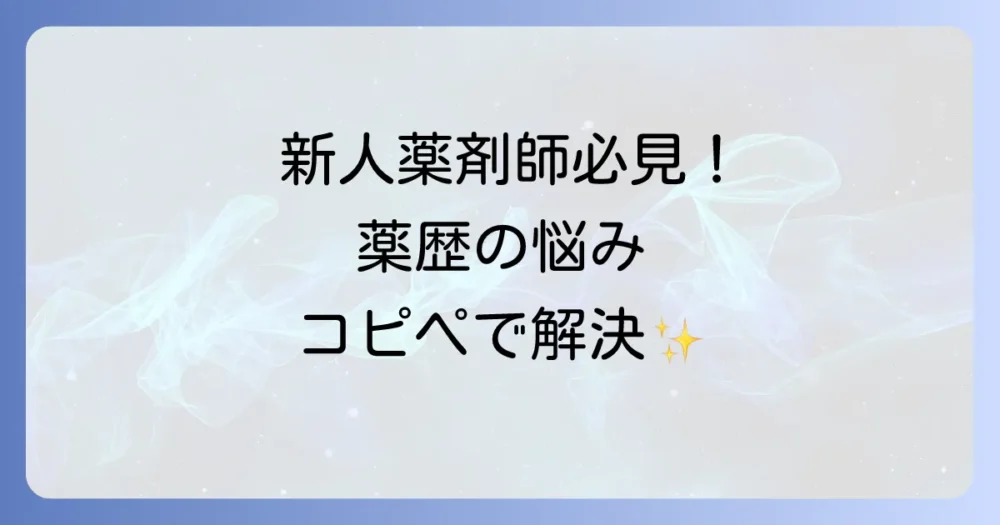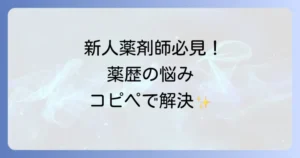「薬歴を書くのに時間がかかりすぎる…」「毎日同じような内容になってしまう…」
多くの薬剤師が抱える薬歴記載の悩み。患者さんへの服薬指導に集中したいのに、記録業務に追われていませんか?特に新人薬剤師の方にとっては、何を書けば良いのか分からず、大きな負担になっているかもしれません。
本記事では、そんな悩みを解決するために、コピペしてすぐに使える薬歴の定型文・例文を豊富に紹介します。SOAP形式に沿って、S・O・A・Pそれぞれの具体的なフレーズを解説。さらに、疾患別・状況別の応用例や、質の高い薬歴を作成するためのコツまで網羅しています。この記事を読めば、薬歴作成の時間を大幅に短縮し、自信を持って日々の業務に取り組めるようになるでしょう。
薬歴作成に時間がかかりすぎていませんか?定型文で業務を効率化しよう
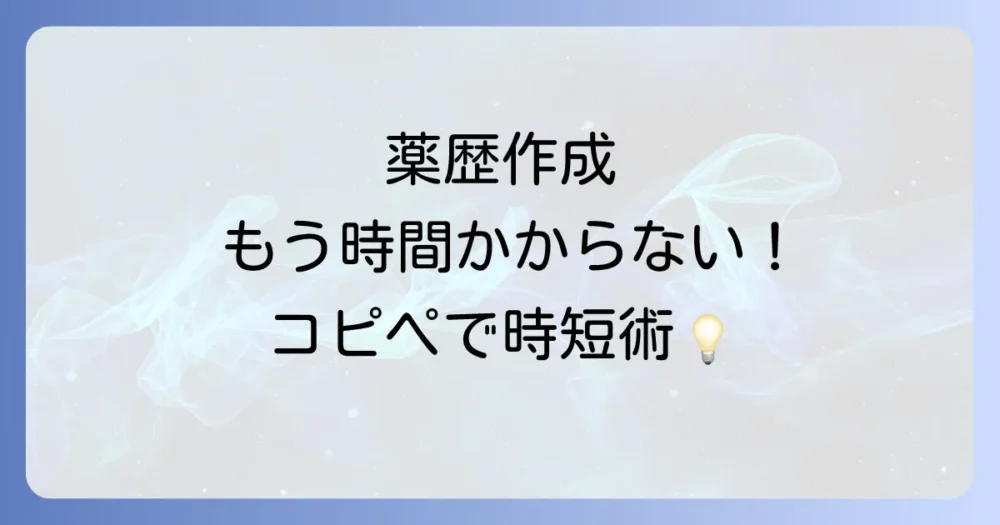
毎日多くの患者さんと向き合う中で、薬歴の作成に多くの時間を費やしている薬剤師は少なくありません。質の高い薬学的管理を行う上で薬歴は不可欠ですが、その作成が負担となり、本来注力すべき患者さんとのコミュニケーションや服薬指導の時間が削られてしまうのは本末転倒です。そんな悩みを解決する有効な手段が、定型文の活用です。
この章では、定型文がいかに薬歴作成の悩みを解決し、日々の業務を効率化するかを解説します。
- 定型文を活用するメリット
- 定型文はいつ、どのように使うのか
定型文を活用するメリット
薬歴作成に定型文を取り入れることには、多くのメリットがあります。まず最も大きな利点は、圧倒的な時間短縮です。毎回ゼロから文章を考える必要がなくなり、入力時間を劇的に減らすことができます。これにより、残業時間の削減や、他の業務への時間確保につながります。
次に、記載内容の標準化と質の担保が挙げられます。薬局内で定型文を共有することで、薬剤師ごとの記載内容のばらつきを防ぎ、誰が読んでも分かりやすい、一定水準以上の薬歴を作成できます。 これは、監査対策としても非常に有効です。
さらに、新人薬剤師の教育にも役立ちます。何をどのような視点で記録すればよいのか、定型文がガイドラインの役割を果たし、質の高い薬歴を早期に作成できるようになるでしょう。 このように、定型文の活用は単なる時短術にとどまらず、薬局全体の業務品質向上に貢献するのです。
定型文はいつ、どのように使うのか
では、具体的に定型文はどのような場面で、どのように活用すれば良いのでしょうか。定型文が特に活躍するのは、毎回確認・指導する項目が決まっているケースです。例えば、初回アンケートの聴取内容、ハイリスク薬の副作用初期症状の確認、吸入薬やインスリン自己注射の手技確認などが挙げられます。 これらの項目を定型文として登録しておけば、チェックリストのように活用でき、指導漏れを防ぐ効果も期待できます。
多くの電子薬歴システムには、定型文やテンプレートを登録する機能が備わっています。 SOAPの各項目(特にOやP)でよく使うフレーズを登録しておくのがおすすめです。 例えば、「お薬手帳の持参あり/なし」「残薬〇日分あり」「〇〇の副作用初期症状について説明」といった基本的なフレーズから、疾患ごとの指導内容まで、自薬局に合わせてカスタマイズしていくと良いでしょう。
ただし、重要なのは定型文をそのまま使うだけでなく、必ず個別情報を追記することです。定型文はあくまで骨格であり、そこに患者さん固有の訴えや状態、指導内容を肉付けすることで、初めて「活きた薬歴」となることを忘れないでください。
【SOAP別】コピペで使える薬歴の定型文・例文集
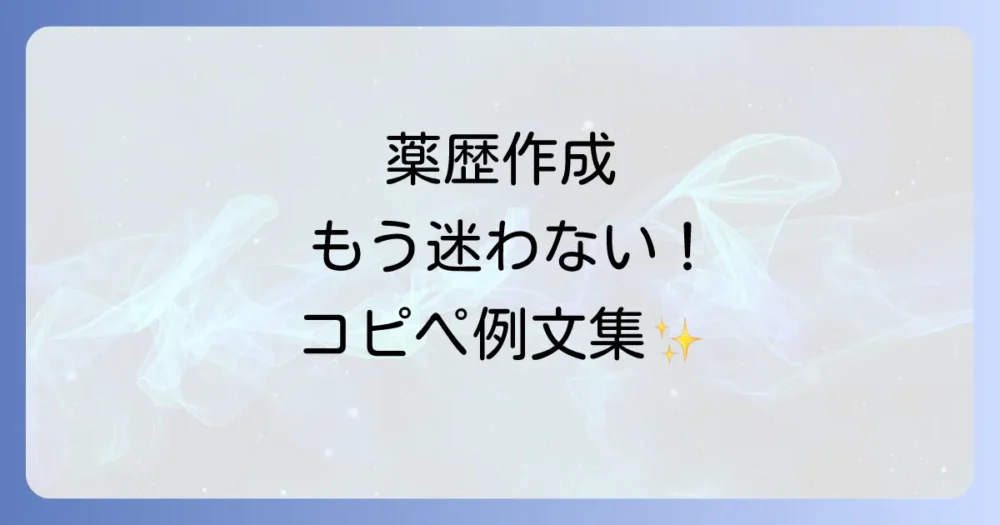
薬歴の基本となるSOAP形式。 しかし、各項目に何を書けばよいか、毎回悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。この章では、S・O・A・Pの各項目でそのまま使える、あるいは少しアレンジするだけで活用できる定型文と具体的な例文を豊富にご紹介します。これらのフレーズを電子薬歴の単語登録やテンプレート機能に設定しておけば、薬歴作成のスピードが格段にアップします。
この章で紹介する定型文・例文は以下の通りです。
- S (Subjective) の定型文・例文
- O (Objective) の定型文・例文
- A (Assessment) の定型文・例文
- P (Plan) の定型文・例文
S (Subjective) の定型文・例文
S情報は、患者さんやその家族からの主観的な訴えを記録する項目です。 患者さんの言葉をそのまま記載することが基本ですが、要点を的確に捉え、簡潔にまとめることが重要です。 ここでは、様々な状況で使えるS情報の定型文と例文を紹介します。
症状・体調に関する定型文
- 症状:変わりなしとのこと。
- (症状)の訴えあり。
- 最近、(症状)が気になる様子。
- 前回訴えのあった(症状)は、改善/悪化/継続しているとのこと。
- 体調は良好とのこと。
服薬状況・副作用に関する定型文
- 服薬状況:良好。飲み忘れなし。
- 時々、朝(夕)の薬を飲み忘れることがあるとのこと。
- (副作用)の自覚症状はないとのこと。
- (薬剤名)を服用後、(症状)が出現したとの訴えあり。
- アドヒアランス良好。
その他
- 特に変わりないとのこと。
- (生活習慣)について変化あり/なし。
- 併用薬(OTC・サプリメント含む):(製品名)を使用中。
- お薬手帳を持参。
例文:
S) 最近、朝の血圧が140mmHgを超えることがあり気になるとのこと。降圧薬の飲み忘れはない。めまいやふらつきなどの自覚症状はなし。
O (Objective) の定型文・例文
O情報は、検査値やバイタルサイン、薬剤師が客観的に観察した事実などを記録する項目です。 数値や事実を箇条書きなどで簡潔に記載するのがポイントです。 定型文を活用しやすい項目でもあります。
バイタルサイン・検査値
- 血圧:〇〇/〇〇 mmHg(自宅測定値)
- HbA1c:〇.〇 %(〇月〇日測定)
- 体重:〇〇 kg
- 検査値データ持参あり/なし。
処方・調剤内容
- 処方内容:前回同様。
- 今回、〇〇錠が〇mgから〇mgへ増量。
- 今回、〇〇が新規処方。
- (薬剤名)が中止。
- 残薬:〇〇錠が〇日分あり。調整依頼済み。
その他
- お薬手帳の持参あり/なし。
- 表情は明るい/硬い。
- 理解度は良好/やや不十分。
- (薬剤師が観察した患者の様子や言動)
例文:
O) 処方内容は前回同様。お薬手帳持参あり。残薬なし。患者持参の血圧手帳を確認。ここ1週間の家庭血圧は140-155/85-95 mmHgで推移。
A (Assessment) の定型文・例文
A情報は、S情報とO情報をもとに、薬剤師が専門的な視点で評価・分析・判断した内容を記載する、薬歴の核となる部分です。 ここでの評価が、次のP(計画)につながります。定型文に頼りすぎず、個々の症例に応じた考察を加えることが重要です。
効果・副作用の評価
- 処方内容、患者の状態から効果は十分/不十分と判断。
- 副作用発現のリスクは低い/高いと判断。
- S)の症状は、〇〇による副作用の可能性が考えられる。
- アドヒアランスは良好/不良と判断。
- 治療目標は達成できている/できていない。
処方に関する評価
- 今回の処方変更は妥当と判断。
- 〇〇と〇〇の相互作用について注意が必要。
- S)の症状から、〇〇の疑いあり。医師への情報提供が必要と判断。
- コンプライアンス低下が治療効果に影響している可能性あり。
患者の状態に関する評価
- 薬剤についての理解は良好。セルフケアが実践できている。
- 副作用への不安が強い様子。精神的なサポートが必要。
- 生活習慣の改善が必要と判断。
例文:
A) 家庭血圧が目標値を超えており、コントロール不良と判断。S)の訴えから、降圧治療に対する不安や関心が高まっている様子。アドヒアランスは良好であるため、現行薬の効果が不十分である可能性が考えられる。医師への情報提供を検討。
P (Plan) の定型文・例文
P情報は、A(評価)に基づいて、今後どのような薬学的管理や指導を行うかの計画を記載する項目です。 次回の服薬指導につながる具体的なアクションプランを示すことが大切です。 Ep(教育計画)、Cp(ケア計画)、Op(観察計画)に分けて記載すると、より分かりやすくなります。
Ep (Educational Plan) – 指導・説明
- 〇〇の効能効果、用法用量について改めて説明。
- 〇〇の副作用初期症状(具体的な症状)について説明し、発現時は連絡するよう指導。
- 生活習慣(減塩、運動など)の重要性を説明。
- 吸入/自己注射の手技を再確認し、正しく実施できていることを確認。
- パンフレット等を用いて〇〇について情報提供。
Cp (Care Plan) – 介入・対応
- 医師へ〇〇について情報提供(疑義照会)を実施。
- 残薬調整を実施。
- 一包化を提案し、医師の了承を得て実施。
- 患者の不安を傾聴し、共感を示した。
Op (Observational Plan) – 観察・モニタリング
- 次回、〇〇の効果(血圧、血糖値など)について確認予定。
- 次回、〇〇の副作用の有無についてヒアリング予定。
- 次回、服薬アドヒアランスを再評価する。
- 継続して〇〇の症状について様子観察。
例文:
P)
Ep) 家庭血圧の継続測定と記録の重要性を改めて説明。目標血圧値を共有し、達成に向けたモチベーション維持を支援。
Cp) 血圧コントロール不良の状況を次回の情報提供書にて医師へ報告する。
Op) 次回来局時、血圧の推移と体調変化(特にめまい、ふらつき等)について再度確認する。
【疾患・状況別】応用できる薬歴の定型文・例文
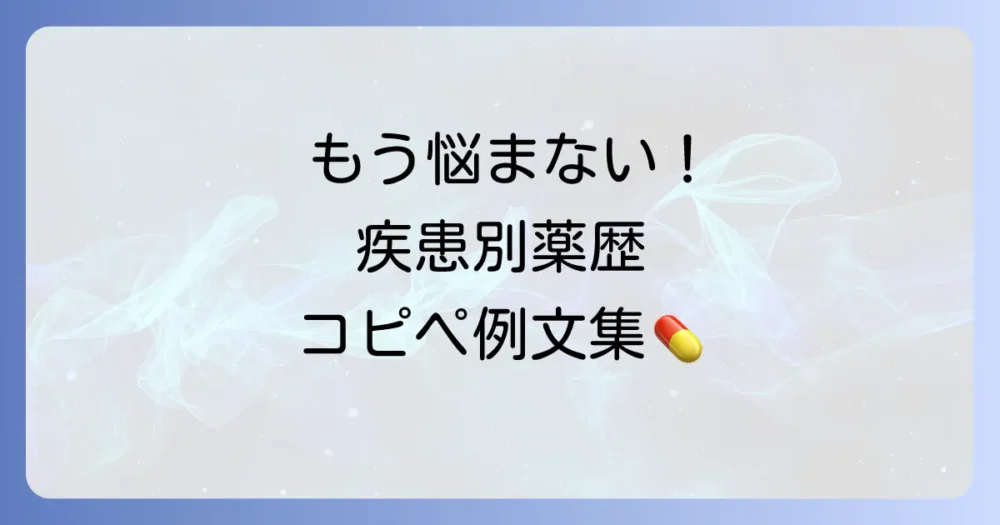
基本的なSOAPの定型文をマスターしたら、次はより具体的な疾患や状況に応用してみましょう。患者さんの状態は千差万別ですが、疾患ごと、あるいは特定の状況ごとに押さえるべきポイントや確認事項はある程度共通しています。この章では、日常業務で遭遇する機会の多いケースを取り上げ、実践的な薬歴の定型文・例文を紹介します。これらの例文を参考に、自薬局のテンプレートを充実させていきましょう。
この章で取り上げるケースは以下の通りです。
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 初回算定・新規患者
- 残薬調整
- 副作用モニタリング
高血圧
高血圧の患者さんでは、継続的な血圧管理と生活習慣の把握が重要です。家庭血圧の測定値や、降圧目標の共有、副作用のモニタリングが薬歴記載のポイントとなります。
例文
S) 自宅での血圧測定を継続中。今週は上が130台、下が80台で安定しているとのこと。めまい、ふらつき等の自覚症状なし。飲み忘れもない。
O) 処方内容は前回同様。血圧手帳持参。記録より家庭血圧が目標値(135/85mmHg未満)を達成できていることを確認。
A) 血圧コントロール良好。アドヒアランスも維持できている。現行処方で継続問題ないと判断。
P) Ep) 引き続き家庭血圧の測定と記録を継続するよう激励。減塩の工夫について尋ね、継続できていることを称賛。
Op) 次回も血圧手帳を確認し、コントロール状態と副作用の有無をモニタリングする。
糖尿病
糖尿病患者さんの薬歴では、血糖コントロール指標(HbA1cや自己測定血糖値)、低血糖症状の有無、足のケアなど、確認すべき項目が多岐にわたります。
例文
S) 先日の受診でHbA1cが7.0%だったとのこと。食事には気をつけているが、時々間食をしてしまうことがある。低血糖症状(冷や汗、動悸など)はなし。足のしびれや傷もない。
O) 今回、メトホルミンが新規処方。HbA1c 7.0%(〇月〇日)。お薬手帳にシックデイに関する記載あり。
A) 血糖コントロールは目標値に近いが、改善の余地あり。食事療法への意識はあるものの、行動変容に課題。新規薬剤の副作用(消化器症状)に注意が必要。
P) Ep) メトホルミンの初期副作用(下痢、吐き気など)について説明。食直前・食後の服用で軽減される場合があることを伝え、まずは少量から開始するよう指導。シックデイルールについて改めて説明。
Op) 次回、メトホルミンの副作用の有無と服薬状況、血糖値の変動について確認する。
脂質異常症
脂質異常症は自覚症状が乏しいため、服薬アドヒアランスの維持が課題となることが多い疾患です。薬物治療の意義や目標値を共有し、継続を促すアプローチが重要です。
例文
S) 特に体調に変わりはない。薬を飲んでいる効果がよくわからないと感じることがあるとのこと。
O) 処方内容はロスバスタチン継続。検査値データなし。残薬なし。
A) 自覚症状がないため、服薬意義への理解が低下し、アドヒアランス低下のリスクあり。スタチン系薬剤の副作用(筋肉痛、肝機能障害)は現時点では認められない。
P) Ep) 脂質異常症治療の目的(動脈硬化の進行予防、心筋梗塞・脳梗塞のリスク低減)を改めて説明。次回の検査で数値が改善しているか一緒に確認することを提案し、服薬継続の重要性を強調。筋肉痛などの症状が出たら相談するよう指導。
Op) 次回、服薬に対するモチベーションの変化と、検査結果について確認する。
初回算定・新規患者
新規の患者さんでは、アレルギー歴、副作用歴、既往歴、生活習慣、併用薬など、基本的な情報を漏れなく聴取し、記録することが最も重要です。
例文
S) 〇〇病院より転院。今回初めての来局。アレルギー歴:ペニシリン系で薬疹。副作用歴:なし。既往歴:高血圧。喫煙・飲酒の習慣なし。現在、他科受診や併用薬(OTC、サプリ含む)はなし。後発医薬品への希望あり。
O) 処方箋、保険証、お薬手帳(持参なし)を確認。アンケート用紙に本人記入。
A) 初回のため、患者情報を収集し、薬歴の基礎情報を確立。アレルギー歴があるため、今後の調剤時に注意が必要。
P) Ep) 当薬局が「かかりつけ薬局」として利用できることを説明。お薬手帳の意義を説明し、次回からの持参を依頼。処方薬の基本的な説明を実施。
Cp) 患者基本情報を薬歴に登録。アレルギー情報を薬歴表紙に明記。
Op) 次回、今回処方された薬剤の効果、副作用の有無を確認する。
残薬調整
残薬の発生は、アドヒアランスの低下や処方変更など様々な原因で起こります。原因を特定し、適切な対応(一包化、疑義照会など)を行い、その経緯を記録します。
例文
S) アムロジピンが20錠ほど余っているとのこと。朝は忙しくて時々飲み忘れてしまうことがある。
O) アムロジピン錠5mg:残薬20Tあり。他薬剤の残薬はなし。処方日数は28日分。
A) 朝の服用コンプライアンス低下により残薬が発生。このままでは治療効果の減弱が懸念される。服用時点の変更や一包化などの介入が必要と判断。
P) Cp) 医師に疑義照会し、残薬調整(今回処方8日分)と、夕食後への用法変更の許可を得た。変更内容を患者に説明し、同意を得た。
Ep) 服用時点が変更になったことを強調し、お薬カレンダーの活用などを提案。
Op) 次回、用法変更後の服薬状況と残薬の有無を再確認する。
副作用モニタリング
特に注意が必要な副作用について、具体的な初期症状を患者さんと共有し、継続的にモニタリングした記録を残すことは、薬剤師の重要な役割です。
例文(SGLT2阻害薬の例)
S) 最近、トイレが近くなった気がするが、排尿時痛や残尿感はないとのこと。陰部のかゆみや痛みもなし。水分は意識して多めに摂るようにしている。
O) ダパグリフロジン錠10mg服用中(開始後1ヶ月)。
A) SGLT2阻害薬の薬理作用による多尿はみられるが、懸念される副作用(尿路・性器感染症、脱水)の兆候は現時点では認められない。セルフケアも適切に実施できていると判断。
P) Ep) 引き続き、水分補給の重要性と、尿路・性器感染症の初期症状(排尿時痛、かゆみ等)が出現した場合はすぐに相談するよう改めて指導。
Op) 継続して上記副作用の有無をモニタリングする。特に夏場は脱水に注意喚起を行う。
定型文を使うだけじゃない!質の高い薬歴を作成する3つのコツ
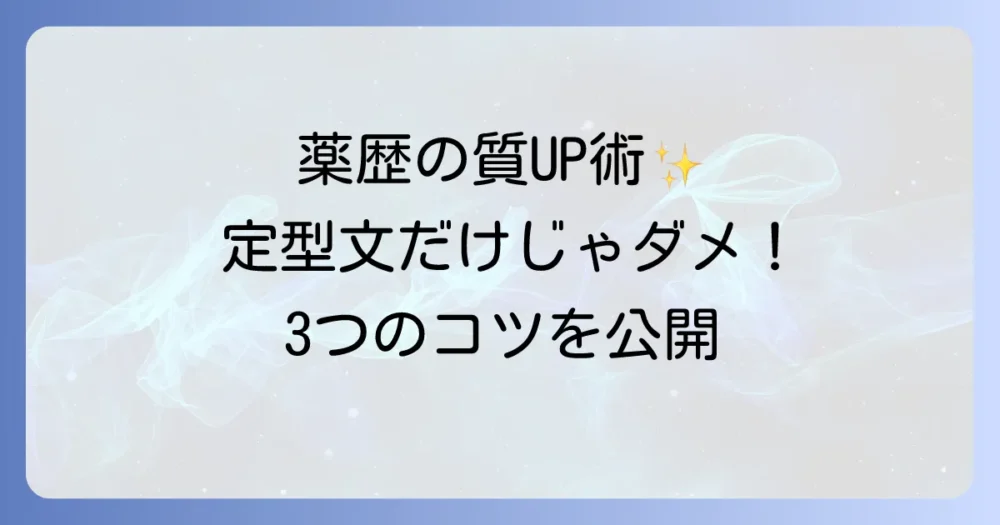
定型文やテンプレートは、薬歴作成を効率化する上で非常に強力なツールです。しかし、それらをただコピー&ペーストするだけでは、画一的で中身のない記録になってしまい、個々の患者さんに寄り添った薬学的管理とはいえません。 本当に質の高い、監査にも耐えうる薬歴を作成するためには、定型文を土台としつつ、薬剤師としての専門性を加える必要があります。 ここでは、そのための3つの重要なコツを紹介します。
質の高い薬歴を作成するためのコツは以下の通りです。
- コツ1:コピペだけでなく個別性を加える
- コツ2:経時変化がわかるように記載する
- コツ3:5W1Hを意識して具体的に書く
コツ1:コピペだけでなく個別性を加える
定型文はあくまで「骨格」です。そこに患者さん一人ひとりの「肉付け」をすることが不可欠です。患者さんが話した言葉の中で、特に印象的だったフレーズや、その人ならではの表現、生活背景が垣間見えるエピソードなどを追記しましょう。
例えば、「変わりなし」という定型文を使う場合でも、「『おかげさまで、変わりなく元気に過ごせてるよ』と笑顔で話された」と加えるだけで、患者さんの状態や満足度がより鮮明に伝わります。また、「副作用なし」だけでなく、「『特に気になる症状はないけど、先生に言われた筋肉痛には気をつけてる』との発言あり」と記載すれば、患者さんの疾患や薬剤に対する理解度や注意の向き方が分かります。このように、患者さん固有の情報を加えることで、薬歴は単なる記録から、その人らしさが見える「物語」へと変わります。これは、次に担当する薬剤師が患者さんとの信頼関係を築く上でも大きな助けとなるでしょう。
コツ2:経時変化がわかるように記載する
薬歴の重要な役割の一つは、治療の経過を追い、薬学的介入の効果を評価することです。そのためには、今回の情報だけでなく、前回の薬歴と比較して何がどう変化したのかを明確に記載することが重要です。
例えば、血圧の薬が変更になった場合、「前回A薬→今回B薬に変更」と事実だけを書くのではありません。「前回、A薬服用中の家庭血圧が150mmHg台で推移していたため、今回B薬へ変更。変更後の血圧の変動に注意が必要」と記載することで、処方変更の意図と、次回のフォローアップ項目が明確になります。また、副作用の訴えがあった場合も、「前回からの症状の強さの変化(例:痛みが10段階中8→5に軽減)」「症状が起きる頻度の変化」などを具体的に記録することで、介入の評価がしやすくなります。このように、常に過去の記録を意識し、点ではなく線で患者さんの状態を捉える視点が、質の高い薬歴には不可欠です。
コツ3:5W1Hを意識して具体的に書く
「誰が(Who)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という5W1Hのフレームワークは、情報を明確かつ具体的に伝えるための基本です。薬歴においても、この5W1Hを意識することで、誰が読んでも状況が正確に理解できる、質の高い記録を作成することができます。
例えば、「飲み忘れあり」と書くだけでなく、「(誰が)本人が、(いつ)朝食後の薬を、(なぜ)仕事で朝が忙しいため、週に2〜3回飲み忘れることがある。(どのように)昼に気づいて飲むこともあるが、そのまま忘れてしまうことも多い」と記載すれば、問題点が非常に具体的になります。これにより、「夕食後に用法変更を提案する」「一包化して目につく場所に置いてもらう」といった、より的確な次のアクション(Plan)を立てることができます。曖昧な表現を避け、常に5W1Hを念頭に置いて記載する習慣をつけることが、質の高い薬歴への近道です。
薬歴作成をさらに効率化する電子薬歴システムの活用法
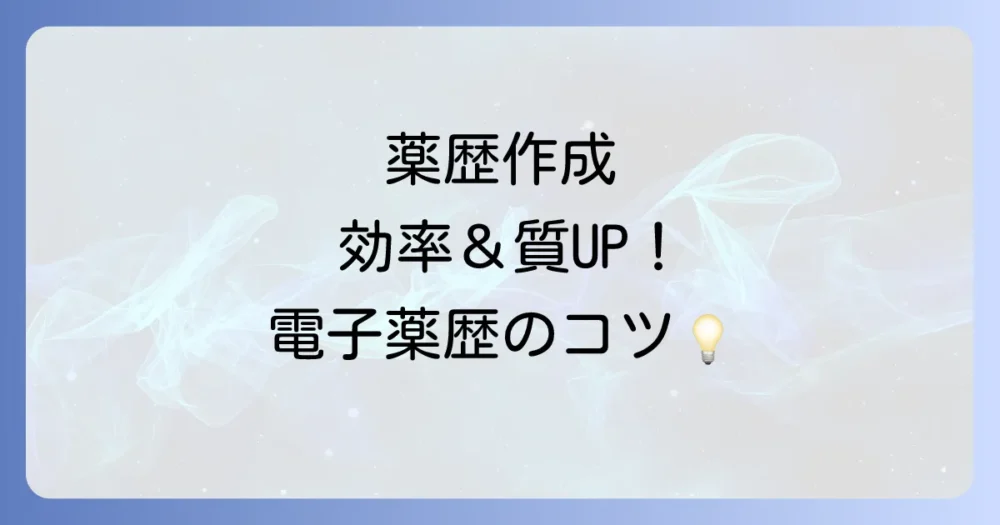
これまで紹介してきた定型文や記載のコツを最大限に活かすためには、電子薬歴システムの機能を使いこなすことが鍵となります。 現代の薬局業務において、電子薬歴は単なる記録ツールではなく、業務効率化と医療の質の向上を両立させるための強力なパートナーです。 各メーカーから様々な特徴を持つシステムが提供されており、自薬局のスタイルに合ったものを選ぶことが重要です。
この章では、薬歴作成をさらにスピードアップさせ、質を高めるための電子薬歴システムの具体的な活用法について解説します。
- 主要な電子薬歴システムとその特徴
- テンプレート・単語登録機能の徹底活用
- 服薬指導支援機能と薬歴作成の連携
主要な電子薬歴システムとその特徴
日本国内では、多くのベンダーが特色ある電子薬歴システムを提供しています。ここでは代表的なシステムをいくつか紹介します。
- Musubi(株式会社カケハシ): 患者さんへの説明に使うタブレット画面のタッチ操作が、そのまま薬歴の下書きになるという特徴があります。指導内容と薬歴記載がシームレスに連動するため、指導後の薬歴作成時間を大幅に短縮できます。
- GooCo(株式会社グッドサイクルシステム): 「かんたん・安心・安全」をコンセプトに、直感的な操作性を追求しています。服薬指導をしながらタッチ操作で薬歴の下書きが作成できる機能や、強力な処方監査機能が魅力です。
- Pharnesシリーズ(ウィーメックス株式会社 旧:PHC株式会社): 薬歴表紙や監査情報、過去薬歴などを一画面で確認できる視認性の高さが特徴です。重複投薬や相互作用チェックなど、豊富なチェック機能で業務ミス防止をサポートします。
- CARADA 電子薬歴 Solamachi(株式会社ソラミチ): 特許取得技術により、指導項目にチェックを入れるだけで、前回とは異なる指導文を提案してくれます。画一的な薬歴になるのを防ぎつつ、効率化を図れるのが強みです。
これらのシステムは、クラウド型かオンプレミス型か、レセコン一体型かなど、様々なタイプがあります。 自薬局の規模や在宅業務の有無、複数の店舗間での連携が必要かといったニーズに合わせて選ぶことが大切です。
テンプレート・単語登録機能の徹底活用
ほとんどの電子薬歴システムには、よく使う文章を保存しておく「テンプレート(定型文)機能」や「単語登録機能」が搭載されています。 これを徹底的に活用することが、効率化の第一歩です。
本記事で紹介したSOAP別、疾患別の定型文を、まずはそのまま登録してみましょう。さらに、「初回」「残薬調整」「副作用疑い」といった状況別のテンプレートを作成しておくのも有効です。例えば、「初回質問テンプレート」として、アレルギー歴、副作用歴、生活習慣などの確認項目をリスト化しておけば、聞き漏れを防ぎ、スムーズに薬歴を作成できます。
単語登録では、「お願」→「〇〇するようお願いした。」、「せつ」→「〇〇について説明した。」、「かく」→「〇〇について確認した。」のように、短い読みで頻出する文末表現を登録しておくと、タイピングの手間を大幅に削減できます。こうした地道なカスタマイズが、日々の業務時間を着実に短縮していきます。
服薬指導支援機能と薬歴作成の連携
近年の電子薬歴システムは、薬歴を作成するだけでなく、服薬指導そのものを支援する機能が充実してきています。 例えば、患者さんに見せるためのイラストや写真が豊富な指導コンテンツが内蔵されていたり、指導中に画面をタッチするだけで薬歴の下書きが自動で作成されたりするシステムがあります。
こうした機能を活用することで、「指導は指導、薬歴は薬歴」という分断された業務フローを改善できます。患者さんとの対話に集中しながら、その場で薬歴の骨子が出来上がっていくため、指導後の「さて、何を書こうか…」と思い出す時間が不要になります。また、指導コンテンツに沿って説明することで、説明の標準化や漏れの防止にも繋がります。
自薬局の電子薬歴にどのような機能があるか、一度マニュアルを確認したり、メーカーの担当者に尋ねたりしてみてください。まだ使っていない便利な機能が見つかるかもしれません。
よくある質問
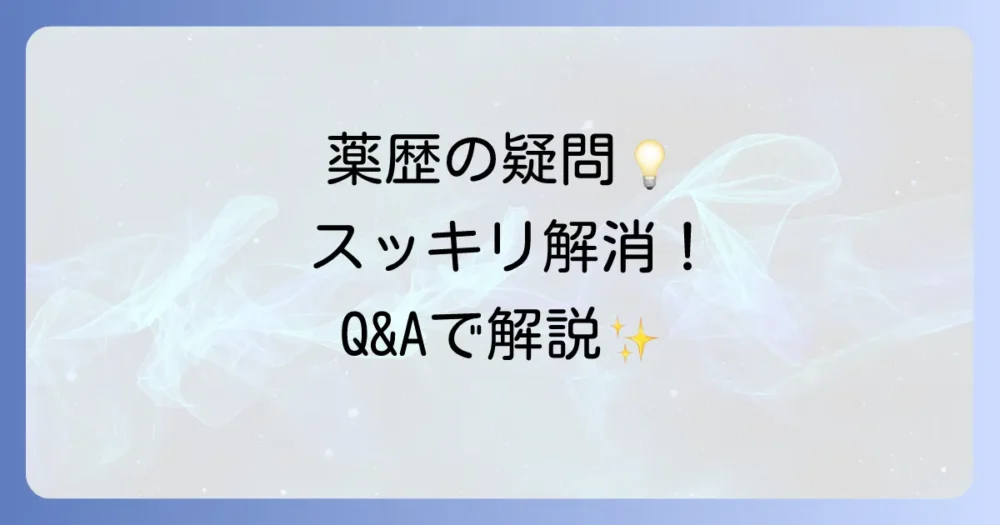
薬歴の定型文や書き方について、多くの薬剤師が抱える共通の疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。日々の業務の参考にしてください。
薬歴の保存期間はどのくらいですか?
薬剤服用歴(薬歴)の保存期間は、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)第八条により、「最終の記入の日から起算して三年間」と定められています。 これは、紙の薬歴でも電子薬歴でも同様です。この期間は、患者さんへの継続的な薬学的管理を提供するだけでなく、調剤報酬請求の根拠となる記録としての意味合いもあります。 したがって、適切に管理・保存することが義務付けられています。
薬歴は手書きでも問題ありませんか?
はい、薬歴は手書き(紙薬歴)でも問題ありません。法令上、薬歴の媒体は電子に限定されていません。実際に、様々な事情で紙薬歴を運用している薬局も存在します。 しかし、電子薬歴の普及率は年々高まっており、厚生労働省も導入を推奨しています。 理由としては、情報の検索性、共有の容易さ、保管スペースの削減、災害時のデータ保全性などのメリットが大きいためです。 手書きの場合は、誰が読んでも判読できる丁寧な字で記載し、紛失や劣化がないよう厳重に保管する必要があります。
薬歴の監査で指摘されやすいポイントは何ですか?
個別指導などの監査で指摘されやすいポイントはいくつかありますが、特に注意すべきは以下の点です。
- 記載内容の不備・不足: 算定要件で定められた項目(患者の基礎情報、服薬状況、併用薬、副作用歴、指導の要点など)に記載漏れがある。
- 画一的な記載: 定型文をコピーしただけで、患者さんごとの個別性が全く見られない薬歴。
- 経時的変化の欠如: Do処方が続く場合に、毎回「変わりなし」と同じ内容の記載が繰り返され、継続的なフォローアップが行われているか不明確。
- 疑義照会の記録: 疑義照会を行ったにもかかわらず、その要点や結果が適切に記載されていない。
- 記載の遅延: 服薬指導後、速やかに薬歴が作成されていない。
これらの指摘を避けるためにも、本記事で紹介した「個別性を加える」「経時変化を記録する」といったコツを意識することが重要です。
Do処方の場合、薬歴には何を書けばよいですか?
Do処方(処方内容に変更がない場合)が続くと、薬歴の内容がマンネリ化しがちです。 しかし、処方が同じでも患者さんの状態は変化している可能性があります。毎回「変わりなし」で済ませるのではなく、以下のような視点で情報を収集し、記載しましょう。
- 体調の微妙な変化: 「変わりない」という言葉の裏にある小さな変化(例:「最近少し立ちくらみがする時がある」)を掘り下げる。
- アドヒアランスの再確認: 飲み忘れや自己判断での中断がないか、具体的な方法で確認する(例:「お薬カレンダーは順調に使えていますか?」)。
- 生活習慣の変化: 食事、運動、睡眠、仕事など、最近の生活で変わったことがないか尋ねる。
- 治療への理解度・満足度の確認: 「このお薬を続けていて、何か良い変化は感じますか?」「治療について何か不安なことはありませんか?」など、患者さんの認識や感情面に焦点を当てる。
- 新たな目標設定: 「次の検査では、HbA1cをもう少し下げられると良いですね」など、小さな目標を共有し、モチベーションを維持する。
これらの対話から得られた情報を記載することで、Do処方であっても中身のある薬歴を作成できます。
まとめ
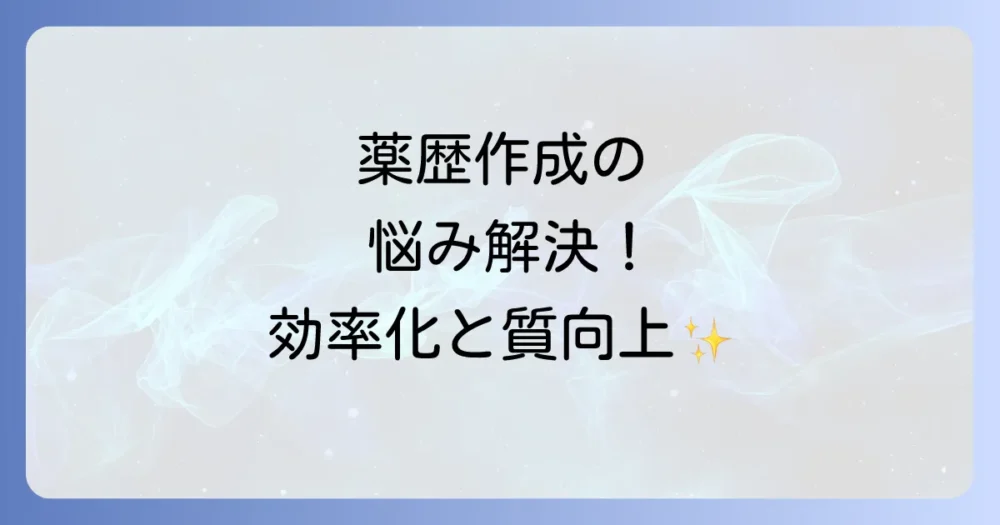
- 薬歴作成に定型文を活用すると、時間短縮や質の標準化が期待できる。
- 定型文は電子薬歴のテンプレート機能に登録して使うと便利である。
- SOAPの各項目(S・O・A・P)には、それぞれに適した定型文の型がある。
- S情報は患者の訴え、O情報は客観的事実を簡潔に記載する。
- A情報は薬剤師の評価、P情報は具体的な行動計画を示す薬歴の核となる。
- 高血圧や糖尿病など、疾患別の定型文を用意すると応用しやすい。
- 初回患者や残薬調整など、特定の状況に応じたテンプレートも有効である。
- 質の高い薬歴のためには、定型文に患者固有の情報を加えることが不可欠。
- 前回の記録と比較し、経時変化が分かるように記載することが重要である。
- 5W1Hを意識すると、具体的で分かりやすい記録になる。
- 電子薬歴システムの機能を最大限活用することで、さらなる効率化が可能。
- MusubiやGooCoなど、各システムには指導と薬歴作成を連携させる機能がある。
- 薬歴の保存期間は最終記入日から3年間と定められている。
- 監査では、記載内容の不備や画一的な記録が指摘されやすい。
- Do処方でも、体調や生活習慣の変化などを聴取し、マンネリ化を防ぐ。