突然の怪我で、「この傷、病院で縫ってもらうべき?」と迷った経験はありませんか?血が止まらなかったり、傷口がパックリ開いていたりすると、どう対処すればいいか不安になりますよね。本記事では、どんな傷を縫う必要があるのか、その明確な基準を分かりやすく解説します。病院に行くべきかどうかの判断に迷ったときの応急処置や、何科を受診すれば良いのかも詳しくご紹介。いざという時に慌てないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
その傷、縫うべき?病院に行くか迷った時の判断基準チェックリスト
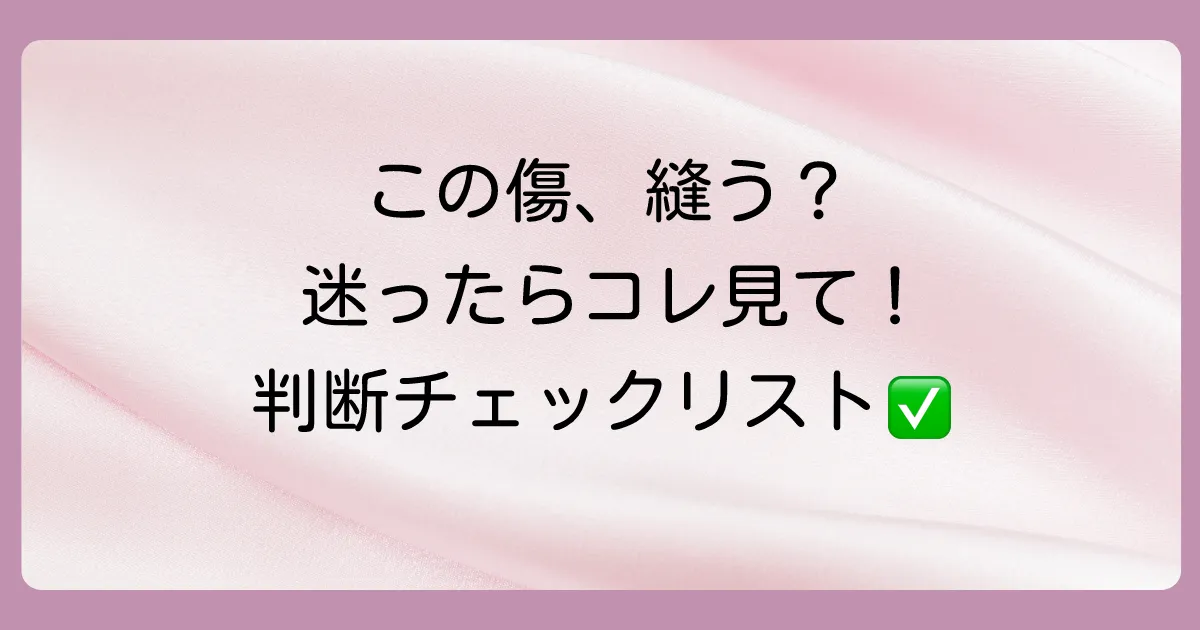
怪我をしたとき、病院で縫うべきかどうかの判断は難しいものです。しかし、いくつかのポイントを確認することで、受診の必要性を判断する助けになります。ご自身の、あるいはご家族の傷が以下の項目に当てはまるか、冷静にチェックしてみてください。
傷の深さ
傷口を覗き込んだとき、皮膚の下にある黄色い脂肪組織が見えている、あるいはそれよりも深く、白い腱や骨が見える場合は縫合が必要です。 浅い擦り傷とは明らかに違う深さだと感じたら、迷わず病院へ行きましょう。
傷の開き具合
傷口がパックリと開いていて、皮膚を寄せてもくっつかない状態は、縫合が必要なサインです。 特に、動かす部分(関節など)でなくても傷が開いたままになっている場合は、自然に閉じるのが難しいため、受診を検討してください。
出血の量と時間
清潔なガーゼやタオルで傷口を10分から20分ほど強く圧迫しても、血が止まらない、あるいは滲み出してくる場合は、太い血管が傷ついている可能性があります。 このような場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
傷の場所
傷跡が残りやすい顔や首、あるいは動きが多くて傷口が開きやすい関節(指、ひじ、ひざなど)にできた傷は、きれいに治すためにも縫合を検討した方が良いでしょう。 特に顔の傷は、美容的な観点からも形成外科など専門医への相談がおすすめです。
異物の有無
ガラス片、木片、砂、土などが傷口に入り込んでいる、またはその可能性がある場合、自分で完全に取り除くのは困難です。 異物が残ったままだと感染の原因になるため、病院で洗浄・処置してもらう必要があります。
原因
動物や人に噛まれた傷は、見た目以上に深く、細菌に感染するリスクが非常に高いです。また、錆びた釘や金属片で負った傷は、破傷風の危険性も考えられます。 このような原因による傷は、必ず病院を受診してください。
これらの項目に一つでも当てはまる場合は、自己判断で済ませずに医療機関を受診することを強くおすすめします。
なぜ傷を縫う必要があるの?放置する3つのリスク
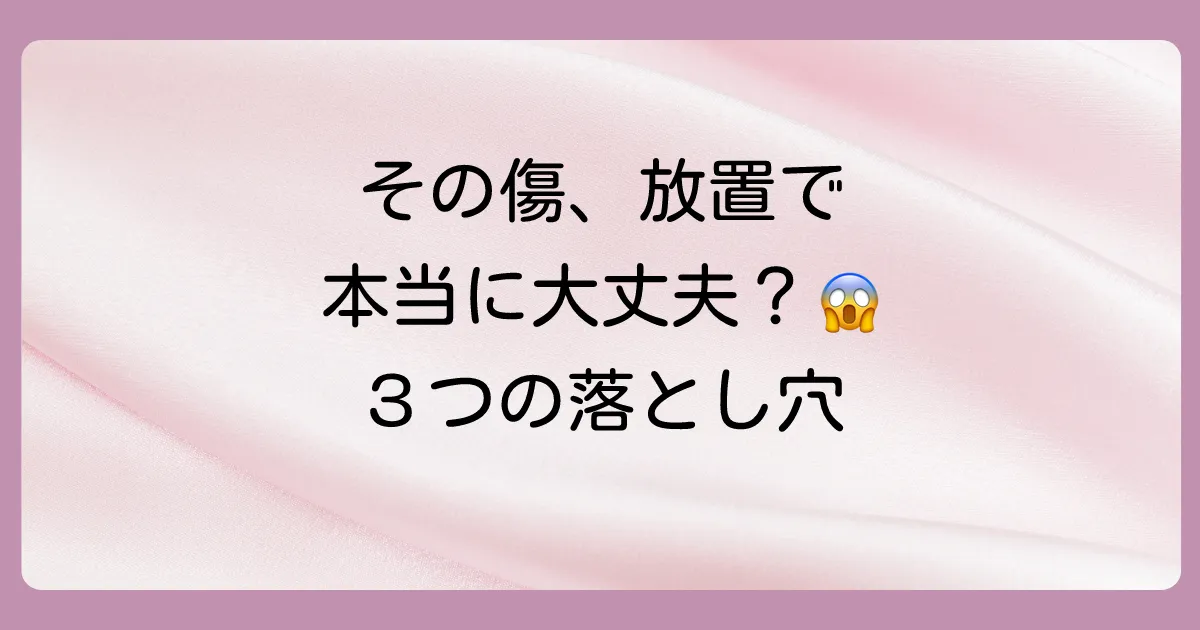
「小さな傷だし、そのうち治るだろう」と安易に考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、縫うべき傷を放置することには、いくつかのリスクが伴います。ここでは、傷を縫わずに放置した場合に起こりうる主な3つのリスクについて解説します。
- リスク1: 傷跡が残りやすくなる
- リスク2: 感染症を引き起こす
- リスク3: 治りが遅くなる
リスク1: 傷跡が残りやすくなる
縫合が必要なほど開いた傷をそのままにしておくと、傷口の縁がうまくくっつかず、幅の広い目立つ傷跡になってしまう可能性が高まります。 皮膚は、開いた空間を埋めようとして、下から肉芽組織というものが盛り上がってきます。この治り方だと、治癒後も皮膚の表面が引きつれたり(瘢痕拘縮)、赤く盛り上がったケロイド状になったりすることがあります。 縫合は、傷の縁をぴったりと合わせることで、皮膚が本来の構造に近い形で再生するのを助け、結果として傷跡を最小限に抑えるための重要な処置なのです。
リスク2: 感染症を引き起こす
私たちの皮膚は、外部の細菌などから体を守るバリアの役割を果たしています。しかし、傷ができてそのバリアが破れると、そこから細菌が侵入しやすくなります。特に、傷口が開いたままになっていると、細菌の侵入経路が確保された状態が続くことになり、感染のリスクが格段に上がります。 傷口が赤く腫れる、熱を持つ、ズキズキと痛む、膿が出るといった症状は感染のサインです。感染を起こすと治りが遅くなるだけでなく、場合によっては全身に影響が及ぶこともあるため、非常に危険です。
リスク3: 治りが遅くなる
傷口を縫合すると、皮膚の縁が固定されるため、体が治癒プロセスに集中しやすくなり、比較的短期間で傷がふさがります。 一方で、開いたままの傷は、傷口を埋めるために多くの時間とエネルギーを必要とします。そのため、治癒までの期間が長引いてしまう傾向にあります。治りが遅いと、その間ずっと痛みが続いたり、日常生活で不便を感じたりする期間も長くなってしまいます。適切な時期に縫合処置を受けることは、早期の社会復帰という観点からも大切です。
怪我をしたら何科に行くべき?症状別の診療科選び
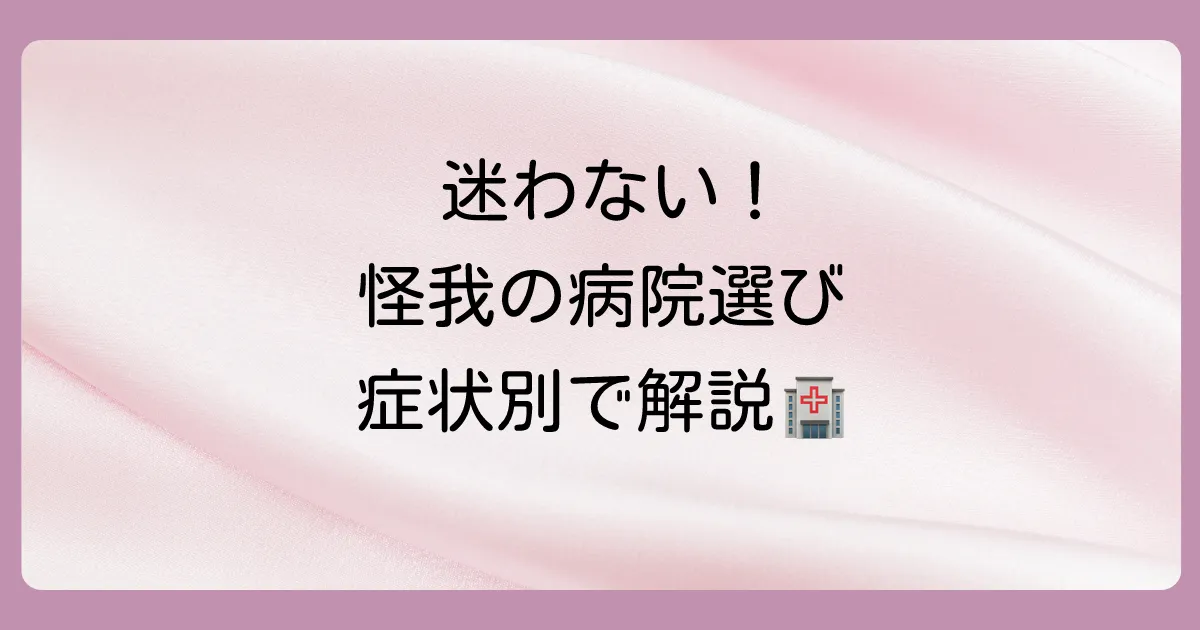
いざ病院に行こうと決めても、「何科を受診すればいいの?」と迷ってしまうことも多いでしょう。怪我の状況や部位によって、適した診療科は異なります。ここでは、代表的な診療科とその特徴について解説しますので、病院選びの参考にしてください。
- 傷跡をきれいに治したいなら「形成外科」
- 骨や腱まで達する深い傷は「整形外科」
- 比較的浅い切り傷なら「皮膚科」
- どこに行けばいいか迷ったら「外科」
- 夜間・休日の緊急時は「救急外来」
傷跡をきれいに治したいなら「形成外科」
形成外科は、体の表面の見た目をより正常に、より美しく治すことを専門とする診療科です。 特に、顔や手足など、人目につきやすい場所の傷をできるだけきれいに治したい場合には、第一の選択肢となります。 形成外科医は、皮膚の構造や傷が治るメカニズムを熟知しており、傷跡が目立ちにくくなるような特殊な縫い方(真皮縫合など)の技術を持っています。 事故や手術後の傷跡修正なども専門分野です。
骨や腱まで達する深い傷は「整形外科」
整形外科は、骨、関節、筋肉、腱、神経といった運動器の専門家です。 傷が深く、骨に達していたり、指を動かすための腱が切れてしまったりした場合(例えば、「指を深く切って動かせない」など)は、整形外科での治療が必要です。 縫合処置だけでなく、骨折の治療や腱の修復手術、その後のリハビリテーションまで一貫して診てもらうことができます。ただし、顔面の骨折や内臓の損傷は専門外となることが多いです。
比較的浅い切り傷なら「皮膚科」
皮膚科は、皮膚そのものの病気やトラブルを診る専門家です。包丁で指を少し切ってしまった、といった比較的浅い切り傷であれば、皮膚科で対応してもらえることが多いです。 縫合処置のほか、化膿止めの薬の処方や、傷の経過観察を行ってくれます。ただし、非常に深い傷や、腱・神経の損傷が疑われる場合は、他の科を紹介されることもあります。
どこに行けばいいか迷ったら「外科」
外科は、手術によって病気や怪我を治療する診療科全般を指します。一般外科は、消化器(胃や腸)の手術などを専門としながらも、切り傷などの外傷にも幅広く対応してくれます。 どの診療科に行けば良いか判断に迷う場合は、まずお近くの外科クリニックに相談してみるのも良いでしょう。総合病院であれば、適切な専門科へ案内してもらえます。
夜間・休日の緊急時は「救急外来」
夜間や休日に怪我をしてしまい、出血が止まらない、傷が非常に深い、意識が朦朧としているなど、緊急性が高い場合は、迷わず救急車を呼ぶか、病院の救急外来を受診してください。 救急外来では、まずは命に関わる状態でないかを確認し、止血などの応急処置が行われます。 専門的な治療が必要な場合は、翌日以降に改めて専門の診療科を受診するように指示されることもあります。
病院に行く前に!自分でできる応急処置の手順
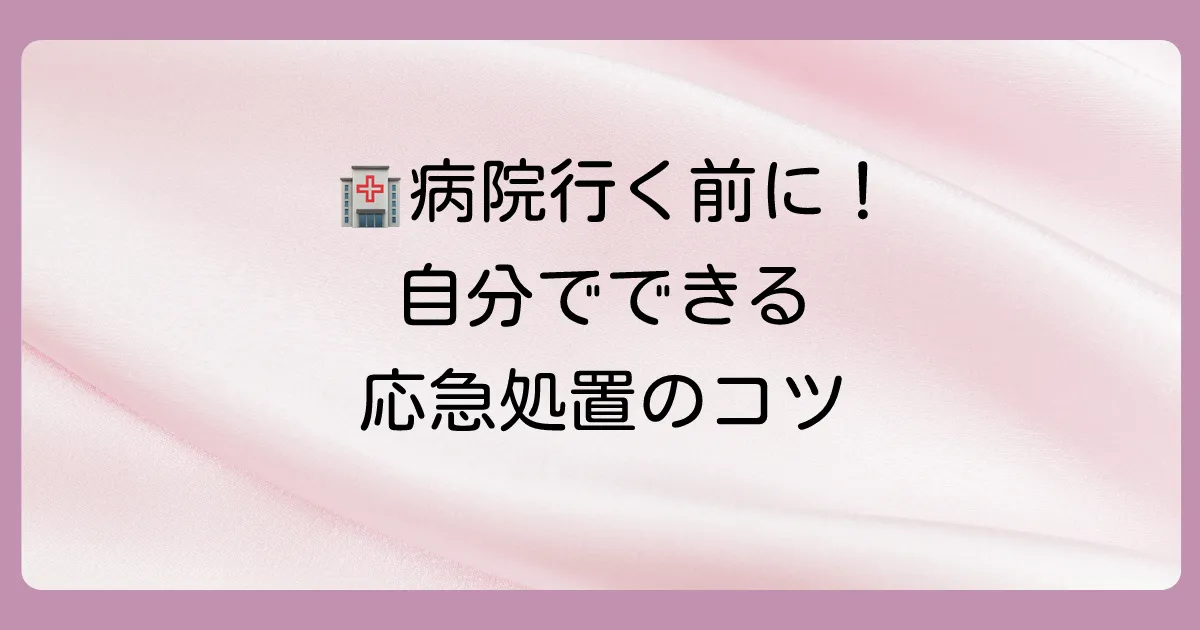
病院に行くべきだと判断した場合でも、すぐに受診できるとは限りません。病院へ向かうまでの間、あるいは診察を待つ間に、適切な応急処置を行うことで、感染のリスクを減らし、治りを良くすることにつながります。慌てず、以下の手順で対処しましょう。
- ステップ1: 傷口を水道水でしっかり洗う
- ステップ2: 清潔なガーゼで圧迫止血する
- ステップ3: 傷口を保護する
ステップ1: 傷口を水道水でしっかり洗う
まず最も大切なことは、傷口を洗浄することです。傷口についた砂や泥、その他の異物や細菌を洗い流すことが、感染予防の第一歩となります。 消毒液を使わなければ、と思うかもしれませんが、現在の創傷治療では、消毒液が傷を治そうとする細胞まで傷つけてしまう可能性があると考えられており、きれいな水道水で十分に洗い流すことが推奨されています。 石鹸をよく泡立てて、優しく洗うのも効果的です。しみるかもしれませんが、ここは我慢してしっかりと洗浄しましょう。
ステップ2: 清潔なガーゼで圧迫止血する
傷口をきれいにしたら、次に出血を止めます。清潔なガーゼやハンカチ、タオルなどを傷口に直接当て、その上から手で強く圧迫してください。 5分から10分程度、じっと圧迫を続けます。途中で様子を見たくてガーゼを剥がすと、固まりかけた血が剥がれてしまい、再び出血してしまいます。焦らず、しっかりと圧迫を続けましょう。腕や足からの出血の場合は、傷口を心臓より高い位置に上げると、血が止まりやすくなります。
ステップ3: 傷口を保護する
止血ができたら、傷口を保護して病院へ向かいます。新しい清潔なガーゼなどを当て、テープや包帯で固定します。近年、傷を乾燥させずに潤った状態に保つ「湿潤療法」が知られていますが、自己判断で市販の湿潤療法用パッド(キズパワーパッドなど)を深い傷に使うのは危険です。 浸出液が多い傷や感染の疑いがある傷に使うと、かえって細菌の温床となり、悪化させてしまう可能性があります。 応急処置の段階では、清潔なガーゼでの保護にとどめておき、医師の判断を仰ぎましょう。
【ケース別】特に注意したい傷の縫合基準
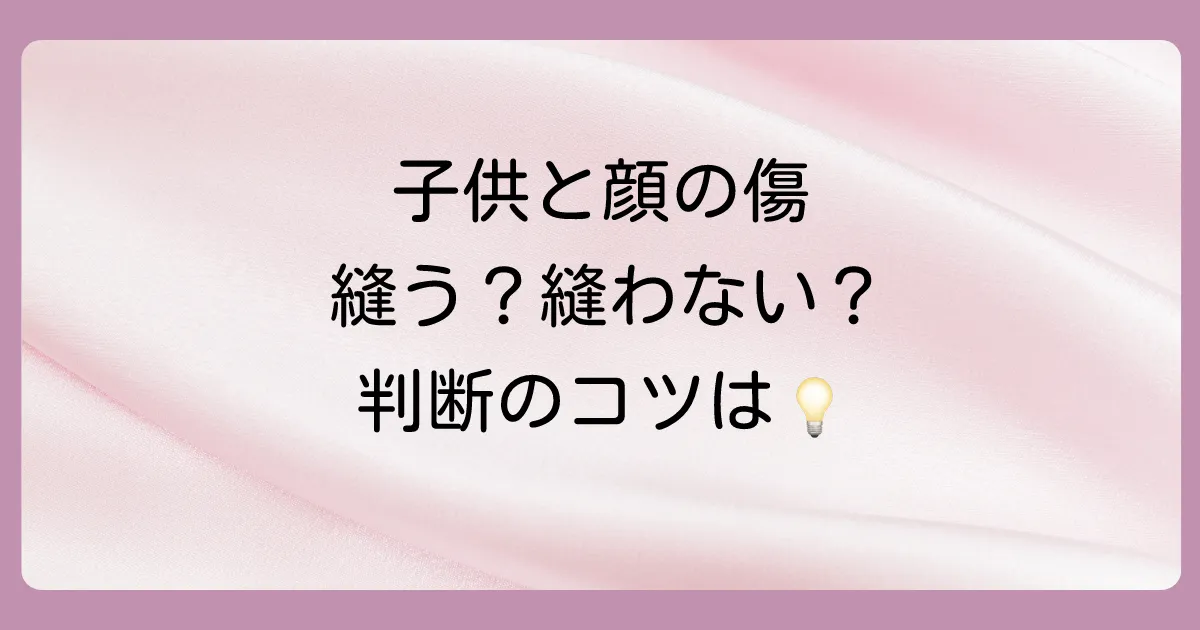
怪我は誰にでも起こり得ますが、特に「子供」や「顔」の怪我は、対処に一層の注意が必要です。それぞれのケースで、どのような点に気をつけて縫合の必要性を判断すればよいのか、詳しく見ていきましょう。
- 子供の怪我の場合
- 顔の怪我の場合
子供の怪我の場合
子供は活発に動き回るため、転んだりぶつけたりと怪我が絶えません。しかし、子供は自分の状態を正確に伝えることが難しいため、周りの大人が冷静に状況を判断してあげる必要があります。 子供の傷で特に注意すべき点は、傷口がぱっくりと開いているかどうかです。 何もしなくても傷の縁が寄っている場合はテープでの固定で済むこともありますが、開いたままになっている場合は、きれいに治すために縫合した方が良いケースが多いです。 また、子供は治療に対して恐怖心を持ちやすいため、病院によっては、押さえつけるのではなく、子供に優しく説明しながら処置を進めてくれるところもあります。 小児科や、子供の治療経験が豊富な形成外科などを選ぶのも良いでしょう。
顔の怪我の場合
顔は最も人目につく場所であり、傷跡が残ると精神的な負担も大きくなります。そのため、顔の怪我はたとえ小さな傷であっても、安易に自己判断せず、形成外科に相談することを強くおすすめします。 形成外科では、傷跡が極力目立たないように、髪の毛よりも細い糸を使ったり、皮膚のしわの方向に沿って縫合したりと、専門的な技術を駆使して治療してくれます。また、怪我をしてから縫合するまでの時間も重要で、「ゴールデンタイム」と呼ばれます。感染のリスクが低く、きれいに治りやすいとされる時間は、顔の場合は24時間以内、その他の部位では6〜8時間以内が目安と言われています。 顔に怪我をした際は、できるだけ早く受診することが、きれいな治癒への鍵となります。
よくある質問
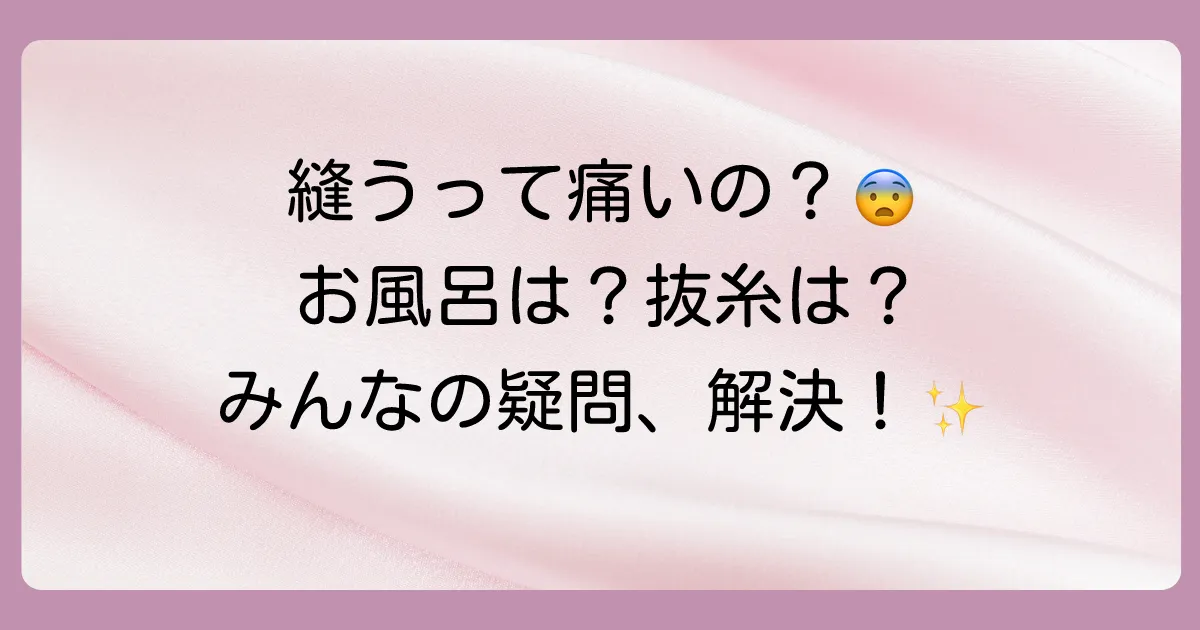
-
Q. 傷を縫うのは痛いですか?
-
A. 縫合処置を行う前には、必ず傷の周りに局所麻酔の注射をします。そのため、縫っている最中に痛みを感じることはほとんどありません。 麻酔の注射自体はチクッとした痛みがありますが、それが終われば痛みなく処置を受けられます。痛みに弱い方や不安な方は、事前に医師に伝えておくと良いでしょう。
-
Q. 縫った後、お風呂には入れますか?
-
A. 医師の指示に従うのが原則ですが、多くの場合、手術当日はシャワーを控え、翌日から可能となることが多いです。 ただし、湯船に浸かるのは、傷口から雑菌が入る可能性があるため、抜糸が終わるまで控えるように指示されるのが一般的です。傷口を濡らした後は、清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、処方された軟膏を塗るなどのケアが必要です。
-
Q. 抜糸はいつ頃しますか?
-
A. 抜糸までの期間は、傷の場所や深さ、治り具合によって異なります。一般的に、血行が良く治りが早い顔や頭部は5日〜1週間程度、動きが多くて皮膚に緊張がかかりやすい手足や関節周りは10日〜2週間程度が目安です。 医師が最適なタイミングを判断しますので、必ず指示された日に受診してください。
-
Q. 縫わずにテープで固定する方法もあると聞きましたが?
-
A. はい、全ての切り傷を糸で縫うわけではありません。傷の深さが比較的浅く、きれいに寄せられる場合は、医療用の皮膚接合用テープ(ステリテープ™など)や、医療用接着剤で傷を固定する方法もあります。 これらの方法は、特に子供の小さな傷や、抜糸の負担を減らしたい場合に選択されることがあります。どの方法が最適かは、医師が傷の状態を見て判断します。
-
Q. 湿潤療法(キズパワーパッドなど)はどんな傷にも使えますか?
-
A. 湿潤療法は、浅い擦り傷や靴擦れなどには非常に有効な治療法です。 しかし、縫合が必要な深い傷、動物に噛まれた傷、異物が混入している傷、すでに感染を起こしている傷には絶対に使用しないでください。 傷口を密閉することで、内部で細菌が繁殖し、かえって状態を悪化させる危険性が高いです。使用できる傷かどうかの判断に迷う場合は、必ず医師に相談してください。
-
Q. 縫合に保険は適用されますか?
-
A. はい、怪我の治療として行われる縫合処置は、基本的に健康保険が適用されます。診察料、処置料、薬剤料などが保険の対象となります。ただし、傷跡をさらにきれいにしたい、といった美容目的の治療(レーザー治療など)に移行する場合は、自費診療になることもあります。詳しくは、受診する医療機関にご確認ください。
まとめ
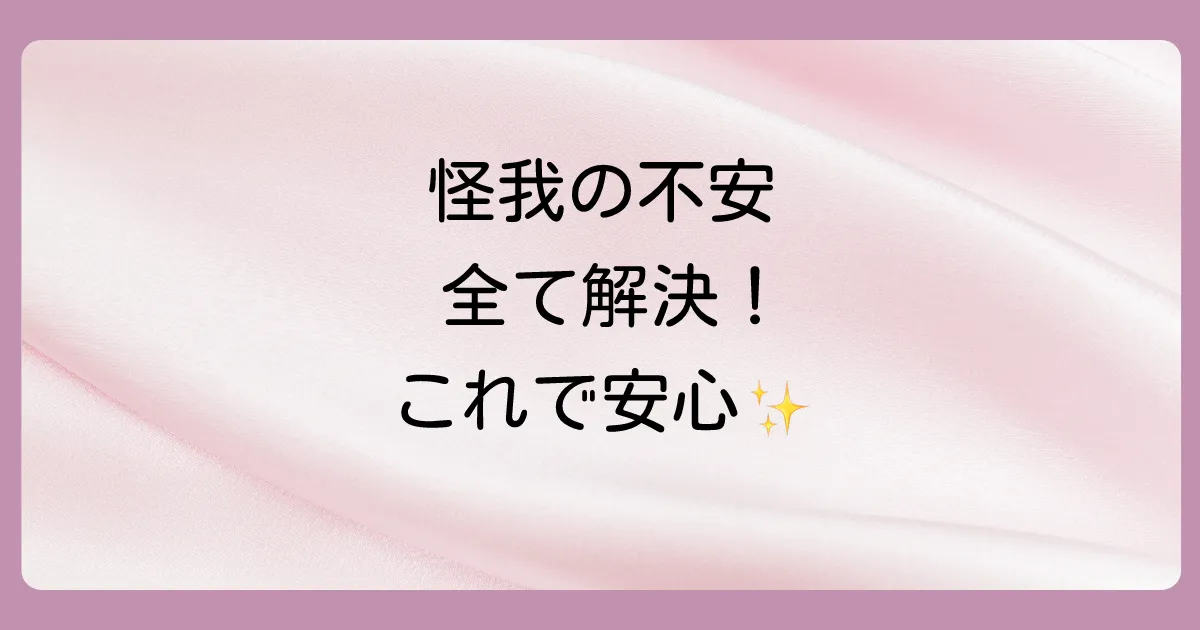
- 傷を縫うか迷ったら、深さ・開き・出血・場所をチェックする。
- 黄色い脂肪が見えたり、圧迫しても血が止まらなかったりしたら病院へ。
- 関節や顔の傷は、きれいに治すために縫合を検討するのがおすすめ。
- 縫うべき傷の放置は、傷跡が目立ったり感染したりするリスクがある。
- 傷跡をきれいに治したいなら「形成外科」が第一選択。
- 深い傷や骨・腱の損傷が疑われる場合は「整形外科」へ。
- 何科か迷ったら「外科」に相談するのも一つの手。
- 夜間・休日の緊急時は迷わず「救急外来」を利用する。
- 応急処置の基本は「洗浄」と「圧迫止血」。
- まずは水道水で傷口の汚れをしっかり洗い流すことが重要。
- 自己判断での湿潤療法パッドの使用は、深い傷では危険。
- 子供の怪我は、大人が冷静に傷の状態を確認して判断する。
- 顔の怪我は、ゴールデンタイム(24時間以内)の受診が鍵。
- 縫合処置は局所麻酔をするため、処置中の痛みはほとんどない。
- – 怪我の治療としての縫合は、健康保険が適用される。
新着記事




