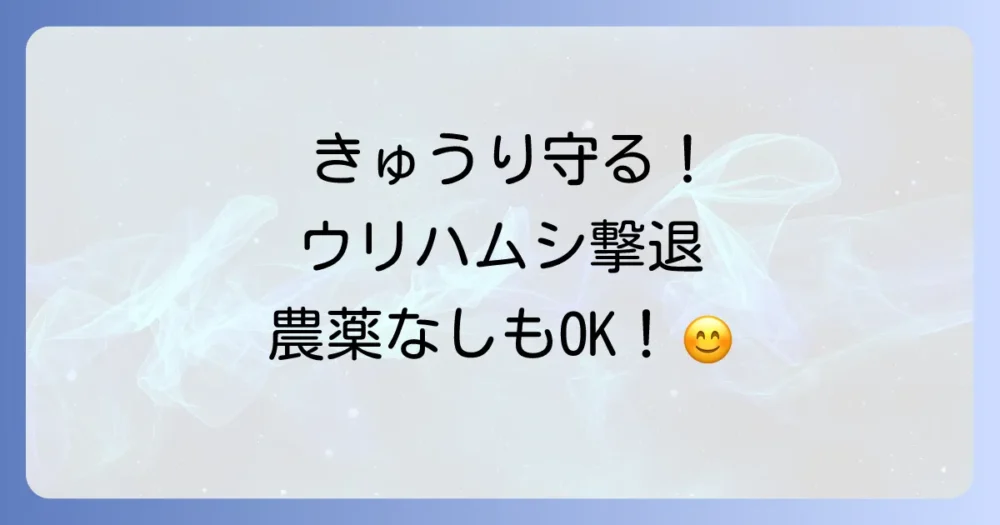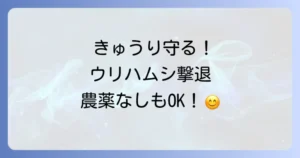大切に育てているきゅうりやカボチャの葉が、気づけば穴だらけに…。「またウリハムシか…」と、ため息をついている方も多いのではないでしょうか。家庭菜園を楽しむ上で、ウリハムシは本当に厄介な害虫ですよね。本記事では、そんな悩みを解決するため、ウリハムシに効果的な殺虫剤の選び方から、具体的なおすすめ商品、さらには農薬を使いたくない方向けの自然な対策まで、ウリハムシ対策の全てを分かりやすく解説します。もうウリハムシに悩まない、元気な野菜作りの一助となれば幸いです。
憎きウリハムシ!その生態と被害とは?
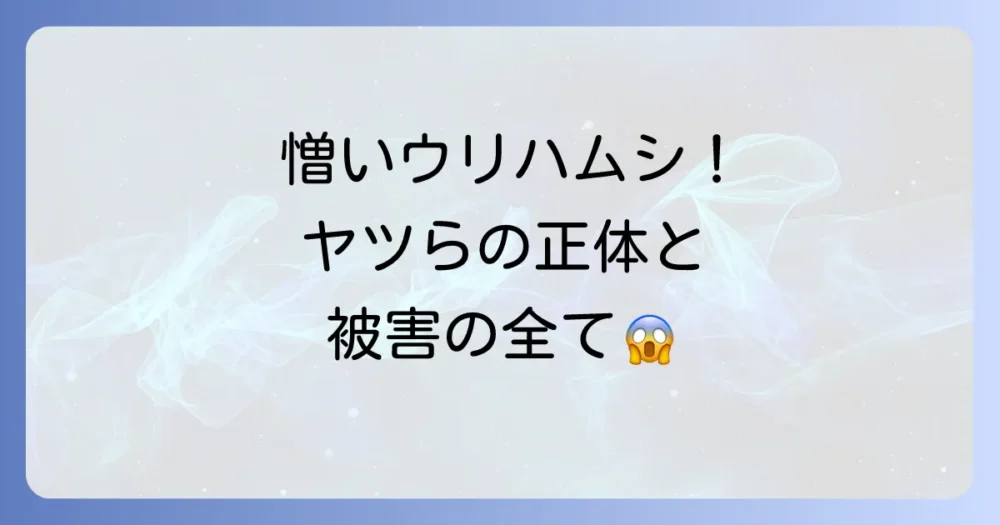
効果的な対策を行うには、まず敵を知ることから。ウリハムシがどのような虫で、どういった被害をもたらすのかを理解することが、駆除への第一歩です。ここでは、ウリハムシの基本的な生態と、家庭菜園に及ぼす恐ろしい被害について解説します。
本章で解説する内容は以下の通りです。
- ウリハムシの基本情報(見た目、ライフサイクル)
- ウリハムシが引き起こす被害(成虫と幼虫)
- ウリハムシが発生しやすい野菜
ウリハムシの基本情報(見た目、ライフサイクル)
ウリハムシは、コウチュウ目ハムシ科に属する昆虫です。 その名の通り、ウリ科の植物を好んで食べます。成虫の体長は7〜9mmほどで、全身が橙黄色や黄褐色をしているのが特徴です。 見た目は可愛らしくも見えますが、その食欲は旺盛で、農作物にとってはまさに天敵と言える存在です。
ウリハムシは成虫の姿で、石垣の隙間や草むらなどで冬を越します。 そして、春になり暖かくなると活動を開始し、4月下旬から5月頃にかけてウリ科の作物に飛来して産卵します。 卵は株元の土中に産み付けられ、孵化した幼虫は土の中で根を食べて成長。 その後、土の中で蛹になり、夏(7〜8月)になると新成虫となって地上に現れます。 このように、成虫と幼虫の両方が植物に害を与えるため、非常に厄介なのです。
ウリハムシが引き起こす被害(成虫と幼虫)
ウリハムシの被害は、成虫と幼虫で異なります。それぞれの被害状況をしっかり把握しておきましょう。
まず、成虫による被害は、主に葉の食害です。成虫は植物の葉を、まるでレースのように円形や網目状に食べてしまいます。 特に、苗がまだ小さいうちにこの被害にあうと、光合成が十分にできなくなり、生育が著しく阻害されてしまいます。ひどい場合には、苗が枯れてしまうことも少なくありません。 また、葉だけでなく、スイカやメロンなどの果実の表面をかじって品質を低下させることもあります。
一方、幼虫による被害は、土の中で静かに進行するため発見が遅れがちです。幼虫は植物の根を食害します。 根が傷つけられると、水分や養分をうまく吸収できなくなり、日中に葉がしおれたり、最悪の場合は株全体が枯死してしまったりします。 成虫の姿が見えなくても、植物の元気がない場合は、土の中の幼虫を疑う必要があるのです。
ウリハムシが発生しやすい野菜
ウリハムシという名前の通り、この害虫が最も好むのはウリ科の植物です。家庭菜園で人気の高い以下の野菜は、特に注意が必要です。
- キュウリ
- カボチャ
- スイカ
- メロン
- ゴーヤ
- ズッキーニ
これらの野菜を育てている場合は、春先の植え付け時期から厳重な警戒が必要です。 逆に、ナスやピーマン、トマトといったウリ科以外の野菜には、あまり被害を及ぼさないとされています。
プロが厳選!ウリハムシに効く殺虫剤おすすめ12選
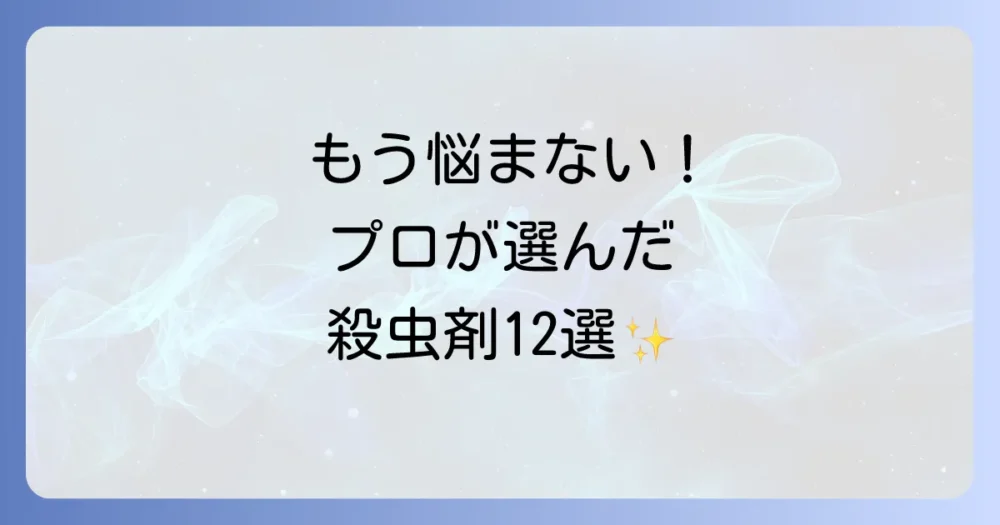
ウリハムシの被害がすでに出てしまっている場合、迅速な駆除が不可欠です。ここでは、家庭菜園でも使いやすく、効果の高い殺虫剤を厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選んでください。
本章で紹介する殺虫剤は以下の通りです。
- 住友化学園芸 オルトランDX粒剤
- エムシー緑化 トレボン粉剤DL
- 住友化学 ダントツ水溶剤
- 住友化学園芸 ベニカ水溶剤
- 住友化学園芸 マラソン乳剤
- 日本農薬 スミチオン乳剤
- 住友化学園芸 ベニカAスプレー
- 住友化学園芸 サンケイダイアジノン粒剤3
- 日本曹達 モスピラン粒剤
- アディオン乳剤
- GFオルトラン粒剤
- ベニカグリーンVスプレー
住友化学園芸 オルトランDX粒剤
土に混ぜ込むだけで効果が持続する、非常に手軽で人気の高い殺虫剤です。最大の特徴は「浸透移行性」という性質。 薬剤の成分が根から吸収され、植物全体に行き渡るため、葉を食べる成虫はもちろん、土の中に隠れている幼虫にも効果を発揮します。 アセフェートとクロチアニジンの2種類の有効成分が含まれており、より効率的な駆除が期待できます。 植え付け時に土に混ぜたり、株元にばらまくだけで良いので、初心者の方にもおすすめです。
エムシー緑化 トレボン粉剤DL
葉の上に直接振りかける粉末タイプの殺虫剤です。即効性と持続性に優れており、散布後すぐに効果が現れ、長期間害虫から作物を守ります。 直接ウリハムシにかけるだけでなく、薬剤が付着した葉を食べさせることでも駆除できるのが強み。カメムシやアオムシなど、ウリハムシ以外の様々な害虫にも効果があるため、一つ持っておくと重宝するでしょう。
住友化学 ダントツ水溶剤
幅広い作物と害虫に使える、プロの農家からも信頼されている殺虫剤です。 ウリハムシにももちろん有効で、少ない量でも長い期間効果が持続します。 オルトランと同様に浸透移行性に優れているため、散布後に新しく出てきた葉に付いたウリハムシにも効果的です。 水に溶かして使うタイプなので、散布には噴霧器などが必要になりますが、その効果は折り紙付きです。
住友化学園芸 ベニカ水溶剤
有効成分「クロチアニジン」を含む、顆粒タイプの水溶剤です。 水に溶かして散布すると、有効成分が葉や根から吸収され、植物全体に広がります。 これにより、葉を食害する成虫と根を食害する幼虫の両方を同時に退治できます。コンパクトなパッケージで、家庭菜園でも扱いやすいのが嬉しいポイントです。
住友化学園芸 マラソン乳剤
野菜から花まで幅広く使える、家庭園芸の代表的な殺虫剤の一つです。 速効性のある有機リン系の殺虫剤で、薬剤がかかった葉をウリハムシが食べることで効果を発揮します。 定期的に散布することで、次々と発生するウリハムシにも対応できます。古くから使われている信頼性の高い農薬です。
日本農薬 スミチオン乳剤
マラソン乳剤と同じく、有機リン系の代表的な殺虫剤です。 稲や果樹、野菜など非常に幅広い作物に使用でき、ウリハムシだけでなくアブラムシやカメムシなど、多くの害虫に効果があります。 即効性があり、害虫の神経系に作用して駆除します。 多くの家庭菜園愛好家に長年利用されている定番商品です。
住友化学園芸 ベニカAスプレー
見つけたらすぐに使える、手軽なスプレータイプです。希釈する必要がなく、ウリハムシを見つけたら直接シュッと吹きかけるだけで駆除できます。速効性があり、すぐに効果を実感したい場合に便利です。1本備えておくと、いざという時にすぐに対応できて安心です。
住友化学園芸 サンケイダイアジノン粒剤3
主にコガネムシの幼虫やネキリムシといった土壌害虫をターゲットにした殺虫剤ですが、ウリハムシの幼虫対策にも有効です。 植え付けの際に土に混ぜ込むことで、根を食べる幼虫の被害を防ぎます。 成虫への直接的な効果はありませんが、幼虫の段階で駆除することで、次世代の発生を抑えることができます。
日本曹達 モスピラン粒剤
定植時に株元に散布することで、長期間にわたってウリハムシの被害を防ぐことができる予防効果の高い薬剤です。 浸透移行性があり、有効成分が根から吸収されて植物全体を守ります。 少量で長く効くのが特徴で、土の中にいる幼虫と、葉を食べる成虫の両方に効果を発揮します。
アディオン乳剤
キュウリをはじめ、70種類以上の作物に登録があり、非常に汎用性の高い殺虫剤です。 ウリハムシはもちろん、様々な害虫から作物を守ることができます。 希釈して使用するタイプで、作物や害虫によって使用方法が異なるため、ラベルをよく確認して使用することが大切です。
GFオルトラン粒剤
株元や植穴にばらまくだけで効果が持続する、手軽さが魅力の浸透移行性殺虫剤です。 野菜や花、観葉植物など幅広い植物に使え、広範囲の害虫に効果があります。ウリハムシ対策としては、植え付け時に土に混ぜ込むことで、幼虫と成虫の両方からの被害を長期間にわたって防ぎます。
ベニカグリーンVスプレー
病気と虫に同時に効く、便利なスプレー剤です。殺虫成分が葉に吸収され、葉の裏に隠れた害虫にも効果を発揮します。 ウリハムシを見つけた時に手軽に使えるだけでなく、うどんこ病などの病気予防も同時にできるため、一石二鳥のアイテムと言えるでしょう。
もう迷わない!ウリハムシ殺虫剤の賢い選び方
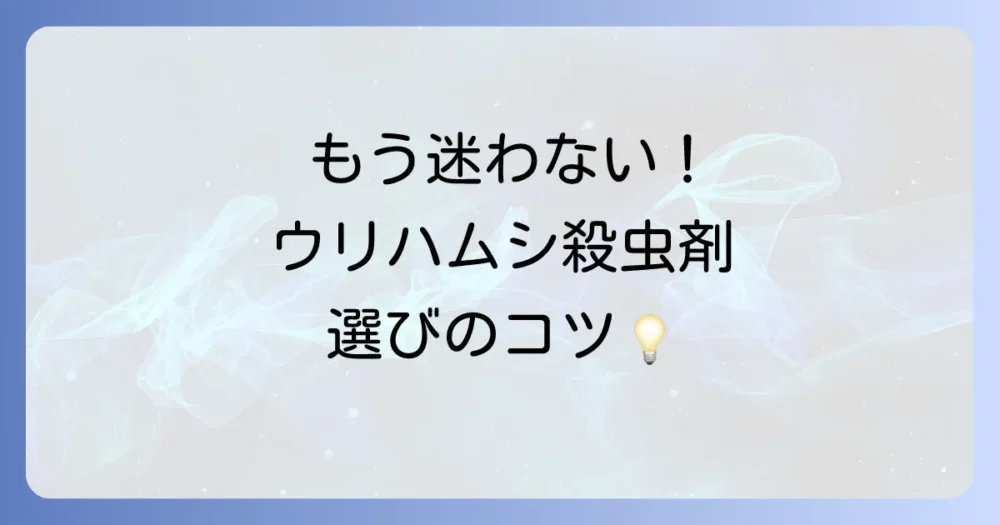
たくさん種類があって、どれを選べばいいか分からない…という方のために、殺虫剤を選ぶ際の3つのポイントを解説します。このポイントを押さえれば、あなたの菜園にぴったりの殺虫剤がきっと見つかります。
本章で解説する内容は以下の通りです。
- ポイント①:効果のタイプで選ぶ(速効性 vs 浸透移行性)
- ポイント②:剤形で選ぶ(スプレー、粒剤、粉剤、乳剤)
- ポイント③:使える作物で選ぶ(農薬登録情報)
ポイント①:効果のタイプで選ぶ(速効性 vs 浸透移行性)
殺虫剤の効果の現れ方には、大きく分けて2つのタイプがあります。
一つは「速効性」の殺虫剤です。これは、薬剤が直接かかった虫をすぐに駆除するタイプで、マラソン乳剤やスミチオン乳剤、スプレー剤などがこれにあたります。 目の前のウリハムシを今すぐ退治したい!という場合に適しています。
もう一つは「浸透移行性」の殺虫剤です。これは、薬剤が根や葉から吸収されて植物全体に行き渡り、その植物を食べた虫を駆除するタイプです。 オルトラン粒剤やダントツ水溶剤などが代表的です。 効果が現れるまでに少し時間はかかりますが、効果の持続期間が長く、葉の裏や土の中に隠れている害虫にも効くのが最大のメリットです。予防的に使う場合や、手間を減らしたい場合におすすめです。
ポイント②:剤形で選ぶ(スプレー、粒剤、粉剤、乳剤)
殺虫剤には様々な形状(剤形)があり、それぞれに使い方や特徴が異なります。
- スプレー剤: 希釈不要ですぐに使える手軽さが魅力。見つけた虫に直接噴射するのに便利。
- 粒剤: 土に混ぜたり、株元に撒くだけで効果が持続。手間がかからず、予防的な使用に最適。
- 粉剤: 葉や茎に直接振りかけるタイプ。広範囲に手早く散布できます。
- 乳剤・水和剤: 水で薄めて噴霧器などで散布するタイプ。手間はかかりますが、コストパフォーマンスに優れ、広範囲の散布に適しています。
ご自身の菜園の規模や、どれだけ手間をかけられるかに合わせて選ぶと良いでしょう。
ポイント③:使える作物で選ぶ(農薬登録情報)
非常に重要なポイントですが、農薬は商品ごとに使用できる作物が法律で定められています。 例えば、同じウリハムシに効く殺虫剤でも、キュウリには使えてもスイカには使えない、といったケースがあります。
購入前には必ず、商品のパッケージや公式サイトで「適用作物」を確認し、自分が育てている野菜に使えるかどうかをチェックしてください。 安全に野菜を育てるための大切なルールです。
【無農薬・減農薬】自然の力でウリハムシを寄せ付けない方法
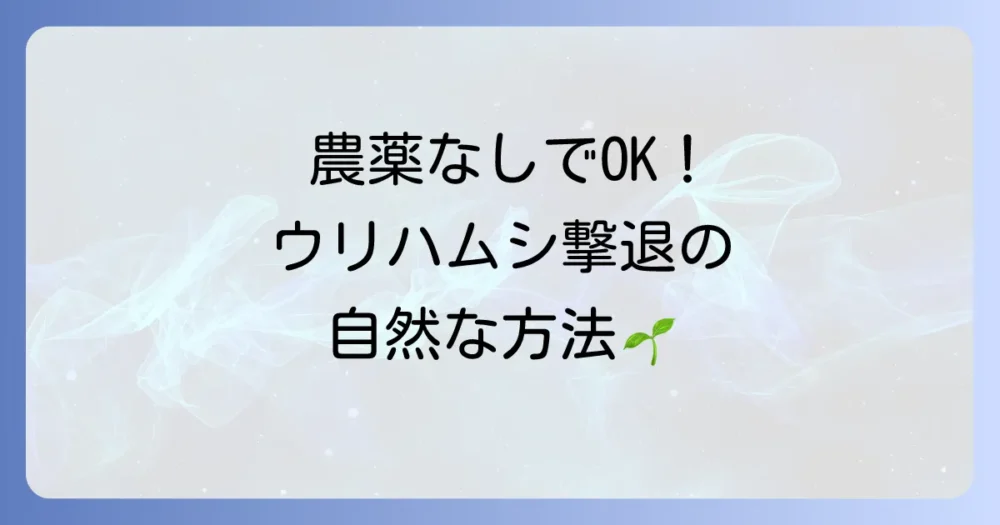
「できるだけ農薬は使いたくない」と考える方は多いはずです。ここでは、化学合成農薬に頼らずにウリハムシの被害を減らすための、環境に優しい予防・対策方法をご紹介します。
本章で解説する内容は以下の通りです。
- 物理的にシャットアウト!
- 嫌なニオイで追い払う!
- 見つけ次第、捕まえる!
物理的にシャットアウト!
ウリハムシが作物に近づけないように、物理的にガードする方法は非常に効果的です。
防虫ネット・寒冷紗
最も確実な方法の一つが、畝全体を防虫ネットや寒冷紗で覆ってしまうことです。 特に、苗が小さく被害を受けやすい時期にトンネル状に被せておくことで、成虫の飛来と産卵を完全に防ぐことができます。 目の細かいネットを選ぶのがポイントです。
シルバーマルチ・反射テープ
ウリハムシは、キラキラと光るものを嫌う性質があります。 この性質を利用して、畝の表面に銀色のシート(シルバーマルチ)を敷くことで、ウリハムシが寄り付きにくくなります。 地温の上昇を抑える効果や、雑草防止効果も期待できるため一石二鳥です。
行灯(あんどん)
植え付けたばかりの幼い苗をピンポイントで守るのに有効なのが「行灯(あんどん)」です。 苗の周りを、肥料の空き袋やポリ袋、笹などで囲い、物理的にウリハムシの侵入を防ぎます。 苗が大きく成長するまでの間の、一時的な保護策として非常に効果的です。
嫌なニオイで追い払う!
ウリハムシが嫌う植物やニオイを利用して、遠ざける方法です。
コンパニオンプランツ
ウリ科の植物の近くに、ウリハムシが嫌うニオイを放つ植物(コンパニオンプランツ)を植える方法です。代表的なのはネギ類(長ネギ、ニラ、タマネギなど)で、その強い香りがウリハムシを遠ざける効果があると言われています。 その他、ラディッシュやジニア(百日草)なども効果が期待できるとされています。
木酢液・竹酢液スプレー
木酢液や竹酢液は、木炭や竹炭を焼くときに出る煙を冷やして液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。 この香りをウリハムシが嫌うため、水で薄めてスプレーすることで忌避効果が期待できます。 土壌の微生物を活性化させる効果もあるとされ、自然派の家庭菜園で人気のある資材です。
見つけ次第、捕まえる!
原始的な方法ですが、地道な捕殺も被害を広げないためには重要です。
手で捕殺
朝早い時間帯など、ウリハムシの動きが鈍い時を狙って、手や捕虫網で捕まえる方法です。ウリハムシは危険を察知するとポトッと下に落ちる習性があるので、葉の下に受け皿や袋を構えておくと捕まえやすいです。
ペットボトルトラップ
ペットボトルを使って簡単に作れるトラップも有効です。 ペットボトルの上部を切り取り、逆さにして本体に差し込むだけで完成。ウリハムシを見つけたら、このトラップの中に指で弾き飛ばして捕獲します。一度入ると出にくい構造なので、効率的に捕殺できます。
よくある質問(Q&A)
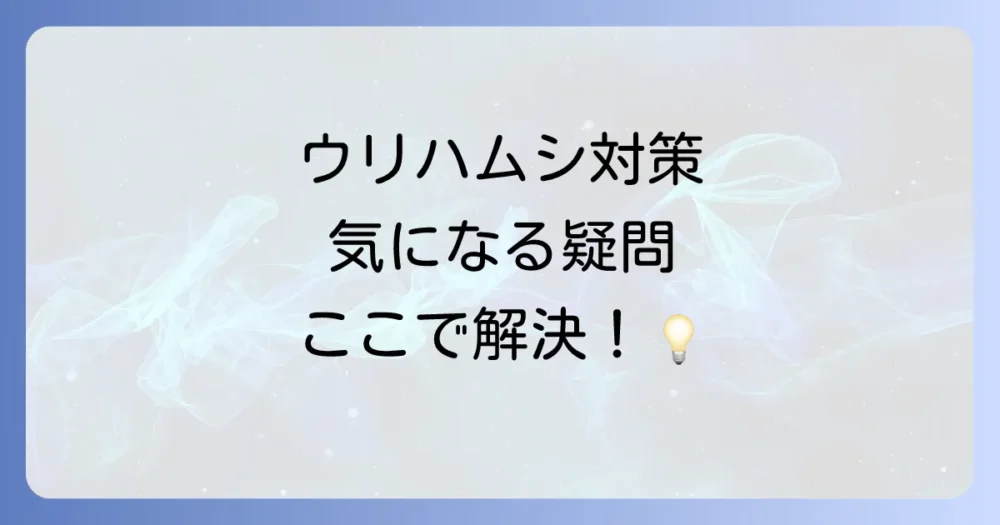
ここでは、ウリハムシ対策に関して、皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。
ウリハムシの天敵はいますか?
残念ながら、ウリハムシにはこれといった有力な天敵がいないと言われています。 テントウムシやクモなどが捕食することもあるようですが、積極的に食べてくれるわけではないため、天敵による防除効果はあまり期待できません。 そのため、人間が積極的に対策を講じる必要があるのです。
木酢液や酢は本当に効きますか?
木酢液や食酢には、殺虫効果はありませんが、ウリハムシが嫌うニオイによる「忌避効果」が期待できます。 定期的に散布することで、ウリハムシを寄せ付けにくくする効果が見込めます。ただし、効果は永続的ではないため、雨が降った後などは再度散布する必要があります。あくまで予防的な手段、または他の対策との組み合わせで活用するのがおすすめです。
殺虫剤のローテーションは必要ですか?
はい、必要です。同じ系統の殺虫剤を使い続けていると、その薬剤に抵抗性を持つウリハムシ(薬剤が効きにくい、または効かない個体)が現れることがあります。 これを防ぐために、作用性の異なる複数の種類の殺虫剤を順番に使う「ローテーション散布」が非常に重要です。 例えば、「今週はAという殺虫剤、来週はBという殺虫剤」というように、系統の違う薬を使い分けるようにしましょう。
殺虫剤はいつ撒くのが効果的ですか?
殺虫剤を散布するのに最も効果的な時間帯は、ウリハムシの活動が活発になる早朝や日中です。 ただし、真夏の炎天下での散布は、薬害(植物が傷むこと)の原因になる可能性があるので避けた方が良いでしょう。また、風の強い日や雨が降りそうな日も、薬剤が流れたり飛散したりしてしまうため効果が薄れます。風のない穏やかな日の午前中などが散布に適しています。
まとめ
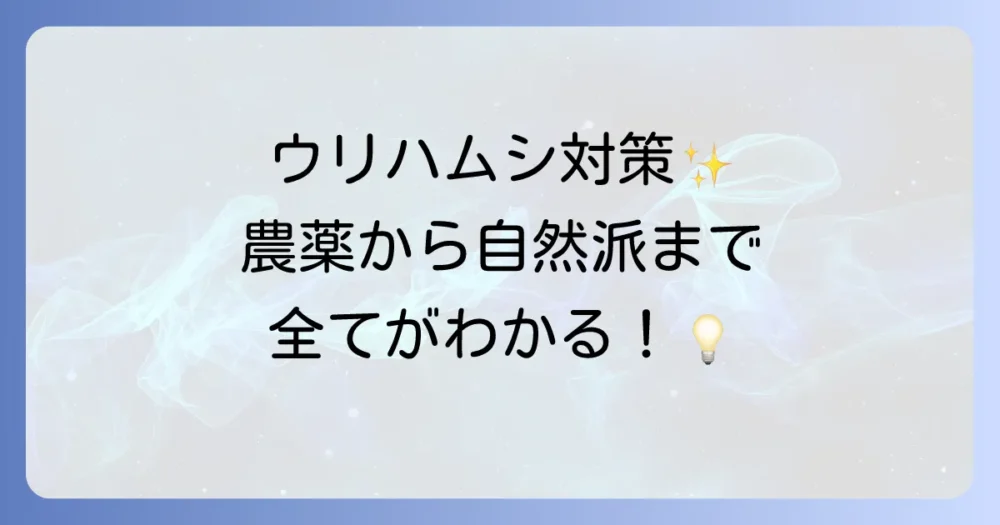
- ウリハムシは成虫が葉を、幼虫が根を食害する厄介な害虫です。
- 被害がすでにある場合は、殺虫剤による迅速な駆除が効果的です。
- 殺虫剤には「速効性」と「浸透移行性」のタイプがあります。
- 浸透移行性の殺虫剤は、予防効果が高く、土中の幼虫にも効きます。
- 殺虫剤は「剤形(スプレー、粒剤など)」で使いやすさが異なります。
- 必ず育てている作物に使える農薬かを確認してから使用しましょう。
- 同じ殺虫剤の連続使用は避け、ローテーション散布を心がけましょう。
- 農薬を使わない対策として、防虫ネットは非常に有効です。
- シルバーマルチは光の反射でウリハムシを寄せ付けにくくします。
- 行灯(あんどん)は植え付け初期の苗を守るのに役立ちます。
- コンパニオンプランツとしてネギ類を植えるのもおすすめです。
- 木酢液や酢のスプレーには、殺虫効果ではなく忌避効果が期待できます。
- 手で捕殺したり、トラップを仕掛けたりする地道な作業も大切です。
- ウリハムシには天敵が少ないため、人の手による対策が不可欠です。
- 殺虫剤での駆除と、物理的な予防策の組み合わせが最も効果的です。