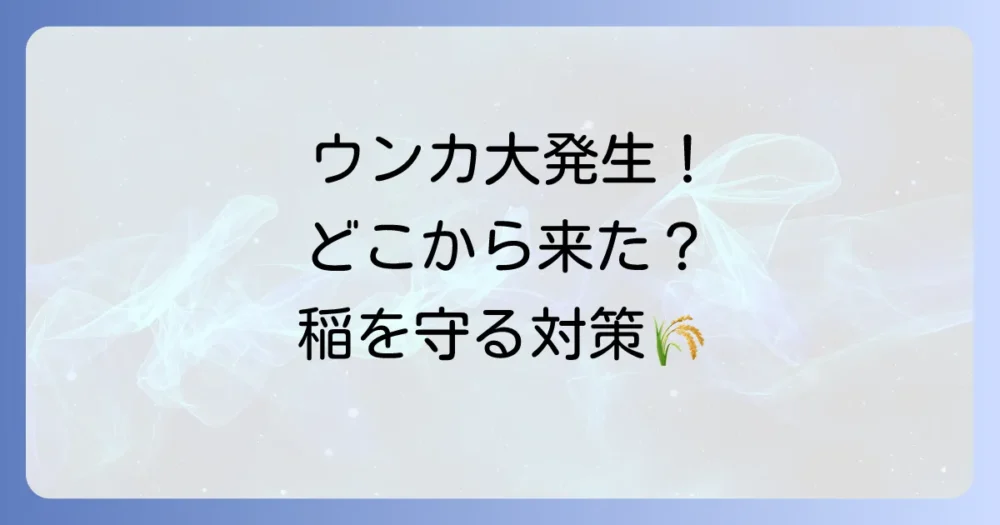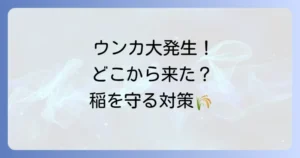「田んぼの稲が急に枯れ始めた…」「ライトに小さな虫がびっしり…」それはもしかしたら、ウンカの大量発生が原因かもしれません。ウンカは稲作にとって深刻な被害をもたらす害虫です。この記事では、ウンカがなぜ大量発生するのか、その驚くべき原因から、具体的な被害、そして今すぐできる駆除・対策方法まで、稲作農家の方々の悩みに寄り添い、分かりやすく解説します。大切な稲を守るための知識を一緒に深めていきましょう。
ウンカの大量発生、その驚くべき原因とは?
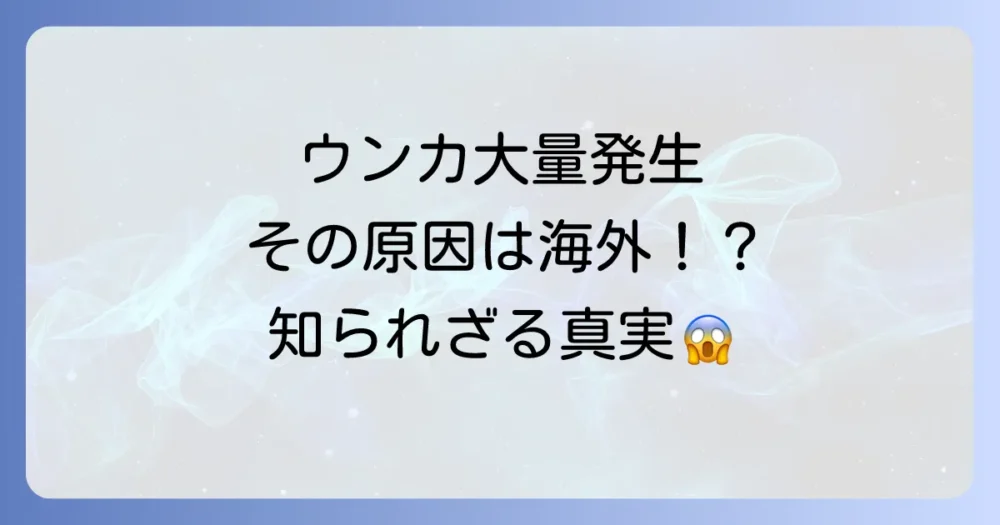
ウンカの大量発生は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って起こります。特に近年、西日本を中心に被害が深刻化している背景には、ウンカの生態と現代の農業環境が大きく関係しています。ウンカの発生源と、大量発生を後押しする主な要因について見ていきましょう。
本章では、以下の内容について詳しく解説します。
- 海外からの飛来が主な原因
- 近年の大量発生を加速させる3つの要因
海外からの飛来が主な原因
日本で問題となるウンカの多くは、実は日本国内で冬を越すことができません。 では、どこからやってくるのでしょうか?その答えは、はるか遠くの海外です。
主にトビイロウンカやセジロウンカは、ベトナム北部や中国南部といった一年中稲作が行われている地域で発生し、世代を繰り返しながら増殖します。 そして、梅雨の時期(6月下旬から7月上旬頃)になると、偏西風の一種である「下層ジェット気流」という強力な風に乗り、海を越えて日本へと飛来してくるのです。
この飛来は、まさに気流に乗った大移動。自分たちの力だけでは長距離を移動できないウンカにとって、この季節風が日本への重要な交通手段となっています。 毎年、この時期になるとウンカの飛来が確認され、その年の発生状況を占う重要な指標となります。
近年の大量発生を加速させる3つの要因
海外から飛来するウンカですが、近年その被害が拡大している背景には、いくつかの要因が考えられます。
- 飛来源(海外)での発生増加
ウンカの発生源であるベトナムや中国で、ウンカが増えやすい品種(多収量米など)の作付けが増加していることが指摘されています。 栄養価が高く、ウンカにとって格好の餌場となる稲が増えたことで、現地でのウンカの発生量が爆発的に増加。その結果、日本へ飛来してくるウンカの絶対数も増えているのです。 - 薬剤抵抗性の発達
長年にわたる農薬の使用により、特定の薬剤が効きにくい「薬剤抵抗性」を持ったウンカが出現・増加しています。 飛来源の国々で多用された薬剤に対して抵抗性を獲得したウンカが日本に飛来するため、これまで効果のあった農薬が効きづらく、防除が困難になるケースが増えています。 これは非常に深刻な問題で、防除体系の見直しが常に求められています。 - 日本国内の気象条件
日本に飛来した後のウンカの増殖には、国内の気象条件が大きく影響します。特に、夏の猛暑はウンカの繁殖活動を活発にし、世代交代のスピードを速めます。 飛来してくるウンカの数が多く、さらに国内の天候が増殖に適している年に、大量発生のリスクは一気に高まるのです。
これらの要因が複合的に絡み合うことで、近年のウンカ大量発生と深刻な被害につながっていると考えられています。
【種類別】ウンカの生態と見分け方
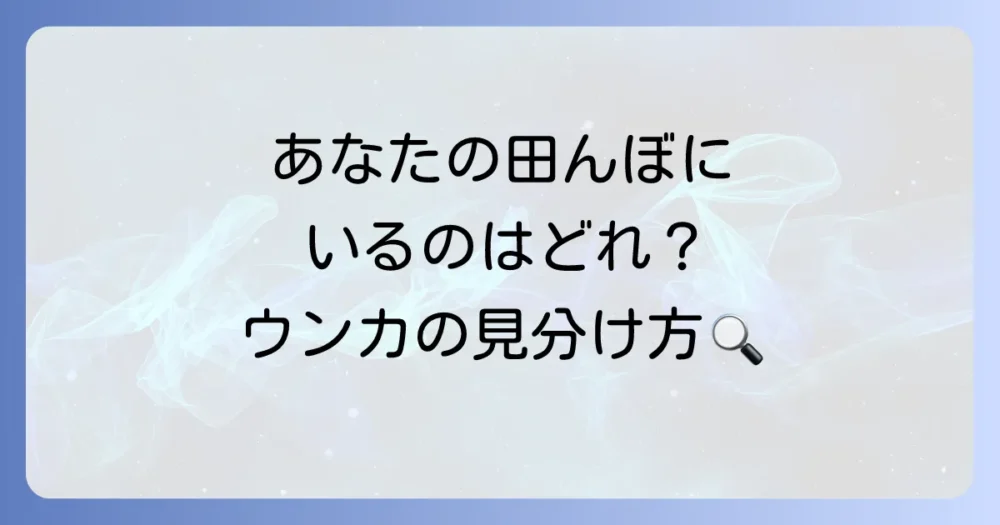
「ウンカ」と一括りにされがちですが、日本で稲に被害をもたらす主なウンカは3種類存在します。 それぞれ生態や被害の出し方が異なるため、特徴を知ることが適切な対策の第一歩です。ここでは、代表的な3種類のウンカについて、その生態と見分け方のポイントを解説します。
本章では、以下のウンカの種類と見分け方について解説します。
- トビイロウンカ(秋ウンカ)
- セジロウンカ(夏ウンカ)
- ヒメトビウンカ
- 簡単な見分け方のポイント
トビイロウンカ(秋ウンカ)
最も警戒すべきウンカと言えるのが、このトビイロウンカです。体長は約4.5mm~5mmほどで、脂ぎった褐色をしています。
9月から10月の秋口に被害が目立つことから「秋ウンカ」とも呼ばれます。 梅雨時期に海外から少数飛来した後、水田で世代を繰り返し、秋に爆発的に増殖するのが特徴です。 1世代の増殖率が非常に高く、メス1匹が数百個の卵を産むため、3世代目には凄まじい数になります。
この大群が一斉に稲の養分を吸うことで、田んぼの一部が円形に枯れてしまう「坪枯れ」という深刻な被害を引き起こします。 坪枯れは収穫間際に発生することが多く、農家にとって壊滅的なダメージとなりかねません。
セジロウンカ(夏ウンカ)
セジロウンカは、7月から8月の夏に多く発生するため「夏ウンカ」と呼ばれます。 体長は3~4mm程度とトビイロウンカよりやや小さく、背中に菱形の白い紋があるのが特徴です。
トビイロウンカと同様に海外から飛来しますが、爆発的に増えることは比較的少なく、坪枯れを起こすことは稀です。 しかし、多数のセジロウンカが稲の葉鞘に産卵することで、稲の生育が抑制されたり、排泄物が原因で「すす病」が発生したりする被害をもたらします。 また、近年ではイネ南方黒すじ萎縮病というウイルス病を媒介することも問題視されています。
ヒメトビウンカ
ヒメトビウンカは、他の2種とは異なり、日本国内で越冬できるのが最大の特徴です。 麦やイネ科の雑草などで冬を越し、春になると水田に移動します。体長は3~4mmと小型です。
吸汁による直接的な被害はほとんどありませんが、イネ縞葉枯病(いねしまはがれびょう)やイネ黒すじ萎縮病といった深刻なウイルス病を媒介する厄介な存在です。 近年では、中国から薬剤抵抗性を持ったヒメトビウンカが飛来する事例も確認されており、注意が必要な害虫です。
簡単な見分け方のポイント
ウンカは非常に小さく、肉眼での正確な種類の特定は難しい場合があります。 しかし、発生時期や被害の状況からある程度推測することが可能です。
| 種類 | 主な発生時期 | 主な被害 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| トビイロウンカ | 9月~10月(秋) | 坪枯れ | 褐色でやや大きい。爆発的に増える。 |
| セジロウンカ | 7月~8月(夏) | 生育抑制、すす病 | 背中に白い紋がある。 |
| ヒメトビウンカ | 年間を通じて | ウイルス病の媒介 | 小型。国内で越冬する。 |
正確な同定にはルーペなどが必要ですが、まずは「秋に坪枯れが出たらトビイロウンカ」「夏に稲の元気がなければセジロウンカ」といったように、時期と被害状況から当たりをつけることが対策の第一歩となります。
ウンカがもたらす深刻な被害
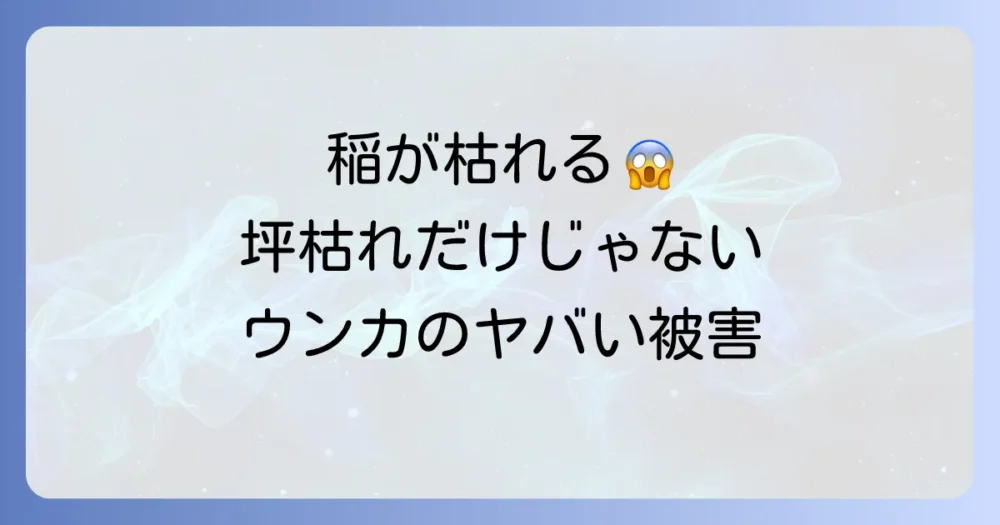
ウンカの大量発生がもたらす被害は、単に稲の生育が悪くなるだけではありません。収穫量の激減に直結する深刻な問題を引き起こし、農家の経営を脅かします。ここでは、ウンカが引き起こす具体的な被害について詳しく見ていきましょう。
本章では、ウンカによる主な被害について解説します。
- 吸汁による直接的な被害(坪枯れ・生育抑制)
- ウイルス病の媒介
- すす病の発生
吸汁による直接的な被害(坪枯れ・生育抑制)
ウンカの最も直接的な被害は、成虫・幼虫ともに稲の茎や葉にストロー状の口を刺し込み、養分(師管液)を吸汁することです。
特にトビイロウンカによる被害は甚大です。秋に爆発的に増殖した大群が、一斉に稲の株元に集まって吸汁するため、稲は養分を奪われて急激に衰弱。ついには、田んぼに穴が空いたように円形にまとまって枯れてしまいます。 これが「坪枯れ」と呼ばれる現象で、一度発生すると被害は急速に拡大し、収穫皆無となることも少なくありません。
一方、セジロウンカは坪枯れを起こすことは稀ですが、多数が吸汁することで稲の生育が阻害される「生育抑制」を引き起こします。 また、葉鞘に産卵するため、その部分が傷ついて褐変し、生育に悪影響を及ぼすこともあります。
ウイルス病の媒介
ウンカは、吸汁する際に植物のウイルス病を媒介する「運び屋」としての役割も果たします。これが間接的でありながら、非常に厄介な被害です。
特にヒメトビウンカは、「イネ縞葉枯病」や「イネ黒すじ萎縮病」といった、稲の生育を著しく阻害し、収量を大きく低下させるウイルスの主な媒介者です。 ウイルスに感染した稲は、葉に黄色い縞模様が現れたり、株全体が萎縮して正常に穂が出なくなったりします。
一度ウイルス病に感染すると治療法はなく、その株からはまともな収穫は期待できません。ウンカが移動することで、病気は次々と健全な稲に広がっていきます。
すす病の発生
ウンカは吸汁した養分の一部を、糖分を多く含んだ甘い排泄物として排出します。この排泄物が稲の葉や茎に付着すると、それを栄養源として黒いカビの一種である「すす病菌」が繁殖します。
すす病が発生すると、稲の葉の表面が黒いすすで覆われたようになります。これにより、光合成が妨げられ、稲の生育が悪くなるだけでなく、米の品質低下にもつながります。特にセジロウンカの多発時に見られる被害です。
このように、ウンカは直接的な吸汁被害だけでなく、病気の媒介や二次的な被害も引き起こす、稲作にとって非常に手強い害虫なのです。
【今すぐできる】ウンカの駆除・対策方法
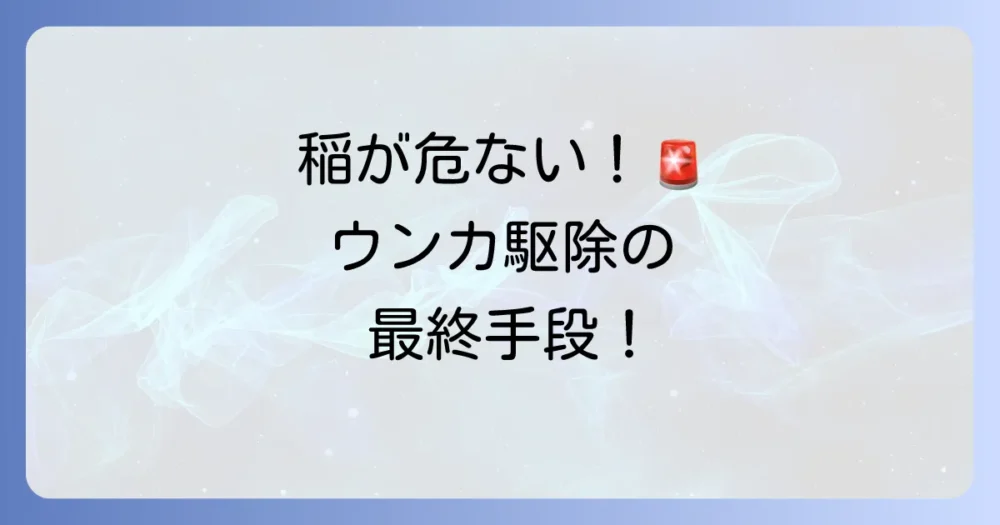
ウンカの被害を最小限に食い止めるためには、早期発見と迅速な対策が何よりも重要です。ここでは、ウンカの発生を確認した際に有効な駆除・対策方法を、専門的なものから農家個人で実践しやすいものまで幅広くご紹介します。
本章で紹介する対策方法は以下の通りです。
- 薬剤による防除(農薬)
- 物理的な駆除方法
- 耕種的防除
薬剤による防除(農薬)
現在、ウンカ対策の最も主流で効果的な方法は、農薬(殺虫剤)による防除です。 農薬にはいくつかの種類があり、使用するタイミングや目的によって使い分けることが重要です。
育苗箱施用剤
最も効果的で省力的な予防策が、田植え前の苗箱に薬剤を処理する「育苗箱施用剤」です。 この薬剤は、有効成分が稲に吸収され、その稲を吸汁したウンカを殺虫する仕組みです。 移植後約50~60日間、効果が持続するため、飛来してくる第一世代のウンカを効果的に叩き、その後の増殖を抑えることができます。
本田散布剤
育苗箱施用剤の効果が切れる頃や、ウンカの発生が多くなった場合には、水田に直接薬剤を散布する「本田散布」が必要になります。 ウンカは稲の株元に生息しているため、薬剤が株元までしっかり届くように散布することがポイントです。
【重要】薬剤抵抗性への注意
前述の通り、近年は特定の薬剤成分に対して抵抗性を持つウンカが増えています。 例えば、トビイロウンカはイミダクロプリド系、セジロウンカはフィプロニル系の薬剤に抵抗性を発達させていることが報告されています。 地域の病害虫防除所などが発表する発生予察情報や薬剤感受性の情報を確認し、効果の高い薬剤を適切に選択することが非常に重要です。 同じ系統の薬剤を連用せず、異なる作用を持つ薬剤をローテーションで使用することも抵抗性の発達を防ぐ上で有効です。
物理的な駆除方法
薬剤に頼らない、あるいは薬剤と併用できる物理的な駆除方法もあります。
廃油を利用した方法
これは昔から伝わる方法の一つで、特にトビイロウンカの発生が目立ち始めた頃に有効です。田んぼの水面に廃食油などを少量垂らして油膜を作ります。 その後、竹竿などで稲の株を揺らしたり、送風機(ブロアー)で風を送ったりしてウンカを水面に叩き落とします。油膜に落ちたウンカは、油が気門(呼吸するための穴)を塞ぐことで窒息死します。
耕種的防除
日々の栽培管理の中で、ウンカが発生しにくい環境を作ることも大切な対策です。これを「耕種的防除」と呼びます。
- 田植え時期の調整: ウンカの飛来ピーク時期を避けて田植えを行うことで、初期の密度を下げることができます。
- 適切な施肥管理: 窒素肥料のやりすぎは、稲を軟弱に育て、ウンカの増殖を助長します。 肥料を多投しない、適切な施肥管理が重要です。
- 水管理: 水位を高めに保つことで、ウンカが産卵したり生息したりする株元の範囲を狭めることができます。
これらの対策を組み合わせ、地域の発生状況に応じて最適な方法を選択することが、ウンカ被害を乗り越える鍵となります。
来年に向けた予防策と長期的な管理
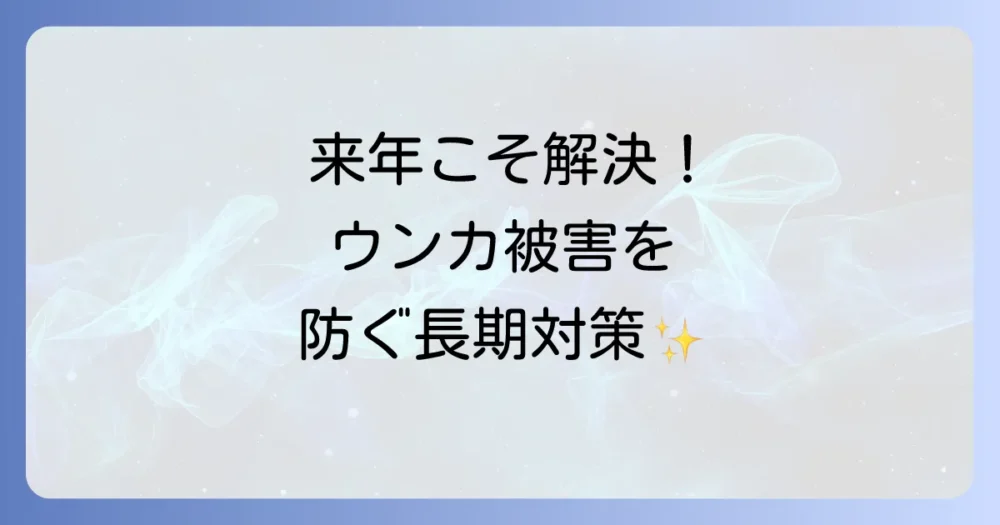
ウンカの被害は、その年だけの問題ではありません。一度大量発生を経験すると、「来年は大丈夫だろうか…」と不安になるのは当然のことです。ここでは、目先の駆除だけでなく、来年以降の発生リスクを低減するための長期的な視点に立った予防策と管理方法について解説します。
本章では、以下の長期的な対策についてご紹介します。
- 抵抗性品種の導入
- 天敵の活用(生物的防除)
- 発生予察情報の活用
抵抗性品種の導入
最も根本的な対策の一つが、ウンカに強い性質を持つ「抵抗性品種」を栽培することです。
研究機関では、ウンカが吸汁しにくい、あるいは吸汁しても増殖しにくいといった性質を持つ稲の品種開発が進められています。 例えば、トビイロウンカ抵抗性を持つ「ヒノヒカリ」の同等品種などが実用化されています。
抵抗性品種を導入することで、殺虫剤への依存度を減らし、環境への負荷を低減しながら安定した生産を目指すことが可能になります。ただし、抵抗性を持つウンカの種類が限定されていたり、地域によってはまだ導入できる品種が少なかったりする場合もあります。地域の農業指導機関などに相談し、自身の栽培環境に適した品種があるか検討してみる価値は十分にあります。
天敵の活用(生物的防除)
水田には、ウンカを捕食してくれる頼もしい「天敵」たちが存在します。これらの天敵を保護し、活用することも有効な防除方法(生物的防除)です。
ウンカの主な天敵には、以下のような生き物がいます。
- クモ類: 水田に生息する多種多様なクモは、ウンカの重要な捕食者です。
- カタグロミドリカスミカメ: ウンカの卵を捕食する天敵として知られています。
- トビイロカマバチ: ウンカに寄生するハチの一種です。
- アイガモ: アイガモ農法で知られるように、アイガモは雑草だけでなく害虫もよく食べます。
殺虫剤の使用は、これらの有益な天敵にも影響を与えてしまうことがあります。 薬剤を使用する際は、天敵への影響が少ないものを選択するなど、生態系全体のバランスを考慮することが、長期的に見て安定した防除につながります。
発生予察情報の活用
ウンカ対策において、「情報戦」を制することは非常に重要です。
各都道府県の病害虫防除所や農研機構などでは、ウンカの飛来状況や発生予測に関する情報を「発生予察情報」として定期的に発表しています。 この情報には、いつ頃、どのくらいの数のウンカが飛来したか、今後の発生量の予測、そして効果的な防除薬剤の種類などが含まれています。
これらの情報をこまめにチェックし、自分の地域の状況を正確に把握することで、「いつ」「何を」すべきかという的確な判断が可能になります。 例えば、「飛来が確認されたので、そろそろ本田散布の準備をしよう」「今年は薬剤抵抗性のウンカが多いようなので、A剤ではなくB剤を使おう」といった具体的な対策を立てることができます。
受け身の対策ではなく、自ら情報を収集し、計画的に防除を行うことが、来年以降のウンカ被害を最小限に抑えるための最も確実な方法と言えるでしょう。
よくある質問
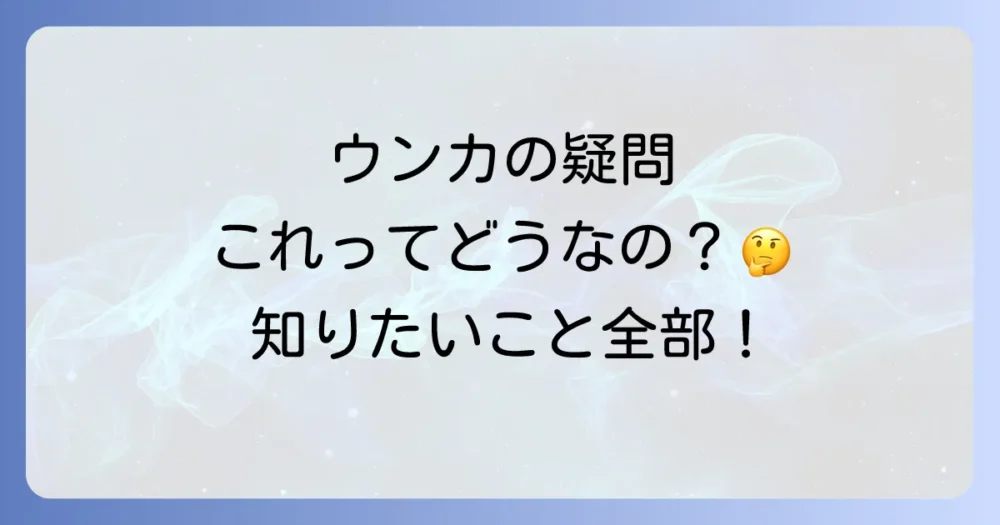
ウンカは人体に害がありますか?
ウンカは稲などの植物の汁を吸う害虫であり、人を刺したり咬んだりすることはありません。また、ウンカが原因で人体に直接的な健康被害が出たという報告も基本的にありません。大量発生した際に、灯りに集まってきて不快に感じることはありますが、毒を持っているわけではないので、その点はご安心ください。
ウンカの寿命はどのくらいですか?
ウンカの成虫の寿命は、種類や環境条件によって異なりますが、一般的に約10日から1ヶ月程度です。 例えば、トビイロウンカの成虫の寿命は約1ヶ月ほどで、その間に数百個の卵を産みます。 気温が高いと活動が活発になり世代交代が早まりますが、寿命自体が大きく変わるわけではありません。薬剤抵抗性を持つ系統では、寿命が短くなるという研究報告もあります。
ウンカはどこから家に入ってくるのですか?家庭での対策は?
ウンカは主に水田などの屋外に生息する昆虫ですが、大量発生した時期には、夜間に照明の光に誘われて家の中に侵入してくることがあります。特に網戸の隙間や、ドアの開閉時に入ってくることが多いです。家庭での対策としては、まず網戸の破れや隙間がないか確認し、必要であれば補修することが重要です。また、夜間は遮光カーテンを閉めて室内の光が外に漏れないように工夫することも効果的です。侵入してしまった場合は、殺虫スプレーなどで駆除できます。
ウンカとアブラムシの違いは何ですか?
ウンカとアブラムシは、どちらも植物の汁を吸う小さな害虫で、大量発生することがあるため混同されがちですが、異なる種類の昆虫です。
- ウンカ: カメムシ目ウンカ科に属します。セミに近い仲間で、比較的活発に飛び回ります。主にイネ科植物に寄生します。
- アブラムシ: カメムシ目アブラムシ科に属します。ほとんど移動せず、植物に群がってコロニーを作ります。非常に多くの種類の植物に寄生します。
簡単に見分けるには、動きと寄生している植物を確認すると良いでしょう。稲に発生し、ピョンピョンと飛び跳ねるように移動するのがウンカの特徴です。
薬剤抵抗性ウンカとは何ですか?
薬剤抵抗性ウンカとは、特定の殺虫剤(農薬)に対して抵抗力を持ち、その薬剤を散布しても死ににくくなったウンカのことです。 同じ系統の殺虫剤が長期間、繰り返し使用されることで、その薬剤に強い個体だけが生き残り、子孫を増やしていくことで発生します。 日本のウンカは海外から飛来するため、飛来源である中国やベトナムなどで薬剤抵抗性を獲得したウンカがやってくることが大きな問題となっています。 このため、防除所などが発表する薬剤感受性の情報を確認し、効果のある薬剤を選択することが非常に重要になります。
まとめ
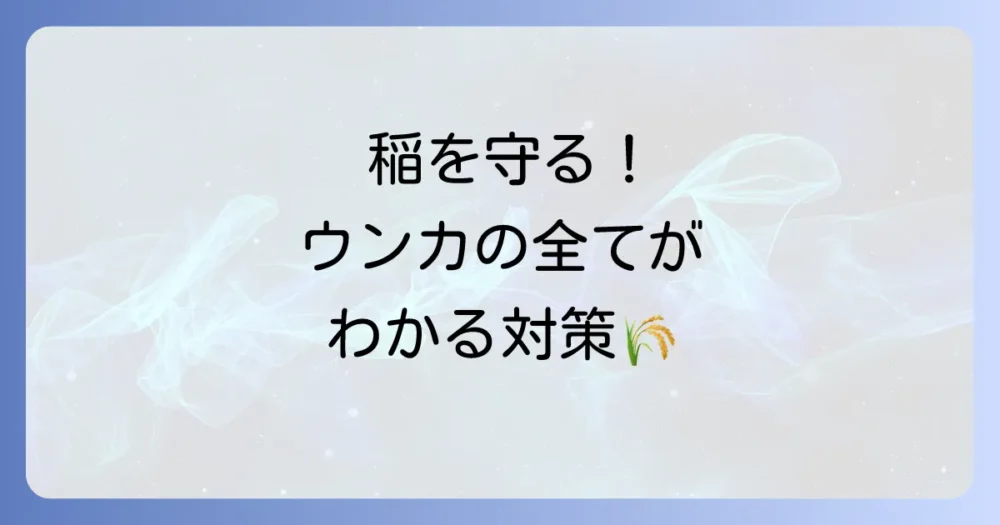
- ウンカの多くは海外からジェット気流に乗り飛来する。
- 飛来源での発生増が日本の大量発生に繋がる。
- 特定の農薬が効かない「薬剤抵抗性」が深刻化。
- 日本の夏の猛暑はウンカの増殖を加速させる。
- 「トビイロウンカ」は秋に坪枯れ被害を起こす。
- 「セジロウンカ」は夏に発生し生育を阻害する。
- 「ヒメトビウンカ」はウイルス病を媒介し国内越冬も可能。
- 被害は吸汁による坪枯れや生育抑制が主である。
- ウイルス病の媒介や、すす病の発生も問題となる。
- 対策の基本は育苗箱施用剤による予防防除。
- 発生後は薬剤が株元に届くよう本田散布を行う。
- 薬剤抵抗性を考慮した農薬選びが非常に重要。
- ウンカに強い「抵抗性品種」の導入も有効な手段。
- クモなどの天敵を活かす生物的防除も大切。
- 地域の発生予察情報を活用し計画的に対策する。