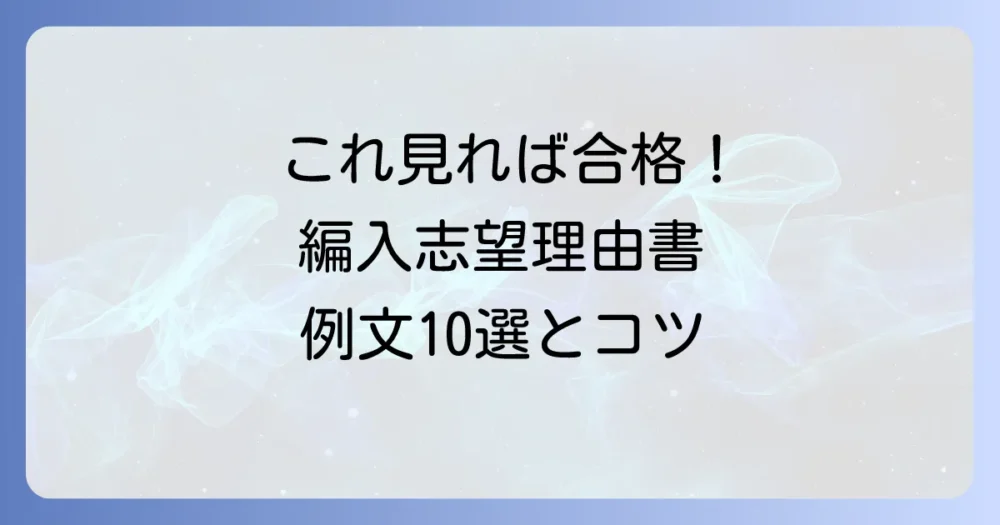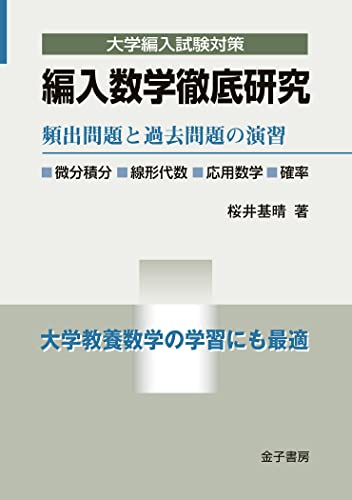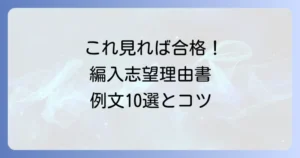編入試験を考えているけれど、「志望理由書って何から書けばいいの?」「どうすれば熱意が伝わる文章になるんだろう…」と、パソコンや原稿用紙を前に手が止まっていませんか?
本記事では、そんなあなたの悩みを解決します。学部別の豊富な例文を参考にしながら、合格を掴むための志望理由書の構成、他の受験生と差をつけるコツ、そして意外と知らないNG例まで、具体的かつ分かりやすく解説していきます。あなたの編入にかける想いを、合格に繋がる言葉に変えましょう。
なぜ編入の志望理由書は重要なのか?
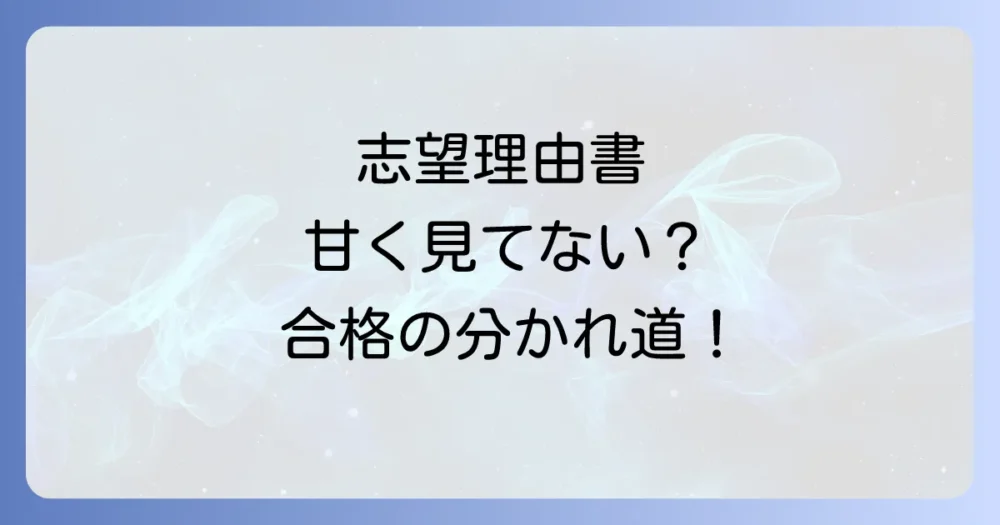
編入試験において、志望理由書は単なる出願書類の一つではありません。筆記試験だけでは測れない、あなたの学習意欲や将来性、そして「なぜこの大学でなければならないのか」という熱意を伝えるための、最も重要なアピールの場です。面接が課される場合は、この志望理由書を基に質問が進められるため、面接の出来をも左右する土台となります。 軽視せず、時間をかけて丁寧に作成することが、合格への第一歩と言えるでしょう。
【学部別】すぐに使える!編入の志望理由書 例文集
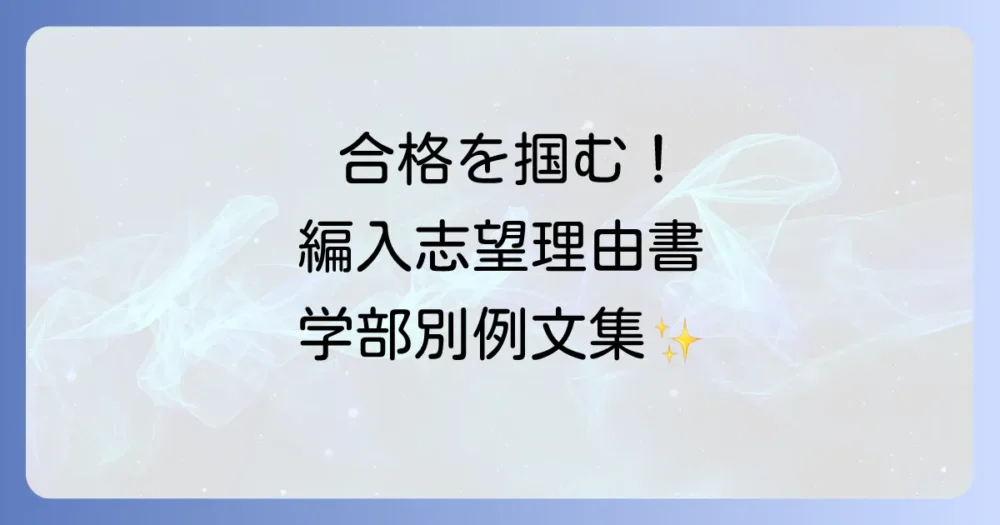
「理屈は分かったけど、具体的なイメージが湧かない…」そんな声にお応えして、学部系統別の志望理由書の例文をご紹介します。構成や表現のポイントを掴み、あなた自身の言葉でアレンジしてみてください。
本章で紹介する例文のポイントは以下の通りです。
- 文系学部(経済学部・法学部)の例文とポイント
- 理系学部(工学部・理学部)の例文とポイント
- 医療系学部(看護学部)の例文とポイント
- 専門学校・短大・高専からの編入 例文とポイント
文系学部(経済学部・法学部)の例文とポイント
文系学部では、社会問題への関心や、論理的な思考力が重視される傾向にあります。自身の経験と学びたい学問分野を具体的に結びつけることが重要です。
経済学部の例文
【例文】
私が貴学経済学部を志望する理由は、現代社会が抱える地域経済の格差問題について、多角的な視点から探求したいと考えているためです。現在、〇〇短期大学で地域創生に関する基礎を学んでおりますが、ゼミ活動で地方都市の商店街の衰退を調査した際、表面的な知識だけでは複雑な要因が絡み合う現状を解決できないと痛感しました。特に、貴学の〇〇教授がご専門とされる計量経済学の手法を用いて地域データを分析し、実証的なアプローチで課題解決の糸口を見つけたいと強く思うようになりました。編入後は、「地域経済論」や「公共経済学」を履修し、〇〇教授のゼミで実践的な研究に取り組みたいです。卒業後は、これまでの学びと貴学で得た専門知識を活かし、地方自治体の職員として、データに基づいた政策立案で地域活性化に貢献したいと考えております。
【ポイント】
- 具体的なきっかけ: 短大での調査という具体的な経験が、編入を志す動機として説得力を持たせています。
- なぜこの大学か: 特定の教授の名前や研究分野(計量経済学)を挙げることで、大学への深い理解と熱意を示しています。
- 明確な将来像: 卒業後のキャリアプラン(地方公務員)が具体的で、大学での学びが将来にどう繋がるかが明確です。
法学部の例文
【例文】
私は、情報化社会における個人の権利保護、特にプライバシー権の問題について深く学び、将来はサイバー犯罪に立ち向かう専門家になりたいと考えています。現在在籍する大学で法学の基礎を学ぶ中で、インターネット上の誹謗中傷や個人情報の流出問題に強い問題意識を抱くようになりました。貴学法学部は、最先端の「情報法」に関する科目が充実しており、この分野の第一人者である△△教授の指導を仰ぎたいと切望しております。また、学生が主体となってリーガルクリニックに参加できるプログラムにも魅力を感じており、実践的な法的思考力を養いたいと考えています。編入後は、△△教授のゼミに所属し、諸外国の法制度との比較研究を通じて、日本の法整備の課題について考察を深めたいです。そして、卒業後は法科大学院へ進学し、情報分野に強い検察官として社会の安全に貢献することが私の目標です。
【ポイント】
- 現代的な問題意識: サイバー犯罪やプライバシー権といった、現代社会の課題への関心は評価されやすいです。
- 具体的な学習計画: 履修したい科目(情報法)や参加したいプログラム(リーガルクリニック)を挙げることで、入学後の学習意欲の高さを示しています。
- 一貫性のあるキャリアパス: 法学部から法科大学院、そして検察官へという一貫したキャリアパスが、志望動機の説得力を高めています。
理系学部(工学部・理学部)の例文とポイント
理系学部では、これまでの学習で得た知識や技術、そして探究心や論理的思考力が問われます。なぜ現在の環境では不十分で、編入先の大学でなければならないのかを明確にしましょう。
工学部の例文
【例文】
私は、再生可能エネルギーの効率的な利用、特に次世代太陽電池の開発に貢献したいという強い思いから、貴学工学部への編入を熱望します。高等専門学校では、物質化学の基礎と実験技術を学んでまいりましたが、より高度な専門知識と最先端の研究環境を求めて大学編入を決意しました。貴学の□□研究室が、ペロブスカイト太陽電池の研究で世界的に高い評価を得ていることを知り、その環境でこそ自身の目標を追求できると確信しております。高専での卒業研究では、有機薄膜太陽電池の作成に取り組みましたが、変換効率の向上に限界を感じました。貴学で材料力学や量子化学の専門知識を深め、□□研究室で最先端の成膜技術や評価手法を学ぶことで、この壁を乗り越えたいです。将来は、貴学で培った研究開発能力を活かし、エネルギー問題の解決に貢献できる技術者になることが目標です。
【ポイント】
- 専門性と具体性: 「ペロブスカイト太陽電池」という具体的な研究分野を挙げることで、専門性の高さとリサーチの深さを示しています。
- 現在の学びとの接続: 高専での卒業研究の経験と、そこで感じた課題が、編入後の学習意欲に繋がっている点が評価されます。
- 研究室への言及: 具体的な研究室名を挙げることは、「この大学で学びたい」という強い意志の表れです。
理学部の例文
【例文】
私が貴学理学部物理学科を志望する理由は、宇宙の根源を解明する素粒子物理学の探求に身を投じたいからです。現在在籍する大学で物理学の基礎を学んでいますが、より専門的で理論的な研究に没頭したいという思いが日に日に強くなっています。特に、貴学が誇る◇◇理論物理学研究センターの存在は、私にとって大きな魅力です。最先端の研究に触れられるだけでなく、国内外の研究者との交流も盛んであると伺っており、そのような刺激的な環境で自身の知的好奇心を満たしたいと考えています。編入後は、量子力学や場の量子論といった基幹科目を徹底的に学び直し、大学院進学を視野に入れながら、超弦理論の研究に取り組みたいです。将来は研究者として、未解明な物理現象の解明に貢献し、人類の知のフロンティアを切り拓く一助となることが私の夢です。
【ポイント】
- 知的好奇心のアピール: 「宇宙の根源」「知のフロンティア」といった言葉で、学問に対する純粋な探究心と情熱を表現しています。
- 研究環境への魅力: 特定の研究センターを挙げ、その環境で学びたい理由を具体的に述べています。
- 長期的な視点: 大学院進学や将来の研究者としてのキャリアを見据えている点は、学習意欲の高さを示す上で有効です。
医療系学部(看護学部)の例文とポイント
医療系学部では、専門知識や技術はもちろんのこと、豊かな人間性やコミュニケーション能力、そして強い倫理観が求められます。自身の経験から得た問題意識と、将来の医療人としてのビジョンを結びつけましょう。
看護学部の例文
【例文】
私は、多様な文化背景を持つ患者一人ひとりに寄り添える看護師になるため、貴学看護学部への編入を強く希望します。短期大学で看護の基礎を学ぶ中で、外国人患者とのコミュニケーションの難しさに直面し、語学力だけでなく、異文化への深い理解に基づいた看護実践の必要性を痛感しました。貴学がグローバルな視点を持つ看護人材の育成に力を入れており、「国際看護学」や多文化共生に関するプログラムが充実している点に、大変魅力を感じています。編入後は、これらの専門科目を履修するとともに、留学生との交流にも積極的に参加し、多様な価値観に触れたいです。そして、〇〇先生のゼミで、在日外国人の医療アクセスに関する研究に取り組みたいと考えております。将来的には、貴学で得た知識と経験を活かし、国際的な医療支援活動にも貢献できる看護師になることが目標です。
【ポイント】
- 明確な問題意識: 外国人患者との関わりという実体験に基づいた問題意識が、志望動機にリアリティを与えています。
- 大学の特色との合致: 大学の強み(グローバル教育)と自身の学びたい方向性が一致していることをアピールできています。
- 社会貢献への意欲: 将来の目標として、国内だけでなく国際的な医療支援にも言及することで、広い視野と高い志を示しています。
専門学校・短大・高専からの編入 例文とポイント
専門学校や短大、高専で培った専門的な知識や技術は、編入試験において大きな強みになります。これまでの学びを土台に、なぜ大学でさらに学びを深めたいのかを論理的に説明することが重要です。
専門学校からの編入例文(情報系)
【例文】
私は、〇〇専門学校でプログラミングとネットワーク技術を学んできましたが、技術の背景にある情報科学の理論的基盤を体系的に学び直したいと考え、貴学情報理工学部への編入を決意しました。実務的なスキルを習得する中で、なぜこのアルゴリズムが最適なのか、なぜこのセキュリティ対策が必要なのかといった根源的な問いに突き当たり、より深い知識の必要性を痛感しています。貴学のカリキュラムは、計算機科学の基礎から応用まで幅広く網羅されており、特に△△教授の「計算理論」の講義に強い関心を抱いています。専門学校で培った実践的スキルと、貴学で学ぶ理論的知識を融合させることで、真に創造的な問題解決能力を持つ技術者になれると信じています。卒業後は、AI開発の分野に進み、社会に貢献する新たなサービスを創出したいです。
【ポイント】
- 実践から理論への深化: 専門学校での実践的な学びの中で生まれた知的好奇心が、大学での理論的な学習意欲に繋がっているというストーリーが説得力を持ちます。
- 学びの目的の明確化: 「体系的に学び直したい」「根源的な問い」といった表現で、大学でしか学べないことを求めている姿勢を明確にしています。
- 相乗効果のアピール: 専門学校でのスキルと大学での知識を「融合させる」ことで、他の学生にはない強みを発揮できる可能性を示唆しています。
合格レベルの志望理由書を書くための基本構成
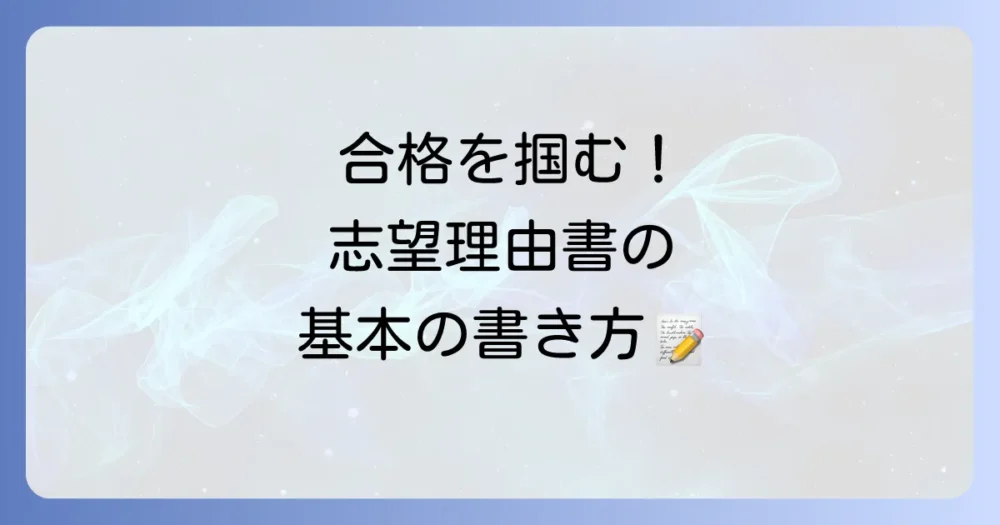
魅力的な志望理由書には、読む人を引き込み、納得させるための「型」があります。ここでは、多くの合格者が用いている基本的な構成を紹介します。この構成に沿って自分の考えを整理することで、論理的で分かりやすい文章を作成することができます。
本章で紹介する基本構成は以下の通りです。
- ①結論:なぜ貴学を志望するのか
- ②理由・きっかけ:編入を志望するに至った具体的な経験
- ③編入後の学習計画:何をどのように学びたいか
- ④将来の展望:卒業後、学びをどう活かしたいか
①結論:なぜ貴学を志望するのか
文章の冒頭で、最も伝えたい結論を簡潔に述べましょう。 「私が貴学〇〇学部を志望する理由は、△△という分野を深く探求し、将来□□として社会に貢献したいからです」というように、志望理由と将来の目標を明確に示します。最初に結論を提示することで、読み手である教授は、あなたが何を伝えたいのかをすぐに理解でき、その後の文章をスムーズに読み進めることができます。ここで曖昧な表現を使うと、文章全体の印象がぼやけてしまうため注意が必要です。
②理由・きっかけ:編入を志望するに至った具体的な経験
次に、なぜその分野に興味を持ち、編入を志すようになったのか、具体的なエピソードを交えて説明します。 例えば、「現在所属する大学の〇〇という授業で△△という課題に触れたこと」や、「専門学校でのインターンシップで□□という経験をしたこと」など、あなた自身の体験に基づいたストーリーは、志望動機に深みと独自性を与えます。この部分で、あなたの問題意識や探究心の源泉を示すことが重要です。ありきたりな理由ではなく、あなただけのオリジナルなきっかけを語りましょう。
③編入後の学習計画:何をどのように学びたいか
ここでは、入学後の学びに対する具体的なプランを示します。 「貴学の〇〇先生のゼミに所属し、△△というテーマで研究したい」「□□という授業や、◇◇というプログラムに積極的に参加し、専門知識を深めたい」など、志望大学のカリキュラムや教授、研究内容を事前にしっかりとリサーチした上で記述することが不可欠です。 この大学でなければならない理由を明確にすることで、あなたの熱意と本気度が伝わります。大学のウェブサイトやパンフレットをただ書き写すのではなく、その中で何に魅力を感じ、自分の学びにどう活かしたいのかを自分の言葉で語りましょう。
④将来の展望:卒業後、学びをどう活かしたいか
最後に、大学での学びを将来どのように活かしていきたいか、卒業後のビジョンを具体的に述べます。 「卒業後は大学院に進学し、研究者を目指したい」「貴学で得た専門性を活かし、〇〇業界で△△として活躍したい」など、明確なキャリアプランを示すことで、学びに対する目的意識の高さをアピールできます。編入後の学習が、その場限りではなく、あなたの人生設計の一部として位置づけられていることを伝えましょう。この展望が、これまでに述べてきた志望理由や学習計画と一貫していることが、説得力のある志望理由書を完成させるための鍵となります。
他の受験生と差をつける!志望理由書の質を高める3つのコツ
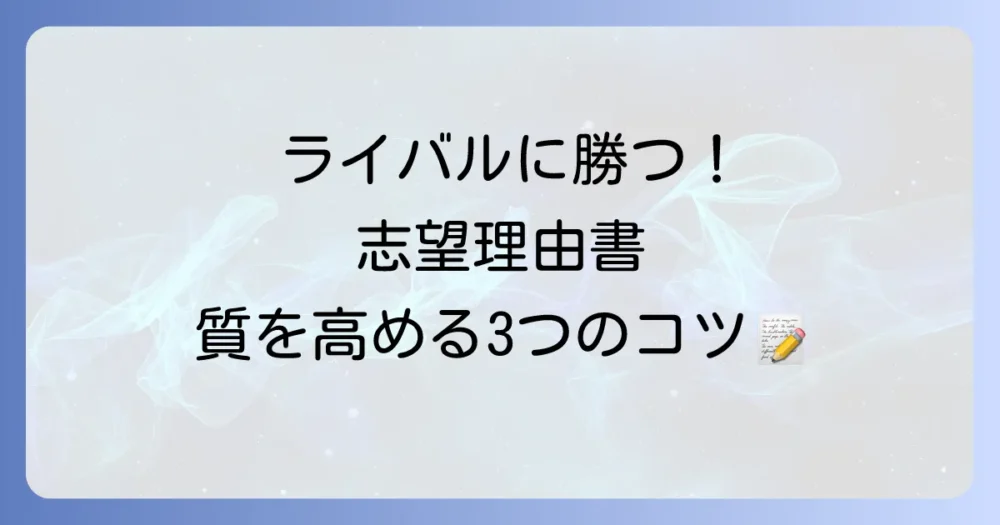
基本的な構成を押さえた上で、さらに一歩進んだ志望理由書を作成するためのコツをご紹介します。これらの点を意識することで、あなたの志望理由書は他の受験生の中から一際輝きを放つでしょう。
本章で紹介するコツは以下の通りです。
- コツ1:なぜ「この大学・この学部」でなければならないのかを明確にする
- コツ2:これまでの学びとこれからの学びを繋げる
- コツ3:具体的なエピソードで独自性を出す
コツ1:なぜ「この大学・この学部」でなければならないのかを明確にする
「他の大学でも学べるのでは?」と教授に思わせてしまっては、合格は遠のきます。「なぜ、この大学でなければならないのか」、その理由を徹底的に掘り下げて説明することが最も重要です。 そのためには、志望大学の理念や特色、カリキュラム、在籍する教授の研究内容などを深くリサーチする必要があります。 例えば、「〇〇教授の△△という研究に強く惹かれた」「貴学独自の□□という教育プログラムに魅力を感じた」など、その大学ならではの具体的なポイントを挙げましょう。この大学で学びたいという強い意志を示すことが、熱意を伝える上で不可欠です。
コツ2:これまでの学びとこれからの学びを繋げる
編入試験では、これまでの学歴(大学、短大、高専、専門学校)で何を学び、それが編入後の学習にどう繋がるのかを論理的に説明することが求められます。過去・現在・未来の学びを一本の線で結びつけることで、あなたの学習意欲に一貫性があることを示せます。 例えば、「高専で学んだ基礎的な技術を土台に、大学ではより高度な理論を学びたい」「短大で抱いた問題意識を、大学での専門的な研究で解決したい」といったように、これまでの学びが次のステップへの動機となっていることを明確にしましょう。これにより、計画性を持って学問に取り組む姿勢をアピールできます。
コツ3:具体的なエピソードで独自性を出す
抽象的な言葉を並べるだけでは、あなたの個性や熱意は伝わりません。あなた自身の具体的な経験やエピソードを盛り込むことで、志望理由書にリアリティと独自性が生まれます。 例えば、ある本を読んで感銘を受けた経験、ボランティア活動で感じた社会課題、授業でのディスカッションで得た気づきなど、あなただけの体験を語りましょう。その経験を通して、あなたが何を考え、どのように成長し、なぜ編入を志すに至ったのかをストーリーとして伝えることで、読み手である教授の心に響く、印象的な志望理由書になります。
これはNG!避けるべき志望理由書の書き方
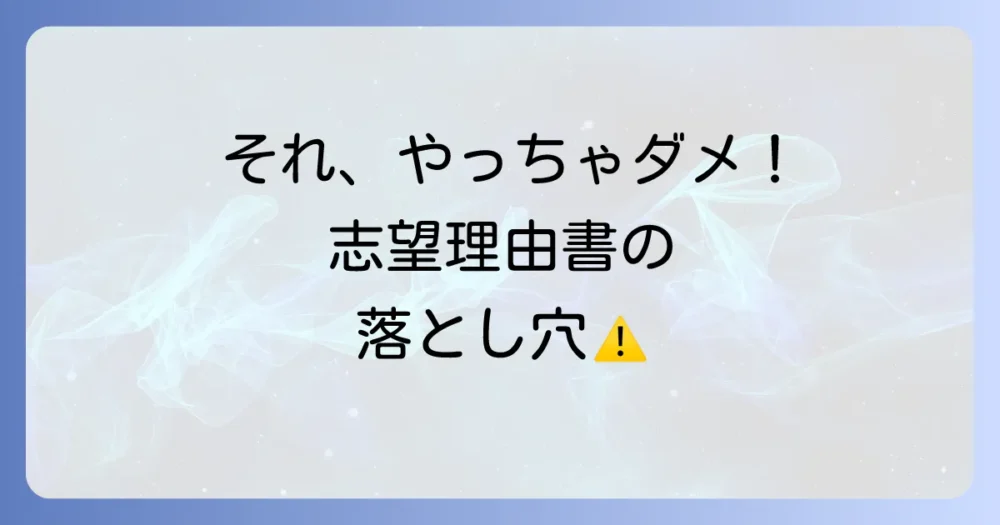
熱意を込めて書いたつもりが、かえってマイナスの印象を与えてしまうこともあります。ここでは、多くの受験生が陥りがちなNG例を紹介します。自分の志望理由書が当てはまっていないか、提出前に必ずチェックしましょう。
本章で紹介するNG例は以下の通りです。
- 抽象的で具体性がない
- 受け身な姿勢が見える
- 大学のウェブサイトやパンフレットの丸写し
- 誤字脱字や文法の間違い
抽象的で具体性がない
「貴学の教育理念に感銘を受けた」「幅広い知識を身につけたい」といった表現は、誰にでも言える抽象的な言葉であり、あなたの熱意は伝わりません。なぜその教育理念に感銘を受けたのか、具体的にどの部分に共感したのかを自分の言葉で説明する必要があります。また、幅広い知識の中でも特に何を学びたいのか、それを学んでどうしたいのかまで踏み込んで記述しなければ、学習意欲を疑われてしまいます。具体例やエピソードを交え、あなた自身の考えを示すことが重要です。
受け身な姿勢が見える
「〇〇を教えてほしい」「充実した環境で学びたい」といった、大学に何かをしてもらうことを期待するだけの受け身な姿勢は禁物です。 大学は、自ら主体的に学び、研究を進めていける学生を求めています。「〇〇という環境を活かして△△を研究したい」「□□の知識を能動的に吸収し、将来に活かしたい」というように、自分が大学の環境をどのように活用し、何を成し遂げたいのかという能動的な姿勢を示すことが大切です。「入学させていただけたら」という謙虚さも必要ですが、それ以上に「自分がこの大学に貢献できる」くらいの気概を見せましょう。
大学のウェブサイトやパンフレットの丸写し
大学のウェブサイトやパンフレットに書かれている美辞麗句をそのまま書き写すのは、リサーチ不足と熱意の欠如の表れと見なされます。 教授たちは、毎年何通もの志望理由書を読んでおり、どこかで見たような表現はすぐに見抜いてしまいます。大切なのは、そこに書かれている情報を自分なりに解釈し、「その情報がなぜ自分にとって魅力的なのか」「自分の学びたいこととどう結びつくのか」を自分の言葉で語ることです。情報を鵜呑みにするのではなく、自分自身のフィルターを通して再構築する作業が不可欠です。
誤字脱字や文法の間違い
基本的なことですが、誤字脱字や文法の間違いは、注意力が散漫である、あるいは志望度が低いという印象を与えかねません。 内容がどれだけ素晴らしくても、些細なミス一つで評価が大きく下がってしまう可能性があります。文章を作成した後は、必ず複数回読み返し、声に出して読んでみるなどして、ミスがないか徹底的に確認しましょう。可能であれば、学校の先生や予備校の講師、信頼できる友人など、第三者に読んでもらい、客観的な視点でチェックしてもらうことを強くおすすめします。
編入の志望理由書に関するよくある質問
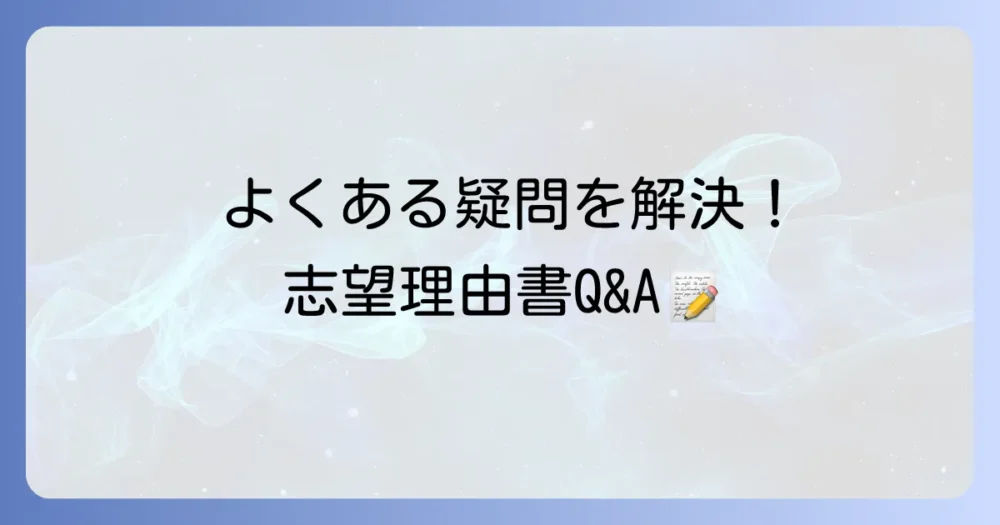
ここでは、編入の志望理由書を作成するにあたって、多くの受験生が抱く疑問にお答えします。
文字数指定はどのくらい守るべき?
大学から指定された文字数に対して、最低でも9割以上は埋めるように心がけましょう。文字数が少なすぎるのは、熱意が不足していると見なされる可能性があります。 逆に、指定文字数を大幅に超えるのも、要点をまとめる能力がないと判断される恐れがあるため避けるべきです。指定された文字数の中で、自分の伝えたいことを簡潔かつ論理的にまとめる練習が必要です。
手書きとパソコン、どちらが良い?
大学からの指定がない限り、手書きでもパソコン作成でも評価に直接的な影響はありません。手書きの場合は、丁寧で読みやすい字を心がけることが大前提です。 字の綺麗さに自信がない場合は、パソコンで作成する方が無難でしょう。パソコンで作成する場合は、大学が指定するフォントや文字サイズがあればそれに従い、なければ明朝体などの標準的なフォントを使用するのが一般的です。
志望理由書と自己推薦書の違いは?
志望理由書は、「なぜその大学・学部で学びたいのか」という未来に向けた学習意欲や計画を中心に記述するものです。一方、自己推薦書は、「自分はどのような強みや実績を持つ人物か」という過去から現在にかけての実績や能力をアピールする側面が強い書類です。ただし、大学によっては両者の区別が曖昧な場合もあるため、募集要項をよく確認し、大学側が何を求めているのかを正確に把握することが重要です。
添削は誰に頼むのがおすすめ?
完成した志望理由書は、必ず第三者に読んでもらい、客観的な意見をもらうことが重要です。 おすすめは、まず在籍している学校の先生(ゼミの担当教員やキャリアセンターの職員など)に相談することです。あなたのことをよく理解しており、専門的な視点からアドバイスをもらえるでしょう。さらに質の高いものを目指すのであれば、編入専門の予備校や添削サービスを利用するのも有効な手段です。 多くの合格者を輩出してきたプロの視点から、より効果的なアピール方法や改善点を指摘してもらえます。
面接では志望理由書について何を聞かれる?
面接は、提出した志望理由書の内容を基に行われることがほとんどです。 特に、「志望動機について、もう少し詳しく教えてください」「なぜ他の大学ではなく本学なのですか?」「入学後の学習計画について具体的に説明してください」「将来の夢と本学での学びはどう繋がりますか?」といった質問は頻出です。 志望理由書に書いた内容を自分の言葉でよどみなく、さらに深く説明できるように準備しておく必要があります。書いた内容を丸暗記するのではなく、その背景にある自分の考えや想いをしっかりと整理しておくことが、面接突破の鍵となります。
まとめ
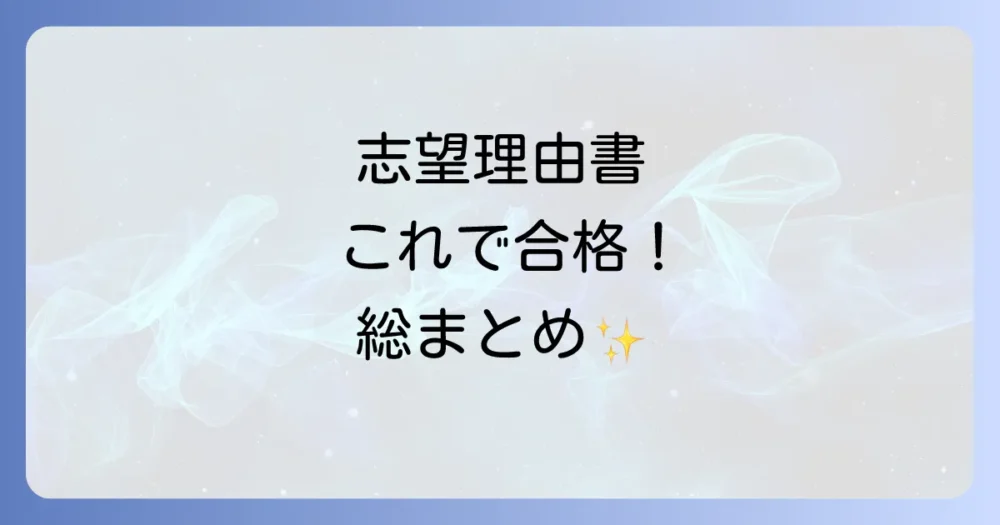
- 志望理由書は学習意欲と熱意を伝える最重要書類である。
- 面接の土台となるため、時間をかけて丁寧に作成する必要がある。
- 例文を参考にしつつ、自分の言葉でオリジナリティを出すことが大切。
- 基本構成は「結論→理由→学習計画→将来の展望」である。
- なぜ「この大学」でなければならないのかを明確にすることが重要。
- これまでの学びとこれからの学びを一貫性のあるストーリーで繋げる。
- 具体的なエピソードを盛り込み、独自性を出すことが差をつけるコツ。
- 抽象的な表現や受け身な姿勢は避けるべきNG例である。
- 大学の情報の丸写しは熱意の欠如と見なされる。
- 誤字脱字は致命的なミスに繋がりかねないため、入念に確認する。
- 文字数指定は9割以上埋めるのが望ましい。
- 手書きかパソコンかは指定がなければどちらでも良い。
- 完成後は必ず第三者に添削を依頼することが推奨される。
- 面接では志望理由書の内容が深掘りされるため、万全の準備が必要。
- 自分の想いを論理的かつ情熱的に伝えることが合格への鍵となる。
新着記事