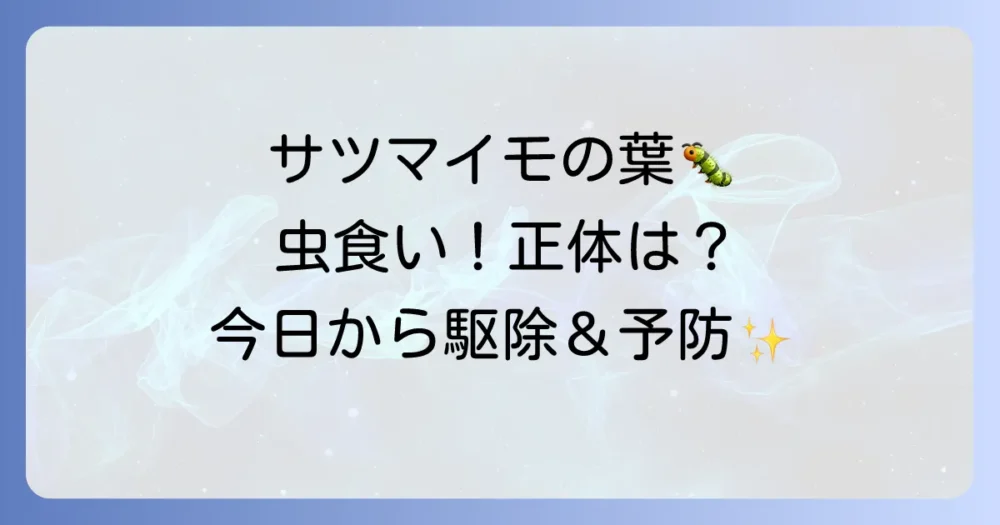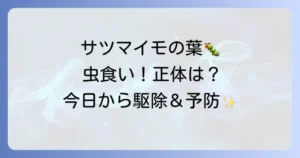大切に育てているサツマイモの葉に、いつの間にか穴が開いていたり、虫がついていたりして「この虫は何だろう?」「どうやって駆除すればいいの?」と悩んでいませんか?サツマイモの葉を食べる虫を放置すると、生育が悪くなり、収穫量が減ってしまうこともあります。でも、ご安心ください。本記事を読めば、サツマイモにつくやっかいな害虫の正体を突き止め、今日からすぐに実践できる対策がわかります。農薬を使わない方法も詳しく解説しているので、安心して栽培を楽しみたい方も必見です。
サツマイモの葉につく虫を放置するリスク
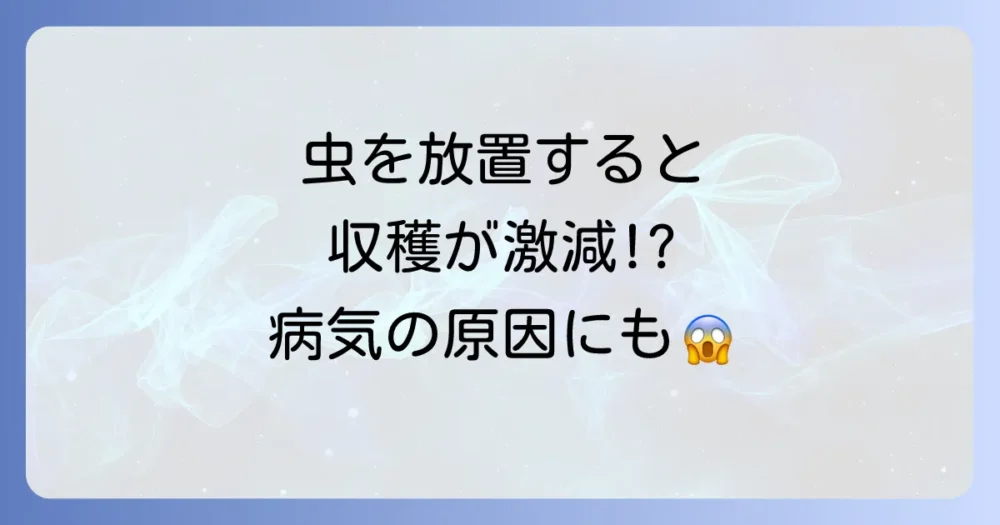
サツマイモの葉に虫がついても、「少しくらいなら大丈夫だろう」と見過ごしていませんか?しかし、その油断が後々の大きな被害につながる可能性があります。害虫を放置すると、サツマイモの生育に様々な悪影響が及ぶため、早期発見と迅速な対策が非常に重要です。
ここでは、害虫を放置した場合に起こりうる具体的なリスクについて解説します。
- 光合成の阻害による生育不良
- 収穫量の減少や品質の低下
- ウイルス病などの病気を媒介する
葉は、太陽の光を浴びて光合成を行い、サツマイモが大きく育つための栄養分を作り出す大切な器官です。その葉が虫に食べられてしまうと、光合成の効率が著しく低下し、芋が十分に大きく育たなくなってしまいます。特に、生育初期に被害を受けると、株全体の成長が止まってしまうことさえあるのです。
また、害虫は単に葉を食べるだけではありません。アブラムシのように、植物の汁を吸う過程でウイルス病を媒介する虫もいます。 病気に感染すると、葉が縮れたり、株全体が枯れてしまったりと、被害はさらに深刻化します。美味しいサツマイモをたくさん収穫するためにも、害虫対策は欠かせない作業なのです。
サツマイモの葉を食べる代表的な害虫と被害症状
「葉を食べている虫の正体がわからない…」そんな悩みを解決するために、ここではサツマイモの葉によくつく代表的な害虫を、被害の症状とともに紹介します。ご自身の畑の状況と見比べて、害虫を特定しましょう。
サツマイモの葉に被害を与える主な害虫は以下の通りです。
- ハスモンヨトウ・ヨトウムシ(夜盗虫)
- ナカジロシタバ
- エビガラスズメ
- アブラムシ類
- ハダニ類
- ヨツモンカメノコハムシ
- イモキバガ(イモコガ)
- コガネムシ類(成虫)
ハスモンヨトウ・ヨトウムシ(夜盗虫)
特徴:
ヨトウムシは「夜盗虫」という名前の通り、昼間は土の中に隠れ、夜になると活動を始める厄介な害虫です。 ハスモンヨトウもヨトウムシの一種で、非常に食欲旺盛なことで知られています。 若い幼虫は緑色や褐色で集団で行動し、葉の裏側から表皮を残して食べるため、葉が白っぽく見えるのが特徴です。 老齢幼虫になると体長4cmほどに成長し、色も黒っぽくなり、葉脈を残して葉全体を食べ尽くすほどの激しい食害をもたらします。
被害症状:
初期段階では、葉の裏側が白くカスリ状に食害されます。被害が進行すると、葉に大きな穴が開いたり、葉脈だけを残して網目のようになってしまったりします。 大発生すると、あっという間に畑全体の葉が食い尽くされることもあるため、早期の発見と駆除が重要です。
ナカジロシタバ
特徴:
ナカジロシタバは、サツマイモの葉を好んで食べる特殊な蛾の幼虫です。 体長は4cm程度で、淡い紫色に黄色の線が入っているのが特徴的なイモムシです。 若い幼虫は、まだ開いていない新しい葉の中に潜んで食害します。 8月下旬から9月中旬にかけて特に発生が多くなります。
被害症状:
新しい葉が食べられ、成長すると葉全体を食害します。摂食量が非常に多く、大発生すると短期間で葉が食べ尽くされ、茎だけが残るという悲惨な状態になることもあります。 収量や品質に直接的な影響が出るため、見つけ次第すぐに対処が必要です。
エビガラスズメ
特徴:
お尻に一本のツノがある、緑色または褐色の大きなイモムシがいたら、それはエビガラスズメの幼虫です。 スズメガの一種で、体長は9cmにも達します。 その大きな体に見合うように、食欲も非常に旺盛です。
被害症状:
被害は非常に分かりやすく、葉がものすごいスピードで食べられ、数日で株が丸裸にされてしまうこともあります。 体が大きいので見つけやすいですが、1匹いるだけでも被害は甚大です。見つけたらすぐに捕殺しましょう。
アブラムシ類
特徴:
体長1~4mm程度の小さな虫で、緑色や黒色など様々な種類がいます。 新芽や葉の裏にびっしりと群生し、植物の汁を吸って加害します。 繁殖力が非常に高く、あっという間に増殖します。
被害症状:
汁を吸われることで生育が阻害され、株が弱ってしまいます。 また、アブラムシの排泄物(甘露)が原因で、葉がベタベタになり、そこにカビが生えて黒くなる「すす病」を併発することがあります。 最も厄介なのは、モザイク病などのウイルス病を媒介することです。 病気にかかると治療法がないため、アブラムシを発生させない予防が重要になります。
ハダニ類
特徴:
体長0.5mm程度と非常に小さく、肉眼での確認が難しい害虫です。 主に葉の裏に寄生し、汁を吸います。乾燥した環境を好み、梅雨明けから夏場にかけて多発します。
被害症状:
葉の裏から汁を吸われるため、葉の表面に針で刺したような白い小さな斑点が無数に現れ、カスリ状になります。 被害が拡大すると、葉全体の色が悪くなって光合成ができなくなり、やがて枯れて落葉します。 密度が高くなると、葉にクモの巣のような細かい糸を張ることもあります。
ヨツモンカメノコハムシ
特徴:
体長7~9mmほどの、亀の甲羅のような形をした茶褐色の面白い見た目の虫です。 サツマイモなどヒルガオ科の植物を好んで食べます。 成虫も幼虫も葉を食害します。
被害症状:
葉に楕円形の穴をあけたり、網目状に食害したりします。 特に生育初期に被害を受けると、成長が著しく悪くなり、収穫に大きな影響が出ます。 見た目はユニークですが、れっきとした害虫なので注意が必要です。
イモキバガ(イモコガ)
特徴:
蛾の幼虫で、葉を巻いたり、二つに折りたたんでその中に潜んでいるのが特徴です。 長雨の年に多発する傾向があります。
被害症状:
幼虫は葉の内側から表皮を残して食べるため、食害された部分が白く透けたようになり、やがて褐色になって枯れてしまいます。 巻かれた葉を開くと、中に幼虫やフンが見つかります。 被害が広がると光合成ができなくなり、生育に影響を及ぼします。
コガネムシ類(成虫)
特徴:
緑色や銅色に光る、丸っこい甲虫です。多くの人が一度は目にしたことがあるでしょう。成虫は夜行性で、様々な植物の葉や花を食べます。
被害症状:
成虫は葉をギザギザに食害します。しかし、サツマイモ栽培で本当に恐ろしいのは幼虫の方です。成虫が土の中に産んだ卵からかえった幼虫が、土の中で芋を食べてしまい、収穫したサツマイモが穴だらけになってしまいます。 葉の被害を見つけたら、土の中の幼虫にも注意が必要です。
今すぐできる!サツマイモの害虫対策【駆除編】
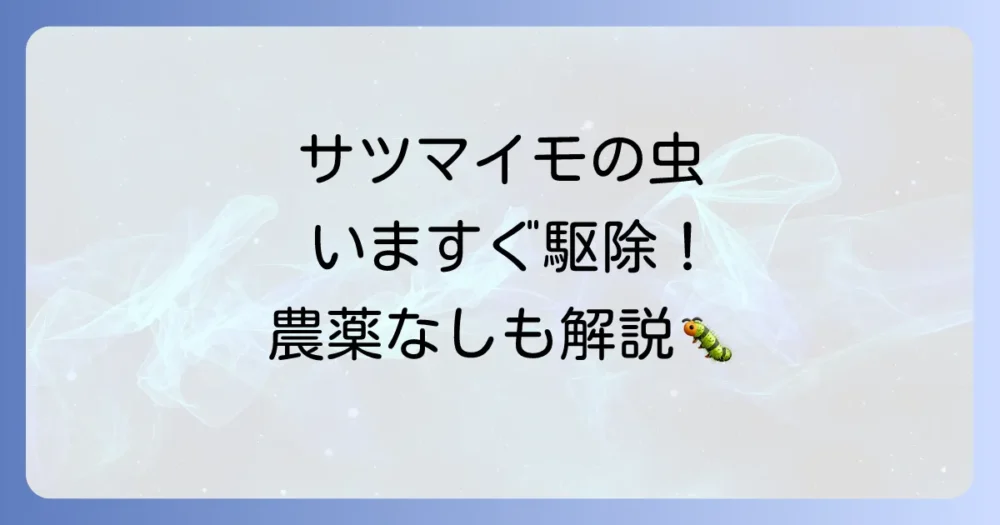
畑に害虫を見つけてしまったら、被害が広がる前に迅速に駆除することが大切です。ここでは、「農薬はあまり使いたくない」という方でも安心して試せる方法から、被害が深刻な場合に頼りになる農薬の使い方まで、具体的な駆除方法を解説します。
駆除方法は、発生している害虫の種類や被害の程度によって使い分けるのが効果的です。まずは、ご自身の状況に合った方法から試してみてください。
- 【農薬を使いたくない人向け】安心な駆除方法
- 【被害がひどい場合】農薬を使った駆除方法
【農薬を使いたくない人向け】安心な駆除方法
家庭菜園で少量栽培している場合や、できるだけ農薬を避けたい場合は、物理的な方法や自然由来のもので駆除を試みましょう。手間はかかりますが、環境にも優しく、安心してサツマイモを育てることができます。
手で捕まえて駆除する
ヨトウムシやエビガラスズメ、コガネムシの成虫など、目に見える大きな虫は、見つけ次第、手で捕まえて駆除するのが最も確実で即効性のある方法です。 虫が苦手な方は、割り箸やピンセットを使うと良いでしょう。ヨトウムシは夜行性なので、早朝や夜間に懐中電灯で照らしながら探すと見つけやすいです。 卵の塊を見つけた場合は、葉ごと切り取って処分しましょう。
牛乳や石鹸水のスプレー
アブラムシやハダニなど、小さくて数の多い虫にはスプレーが効果的です。牛乳を水で薄めずにスプレーし、乾かすことで膜を作り、虫を窒息させる方法があります。 また、水500mlに食器用洗剤を2~3滴混ぜた石鹸水も、虫の体を覆って呼吸を妨げる効果が期待できます。 ただし、これらのスプレーをかけた後は、植物への負担を減らすために水で洗い流すことを忘れないでください。
粘着テープで捕獲する
葉の裏にびっしりついたアブラムシには、粘着力の弱いマスキングテープやセロハンテープを貼り付けて、ペタペタと取り除く方法も有効です。 葉を傷つけないように、優しく行うのがコツです。広範囲に発生している場合は大変ですが、発生初期であれば手軽に試せる方法です。
【被害がひどい場合】農薬を使った駆除方法
害虫が大量発生してしまい、手作業での駆除が追いつかない場合は、農薬の使用も検討しましょう。正しく使えば、効率的に被害を食い止めることができます。
農薬選びのポイント
農薬を選ぶ際は、まず「サツマイモ」に登録があり、駆除したい「害虫名」が適用となっているかを必ず確認してください。 農薬には様々な種類があり、それぞれ効果のある害虫が異なります。 また、収穫までの使用日数や使用回数にも制限があるため、ラベルをよく読んで正しく使用することが重要です。
おすすめの農薬
サツマイモの害虫に幅広く使える農薬としては、以下のようなものがあります。
- GFオルトラン粒剤・水和剤: 浸透移行性があり、アブラムシやヨトウムシなどに効果があります。株元に撒く粒剤タイプと、水に溶かして散布する水和剤タイプがあります。
- ベニカXファインスプレー: 殺虫成分と殺菌成分が入っており、害虫と病気を同時に防除できるスプレータイプの農薬です。手軽に使えるので家庭菜園におすすめです。
- ディアナSC: ハスモンヨトウやナカジロシタバ、エビガラスズメなど、大型のイモムシ類に高い効果を発揮します。
どの農薬を使うか迷った場合は、ホームセンターの園芸担当者やJAの指導員に相談するのも良いでしょう。
農薬使用時の注意点
農薬を使用する際は、必ずマスクや手袋、保護メガネを着用し、風のない天気の良い日中に散布しましょう。定められた希釈倍率や使用回数を守り、周囲の作物や人にかからないように注意が必要です。 同じ系統の農薬を連続して使用すると、害虫に抵抗性がついて効きにくくなることがあるため、異なる系統の農薬をローテーションで使うのが効果的です。
虫を寄せ付けない!サツマイモの害虫対策【予防編】
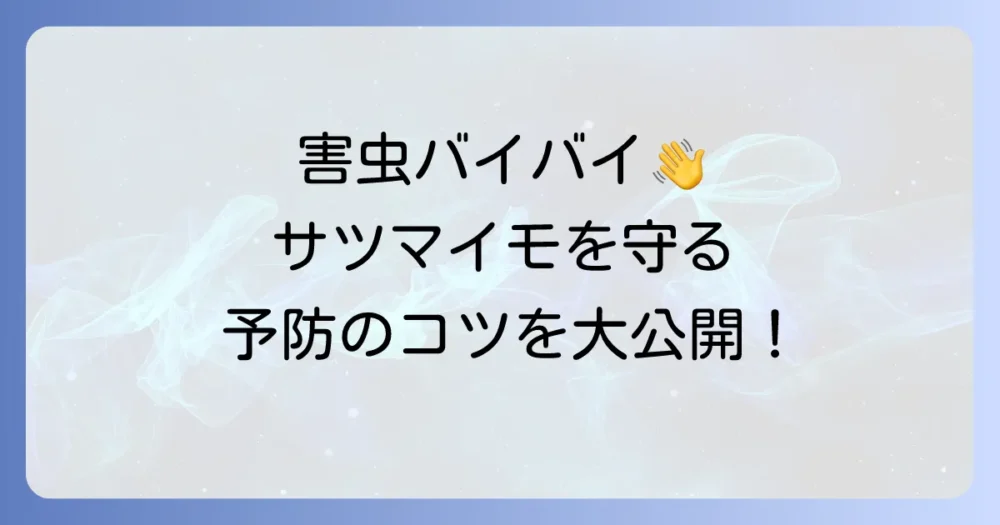
害虫対策で最も重要なのは、そもそも虫を発生させない「予防」です。植え付けの段階から収穫まで、ちょっとした工夫を積み重ねることで、害虫の被害を大幅に減らすことができます。ここでは、誰でも簡単に取り組める予防策を紹介します。
大切なサツマイモを害虫から守るために、以下の予防策をぜひ実践してみてください。
- 植え付け時からできる予防策
- 栽培管理でできる予防策
植え付け時からできる予防策
栽培を始める最初の段階での準備が、その後の害虫の発生を大きく左右します。苗選びから植え付けの工夫まで、スタートダッシュで害虫に強い畑を作りましょう。
無病の健全な苗を選ぶ
全ての基本は、病害虫に侵されていない健康な苗を選ぶことです。 葉の色が濃く、茎がしっかりとしていて、アブラムシなどが付着していないかよく確認してから購入しましょう。ウイルス病などは苗から持ち込まれることが多いため、苗選びは慎重に行う必要があります。
防虫ネットをかける
植え付け直後から防虫ネットでトンネルを作ることで、蛾やカメムシ、コガネムシなどの成虫が飛来して葉に卵を産み付けるのを物理的に防ぐことができます。 特に、害虫の活動が活発になる初夏から秋にかけては非常に効果的な方法です。ネットの目が細かいほど小さな虫の侵入も防げますが、風通しが悪くならないように注意しましょう。
コンパニオンプランツを植える
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いに良い影響を与え合う植物のことです。サツマイモの場合、赤シソやマメ科の植物(枝豆など)がおすすめです。 赤シソの独特の香りは、コガネムシなどの害虫を遠ざける効果があると言われています。 また、マメ科植物の根に共生する根粒菌は、空気中の窒素を土壌に供給してくれるため、サツマイモの生育を助ける効果も期待できます。
栽培管理でできる予防策
日々の畑の管理も、害虫予防には欠かせません。風通しや雑草の管理など、少しの気配りで害虫が住みにくい環境を作ることができます。
風通しを良くする
株間を適切にとり、葉が密集しすぎないように管理することで、畑全体の風通しを良くしましょう。湿気がこもるのを防ぎ、病害虫が発生しにくい環境を作ることができます。ハダニなどは乾燥を好みますが、多くの病気や害虫は多湿で風通しの悪い場所を好むため、適切な株間は基本中の基本です。
雑草をこまめに除去する
畑の周りの雑草は、害虫の隠れ家や繁殖場所になります。 特に、サツマイモと同じヒルガオ科の雑草は、共通の害虫の発生源となるため注意が必要です。こまめに草取りを行い、害虫が寄り付く場所をなくしましょう。
連作を避ける
同じ場所で毎年サツマイモを栽培する「連作」を行うと、土壌中の特定の病原菌やセンチュウなどの害虫が増えやすくなります。 可能であれば、3~4年はアブラナ科やイネ科など、異なる科の野菜を育てる「輪作」を心がけましょう。これにより、土壌のバランスが保たれ、病害虫の発生リスクを低減できます。
天敵を活かす
畑には、害虫を食べてくれるクモやカマキリ、テントウムシ、アリといった「天敵」もたくさんいます。 むやみに殺虫剤を使うと、これらの益虫まで殺してしまい、かえって害虫が増える原因になることも。天敵の働きを理解し、彼らが活動しやすい環境を整えることも、無農薬栽培における重要なポイントです。
よくある質問
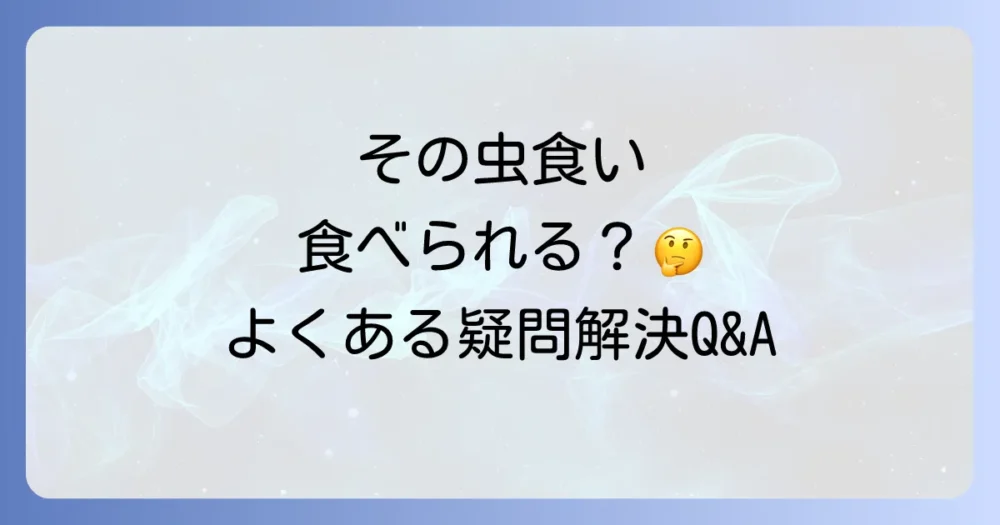
ここでは、サツマイモの害虫に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
虫食いの葉やサツマイモは食べられますか?
はい、食べられます。葉が多少虫に食われていても、芋の味や品質に直接影響することはほとんどありません。収穫したサツマイモに虫食いの穴が開いている場合も、その部分と周りを少し大きめに包丁で取り除けば、問題なく食べることができます。 虫食いは、農薬をあまり使っていない安全な証拠と捉えることもできますね。 ただし、腐っていたり、異臭がしたりする場合は食べるのをやめましょう。
サツマイモの葉に白い斑点ができています。これは何ですか?
葉の表面に、針で刺したような白い小さな斑点が無数にできている場合、それはハダニの被害である可能性が高いです。 ハダニは非常に小さく、葉の裏に寄生して汁を吸います。乾燥した環境で発生しやすいため、被害が広がる前に葉の裏に水をかける(葉水)などの対策が有効です。
サツマイモの葉が縮れている原因は何ですか?
葉が縮れたり、モザイク状になったりする原因としては、アブラムシが媒介するウイルス病(モザイク病など)が考えられます。 ウイルス病には治療薬がないため、感染した株は残念ながら抜き取って処分し、被害の拡大を防ぐ必要があります。予防として、原因となるアブラムシを早期に駆除することが最も重要です。
おすすめのコンパニオンプランツは何ですか?
サツマイモのコンパニオンプランツとして特におすすめなのは「赤シソ」と「枝豆(マメ科)」です。 赤シソの香りは害虫を遠ざける効果が期待でき、枝豆は土壌を豊かにしてくれます。 サツマイモの株間に植えることで、互いの生育を助け、病害虫のリスクを減らすことができます。
農薬はいつ撒くのが効果的ですか?
農薬を散布するタイミングは、害虫の発生初期が最も効果的です。 特にヨトウムシなどは、幼虫が小さいうち(若齢幼虫)の方が薬剤が効きやすいため、こまめに畑を観察し、被害を見つけたらすぐに対応することが重要です。 また、散布は風のない晴れた日の午前中に行うのが一般的です。雨が降ると薬剤が流れてしまうため、天気予報を確認してから散布しましょう。
まとめ
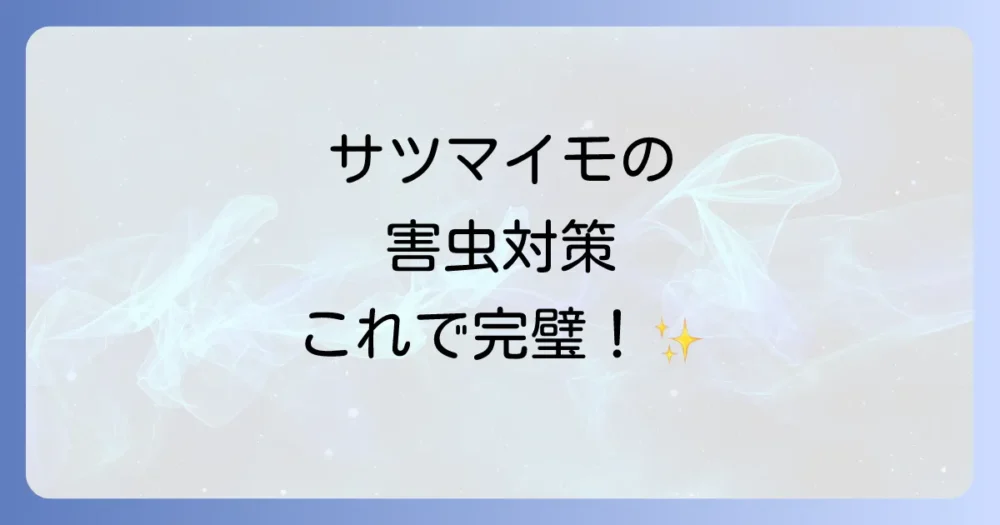
- サツマイモの葉の虫は放置すると生育不良や病気の原因になる。
- 代表的な害虫はヨトウムシ、ナカジロシタバ、アブラムシなど。
- 害虫の特定には、葉の被害状況(穴、白い斑点など)を観察する。
- 大きな虫は手で捕殺するのが確実で早い方法である。
- アブラムシには牛乳や石鹸水のスプレーが有効。
- 被害が深刻な場合は、サツマイモに登録のある農薬を正しく使う。
- 予防の基本は、健康な苗を選び、防虫ネットを活用すること。
- コンパニオンプランツ(赤シソ、枝豆)は害虫予防に効果的。
- 風通しを良くし、雑草をこまめに除去することが大切。
- 連作を避けることで、土壌伝染性の病害虫リスクを減らせる。
- クモやカマキリなどの天敵は、害虫を減らしてくれる味方。
- 虫食いの葉や芋も、被害部分を取り除けば食べられる。
- 葉の白い斑点はハダニ、葉の縮れはウイルス病の可能性が高い。
- 農薬散布は、害虫の発生初期に行うのが最も効果的。
- 害虫対策は、早期発見と迅速な対応が成功の鍵となる。