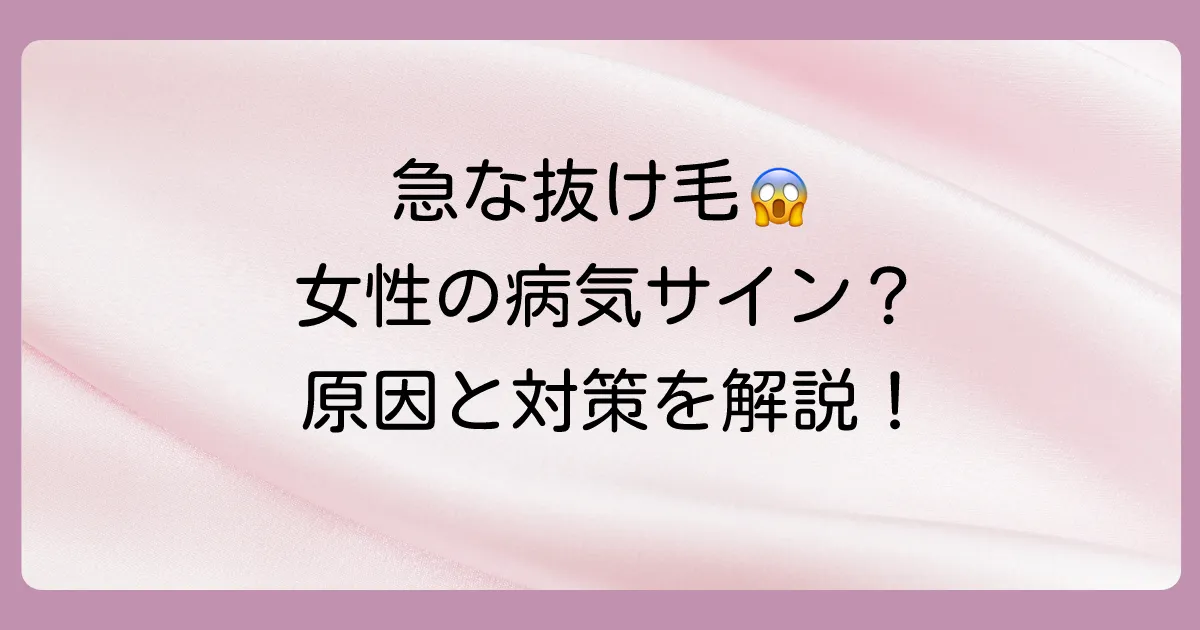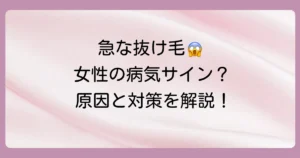「最近、シャンプーのたびに排水溝に溜まる髪の毛の量が増えた…」「朝起きると、枕に抜け毛がたくさん…」そんな経験はありませんか?いつもと違う抜け毛の量に、何か病気なのではと不安に感じている女性は少なくありません。髪は女性にとって大切なものだからこそ、その悩みは深刻です。
本記事では、急に髪の毛が抜ける原因として考えられる女性特有の病気や、病気以外の原因について詳しく解説します。さらに、何科を受診すればよいのか、自分でできる対策まで、あなたの不安を解消するための情報を網羅しています。この記事を読めば、きっとあなたの悩みを解決する糸口が見つかるはずです。
女性が急に髪の毛が抜ける場合に考えられる病気とは?
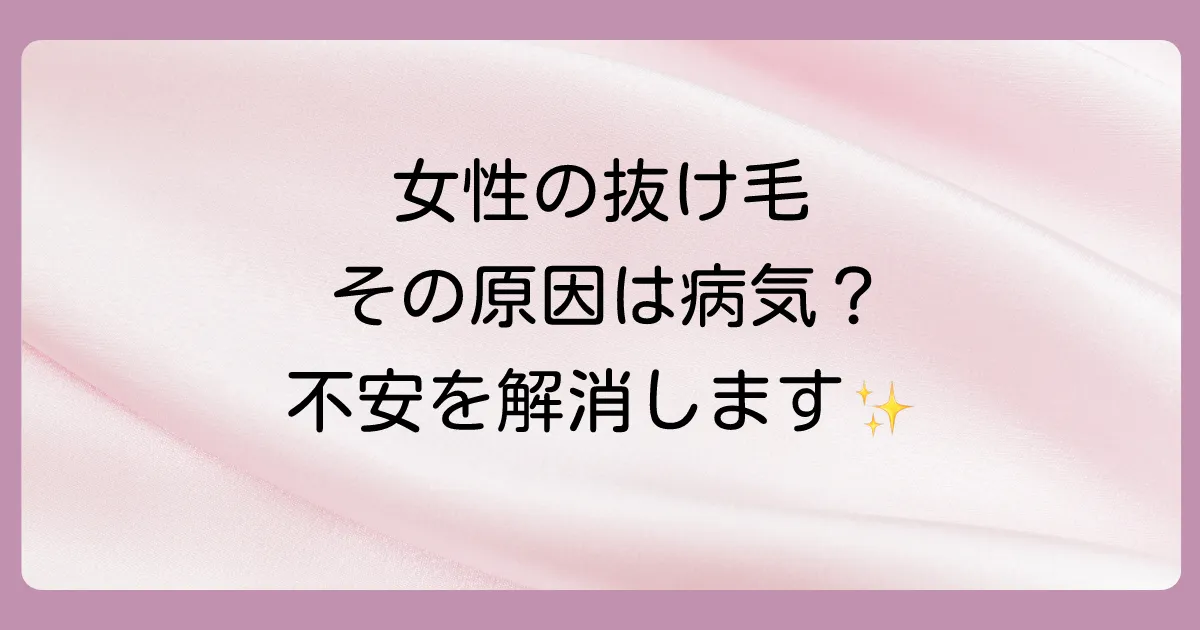
ある日突然、ごっそりと髪の毛が抜ける…。そんな経験をしたら、誰でも「何か重い病気なのでは?」と不安になりますよね。女性の急な抜け毛は、単なるヘアサイクルの乱れだけでなく、体に潜む病気のサインである可能性も考えられます。ここでは、女性の急な抜け毛の原因となりうる代表的な病気について解説します。
本章で解説する主な病気は以下の通りです。
- びまん性脱毛症
- 円形脱毛症
- 甲状腺機能の異常
- 膠原病
- 鉄欠乏性貧血
- 婦人科系の病気
- 薬剤性脱毛症
これらの病気は、それぞれ特徴的な症状や原因があります。ご自身の症状と照らし合わせながら、読み進めてみてください。早期発見・早期治療が、健やかな髪を取り戻すための第一歩です。
びまん性脱毛症
びまん性脱毛症は、女性の薄毛で最も多いとされる症状の一つです。 特定の部位が薄くなるのではなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなり、ボリュームが失われていくのが特徴です。 そのため、初期段階では変化に気づきにくく、「最近分け目が目立つようになった」「髪にハリやコシがなくなった」と感じることから始まることが多いようです。
主な原因は、加齢やホルモンバランスの乱れ、ストレス、生活習慣の乱れなどが複雑に絡み合っていると考えられています。 特に女性は、妊娠・出産や更年期など、生涯を通じてホルモンバランスが大きく変動するため、びまん性脱毛症を発症しやすいと言われています。 進行すると地肌が透けて見えるようになり、精神的なストレスを抱える方も少なくありません。 思い当たる症状があれば、早めに専門医に相談することが大切です。
円形脱毛症
円形脱毛症は、突然、円形や楕円形に髪の毛が抜けてしまう病気です。 一般的に「10円ハゲ」として知られていますが、1箇所だけでなく複数箇所にできたり、頭部全体に広がったり、重症の場合は眉毛やまつ毛など体毛にまで症状が及ぶこともあります。 年齢や性別に関わらず誰にでも発症する可能性がありますが、女性特有の原因も指摘されています。
主な原因として、自己免疫疾患が有力視されています。 本来、体を守るはずの免疫機能が異常をきたし、自身の毛根を攻撃してしまうことで脱毛が起こります。 その他にも、出産に伴うホルモンバランスの急激な変化、アトピー素因、そして精神的なストレスなどが引き金になることがあると考えられています。 以前はストレスが主な原因と思われがちでしたが、現在では様々な要因が複雑に絡み合って発症すると理解されています。
甲状腺機能の異常
首の前側にある甲状腺は、体の新陳代謝を活発にする「甲状腺ホルモン」を分泌しています。このホルモンのバランスが崩れる病気も、急な抜け毛の原因となることがあります。 甲状腺の病気は女性に多く見られるのが特徴です。
具体的には、以下の2つの病気が挙げられます。
- 甲状腺機能低下症(橋本病など): 甲状腺ホルモンの分泌が不足する病気です。 代謝が低下するため、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなり、抜け毛が増えることがあります。 髪全体が薄くなる「びまん性脱毛」や、髪のパサつき、眉毛の外側が薄くなるなどの症状が見られることもあります。
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病など): 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。 新陳代謝が活発になりすぎることで、ヘアサイクルが乱れ、成長期の髪が早く抜け落ちてしまうことがあります。
抜け毛の他に、疲れやすさ、体重の変化、むくみ、動悸などの全身症状を伴う場合は、内科や内分泌科の受診をおすすめします。
膠原病
膠原病(こうげんびょう)は、本来ウイルスや細菌などから体を守る免疫システムが、誤って自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の総称です。 この病気は全身の様々な臓器に影響を及ぼす可能性があり、皮膚や髪の毛も例外ではありません。
膠原病の中でも、特に全身性エリテマトーデス(SLE)などで脱毛の症状が見られることがあります。 免疫の異常によって毛根が攻撃されることで、髪の毛が抜けやすくなります。 脱毛の仕方は、特定の場所だけが抜けるのではなく、頭部全体が薄くなる「びまん性脱毛」や、切れ毛が増えるといった特徴があります。 また、頭皮に赤みや炎症が見られることもあります。
抜け毛の他に、原因不明の発熱、関節の痛み、顔や手足の発疹などの症状が見られる場合は、膠原病の可能性も考えられるため、リウマチ科や膠原病内科などの専門医に相談することが重要です。
鉄欠乏性貧血
「疲れやすい」「めまいがする」といった症状で知られる貧血ですが、実は髪の毛にも大きな影響を与えます。特に女性は月経や妊娠、過度なダイエットなどで鉄分が不足しやすく、「鉄欠乏性貧血」になりやすい傾向があります。
髪の毛の主成分はタンパク質ですが、その成長には酸素や栄養素が不可欠です。鉄は、血液中で酸素を運ぶヘモグロビンの重要な構成成分。 鉄分が不足すると、ヘモグロビンが十分に作られなくなり、頭皮の毛母細胞に十分な酸素が届かなくなってしまいます。 これにより、髪の毛が細くなったり、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増えたりするのです。
見た目には貧血の症状がなくても、体内の貯蔵鉄(フェリチン)が不足している「かくれ貧血」の状態でも、髪への影響は現れ始めます。 抜け毛だけでなく、爪がもろくなったり、スプーンのように反り返ったりするといった症状も鉄欠乏のサインです。 食生活の見直しや、必要であれば内科での相談をおすすめします。
婦人科系の病気
女性ホルモンのバランスは、髪の健康と密接に関わっています。そのため、子宮や卵巣など、女性特有の臓器の病気が抜け毛の原因となることがあります。
例えば、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、卵巣で男性ホルモンが多く作られてしまう病気で、月経不順やにきびなどと共に、男性型脱毛症(AGA)に似た薄毛の症状が現れることがあります。また、子宮筋腫や子宮内膜症などの治療でホルモン剤を使用した場合、その副作用として一時的に抜け毛が増えることも考えられます。
さらに、更年期になると女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まることで、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりします。 これは「女性男性型脱毛症(FAGA/FPHL)」とも呼ばれ、頭頂部や分け目を中心に薄毛が進行するのが特徴です。
抜け毛に加えて、月経不順や不正出血、下腹部痛などの症状がある場合は、婦人科を受診して相談してみましょう。
薬剤性脱毛症
特定の薬を服用したことが原因で、髪の毛が抜けてしまうことを「薬剤性脱毛症」と呼びます。 最もよく知られているのは抗がん剤による脱毛ですが、それ以外にも身近な薬が原因となる可能性があります。
原因となりうる薬剤は多岐にわたりますが、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 免疫抑制薬
- 高血圧の治療薬
- 脂質異常症(高コレステロール血症)の治療薬
- 抗うつ薬
- ホルモン剤
薬を飲み始めてから数週間から数ヶ月後に抜け毛が始まることが多いとされています。 脱毛の程度は、薬の種類や量、個人の体質によって様々です。原因となっている薬の服用を中止すれば、多くの場合、髪の毛は再び生えてきますが、自己判断で薬をやめるのは非常に危険です。 新しい薬を飲み始めてから抜け毛が気になり始めた場合は、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。
病気以外で考えられる急な抜け毛の原因
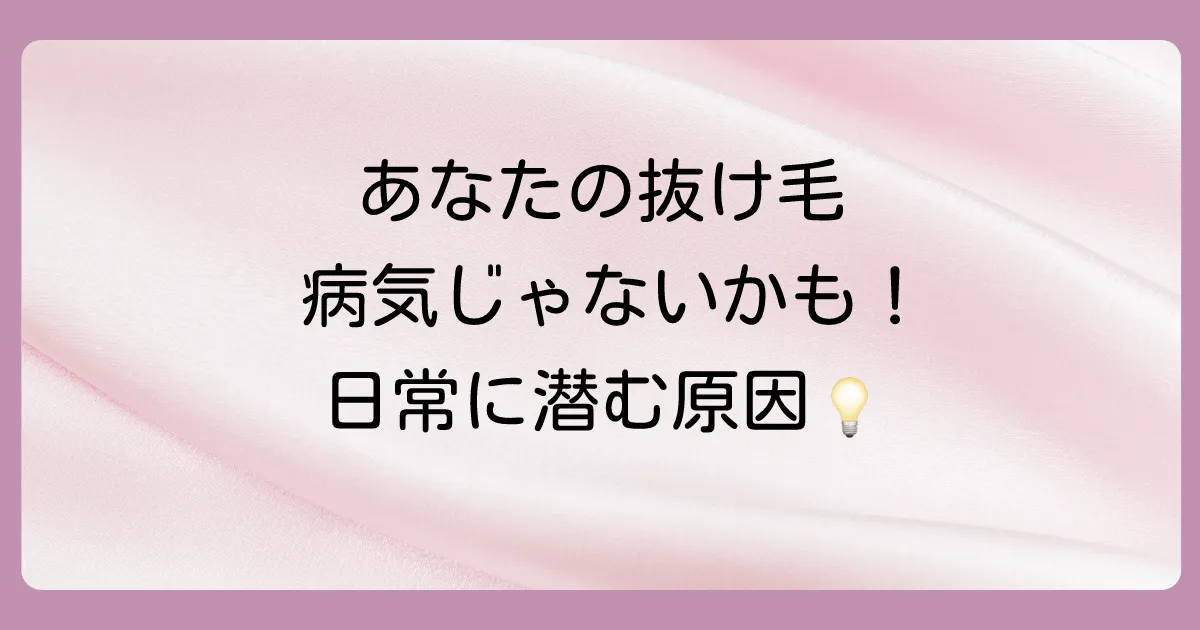
急な抜け毛は、必ずしも病気が原因とは限りません。私たちの髪は非常にデリケートで、日々の生活習慣や精神的な状態に大きく影響されます。ここでは、病気以外で考えられる急な抜け毛の主な原因について解説します。心当たりがないか、ご自身の生活を振り返ってみましょう。
本章で解説する主な原因は以下の通りです。
- 過度なストレス
- 生活習慣の乱れ
- 過度なダイエット
- 間違ったヘアケア
- 出産・産後
これらの要因は、一つだけでなく複数が絡み合って抜け毛を引き起こしていることも少なくありません。原因を知ることが、改善への第一歩です。
過度なストレス
「ストレスで髪が抜ける」とよく言われますが、これは医学的にも根拠のある話です。 強いストレスを感じると、私たちの体は緊張状態になり、自律神経のバランスが乱れてしまいます。 自律神経のうち、体を興奮させる働きを持つ交感神経が優位になると、血管が収縮し、血行が悪化します。
頭皮の血行が悪くなると、髪の毛を育てる毛母細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなり、健康な髪の成長が妨げられてしまいます。その結果、髪が細くなったり、成長しきる前に抜けてしまったりするのです。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにも繋がります。 髪の成長を促す女性ホルモンの分泌が減少し、抜け毛を引き起こす一因となることもあります。 仕事や人間関係、家庭環境の変化など、大きなストレスを感じた後に抜け毛が増えたと感じる場合は、ストレスが原因である可能性が高いでしょう。
生活習慣の乱れ
健やかな髪を育むためには、規則正しい生活習慣が欠かせません。特に「睡眠」と「食事」は、髪の健康に直接的な影響を与えます。
睡眠不足は、髪の成長を妨げる大きな要因です。髪の毛は、私たちが眠っている間に分泌される成長ホルモンによって成長が促進されます。睡眠時間が不足したり、眠りの質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長サイクルが乱れて抜け毛に繋がります。
また、食生活の乱れも深刻な影響を及ぼします。 ファストフードやインスタント食品に偏った食事、欠食などは、髪の毛の主成分であるタンパク質や、その合成を助けるビタミン、ミネラルなどの栄養素の不足を招きます。特に、髪の健康に不可欠な亜鉛などが不足すると、髪が弱くなり、抜けやすくなってしまいます。 バランスの取れた食事と十分な睡眠は、美しく健康な髪を保つための基本中の基本と言えるでしょう。
過度なダイエット
美しい体型を目指すためのダイエットも、やり方を間違えると髪に大きなダメージを与えてしまいます。 特に、極端な食事制限を伴う過度なダイエットは、急な抜け毛の直接的な原因となり得ます。
食事量を急激に減らすと、体は生命維持に必要なエネルギーを優先的に確保しようとします。そのため、髪の毛のような生命維持に直接関わらない部分への栄養供給は後回しにされてしまいます。髪の主成分であるタンパク質はもちろん、ビタミンやミネラルといった髪の成長に不可欠な栄養素が全体的に不足し、髪が作られにくくなったり、細く弱い髪しか生えなくなったりするのです。
その結果、髪全体のボリュームが失われ、びまん性の脱毛につながることがあります。 健康的に痩せるためには、バランスの取れた食事を基本とし、適度な運動を取り入れることが大切です。髪のためにも、無理なダイエットは避けましょう。
間違ったヘアケア
良かれと思って行っている日々のヘアケアが、実は頭皮や髪に負担をかけ、抜け毛の原因になっていることがあります。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったり、爪を立ててゴシゴシと力強く洗ったりすると、頭皮を守るために必要な皮脂まで奪ってしまい、頭皮を乾燥させてしまいます。乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、かゆみやフケ、炎症を引き起こし、抜け毛に繋がりやすくなります。
また、ポニーテールやお団子など、毎日同じ髪型で強く髪を引っ張ることも「牽引性(けんいんせい)脱毛症」の原因となります。 長時間にわたって毛根に負担がかかり続けることで、その部分の血行が悪くなり、髪が抜けやすくなってしまうのです。特に、生え際や分け目の部分に症状が出やすいのが特徴です。
その他、カラーリングやパーマの頻度が高すぎると、薬剤が頭皮にダメージを与え、抜け毛を誘発することもあります。 心当たりのある方は、一度ヘアケアの方法を見直してみることをおすすめします。
出産・産後
出産を経験した多くの女性が、産後に抜け毛が急増する「分娩後脱毛症(産後脱毛症)」を経験します。 これは病気ではなく、女性ホルモンの急激な変化によって起こる一時的な生理現象です。
妊娠中は、女性ホルモン(特にエストロゲンやプロゲステロン)の分泌量が非常に高くなります。 これらのホルモンには、髪の毛の成長期を維持する働きがあるため、妊娠中は本来抜けるはずの髪が抜けにくくなり、毛量が増えたように感じることがあります。
しかし、出産を終えると、これらの女性ホルモンの分泌量は一気に通常レベルまで減少します。 すると、成長期を維持されていた髪の毛が一斉に休止期に入り、産後2〜3ヶ月頃からごっそりと抜け始めるのです。
この抜け毛は、通常、産後半年から1年ほどで自然に落ち着きます。 しかし、慣れない育児によるストレスや睡眠不足、栄養不足が重なると、回復が遅れることもあります。 一時的なものだと理解し、あまり心配しすぎずに栄養バランスの取れた食事や休息を心がけることが大切です。
急に髪の毛が抜けたら何科を受診すべき?
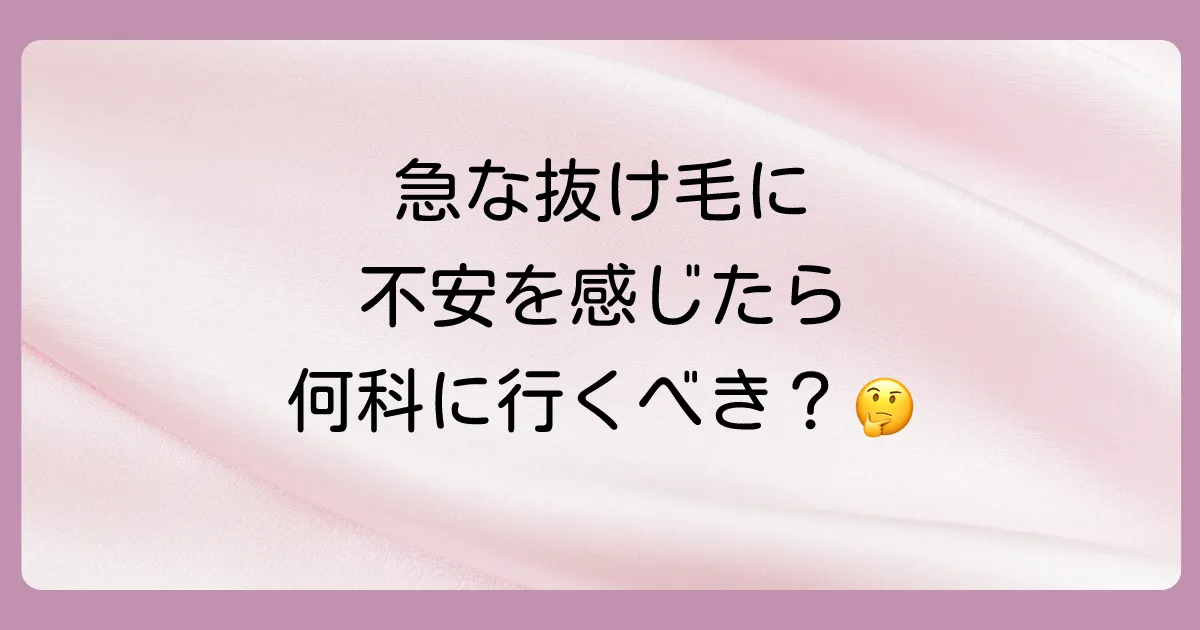
急な抜け毛に気づいたとき、「病院に行くべきか、行くなら何科がいいのか」と迷う方は多いでしょう。原因によって適切な診療科は異なります。ここでは、症状に応じた受診先の目安をご紹介します。自己判断で放置せず、専門家のアドバイスを受けることが解決への近道です。
受診を検討すべき主な診療科は以下の通りです。
- 皮膚科
- 女性専門の薄毛クリニック
- 内科・婦人科など
それぞれの診療科の特徴を理解し、ご自身の症状に最も適した場所を選びましょう。
まずは「皮膚科」へ相談
抜け毛や薄毛の悩みで、まず最初に相談するべき診療科は「皮膚科」です。 髪の毛は皮膚の一部であり、頭皮のトラブルが抜け毛に直結しているケースも少なくありません。
皮膚科では、円形脱毛症や、フケ・かゆみを伴う脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎など、頭皮の病気が原因の脱毛症の診断と治療を行います。 保険適用で治療を受けられる場合が多いのも特徴です。
また、問診や視診、血液検査などを通じて、抜け毛の原因が皮膚疾患によるものか、あるいは内科的な病気やホルモンバランスの乱れなど、他の要因が考えられるかを総合的に判断してくれます。もし、より専門的な治療が必要だと判断された場合は、適切な専門クリニックや他の診療科を紹介してもらえることもあります。
何が原因かわからず、どこに相談すればよいか迷ったら、まずは身近な皮膚科を受診するのが良いでしょう。
より専門的な治療なら「女性専門の薄毛クリニック」
「びまん性脱毛症」や「女性男性型脱毛症(FAGA)」など、より専門的で多角的なアプローチが必要な薄毛の悩みには、「女性専門の薄毛クリニック」が適しています。
これらのクリニックは、女性の薄毛治療に特化しているため、豊富な知識と治療実績を持っています。 一般的な皮膚科では行われていないような、ミノキシジルやスピロノラクトンといった内服薬・外用薬の処方、頭皮に直接有効成分を注入するメソセラピーなど、幅広い治療の選択肢があるのが最大の強みです。
また、プライバシーに配慮された空間で、女性カウンセラーによる丁寧なカウンセリングを受けられる場合が多く、デリケートな髪の悩みを安心して相談できる環境が整っています。治療は自由診療となるため費用はかかりますが、本気で薄毛を改善したい、より効果的な治療を受けたいと考えている方には、心強い選択肢となるでしょう。
全身の不調も感じるなら「内科」や「婦人科」も
抜け毛だけでなく、体に他の不調も感じている場合は、その症状に合わせて「内科」や「婦人科」の受診も検討しましょう。
例えば、疲れやすさ、急な体重の増減、むくみ、動悸といった症状が伴う場合は、甲状腺機能の異常が隠れている可能性があります。 この場合は「内科」または「内分泌内科」を受診することで、血液検査などにより原因を特定できます。
また、めまいや立ちくらみ、息切れがひどい場合は、鉄欠乏性貧血が原因かもしれません。これも「内科」で相談できます。
月経不順や不正出血、更年期のような症状と共に抜け毛が増えている場合は、ホルモンバランスの乱れが原因である可能性が高いため、「婦人科」への相談が適切です。
これらの病気が原因の場合、まずは原因となっている病気の治療を優先することが、抜け毛の改善に繋がります。
今日からできる!抜け毛を予防・改善するためのセルフケア
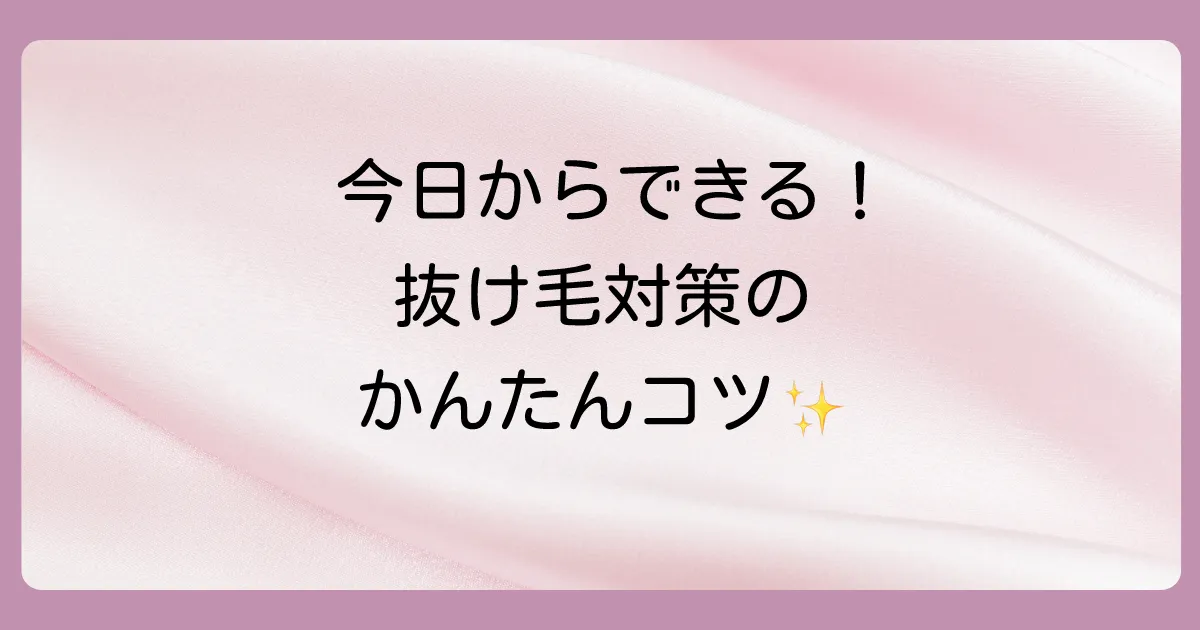
病気が原因の抜け毛は専門的な治療が必要ですが、日々の生活習慣を見直すことも、健やかな髪を育むためには非常に重要です。ここでは、今日からすぐに始められる、抜け毛の予防・改善に役立つセルフケアの方法をご紹介します。できることから少しずつ取り入れて、髪と頭皮に良い環境を整えていきましょう。
本章で紹介するセルフケアは以下の通りです。
- 栄養バランスの取れた食生活
- 質の良い睡眠を心がける
- ストレスを上手に発散する
- 正しいヘアケアを実践する
- 頭皮マッサージを取り入れる
これらの積み重ねが、未来の美しい髪へと繋がります。
栄養バランスの取れた食生活
美しい髪は、体の中から作られます。そのため、毎日の食事が非常に重要です。 特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食材をバランス良く摂ることを心がけましょう。
特に意識して摂取したい栄養素は以下の通りです。
- タンパク質: 髪の主成分であるケラチンの材料。肉、魚、卵、大豆製品などに豊富です。
- 亜鉛: タンパク質を髪の毛に変える働きを助けるミネラル。牡蠣、レバー、牛肉などに多く含まれます。不足すると髪が作られにくくなります。
- 鉄分: 血液中の酸素を運び、頭皮に栄養を届けるために不可欠。レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじきなどから摂取できます。
- ビタミン類: 特にビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、ビタミンEは血行を促進します。緑黄色野菜や果物、ナッツ類などを積極的に摂りましょう。
- 大豆イソフラボン: 女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをし、ホルモンバランスを整える効果が期待できます。豆腐、納豆、豆乳などの大豆製品に含まれています。
無理なダイエットは避け、これらの栄養素を意識したバランスの良い食事を1日3食しっかり摂ることが、抜け毛予防の基本です。
質の良い睡眠を心がける
睡眠は、単に体を休めるだけでなく、髪を育て、日中のダメージを修復するための大切な時間です。 私たちの体では、眠っている間に「成長ホルモン」が分泌されます。この成長ホルモンは、細胞の修復や新陳代謝を促す働きがあり、髪の毛を太く健康に育てるためにも不可欠です。
特に、成長ホルモンが多く分泌されるのは、入眠後すぐの深い眠り(ノンレム睡眠)の時と言われています。そのため、単に長く眠るだけでなく、「質の良い睡眠」をとることが重要になります。
質の良い睡眠をとるためのコツは以下の通りです。
- 毎日なるべく同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつける。
- 寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを避ける。
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスする。
- カフェインやアルコールの摂取は寝る数時間前から控える。
- 自分に合った寝具(枕やマットレス)を選ぶ。
十分な睡眠時間を確保し、眠りの質を高めることで、髪の成長を最大限にサポートしましょう。
ストレスを上手に発散する
現代社会でストレスを完全になくすことは難しいですが、溜め込まずに上手に発散する方法を見つけることが、髪の健康を守る上で非常に重要です。 ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を招くため、抜け毛の大きな原因となります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活にうまく取り入れましょう。以下に例を挙げます。
- 適度な運動: ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、血行を促進し、気分をリフレッシュさせる効果があります。
- 趣味に没頭する時間を作る: 読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ガーデニングなど、好きなことに集中する時間は心を落ち着かせます。
- リラックスできる時間を持つ: アロマテラピーを楽しんだり、ハーブティーを飲んだり、ゆっくりお風呂に浸かったりするのも良いでしょう。
- 親しい人と話す: 友人や家族に悩みを聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
「頑張りすぎない」「完璧を目指さない」ことも大切です。心と体の緊張をほぐし、リラックスできる時間を持つことを意識してみてください。
正しいヘアケアを実践する
毎日行うシャンプーやブラッシングも、方法が間違っていると頭皮や髪にダメージを与え、抜け毛の原因になります。 この機会に、ご自身のヘアケア方法を見直してみましょう。
【正しいシャンプーの方法】
- ブラッシング: シャンプー前に髪のもつれを優しくとき、ホコリや汚れを浮かせる。
- 予洗い: 38℃程度のぬるま湯で、髪と頭皮を1〜2分かけてしっかりとすすぐ。これだけで汚れの7割は落ちると言われています。
- シャンプー: シャンプーを手のひらでよく泡立て、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪を立てるのは厳禁です。
- すすぎ: シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧にすすぐ。特に生え際や襟足は残りやすいので注意。
- ドライ: タオルで優しく水分を拭き取った後、ドライヤーで根元から乾かす。頭皮から20cmほど離し、同じ場所に熱が集中しないように動かしながら乾かすのがコツです。
また、自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選ぶことも大切です。 乾燥肌の人は保湿成分配合のもの、脂性肌の人はさっぱりとした洗い上がりのものなど、適切な製品を選びましょう。
頭皮マッサージを取り入れる
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに効果的なセルフケアです。 頭皮の血流が良くなることで、髪の毛を育てる毛母細胞に栄養が届きやすくなり、健康な髪の成長をサポートします。
シャンプーのついでや、お風呂上がりのリラックスタイムなど、毎日の習慣に取り入れてみましょう。
【簡単な頭皮マッサージの方法】
- 両手の指の腹を使い、生え際から頭頂部に向かって、円を描くように優しく揉みほぐします。
- 耳の上あたりに指を置き、同じように頭頂部に向かって引き上げるようにマッサージします。
- 後頭部の襟足あたりから頭頂部に向かっても同様に行います。
- 最後に、頭頂部にある「百会(ひゃくえ)」というツボを、気持ちいいと感じる強さで数秒間押します。
力を入れすぎず、指の腹で優しく行うのがポイントです。 爪を立てて頭皮を傷つけないように注意してください。リラックス効果も期待できるので、一日の終わりにぜひ試してみてください。
よくある質問
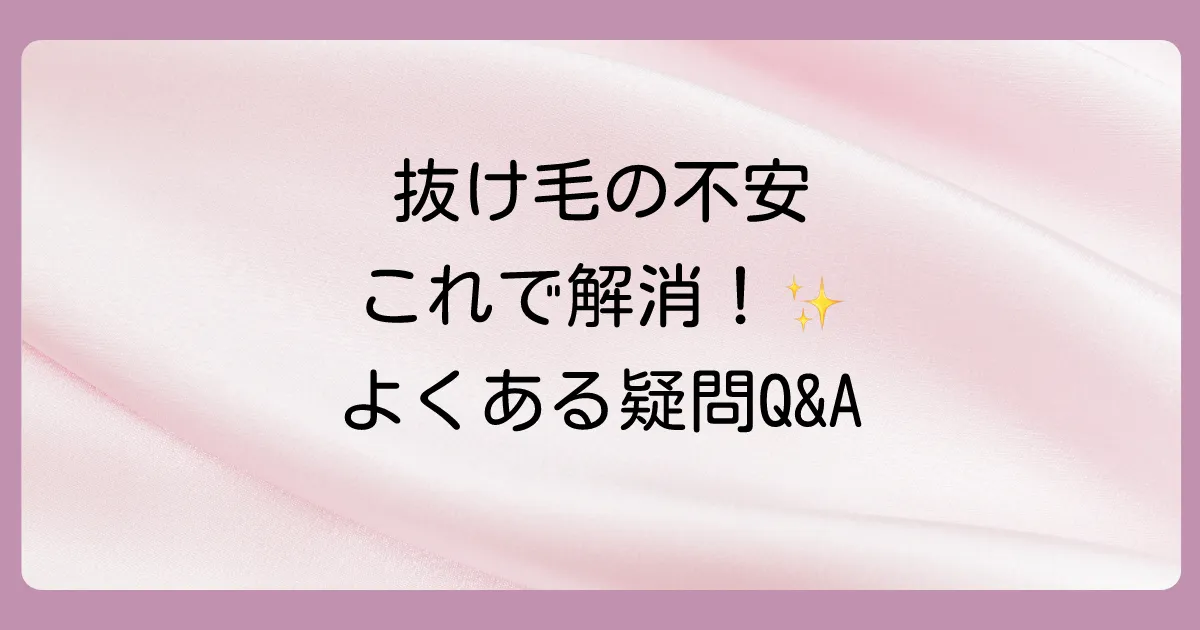
急な抜け毛に関して、多くの方が抱える疑問や不安にお答えします。
Q1: 抜け毛が何本くらいから「異常」と言えますか?
A1: 健康な人でも、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜けています。 これはヘアサイクルによる自然な現象です。しかし、シャンプーやブラッシングの際に明らかに以前より量が増えたり、1日に200本以上抜けるような状態が続いたりする場合は、注意が必要なサインと言えるでしょう。 枕元の抜け毛の量や、部屋に落ちている髪の毛が目に見えて増えたと感じたら、一度専門医に相談することをおすすめします。
Q2: 20代や30代の若い女性でも、急に髪が抜けることはありますか?
A2: はい、あります。若い世代の女性でも、過度なダイエットによる栄養不足、就職や転職、人間関係などの強いストレス、睡眠不足といった生活習慣の乱れが原因で、急に抜け毛が増えることがあります。 また、円形脱毛症は年齢に関わらず発症しますし、甲状腺の病気や鉄欠乏性貧血なども若い女性に見られることがあります。 年齢が若いからと安心せず、気になる症状があれば早めに対処することが大切です。
Q3: 新型コロナウイルスの後遺症で髪が抜けることはありますか?
A3: はい、新型コロナウイルス感染症の後遺症の一つとして、脱毛が報告されています。感染による高熱や体への強いストレス、免疫反応などが原因で、ヘアサイクルが乱れ「休止期脱毛」という状態になるためと考えられています。 通常、感染から2〜3ヶ月後に抜け毛が始まり、数ヶ月で自然に回復することが多いですが、症状が長引く場合や不安な場合は、皮膚科などの医療機関に相談してください。
Q4: 抜け毛予防に効果的なサプリメントはありますか?
A4: 髪の健康をサポートするサプリメントはたくさんありますが、まずはバランスの取れた食事が基本です。その上で、食事だけでは不足しがちな栄養素を補う目的で利用するのが良いでしょう。具体的には、髪の主成分となるタンパク質(アミノ酸)、その合成を助ける亜鉛、血行を促進するビタミンE、頭皮環境を整えるビタミンB群、そして女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンなどが挙げられます。ただし、サプリメントはあくまで補助的なものです。過剰摂取は体に害を及ぼす可能性もあるため、摂取する場合は推奨量を守りましょう。
Q5: 治療をすれば、抜けた髪はまた生えてきますか?
A5: 原因によって異なりますが、多くの場合、適切な治療やケアを行えば、髪は再び生えてくる可能性があります。例えば、鉄欠乏性貧血や甲状腺疾患が原因であれば、その病気の治療をすることで抜け毛は改善します。 円形脱毛症も、多くは自然に、あるいは治療によって回復します。 FAGA(女性男性型脱毛症)の場合も、早期に治療を開始すれば、進行を抑え、発毛を促すことが期待できます。大切なのは、自己判断で諦めずに、できるだけ早く専門医に相談し、原因を特定して適切な対策を始めることです。
まとめ
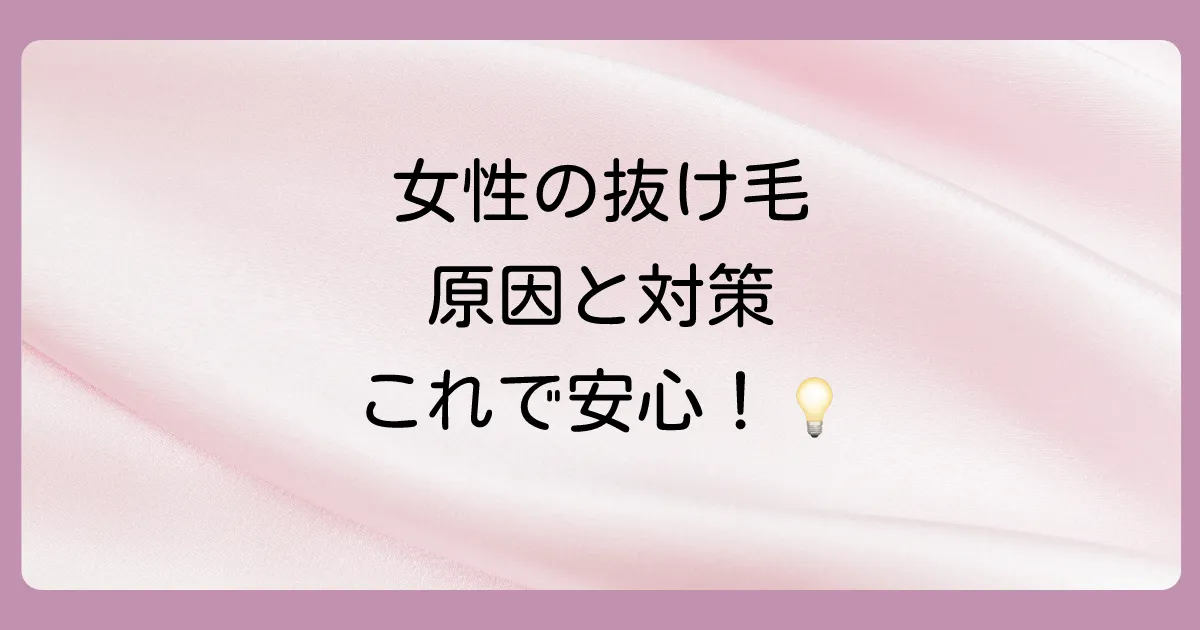
- 女性の急な抜け毛は病気のサインの可能性がある。
- 考えられる病気には、びまん性脱毛症や円形脱毛症がある。
- 甲状腺の異常や膠原病、貧血も抜け毛の原因になる。
- 婦人科系の病気や薬剤の副作用も考えられる。
- 病気以外では、ストレスや生活習慣の乱れが主な原因。
- 過度なダイエットや間違ったヘアケアも髪に悪影響。
- 産後の抜け毛は一時的なホルモン変化によるもの。
- 抜け毛の相談は、まず皮膚科を受診するのが基本。
- 専門的な治療を望むなら女性専門の薄毛クリニックへ。
- 全身の不調があれば内科や婦人科の受診も検討する。
- 栄養バランスの取れた食事が健やかな髪の基本。
- 質の良い睡眠は髪の成長に不可欠である。
- ストレスを溜めず、上手に発散することが大切。
- 正しいヘアケアと頭皮マッサージで頭皮環境を整える。
- 原因に応じた適切な対処で、抜け毛は改善できる。
新着記事