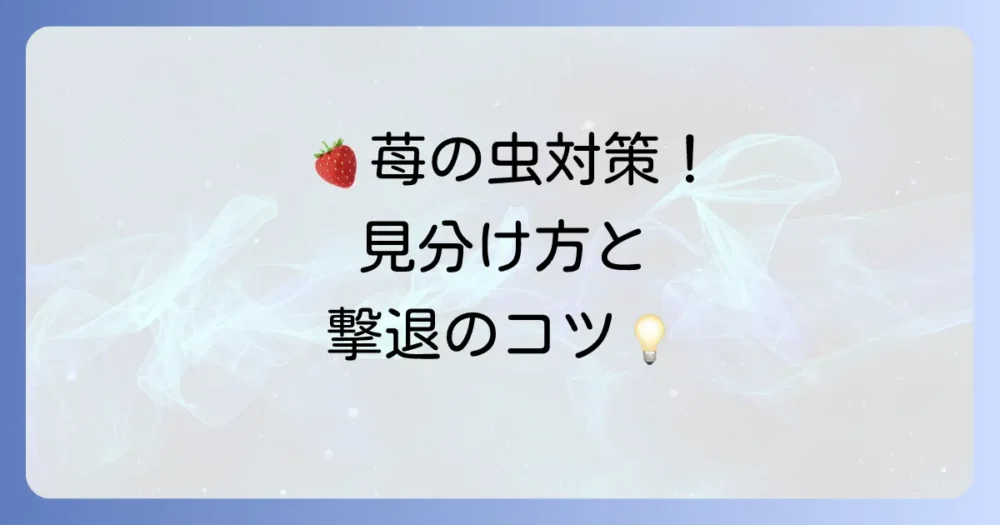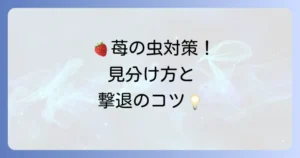大切に育てている苺に、いつの間にか虫が…!家庭菜園で甘くて美味しい苺を収穫するのを楽しみにしていたのに、がっかりしてしまいますよね。葉っぱに穴が開いていたり、実に黒いツブツブがついていたりすると、「この苺、もう食べられないのかな?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。でも、安心してください。苺につく虫の種類と、その対策方法を知っていれば、初心者でも美味しい苺を守ることができます。本記事では、苺に発生しやすい代表的な害虫の種類から、農薬を使わない安全な対策、効果的な農薬の使い方まで、写真付きで詳しく解説します。
【要点整理】苺につきやすい虫と対策早見表
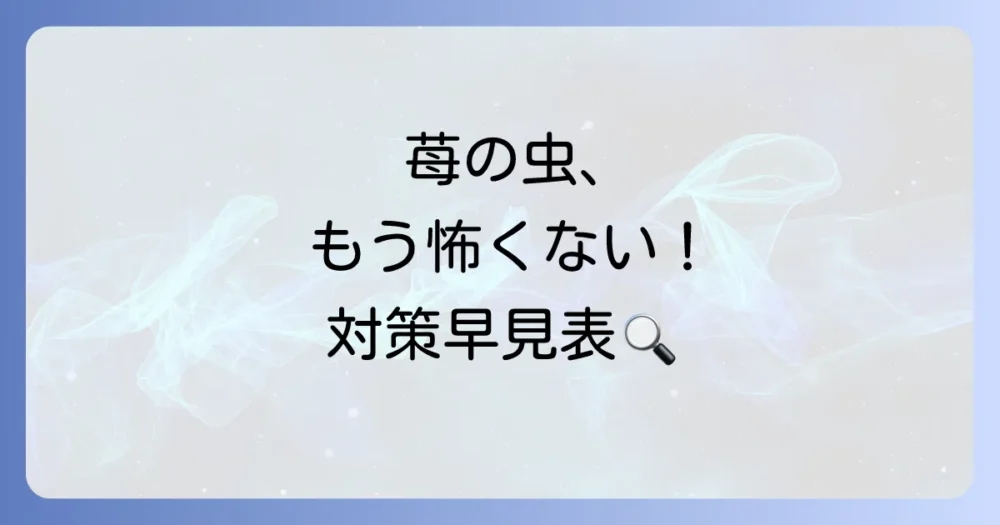
まずは、苺に発生しやすい代表的な虫とその対策を一覧でご紹介します。詳しい対策は後の章で解説しますが、今すぐ何とかしたい!という方は、こちらを参考にしてください。
| 害虫の種類 | 主な被害 | 主な対策方法 |
|---|---|---|
| アブラムシ | 葉や茎、新芽から汁を吸う。ウイルス病を媒介する。 | 牛乳スプレー、木酢液、粘着テープ、天敵(テントウムシ) |
| ハダニ | 葉の裏から汁を吸い、葉が白っぽくなる。クモの巣状の糸を張る。 | 葉水(霧吹きで水をかける)、でんぷんスプレー、天敵(カブリダニ) |
| ナメクジ | 夜間に活動し、実や葉を食べる。食べた跡が光る。 | ビールトラップ、銅線、コーヒーかす、ナメクジ駆除剤 |
| ヨトウムシ・イモムシ類 | 夜間に葉や実を食べる。昼間は土の中に隠れている。 | 見つけ次第捕殺、米ぬか、コンパニオンプランツ |
| イチゴハナゾウムシ | つぼみや花を食害し、実がつかなくなる。 | 被害を受けたつぼみを摘み取る、農薬散布 |
苺に虫がつく原因とは?
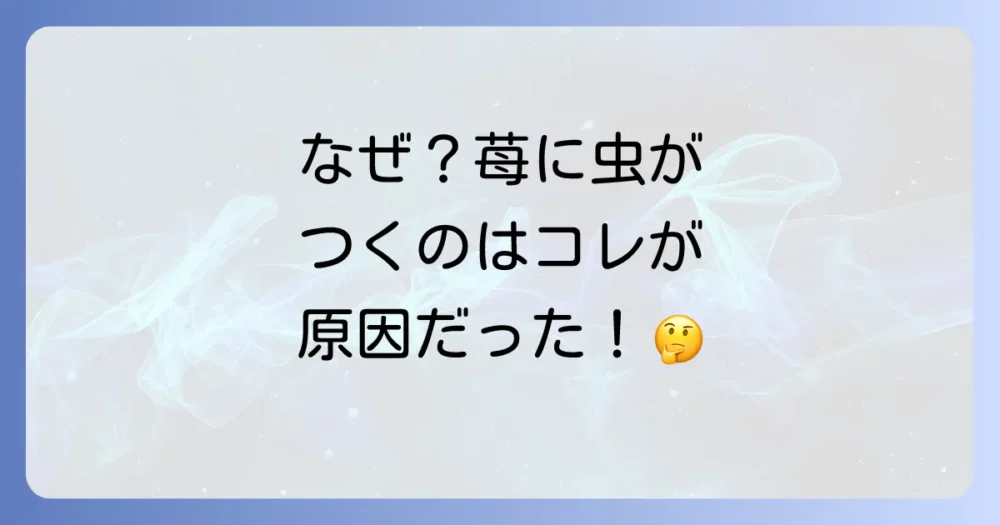
そもそも、なぜ大切に育てている苺に虫がついてしまうのでしょうか。原因を知ることで、効果的な予防策を立てることができます。主な原因は以下の通りです。
風通しの悪さ
葉が密集して風通しが悪くなると、湿気がこもりやすくなります。このような環境は、アブラムシやハダニ、うどんこ病などの病害虫が発生しやすい絶好の場所になってしまいます。特に梅雨時期は注意が必要です。古い葉や傷んだ葉はこまめに摘み取り、株全体の風通しを良くしてあげましょう。プランター栽培の場合は、鉢と鉢の間隔を十分に空けることも大切です。
雑草の放置
プランターや畑の周りに雑草が生い茂っていませんか?雑草は、害虫の隠れ家や繁殖場所になります。 特にハダニなどは雑草で増殖し、そこから苺へと移動してくることがあります。 苺の株周りはもちろん、栽培している場所全体の雑草を定期的に取り除くことで、害虫の発生リスクを大幅に減らすことができます。
購入した苗からの持ち込み
新しく苺の苗を購入する際は、注意深く観察することが重要です。一見きれいに見える苗でも、葉の裏や付け根に害虫の卵や小さな幼虫が潜んでいることがあります。 特にアブラムシやハダニは非常に小さいため、見落としがちです。購入後はすぐに植え付けるのではなく、数日間は他の植物と離れた場所で様子を見るのも一つの方法です。
窒素肥料の与えすぎ
苺を元気に育てたい一心で、肥料をたくさん与えていませんか?特に、葉や茎の成長を促す窒素成分が多い肥料を与えすぎると、葉が茂りすぎて風通しが悪くなるだけでなく、植物の組織が柔らかくなり、アブラムシなどの害虫がつきやすくなると言われています。肥料は規定量を守り、バランスの取れたものを選ぶようにしましょう。
【種類別】苺の代表的な害虫と駆除・対策方法
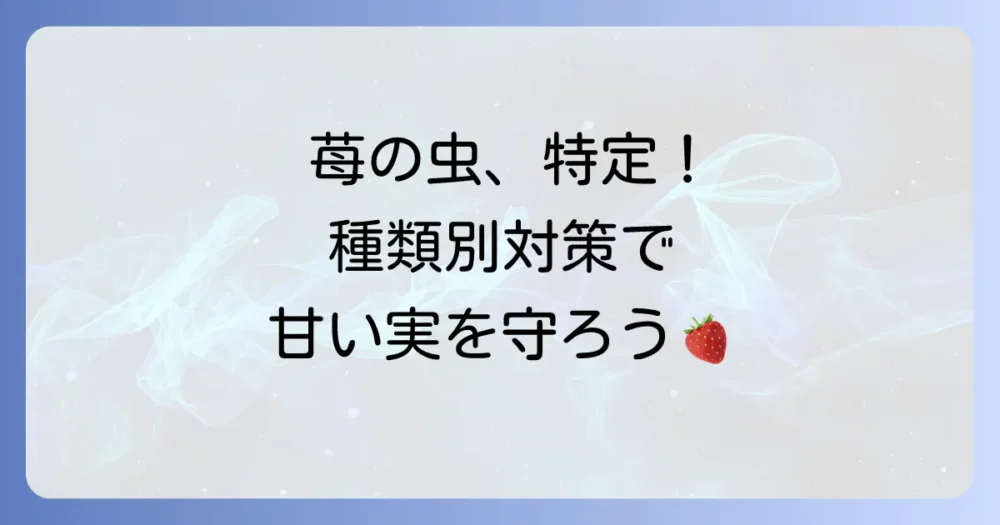
ここでは、苺に発生しやすい代表的な害虫の種類と、それぞれの特徴、効果的な駆除・対策方法を詳しく解説していきます。
アブラムシ
体長0.5mm~3mmほどの小さな虫で、緑色や黒色など様々な種類がいます。 新芽や葉の裏にびっしりと群生し、植物の汁を吸って弱らせます。繁殖力が非常に高く、あっという間に増殖するのが特徴です。
被害
アブラムシに汁を吸われると、苺の生育が悪くなります。また、アブラムシの排泄物は「甘露」と呼ばれ、これが原因で葉や実がベタベタになり、「すす病」という黒いカビが発生して光合成を妨げます。 さらに、ウイルス病を媒介することもあるため、早期の対策が非常に重要です。
駆除・対策方法
発生初期であれば、セロハンテープやガムテープで貼り付けて取り除くのが手軽でおすすめです。 指で潰すのに抵抗がある方は試してみてください。数が増えてしまった場合は、牛乳や石鹸水を薄めたものをスプレーで吹きかけると、アブラムシが窒息して駆除できます。 吹きかけた後は、水で洗い流すのを忘れないようにしましょう。天敵であるテントウムシを放つのも効果的です。
ハダニ
体長0.5mm~1mmほどの非常に小さな虫で、肉眼での確認は困難です。 葉の裏に寄生して汁を吸います。乾燥した環境を好み、特に梅雨明けから夏にかけて発生しやすくなります。
被害
ハダニに寄生されると、葉の裏から汁を吸われ、葉の表面に白いカスリ状の小さな斑点が現れます。 被害が進行すると葉全体が白っぽくなり、光合成ができなくなって枯れてしまいます。 また、数が増えるとクモの巣のような細かい糸を出すのも特徴です。
駆除・対策方法
ハダニは水に弱い性質があるため、定期的に葉の裏に霧吹きで水をかける「葉水」が予防に効果的です。発生してしまった場合は、でんぷんを主成分としたスプレー(粘着くんなど)が有効です。 でんぷんがハダニを覆って窒息させます。ハダニの天敵であるカブリダニを利用した生物農薬も市販されています。
ナメクジ
夜行性で、昼間はプランターの底やマルチの下など、湿っていて暗い場所に隠れています。雨の日やその翌日によく活動します。
被害
熟した苺の実に穴を開けて食害します。 食べた跡がキラキラと光る筋状の粘液でわかるのが特徴です。葉や花を食べることもあります。せっかく赤くなった苺を食べられてしまうと、ショックは大きいですよね。
駆除・対策方法
夜間に見つけて割り箸などで捕殺するのが確実です。ビールを入れた容器を苺の近くに置いておくと、匂いに誘われたナメクジが溺死する「ビールトラップ」も効果的です。 ナメクジは銅を嫌う性質があるため、プランターの周りに銅線を巻いたり、銅板を置いたりするのも有効な忌避策になります。 コーヒーかすや木酢液を撒くのも一定の効果が期待できます。
ヨトウムシ・イモムシ類
ヨトウムシは「夜盗虫」と書くように、夜間に活動して葉や実を食べるガの幼虫です。 昼間は土の中に潜んでいます。他にもハスモンヨトウなど、様々な種類のイモムシが苺の葉を食害します。
被害
葉が大きく食べられ、穴が開いたり、葉脈だけが残されたりします。 幼虫が小さいうちは集団で葉の裏を食害しますが、大きくなると分散し、食欲も旺盛になるため被害が拡大します。
駆除・対策方法
夜間に懐中電灯で照らし、見つけ次第捕殺するのが最も効果的です。 触ると丸まって地面に落ちる習性があるので、見失わないように注意しましょう。 米ぬかを株元に撒いておくと、ヨトウムシがそれを食べて消化不良を起こして死ぬと言われています。農薬を使いたくない場合は試してみる価値があります。
イチゴハナゾウムシ
体長3mmほどの黒褐色のゾウムシの一種です。 成虫で越冬し、春になると活動を始めます。
被害
被害は主に蕾(つぼみ)に現れます。 成虫が産卵管を刺して蕾に穴を開け、その中に卵を産み付けます。産卵後、雌は花茎をかじって傷つけるため、蕾はしおれて枯れてしまい、実がつきません。 これにより収穫量が大きく減少してしまいます。
駆除・対策方法
被害を受けた蕾は、中に幼虫がいる可能性が高いのですぐに摘み取って処分しましょう。 これが最も重要な対策です。成虫を見つけたら捕殺しますが、動きが素早いので簡単ではありません。被害が多い場合は、適用のある農薬を使用する必要があります。
その他の害虫
上記以外にも、苺には様々な虫がつくことがあります。
- コナジラミ: 白くて小さな虫で、葉の裏に寄生します。アブラムシと同様にすす病の原因になります。黄色い粘着シートで捕獲するのが効果的です。
- アザミウマ: 体長1~2mmの細長い虫で、花の中に潜んで汁を吸います。 被害を受けると果実が褐色に変色し、奇形になることがあります。 光るものを嫌う性質があるため、シルバーマルチを敷くと飛来を防ぐ効果があります。
- コガネムシの幼虫: 土の中に生息し、苺の根を食害します。株が急に元気がなくなったり、ぐらついたりする場合は、根が食べられている可能性があります。見つけ次第、取り除きましょう。
農薬を使いたくない人へ!無農薬でできる苺の虫対策
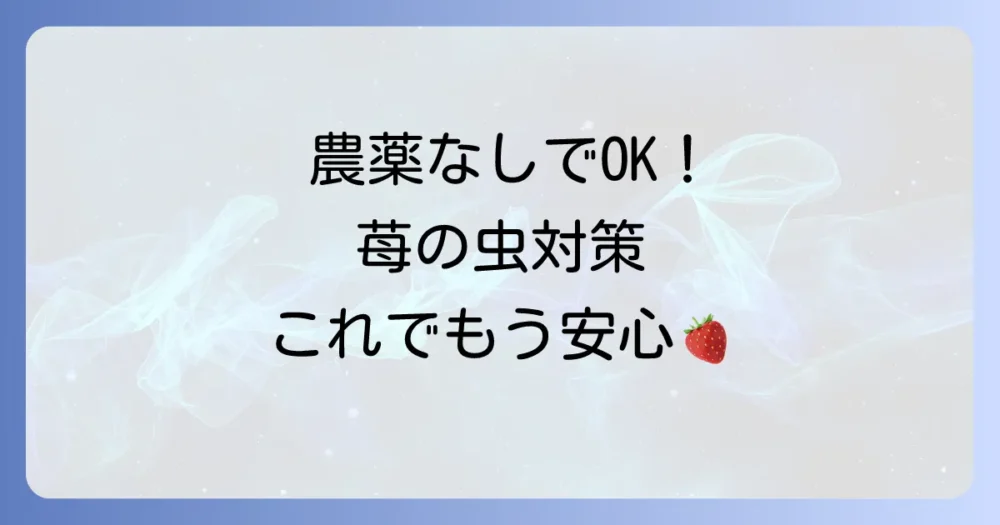
「家庭菜園だから、できるだけ農薬は使いたくない」そう考える方は多いですよね。ここでは、化学農薬に頼らずにできる、環境にも人にも優しい虫対策をご紹介します。
手で取る(テデトール)
最も原始的で、しかし確実な方法が「手で取る」、通称「テデトール」です。 アブラムシやヨトウムシなど、目に見える虫は、見つけ次第、手や割り箸で取り除きましょう。虫が苦手な方は、古い歯ブラシでこすり落としたり、セロハンテープで貼り付けたりする方法もあります。 毎日の観察を習慣にし、虫が少ないうちに対処することが、被害を最小限に抑えるコツです。
手作りスプレーで撃退
ご家庭にあるもので、安全な虫除けスプレーを作ることができます。
- 牛乳スプレー: 牛乳と水を1:1で混ぜたものをアブラムシに吹きかけます。牛乳が乾くときに膜を作り、アブラムシを窒息させます。使用後は、カビや臭いを防ぐために水で洗い流しましょう。
- 石鹸水スプレー: 食器用洗剤(自然由来のものが望ましい)を水で500倍程度に薄めてスプレーします。 これもアブラムシやハダニに効果があります。こちらも使用後は洗い流してください。
- 木酢液・竹酢液スプレー: 木酢液や竹酢液を規定の倍率に薄めて散布します。独特の燻製のような香りで害虫を寄せ付けにくくする効果や、土壌の微生物を活性化させる効果も期待できます。
- 唐辛子焼酎液: 焼酎に唐辛子を漬け込んだものです。 唐辛子の辛み成分であるカプサイシンが害虫を忌避します。これをさらに水で薄めて使用します。
これらの手作りスプレーは、効果が穏やかで持続性も低いため、こまめに散布する必要があります。また、使用前には必ず目立たない葉で試して、植物に影響がないか確認してから全体に使用してください。
コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることでお互いに良い影響を与え合う植物のことです。害虫を遠ざけたり、天敵を呼び寄せたりする効果が期待できます。
- ニンニク・ネギ類: 強い香りでアブラムシを遠ざける効果があります。 また、土壌の病原菌を抑える効果も期待できます。
- マリーゴールド: 根に寄生するネコブセンチュウという害虫を抑制する効果で有名です。独特の香りで様々な害虫を遠ざけます。
- ボリジ、ペチュニア: ミツバチなどの受粉を助ける虫(益虫)を呼び寄せてくれます。 これにより、苺の受粉が促され、実付きが良くなる効果も期待できます。
- クリムゾンクローバー: アブラムシの天敵であるヒラタアブなどを呼び寄せる効果があります。
見た目も華やかになり、一石二鳥なので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
物理的に虫を防ぐ
虫を寄せ付けないための物理的な防御策も非常に有効です。
- 防虫ネット: プランターや畝全体を目の細かい防虫ネットで覆うことで、ガやチョウ、アブラムシなどの飛来を防ぎます。 ネットをかける際は、葉に直接触れないように支柱を立てて空間を作ることがポイントです。
- マルチング: 株元を黒いビニールマルチや敷きわらで覆うことをマルチングといいます。これにより、土の中からの害虫の発生を抑えたり、ナメクジの隠れ場所を減らしたりする効果があります。 また、泥はねを防いで病気を予防し、果実が直接土に触れて傷むのを防ぐ効果もあります。
- シルバーマルチ・アルミホイル: アブラムシやアザミウマは光の反射を嫌う性質があります。 株元にシルバーマルチを敷いたり、アルミホイルを敷き詰めたりすることで、これらの害虫を寄せ付けにくくする効果が期待できます。
どうしても虫がいなくならない!効果的な農薬の選び方と使い方
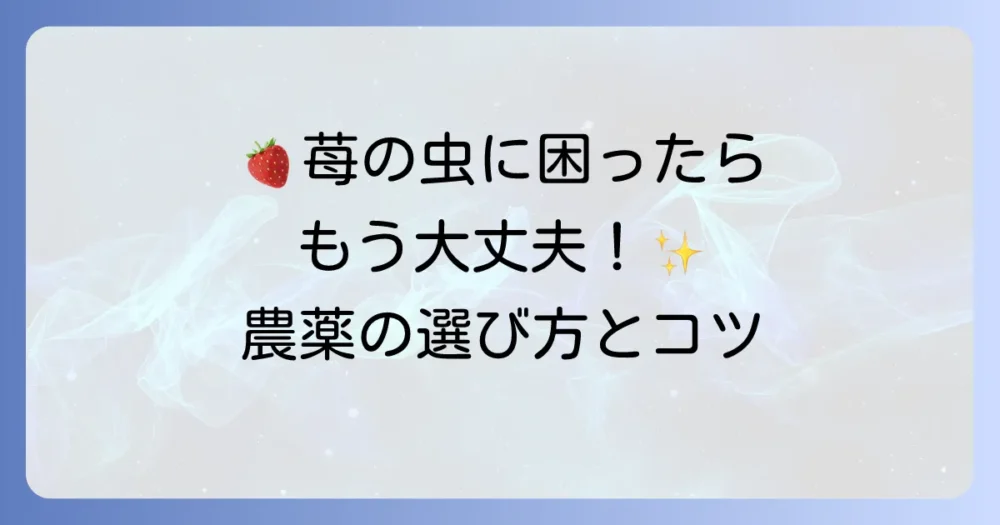
無農薬対策を試しても害虫の被害が収まらない、大量発生してしまったという場合は、農薬の使用も検討しましょう。正しく使えば、大切な苺を守るための力強い味方になります。
農薬選びのポイント
農薬を選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。
- 「いちご」に登録があるか: 農薬は、作物ごとに使用できるものが法律で定められています。必ずラベルを確認し、「いちご」に使用できる農薬を選びましょう。
- 対象の害虫に効果があるか: 発生している害虫の名前を確認し、その害虫に効果のある農薬を選びます。
- 使用時期と回数を守る: 「収穫〇日前まで使用可能」「使用回数は〇回以内」といった規定が必ず記載されています。これを厳守しないと、農薬が残留した苺を収穫してしまうことになります。
- 剤形を選ぶ: スプレータイプはそのまま使えて手軽ですが、広い範囲には希釈タイプが経済的です。粒剤は土に混ぜて使うなど、用途に合わせて選びましょう。
おすすめの農薬
家庭菜園で使いやすい、代表的な農薬をいくつかご紹介します。
- ベニカマイルドスプレー(住友化学園芸): 食品由来成分(還元でんぷん分解物)でできており、アブラムシやハダニに効果があります。 収穫前日まで使用できるのが嬉しいポイントです。
- 粘着くん液剤: でんぷん由来の成分で、物理的に害虫を窒息させます。 薬剤抵抗性がつきにくいのが特徴です。有機JAS適合の農薬です。
- スラゴ(ハイポネックス): ナメクジやカタツムリに効果のある粒状の駆除剤です。 有効成分は天然にも存在する鉄化合物なので、ペットがいるご家庭でも比較的安心して使用できます。
- スピノエース顆粒水和剤: アザミウマ類やヨトウムシに効果があります。 有機JAS適合の農薬です。
※農薬を使用する際は、必ず製品のラベルをよく読み、記載されている使用方法、希釈倍率、使用時期、回数などを厳守してください。
農薬の安全な使い方
農薬を安全に使うために、以下の点を必ず守りましょう。
- 保護具を着用する: 散布する際は、マスク、ゴーグル、長袖、長ズボン、手袋などを着用し、薬剤を吸い込んだり、皮膚に付着したりしないようにします。
- 風のない日に散布する: 風が強い日に散布すると、薬剤が飛散して自分にかかったり、近隣の作物に影響を与えたりする可能性があります。風のない、穏やかな日の朝か夕方に行いましょう。
- – 葉の裏にもしっかり散布する: アブラムシやハダニは葉の裏にいることが多いので、葉の裏までしっかりと薬剤がかかるように散布するのが効果を高めるコツです。
- 使い残しは適切に保管・処分する: 使い残した農薬は、子どもの手の届かない冷暗所に保管します。希釈した液は作り置きせず、その日のうちに使い切りましょう。
よくある質問
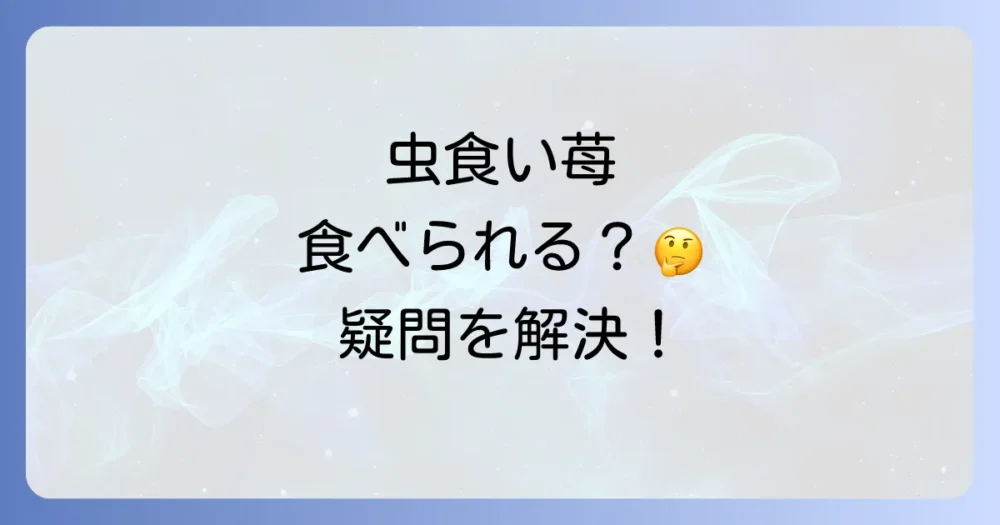
虫食いの苺は食べられますか?
虫が食べた跡がある苺でも、虫やフン、傷んだ部分をきれいに取り除けば、食べること自体に問題はありません。しかし、ナメクジが這った跡には寄生虫がいる可能性もゼロではないため、気になる方は加熱調理するか、食べるのを避けた方が安心です。基本的には、よく洗って傷んだ部分を取り除けば大丈夫と考えてよいでしょう。
苺の葉っぱに白い斑点が…これって虫?
葉の表面に、白いカスリ状の小さな斑点がたくさん出ている場合、ハダニの被害である可能性が高いです。 葉の裏をよく観察してみてください。非常に小さいですが、赤い点やクリーム色の点が見えたり、クモの巣のようなものが張っていたりすれば、ハダニが発生しています。早急に葉水などで対策しましょう。
苺の周りを飛んでいる黒い小さい虫の正体は?
苺の周りを飛んでいる小さな黒い虫は、羽が生えたアブラムシ(有翅アブラムシ)である可能性が高いです。 アブラムシは、生息密度が高くなると、新しい住処を求めて羽の生えた個体を生み出し、飛んで移動します。 飛んでいるのを見かけたら、すでに株にアブラムシが大量発生しているサインかもしれません。すぐに株全体をチェックしましょう。
プランター栽培で特に気を付けるべき虫は?
プランター栽培では、地面から離れているためナメクジの被害は比較的少ないですが、アブラムシやハダニには特に注意が必要です。プランターは乾燥しやすいため、ハダニが好む環境になりがちです。こまめな葉水で乾燥を防ぎましょう。また、風通しが悪くならないように、葉の管理や鉢の配置に気を配ることが大切です。
100均グッズで虫対策はできますか?
はい、できます。100円ショップで販売されている防虫ネットや支柱、スプレーボトルなどは虫対策に活用できます。 例えば、スプレーボトルは手作りスプレーを散布するのに便利ですし、支柱と防虫ネットを組み合わせれば、立派な虫除けトンネルを作ることができます。 黄色い粘着シートなども、コナジラミ対策に有効です。工夫次第でコストを抑えながら対策が可能です。
まとめ
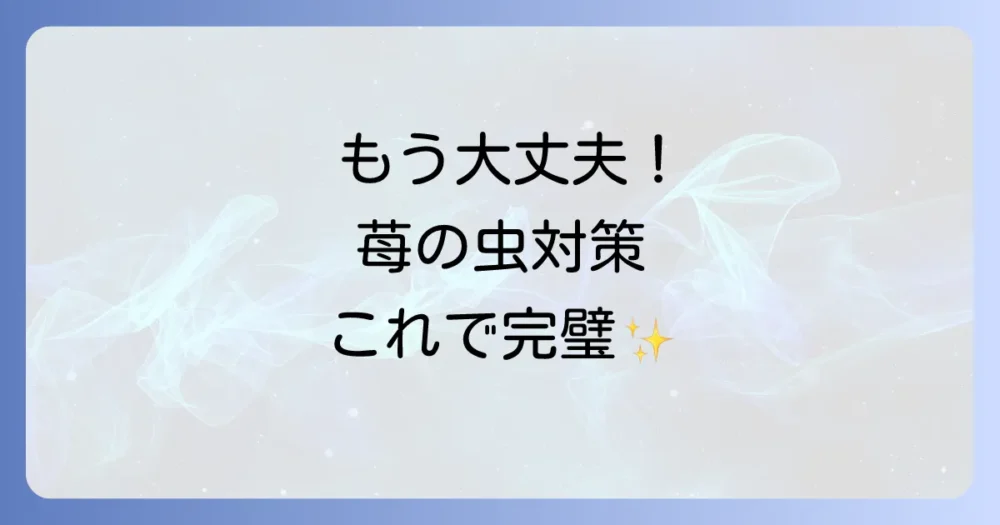
- 苺にはアブラムシやハダニなど様々な虫がつく。
- 虫がつく主な原因は風通しの悪さや雑草。
- 害虫は種類によって被害の場所や特徴が異なる。
- まずは手で取る、手作りスプレーなどの無農薬対策を試す。
- コンパニオンプランツは害虫予防と益虫誘引に効果的。
- 防虫ネットやマルチングなどの物理的防御も有効。
- アブラムシには牛乳スプレーや粘着テープが手軽。
- ハダニは乾燥を嫌うため葉水が予防になる。
- ナメクジにはビールトラップや銅製品が効果的。
- ヨトウムシは夜間に活動するため夜間の捕殺が基本。
- 被害が深刻な場合は農薬の使用も検討する。
- 農薬は「いちご」に登録があるものを選ぶこと。
- 農薬の使用時期や回数などのルールを必ず守る。
- 虫食いの苺は傷んだ部分を取り除けば食べられる。
- 日々の観察が早期発見・早期対策の鍵となる。
新着記事