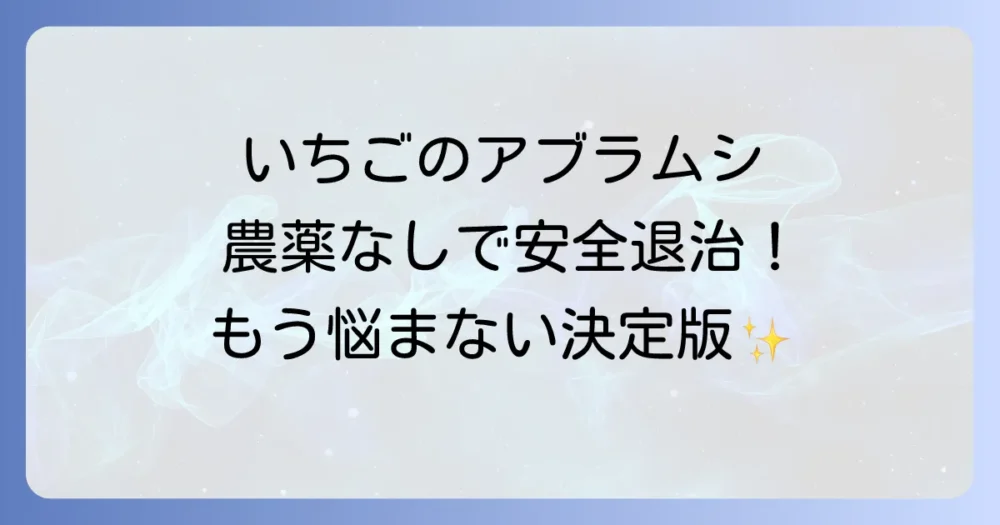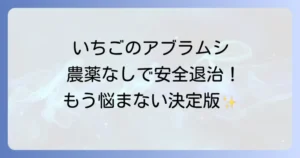家庭菜園で人気のいちご🍓。甘くて美味しい実がなるのを楽しみに育てている方も多いのではないでしょうか。しかし、そんな楽しいいちご栽培に突如現れる厄介な存在が「アブラムシ」です。葉や茎にびっしりと付いているのを見つけた時のがっかり感は大きいですよね。本記事では、大切ないちごをアブラムシから守るための駆除方法を、農薬を使わない安全な方法を中心に、発生原因から再発防止策まで詳しく解説します。
まずはチェック!いちごのアブラムシ発生サインと被害
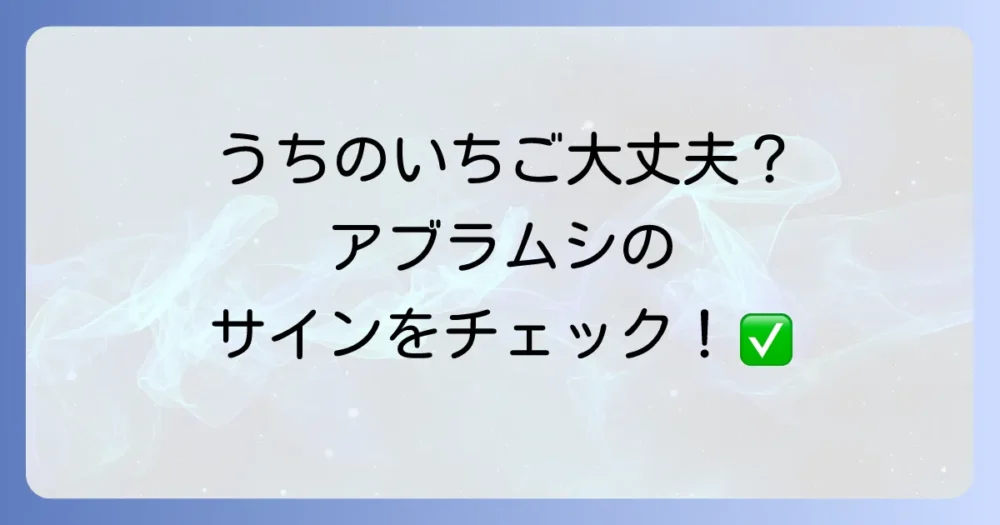
アブラムシの駆除を始める前に、まずは敵を知ることが大切です。アブラムシがどんな虫で、いちごにどのような影響を与えるのかを正しく理解し、早期発見・早期対応を心がけましょう。ここでは、アブラムシの生態や発生したときのサイン、そして放置した場合の被害について解説します。
- アブラムシってどんな虫?その生態
- 見逃さないで!アブラムシ発生の初期症状
- 放置は危険!アブラムシが引き起こす深刻な被害
アブラムシってどんな虫?その生態
アブラムシは、カメムシ目に属する体長2~4mmほどの小さな昆虫です。体色は緑色や黒色、赤色など種類によって様々ですが、いちごには主に「ワタアブラムシ」や「モモアカアブラムシ」が発生します。アブラムシの最大の特徴は、驚異的な繁殖力にあります。春から秋にかけては、メスだけで単為生殖を繰り返し、爆発的に増殖します。暖かい環境が続くと、1週間ほどで成虫になり、1日に数匹から十数匹の子を産むため、発見が遅れるとあっという間に大群になってしまうのです。
また、アブラムシは口針をいちごの葉や茎に突き刺し、師管液(栄養分)を吸って生活しています。この吸汁行為が、いちごの生育を阻害する直接的な原因となります。新芽や若葉など、柔らかい部分を好んで集まる傾向があります。
見逃さないで!アブラムシ発生の初期症状
アブラムシは小さいため、初期段階では見つけにくいかもしれません。しかし、いくつかのサインに注意することで、早期発見が可能です。まず確認すべきは、いちごの葉の裏側です。アブラムシは天敵から身を守るため、葉の裏に潜んでいることがほとんどです。定期的に葉をめくってチェックする習慣をつけましょう。
また、アブラムシの排泄物である「甘露(かんろ)」も重要なサインです。この甘露は糖分を多く含んでおり、葉や茎がベタベタしていたり、キラキラと光って見えたりする場合は、アブラムシがいる可能性が高いです。この甘露を目当てにアリが集まってくることもあるため、いちごの周りにアリが多く見られるようになったら注意が必要です。アリはアブラムシの天敵を追い払うことがあるため、アブラムシの繁殖を助長してしまうケースもあります。
放置は危険!アブラムシが引き起こす深刻な被害
「少しぐらいなら大丈夫だろう」とアブラムシを放置してしまうと、いちごに深刻な被害が及ぶ可能性があります。まず、大量のアブラムシに吸汁されることで、いちごの生育が悪くなります。葉が縮れたり、変形したり、最悪の場合は株全体が弱って枯れてしまうこともあります。
さらに厄介なのが、アブラムシが媒介する病気です。アブラムシは、吸汁する際にウイルスを媒介することがあり、「モザイク病」などの病気を引き起こす原因となります。モザイク病にかかると葉にまだら模様が現れ、治療法がないため、株ごと処分するしかありません。
また、アブラムシの排泄物である甘露を放置すると、それを栄養源として「すす病」という黒いカビが発生します。すす病が葉の表面を覆うと、光合成が妨げられ、生育不良や果実の品質低下につながります。このように、アブラムシは直接的な被害だけでなく、二次的な被害も引き起こす非常に厄介な害虫なのです。
【即効性重視】今すぐできる!いちごのアブラムシ駆除方法5選
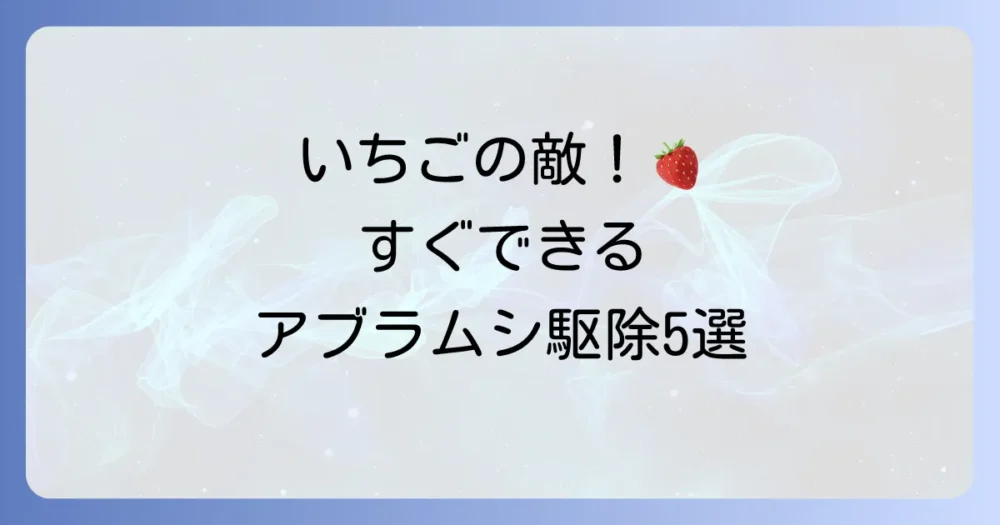
アブラムシを見つけたら、とにかく早く駆除することが重要です。ここでは、ご家庭で手軽に試せる、即効性の高い駆除方法を5つご紹介します。農薬を使わない方法を中心に解説しますので、お子様やペットがいるご家庭でも安心して実践できます。
- ① 物理的に取り除く(テープ、歯ブラシ)
- ② 牛乳スプレーで窒息させる
- ③ 木酢液・竹酢液で忌避する
- ④ 食品由来成分のスプレーを使う(市販品)
- ⑤ どうしてもダメなら…低リスクな農薬の選び方
① 物理的に取り除く(テープ、歯ブラシ)
アブラムシの数がまだ少ない初期段階であれば、物理的に取り除くのが最も手軽で確実な方法です。用意するものは、粘着テープ(ガムテープやセロハンテープ)や使い古しの歯ブラシだけ。
やり方はとても簡単です。粘着テープを指に巻き付け、アブラムシがいる葉の裏などにペタペタと貼り付けて剥がすだけ。アブラムシがテープにくっついてきれいに取れます。歯ブラシを使う場合は、葉を傷つけないように優しくこすり落とします。この方法は、薬剤を使わないので、いちごへの影響も全くなく、収穫直前でも行えるのが最大のメリットです。ただし、アブラムシが大量発生してしまった後では、手間がかかりすぎるため、他の方法と組み合わせるのがおすすめです。
② 牛乳スプレーで窒息させる
農薬を使わない駆除方法として有名なのが、牛乳スプレーです。牛乳を水で薄めずにそのままスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接吹きかけます。牛乳が乾く際に膜を作り、アブラムシの気門(呼吸するための穴)を塞いで窒息させるという仕組みです。
この方法のポイントは、牛乳が乾くまで待つこと。散布後は、牛乳が乾いたら必ず水で洗い流してください。牛乳をそのままにしておくと、腐敗して悪臭の原因になったり、カビが発生したりする可能性があります。また、牛乳の脂肪分が葉に残ると、油膜となって光合成を妨げることもあるため注意が必要です。晴れた日の午前中に行い、午後には洗い流すのが理想的です。
③ 木酢液・竹酢液で忌避する
木酢液(もくさくえき)や竹酢液(ちくさくえき)は、木炭や竹炭を作る際に出る煙を冷却して液体にしたものです。独特の燻製のような香りが特徴で、この香りをアブラムシが嫌うため、忌避効果が期待できます。殺虫効果というよりは、「アブラムシを寄せ付けない」という予防的な意味合いが強い方法です。
使用する際は、製品に記載されている希釈倍率(一般的には500倍~1000倍)を守って水で薄め、スプレーで散布します。葉の裏までしっかりと吹きかけるのがコツです。木酢液や竹酢液には、土壌の微生物を活性化させる効果もあるとされ、植物の成長を助ける副次的な効果も期待できます。ただし、濃度が濃すぎると植物に害を与える可能性があるため、必ず規定の倍率を守って使用してください。
④ 食品由来成分のスプレーを使う(市販品)
「自分でスプレーを作るのは面倒…」という方には、市販されている食品由来成分の殺虫剤がおすすめです。これらの製品は、酢やデンプン、食用油など、食品や食品添加物を有効成分としており、安全性が高いのが特徴です。
例えば、アース製薬の「アースガーデン やさお酢」や住友化学園芸の「ベニカマイルドスプレー」などが有名です。これらの製品は、アブラムシを物理的に包み込んで窒息させたり、忌避させたりする効果があります。収穫前日まで使えるものが多く、いちごのような野菜や果物にも安心して使用できます。購入する際は、適用作物に「いちご」が含まれているか、使用回数や時期の制限などを必ず確認しましょう。
⑤ どうしてもダメなら…低リスクな農薬の選び方
様々な方法を試してもアブラムシの勢いが止まらない、大量発生してしまったという場合には、最終手段として農薬の使用も検討します。家庭菜園で農薬を使うことに抵抗がある方も多いと思いますが、最近では、天然成分由来で人や環境への影響が少ない製品も増えています。
農薬を選ぶ際は、「JAS(有機JAS規格)」で使用が認められているものを選ぶと、比較的安心して使用できます。例えば、除虫菊から抽出した「ピレトリン」や、微生物が作る殺虫成分を利用した「スピノサド」などがあります。住友化学園芸の「ベニカXファインスプレー」などは、殺虫・殺菌効果があり、病気の予防も同時にできるため便利です。農薬を使用する際は、必ず製品ラベルをよく読み、記載されている使用方法、希釈倍率、使用時期、使用回数を厳守してください。特に収穫までの日数制限は必ず守り、安全ないちご作りを心がけましょう。
【根本解決】もう発生させない!いちごのアブラムシ予防策
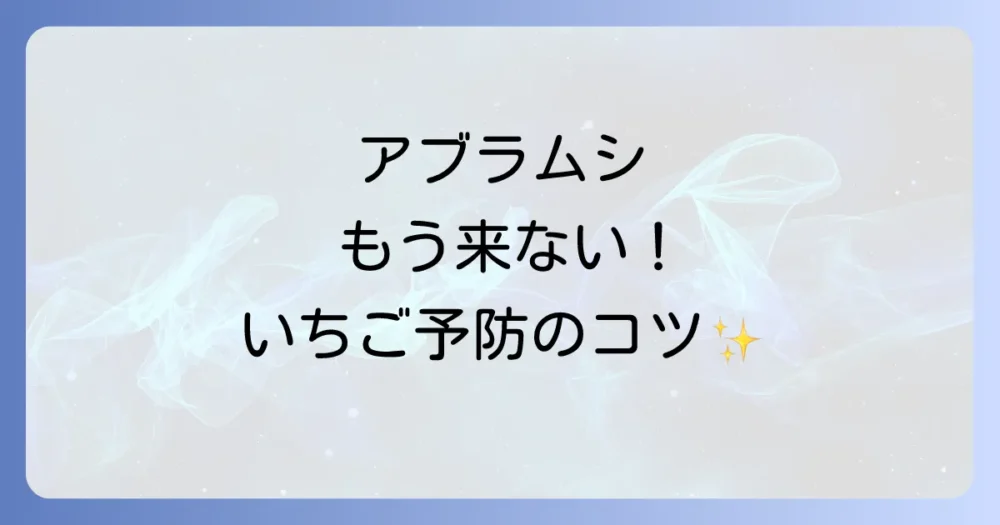
アブラムシの駆除も大切ですが、それ以上に重要なのが「そもそもアブラムシを発生させない」ための予防です。アブラムシが好む環境をなくし、嫌う環境を作ることで、発生リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、今日から始められる効果的な予防策をご紹介します。
- アブラムシが好む環境、嫌う環境とは?
- 予防策① 風通しと日当たりを改善する
- 予防策② 天敵(テントウムシ)を味方につける
- 予防策③ コンパニオンプランツを活用する
- 予防策④ 窒素肥料の与えすぎに注意する
アブラムシが好む環境、嫌う環境とは?
アブラムシ対策の基本は、彼らがどのような環境を好み、どのような環境を嫌うかを知ることから始まります。アブラムシが好むのは、風通しが悪く、湿度が高い場所です。葉が密集していると、天敵から身を隠しやすく、湿気がこもるため、アブラムシにとって絶好の住処となります。また、窒素過多で軟弱に育った植物も大好きです。柔らかい葉や茎は、アブラムシにとって吸汁しやすいためです。
逆に、アブラムシが嫌うのは、風通しが良く、乾燥した環境です。また、キラキラと光るものを嫌う習性があると言われています。これらの性質を利用して、アブラムシが寄り付きにくい環境を意図的に作ることが、効果的な予防につながります。
予防策① 風通しと日当たりを改善する
アブラムシ予防の第一歩は、いちごの株周りの環境を整えることです。まずは、古い葉や枯れた葉、混み合っている葉をこまめに取り除き、株全体の風通しを良くしましょう。これを「葉かき」と呼びます。葉かきをすることで、株元まで日光が当たりやすくなり、湿気がこもるのを防ぎます。
プランターで育てている場合は、プランター同士の間隔を十分に空けることも大切です。また、雑草が生い茂っていると、風通しが悪くなるだけでなく、アブラムシの隠れ家や発生源になることもあります。株周りの雑草はこまめに抜くように心がけましょう。風通しと日当たりを確保するだけで、アブラムシだけでなく、うどんこ病などの病気予防にもつながります。
予防策② 天敵(テントウムシ)を味方につける
自然の力を借りるのも、非常に有効な予防策です。アブラムシには、たくさんの天敵がいます。その代表格がテントウムシです。テントウムシの成虫も幼虫も、アブラムシを大好物としており、1匹いるだけで数百匹のアブラムシを食べてくれると言われています。
テントウムシを呼び寄せるためには、彼らが好む植物を近くに植えるのが効果的です。キク科の植物(カモミール、マリーゴールドなど)やセリ科の植物(パセリ、ニンジンなど)は、テントウムシが好むため、コンパニオンプランツとしておすすめです。また、農薬の使用を控えることも、天敵を守る上で非常に重要です。益虫であるテントウムシやヒラタアブ、クサカゲロウなどを大切にすることで、アブラムシが増えにくい生態系のバランスを作り出すことができます。
予防策③ コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いによい影響を与え合う植物のことです。アブラムシ対策としては、いくつかの植物が有効とされています。
一つは、キラキラ光るものを嫌うアブラムシの習性を利用する方法です。株元にアルミホイルやシルバーマルチを敷くことで、光が乱反射し、アブラムシが寄り付きにくくなります。
もう一つは、特定の香りでアブラムシを遠ざける方法です。ニンニクやネギ類、ハーブ類(ミント、ローズマリー、ナスタチウムなど)は、アブラムシが嫌う強い香りを放ちます。これらの植物をいちごの近くに植えることで、忌避効果が期待できます。特にマリーゴールドは、根に寄生するネコブセンチュウを防ぐ効果もあるとされ、一石二鳥です。様々なコンパニオンプランツを試して、ご自身の菜園に合った組み合わせを見つけるのも楽しいでしょう。
予防策④ 窒素肥料の与えすぎに注意する
いちごを元気に育てたい一心で、ついつい肥料を多く与えすぎてしまうことがあります。しかし、窒素(N)成分の多い肥料を与えすぎると、葉や茎ばかりが茂り、植物体が軟弱に育ってしまいます。このような柔らかい植物は、アブラムシにとって格好の餌食です。
肥料を与える際は、製品に記載されている規定量を守ることが基本です。特に、追肥のタイミングや量には注意しましょう。窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)がバランスよく配合された肥料を選ぶことが大切です。リン酸は実付きを良くし、カリウムは根を丈夫にする働きがあります。健全で丈夫ないちごを育てることが、結果的にアブラムシをはじめとする病害虫への抵抗力を高めることにつながるのです。
よくある質問
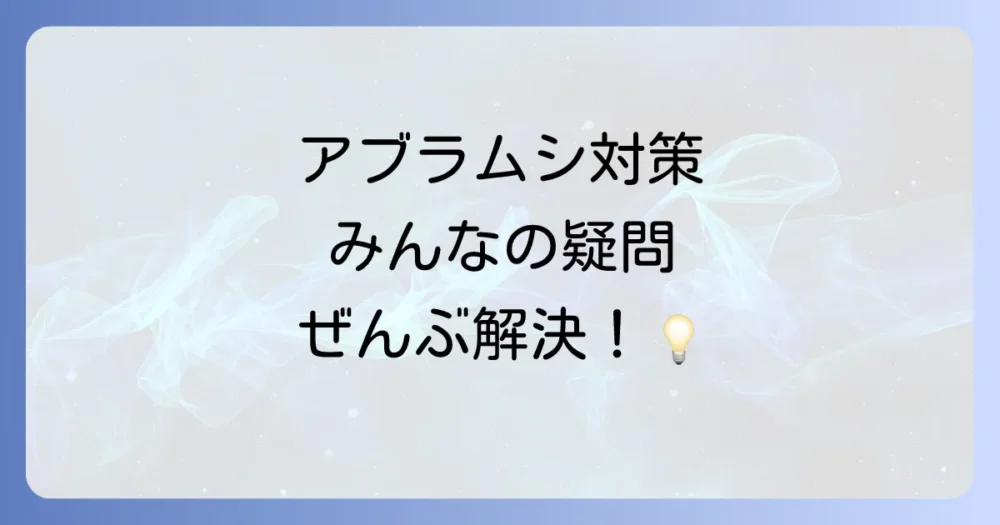
牛乳スプレーは本当に効果がありますか?注意点は?
はい、牛乳スプレーはアブラムシ駆除に効果が期待できます。牛乳が乾く際の膜でアブラムシを窒息させる仕組みです。ただし、いくつか注意点があります。まず、効果を発揮させるためには、アブラムシに直接かかるように、葉の裏まで念入りにスプレーする必要があります。そして最も重要なのは、散布後、牛乳が乾いたら必ず水で洗い流すことです。放置すると腐敗臭やカビの原因になります。また、脂肪分が葉に残り光合成を妨げる可能性もあるため、晴れた日の午前中に散布し、午後に洗い流すのがおすすめです。
木酢液の正しい使い方は?
木酢液は、製品に記載されている希釈倍率を必ず守って水で薄めてから使用します。一般的には500倍から1000倍程度に希釈します。これをスプレーボトルに入れ、アブラムシが発生している場所や、発生を予防したい場所に散布します。特に葉の裏側はアブラムシが潜みやすいので、念入りにスプレーしましょう。散布の頻度は、製品にもよりますが、1~2週間に1回程度が目安です。濃度が濃すぎると植物を傷める原因になるため、欲張って濃くしないように注意してください。
テントウムシはどこで手に入りますか?
テントウムシは、自然に飛んでくるのを待つのが基本です。カモミールやマリーゴールドなど、テントウムシが好む植物を植えておくと集まりやすくなります。もし、どうしても見つからない場合は、インターネット通販などで「天敵製剤」として販売されていることがあります。ただし、これは主に施設園芸向けで高価な場合が多いです。まずは、農薬の使用を控え、テントウムシが住みやすい環境を整えてあげることから始めるのが良いでしょう。
アブラムシ駆除に重曹や酢は使えますか?
重曹や食酢を使った駆除方法もインターネットなどで紹介されていますが、効果や植物への影響については注意が必要です。重曹スプレーは、濃度によってはうどんこ病に効果があるとされますが、アブラムシへの直接的な殺虫効果は限定的です。また、アルカリ性が強いため、植物にダメージを与える可能性があります。食酢も同様に、酸性が強すぎると葉が焼けたり生育不良を起こしたりする危険性があります。もし試す場合は、ごく薄い濃度から始め、目立たない部分で試してから全体に散布するなど、慎重に行う必要があります。基本的には、安全性が確認されている牛乳や市販の食品由来スプレーの使用をおすすめします。
駆除後のいちごは食べられますか?
使用した駆除方法によります。テープや歯ブラシで物理的に取り除いた場合は、もちろん問題なく食べられます。牛乳スプレーや木酢液、食品由来の市販スプレーを使った場合も、基本的には安全ですが、念のため食べる前によく水で洗うようにしましょう。特に牛乳は洗い流しが不十分だと衛生的によくありません。農薬を使用した場合は、製品ラベルに記載されている「収穫前日数」を必ず守ってください。この期間を過ぎていれば、安全に食べることができます。
アブラムシはどこからやってくるのですか?
アブラムシは、様々な方法でやってきます。最も多いのは、羽の生えた成虫(有翅虫)が風に乗って飛んでくるケースです。春や秋になると、新しい餌場を求めて移動し、あなたのいちごにたどり着きます。また、購入した苗に最初から卵や幼虫が付着していることもあります。新しい苗を植え付ける際は、アブラムシがいないかよく確認しましょう。さらに、アリが他の場所からアブラムシを運んでくることもあります。
まとめ
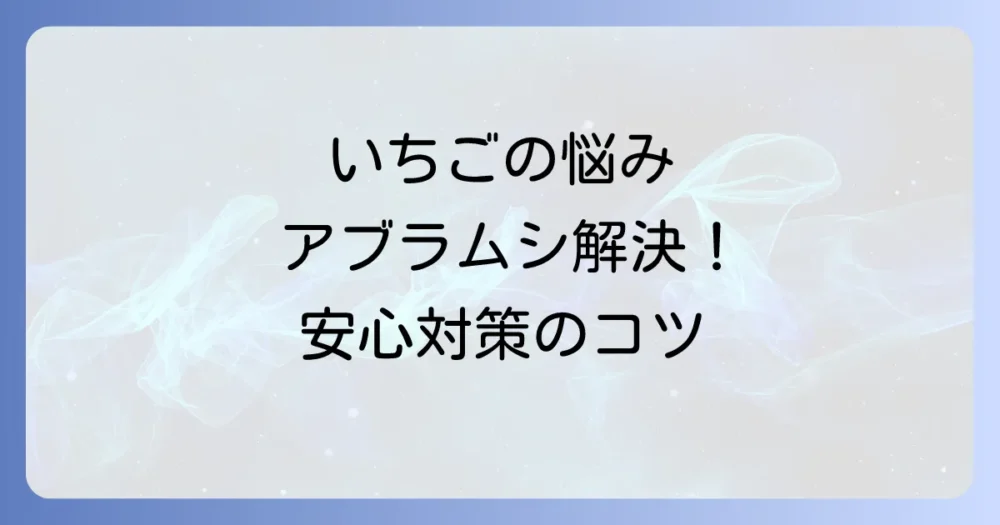
- アブラムシは葉裏に潜み、驚異的な繁殖力を持つ。
- 放置すると生育不良やすす病、ウイルス病の原因になる。
- 初期段階ならテープや歯ブラシでの物理的除去が有効。
- 牛乳スプレーは窒息効果があるが、散布後の水洗いが必須。
- 木酢液・竹酢液は忌避効果が期待でき、予防に使える。
- 安全性を重視するなら市販の食品由来スプレーが手軽。
- 大量発生時は有機JAS適合の低リスク農薬も選択肢。
- 予防の基本は、葉かきによる風通しと日当たりの改善。
- 天敵のテントウムシはアブラムシの強力な捕食者。
- テントウムシを呼ぶにはキク科やセリ科の植物が有効。
- アルミホイルやハーブ類でアブラムシを寄せ付けない。
- 窒素肥料の与えすぎは軟弱な株を作り、アブラムシを呼ぶ。
- 肥料はバランスの取れたものを規定量与えることが重要。
- 新しい苗を植える際は、アブラムシが付いていないか確認する。
- アブラムシ対策は、駆除と予防の両輪で行うことが大切。