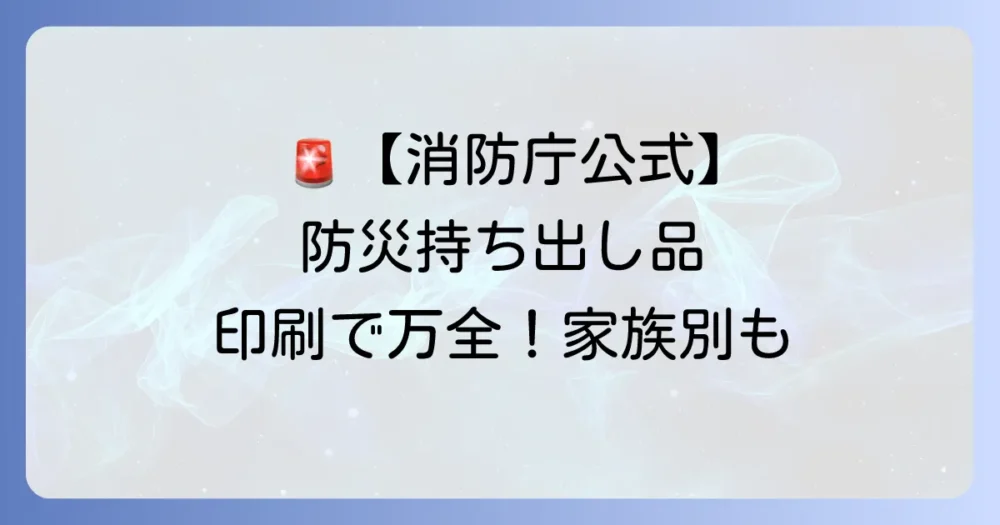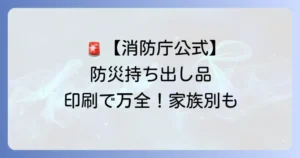「災害は忘れたころにやってくる」と言われますが、いつどこで起こるか分からないのが自然災害の怖いところです。いざという時に自分と大切な家族の命を守るため、事前の備えが何よりも重要になります。でも、「何から準備すればいいの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、消防庁の公式情報に基づいた「非常用持ち出し品チェックシート」を、誰にでも分かりやすく、そして印刷してすぐに使える形でご紹介します。さらに、ご家庭の状況に合わせた必需品も解説。この記事を最後まで読めば、災害への備えは万全です。
【印刷OK】消防庁推奨!非常用持ち出し品チェックシート(一次持ち出し品)
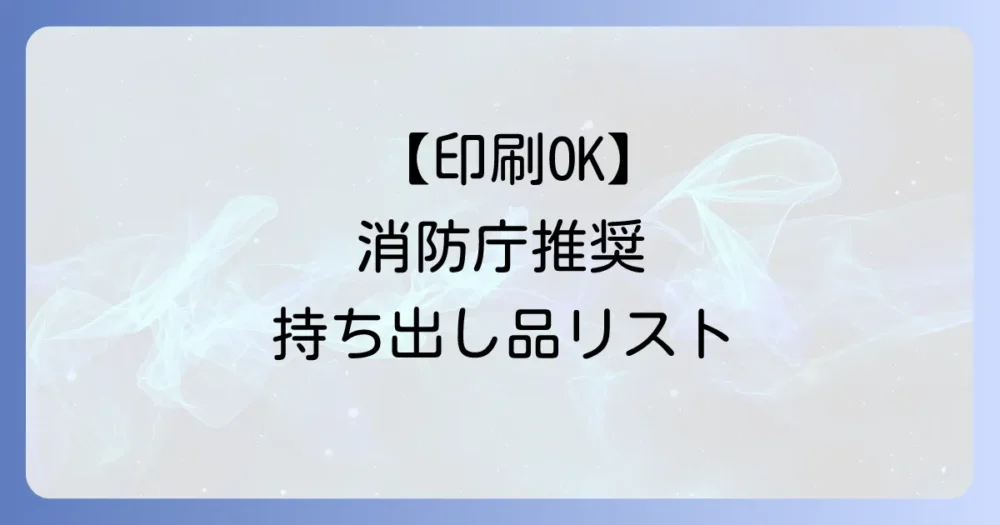
災害が発生し、避難が必要になった時に、まず最初に持ち出すべきものが「一次持ち出し品」です。命を守るための最低限のアイテムを、すぐに持ち出せるリュックサックなどにまとめておきましょう。ここでは、消防庁が推奨するリストを基に、具体的なチェックシートを作成しました。印刷して、準備の際にぜひご活用ください。
この章では、以下の項目について詳しく解説していきます。
- 貴重品
- 避難用品
- 食料・水
- 衛生用品・救急用品
- 情報収集ツール
- その他
貴重品
避難後の生活再建に不可欠なものです。コピーやデータをUSBメモリなどに保存し、別途保管しておくのも有効な手段です。特に現金は、停電時に電子マネーやクレジットカードが使えなくなるため、公衆電話で使える10円玉を含めて多めに用意しておくと安心です。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 現金(公衆電話用に10円玉も) | 停電に備え、数日分の生活費を。 |
| ☐ | 預金通帳、印鑑 | コピーやWeb通帳の活用も検討。 |
| ☐ | 健康保険証、運転免許証 | 身分証明に必須。コピーも用意。 |
| ☐ | お薬手帳、母子手帳 | 持病やアレルギーの情報を正確に伝えるために。 |
避難用品
安全に避難し、避難場所での過酷な環境を少しでも快適に過ごすためのアイテムです。特に懐中電灯は、停電時の夜間の移動や作業に必須です。両手が自由に使えるヘッドライト型が非常におすすめ。また、救助を求める際に体力を消耗せず居場所を知らせることができるホイッスルも、必ず準備しておきましょう。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 懐中電灯(ヘッドライトが便利) | 一人一つが理想。予備電池も忘れずに。 |
| ☐ | ヘルメット、防災ずきん | 落下物から頭部を守る。 |
| ☐ | 軍手、革手袋 | ガラス片などから手を守る。滑り止め付きが◎。 |
| ☐ | ホイッスル(笛) | 救助を求める際に。 |
| ☐ | アルミ製ブランケット | 薄くて軽いが保温効果が高い。 |
食料・水
救援物資が届くまでには時間がかかる場合があります。最低でも1日分、できれば3日分の食料と水を非常用持ち出し袋に入れておきましょう。調理不要でそのまま食べられるもの、カロリーが高く腹持ちが良いものが適しています。アメやチョコレートは、手軽に糖分を補給でき、精神的な安らぎにも繋がります。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 飲料水(500ml×2本程度) | 持ち運べる範囲で。1人1日3Lが目安。 |
| ☐ | 非常食(乾パン、缶詰、栄養補助食品) | 調理不要ですぐ食べられるもの。 |
| ☐ | アメ、チョコレート | 手軽な糖分補給に。 |
衛生用品・救急用品
避難所での集団生活では、衛生環境が悪化しがちです。感染症を防ぎ、健康を維持するために衛生用品は欠かせません。特に断水時にトイレが使えなくなる問題は深刻です。携帯トイレは必ず準備しましょう。また、普段から服用している薬がある方は、最低でも3日分、できれば1週間分をお薬手帳のコピーと一緒に準備しておくことが極めて重要です。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | マスク | 感染症予防、防寒、防塵に。 |
| ☐ | 携帯トイレ、トイレットペーパー | 断水時に必須。最低でも5回分/人。 |
| ☐ | ウェットティッシュ、除菌ジェル | 水が使えない時の手洗いや体の清拭に。 |
| ☐ | 救急セット(絆創膏、消毒液、包帯など) | 基本的な応急手当ができるように。 |
| ☐ | 常備薬 | 持病の薬は絶対忘れないように。 |
情報収集ツール
災害時には正確な情報が命を守ります。停電や通信障害が起こる可能性を考えると、スマートフォンだけに頼るのは危険です。電池で動き、手回し充電もできる携帯ラジオは非常に頼りになる存在です。モバイルバッテリーも、フル充電の状態を保っておきましょう。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 携帯ラジオ | 手回し充電式がおすすめ。予備電池も。 |
| ☐ | モバイルバッテリー、予備電池 | スマホの充電確保は死活問題。 |
| ☐ | 筆記用具、メモ帳 | 伝言や情報のメモに。油性ペンも便利。 |
その他
その他、あると便利なアイテムです。ビニール袋は、ゴミ袋としてだけでなく、水の運搬、敷物、雨具の代わりなど、様々な用途に使えて重宝します。ライターやマッチは、火を起こすだけでなく、暗闇での明かりにもなります。タオルも複数枚あると、体を拭くだけでなく、防寒やケガの手当てにも使えます。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | ビニール袋(大小複数枚) | 用途は無限大。多めに準備。 |
| ☐ | ライター、マッチ | 防水ケースに入れておくと安心。 |
| ☐ | タオル | 複数枚あると便利。圧縮タオルも省スペース。 |
| ☐ | 着替え、下着、靴下 | 体を清潔に保ち、体温調節に。 |
| ☐ | 使い捨てカイロ | 冬場の避難や、体調不良時に。 |
さらに万全を期すために!二次持ち出し品(備蓄品)リスト
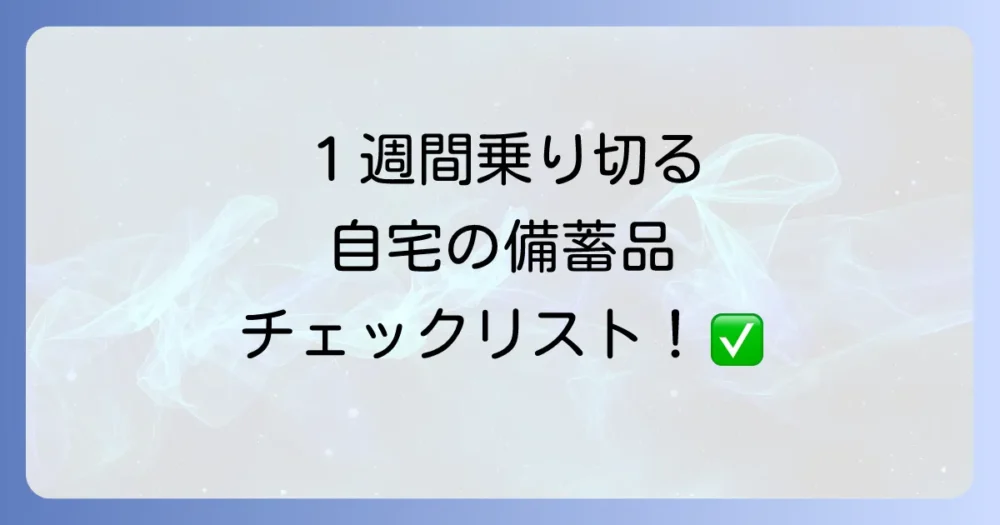
ライフラインが止まり、避難生活が長引く場合に備えて、自宅にストックしておくのが「二次持ち出し品(備蓄品)」です。災害発生から3日間、できれば1週間は自力で生活できるだけの量を準備しておくことが推奨されています。一次持ち出し品と合わせて、計画的に備えましょう。
この章では、二次持ち出し品として備えておきたいものをリストアップします。
- 食料・水(3日〜1週間分)
- 生活用品
- 燃料・調理器具
食料・水(3日〜1週間分)
家族全員が最低3日間、できれば1週間過ごせる量を備蓄しましょう。水は飲料水とは別に、調理や手洗いなどに使う生活用水も必要です。お風呂の水を常に溜めておく、ポリタンクに水道水を汲んでおくなどの習慣が役立ちます。食料は、普段の食事で食べているレトルト食品や缶詰などを少し多めに買っておく「ローリングストック法」がおすすめです。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 飲料水 | 1人1日3L×家族の人数×7日分が理想。 |
| ☐ | レトルトご飯、アルファ米 | お湯や水で戻せるご飯は主食として必須。 |
| ☐ | レトルト食品、缶詰 | おかず、果物、魚などバランス良く。 |
| ☐ | カップ麺、インスタント味噌汁 | 温かい食事は心も体も温める。 |
| ☐ | 調味料(塩、砂糖、醤油など) | 味付けのバリエーションに。 |
生活用品
電気や水道が止まった生活を想定し、必要なものをリストアップしましょう。特に衛生管理は重要です。簡易トイレは多めに備蓄しておくと安心です。また、ラップは食器に敷いて使えば洗い物を減らせるなど、様々な場面で活躍する万能アイテムです。新聞紙も、防寒や敷物、着火剤代わりになるなど、意外なところで役立ちます。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 簡易トイレ | 1人1日7回×家族の人数×7日分が目安。 |
| ☐ | ティッシュ、トイレットペーパー | 多めにストックを。 |
| ☐ | ラップ、アルミホイル | 食器を汚さない、保温など多用途。 |
| ☐ | ポリタンク | 給水車から水をもらう際に必要。 |
| ☐ | 歯ブラシ、歯磨き粉(液体歯磨きも) | 口腔ケアは感染症予防の基本。 |
| ☐ | 新聞紙 | 防寒、敷物、簡易トイレの目隠しなどに。 |
燃料・調理器具
カセットコンロとカセットボンベがあれば、電気やガスが止まっても温かい食事を作ることができます。これは、体力を維持し、精神的な安定を保つ上で非常に重要です。ボンベは1本で約1時間使用できます。1週間の備蓄を考えると、家族の人数にもよりますが6本以上あると安心です。使用期限も確認しておきましょう。
| チェック | 品目 | ポイント |
|---|---|---|
| ☐ | カセットコンロ | 温かい食事は心と体の支え。 |
| ☐ | カセットボンベ | 多めに備蓄(1週間で6本以上が目安)。 |
| ☐ | 鍋、やかん | 調理や湯沸かしに。 |
| ☐ | 紙皿、割り箸、紙コップ | 洗い物を減らす工夫。 |
【家族構成別】あなたの家族に本当に必要な追加アイテム
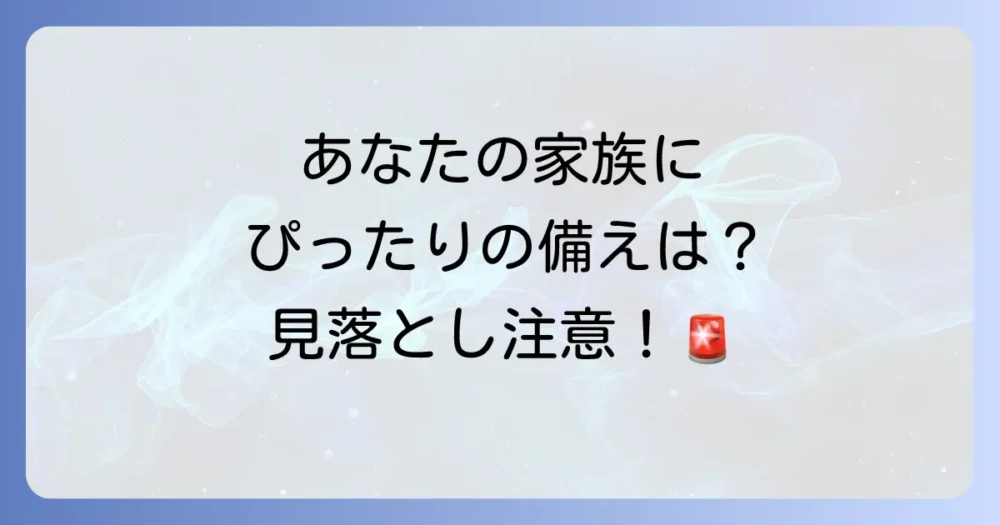
消防庁が推奨する基本リストに加えて、ご家族の状況に合わせて必要なものは異なります。ここでは、女性、赤ちゃん、高齢者、ペットなど、それぞれの状況で特に重要となるアイテムをリストアップしました。ご自身の家庭環境と照らし合わせ、備えに加えてください。
この章では、以下の家族構成に合わせた追加アイテムを紹介します。
- 👩🦰 女性が追加で備えたいもの
- 👶 赤ちゃん・乳幼児がいる家庭の必需品
- 👵 高齢者がいる家庭で準備すべきもの
- 🐶 ペット(犬・猫)と一緒に避難するために
- 💊 持病がある方・アレルギー体質の方
👩🦰 女性が追加で備えたいもの
災害時、女性特有のニーズは後回しにされがちです。プライバシーの確保や衛生面の維持は、心身の健康を守る上で非常に重要。生理用品は入手困難になる可能性が高いため、最低でも2周期分は備蓄しておくと安心です。また、防犯ブザーは、避難所や夜間のトイレなど、不安な状況でのお守りになります。
- 生理用品: 普段使っているものを多めに。昼用・夜用など種類も考慮。
- サニタリーショーツ: 洗濯が難しい状況でも安心。
- おりものシート: 下着を替えられない時に。
- 中身の見えないビニール袋: 使用済みナプキンを捨てる際にプライバシーを守る。
- 防犯ブザー: 避難所や夜間の移動時の安心材料に。
- ヘアゴム、ドライシャンプー: 髪をまとめ、清潔に保つ。
- スキンケア用品(試供品など): 環境の変化による肌荒れを防ぐ。
👶 赤ちゃん・乳幼児がいる家庭の必需品
赤ちゃんは環境の変化に非常に敏感で、大人と同じものは使えません。特にミルクや離乳食、おむつは命に直結する必需品です。普段使っているものを切らさないように備蓄しましょう。お湯がなくてもすぐに授乳できる液体ミルクは、災害時に非常に役立ちます。アレルギー対応のミルクや離乳食も忘れずに。
- 粉ミルク・液体ミルク: 最低1週間分。液体ミルクは調乳不要で便利。
- 哺乳瓶(使い捨てタイプも): 消毒が難しい場合に備える。
- 離乳食、ベビーフード: 赤ちゃんの月齢に合ったものを。
- 紙おむつ、おしりふき: 多めにストック。サイズアウトに注意。
- 抱っこ紐: 両手が空き、瓦礫の多い場所でも安全に移動できる。
- おくるみ、バスタオル: 体温調節や授乳ケープ、おむつ替えシート代わりにも。
- 子どものお気に入りのおもちゃ、絵本: 不安を和らげるために。
👵 高齢者がいる家庭で準備すべきもの
高齢者は体力の低下や持病により、災害時の負担が大きくなります。普段使っているものがなければ、生活の質が著しく低下し、命に関わることも。常備薬とお薬手帳は絶対に忘れないようにしましょう。入れ歯や補聴器など、生活に不可欠なものの予備も準備しておくと安心です。また、食べ慣れた柔らかい食事も重要です。
- 常備薬、お薬手帳のコピー: 1週間分以上を目安に。
- 入れ歯、洗浄剤: 予備の入れ歯もあれば安心。
- 補聴器、予備の電池: 情報収集やコミュニケーションに不可欠。
- 杖、歩行器: 普段使っているものの予備や折りたたみ式のものを。
- 大人用紙おむつ、尿とりパッド: トイレ問題は深刻。
- おかゆ、刻み食などの介護食: 食べ慣れたものを。
- 老眼鏡: 予備を準備。細かい文字を読む際に必要。
🐶 ペット(犬・猫)と一緒に避難するために
ペットも大切な家族の一員です。避難所によってはペットと一緒に入れない場合もあるため、事前に地域の避難ルールを確認しておくことが重要です。「同行避難」できても、ペットの世話は飼い主の責任。ペット用の非常食や水、常備薬などを忘れずに準備しましょう。迷子になった時のために、首輪に迷子札をつけ、マイクロチップの情報も確認しておきましょう。
- ペットフード、水: 最低5日分。食べ慣れたものを。
- 常備薬、療法食: 持病がある場合は必須。
- 食器、トイレ用品(ペットシーツ、猫砂など): 使い慣れたものを。
- ケージ、キャリーバッグ: 避難所での居場所確保に。
- 首輪、リード(予備も): 迷子防止の基本。
- ペットの写真、ワクチン証明書などのコピー: 迷子になった時や預ける際に必要。
- おもちゃ、タオルなど: ペットのストレスを和らげるために。
💊 持病がある方・アレルギー体質の方
特定の病気やアレルギーがある方は、自分専用の備えが不可欠です。災害時は医療機関も混乱し、いつもの薬や食品が手に入るとは限りません。かかりつけ医と相談し、災害時にどう対応すべきか、薬はどのくらい備蓄しておくべきかを確認しておきましょう。アレルギー表示が分かりやすい食品を選んで備蓄することも大切です。
- 処方薬: 最低でも1週間分、できればそれ以上。
- 自己注射薬、吸入薬など: 必要な器具や消耗品も忘れずに。
- アレルギー対応食品: 普段から食べ慣れているものをストック。
- アレルギー情報を記載したカード: 周囲に配慮を求めるために。
- エピペンなどの緊急補助治療薬: 必要な方は必ず携帯。
- 医師の連絡先、診断書のコピー: 専門的な治療が必要な場合に備える。
防災のプロが教える!非常用持ち出し品を準備・管理する5つのコツ
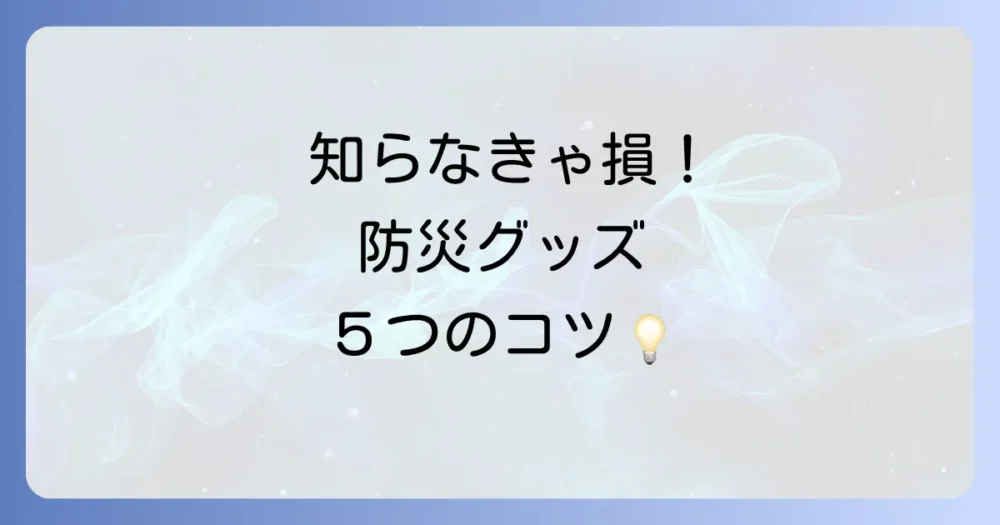
非常用持ち出し品は、ただ揃えれば良いというものではありません。いざという時に本当に役立つように、準備と管理にはいくつかのコツがあります。ここでは、防災の専門家も推奨する5つのポイントをご紹介します。今日から実践できることばかりですので、ぜひ参考にしてください。
この章で紹介する5つのコツはこちらです。
- コツ1:リュックは両手が空くタイプを選び、重すぎないように
- コツ2:すぐに取り出せる場所に保管する
- コツ3:「ローリングストック法」で食料を賢く備蓄
- コツ4:年に2回は中身を見直す習慣を
- コツ5:家族で情報を共有しておく
コツ1:リュックは両手が空くタイプを選び、重すぎないように
避難する際は、転倒の危険や障害物があることを想定しなければなりません。そのため、両手が自由に使えるリュックサック型の持ち出し袋が最適です。重さの目安は、すぐに持ち出して避難できることが最優先なので、男性で15kg、女性で10kg程度と言われています。体力に自信のない方や高齢者は、さらに軽くする必要があります。実際に背負ってみて、無理なく歩ける重さかどうかを確認しましょう。あまりに重すぎると、かえって避難の妨げになってしまいます。
コツ2:すぐに取り出せる場所に保管する
非常用持ち出し袋は、いざという時にすぐに持ち出せなければ意味がありません。玄関や寝室、リビングなど、すぐに手の届く場所に保管しましょう。クローゼットの奥深くにしまい込んでしまうと、緊急時に取り出すことが困難になります。また、車で避難する可能性が高い場合は、車内にも水や簡易トイレなどを備えておくとさらに安心です。家族全員が保管場所を把握しておくことも大切です。
コツ3:「ローリングストック法」で食料を賢く備蓄
「ローリングストック法」とは、普段の生活の中で非常食を消費し、消費した分を買い足していく備蓄方法です。缶詰やレトルト食品、乾麺など、日持ちのする食品を少し多めに買っておき、賞味期限の古いものから順番に食べていきます。これにより、常に一定量の食料を備蓄できるだけでなく、いざという時に食べ慣れたものを食べられるというメリットがあります。特別な非常食を準備するよりも手軽で、食品ロスも防げる賢い方法です。
コツ4:年に2回は中身を見直す習慣を
一度準備したら終わり、ではありません。非常用持ち出し袋の中身は、定期的に見直す必要があります。「防災の日(9月1日)」や「防災とボランティア週間(1月15日~21日)」などを目安に、年に2回は中身をチェックする習慣をつけましょう。チェックするポイントは、食料や飲料水の賞味期限、医薬品の使用期限、電池の残量、そして季節に合わせた衣類(夏は冷却シート、冬はカイロなど)の入れ替えです。子どもの成長に合わせて、おむつのサイズや衣類を見直すことも忘れないでください。
コツ5:家族で情報を共有しておく
防災対策は、家族全員で取り組むことが重要です。非常用持ち出し袋の置き場所はもちろんのこと、災害時の連絡方法、避難場所、集合場所などを事前に話し合って決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を確認したり、地域のハザードマップを見て危険な場所を把握したりすることも大切です。日頃から家族で防災について話し合う機会を持つことが、いざという時の冷静な行動に繋がります。
よくある質問
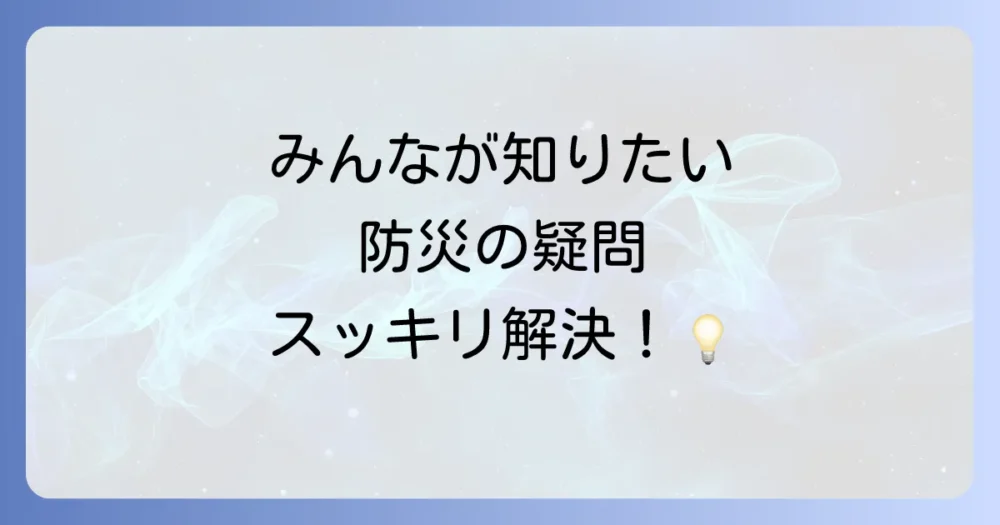
ここでは、非常用持ち出し品の準備に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
Q. 非常用持ち出し袋と備蓄品の違いは何ですか?
A. 「非常用持ち出し袋(一次持ち出し品)」は、災害発生時に命を守るため、避難する際に最初に持ち出す最低限の物品です。一方、「備蓄品(二次持ち出し品)」は、ライフラインが止まった後、自宅や避難所で数日間生活するために備えておく食料や生活用品を指します。持ち出し袋はすぐに避難できるよう軽く、備蓄品は3日~1週間分を目安に準備します。
Q. 非常食は何日分用意すればいいですか?
A. 最低でも3日分、大規模災害を想定すると1週間分の備蓄が推奨されています。 これは、災害発生後の72時間は人命救助が優先され、支援物資がすぐには届かない可能性があるためです。特に食料と水、簡易トイレは多めに準備しておくと安心です。
Q. 持ち出し袋の重さはどのくらいが目安ですか?
A. 一般的に、男性なら15kg、女性なら10kg程度が目安とされています。 しかし、これはあくまで目安であり、年齢や体力によって調整が必要です。実際に背負ってみて、速やかに歩いて避難できる重さにすることが最も重要です。重すぎて避難が遅れては本末転倒です。
Q. 消防庁のチェックシートはどこでダウンロードできますか?
A. 消防庁のウェブサイト内にある「防災マニュアル」のページなどで、非常用持ち出し品や備蓄品のチェックシートがPDF形式で提供されています。 「消防庁 防災マニュアル」などで検索すると見つけることができます。また、多くの自治体でも独自のチェックリストを配布しているので、お住まいの市区町村のホームページも確認してみましょう。
Q. 市販の防災セットは買ったほうがいいですか?
A. 市販の防災セットは、基本的なアイテムがまとめて揃うので、「何から揃えたらいいか分からない」という方には非常に便利です。 ただし、セット内容は画一的なので、購入後は必ず中身を確認し、常備薬や家族構成に合わせた必要なものを追加し、不要なものは 빼るなど、自分仕様にカスタマイズすることが大切です。
まとめ
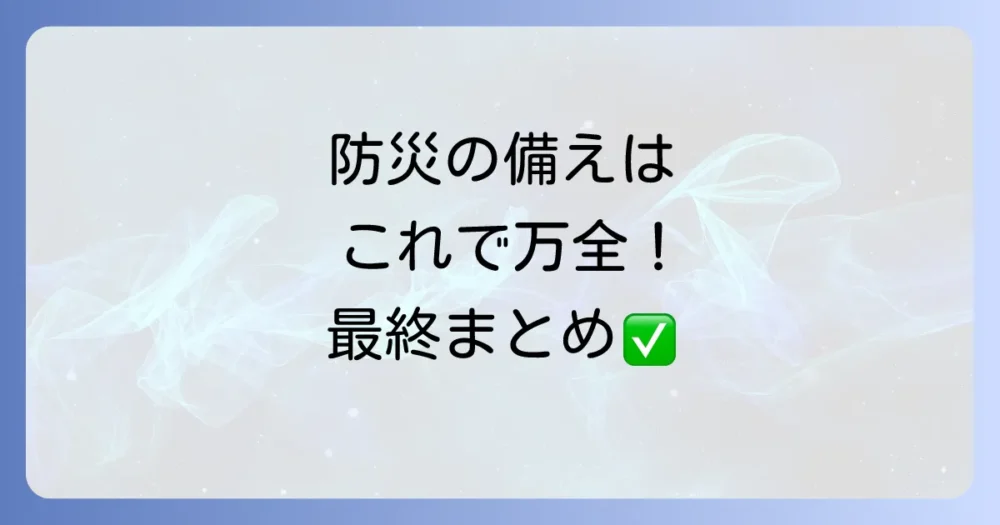
- 災害への備えは「一次持ち出し品」と「二次備蓄品」に分けて考える。
- 一次持ち出し品は、命を守るため避難時にすぐ持ち出すもの。
- 二次備蓄品は、ライフライン停止に備え自宅にストックするもの。
- 消防庁のチェックシートを基本に、必要なものを揃える。
- 現金やモバイルバッテリーは停電時に非常に重要。
- 衛生管理のため、携帯トイレやウェットティッシュは必須。
- 家族構成に合わせて、必要なものを追加で準備する。
- 女性は生理用品や防犯グッズを忘れずに。
- 赤ちゃんには液体ミルクやおむつを十分に。
- 高齢者には常備薬や介護用品が不可欠。
- 持ち出し袋は両手が空くリュックサックが最適。
- 重さは無理なく避難できる範囲に留める。
- 保管場所は玄関や寝室など、すぐに取り出せる場所に。
- 食料は「ローリングストック法」で賢く備蓄する。
- 年に2回は中身を見直し、期限切れや季節品を入れ替える。
新着記事