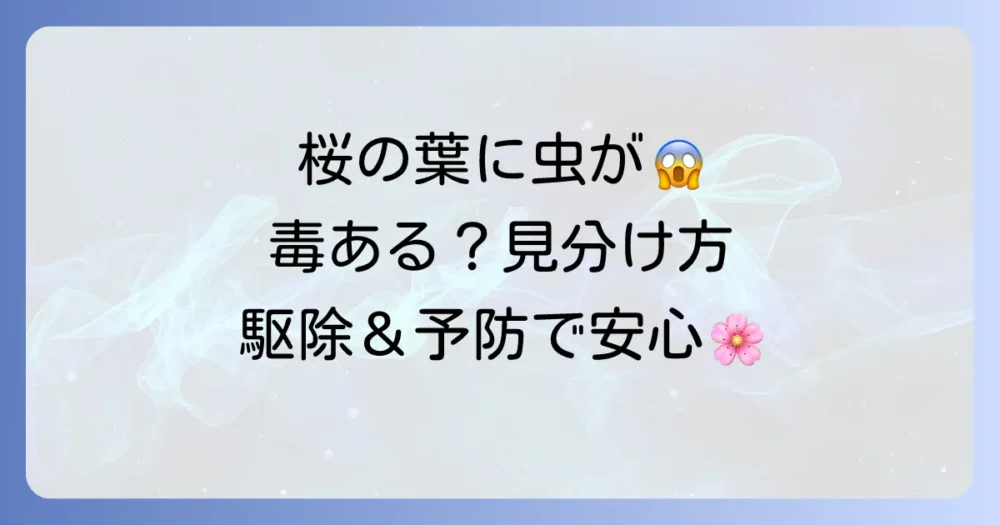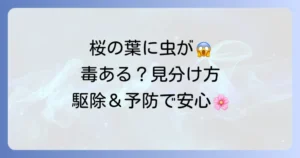大切に育てている桜の葉に、いつの間にか虫がついていてショックを受けた経験はありませんか?「この虫は何だろう?」「毒はあるの?」「どうやって駆除すればいいの?」そんな不安や疑問でいっぱいかもしれません。桜は美しい花を咲かせる一方で、実は害虫がつきやすい樹木でもあります。放置すると葉を食べ尽くされ、見た目が悪くなるだけでなく、桜の木自体が弱ってしまうことも。中には人に害を及ぼす毒を持つ虫もいるため、正しい知識と対策が不可欠です。
本記事では、桜の葉によくつく代表的な虫の種類から、安全で効果的な駆除方法、そして大切な桜を来年も美しく咲かせるための予防策まで、詳しく解説します。この記事を読めば、あなたを悩ませる虫の正体がわかり、きっと適切な対処法が見つかるはずです。
桜の葉を食べる代表的な虫
桜の葉に虫を見つけたら、まずはその正体を知ることが対策の第一歩です。ここでは、特に桜の木でよく見られる代表的な害虫を、詳しく解説します。見た目の特徴や発生時期を知って、早期発見・早期駆除につなげましょう。
本章で紹介する害虫は以下の通りです。
- アメリカシロヒトリ
- モンクロシャチホコ
- イラガ
- アブラムシ
アメリカシロヒトリ
アメリカシロヒトリは、戦後に日本へ侵入した外来種の蛾の幼虫です。 白い毛に覆われた見た目が特徴で、桜をはじめ、カキやプラタナスなど100種類以上の多くの広葉樹の葉を食害します。 繁殖力が非常に強く、年に2回(6月~7月と8月~9月頃)発生し、あっという間に増えてしまうため注意が必要です。
孵化したばかりの幼虫は、葉に白いクモの巣のような「巣網」を作って集団で生活するのが大きな特徴です。 この巣網を見つけたら、中にたくさんの幼虫がいるサイン。成長すると体長3cmほどになり、巣から分散して木全体の葉を食い荒らしてしまいます。 幸いなことに毒はなく、人に直接的な害はありませんが、その食欲旺盛さから樹木を丸裸にしてしまうこともある厄介な害虫です。
モンクロシャチホコ
モンクロシャチホコも、桜の葉を好んで食べる代表的な蛾の幼虫です。 「桜毛虫」とも呼ばれるほどで、夏から秋(8月~10月頃)にかけて大発生し、桜の木を丸坊主にしてしまうことがあります。
幼虫は成長すると体長5cmほどの黒い体に、黄白色の長い毛が生えた姿になります。 若い頃は集団で葉の裏にいますが、大きくなると分散して葉を食べ尽くします。 危険を感じると頭とお尻を反り返らせる特徴的なポーズをとることから、「シャチホコ」の名前がつきました。 この毛虫にも毒はありませんが、大発生すると桜の開花に影響が出ることもあるため、早めの対策が重要です。 ちなみに、この虫は桜の葉しか食べないため、食べると桜餅の風味がすると言われ、昆虫食ファンの間では知られた存在です。
イラガ
イラガの幼虫は、その独特な見た目と、触れると激しい痛みを引き起こすことから「電気虫」とも呼ばれる危険な害虫です。 体長は2.5cmほどで、体中に毒のあるトゲ(毒針毛)を持っています。
サクラやウメ、カキ、リンゴなど様々な樹木に発生し、年に1~2回、初夏から秋にかけて活動します。 葉の裏にいることが多く、気づかずに触れてしまう被害が後を絶ちません。刺されると電気が走ったような激痛があり、その後、かゆみや発疹が数日間続くこともあります。 絶対に素手で触らないようにしてください。 冬の間は、枝や幹にウズラの卵のような固い繭を作って越冬します。この繭を見つけたら、中に幼虫がいる証拠なので、冬の間に駆除しておくのが効果的です。
アブラムシ
アブラムシは、体長2~4mmほどの小さな虫で、新芽や若い葉、茎にびっしりと群がって汁を吸います。 体色は緑色や黒色など様々です。
春から秋にかけて、特に4月~6月と9月~10月に多く発生します。 驚異的な繁殖力を持ち、雌だけで子どもを産む「単為生殖」ができるため、あっという間に増殖します。 アブラムシの被害は、植物の汁を吸って生育を妨げるだけではありません。排泄物(甘露)が原因で、葉が黒いすすで覆われたようになる「すす病」を誘発することもあります。 直接的な毒はありませんが、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第、早急に駆除する必要があります。
【要注意】桜の葉につく毒を持つ危険な虫
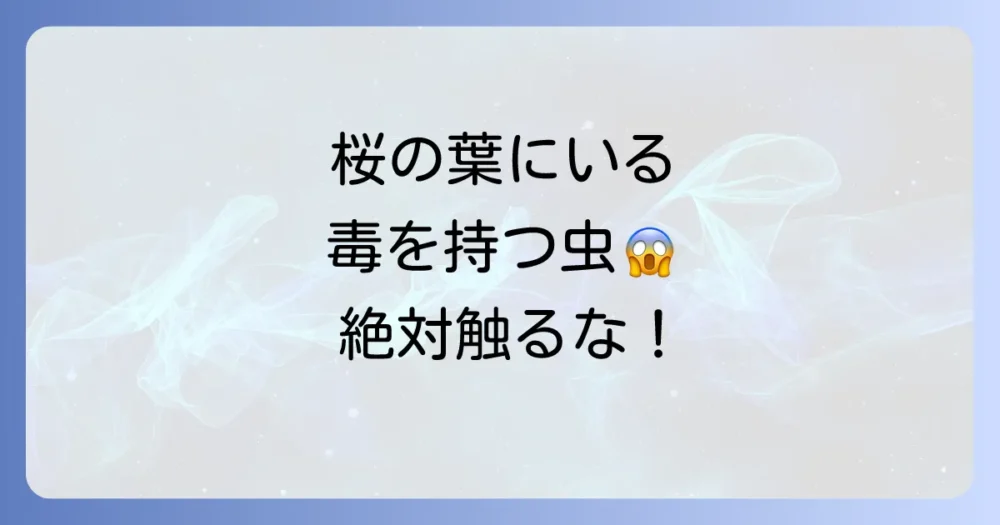
桜の木には、先ほど紹介したイラガのように、触れると危険な毒を持つ虫が他にもいます。見た目が似ている無毒の毛虫と間違えてしまうと、思わぬ被害にあう可能性があります。ここでは、特に注意が必要な毒毛虫の種類と、その見分け方について詳しく解説します。
本章で紹介する毒を持つ害虫は以下の通りです。
- ドクガ類(ドクガ、チャドクガ)
- ヒロヘリアオイラガ
ドクガ類(ドクガ、チャドクガ)
ドクガやその仲間であるチャドクガは、非常に危険な毒毛虫の代表格です。その名の通り、幼虫(毛虫)の時期だけでなく、卵、蛹、成虫(蛾)に至るまで、一生を通じて毒針毛(どくしんもう)を持っています。 この毒針毛は非常に細かく、風に乗って飛散することもあるため、直接触れなくても皮膚に付着して炎症を起こすことがあります。
ドクガの幼虫は体長3~4cmほどで、黒褐色にオレンジ色の模様が特徴です。 一方、チャドクガはツバキやサザンカを好みますが、桜につくこともあります。ドクガ類は4月~9月頃に発生し、特に若い幼虫は葉の裏に集団でいることが多いです。 もし見つけても、絶対に素手で触ったり、払いのけたりしないでください。 駆除する際は、肌の露出がないように完全防備で行う必要があります。
ヒロヘリアオイラガ
ヒロヘリアオイラガは、イラガの仲間で、こちらも強力な毒を持っています。幼虫は鮮やかな緑色で、体中にトゲのついた突起があり、見た目にも警戒心を抱かせる姿をしています。
イラгаと同様に、サクラ、カキ、カエデなどの葉を食べます。 刺されると激しい痛みが走り、赤く腫れ上がります。イラガとの大きな違いは、冬に作る繭にも毒がある点です。 樹皮についている繭を不用意に触ると、毒針毛が刺さって被害にあうことがあります。剪定作業中などに被害にあうケースも多いため、冬場の作業でも注意が必要です。見慣れない繭を見つけた場合は、安易に触らず、道具を使って慎重に取り除くようにしましょう。
桜の葉につく虫の駆除方法
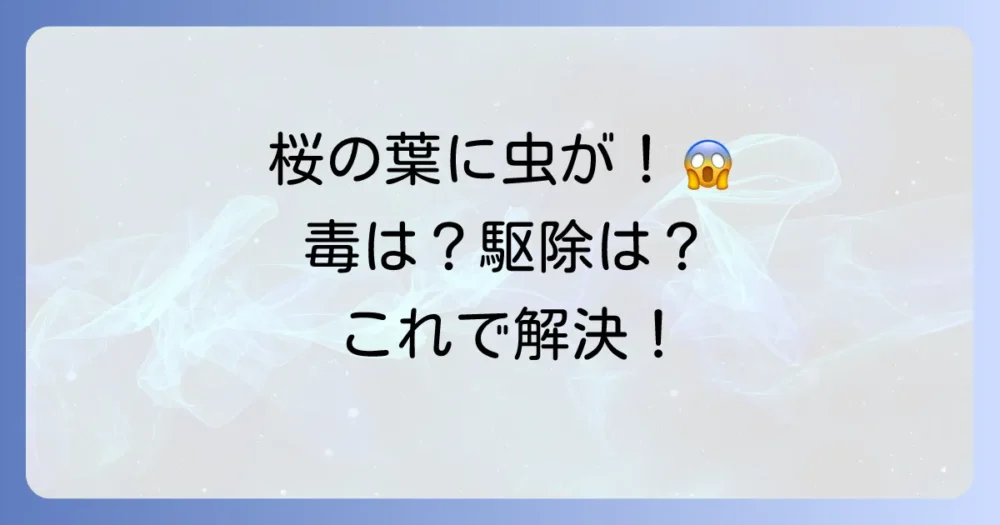
害虫を見つけたら、被害が広がる前に迅速に駆除することが大切です。駆除方法は、虫の種類や発生状況によって異なります。ここでは、自分でできる基本的な駆除方法から、専門業者に依頼する場合まで、具体的な方法を解説します。
本章で紹介する駆除方法は以下の通りです。
- 物理的に取り除く(捕殺)
- 殺虫剤・薬剤を使用する
- 専門の駆除業者に依頼する
物理的に取り除く(捕殺)
害虫の数が少ない初期段階であれば、物理的に取り除くのが最も手軽で確実な方法です。
アメリカシロヒトリのように巣網を作って集団でいる場合は、巣ごと枝を切り取ってしまうのが最も効果的です。 切り取った枝葉は、中の幼虫が出てこないようにビニール袋などに入れて口をしっかり縛り、踏みつぶすなどして確実に駆除してから燃えるゴミとして処分してください。
アブラムシが新芽にびっしりついている場合は、粘着テープで貼り付けて取り除いたり、歯ブラシなどでこすり落としたりする方法もあります。ただし、ドクガやイラガなどの毒毛虫にはこの方法は絶対に行わないでください。毒針毛が飛び散り、被害が拡大する恐れがあります。
殺虫剤・薬剤を使用する
虫が広範囲に分散してしまったり、数が多くて物理的な駆除が難しい場合は、殺虫剤の使用が有効です。園芸店やホームセンターでは、様々な種類の殺虫剤が販売されています。
スプレータイプの殺虫剤は、見つけた害虫に直接噴射できるので手軽です。アメリカシロヒトリやモンクロシャチホコなど、様々な害虫に効果のある製品を選びましょう。
木全体に薬剤を散布する場合は、水で薄めて使う乳剤タイプが適しています。スミチオン乳剤やオルトラン水和剤などが一般的です。 薬剤を使用する際は、必ず製品のラベルをよく読み、対象となる害虫や植物、使用方法を確認してください。 また、散布する際は風向きに注意し、近隣の住宅や洗濯物、通行人などに飛散しないよう十分に配慮しましょう。マスクや手袋、保護メガネを着用し、薬剤が体にかからないようにすることも重要です。
以下に代表的な薬剤をまとめました。
| 薬剤の種類 | 特徴 | 代表的な商品例 |
|---|---|---|
| スプレー剤 | 見つけた害虫に直接噴射でき手軽。即効性が高い。 | ベニカXファインスプレー(住友化学園芸)、アースガーデン ケムシ撃滅(アース製薬) |
| 乳剤・水和剤 | 水で希釈して噴霧器で散布。広範囲に対応可能。 | スミチオン乳剤、オルトラン水和剤、トレボン乳剤 |
| 固着剤 | 毒針毛を固めて飛散を防ぐ。チャドクガなどの駆除に有効。 | チャドクガ毒針毛固着剤(住友化学園芸) |
専門の駆除業者に依頼する
桜の木が高くて自分では作業ができない場合や、毒毛虫が大量に発生してしまって危険な場合、自分で駆除するのに抵抗がある場合は、無理せず専門の業者に依頼することをおすすめします。
造園業者や害虫駆除の専門業者、地域のシルバー人材センターなどが対応してくれます。 費用はかかりますが、専門的な知識と道具で安全かつ確実に駆除してもらえます。複数の業者から見積もりを取り、作業内容や料金を比較検討すると良いでしょう。自治体によっては、害虫駆除に関する相談窓口を設けていたり、防除用の機材を貸し出している場合もあるので、一度問い合わせてみるのも一つの方法です。
もう寄せ付けない!桜の葉の虫を予防する方法
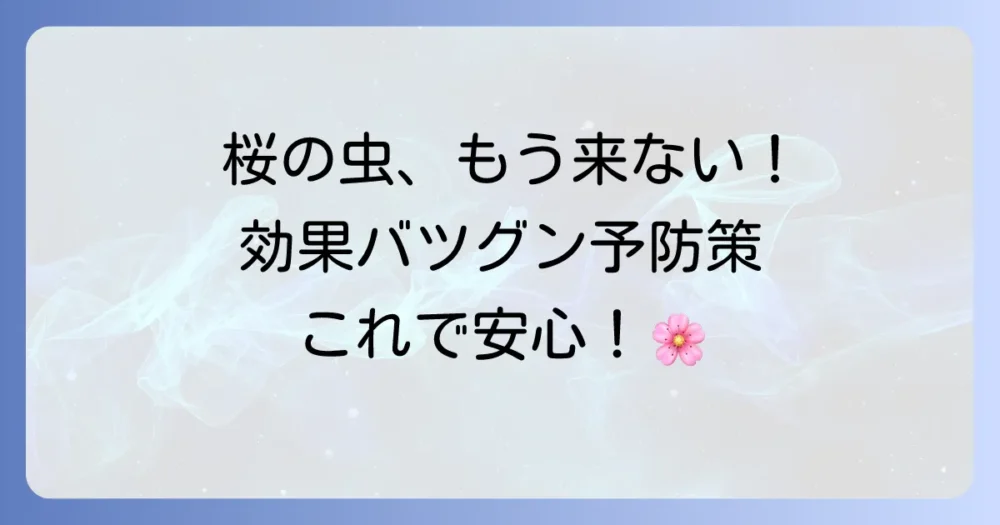
一度害虫を駆除しても、また次のシーズンに発生してしまっては意味がありません。大切なのは、害虫が発生しにくい環境を整えることです。ここでは、今日からできる効果的な予防策をいくつかご紹介します。
本章で紹介する予防方法は以下の通りです。
- 定期的な剪定で風通しを良くする
- 発生初期に薬剤を散布する
- 冬の間に越冬する害虫を駆除する
定期的な剪定で風通しを良くする
害虫予防の基本は、木の健康を保つことです。 そのために最も重要なのが「剪定」です。枝が混み合って日当たりや風通しが悪くなると、湿気がこもりやすくなり、病害虫が発生する絶好の環境となってしまいます。
不要な枝や枯れ枝、内側に向かって伸びる枝などを切り落とし、木全体の風通しと日当たりを良くしましょう。 これにより、害虫が隠れる場所を減らし、卵を産み付けられにくくする効果が期待できます。また、木の内部までよく見えるようになるため、害虫の早期発見にも繋がります。桜の剪定は、落葉後の冬期(11月~2月頃)が適期ですが、病害虫の被害にあった枝は、見つけ次第すぐに切り落とすようにしましょう。
発生初期に薬剤を散布する
毎年同じような害虫に悩まされている場合は、本格的な発生時期を迎える前に予防的に薬剤を散布するのが非常に効果的です。
例えば、アメリカシロヒトリやアブラムシは春から活動を始めます。 桜の新芽が出始める頃や、害虫が発生し始める少し前のタイミングで、浸透移行性のある殺虫剤(オルトラン粒剤など)を株元に撒いたり、予防効果のあるスプレー剤を散布しておくと、長期間にわたって害虫の発生を抑えることができます。
薬剤を使用する際は、駆除の時と同様に、使用方法をよく確認し、安全に配慮して行ってください。定期的な予防散布で、害虫が大量発生するリスクを大幅に減らすことができます。
冬の間に越冬する害虫を駆除する
冬は害虫の活動が止まる時期ですが、油断は禁物です。多くの害虫は、卵や蛹、繭の姿で冬を越しています。 この越冬している害虫を駆除することで、春以降の発生を効果的に抑えることができます。
イラガは枝や幹に固い繭を作って越冬します。 見つけたらヘラなどで削ぎ落として駆除しましょう。また、モンクロシャチホコは土の中で蛹になって冬を越します。 桜の木の根元を少し掘り返してみるのも良いでしょう。
また、木の幹に「こも巻き」をしておくのも伝統的な予防法の一つです。これは、秋に藁(わら)を幹に巻き付け、越冬のために降りてくる害虫を藁の中に誘い込み、春になる前に藁ごと焼却して駆除するという方法です。手間はかかりますが、薬剤を使わない環境に優しい予防策です。
桜の葉の異常は虫だけじゃない?似ている病気との見分け方
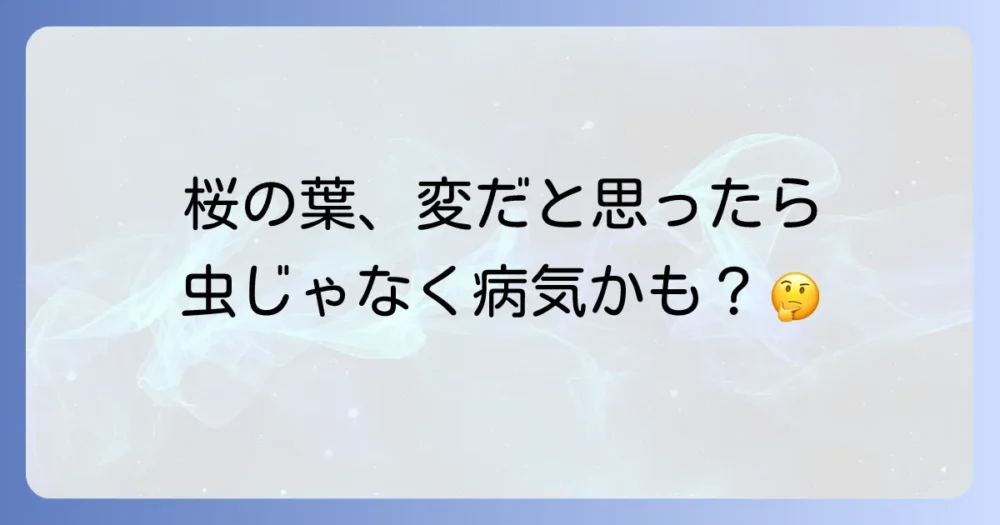
桜の葉に異変が見られたとき、すぐに「虫のせいだ」と決めつけてしまうのは早計かもしれません。中には、害虫の被害とよく似た症状を示す病気もあります。代表的なのが「うどんこ病」です。正しい対処をするためにも、病気の特徴を知っておきましょう。
本章で紹介する病気は以下の通りです。
- うどんこ病
- せん孔褐斑病
うどんこ病
うどんこ病は、その名の通り、葉の表面にうどんの粉をまぶしたような白いカビが生える病気です。 この白い粉はカビの菌糸や胞子で、植物の栄養を吸い取って生育を妨げます。
一見すると、カイガラムシの仲間がびっしりついているように見えることもありますが、触っても虫の感触はなく、粉っぽいのが特徴です。日当たりや風通しが悪いと発生しやすく、特に春から秋にかけての、乾燥して湿度が低い時期に広がりやすい傾向があります。
放置すると葉全体が白くなり、光合成ができなくなって黄色く枯れてしまいます。 症状が軽い初期段階であれば、重曹や食酢を水で薄めたものをスプレーすることで進行を抑えられる場合があります。 被害が広がった葉は元に戻らないため、見つけ次第切り取って処分し、専用の殺菌剤を散布してまん延を防ぎましょう。
せん孔褐斑病
せん孔褐斑病(せんこうかっぱんびょう)は、5月~6月頃に発生しやすい病気です。 最初は葉に褐色の小さな斑点ができ、やがてその部分が枯れて抜け落ち、まるで虫に食われたかのように小さな穴が空いてしまうのが特徴です。
虫食い跡と間違えやすいですが、穴の周りが褐色に変色している点で見分けることができます。この病気もカビが原因で、雨によって胞子が飛散し、感染が広がります。被害を受けた葉は光合成が十分にできなくなり、やがて黄色くなって落葉してしまいます。
この病気にかかってしまった葉は、見つけ次第すぐに取り除き、地面に落ちた葉もきれいに清掃して、菌の発生源をなくすことが重要です。その上で、ダコニール1000などの専用の殺菌剤を散布して、さらなる感染拡大を防ぎましょう。
よくある質問
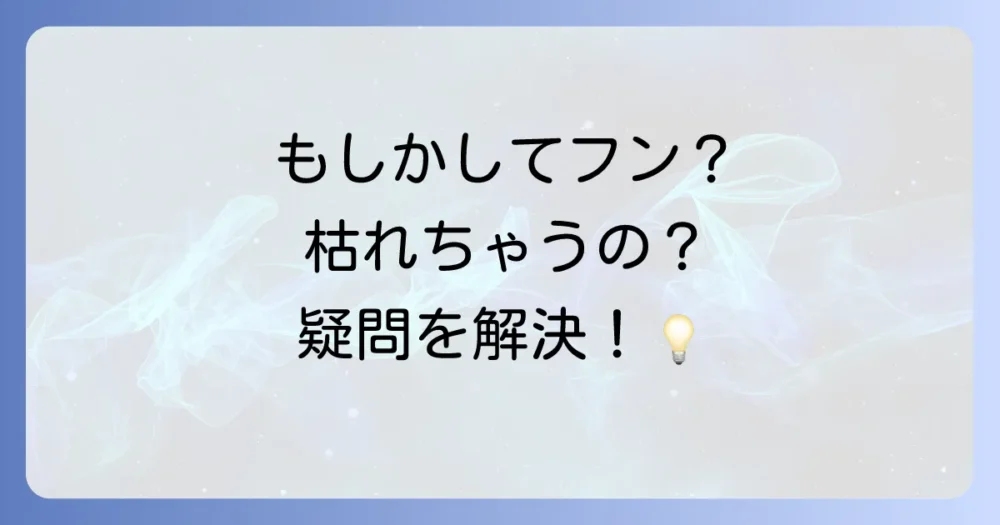
桜の木の下に黒い粒々が落ちているのは何ですか?
桜の木の下に黒や緑色の小さな粒々がたくさん落ちていたら、それは毛虫のフンである可能性が非常に高いです。 特にモンクロシャチホコなどが大量に発生していると、フンの量も相当なものになります。 上を見上げて、葉が食べられていないか、毛虫がいないかを確認してください。フンが落ちているということは、今まさに木の上で害虫が活動している証拠です。早急に駆除対策を検討しましょう。
殺虫剤はいつ撒くのが効果的ですか?
殺虫剤を撒くタイミングは、目的によって異なります。
駆除が目的の場合は、害虫を見つけ次第、すぐに散布するのが基本です。特に、アメリカシロヒトリやモンクロシャチホコなどの幼虫がまだ小さく、集団でいるうちに叩くのが最も効果的です。
予防が目的の場合は、害虫が発生し始める少し前の時期が狙い目です。アブラムシなら新芽が出る頃、アメリカシロヒトリなら発生時期である6月や8月の上旬に散布しておくと、発生を抑えることができます。 薬剤散布は、風のない穏やかな日の早朝か夕方に行うのがおすすめです。
虫が大量発生して葉がほとんどなくなってしまいました。桜は枯れてしまいますか?
アメリカシロヒトリやモンクロシャチホコなどによって葉をほとんど食べられてしまっても、すぐに木が枯れてしまうことは稀です。 樹勢は弱まりますが、落葉樹である桜は生命力が強く、翌春にはまた新しい葉を出してくれることがほとんどです。
しかし、被害が何年も続くと木が衰弱し、病気にかかりやすくなったり、最悪の場合枯れてしまうこともあります。葉がなくなったからといって諦めず、まずは残っている害虫を駆除し、来シーズンに向けて適切な剪定や施肥を行い、木の体力を回復させてあげることが大切です。
桜の毛虫に刺された(触れた)場合の対処法は?
万が一、ドクガやイラガなどの毒毛虫に触れてしまった場合は、絶対にこすらず、慌てずに対処することが重要です。
- まず、セロハンテープやガムテープなどをそっと皮膚に貼り、ゆっくり剥がして目に見えない毒針毛を取り除きます。
- 次に、流水と石鹸で優しく洗い流します。
- その後、かゆみや痛みがある場合は、抗ヒスタミン成分やステロイド成分が含まれた軟膏(市販の虫刺され薬など)を塗布します。
症状がひどい場合や、じんましん、吐き気などの全身症状が出た場合は、速やかに皮膚科を受診してください。
まとめ
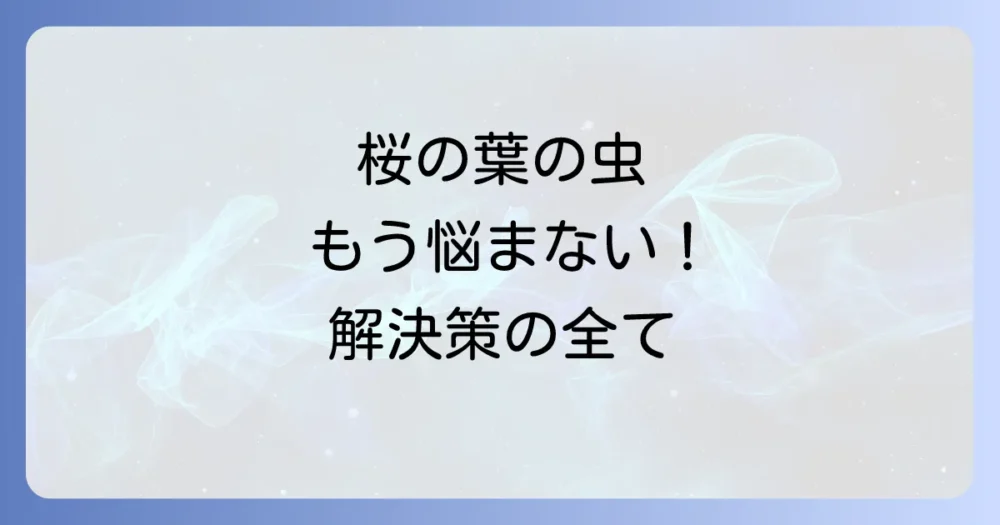
- 桜の葉にはアメリカシロヒトリやモンクロシャチホコがつきやすい。
- これらの毛虫に毒はないが、食欲旺盛で木を弱らせる。
- イラガやドクガ類は毒を持つため絶対に素手で触らないこと。
- 害虫の初期発見が駆除の鍵となる。
- アメリカシロヒトリは白い巣網が目印。
- 巣網は枝ごと切り取って駆除するのが最も効果的。
- 虫が分散したら殺虫剤の使用を検討する。
- 薬剤散布は風のない日に行い、周囲への配慮を忘れない。
- 毒毛虫に刺されたらこすらず、テープで毒針毛を取り除く。
- 予防には冬の剪定で風通しを良くすることが重要。
- イラガの繭など、越冬している害虫を冬の間に駆除する。
- 毎年発生する場合は、予防的な薬剤散布が効果的。
- 葉の異常はうどんこ病などの病気の可能性も考慮する。
- 木の下の黒い粒は毛虫のフンの可能性が高い。
- 高所や大量発生時は無理せず専門業者に相談する。