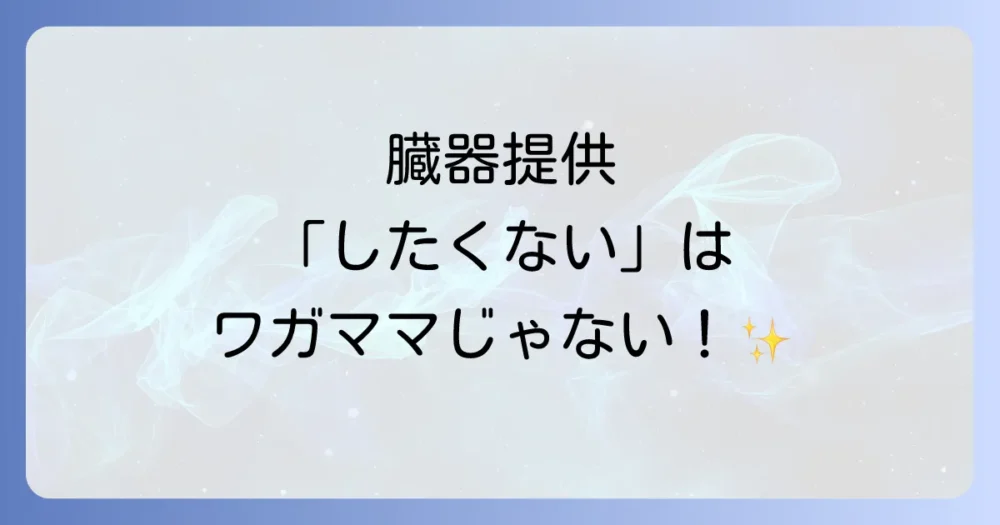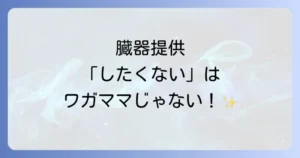「もしもの時、臓器提供したいと思いますか?」と聞かれて、すぐに「はい」と答えられない方は少なくないでしょう。臓器提供をしたくない、あるいはためらいを感じるという気持ちは、決して特別なことではありません。大切な自分の体の一部だからこそ、様々な思いが交錯するのは当然のことです。
本記事では、臓器提供をしたくないと感じる理由を深掘りし、その意思を明確に表示する方法、そして臓器提供に関する日本の現状について詳しく解説します。この記事を読めば、臓器提供に対するあなたの考えを整理し、自信を持って意思表示できるようになるでしょう。
臓器提供をしたくないと感じる主な理由
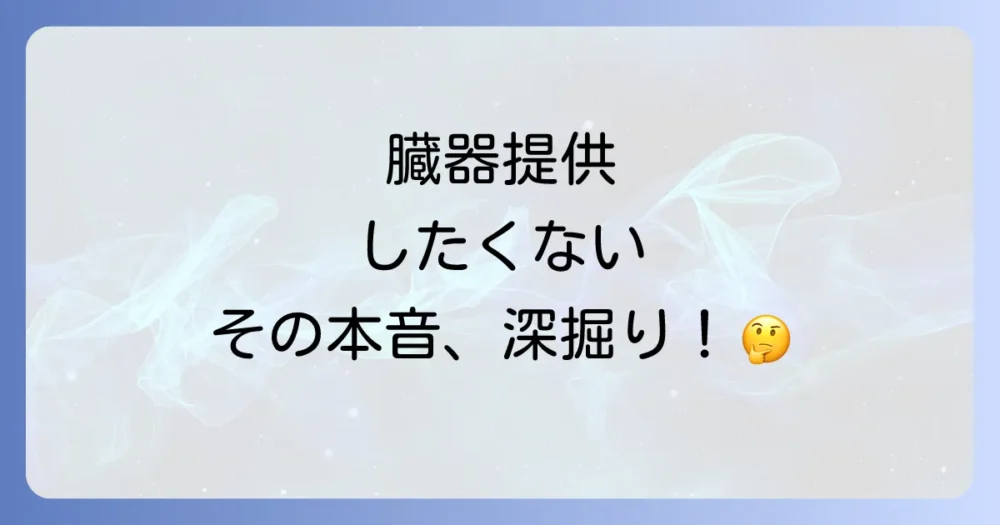
臓器提供に対して、ためらいや拒否感を抱くのはなぜでしょうか。その背景には、身体的なこと、精神的なこと、あるいは社会的なことまで、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、多くの方が「臓器提供をしたくない」と感じる主な理由について、多角的に掘り下げていきます。
身体的な完全性への思い
「自分の体を傷つけたくない」「最期は五体満足のままでいたい」という思いは、臓器提供をためらう非常に大きな理由の一つです。これは、古くから多くの文化圏で見られる死生観や身体観に根差しています。自分の身体は、単なる物質的な存在ではなく、自分という存在そのものであり、かけがえのないものであるという感覚です。
手術によって体にメスが入ることに抵抗を感じるのは自然な感情です。特に、亡くなった後に自分の身体が切り開かれることを想像すると、恐怖や不快感を覚える人もいるでしょう。また、臓器を摘出した後の体の状態を心配する声も聞かれます。摘出手術後は、傷跡が目立たないように丁寧に縫合され、外見上は分からなくなりますが、それでも「元のままの姿で家族とお別れしたい」という願いを持つことは、尊重されるべき個人の感情と言えます。
脳死判定への不信感や恐怖
臓器提供、特に心臓や肺などの提供は、脳死判定が前提となります。 しかし、この「脳死」という状態そのものに対する理解が十分に進んでいなかったり、判定基準に対して疑問や不信感を抱いていたりするケースが少なくありません。「脳死は本当に人の死なのか」「まだ生きているのではないか」という疑念は、提供を決断する上で大きな心理的障壁となります。
脳死は、脳幹を含む脳全体の機能が不可逆的に停止した状態であり、回復の見込みはありません。 人工呼吸器によって心臓は動いていますが、いずれは心停止に至ります。 しかし、体が温かく、心臓も動いている状態を「死」として受け入れることは、感情的に非常に難しいことです。 この脳死判定のプロセスや基準に対する不信感が、「万が一、誤って判定されたら」という恐怖につながり、臓器提供をためらわせる大きな要因となっているのです。
宗教・思想上の信条
個人の信じる宗教や思想も、臓器提供への意思決定に大きく影響します。世界には様々な宗教があり、死生観や身体に対する考え方も多岐にわたります。例えば、キリスト教の一部では臓器提供を「愛の行為」として肯定的に捉える一方、伝統的な仏教の一部では心身の全体性を重んじる考えから、脳死を人の死とすることに慎重な立場を示す宗派もあります。
また、特定の宗教を信仰していなくても、「死後は自然の摂理に任せたい」「人の手によって身体に手を加えるべきではない」といった個人の哲学や思想を持つ人もいます。これらの信条は、その人の生き方や価値観の根幹をなすものであり、非常に尊重されるべきです。自分の信条に反してまで臓器提供を行う必要はない、と考えるのは当然の権利と言えるでしょう。
家族への精神的・身体的負担への懸念
万が一の時、残された家族に大きな決断を迫り、精神的な負担をかけてしまうのではないかという懸念も、提供をためらう理由の一つです。本人の意思が不明な場合、臓器提供を行うかどうかの最終的な判断は家族に委ねられます。 愛する人を失った悲しみの中で、「臓器を提供するか否か」という重い決断を迫られることは、家族にとって計り知れないストレスとなります。
内閣府の世論調査では、本人の意思が不明な場合に家族が臓器提供の決断をすることに「負担を感じる」と答えた人は85.6%にものぼります。 また、臓器提供のプロセスには、脳死判定や摘出手術などで時間がかかり、家族が故人と過ごす最後の時間が制約される可能性もあります。 このような家族への負担を考えると、「提供したくない」という結論に至る人も少なくありません。
臓器提供に関する情報不足と漠然とした不安
臓器提供の仕組みや脳死判定のプロセスについて、正確な情報を得る機会は限られています。茨城県のアンケート調査では、意思表示をしていない理由として「自分の意思が決まらない、あるいは後で記入しようと思っていた」「臓器提供に抵抗感がある」といった回答が多く見られました。 これは、知識が不十分なために、漠然とした不安や抵抗感を抱いている人が多いことを示唆しています。
例えば、「臓器提供をすると、治療を早く打ち切られるのではないか」「臓器売買のようなことに関わってしまうのではないか」といった誤解や偏見も根強く存在します。臓器売買は法律で固く禁じられており、臓器の提供は公平な基準に基づいて行われます。 しかし、こうした事実が十分に知られていないことが、不信感や恐怖心を生み出し、「よく分からないから、とりあえず提供しないでおこう」という判断につながっている側面があるのです。
「提供しない」という意思を明確にする方法
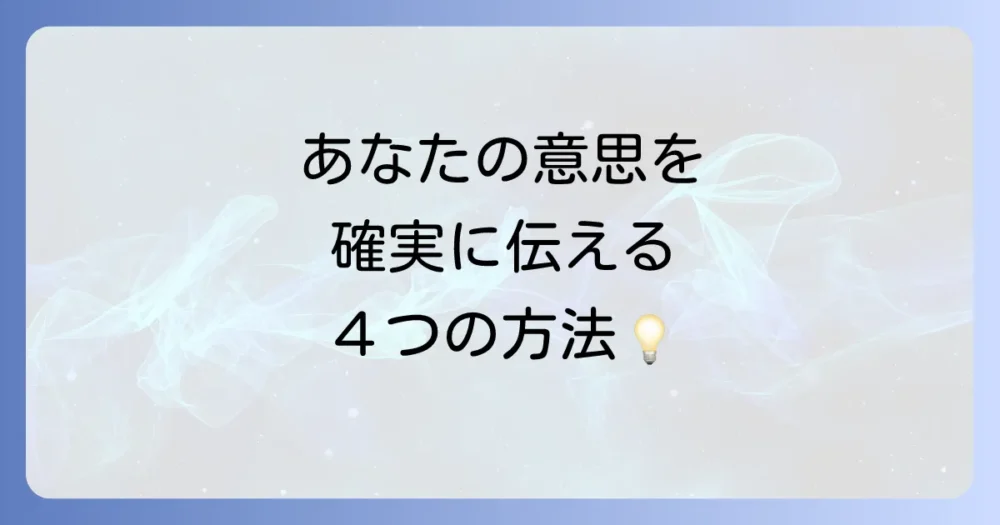
臓器提供をしたくないという意思は、提供したいという意思と同様に尊重されるべき大切な個人の権利です。その意思を明確に示しておくことは、万が一の時に自分の思いが確実に尊重されるため、そして残された家族の精神的な負担を軽減するためにも非常に重要です。ここでは、その具体的な方法について解説します。
意思表示カード・シールへの記入
最も手軽で広く知られている方法が、「臓器提供意思表示カード」やシールへの記入です。これらのカードは、市区町村の役場窓口、保健所、一部の病院や協力企業の店舗などで入手できます。
カードには、臓器を提供する意思の有無を選択する欄があります。ここで、「私は、臓器を提供しません」という選択肢に〇をつけ、署名と日付を記入することで、「提供しない」という明確な意思表示になります。 このカードを財布や定期入れなど、常に携帯するものに入れておくことで、万が一の際に医療関係者があなたの意思を確認することができます。記入した内容はいつでも変更可能です。
健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄
より身近なものとして、健康保険証(※)、運転免許証、マイナンバーカードの裏面にも臓器提供の意思表示欄が設けられています。 これらのカードは日常的に携帯することが多いため、意思表示の手段として非常に有効です。
記入方法は意思表示カードと同様で、「提供しない」という意思を選択し、署名を行います。特に運転免許証やマイナンバーカードは公的な身分証明書でもあるため、意思の証明力という点でも信頼性が高いと言えるでしょう。免許の更新時やマイナンバーカードの交付時に、改めて自分の意思を確認し、記入する習慣をつけることをおすすめします。
※健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終了し、マイナ保険証に移行する予定です。既存の保険証は有効期限まで使用可能です。
インターネットによる意思登録
パソコンやスマートフォンから、日本臓器移植ネットワーク(JOT)のウェブサイトを通じて意思登録を行うことも可能です。 この方法は、カードを紛失する心配がなく、24時間いつでもどこでも登録・変更ができるという利点があります。
登録サイトにアクセスし、画面の指示に従って個人情報と意思(提供しない意思を含む)を入力します。登録が完了すると、IDが記載された登録カードが郵送されます。 このシステムに登録しておくことで、医療機関がJOTに照会した際に、あなたの意思がより確実に確認されることになります。
家族への口頭での伝達と対話の重要性
書面での意思表示とあわせて、あるいは書面での表示が難しい場合でも、家族や親しい人に「自分は臓器提供をしたくない」という意思をはっきりと伝えておくことが極めて重要です。
2010年の臓器移植法改正により、本人の意思が不明な場合でも家族の承諾があれば臓器提供が可能になりました。 逆に言えば、あなたが「提供しない」という意思を明確に示していないと、残された家族がその判断を迫られることになります。 悲しみの中にいる家族に、そのような重い決断をさせないためにも、日頃から自分の死生観や臓器提供に対する考えを話し合っておくことが大切です。たとえ家族の中に提供に賛成の人がいても、あなたの意思を伝えておくことで、いざという時に尊重してもらいやすくなります。
日本の臓器提供の現状と課題
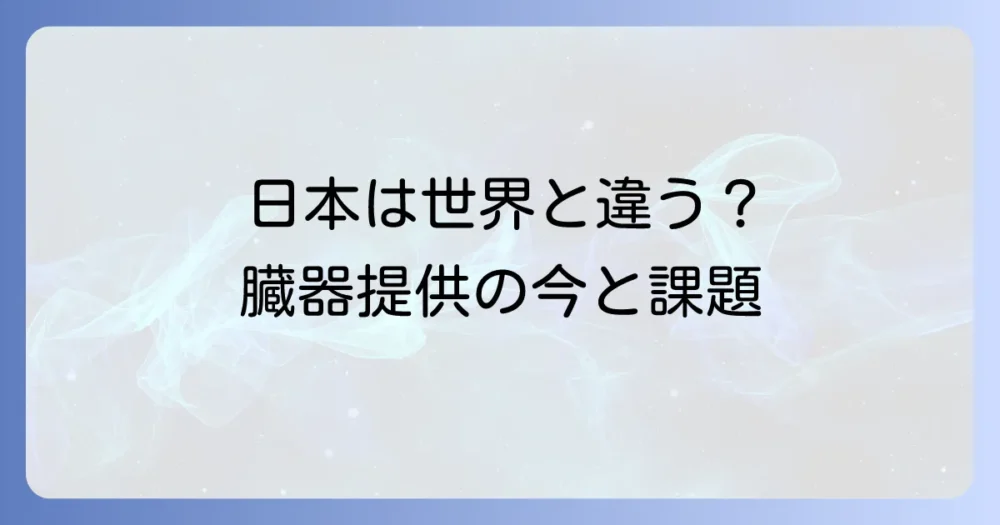
臓器提供について考える上で、日本の現状を知ることは欠かせません。法律や社会的な背景、そして実際にどれくらいの人が移植を待ち、提供が行われているのか。ここでは、データや法制度の側面から、日本の臓器提供が置かれている状況と、そこに見える課題について解説します。
臓器提供者(ドナー)数の国際比較
日本の臓器提供者(ドナー)数は、欧米諸国と比較して極めて少ないのが現状です。2022年のデータによると、人口100万人あたりの死体ドナーからの提供件数は、アメリカが41.6件、スペインが40.8件であるのに対し、日本はわずか0.62件です。 この差は、臓器移植を待つ患者さんにとって深刻な状況を生み出しています。
現在、日本で臓器移植を希望して登録している人は約16,000人いますが、1年間に移植を受けられるのはそのうちの約4%、約600人にとどまっています。 この背景には、本記事で見てきたような脳死に対する考え方の違いや、死について家族と話し合う文化が根付いていないことなどが指摘されています。
臓器移植法の変遷と意思表示の重要性
日本の臓器移植に関するルールは、「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」によって定められています。この法律は1997年に施行され、2010年7月に大きな改正が行われました。
改正前の法律では、脳死下での臓器提供には本人が生前に書面で提供の意思を表示していることが必須でした。しかし、改正後は本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供が可能になりました。 これは、提供の機会を増やすことを目的としたものですが、同時に「提供したくない」という意思表示の重要性をより高めることにもなりました。なぜなら、「提供しない」という意思が書面で示されていれば、家族が提供に同意したとしても、その意思が尊重され、臓器提供が行われることはないからです。
意思表示をしていない場合の家族の役割
前述の通り、本人が意思表示をしていない場合、その判断は家族に委ねられます。 家族は、故人が生前どのような考えを持っていたかを推し量り、臓器提供を行うかどうかを話し合って決めることになります。
しかし、これは家族にとって非常に重い決断です。内閣府の世論調査では、本人の意思が書面で示されていれば90.9%の家族がその意思を尊重すると回答しているのに対し、意思が不明な場合に提供の決断をすることに85.6%が「負担を感じる」と答えています。 このデータは、自分の意思を明確にしておくことが、残される家族の心理的負担を大きく軽減することを明確に示しています。
小児からの臓器提供の現状
2010年の法改正により、15歳未満の子どもからの脳死下での臓器提供も可能になりました。 これにより、心臓や肺の移植を必要とする多くの子どもたちに国内で移植を受ける道が開かれました。法改正後、18歳未満からの臓器提供は行われており、2022年9月までに66件の実績があります。
しかし、小児の臓器提供には、虐待を受けた子どもからは提供を行わないといった特別な配慮が必要であり、その判断は非常に慎重に行われます。 また、親が子どもの死を受け入れ、さらに臓器提供という決断をすることは、精神的に極めて過酷な状況であり、社会全体の深い理解とサポート体制が不可欠です。 小さな命をめぐるこの問題は、臓器提供が単なる医療技術の問題ではなく、深い倫理観や死生観と結びついていることを象徴しています。
よくある質問
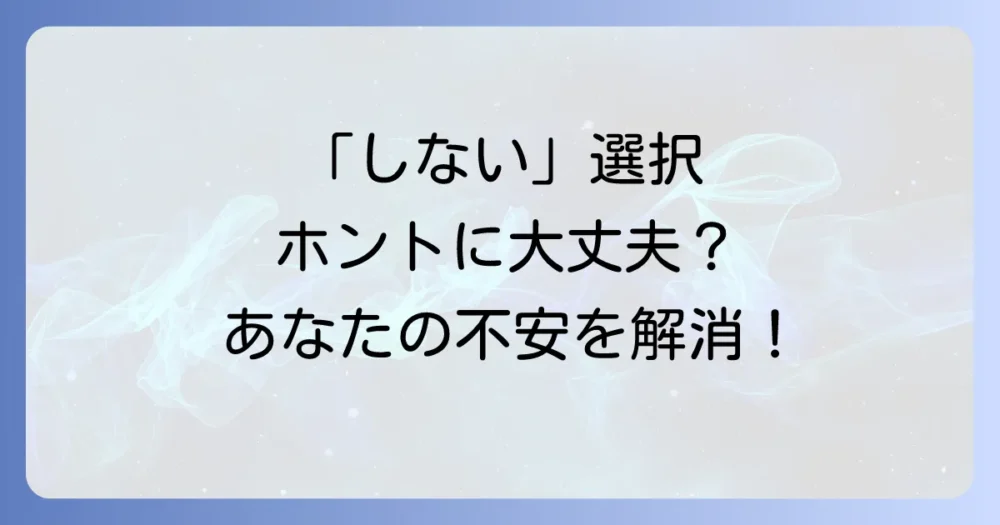
ここでは、臓器提供に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 臓器提供をしたくない場合、罰則などはありますか?
A1. 一切ありません。臓器提供は、あくまで個人の自由な意思に基づく善意の行為です。提供する・しないは完全に個人の選択に委ねられており、提供しないことを選択したからといって、何らかの不利益や罰則を受けることは絶対にありません。
Q2. 一度「提供しない」と意思表示したら、変更はできませんか?
A2. いつでも変更できます。臓器提供に関する意思は、何度でも変更することが可能です。意思表示カードや運転免許証の表示を書き換えたり、インターネットの登録情報を更新したりすることで、最新の意思が尊重されます。考えが変わった場合は、その都度、最新の意思表示をしておくことが大切です。
Q3. 家族が臓器提供に賛成している場合、自分の「提供しない」という意思は無視されますか?
A3. 無視されることはありません。あなたが書面で「臓器を提供しない」という意思を明確に表示している場合、それが最も尊重されます。 法律上、本人の拒否の意思表示がある場合は、たとえ家族全員が提供を希望したとしても、臓器提供は行われません。だからこそ、書面での意思表示が重要なのです。
Q4. 意思表示をしていない場合、勝手に臓器提供されることはありますか?
A4. 勝手に提供されることはありません。本人の意思が不明な場合は、必ず家族に臓器提供を行うかどうかの確認がなされます。家族の総意としての承諾がなければ、臓器提供が行われることはありません。 ただし、前述の通り、この判断は家族にとって大きな負担となる可能性があります。
Q5. 臓器提供にかかる費用は誰が負担するのですか?
A5. 臓器提供に関する費用(摘出手術など)を、提供者側(ドナーやその家族)が負担することは一切ありません。これらの費用は、移植を受ける側(レシピエント)が加入する医療保険で賄われます。また、提供に対する謝礼金などが支払われることもありません。 臓器提供は、あくまで無償の善意によるものです。
まとめ
- 臓器提供をしたくない理由は身体的、精神的、宗教的など様々である。
- 「体を傷つけたくない」という思いは自然な感情である。
- 脳死判定への不信感や恐怖も提供をためらう大きな要因となる。
- 個人の宗教や思想・信条は尊重されるべきである。
- 家族への精神的負担を懸念する声も多い。
- 情報不足による漠然とした不安も背景にある。
- 「提供しない」意思は意思表示カード等で明確に示せる。
- 健康保険証や運転免許証の意思表示欄も有効な手段である。
- インターネットでの意思登録も可能で、確実性が高い。
- 書面での表示に加え、家族に口頭で伝えておくことが非常に重要である。
- 日本の臓器提供者数は国際的に見て極めて少ない。
- 法改正により本人の意思不明でも家族の承諾で提供可能になった。
- 「提供しない」という書面での意思表示は家族の同意より優先される。
- 自分の意思表示は、残される家族の負担を大きく軽減する。
- 提供しないことを選択しても、何ら不利益はない。
新着記事