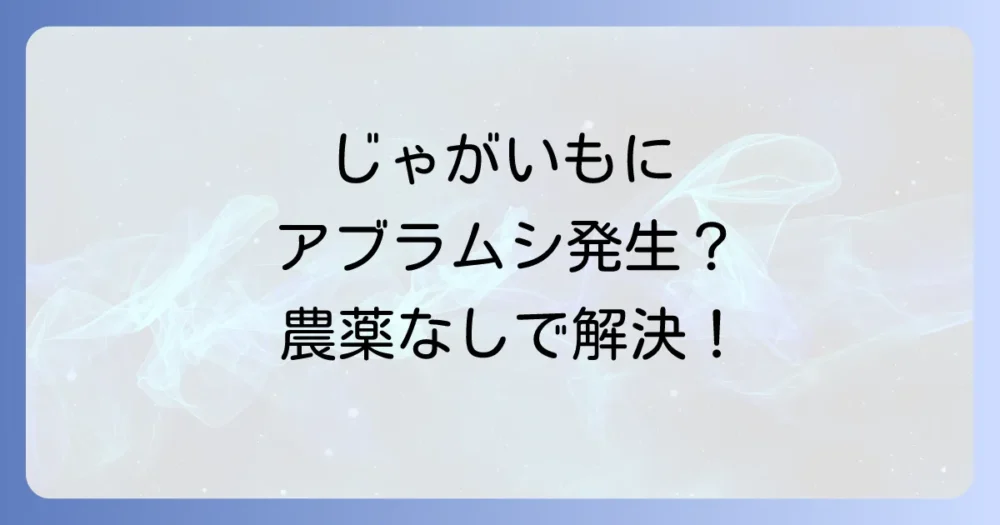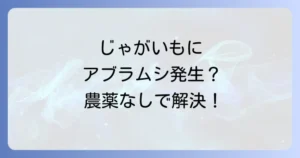家庭菜園で人気のじゃがいも。愛情を込めて育てているのに、新芽や葉の裏に緑色や黒色の小さな虫がびっしり…なんて経験はありませんか?その正体は、やっかいな害虫「アブラムシ」です。アブラムシは、じゃがいもの生育を妨げるだけでなく、病気を媒介することもあるため、見つけたらすぐに対策が必要です。本記事では、じゃがいもにアブラムシが発生する原因から、農薬を使わない安全な駆除方法、効果的な予防策まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。大切なじゃがいもをアブラムシから守り、秋にはたくさんの収穫を目指しましょう!
まずは知っておきたい!じゃがいもにアブラムシが発生する主な原因
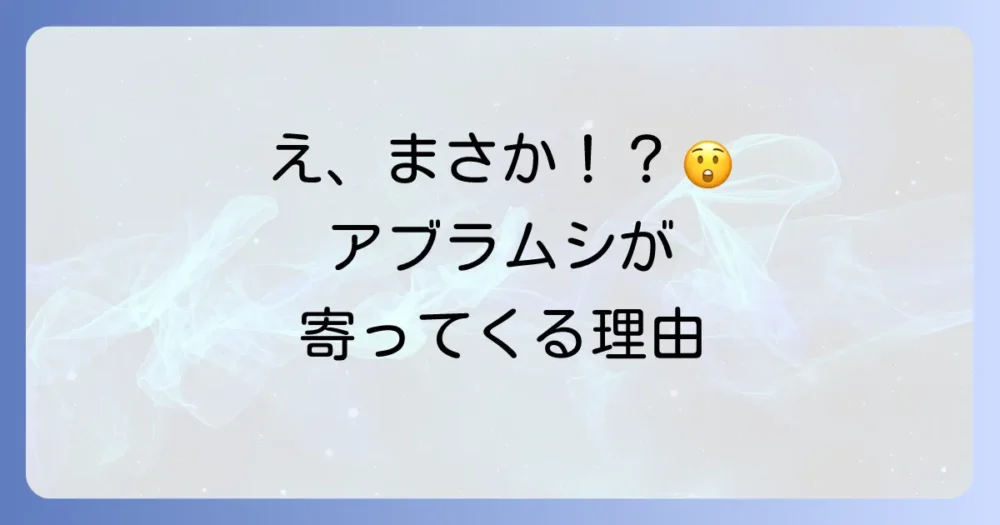
じゃがいもにアブラムシがびっしりと付いているのを見ると、どこからやってきたのだろうと不思議に思いますよね。アブラムシの発生には、いくつかの原因が考えられます。原因を知ることで、効果的な対策を立てることができます。
この章では、じゃがいもにアブラムシが発生する主な原因について解説します。
- 窒素肥料の与えすぎ
- 風通しの悪い環境
- 周囲の雑草からの飛来
窒素肥料の与えすぎ
じゃがいもを元気に育てようと、良かれと思って与えた肥料が、実はアブラムシを呼び寄せる原因になっているかもしれません。特に、窒素成分の多い肥料を過剰に与えると、植物の体内でアミノ酸が増えすぎます。アブラムシはこのアミノ酸が大好物なため、窒素過多になったじゃがいもは、アブラムシにとって魅力的なごちそうに見えてしまうのです。
肥料を与える際は、パッケージに記載されている適量を守ることが大切です。特に、葉や茎を育てる効果のある窒素肥料は、与えすぎに注意しましょう。バランスの取れた肥料を適切に使うことが、アブラムシの発生を抑える第一歩です。
風通しの悪い環境
じゃがいもの株間が狭かったり、葉が密集して茂りすぎたりすると、風通しが悪くなります。風通しが悪く、湿気がこもりがちな場所は、アブラムシにとって非常に快適な住処となります。 また、密集していると、アブラムシが他の株へ移動しやすく、あっという間に被害が広がってしまう原因にもなります。
じゃがいもを植え付ける際には、適切な株間を確保することが重要です。 生育して葉が混み合ってきたら、適度に「芽かき」や剪定を行い、株元まで風が通るようにしてあげましょう。 日当たりと風通しを良くすることで、アブラムシが住み着きにくい環境を作ることができます。
周囲の雑草からの飛来
畑やプランターの周りに生えている雑草も、アブラムシの発生源となります。特に、ヨモギやタンポポなど、アブラムシが好む雑草が生えていると、そこから羽の生えたタイプのアブラムシが飛来し、じゃがいもに被害を及ぼすことがあります。
畑の周りの除草をこまめに行うことは、アブラムシ対策の基本です。 雑草を放置していると、アブラムシの温床になるだけでなく、他の病害虫の原因にもなります。じゃがいもだけでなく、栽培環境全体を清潔に保つことを心がけましょう。
【今すぐできる】じゃがいものアブラムシ駆除方法5選
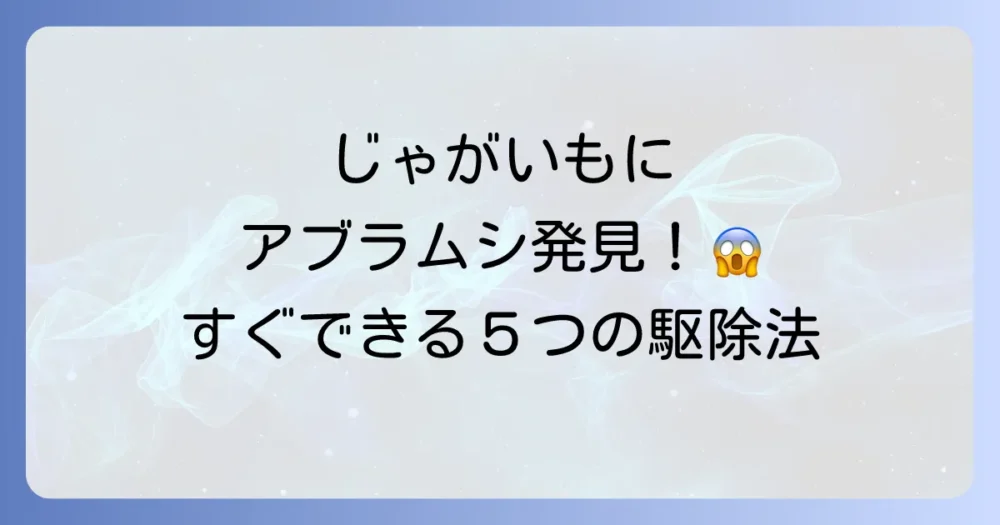
じゃがいもにアブラムシを見つけたら、数が少ないうちに駆除することが大切です。繁殖力が非常に高いため、放置するとあっという間に増えてしまいます。 ここでは、ご家庭で今すぐ実践できるアブラムシの駆除方法を、手軽なものから順にご紹介します。
- 物理的に取り除く(テープや歯ブラシ)
- 水で洗い流す
- 【農薬を使わない】牛乳スプレーで窒息させる
- 【農薬を使わない】木酢液・食酢スプレーで忌避する
- 【最終手段】効果的な農薬・殺虫剤を使う
物理的に取り除く(テープや歯ブラシ)
アブラムシの数がまだ少ない初期段階であれば、物理的に取り除くのが最も手軽で確実な方法です。粘着テープやガムテープをペタペタと貼り付けて捕獲したり、使い古しの歯ブラシなどで優しくこすり落としたりします。
この方法のメリットは、なんといっても安全でコストがかからない点です。ただし、じゃがいもの新芽や柔らかい葉を傷つけないように、力加減には注意が必要です。葉の裏までしっかりチェックして、見つけ次第、地道に取り除きましょう。
水で洗い流す
ホースのシャワーや霧吹きを使って、勢いよく水をかけてアブラムシを洗い流す方法も効果的です。 アブラムシは水に弱いため、直接水流を当てることで、じゃがいもから剥がし落とすことができます。
この方法は、広範囲にアブラムシが発生してしまった場合に特に有効です。ただし、あまり水圧を強くしすぎると、植物を傷めてしまう可能性があるので注意しましょう。また、洗い流したアブラムシが地面に落ちて、再び登ってくることもあるため、定期的に行うことが大切です。
【農薬を使わない】牛乳スプレーで窒息させる
農薬を使いたくない方におすすめなのが、牛乳を使った駆除方法です。牛乳を水で薄めたものをスプレーでアブラムシに吹きかけると、牛乳が乾く過程で膜を作り、アブラムシの呼吸器官である気門を塞いで窒息死させることができます。
牛乳スプレーの作り方と使い方
作り方はとても簡単です。牛乳と水を1:1の割合で混ぜるか、牛乳を10倍程度に水で薄めてスプレーボトルに入れるだけです。 出来上がった牛乳スプレーを、アブラムシが発生している場所に、葉の裏までまんべんなく吹きかけます。
使用する際の注意点
牛乳スプレーは、必ず晴れた日の午前中に散布しましょう。 散布後、牛乳がしっかりと乾くことで効果を発揮します。散布した後は、牛乳が腐敗して悪臭を放ったり、カビの原因になったりするのを防ぐため、必ずその日のうちに水でしっかりと洗い流してください。 また、牛乳アレルギーのある方は取り扱いに注意が必要です。
【農薬を使わない】木酢液・食酢スプレーで忌避する
木酢液や食酢には、アブラムシが嫌う匂いや成分が含まれており、忌避効果が期待できます。 これらは殺虫効果があるわけではありませんが、アブラムシを寄せ付けにくくする予防策として有効です。
木酢液・食酢スプレーの作り方と使い方
木酢液や食酢を、製品の指示に従って水で希釈し、スプレーボトルに入れます。一般的に、木酢液は200~500倍、食酢は10倍程度に薄めて使用します。 これをじゃがいもの葉の表裏や茎に定期的に散布します。唐辛子やニンニクを一緒に漬け込むと、さらに効果が高まるとも言われています。
期待できる効果と注意点
これらのスプレーは、あくまでアブラムシを「寄せ付けにくくする」ためのものです。すでに大量発生してしまったアブラムシを駆除する力は弱いため、発生初期の予防策として活用するのがおすすめです。 使用する際は、必ず規定の希釈倍率を守ってください。濃度が濃すぎると、じゃがいもの葉を傷めてしまう「薬害」が起こる可能性があります。
【最終手段】効果的な農薬・殺虫剤を使う
いろいろな方法を試してもアブラムシの勢いが止まらない、大量に発生して手に負えない、という場合には、農薬の使用も検討しましょう。じゃがいもに使用できるアブラムシ向けの農薬は、ホームセンターなどで手軽に入手できます。
農薬選びのポイント
農薬を選ぶ際は、必ず「じゃがいも」と「アブラムシ類」に適用があることを確認してください。 また、天然成分由来で収穫前日まで使えるものや、散布回数に制限がないものなど、様々な種類があります。 ご自身の栽培スタイルや、収穫までの期間を考慮して選びましょう。例えば、アース製薬の「やさお酢」や住友化学園芸の「ベニカマイルドスプレー」などは、食品成分を由来としているため、家庭菜園でも使いやすい製品です。
おすすめの農薬
代表的な農薬には以下のようなものがあります。使用前には必ずラベルをよく読み、使用方法、希釈倍率、使用時期、使用回数を守って正しく使いましょう。
- スプレータイプ: 手軽にそのまま使えるタイプ。発生した場所にピンポイントで散布できます。
- 希釈タイプ: 水で薄めて噴霧器などで散布するタイプ。広範囲に効率よく散布できます。(例:スタークル顆粒水溶剤、モスピラン顆粒水溶剤など)
- 粒剤タイプ: 株元にまくことで、成分が根から吸収され、植物全体に効果が広がるタイプ。効果が長期間持続します。(例:アドマイヤー1粒剤など)
被害を未然に防ぐ!じゃがいものアブラムシ予防策
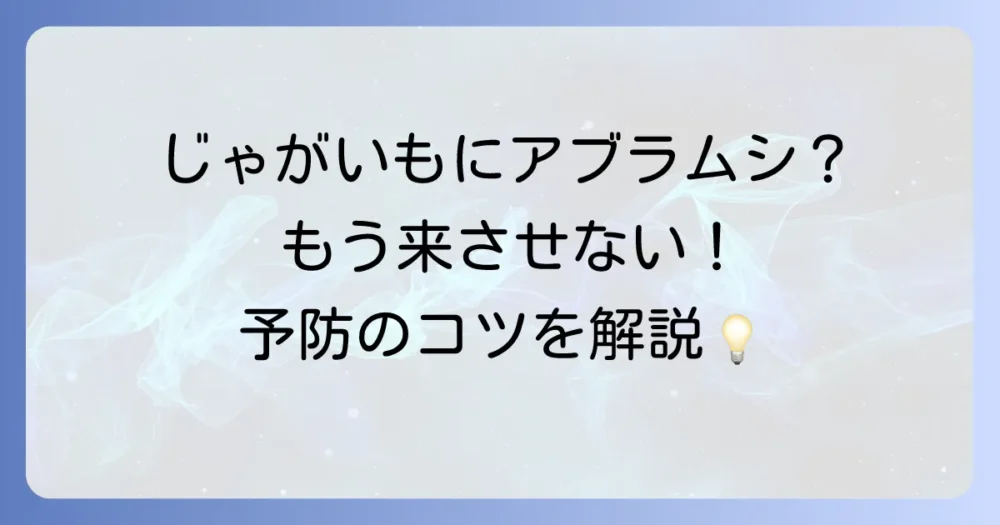
アブラムシの被害を最小限に抑えるには、発生してから駆除するよりも、そもそも発生させない「予防」が非常に重要です。 ちょっとした工夫で、アブラムシが寄り付きにくい環境を作ることができます。ここでは、誰でも簡単にできるアブラムシの予防策をご紹介します。
- シルバーマルチやキラキラテープで飛来を防ぐ
- コンパニオンプランツを活用する
- 天敵(テントウムシなど)を味方につける
- 適切な施肥管理と風通しの確保
シルバーマルチやキラキラテープで飛来を防ぐ
アブラムシは、キラキラと乱反射する光を嫌う性質があります。 この性質を利用したのが、シルバーマルチやアルミホイル、キラキラ光る防鳥テープなどです。じゃがいもを植え付ける際に畝をシルバーマルチで覆ったり、支柱にキラキラテープを張ったりすることで、アブラムシが飛来するのを物理的に防ぐ効果が期待できます。
シルバーマルチは、アブラムシ除けだけでなく、地温の上昇を抑えたり、雑草の発生を防いだり、雨による土の跳ね返りを防いで病気を予防したりと、様々なメリットがあります。 手軽にできる効果的な予防策として、ぜひ取り入れてみてください。
コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることでお互いによい影響を与え合う植物のことです。アブラムシ対策として有名なコンパニオンプランツには、マリーゴールドやカモミール、ネギ類などがあります。
マリーゴールドの独特の香りには、アブラムシを遠ざける効果があると言われています。 また、ネギ類も同様に忌避効果が期待できます。これらの植物をじゃがいもの近くに植えることで、アブラムシが寄り付きにくい環境を作ることができます。見た目も華やかになり、一石二鳥の対策です。
天敵(テントウムシなど)を味方につける
自然界には、アブラムシを食べてくれる頼もしい味方がいます。その代表格がテントウムシです。 テントウムシの成虫も幼虫も、アブラムシを大好物としてたくさん捕食してくれます。その他にも、ヒラタアブの幼虫やクサカゲロウの幼虫、アブラバチなどもアブラムシの天敵です。
これらの天敵を畑に呼び込むためには、農薬の使用を控えることが大切です。 殺虫剤は、害虫だけでなく天敵などの益虫にも影響を与えてしまいます。天敵が活動しやすい環境を整えることで、自然の力でアブラムシの数をコントロールすることができます。
適切な施肥管理と風通しの確保
アブラムシの発生原因でも触れましたが、窒素肥料の与えすぎと風通しの悪さは、アブラムシの発生を助長します。 予防の観点からも、この2点は非常に重要です。
肥料は規定量を守り、特に窒素過多にならないように注意しましょう。 また、株間を適切にとり、葉が茂りすぎたら剪定して風通しを良く保つことを常に心がけてください。 これらはアブラムシだけでなく、様々な病害虫の予防につながる、健康なじゃがいもを育てるための基本となります。
放置は危険!アブラムシが引き起こす二次被害
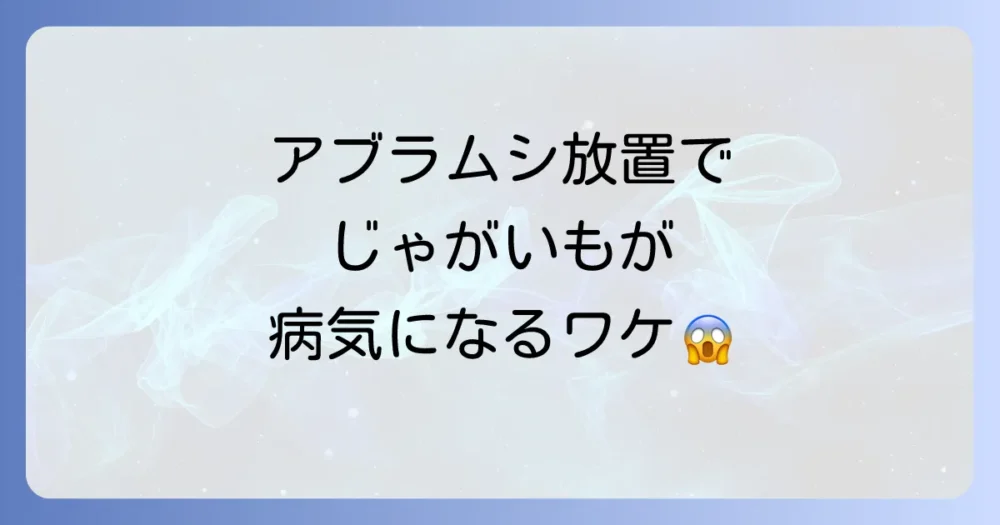
「アブラムシは小さい虫だから、少しぐらいなら大丈夫だろう」と油断してはいけません。アブラムシを放置すると、直接的な被害だけでなく、さらに深刻な二次被害を引き起こす可能性があります。大切なじゃがいもを守るためにも、アブラムシがもたらすリスクを正しく理解しておきましょう。
- 生育不良と収穫量の減少
- 排泄物が原因の「すす病」
- ウイルスを媒介する「モザイク病」
生育不良と収穫量の減少
アブラムシは、じゃがいもの葉や茎に口針を突き刺し、養分(師管液)を吸い取って生活しています。 少数であれば大きな影響はありませんが、大量に発生すると、じゃがいもは栄養分を奪われてしまいます。その結果、株全体の生育が悪くなり、葉が縮れたり、元気がなくなったりします。 養分が不足すれば、地中のイモの肥大も悪くなり、最終的には収穫量の減少につながってしまうのです。
排泄物が原因の「すす病」
アブラムシは、養分を吸った後、「甘露(かんろ)」と呼ばれる甘くてベタベタした排泄物を出します。 この甘露が葉や茎に付着すると、それを栄養源にして黒いカビが発生することがあります。これが「すす病」です。
すす病になると、葉の表面が黒いすすで覆われたようになり、見た目が悪くなるだけでなく、光合成が妨げられてしまいます。 光合成が十分にできないと、じゃがいもは成長するためのエネルギーを作れなくなり、さらなる生育不良を引き起こします。また、甘露はアリを誘引する原因にもなります。
ウイルスを媒介する「モザイク病」
アブラムシがもたらす最も深刻な被害の一つが、ウイルス病の媒介です。 アブラムシは、ウイルスに感染した植物の汁を吸った後、健康なじゃがいもに移動して汁を吸うことで、ウイルスを次々と広めてしまいます。じゃがいもで特に問題となるのが「モザイク病」です。
モザイク病に感染すると、葉に緑色の濃淡のまだら模様(モザイク症状)が現れたり、葉が縮れたり、株全体が萎縮したりします。 一度ウイルス病に感染してしまうと、治療するための有効な薬剤はなく、株を抜き取って処分するしかありません。 そのため、ウイルスを運んでくるアブラムシを、そもそも畑に侵入させない、増やさない対策が極めて重要になるのです。
よくある質問
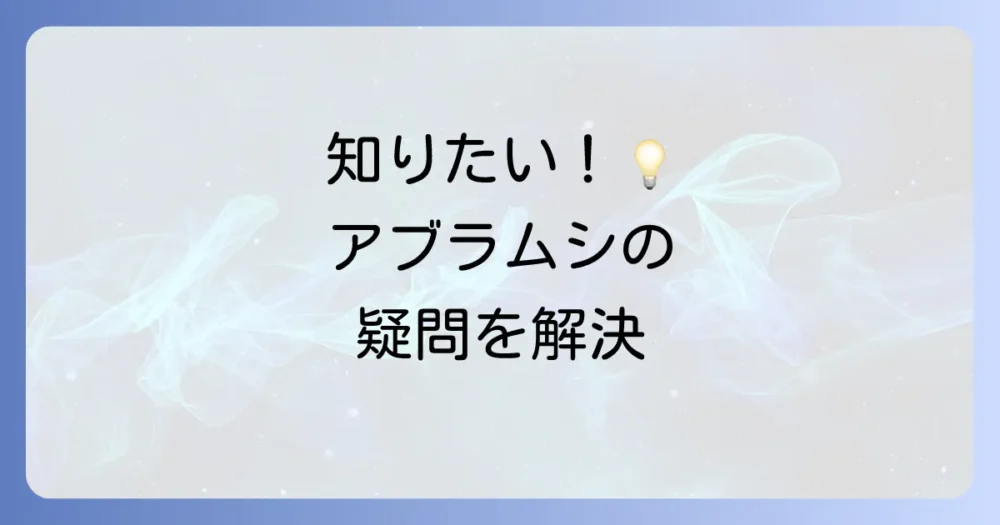
アブラムシ対策にテントウムシを連れてきてもいい?
テントウムシはアブラムシを捕食してくれる益虫ですが、注意点があります。テントウムシによく似た「ニジュウヤホシテントウ(テントウムシダマシ)」という害虫が存在します。 この虫はアブラムシを食べず、じゃがいもの葉を網目状に食害します。益虫のナナホシテントウは背中がツルツルしているのに対し、害虫のニジュウヤホシテントウは細かい毛が生えていて光沢がありません。見分けた上で、益虫のテントウムシを畑に放すのは有効な対策です。
牛乳スプレーはなぜ効くの?腐らない?
牛乳スプレーがアブラムシに効くのは、牛乳が乾燥する際にできる膜が、アブラムシの体の側面にある呼吸するための穴(気門)を塞ぎ、窒息させるためです。 殺虫成分ではないため、比較的安全に使えるのがメリットです。ただし、散布した牛乳をそのままにしておくと、乾いた後も腐敗して悪臭を放ったり、カビや他の病気の原因になったりすることがあります。 そのため、散布した後は必ず水で洗い流すことが重要です。
木酢液に殺虫効果はある?
木酢液には、アブラムシを直接殺すような強い殺虫効果は期待できません。 主な効果は、木酢液独特の燻製のような匂いによる「忌避効果」、つまりアブラムシを寄せ付けにくくする効果です。 そのため、すでに大量発生してしまったアブラムシを駆除する目的ではなく、発生を予防する目的で定期的に散布するのが効果的な使い方です。
アブラムシとアリの関係は?
畑でアリをよく見かける場合、近くにアブラムシがいる可能性があります。アブラムシは、植物の汁を吸った後に出す甘い排泄物「甘露」をアリに提供します。その見返りとして、アリはアブラムシの天敵であるテントウムシなどを追い払い、アブラムシを守ります。 このような「共生関係」にあるため、アリを駆除することも間接的なアブラムシ対策につながります。
じゃがいもの花にアブラムシが集中するのはなぜ?
じゃがいもの花や新芽の部分は、細胞分裂が活発で、柔らかく栄養分が豊富です。 アブラムシは、そうした柔らかくて栄養価の高い部分を好んで吸汁するため、特に花や新芽に集まりやすい傾向があります。 花にアブラムシが群がっているのを見つけたら、株全体に広がっている可能性が高いので、早急に対処しましょう。
まとめ
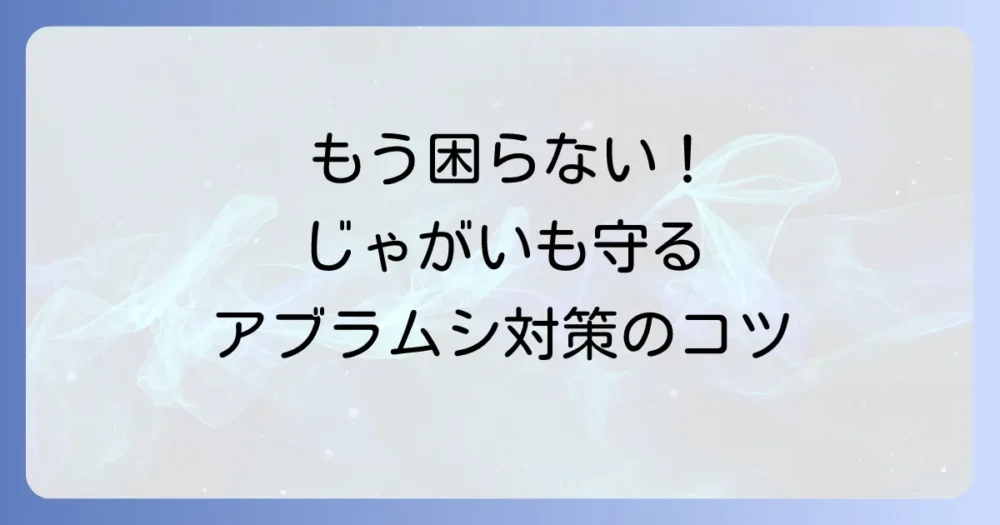
- じゃがいものアブラムシは早めの対策が肝心です。
- 窒素肥料のやり過ぎはアブラムシを呼び寄せます。
- 風通しを良くすることが基本的な予防策になります。
- 初期のアブラムシはテープや水で物理的に除去できます。
- 農薬を使わないなら牛乳スプレーが効果的です。
- 牛乳スプレー使用後は必ず洗い流しましょう。
- 木酢液や食酢は殺虫より忌避効果を期待します。
- シルバーマルチはアブラムシの飛来を防ぎます。
- テントウムシはアブラムシの頼れる天敵です。
- ニジュウヤホシテントウは害虫なので注意が必要です。
- アブラムシは「すす病」の原因になります。
- 最も怖いのはウイルス病「モザイク病」の媒介です。
- モザイク病は治療法がなく、株を抜くしかありません。
- 手に負えない場合は適切な農薬を使いましょう。
- 予防と早期発見で、じゃがいもを守りましょう。