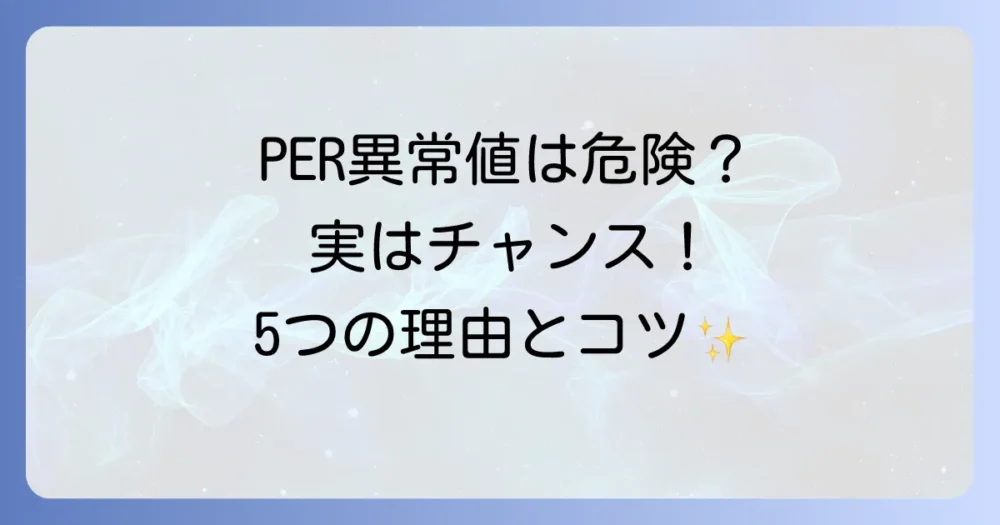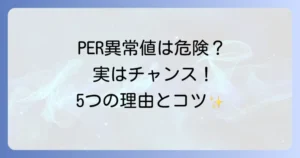株式投資で銘柄を探していると、PER(株価収益率)が100倍を超えるなど、異常に高い数値の企業を見かけることがあります。「この株は高すぎるのでは?」「バブル状態なのでは?」と不安に感じ、投資をためらってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、PERが異常に高いことは、必ずしも「割高で危険」というサインではありません。その背景には、市場の大きな期待や企業特有の事情が隠されていることが多いのです。その理由を正しく理解しなければ、大きな成長のチャンスを逃してしまう可能性もあります。
本記事では、PERが異常に高くなる5つの主な理由を、初心者の方にも分かりやすく解説します。さらに、PERが高い銘柄に投資する際の注意点や、将来性のある銘柄を見抜くための具体的な判断のコツまで詳しくご紹介します。この記事を読めば、PERの高さに惑わされず、自信を持って投資判断ができるようになるでしょう。
そもそもPERとは?おさらいしておきたい基本のキ
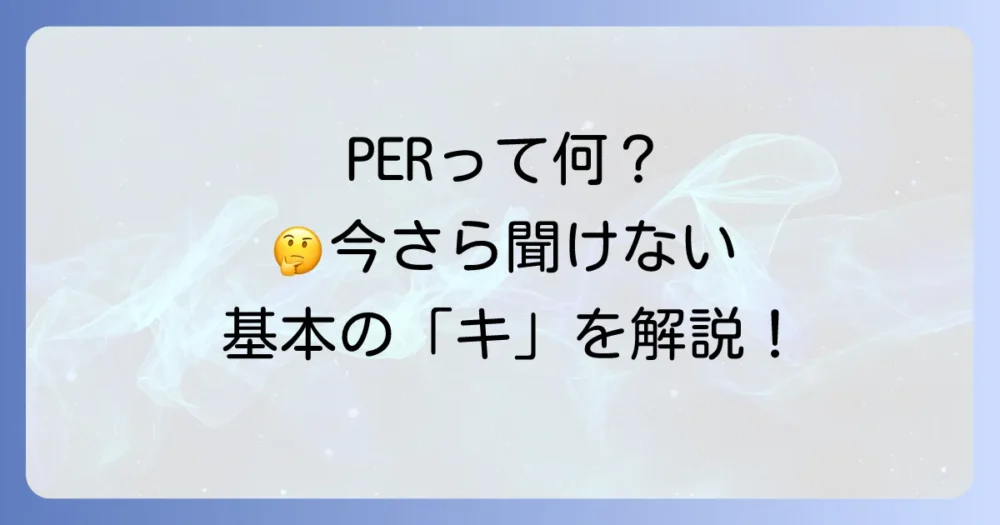
「PERが異常に高い理由」を理解するためには、まずPERそのものが何を示す指標なのかを正確に把握しておく必要があります。ここでは、PERの基本的な考え方についておさらいしましょう。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- PER(株価収益率)の計算方法
- PERの目安はどのくらい?
- PERが高い=割高、低い=割安とは限らない
PER(株価収益率)の計算方法
PER(Price Earnings Ratio)は、日本語で「株価収益率」と訳され、現在の株価がその企業の「1株当たりの利益(EPS)」の何倍になっているかを示す指標です。 計算式は非常にシンプルです。
PER(倍) = 株価 ÷ 1株当たり純利益(EPS)
例えば、株価が2,000円で、1株当たり純利益(EPS)が100円の企業があったとします。この場合のPERは「2,000円 ÷ 100円 = 20倍」となります。これは、現在の株価が1年間の利益の20倍で評価されている、と解釈できます。別の見方をすれば、投資した資金をその企業の利益で回収するのに20年かかる、と考えることもできます。
このPERの数値を見ることで、企業の収益力に対して現在の株価が割安なのか、それとも割高なのかを判断する一つの材料とすることができます。
PERの目安はどのくらい?
では、PERは何倍くらいが一般的なのでしょうか。よく言われる目安として「15倍」という数字があります。 これは、過去の日経平均株価のPERが概ね15倍前後で推移してきたことに由来します。 そのため、一般的にはPERが15倍より低いと割安、高いと割高と判断されることがあります。
しかし、この「15倍」という数字は、あくまでも全体的な目安に過ぎません。PERに適正とされる絶対的な基準はなく、業種や企業の成長段階によって平均値は大きく異なります。 例えば、IT関連やバイオテクノロジーなどの成長性が期待される業種ではPERが高くなる傾向があり、一方で、銀行や電力会社などの成熟した業種ではPERが低めになることが一般的です。
したがって、特定の銘柄のPERを評価する際は、市場全体の平均値だけでなく、同業他社のPERと比較することが非常に重要になります。
PERが高い=割高、低い=割安とは限らない
株式投資の入門書などでは「PERが低い株は割安でお買い得」と説明されることがよくあります。 もちろん、それは基本的な考え方として正しいのですが、その言葉通りに受け取ってしまうのは危険です。
なぜなら、株価は常に企業の将来性を織り込んで変動するものだからです。PERが高いということは、それだけ多くの投資家がその企業の将来の利益成長を期待して、現在の利益水準から見れば割高でも株を買っている、という証拠でもあるのです。 つまり、高いPERは「将来性への期待の表れ」と捉えることができます。
逆に、PERが低い銘柄は、将来の成長が見込めない、あるいは何か問題を抱えていると市場から判断されている可能性も考えられます。 そのため、「PERが高いから売り」「PERが低いから買い」と短絡的に判断するのではなく、なぜそのPERになっているのか、その背景にある理由を探ることが極めて重要なのです。
PERが異常に高くなる5つの主な理由
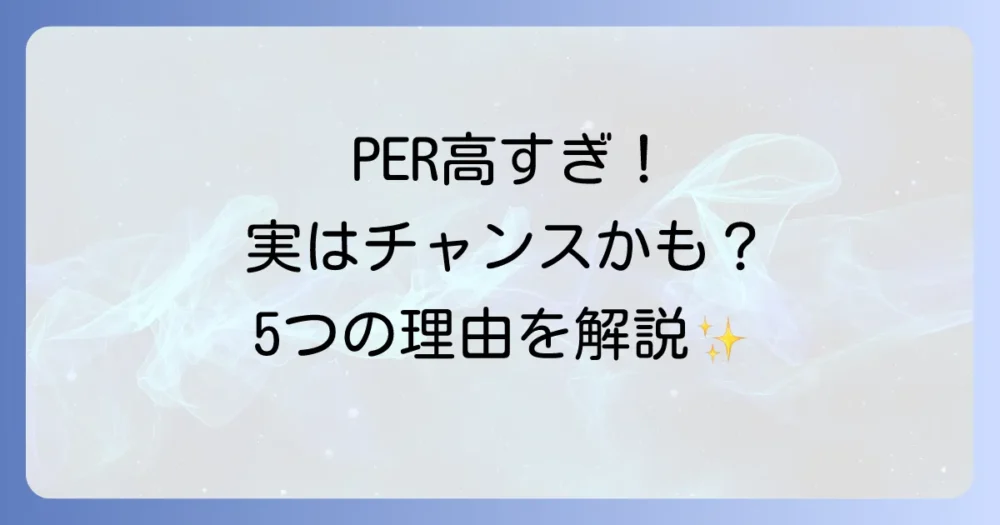
PERが100倍を超えるなど、一般的な目安とされる15倍をはるかに上回る水準になるのには、必ず理由があります。それは単に人気が集まっているから、というだけではありません。ここでは、PERが異常に高くなる主な5つの理由について、具体的に掘り下げていきます。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 理由1:将来への圧倒的な成長期待
- 理由2:一時的な要因による利益の減少
- 理由3:先行投資がかさむ業種特性
- 理由4:市場のテーマ性や人気による資金集中
- 理由5:M&Aや自社株買いなどへの期待
理由1:将来への圧倒的な成長期待
PERが異常に高くなる最も代表的な理由が、将来の利益成長に対する市場からの圧倒的な期待です。 これは特に、革新的な技術や新しいビジネスモデルを持つ「グロース株(成長株)」によく見られる現象です。
投資家たちは、現在の利益が小さくても、数年後には利益が何十倍、何百倍にもなると予測しています。その未来の大きな利益を先取りする形で株価が形成されるため、現在の利益(分母)に対して株価(分子)が非常に大きくなり、結果としてPERが100倍を超えるような高い数値になるのです。
例えば、今まさに世界を変えようとしているAI関連企業や、画期的な新薬を開発中のバイオベンチャーなどがこれに該当します。投資家たちは「5年後、10年後には今の利益の3倍、5倍になる」と信じているため、現在の利益水準で計算したPERが60倍であっても、将来の利益で見れば割高ではないと判断するのです。 このような銘柄は、期待が現実となれば株価の大きな上昇が見込めますが、成長が鈍化すると判断されると株価が急落するリスクもはらんでいます。
理由2:一時的な要因による利益の減少
企業の将来性とは関係なく、一時的な要因で利益が大幅に落ち込んだ結果、PERが高騰するケースもあります。PERの計算式は「株価 ÷ 1株当たり純利益」ですから、分母である「1株当たり純利益」が極端に小さくなると、PERの数値は跳ね上がります。
一時的な利益の減少要因としては、以下のようなものが考えられます。
- 大規模なリストラに伴う特別損失の計上
- 工場の火災や自然災害による損失
- 保有資産の売却による損失
- 訴訟による多額の和解金の支払い
このような場合、株価があまり下落しない一方で、当期の純利益だけが大きく減少するため、計算上PERが異常に高くなります。しかし、これはあくまで一過性の出来事です。来期以降、利益水準が元に戻れば、PERも正常な範囲に落ち着くことが期待されます。したがって、PERの高さだけを見て「割高だ」と判断するのは早計です。なぜ利益が減少したのか、その原因が一時的なものなのか、それとも構造的な問題なのかを見極めることが重要です。
理由3:先行投資がかさむ業種特性
業種によっては、ビジネスモデルそのものが高いPERになりやすい特性を持っている場合があります。特に、研究開発や設備投資など、事業の初期段階で大規模な先行投資が必要となる業種がこれに当たります。
例えば、以下のような業種です。
- IT・ソフトウェア業界:新しいサービスの開発に多額の費用がかかるが、一度完成すれば少ない追加コストで多くのユーザーに提供できる。
- バイオ・製薬業界:新薬の開発には長い年月と莫大な研究開発費が必要だが、承認されれば特許期間中に大きな利益を生む可能性がある。
- インフラ関連業界:通信網やプラント建設など、初期に巨額の設備投資が必要となる。
これらの企業は、将来の大きなリターンを得るために、現在は利益を度外視して投資を行っている段階です。そのため、利益は小さいか、あるいは赤字の状態が続きます。しかし、市場はその先行投資の先にある大きな成長ポテンシャルを評価し、高い株価をつけます。その結果、利益が少ない状態(分母が小さい)で株価が高い(分子が大きい)ため、PERは必然的に高くなるのです。
理由4:市場のテーマ性や人気による資金集中
企業の業績や将来性そのものとは別に、その時々の市場のテーマやトレンドに乗って、特定の銘柄群に投資家の人気が集中することでもPERは高騰します。これを「テーマ株相場」などと呼びます。
過去には、以下のようなテーマが市場を賑わせました。
- AI(人工知能)
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- 脱炭素・再生可能エネルギー
- 半導体
- インバウンド(訪日外国人観光客)
あるテーマが注目されると、関連する企業の株が、業績の実態以上に買われることがあります。投資家心理として「この流れに乗り遅れたくない」という気持ちが働き、買いが買いを呼ぶ展開になるのです。このような状況では、企業のファンダメンタルズ(基礎的条件)からかけ離れた水準まで株価が上昇し、結果としてPERが異常に高くなることがあります。
このタイプのPER上昇は、人気が続いている間は株価も上昇を続けますが、市場の関心が他のテーマに移ると、急速に資金が引いて株価が急落するリスクがあります。そのため、なぜその銘柄が人気化しているのか、そのテーマの持続性を見極める冷静な視点が求められます。
理由5:M&Aや自社株買いなどへの期待
企業の財務戦略に対する期待感からPERが高くなるケースもあります。具体的には、M&A(企業の合併・買収)や自社株買いへの期待です。
例えば、ある企業が将来有望なベンチャー企業を買収するという発表があったとします。市場は、このM&Aによって将来的に大きなシナジー効果が生まれ、利益が拡大すると期待します。その期待が株価を押し上げ、PERが上昇するのです。
また、企業が「自社株買い」を行うと、市場に流通する株式数が減少します。PERの計算式の分母である「1株当たり純利益(EPS)」は「純利益 ÷ 発行済株式総数」で計算されるため、発行済株式総数が減ればEPSは向上します。EPSが向上すれば、株価が同じでもPERは低下しますが、市場はEPSの向上を好感して株を買い、結果的に株価が上昇して高いPERが維持される、あるいはさらに上昇することがあります。
これらの財務戦略は、企業の価値向上に対する経営陣の積極的な姿勢と受け取られ、投資家からの評価を高める要因となり、PERを押し上げる力を持つのです。
「PERが異常に高い=危険」とは限らない!投資する際の注意点
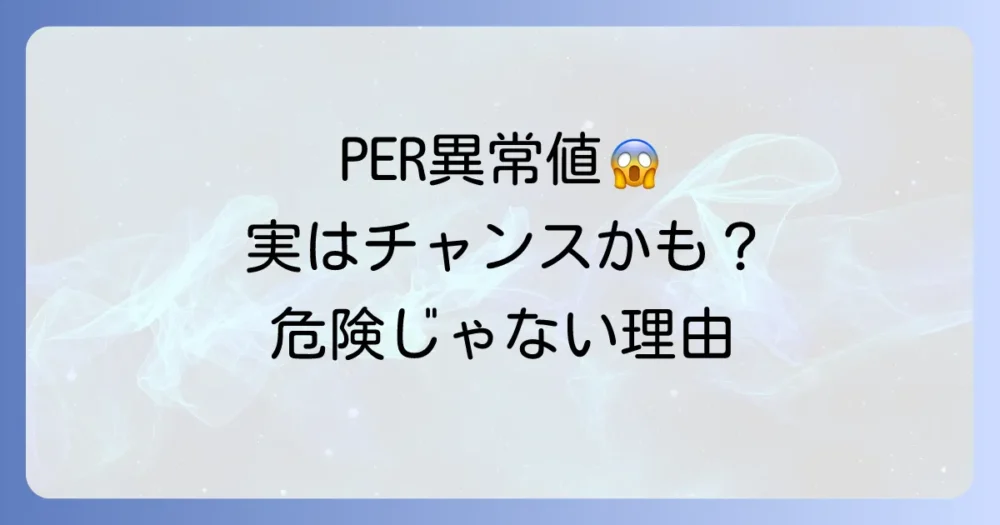
PERが異常に高い銘柄は、大きなリターンをもたらす可能性を秘めている一方で、相応のリスクも伴います。ハイリスク・ハイリターンな投資対象であると心得るべきでしょう。ここでは、PERが高い銘柄に投資する際に、失敗を避けるために押さえておきたい注意点を解説します。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- なぜPERが高いのか、その理由を徹底的に分析する
- 成長ストーリーが継続しているかを見極める
- 決算発表は特に注意深くチェックする
- 他の指標と組み合わせて多角的に判断する
なぜPERが高いのか、その理由を徹底的に分析する
最も重要なことは、「なぜこの銘柄のPERはこんなに高いのか?」という理由を自分自身で徹底的に分析し、納得することです。 前の章で解説した5つの理由のうち、どれに当てはまるのか、あるいは複合的な要因なのかを突き止めましょう。
例えば、「将来への成長期待」が理由なのであれば、その企業のビジネスモデル、市場の規模、競合との差別化要因などを詳しく調べ、「確かにこれなら数年後に利益が数倍になってもおかしくない」と確信できるかどうかがポイントです。もし「一時的な利益の減少」が理由なら、その原因となった事象が本当に一過性のもので、来期以降の業績回復が見込めるのかどうかを、決算資料などから読み解く必要があります。
理由が曖昧なまま、ただ「人気だから」「話題だから」という理由で投資するのは非常に危険です。株価が下落した際に、狼狽売りをしてしまう原因にもなります。自分なりの根拠を持つことが、高PER銘柄への投資における第一歩です。
成長ストーリーが継続しているかを見極める
特に「成長期待」によってPERが高くなっている銘柄の場合、投資家が信じている「成長ストーリー」が崩れていないか、常にチェックし続ける必要があります。
成長ストーリーとは、例えば「この新技術によって、既存の市場を破壊的に変革し、圧倒的なシェアを獲得する」といった、その企業の未来像です。このストーリーが続く限り、高いPERは正当化され、株価も上昇を続ける可能性があります。
しかし、以下のような事態が発生すると、成長ストーリーに陰りが見え始めます。
- 強力な競合他社が出現した
- 技術開発が想定通りに進んでいない
- 法規制の変更によってビジネス環境が悪化した
- 主要な製品やサービスの売上成長が鈍化した
このようなニュースが出た場合、市場の期待は急速にしぼみ、株価の急落につながる恐れがあります。日々のニュースや企業のIR情報に注意を払い、成長ストーリーの前提が崩れていないかを見極めることが、高値掴みを避けるために不可欠です。
決算発表は特に注意深くチェックする
高PER銘柄にとって、四半期ごとの決算発表は「審判の時」と言っても過言ではありません。なぜなら、市場の高い期待に応えられているかどうかを、具体的な数字で証明する場だからです。
チェックすべきポイントは、単に売上や利益の数字だけではありません。
- 売上高や利益の成長率:市場の期待(コンセンサス予想)を上回っているか。
- 利益率の推移:しっかりと利益を出せる体質になっているか。
- 次期の業績予想:会社側が強気の見通しを示しているか。
たとえ増収増益であっても、その伸び率が市場の期待に届かなかっただけで、「成長が鈍化した」と見なされ、株価が暴落することもあります。これを「決算クリア」などと呼びます。高PER銘柄は、常に「期待を上回り続けること」を求められる、非常にハードルの高い銘柄なのです。決算短信や説明会資料を読み込み、数字の裏にある意味を理解する努力が求められます。
他の指標と組み合わせて多角的に判断する
PERは非常に便利な指標ですが、万能ではありません。特にPERが異常に高い銘柄や、赤字でPERが算出できない銘柄を評価する際には、PERだけに頼らず、他の指標と組み合わせて多角的に分析することが重要です。
例えば、以下のような指標を併用することで、より企業の全体像を捉えやすくなります。
- PBR(株価純資産倍率):企業の資産面から株価の割安性を測る指標。
- PSR(株価売上高倍率):売上高から株価の割安性を測る指標。赤字の成長企業にも使える。
- PEGレシオ:PERを利益成長率で割った指標。成長性を加味して割安性を測る。
これらの指標を組み合わせることで、「PERは高いが、PSRで見るとまだ割安の範囲かもしれない」「PERは高いが、PEGレシオで見ると成長率に見合った水準だ」といった、より深い分析が可能になります。一つのモノサシだけで判断せず、複数の視点から企業価値を評価する癖をつけましょう。
PERだけじゃない!合わせてチェックしたい株式指標
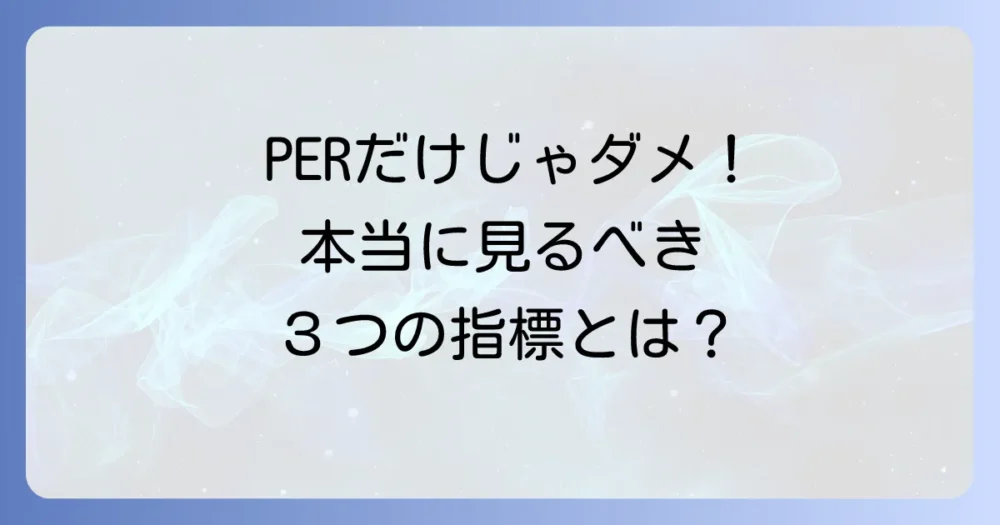
PERが異常に高い銘柄を分析する際、PERだけを見ていると判断を誤る可能性があります。企業の価値をより正確に把握するためには、他の指標と組み合わせて多角的な視点を持つことが不可欠です。ここでは、PERと合わせてチェックしたい代表的な株式指標を3つご紹介します。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- PBR(株価純資産倍率)
- PSR(株価売上高倍率)
- PEGレシオ(株価収益成長率)
PBR(株価純資産倍率)
PBR(Price Book-value Ratio)は「株価純資産倍率」のことで、企業の資産面から株価の割安・割高を判断するための指標です。 計算式は以下の通りです。
PBR(倍) = 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)
1株当たり純資産(BPS)は、会社が解散した場合に株主の手元に残る価値(解散価値)とも言われます。そのため、PBRは「現在の株価が解散価値の何倍か」を示していると解釈できます。一般的にPBRは1倍が基準とされ、1倍を割っていると、株価が解散価値よりも安く、割安だと判断されることがあります。
PERが利益という「フロー」の側面から株価を評価するのに対し、PBRは純資産という「ストック」の側面から評価します。PERが高くても、PBRが著しく高いわけでなければ、「資産背景に裏付けがある」と見なせるかもしれません。逆に、PERもPBRも異常に高い場合は、より慎重な判断が求められます。利益と資産の両面から企業の価値を測ることで、よりバランスの取れた評価が可能になります。
PSR(株価売上高倍率)
PSR(Price to Sales Ratio)は「株価売上高倍率」のことで、企業の売上高に対して株価がどの程度の水準にあるかを示す指標です。計算式は以下の通りです。
PSR(倍) = 時価総額 ÷ 年間売上高
PSRの大きな特徴は、利益が赤字の企業でも評価できる点です。PERは利益が赤字だとマイナスになり、指標として機能しません。 しかし、ITベンチャーやバイオ企業など、先行投資によって今は赤字でも、急成長している企業はたくさんあります。そうした企業の株価の割安・割高を判断する際に、PSRは非常に有効なツールとなります。
一般的に、PSRは20倍を超えると割高、低いほど割安とされますが、これも業種によって水準は大きく異なります。PERが異常に高い、あるいは赤字で算出不能なグロース株を評価する際には、「売上は順調に伸びているか?」「その売上規模に対して、現在の時価総額は妥当か?」という視点を与えてくれるPSRのチェックは欠かせません。
PEGレシオ(株価収益成長率)
PEGレシオ(Price Earnings to Growth Ratio)は、PERを利益の成長率で割ることで、企業の成長性を加味して株価の割安度を測る指標です。計算式は以下の通りです。
PEGレシオ = PER ÷ 1株当たり利益成長率(%)
PERが高い銘柄でも、それ以上に高い利益成長率を達成していれば、PEGレシオは低くなります。一般的に、PEGレシオは1倍から2倍程度が適正水準とされ、1倍を下回ると割安、2倍を上回ると割高と判断される傾向があります。
例えば、PERが50倍のA社と、PERが20倍のB社があったとします。PERだけ見るとA社の方が圧倒的に割高です。しかし、A社の利益成長率が50%で、B社の利益成長率が10%だった場合、PEGレシオは以下のようになります。
- A社のPEGレシオ:50 ÷ 50 = 1倍
- B社のPEGレシオ:20 ÷ 10 = 2倍
この場合、成長性を考慮すると、実はA社の方が割安であると評価できるのです。PERが高いグロース株に投資する際には、そのPERが成長率に見合ったものなのかを判断するために、PEGレシオは非常に強力な武器となります。
よくある質問
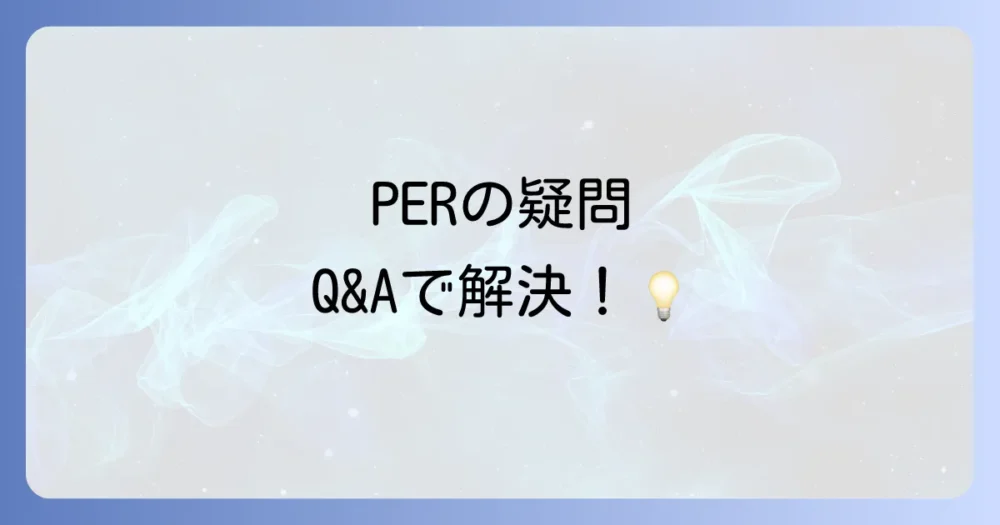
ここでは、PERに関して多くの投資家が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
PERがマイナス(赤字)の場合はどう考えればいいですか?
PERの計算式の分母である「1株当たり純利益(EPS)」がマイナス、つまり企業が赤字決算の場合、PERもマイナスで表示されるか、「-(ハイフン)」や「算出不能」と表示されます。 このマイナスのPERは、一見すると「すごく割安」に見えるかもしれませんが、これは大きな誤解です。PERは本来、投資した資金を何年で回収できるかを示す指標なので、利益が出ていない赤字企業においては、指標として全く意味をなしません。 赤字企業を分析する際は、PERではなく、なぜ赤字なのかという理由の分析や、PSR(株価売上高倍率)、PBR(株価純資産倍率)といった他の指標を用いて評価する必要があります。
PERの適正水準は業種によって違いますか?
はい、大きく異なります。PERの適正水準に絶対的な基準はなく、業種ごとのビジネスモデルや成長期待によって平均値は変わってきます。 例えば、ITや医薬品といった将来の高い成長が期待される業種(グロース業種)はPERが高くなる傾向にあります。 一方で、銀行、鉄鋼、電力などの成熟産業とされる業種(バリュー業種)は、安定しているものの高い成長は期待されにくいため、PERは低くなる傾向があります。そのため、ある企業のPERを評価する際は、日経平均などの市場全体の平均と比較するだけでなく、必ず同業他社のPERと比較することが重要です。
PERが高いグロース株と低いバリュー株、どちらに投資すべきですか?
これは投資家の投資スタイルやリスク許容度によって答えが変わるため、一概にどちらが良いとは言えません。
グロース株(成長株)は、PERは高いですが、将来の大きな株価上昇(キャピタルゲイン)が期待できます。その反面、期待通りに成長しなかった場合、株価が急落するリスクも高くなります。
一方、バリュー株(割安株)は、PERが低く、株価が本来の企業価値より割安に放置されているため、いずれ株価が見直されることで上昇が期待できます。また、配当利回りが高い銘柄が多いのも特徴です。
ご自身の投資目的(大きなリターンを狙いたいのか、安定したリターンを求めるのか)や、どの程度のリスクなら受け入れられるかを考え、自分に合った投資スタイルを選ぶことが大切です。
PERの調べ方を教えてください。
PERは、様々な金融情報サイトや証券会社のウェブサイト、取引ツールで簡単に調べることができます。
例えば、Yahoo!ファイナンスや各証券会社の個別銘柄ページにアクセスし、調べたい企業の銘柄名や証券コードを入力して検索すれば、株価やチャートと並んで「PER(予)」や「PBR(実)」といった指標が表示されます。
「(予)」は予想PER、「(実)」は実績PERを意味します。株価は将来の期待を織り込んで動くため、一般的には今期や来期の業績予想を基に算出された「予想PER」を重視するのが良いでしょう。
まとめ
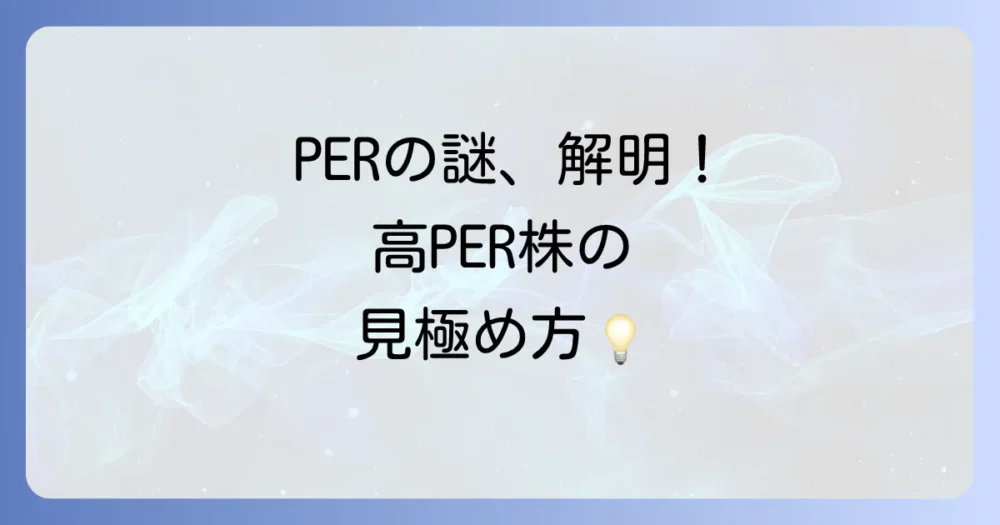
- PERは株価が1株当たり利益の何倍かを示す指標です。
- PERが異常に高い理由は主に5つあります。
- 理由1は、将来への圧倒的な成長期待です。
- 理由2は、一時的な要因による利益の減少です。
- 理由3は、先行投資がかさむ業種特性です。
- 理由4は、市場のテーマ性や人気による資金集中です。
- 理由5は、M&Aや自社株買いなどへの期待です。
- 「PERが高い=危険」と短絡的に判断してはいけません。
- なぜPERが高いのか、その理由を分析することが最も重要です。
- 企業の成長ストーリーが継続しているかを見極める必要があります。
- 高PER銘柄にとって決算発表は非常に重要です。
- PERだけでなくPBRやPSRなど他の指標と組み合わせることが大切です。
- 赤字企業のマイナスPERは指標として意味がありません。
- PERの適正水準は業種によって大きく異なります。
- 自分の投資スタイルに合った銘柄を選ぶことが成功の鍵です。
新着記事