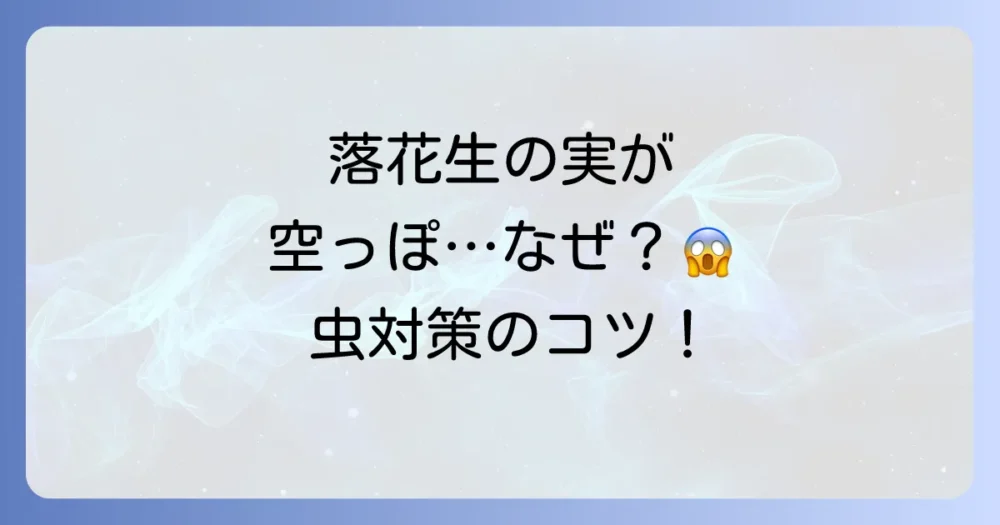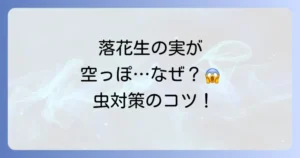丹精込めて育てた落花生が、害虫の被害にあってがっかりした経験はありませんか?「葉っぱに穴が…」「収穫したら実が食べられていた…」そんな悲しい思いをしないために、本記事では落花生に発生する害虫の種類から、効果的な農薬、そして家庭菜園でもできる無農薬での対策まで、あなたの落花生を守るための全てを詳しく解説します。この記事を読めば、害虫対策は万全です!
【要注意】落花生に発生する主要な害虫リスト
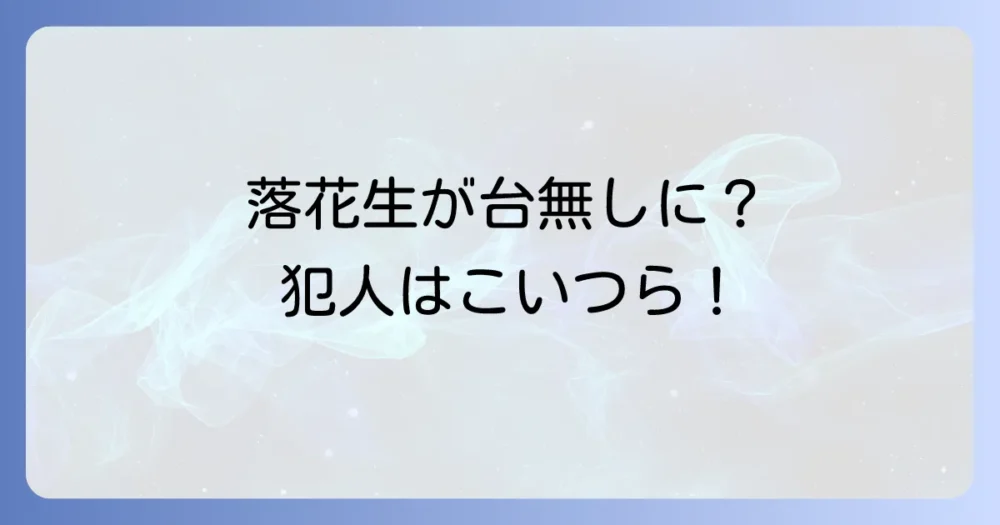
落花生栽培で美味しい実をたくさん収穫するためには、まず敵を知ることが重要です。落花生には、土の中に潜んで根や莢(さや)を食害する害虫と、地上部で葉や茎を食べる害虫がいます。それぞれの特徴と被害をしっかり把握して、早期発見・早期対策につなげましょう。
- 土の中に潜む害虫
- 葉や茎を食害する害虫
- その他の害虫
土の中に潜む害虫
土の中にいる害虫は、被害が目に見えにくく、気づいた時には手遅れになっていることも少なくありません。特に注意すべき害虫について解説します。
コガネムシ(幼虫)
落花生栽培で最も警戒すべき害虫の一つがコガネムシの幼虫です。カブトムシの幼虫を小さくしたような見た目で、土の中で落花生の根や、なんと実(莢)まで食べてしまいます。 被害にあうと、株全体の生育が悪くなったり、ひどい場合には枯れてしまったりします。 収穫してみたら殻に穴が開いていて中身が空っぽだった、という悲しい結果の多くは、このコガネムシの幼虫が原因です。
8月頃から株が急にしおれて枯死するような症状が見られたら、コガネムシの幼虫による被害を疑いましょう。 被害株の根元を掘ってみると、幼虫が見つかることがあります。
ネキリムシ
ネキリムシは、その名の通り、発芽したばかりの若い苗の地際部分を食いちぎってしまう、非常に厄介な害虫です。 ヤガ科の蛾の幼虫で、夜間に活動して悪さをします。 せっかく芽が出たのに、翌朝見たら根元からポッキリと倒れていた、という場合はネキリムシの仕業かもしれません。 被害を見つけたら、株の周りの土を少し掘ってみると、丸まった幼虫が見つかることが多いです。
ヒョウタンゾウムシ
ヒョウタンゾウムシ類の幼虫も土の中で落花生の莢に穴を開けて食害します。 成虫は、展開する前の若い葉を左右対称に食べるという特徴的な食害痕を残します。 もし、葉っぱがきれいな半円状にかじられていたら、ヒョウタンゾウムシがいるサインかもしれません。 幼虫による莢の被害は収量に直接影響するため、見逃せない害虫です。
葉や茎を食害する害虫
地上部で葉や茎を食べる害虫は、被害が目に見えやすいため比較的発見しやすいですが、放置すると光合成を妨げ、株の生育を著しく悪化させます。
アブラムシ
アブラムシは、新芽や葉の裏にびっしりと群生し、吸汁して株を弱らせる小さな害虫です。 生育を阻害するだけでなく、ウイルス病を媒介するため、特に注意が必要です。 アブラムシの排泄物は「すす病」の原因にもなり、葉が黒く汚れて光合成を妨げます。繁殖力が非常に高いため、見つけ次第すぐに対処することが大切です。
ハダニ
ハダニは非常に小さく、肉眼では見つけにくい害虫です。葉の裏に寄生して汁を吸い、被害が進むと葉に白いカスリ状の斑点がたくさん現れます。 さらに多発すると、葉全体が茶色く変色して枯れてしまい、株の生育に大きな影響を与えます。 乾燥した環境を好むため、梅雨明け後の高温乾燥期に特に発生しやすくなります。
ヨトウムシ
ヨトウムシは「夜盗虫」と書くように、夜間に活動して葉を食い荒らす蛾の幼虫です。 昼間は土の中に隠れているため見つけにくいですが、葉に大きな食害痕があればヨトウムシの被害を疑いましょう。若齢幼虫は集団で葉の裏から食害し、葉が白っぽく見えることもあります。成長すると食欲旺盛になり、一晩で葉を食べ尽くされてしまうこともあるので油断できません。
マメヒメサヤムシガ
ハマキムシの仲間で、緑色の幼虫が糸で葉をつづり合わせて、その中で葉を食害します。 葉だけでなく、莢も食害して黒く変色させることがあるため、品質低下に直結します。 葉が不自然に折りたたまれていたり、つづり合わされていたりしたら、中に幼虫が潜んでいる可能性が高いです。
害虫だけじゃない!落花生がかかりやすい病気と対策
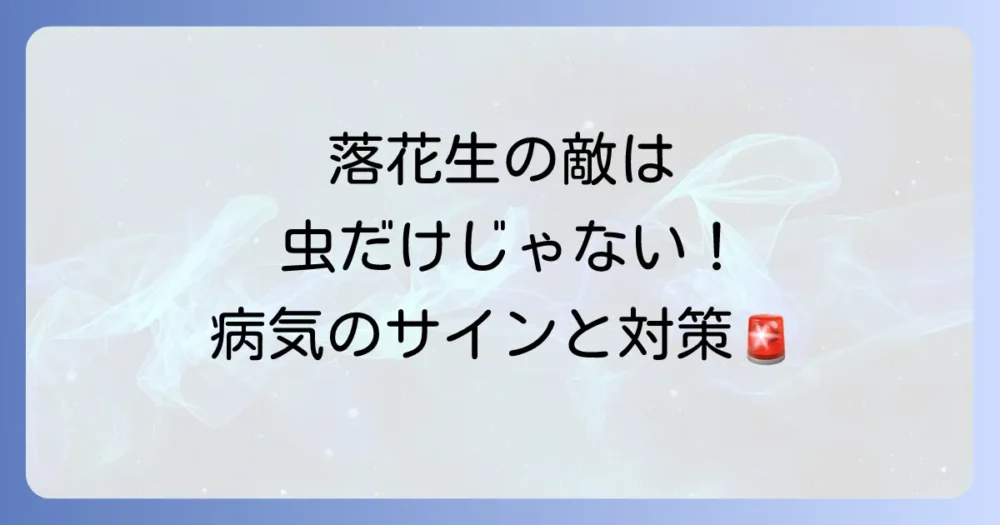
落花生の栽培では、害虫だけでなく病気にも注意が必要です。特に、連作すると土壌中の病原菌が増え、病気が発生しやすくなります。 ここでは、落花生がかかりやすい代表的な病気とその対策について解説します。病気を早期に発見し、適切に対処することで、被害を最小限に抑えましょう。
- 白絹病
- 褐斑病
- そうか病
- 茎腐病
白絹病
白絹病は、高温多湿の時期、特に7月から8月にかけて発生しやすい恐ろしい土壌伝染性の病気です。 症状としては、まず株の地際部が侵され、白い絹糸のようなカビ(菌糸)がびっしりと生えます。 やがて茎葉が黄色く変色してしおれ、株全体が枯死に至ります。 被害株の地際部には、粟粒のような茶色い菌核が形成されるのも特徴です。
この病原菌は土の中で長期間生存するため、一度発生すると根絶が難しいのが特徴です。発病した株は、周りの土ごと速やかに抜き取り、畑の外に持ち出して処分することが重要です。 また、排水を良くして土壌が過湿にならないように管理することも予防につながります。
褐斑病
褐斑病は、葉や茎、葉柄に黄褐色の斑点ができる病気です。 初期には淡褐色の小さな斑点ですが、次第に大きくなり、色が暗褐色に変化します。 病斑の周りが黄色く縁取られるのが特徴で、症状が進行すると病斑同士がくっついて葉全体が枯れ落ちてしまいます。 落葉が激しいと光合成ができなくなり、収量や品質の低下につながります。
この病気もカビ(糸状菌)が原因で、高温多湿の梅雨時期に発生しやすくなります。 雨や風によって胞子が飛散し、次々と感染が広がるため、発病した葉は早めに取り除いて処分しましょう。 風通しを良くし、畑が過湿にならないように管理することが予防の基本です。
そうか病
そうか病は、葉や茎、そして莢にまでかさぶた状の病斑ができる病気です。 葉では淡褐色の小斑点が少し盛り上がり、1~2mmのかさぶた状になります。 多発すると葉が巻いて縮れてしまうこともあります。莢に発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、子房柄が侵されることで実の付きが悪くなったり、実の充実が妨げられたりします。
ジャガイモにも発生する病気として知られていますが、落花生でも注意が必要です。 この病気も糸状菌が原因で、雨によって感染が広がるため、水はけの良い畑で育てることが大切です。
茎腐病
茎腐病は、その名の通り、茎の地際部が腐って黒褐色になり、株が枯れてしまう病気です。 地上部がしおれて元気がなくなり、やがて枯死します。枯れた株の茎の表面には、多数の小さな黒い点(柄子殻)が形成されるのが特徴です。 この病気も土壌伝染性で、一度発生した畑では連作を避ける必要があります。
対策としては、無病の健全な種子を使用すること、発病株を早期に発見して抜き取り、圃場外に持ち出すことが基本です。 以前は登録農薬がありませんでしたが、近年では「トップジンM水和剤」や「ベンレート水和剤」などが適用拡大され、発生初期からの散布が有効とされています。
【農薬を使いたい方へ】落花生に登録のあるおすすめ農薬
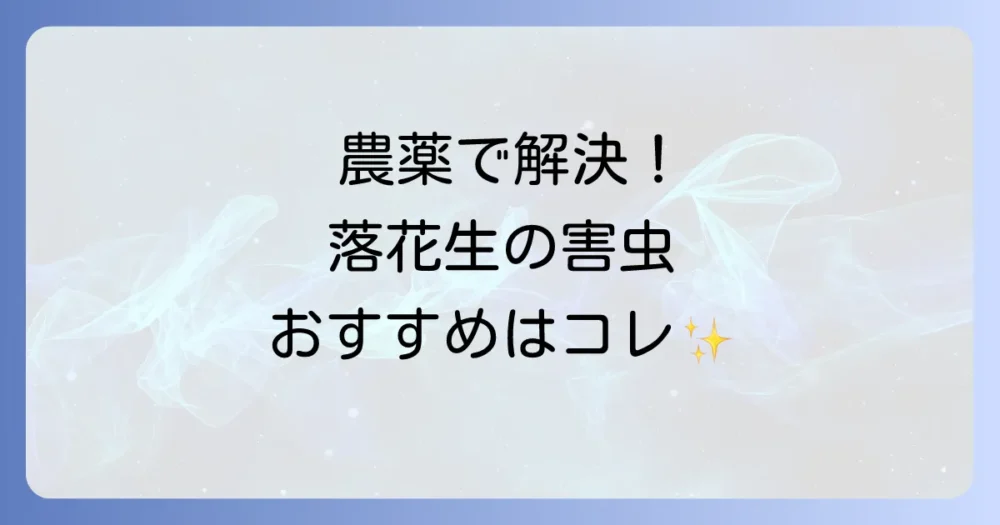
害虫や病気の被害が広範囲に及ぶ場合や、確実な防除を行いたい場合には、農薬の使用が有効な手段となります。落花生に使用できる農薬は限られているため、購入・使用前には必ずラベルを確認し、「落花生」に適用があることを確かめてください。 ここでは、害虫の種類別に効果的な農薬や、農薬の基本的な使い方について解説します。
害虫の種類別・効果的な農薬一覧
害虫の種類によって有効な農薬は異なります。自分の畑で発生している害虫に合わせて、適切な農薬を選びましょう。以下に代表的な害虫と、それに対応する農薬の例を挙げます。
| 対象害虫 | 農薬名(例) | 有効成分(例) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| コガネムシ類(幼虫) | ダイアジノン粒剤5、フォース粒剤 | ダイアジノン、テフルスリン | 種まき時や植え付け時に土に混ぜ込むことで、土中の幼虫を防除します。 |
| ネキリムシ類 | デナポン粒剤5 | NAC | 株元に散布することで、夜間に活動するネキリムシを駆除します。 |
| アブラムシ類 | ダントツ水溶剤、モスピラン顆粒水溶剤 | クロチアニジン、アセタミプリド | 浸透移行性があり、散布することで葉の裏にいるアブラムシにも効果を発揮します。 ウイルス病の媒介を防ぐためにも早期の防除が重要です。 |
| ハダニ類 | コロマイト乳剤、ダニトロンフロアブル | ミルベメクチン、フェンピロキシメート | ハダニ専門の殺ダニ剤。発生初期に葉の裏までしっかりかかるように散布します。 |
| ヨトウムシなど食葉性害虫 | プレバソンフロアブル5 | クロラントラニリプロール | 幅広いチョウ目害虫に効果があり、効果の持続期間が長いのが特徴です。 |
※上記はあくまで一例です。農薬を使用する際は、必ず最新の登録情報を確認し、ラベルに記載された使用方法、時期、回数を厳守してください。
農薬の正しい使い方と注意点
農薬は、正しく使ってこそ効果を発揮し、安全性も確保されます。以下の点に注意して使用しましょう。
使用時期を守る
農薬には「収穫〇日前まで」といった使用時期の制限があります。これを守らないと、収穫した落花生に農薬が残留してしまう可能性があります。また、害虫の発生初期に散布するのが最も効果的です。
希釈倍率と散布量を守る
農薬は、定められた希釈倍率を正確に守って水で薄めてから使用します。 濃すぎると薬害が出たり、薄すぎると効果がなかったりします。散布する量も、多すぎず少なすぎず、作物全体に均一にかかるようにしましょう。
安全な取り扱い
農薬を散布する際は、マスク、ゴーグル、長袖・長ズボン、手袋などを着用し、薬剤が皮膚に付着したり、吸い込んだりしないように注意してください。散布後は手や顔をよく洗い、うがいをしましょう。また、農薬は子どもの手の届かない、鍵のかかる場所に保管してください。
【無農薬・減農薬】家庭菜園でできる害虫対策
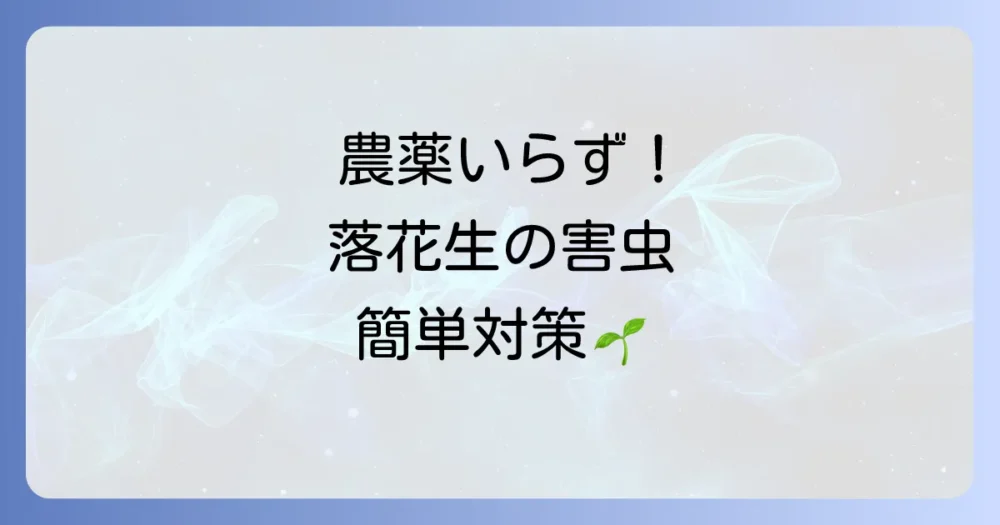
「できるだけ農薬は使いたくない」と考える方も多いでしょう。家庭菜園のような小規模な栽培であれば、農薬を使わずに害虫の被害を抑えることも可能です。ここでは、環境にも優しく、手軽に始められる無農薬・減農薬の害虫対策をご紹介します。日々のこまめな観察と対策が、健康な落花生を育てる鍵となります。
物理的な防除方法
物理的な方法は、害虫を直接畑に入れない、または取り除くという最もシンプルで効果的な対策です。
防虫ネット・不織布の活用
種まき直後から、防虫ネットや不織布でトンネルがけをすることで、多くの害虫の飛来や産卵を防ぐことができます。 特に、鳥による種や若い苗の食害対策としても非常に有効です。 ネットの目は、アブラムシなどの小さな害虫も防げる細かいものを選ぶと良いでしょう。
手で取り除く
コガネムシの成虫やヨトウムシ、葉についたアブラムシなど、目に見える害虫は見つけ次第、手で捕殺するのが確実な方法です。 面倒に感じるかもしれませんが、被害が広がる前にこまめに取り除くことが、結果的に被害を最小限に抑えることにつながります。
耕種的防除
畑の環境を整え、害虫が発生しにくい状況を作ることも重要です。
連作を避ける
同じ場所で同じ科の作物を続けて栽培すると、特定の病原菌や害虫が土壌に増えやすくなります。 落花生はマメ科なので、マメ科以外の作物と輪作することで、病害虫の発生リスクを減らすことができます。
土づくり
堆肥などの有機物をしっかり施して、水はけと水持ちの良い健全な土を作ることが、植物を健康に育て、病害虫への抵抗力を高める基本です。 また、夏場の太陽熱を利用して土壌を消毒する「太陽熱消毒」は、土の中の病原菌や害虫を減らすのに効果的です。
コンパニオンプランツ
落花生の近くに特定の植物を植えることで、害虫を遠ざける効果が期待できます。例えば、マリーゴールドは根に寄生するセンチュウを、ネギ類はその強い香りでウリハムシなどを遠ざける効果があると言われています。
天敵を利用する
害虫を食べてくれるテントウムシやカマキリ、クモなどの益虫は、畑の頼もしい味方です。殺虫剤をむやみに使うと、こうした益虫まで殺してしまいます。多様な生物が共存できる環境を整えることで、害虫の異常発生を自然に抑制することができます。
自然由来の資材を使う
木酢液や竹酢液、あるいは食酢や焼酎、唐辛子などを混ぜて作る「ストチュウ」などを定期的に散布することで、害虫を寄せ付けにくくする効果が期待できると言われています。 これらは農薬と違い、劇的な効果はありませんが、予防的な手段として試してみる価値はあります。
よくある質問
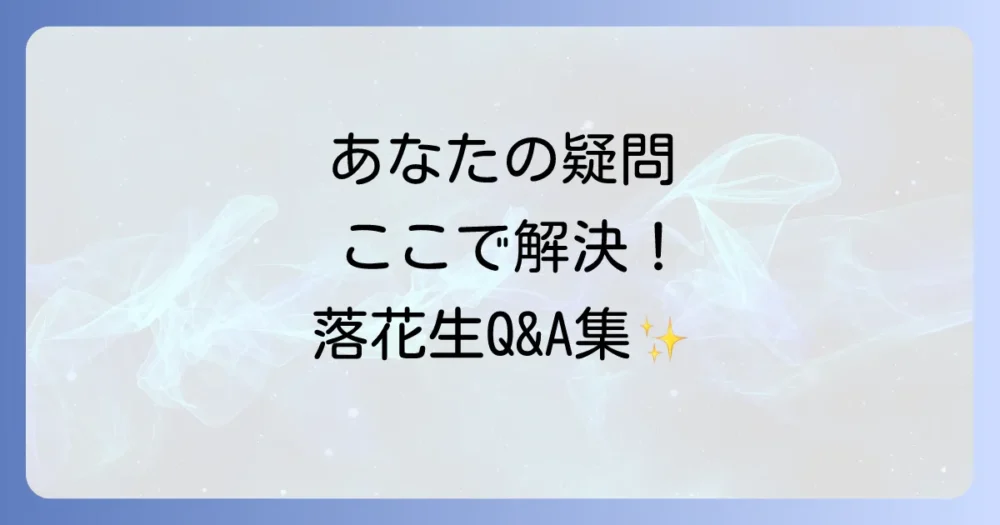
落花生の葉が食べられていますが、何の虫ですか?
落花生の葉を食べる害虫はいくつか考えられます。葉に大きな穴が開いている場合はヨトウムシ、小さな白い斑点が多数ある場合はハダニ、葉が左右対称にかじられている場合はヒョウタンゾウムシの成虫、葉が糸でつづられている場合はマメヒメサヤムシガの可能性があります。食害の痕をよく観察して、原因となっている害虫を特定しましょう。
収穫した落花生の殻に穴が開いている原因は何ですか?
収穫した落花生の殻に穴が開いている場合、その主な原因は土の中にいるコガネムシの幼虫である可能性が非常に高いです。 コガネムシの幼虫は、落花生の根だけでなく、地中で成長している莢(実)も食害します。 収穫期になって初めて被害に気づくケースが多く、深刻な減収につながります。
農薬はいつ撒くのが効果的ですか?
農薬を散布する最も効果的なタイミングは、病害虫の発生初期です。 被害が広がってからでは、完全に抑えるのが難しくなります。日頃から落花生の様子をよく観察し、異常を早期に発見することが重要です。また、土壌処理剤のように、種まき時や植え付け時に使用するタイプの農薬もあります。 農薬の種類によって適切な使用時期が異なるため、必ずラベルを確認してください。
家庭菜園で使いやすい農薬はありますか?
家庭菜園では、計量が簡単で使いやすいスプレータイプの製品や、少量で販売されている農薬が便利です。また、天然成分由来の農薬(例えば、デンプンを主成分とするものなど)は、化学合成農薬に抵抗がある方にも比較的使いやすいでしょう。 いずれの農薬を使用する場合でも、必ず「落花生」に登録があることを確認し、使用方法を守って安全に使用してください。
落花生が枯れる原因は何ですか?
落花生が枯れる原因は様々ですが、主に病気か害虫が考えられます。地際から白いカビが生えて枯れる場合は白絹病、茎の根元が腐って枯れる場合は茎腐病が疑われます。また、土中のコガネムシの幼虫に根を食べられて枯れてしまうこともあります。 枯れた株の状態をよく観察し、原因を特定することが次の対策につながります。
まとめ
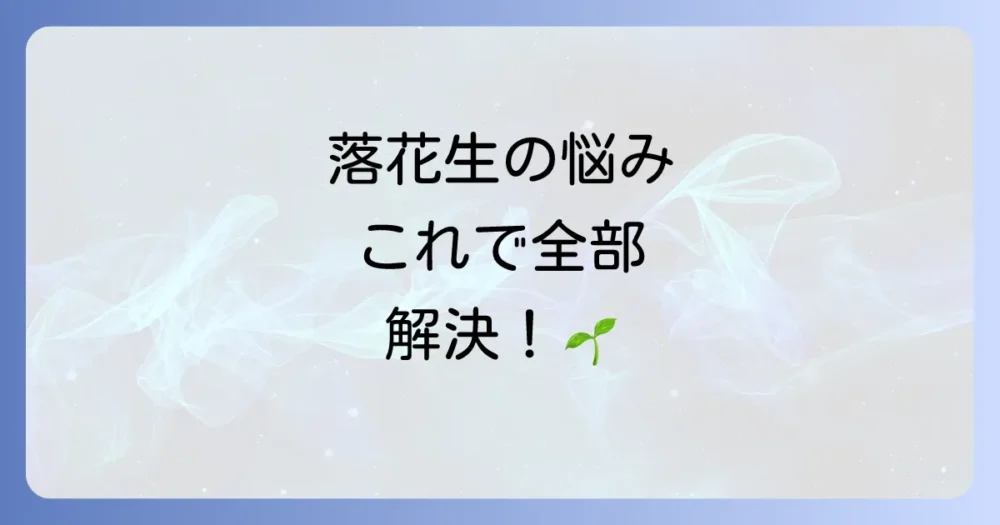
- 落花生の害虫は土中と地上部の両方に発生する。
- 土中の害虫で特に注意すべきはコガネムシの幼虫。
- コガネムシの幼虫は根だけでなく実(莢)も食害する。
- ネキリムシは若い苗の茎を地際から切り倒す。
- 葉を食べる害虫にはアブラムシやハダニ、ヨトウムシがいる。
- アブラムシはウイルス病を媒介するため特に注意が必要。
- 害虫だけでなく白絹病や褐斑病などの病気にも注意する。
- 病害虫対策の基本は、連作を避け、畑の環境を整えること。
- 農薬を使用する際は必ず「落花生」への登録を確認する。
- 農薬は害虫の種類や病気に合わせて適切なものを選ぶ。
- 農薬の使用時期、希釈倍率、使用回数を厳守することが重要。
- 家庭菜園では防虫ネットや手での捕殺が有効な対策。
- コンパニオンプランツや天敵の利用も無農薬栽培の助けになる。
- 被害の早期発見・早期対応が被害を最小限に抑える鍵。
- 枯れた原因を特定することが翌年の栽培成功につながる。