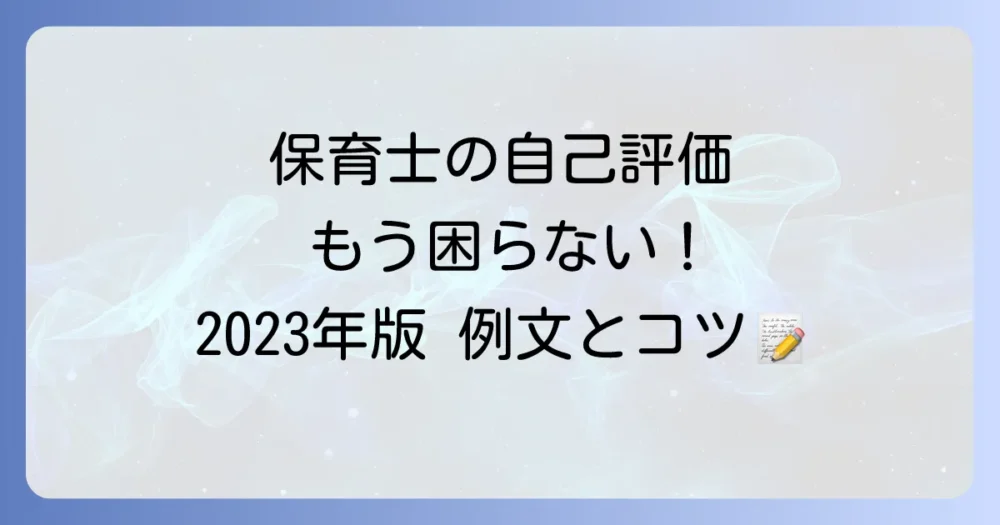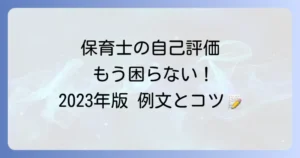毎年やってくる自己評価の季節。「何を書けばいいんだろう…」「去年と同じような内容になってしまう」と、頭を悩ませている保育士さんは多いのではないでしょうか。特に2023年は、保育の現場も様々な変化があった年。子どもたち一人ひとりと向き合う中で、ご自身の保育を振り返る大切な機会ですが、忙しい毎日の中では負担に感じてしまうこともありますよね。
本記事では、2023年度の自己評価にすぐに役立つ、具体的なチェックリストの項目や、経験年数・立場別の書き方、そしてそのまま使える例文を豊富にご紹介します。自己評価が苦手な方でも、この記事を読めばスラスラ書けるようになるコツが満載です。あなたの素晴らしい保育実践を、自信を持って言葉にしていきましょう!
保育士の自己評価とは?2023年も重要な理由
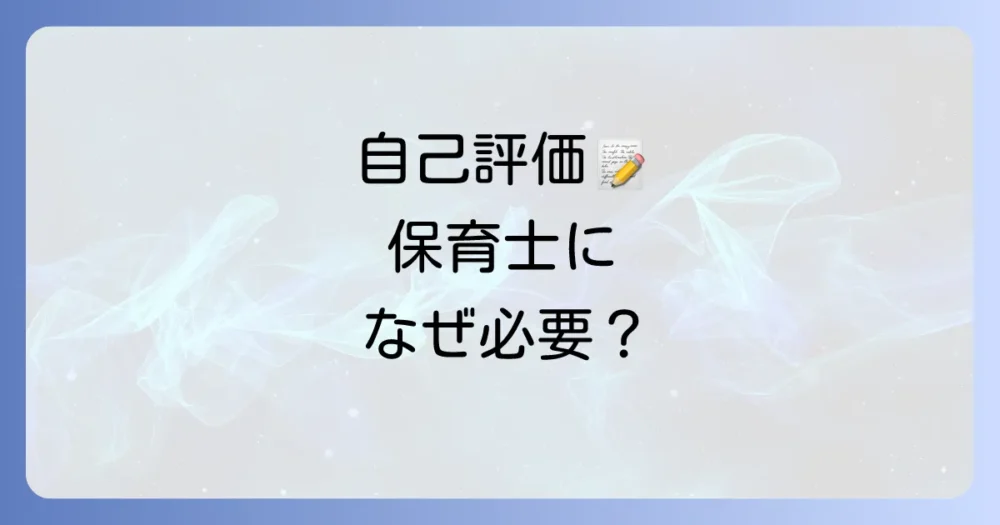
自己評価と聞くと、少し堅苦しく感じてしまうかもしれません。しかし、これは保育士として成長し、より良い保育を実現するために欠かせない大切な取り組みです。まずは、自己評価の目的や重要性について、改めて確認していきましょう。
この章では、以下の内容について解説します。
- 自己評価の目的は「保育の質の向上」と「自身の成長」
- キャリアアップ研修や処遇改善との密接な関係
- 法律・指針上の根拠
自己評価の目的は「保育の質の向上」と「自身の成長」
保育士の自己評価の最大の目的は、「保育の質を向上させること」です。 日々の保育を振り返り、自分の実践の良い点や課題を客観的に把握することで、子どもたち一人ひとりへの理解が深まります。 そして、その気づきを次の保育計画に活かすことで、より良い環境構成や関わり方ができるようになるのです。
もう一つの大切な目的は、「保育士自身の成長」に繋がることです。 自分の保育を言語化する作業は、保育観を深め、専門性を高める絶好の機会となります。 できたことを認識すれば自信になり、課題が見つかれば次への目標が明確になります。この繰り返しが、保育士としてのスキルアップを促してくれるのです。
キャリアアップ研修や処遇改善との密接な関係
近年、保育士の専門性向上と待遇改善を目的とした「キャリアアップ研修」や「処遇改善等加算」の制度が導入されています。実は、自己評価はこれらの制度とも深く関わっています。
キャリアアップ研修では、研修を受ける前に自己評価を行い、自身の課題を明確にすることが求められます。また、処遇改善等加算の要件として、職員一人ひとりの自己評価に基づいたキャリアパスや研修計画の策定が挙げられている園も少なくありません。つまり、適切な自己評価を行うことが、自身のキャリアアップや給与アップに直結する可能性があるのです。
法律・指針上の根拠
保育士の自己評価は、単に園が独自に行っているものではありません。厚生労働省が定める「保育所保育指針」において、保育士が自らの保育実践を振り返り、自己評価を行うことが努力義務として明記されています。 さらに、2020年に改訂された「保育所における自己評価ガイドライン」では、その具体的な方法や考え方が示されています。
このように、自己評価は国が定めるガイドラインに基づいた、保育の質を保証するための重要な取り組みなのです。 苦手意識を持つ方もいるかもしれませんが、自分の保育を社会的に認められた基準に照らして見つめ直す、前向きな機会と捉えてみましょう。
【2023年版】保育士の自己評価チェックリストの具体的な項目例
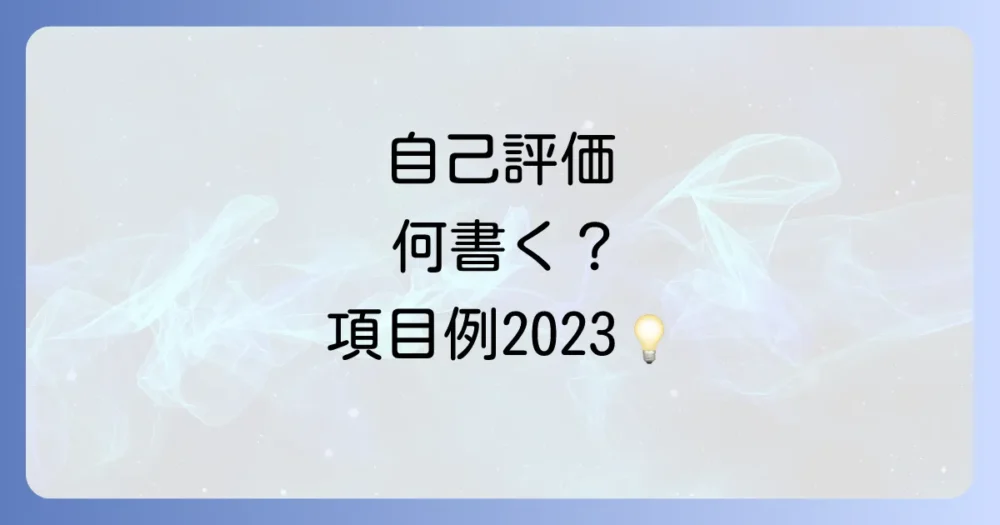
「自己評価が大切だとは分かったけれど、具体的にどんな視点で振り返ればいいの?」と感じる方も多いでしょう。ここでは、厚生労働省のガイドラインなどを基にした、自己評価の具体的なチェック項目例をご紹介します。これらを参考に、ご自身の1年間を振り返ってみましょう。
この章では、以下の内容について解説します。
- 厚生労働省のガイドラインに基づく3つの観点
- 園独自の項目にも注目しよう
厚生労働省のガイドラインに基づく3つの観点
厚生労働省の「保育所における自己評価ガイドライン」では、自己評価を行う際の観点として、大きく分けて以下の3つが示されています。 多くの園の自己評価シートは、これらの観点を基に作成されています。
それぞれの観点と、具体的なチェック項目の例を下の表にまとめました。
| 観点 | 具体的なチェック項目例 |
|---|---|
| 1. 保育の基本的理念と実践に係る観点 (子どもや保育そのものについて) |
|
| 2. 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点 (保護者や地域との関わりについて) |
|
| 3. 保育の実施運営・体制全般に係る観点 (職員としての姿勢や組織の一員として) |
|
これらの項目を一つひとつ確認しながら、「できたこと(自己評価)」「その根拠となる具体的なエピソード」「課題・改善点」「来年度に向けた目標」を整理していくと、自己評価がスムーズに進みます。
園独自の項目にも注目しよう
上記の項目はあくまで一般的なものですが、多くの保育園では、園の保育目標や方針に沿った独自の評価項目を設けています。 例えば、「食育に力を入れている園」であれば食育に関する項目が、「異年齢保育を重視している園」であればその関わりに関する項目が追加されているでしょう。
自己評価を行う際は、まずご自身の園の自己評価シートの項目をしっかりと確認し、何が求められているのかを理解することが大切です。 園の方針を意識することで、より的確で評価されやすい自己評価を書くことができます。
【経験年数・立場別】自己評価の書き方とそのまま使える例文集
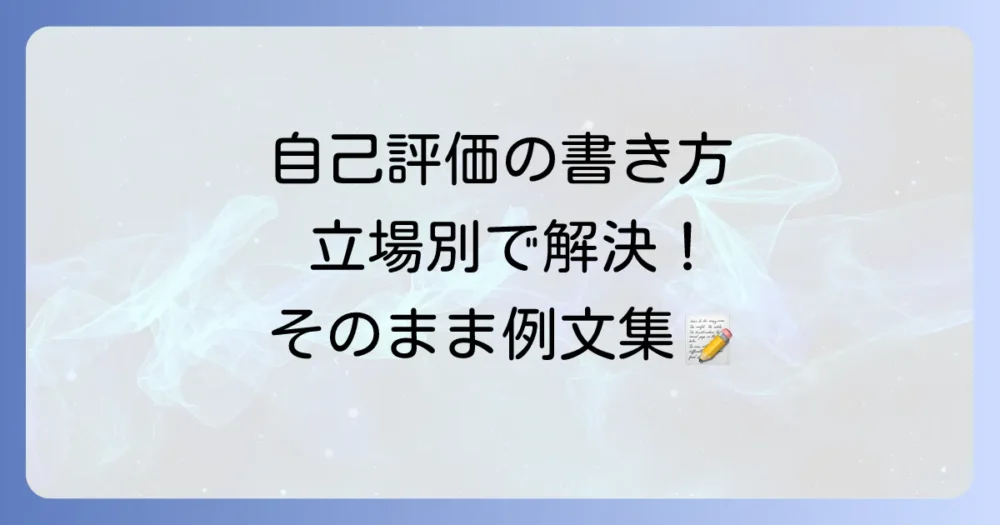
自己評価で書くべき内容は、保育士としての経験年数や立場によって異なります。ここでは、それぞれの状況に合わせた書き方のポイントと、具体的な例文をご紹介します。ご自身の状況に近いものを参考に、アレンジして活用してみてください。
この章では、以下の内容について解説します。
- 自己評価を書く前の準備と心構え
- 【1年目・新人保育士】の例文とポイント
- 【3年目・中堅保育士】の例文とポイント
- 【5年目以上・ベテラン保育士】の例文とポイント
- 【主任・リーダー保育士】の例文とポイント
- 【乳児クラス担当】の例文とポイント
- 【幼児クラス担当】の例文とポイント
自己評価を書く前の準備と心構え
いきなり書き始めるのではなく、まずは準備を整えましょう。1年間の保育日誌やクラスだより、行事の記録などに目を通し、具体的なエピソードを思い出しておくと筆が進みやすくなります。
書く際には、「できたこと」と「課題」の両方をバランス良く書くことが大切です。謙遜しすぎず、自分の頑張りをきちんと認めましょう。課題を書くときは、「~できなかった」で終わらせず、「来年度は~していきたい」という前向きな言葉で締めくくるのがポイントです。
【1年目・新人保育士】の例文とポイント
1年目は、園の生活や仕事の流れを覚えることが中心です。 先輩の指導を素直に受け入れ、積極的に学ぼうとする姿勢をアピールしましょう。
【例文】
【できたこと・自己評価】
先輩保育士の指導を仰ぎながら、子どもたち一人ひとりと信頼関係を築くことを第一に考えて関わることができました。 特に、笑顔で接することと、子どもの目線に合わせて話すことを常に意識しました。 分からないことはすぐに質問し、メモを取ることで、日々の保育の流れや基本的な業務を覚えることができました。
【課題・改善点】
突発的な出来事への対応に戸惑う場面があり、先輩保育士に助けていただくことが多くありました。また、保護者対応において、子どもの様子を具体的に伝える語彙が不足していると感じることがありました。
【来年度の目標】
来年度は、様々な状況を想定し、自分で考えて行動できる場面を増やしていきたいです。また、子どもの姿をより多角的に捉え、保護者に安心していただけるような言葉で伝えられるよう、日々の記録や言葉遣いを工夫していきます。
【3年目・中堅保育士】の例文とポイント
3年目頃になると、クラス運営の中心的な役割を担うことが増えてきます。 自分の保育観を持ちつつ、後輩への指導やクラス全体を見通した動きが求められます。
【例文】
【できたこと・自己評価】
子どもの発達段階や興味関心に合わせた活動を計画し、主体性を引き出す保育を実践できました。 特に、子どもたちの発案から発展させたお店屋さんごっこでは、子ども同士で役割分担をしたり、工夫したりする姿が見られ、大きな成長を感じました。後輩保育士の相談に乗り、自分の経験を伝えることで、クラス全体の保育の質の向上に貢献できたと思います。
【課題・改善点】
日々の業務に追われ、個々の子どもとじっくり関わる時間の確保が難しいと感じることがありました。また、保護者からの少し複雑な相談に対し、より丁寧な対応が必要だったと反省しています。
【来年度の目標】
来年度は、業務の効率化を図り、子ども一人ひとりと向き合う時間を意識的に作ります。保護者支援に関する研修にも参加し、専門的な知識を深め、より信頼される存在を目指します。
【5年目以上・ベテラン保育士】の例文とポイント
ベテラン保育士には、自身の専門性をさらに高めるとともに、園全体の保育の質を向上させる視点が期待されます。 経験に裏打ちされた深い洞察や、組織への貢献をアピールしましょう。
【例文】
【できたこと・自己評価】
長年の経験を活かし、特に配慮が必要な子どもやその家庭に対して、関係機関と連携しながら適切な支援を行うことができました。 園内研修の企画・運営を担当し、若手保育士の育成に貢献しました。保育所保育指針の改定内容を深く理解し、園の保育方針と照らし合わせながら、保育課程の見直しを提案・実行しました。
【課題・改善点】
自身の保育スタイルが確立している一方で、新しい保育理論や情報を取り入れる柔軟性が課題だと感じています。また、ミドルリーダーとして、職員間の意見調整にさらに配慮が必要な場面がありました。
【来年度の目標】
来年度は、外部の研修会や学会に積極的に参加し、新たな知見を園の保育に還元していきたいです。また、ファシリテーションの技術を学び、職員会議がより活発で建設的な場になるよう働きかけていきます。
【主任・リーダー保育士】の例文とポイント
主任やリーダーは、園の運営や職員のマネジメントという重要な役割を担います。 園長を補佐し、園全体の保育の方向性を示し、職員をまとめるリーダーシップが評価のポイントです。
【例文】
【できたこと・自己評価】
園長の方針のもと、園全体の保育の質が向上するよう、各クラスの状況を把握し、職員への助言やサポートを行いました。 定期的な面談を通して職員一人ひとりのキャリアプランや悩みに耳を傾け、働きやすい職場環境づくりに努めました。保護者や地域からの信頼を得られるよう、園の代表として丁寧な対応を心がけました。
【課題・改善点】
各職員の能力や個性をさらに引き出し、適材適所の人員配置を行うための視点が不足していました。また、多岐にわたる業務の中で、情報共有の仕組みに改善の余地があると感じています。
【来年度の目標】
来年度は、職員一人ひとりの強みが発揮できるような業務分担やチーム編成を検討します。ICTツールなども活用しながら、園内の情報伝達をよりスムーズにし、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。
【乳児クラス担当】の例文とポイント
乳児クラスでは、一人ひとりの生活リズムや発達に合わせた、丁寧で愛着形成を重視した関わりが何よりも大切です。 安全への配慮と、保護者との密な連携を具体的に記述しましょう。
【例文】
【できたこと・自己評価】
一人ひとりの子どもの欲求を丁寧にくみ取り、スキンシップを大切にしながら、安心して過ごせる環境づくりに努めました。 連絡帳や送迎時の対話を通して、家庭での様子を細やかに伺い、園と家庭とで連携を取りながら離乳食や生活習慣の自立を進めることができました。ささいな変化も見逃さないよう、常に子どもの表情やしぐさに注意を払い、安全な環境を保ちました。
【課題・改善点】
言葉でのコミュニケーションが難しい分、子どもの気持ちを的確に読み取れないこともあり、試行錯誤の連続でした。また、複数の子どもが同時に泣いてしまった際の対応に、より工夫が必要だと感じました。
【来年度の目標】
来年度は、わらべうたやふれあい遊びのレパートリーを増やし、子どもとの情緒的な関わりをさらに深めていきたいです。また、発達心理に関する知識を学び直し、非言語的なサインから子どもの思いをより深く理解できるよう努めます。
【幼児クラス担当】の例文とポイント
幼児クラスでは、子どもの自主性や協同性を育む活動、そして就学を見据えた育ちの援助が重要なテーマになります。 子ども同士の関わりをどう促したか、という視点がポイントです。
【例文】
【できたこと・自己評価】
子どもたちの「やってみたい」という気持ちを尊重し、遊びが発展していくような環境構成や声かけを意識しました。友達との間で葛藤が生まれた際には、すぐに仲裁に入るのではなく、子どもたち自身で気持ちを伝え合い、解決しようとする過程を見守り、必要に応じて援助することができました。 就学に向けて、時計を意識した行動や、自分の持ち物を管理する習慣が身につくよう、根気強く働きかけました。
【課題・改善点】
クラス全体での活動において、一部の子どもに活動への参加を促すことに難しさを感じました。一人ひとりの興味関心に、よりきめ細かく対応する必要があったと反省しています。
【来年度の目標】
来年度は、一斉活動の中にも個別に対応できるような計画を工夫し、すべての子どもが「楽しい」と感じられる保育を目指します。また、小学校との連携をさらに密にし、子どもたちが期待をもって就学できるよう、より具体的な接続活動を取り入れていきます。
どうしても書けない…自己評価が苦手な保育士さんのための克服法
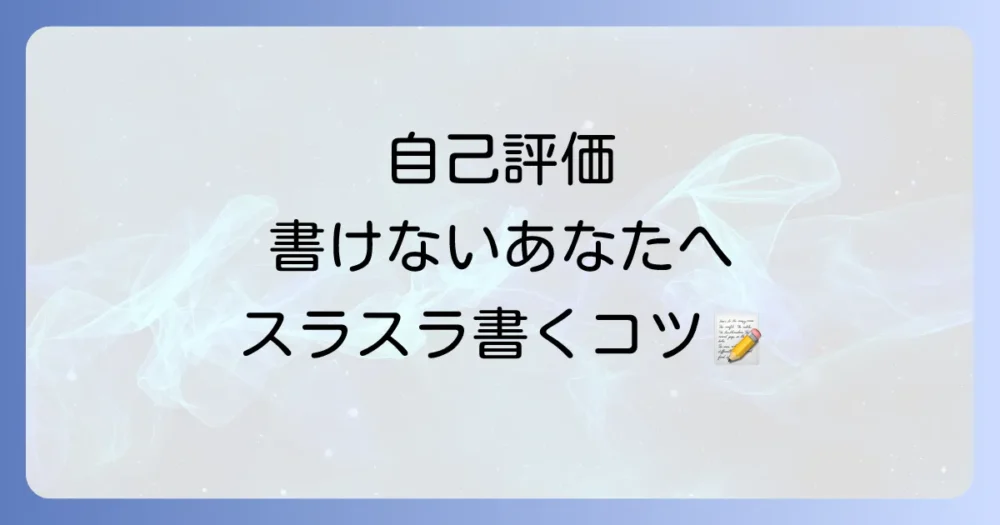
「例文を読んでも、自分の言葉で書こうとすると手が止まってしまう…」そんな風に、自己評価に苦手意識を持っている方も少なくないでしょう。大丈夫です。ここでは、書けない悩みを解決するための具体的な方法をいくつかご紹介します。
この章では、以下の内容について解説します。
- 1年間の保育記録や日誌を振り返る
- 同僚や先輩に相談してみる
- 小さな目標から設定してみる
- ポジティブな言葉に言い換える練習
1年間の保育記録や日誌を振り返る
記憶だけで書こうとすると、どうしても漠然とした内容になりがちです。まずは、ご自身が書きためてきた保育日誌、週案・月案、行事の記録、クラスだよりの原稿などを机に広げてみましょう。
そこには、あなたが子どもたちと過ごした日々の具体的な記録が詰まっています。「あの子がこんな言葉を話せるようになった日」「この行事の準備、大変だったけど子どもたちが喜んでくれたな」など、具体的なエピソードが次々と思い出されるはずです。その一つひとつのエピソードが、あなたの自己評価を裏付ける大切な根拠になります。
同僚や先輩に相談してみる
一人で抱え込まず、信頼できる同僚や先輩に相談してみるのも非常に有効な方法です。 「自己評価、何を書いたらいいか分からなくて…」と正直に打ち明けてみましょう。
自分では気づかなかった自分の強みや、成長した点を客観的な視点から教えてもらえるかもしれません。 「〇〇先生、あの子への声かけがすごく丁寧でいつも感心してるよ」「去年に比べて、保護者対応がすごくスムーズになったよね」といった言葉が、自信につながることもあります。また、他の先生がどんな視点で自己評価を書いているのかを聞くのも、大きな参考になるでしょう。
小さな目標から設定してみる
「立派なことを書かなければ」と気負いすぎていませんか?自己評価は、完璧な自分をアピールする場ではありません。まずは、ごく身近で小さな「できたこと」を探してみましょう。
例えば、「毎日、子ども全員の名前を呼んで挨拶ができた」「手遊びのレパートリーが3つ増えた」 「苦手だった保護者に、自分から声をかけられた」など、どんなに些細なことでも構いません。小さな成功体験を積み重ねていくことで、自己肯定感が高まり、書くことへのハードルがぐっと下がります。
ポジティブな言葉に言い換える練習
自己評価を書く際、つい「~できなかった」「~が足りなかった」という反省点ばかりに目が行きがちです。もちろん課題の分析は大切ですが、ネガティブな表現ばかりでは、書いている自分も辛くなってしまいます。
そこで、ネガティブな事実をポジティブな課題設定に言い換える練習をしてみましょう。 例えば、
- 「計画通りに進まなかった」→「子どもの実態に合わせて、柔軟に対応する必要性を学んだ」
- 「保護者への説明がうまくできなかった」→「より具体的に伝えるための語彙力向上が今後の課題」
- 「子ども同士のトラブルにすぐ介入してしまった」→「子ども自身で解決する力を見守る視点を持ちたい」
このように視点を変えるだけで、前向きな目標設定につながり、自己評価を「成長のためのステップ」として捉えられるようになります。
自己評価を提出する際の注意点と今後の活かし方
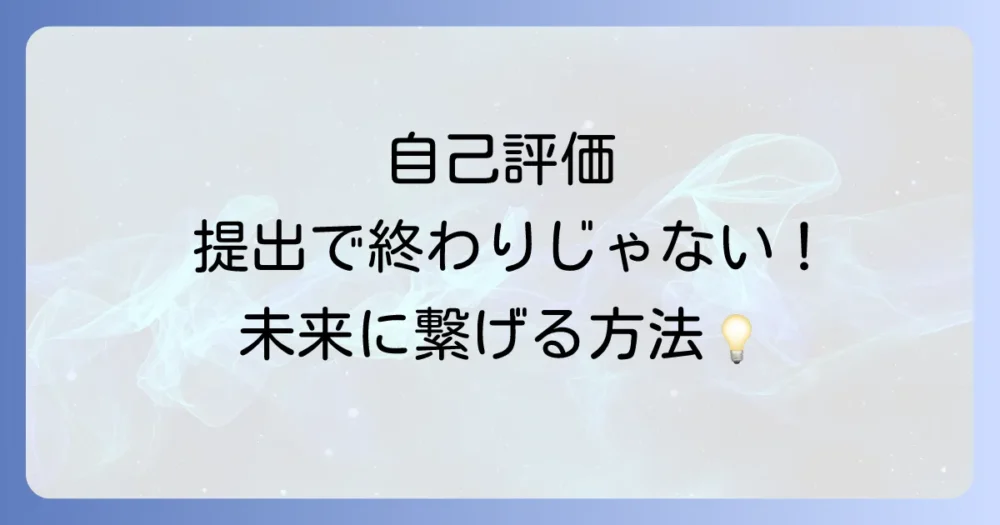
自己評価を書き終えたら、それで終わりではありません。提出する際の注意点を押さえ、その後の面談や来年度の保育にどう活かしていくかが非常に重要です。自己評価を、やりっぱなしの作業にしないためのポイントをお伝えします。
この章では、以下の内容について解説します。
- 嘘や誇張はNG!客観的な事実を基に書く
- 謙遜しすぎず、できたことを正当に評価する
- 園長や上司からのフィードバックを真摯に受け止める
- 次年度の目標設定に繋げる
嘘や誇張はNG!客観的な事実を基に書く
自分を良く見せたいという気持ちから、事実を誇張したり、やっていないことを書いたりするのは絶対にやめましょう。自己評価は、園長や上司との面談の資料にもなります。具体的なエピソードについて質問された際に、しどろもどろになってしまっては、かえって信頼を失いかねません。
大切なのは、保育日誌などの記録に基づいた客観的な事実を記述することです。 等身大の自分を正直に表現することが、適切な評価と次への成長につながります。
謙遜しすぎず、できたことを正当に評価する
特に真面目な方ほど、「まだまだです」「できていません」と謙遜しすぎてしまう傾向があります。しかし、自己評価はあなたの1年間の頑張りを伝える大切な機会です。できたこと、成長したことは、自信を持って具体的に記述しましょう。
例えば、「子どもとの信頼関係を築けた」と書くだけでなく、「人見知りだったAちゃんが、私には笑顔で駆け寄ってきてくれるようになった」というように、具体的なエピソードを添えると、評価する側にもあなたの努力がより明確に伝わります。
園長や上司からのフィードバックを真摯に受け止める
自己評価を提出した後、多くの場合、園長や主任との面談が行われます。そこでは、あなたの自己評価に対するフィードバックが伝えられます。自分では気づかなかった強みを褒めてもらえることもあれば、厳しい指摘を受けることもあるかもしれません。
どんな内容であれ、それはあなたの成長を願っての貴重なアドバイスです。 感情的にならず、まずは真摯に耳を傾けましょう。もし、評価に納得できない点があれば、「なぜそのように評価されたのか」を冷静に質問し、認識のズレを埋めていくことが大切です。この対話こそが、自己評価をより意味のあるものにします。
次年度の目標設定に繋げる
自己評価の最終的なゴールは、「次の保育をより良くすること」です。 自己評価で明らかになった課題や、面談で受けたアドバイスをもとに、来年度の具体的な目標を設定しましょう。
「来年度は、〇〇に関する研修に参加する」「保護者とのコミュニケーション方法として、△△を試してみる」など、具体的で実行可能なアクションプランに落とし込むことがポイントです。 作成した自己評価シートは、年度末にしまい込まず、来年度の保育に迷ったときに見返せるようにしておくと、自分自身の成長の羅針盤となってくれるでしょう。
よくある質問
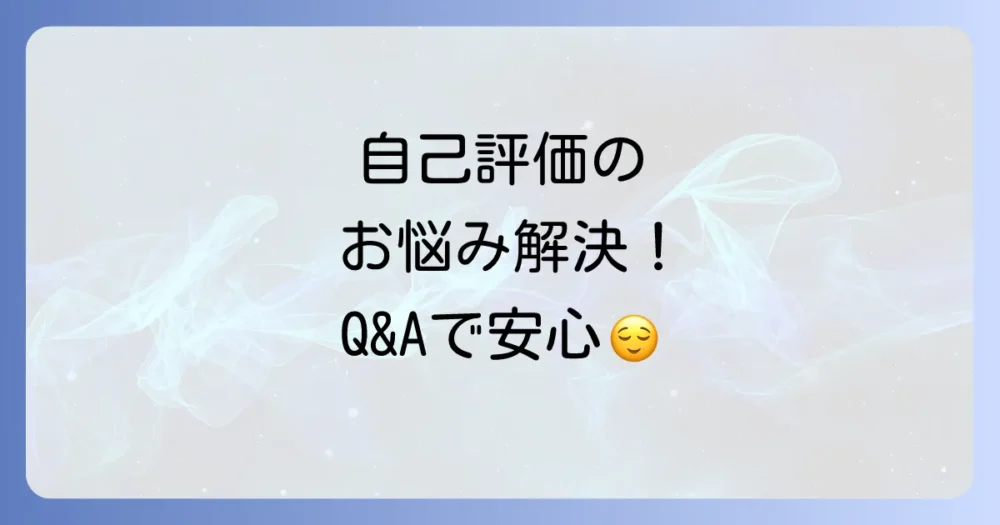
ここでは、保育士の自己評価に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
自己評価シートはどこでダウンロードできますか?
多くの保育園では、園独自のフォーマットが用意されています。 まずはご自身の園で配布されるものを使用するのが基本です。もし、個人的に参考にしたい、または園で特定のフォーマットがない場合は、インターネット上で「保育士 自己評価シート テンプレート 無料」などと検索すると、様々な書式のものをダウンロードできるサイトが見つかります。 自治体のホームページで、管内の保育園向けの参考様式を公開している場合もありますので、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認してみるのも良いでしょう。
自己評価はいつまでに書けばいいですか?
自己評価シートを記入・提出する時期は、園によって異なりますが、一般的には年度末が近づく1月~3月頃に行われることが多いです。園の人事評価や、次年度のクラス編成、指導計画の作成などと連動しているため、園から示される提出期限は必ず守るようにしましょう。余裕を持って取り組めるよう、早めに1年間の振り返りを始めておくことをおすすめします。
パートや非正規の保育士も自己評価は必要ですか?
はい、必要となるケースがほとんどです。保育所保育指針が示す自己評価の努力義務は、正規・非正規といった雇用形態に関わらず、すべての保育士等を対象としています。 もちろん、常勤の職員とは評価項目や求められるレベルが異なる場合はありますが、パート職員であっても、自身の保育を振り返り、質の向上を目指す姿勢は同様に重要です。 自分の働き方の中で、どのような貢献ができたか、今後の課題は何か、という視点で記述しましょう。
自己評価の文字数はどのくらいが適切ですか?
これも園の書式によって異なりますが、各項目について200字~400字程度でまとめるのが一般的です。長すぎると要点が伝わりにくく、短すぎると具体性に欠けてしまいます。大切なのは文字数そのものよりも、具体的なエピソードを交えながら、評価の根拠を分かりやすく記述することです。まずは要点を箇条書きで整理してから、文章にまとめていくとスムーズです。
良い評価をもらうためのコツはありますか?
良い評価を得るためには、単に「できました」と書くだけでなく、園の保育理念や方針を理解し、それに貢献できた点をアピールすることが重要です。 また、課題や反省点を書く際に、「~が課題なので、来年度は〇〇という研修に参加して改善したいです」のように、改善に向けた具体的な行動目標をセットで示すと、向上心や意欲が高いと評価されやすくなります。 ポジティブな表現を心がけることもポイントです。
自己評価と他者評価が違う場合はどうすればいいですか?
自己評価と、園長や上司からの他者評価にギャップがあることは、決して珍しいことではありません。 大切なのは、その違いをネガティブに捉えるのではなく、自己理解を深めるチャンスと考えることです。面談などの場で、「私は〇〇と考えていたのですが、△△と評価いただいた理由をもう少し詳しく教えていただけますか?」と、冷静に理由を尋ねてみましょう。自分では気づかなかった視点や、相手からの期待を知ることで、より客観的に自分を見つめ直すことができます。
まとめ
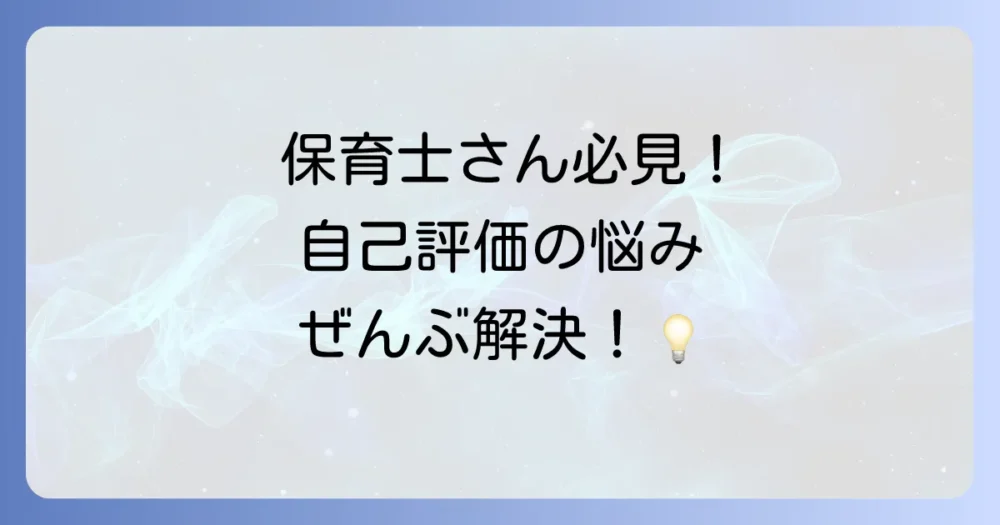
- 自己評価は保育の質の向上と自身の成長のために不可欠です。
- キャリアアップや処遇改善にも繋がる重要な取り組みです。
- 厚生労働省のガイドラインが自己評価の根拠となっています。
- 評価項目は「保育実践」「家庭・地域連携」「運営体制」が基本です。
- 園独自の方針を理解し、それに沿って書くことが大切です。
- 経験年数や立場に応じた視点で振り返りましょう。
- 1年目・新人は学ぶ姿勢を、3年目・中堅は主体性をアピールします。
- 5年目以上・ベテランは専門性と園への貢献を記述します。
- 主任・リーダーはマネジメントやリーダーシップが問われます。
- 書けない時は保育記録を振り返り、同僚に相談しましょう。
- 小さな「できたこと」を見つけ、ポジティブな言葉で書くのがコツです。
- 嘘や誇張はせず、客観的な事実に基づいて記述します。
- できたことは謙遜しすぎず、具体的にアピールしましょう。
- 上司からのフィードバックは真摯に受け止め、対話することが大切です。
- 自己評価を次年度の具体的な目標設定に活かすことがゴールです。
新着記事