「古文の『ぬべし』って、どうやって品詞分解すればいいの…?」「『ぬ』と『べし』、それぞれの意味が複雑で訳せない…」古文の学習で、そんな悩みを抱えていませんか?助動詞が2つ続く「ぬべし」は、多くの学習者がつまずきやすいポイントです。しかし、それぞれの助動詞の役割を正しく理解すれば、決して難しいものではありません。
本記事では、「ぬべし」の品詞分解を、古文が苦手な方にも分かりやすく、ステップバイステップで徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、「ぬべし」への苦手意識がなくなり、自信を持って現代語訳できるようになるでしょう。
結論:「ぬべし」は完了の助動詞「ぬ」+推量の助動詞「べし」
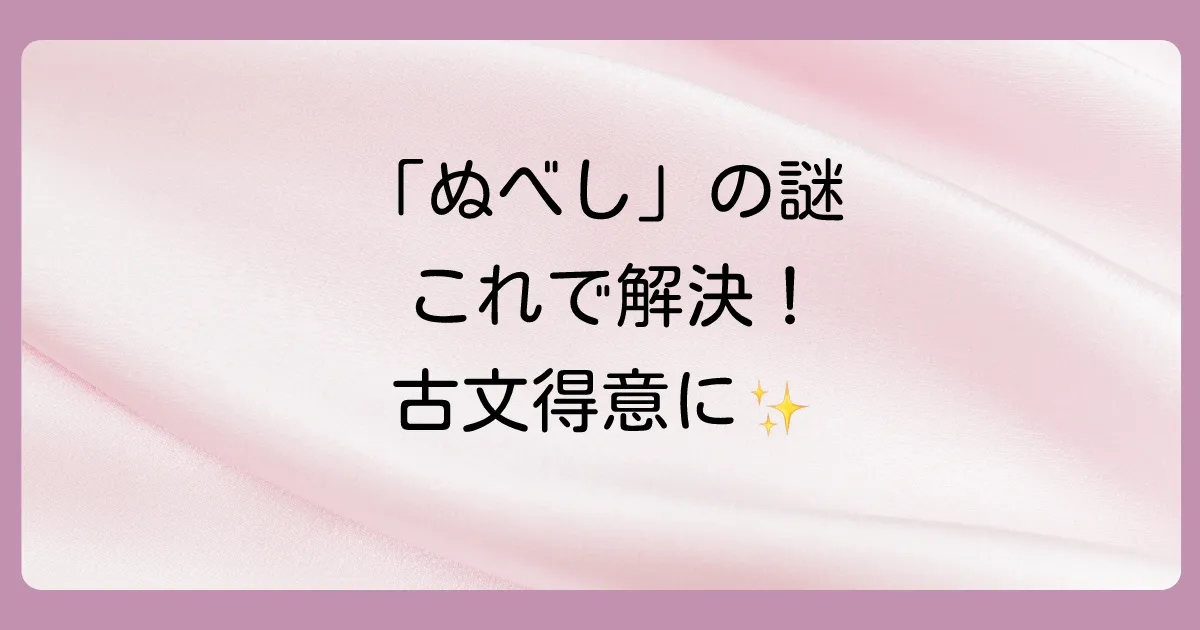
まず結論からお伝えします。「ぬべし」は、完了の助動詞「ぬ」の終止形と、推量の助動詞「べし」が組み合わさった形です。 この2つの助動詞が連続することで、意味を強める働きをします。品詞分解する際は、まず「ぬ」と「べし」に分け、それぞれの意味や活用を考えるのが基本です。
この章では、「ぬべし」を分解した「ぬ」と「べし」それぞれの基本的な情報と、品詞分解の全体像を掴んでいきましょう。
- ステップ1:助動詞「ぬ」を品詞分解する
- ステップ2:助動詞「べし」を品詞分解する
- 「ぬべし」の訳し方のコツとパターン
- 品詞分解でつまずかないための重要ポイント
以下の表で、「ぬ」と「べし」の基本情報を確認してください。
| 助動詞「ぬ」 | 助動詞「べし」 | |
|---|---|---|
| 意味 | ①完了(~てしまった) ②強意(きっと~) | ①推量(~だろう) ②意志(~よう) ③可能(~できる) ④当然(~はずだ) ⑤命令(~せよ) ⑥適当(~のがよい) |
| 活用 | ナ行変格活用(な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね) | 形容詞型(ク活用)((べく)・べから/べく・べかり/べし/べき・べかる/べけれ/〇) |
| 接続 | 連用形 | 終止形(ラ変型には連体形) |
ステップ1:助動詞「ぬ」を品詞分解する
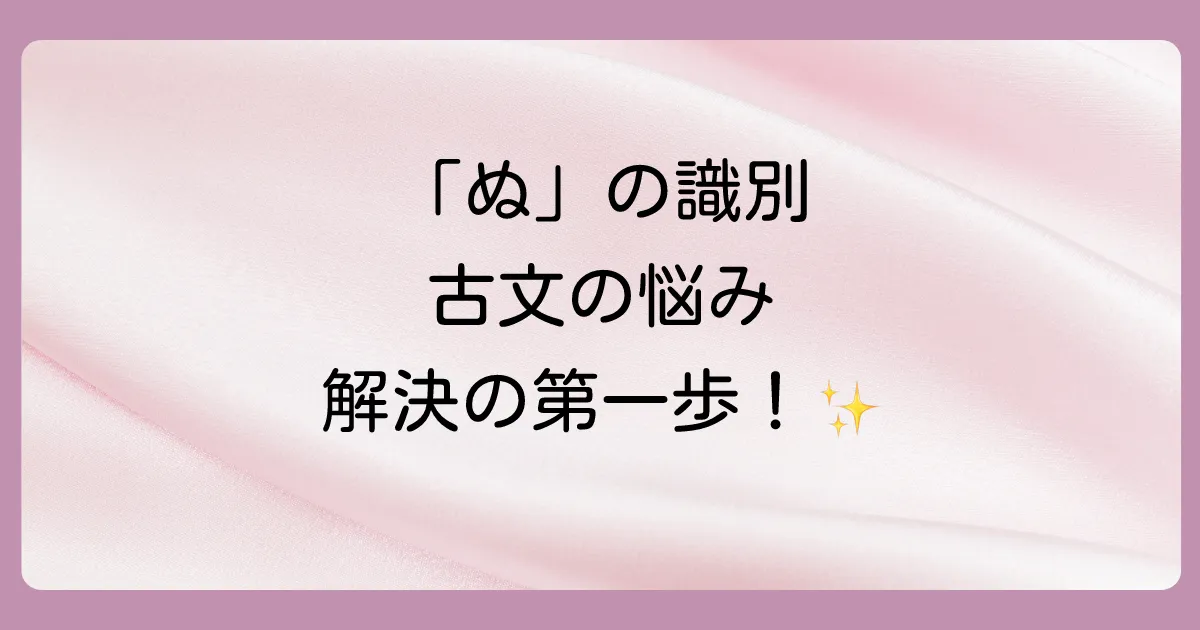
「ぬべし」の品詞分解、最初のステップは助動詞「ぬ」の理解です。「ぬ」は古文で頻出の助動詞ですが、複数の意味や紛らしい識別があるため、正確に捉えることが重要です。ここで「ぬ」の基本をしっかり押さえ、品詞分解の土台を固めましょう。
この章では、以下の内容について詳しく解説していきます。
- 助動詞「ぬ」の基本情報(接続・活用・意味)
- 例文で見る「ぬ」の品詞分解
助動詞「ぬ」の基本情報(接続・活用・意味)
助動詞「ぬ」を理解するためには、「接続」「活用」「意味」の3つのポイントを押さえることが不可欠です。これらは「ぬ」が文中どのような働きをするかを決定づける重要な要素です。
接続:連用形に接続
助動詞「ぬ」は、動詞や一部の助動詞の連用形に接続します。 例えば、「花咲きぬ」の「咲き」は、動詞「咲く」の連用形です。この接続のルールは、「ぬ」が完了の助動詞か、それとも他の語(例えば打消の助動詞「ず」の連体形)かを見分ける上で非常に重要な手がかりとなります。
活用:ナ行変格活用
「ぬ」の活用は、動詞のナ行変格活用(死ぬ、往ぬ)と同じく、「な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね」と変化します。 この活用を覚えておくことで、文中で「ぬ」がどのような形で現れても、正しく識別できるようになります。
| 活用形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬ | な | に | ぬ | ぬる | ぬれ | ね |
意味:完了と強意
助動詞「ぬ」には、主に2つの意味があります。
- 完了:「~てしまった」「~た」と訳します。動作や作用が完了したことを表す、最も基本的な意味です。
- 強意:「きっと~」「必ず~」と訳します。他の語(特に推量や意志を表す助動詞)と結びついて、その意味を強める働きをします。 「ぬべし」の「ぬ」はこちらの強意で使われることが多いです。
完了と強意の見分け方は、文脈判断が基本ですが、一般的に「ぬ」の後に推量の助動詞(む、べし、らむ、まし など)が続く場合は強意、そうでない場合は完了と判断することが多いです。このパターンを覚えておくと、読解のスピードが格段に上がりますよ。
例文で見る「ぬ」の品詞分解
それでは、実際の例文を通して「ぬ」の品詞分解を見ていきましょう。具体的な文の中でどのように使われているかを確認することで、理解がより深まります。
例文1:秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる(古今和歌集)
- 品詞分解:秋来(カ行変格活用動詞「来」の連用形)+ぬ(完了の助動詞「ぬ」の終止形)
- 現代語訳:秋が来たと、目にははっきりと見えないけれど、風の音で(秋の到来に)はっと気づかされたことだ。
この例文の「来ぬ」の「ぬ」は、動詞「来(く)」の連用形「来(き)」に接続しており、文末にあることから終止形であることがわかります。意味は「秋が来てしまった」という「完了」です。
例文2:今は昔、竹取の翁といふものありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきの造となむいひける。その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。
この有名な『竹取物語』の冒頭部分には、助動詞「ぬ」は直接出てきませんが、品詞分解の練習として見てみましょう。品詞分解は、このように文章の最小単位に区切り、それぞれの品詞と活用形を明らかにしていきます。 この地道な作業が、古文読解の正確性を高めるのです。
ステップ2:助動詞「べし」を品詞分解する
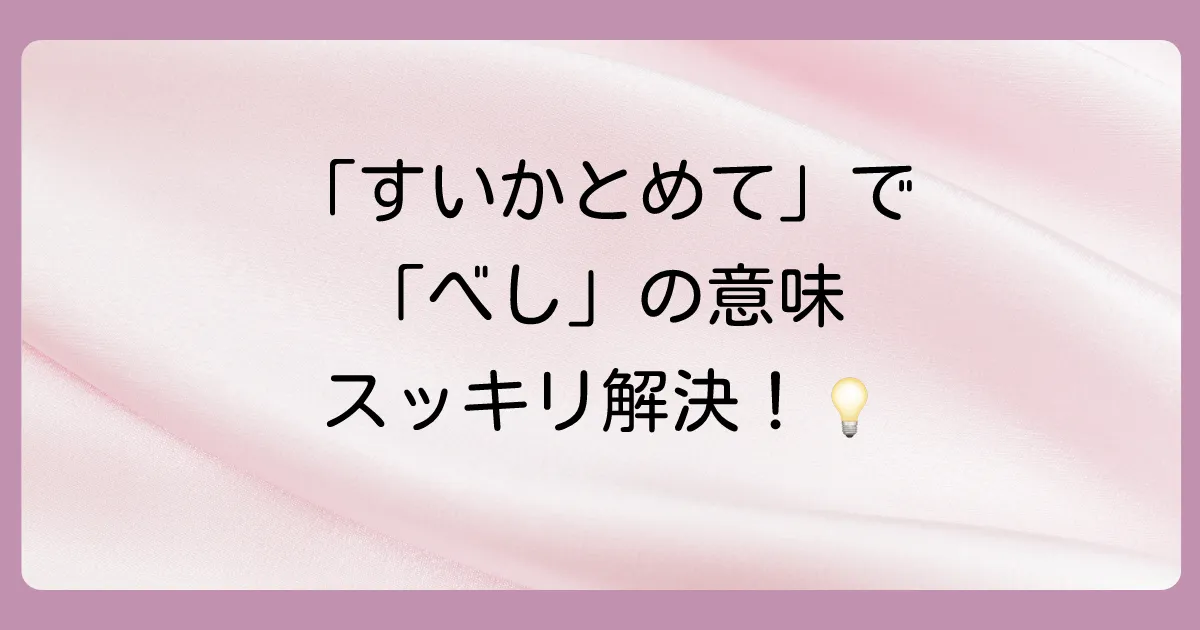
「ぬ」を理解したら、次は「べし」です。「べし」は意味が多岐にわたるため、難しく感じるかもしれませんが、基本的なルールと見分け方のコツさえ掴めば大丈夫です。このステップで「べし」をマスターし、「ぬべし」の完全理解に繋げましょう。
この章では、以下の内容を詳しく解説します。
- 助動詞「べし」の基本情報(接続・活用・意味)
- 例文で見る「べし」の品詞分解
助動詞「べし」の基本情報(接続・活用・意味)
助動詞「べし」を攻略する鍵も、「接続」「活用」「意味」の3点セットです。特に意味の多さが特徴ですが、一つひとつ整理していけば怖くありません。
接続:終止形に接続(ラ変型には連体形)
助動詞「べし」は、原則として活用語の終止形に接続します。 ただし、相手がラ行変格活用(あり、をり、はべり、いまそかり)の語の場合は、連体形に接続するという重要な例外があります。 「ぬべし」の場合は、完了の助動詞「ぬ」の終止形に接続しています。
活用:形容詞型(ク活用)
「べし」の活用は、ク活用の形容詞と同じです。「(べく)・べから/べく・べかり/べし/べき・べかる/べけれ/〇」と活用します。 形容詞の活用を覚えていれば、そのまま応用できますね。
| 活用形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| べし | (べく) べから | べく べかり | べし | べき べかる | べけれ | 〇 |
意味:6つの意味(推量・意志・可能・当然・命令・適当)
「べし」の最大の難関が、この6つの意味です。 しかし、これには有名な覚え方があります。
「すいかとめて」で覚えましょう!
- す:推量(~にちがいない、~だろう)
- い:意志(~しよう、~するつもりだ)
- か:可能(~できる、~できそうだ)
- と:当然(~はずだ、~べきだ)
- め:命令(~せよ)
- て:適当(~のがよい)
これらの意味は、文脈や主語の人称によって見分けます。 例えば、主語が一人称(私)なら「意志」、二人称(あなた)なら「命令・適当」、三人称なら「推量」になることが多いです。 また、「~べからず」のように下に打消の語を伴う場合は「可能」の意味(~できない)になることが多い、というルールもあります。
例文で見る「べし」の品詞分解
それでは、実際の例文で「べし」がどのように使われるかを見ていきましょう。意味の多さに惑わされず、文脈から最適な訳を見つける練習です。
例文1:子となり給ふべき人なめり。(竹取物語)
- 品詞分解:給ふ(ハ行四段活用動詞「給ふ」の連体形)+べき(当然の助動詞「べし」の連体形)
- 現代語訳:(私)の子におなりになるはずの人であるようだ。
この文では、「べき」の下に名詞「人」が来ているため、連体形です。文脈から、かぐや姫が翁の子になる運命であることを示しており、「当然」の意味で訳すのが最も自然です。
例文2:家の造りやうは、夏をむねとすべし。(徒然草)
- 品詞分解:す(サ行変格活用動詞「す」の終止形)+べし(適当の助動詞「べし」の終止形)
- 現代語訳:家の造り方は、夏(に暮らしやすいこと)を主とするのがよい。
この文は、筆者(兼好法師)の考えを述べている部分です。「~するのがよい」と訳す「適当」の意味がしっくりきます。このように、文章の種類(物語、随筆など)も意味を判断するヒントになります。
「ぬべし」の訳し方のコツとパターン
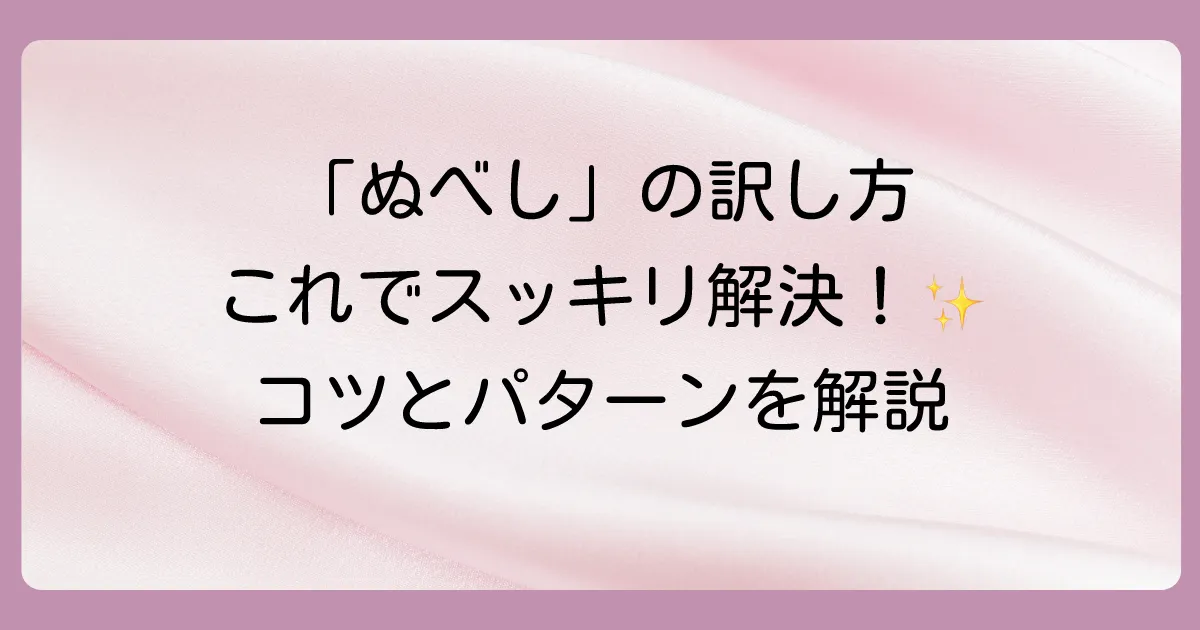
「ぬ」と「べし」をそれぞれ理解したところで、いよいよ本題の「ぬべし」の訳し方です。基本的には「ぬ」の強意と「べし」の各意味を組み合わせることで、自然な現代語訳ができます。ここでは、代表的な訳し方のパターンと、実際の例文での応用を見ていきましょう。
この章で解説する主な内容は以下の通りです。
- 「強意+推量」で訳すのが基本
- 文脈に応じた様々な訳し方
- 例文で実践!「ぬべし」の現代語訳
「強意+推量」で訳すのが基本
「ぬべし」の最も基本的な訳し方は、「ぬ」を強意、「べし」を推量として組み合わせるパターンです。 これにより、「きっと~だろう」「~にちがいない」「~てしまうだろう」といった、確信度の高い推量を表すことができます。 古文で「ぬべし」が出てきたら、まずこの訳を当てはめてみると、文意が通ることが多いです。
例えば、「雨降りぬべし」という文があった場合、「雨が降る」という事態に、強意の「ぬ」と推量の「べし」が加わります。そのため、「きっと雨が降るだろう」「雨が降ってしまうにちがいない」と訳すことができ、単に「雨が降るだろう」と推量するよりも、確信の度合いが強いニュアンスが伝わります。
文脈に応じた様々な訳し方
基本は「強意+推量」ですが、「べし」が持つ他の意味と「ぬ」の強意が結びつくこともあります。文脈に応じて、柔軟に訳し分けることが重要です。
- 強意 + 意志:「きっと~しよう」「必ず~してしまうつもりだ」
- 強意 + 当然:「きっと~はずだ」「~してしまわなければならない」
- 強意 + 適当:「きっと~するのがよい」「~してしまうのがよい」
- 強意 + 可能:「きっと~できるだろう」「~できそうだ」
どの意味が最も適切かは、前後の文脈や、主語の人称、会話文か地の文か、といった要素から総合的に判断する必要があります。例えば、主語が一人称で決意を述べるような場面であれば「強意+意志」、社会的な常識や道理について述べている場面であれば「強意+当然」が当てはまりやすいでしょう。
例文で実践!「ぬべし」の現代語訳
それでは、古典作品の実際の例文を使って、「ぬべし」の訳し方を実践してみましょう。
例文1:潮満ちぬ。風も吹きぬべし。(土佐日記)
- 品詞分解:吹き(カ行四段活用動詞「吹く」の連用形)+ぬ(強意の助動詞「ぬ」の終止形)+べし(推量の助動詞「べし」の終止形)
- 現代語訳:潮も満ちてきた。風もきっと吹くだろう。
これは「強意+推量」の典型的な例です。「潮が満ちてきた」という状況から、「風も吹くだろう」と強く推量している様子がうかがえます。
例文2:さらずまかりぬべければ、おぼし嘆かむが悲しきことを…(竹取物語)
- 品詞分解:まかり(ラ行四段活用動詞「まかる」の連用形)+ぬ(強意の助動詞「ぬ」の終止形)+べけれ(当然の助動詞「べし」の已然形)
- 現代語訳:どうしても(月の世界へ)帰ってしまわなければならないので、(翁たちが)お嘆きになるだろうことが悲しいのです。
これはかぐや姫が昇天する場面のセリフです。自分の意志では逆らえない運命について語っているため、「強意+当然(義務)」で訳すのが適切です。「~しなければならない」という強い義務感を表しています。
例文3:我はかくて閉ぢこもりぬべきぞ。(更級日記)
- 品詞分解:こもり(ラ行四段活用動詞「こもる」の連用形)+ぬ(強意の助動詞「ぬ」の終止形)+べき(意志の助動詞「べし」の連体形)
- 現代語訳:私はこうして(家に)閉じこもってしまうつもりだ。
この文の主語は「我(私)」、つまり一人称です。そのため、「べし」は「意志」と解釈するのが自然です。「ぬ」の強意と合わさって、「必ず閉じこもる」という強い決意が表現されています。
品詞分解でつまずかないための重要ポイント
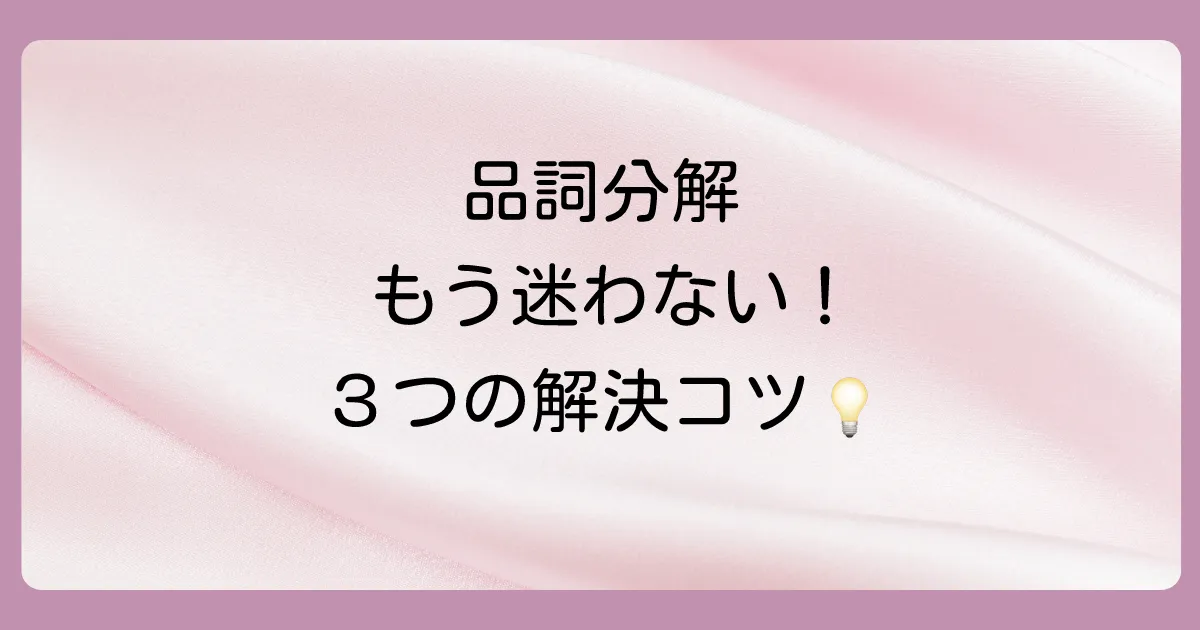
品詞分解は、古文を正確に読解するための基礎体力です。特に「ぬ」のように、形が同じで意味が異なる語を正しく見分けることが、読解の精度を大きく左右します。ここでは、品詞分解でつまずきがちなポイントと、その解決策を解説します。
この章で取り上げるのは、以下の3つのポイントです。
- 識別が重要!「ぬ」と他の語の見分け方
- 活用の暗記は必須!効率的な覚え方
- とにかく多くの文章に触れる
識別が重要!「ぬ」と他の語の見分け方
古文には、「ぬ」という音を持つ語が複数存在します。これらを正しく識別することが、品詞分解の第一歩です。特に注意すべきは以下の3つです。
- 完了の助動詞「ぬ」
- 接続:連用形
- 意味:完了(~てしまった)、強意(きっと~)
- 見分け方:上の語が連用形になっているかで判断します。「花咲きぬ」の「咲き」は連用形なので、この「ぬ」は完了の助動詞です。
- 打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」
- 接続:未然形
- 意味:~ない
- 見分け方:上の語が未然形であり、下に名詞(体言)が続く場合が多いです。「見ぬ人」の「見」は未然形、「人」は名詞なので、この「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形です。
- ナ行変格活用動詞「死ぬ」「往(い)ぬ」の一部
- 見分け方:これは文脈で判断するしかありません。「山に往ぬ」と言えば「山に行ってしまう」という意味の動詞です。 助動詞ではないので注意しましょう。
この識別の鍵は、直前の語の活用形です。連用形接続なら完了、未然形接続なら打消。このルールを徹底することが、混乱を避けるための最も確実な方法です。
活用の暗記は必須!効率的な覚え方
品詞分解の土台となるのが、動詞や助動詞の活用を正確に覚えていることです。活用が分からなければ、接続を見分けることもできません。退屈な作業に思えるかもしれませんが、ここを乗り越えれば古文の世界が一気に広がります。
効率的な暗記のコツは、声に出してリズムで覚えることです。例えば、完了の助動詞「ぬ」なら「な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね」と何度も唱える。助動詞「べし」なら「べく・べから・べく・べかり・べし・べき・べかる・べけれ」と、呪文のように口ずさむことで、自然と頭に入ってきます。
また、ただ暗記するだけでなく、「なぜこの活用形になるのか」を意識することも大切です。例えば、「ぬる」の後には名詞が来ることが多い(連体形だから)、「ぬれ」の後には「ば」が来ることが多い(已然形だから)といったように、活用形とそれに続く語の関係性をセットで覚えると、より実践的な知識になります。
とにかく多くの文章に触れる
文法知識を覚えたら、最後は実践あるのみです。品詞分解は、スポーツや楽器の練習と同じで、反復練習によって上達します。 最初は時間がかかっても、一文一文丁寧に品詞分解を行うことで、だんだんとスピードと正確性が上がっていきます。
学校の教科書や問題集に出てくる文章を、すべて品詞分解するくらいの気持ちで取り組んでみましょう。 分からない単語や文法が出てきたら、その都度辞書や参考書で確認する。この地道な作業の繰り返しが、盤石な古文読解力を築き上げます。多くの文章に触れることで、文法知識が単なる暗記事項ではなく、「生きた知識」として定着していくのを実感できるはずです。
よくある質問
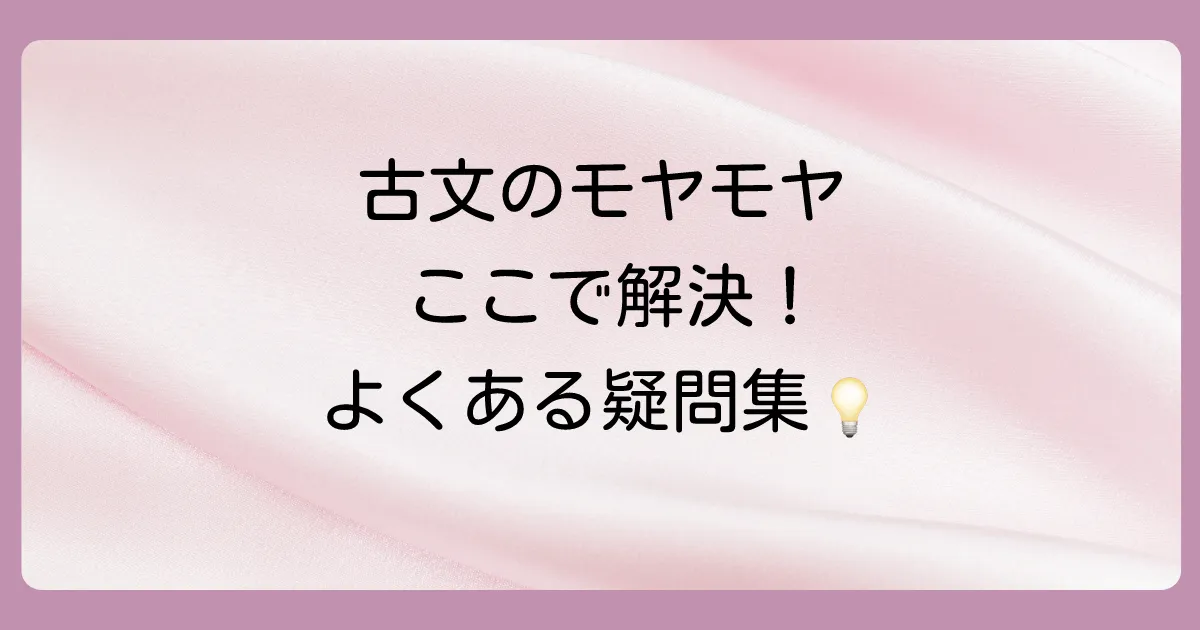
「ぬべし」の品詞は何ですか?
「ぬべし」は、完了(または強意)の助動詞「ぬ」の終止形と、推量の助動詞「べし」が接続した連語(二つ以上の単語が結びついて一つの単語のように使われる語)です。 品詞分解する際は、「ぬ」と「べし」という二つの助動詞に分けて考えます。
助動詞「ぬ」の意味は何ですか?
助動詞「ぬ」には、主に二つの意味があります。
- 完了:「~てしまった」「~た」と訳し、動作が完了したことを表します。
- 強意:「きっと~」「必ず~」と訳し、後に続く語の意味を強めます。「ぬべし」の「ぬ」はこちらの意味で使われることが多いです。
助動詞「べし」の意味が多すぎて覚えられません。
助動詞「べし」には6つの意味がありますが、語呂合わせで覚えるのがおすすめです。「すいかとめて」と覚えましょう。
- す:推量(~だろう)
- い:意志(~しよう)
- か:可能(~できる)
- と:当然(~べきだ)
- め:命令(~せよ)
- て:適当(~のがよい)
どの意味になるかは、文脈や主語の人称で見分けるのが基本です。
「ぬ」と「ね」の違いは何ですか?
「ぬ」と「ね」は、同じ助動詞から派生することがありますが、品詞や意味が異なります。注意すべきは以下の2つの助動詞です。
- 完了の助動詞「ぬ」:活用形が「な・に・ぬ(終止形)・ぬる・ぬれ(已然形)・ね(命令形)」です。 つまり、「ぬ」は終止形、「ね」は命令形です。
- 打消の助動詞「ず」:活用形が「ず・ず・ぬ(連体形)・ね(已然形)・ざら・ざり・ざる・ざれ」です。 この場合、「ぬ」は連体形、「ね」は已然形です。
どちらの助動詞かを見分けるには、直前の語の活用形(接続)を確認することが重要です。連用形に接続していれば完了、未然形に接続していれば打消です。
品詞分解はなぜ勉強する必要があるのですか?
品詞分解は、古文を感覚ではなく論理的に、正確に読解するために不可欠なスキルです。 古文は主語が省略されたり、現代語とは語順が異なったりすることが多いため、単語の意味だけを追っていても内容を正しく理解できません。 一つ一つの単語の品詞や活用形、接続関係を明らかにすることで、文の構造が明確になり、筆者の意図を正確に読み取れるようになります。大学入試などでは、この品詞分解の知識が直接問われることも多く、古文学習の根幹と言えます。
まとめ
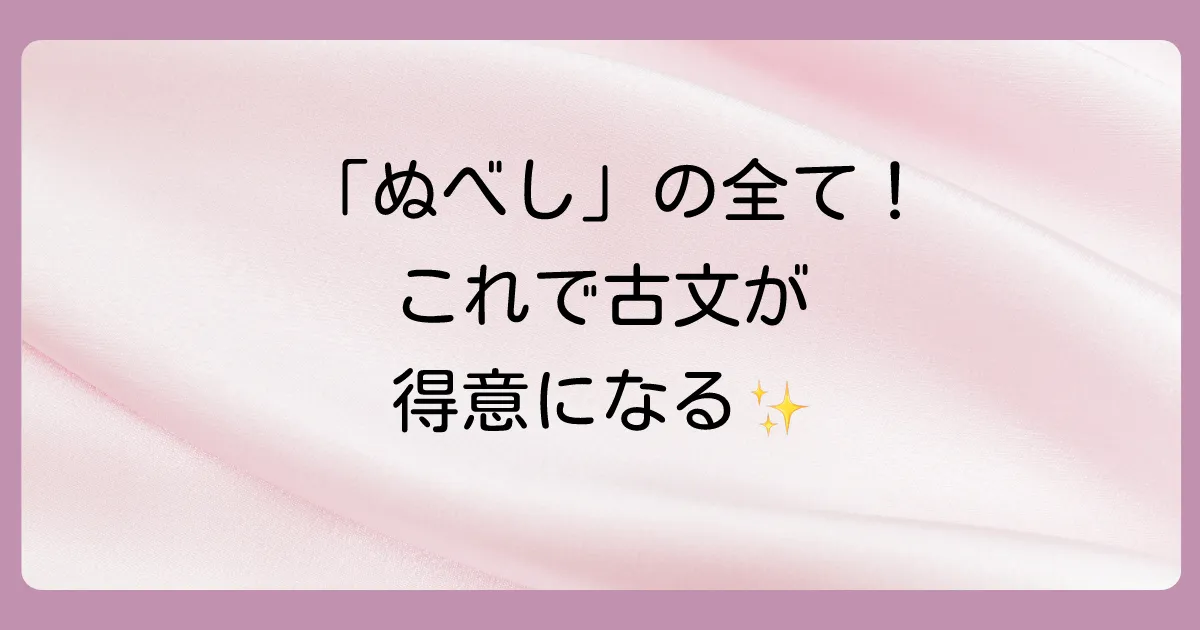
- 「ぬべし」は完了(強意)の助動詞「ぬ」と推量の助動詞「べし」の連語です。
- 品詞分解では「ぬ」と「べし」の二つの助動詞に分けます。
- 助動詞「ぬ」は連用形に接続し、意味は「完了」と「強意」です。
- 助動詞「べし」は終止形に接続し、意味は「すいかとめて」の6つです。
- 「ぬべし」の基本的な訳は「きっと~だろう」という強い推量です。
- 文脈により「強意+意志」や「強意+当然」などにも訳せます。
- 「ぬ」の識別は直前の語の活用形が鍵です(連用形接続なら完了)。
- 打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」(未然形接続)との違いに注意が必要です。
- ナ行変格活用動詞「死ぬ」「往ぬ」とも区別する必要があります。
- 助動詞「べし」の意味は主語の人称や文脈で判断します。
- 活用の暗記は声に出してリズムで覚えるのが効果的です。
- 品詞分解は古文を正確に読むための基礎体力です。
- 多くの文章に触れて、品詞分解の練習を繰り返すことが上達の近道です。
- 品詞分解ができれば、古文の読解力は飛躍的に向上します。
- 苦手意識を克服し、自信を持って古文読解に臨みましょう。
新着記事




