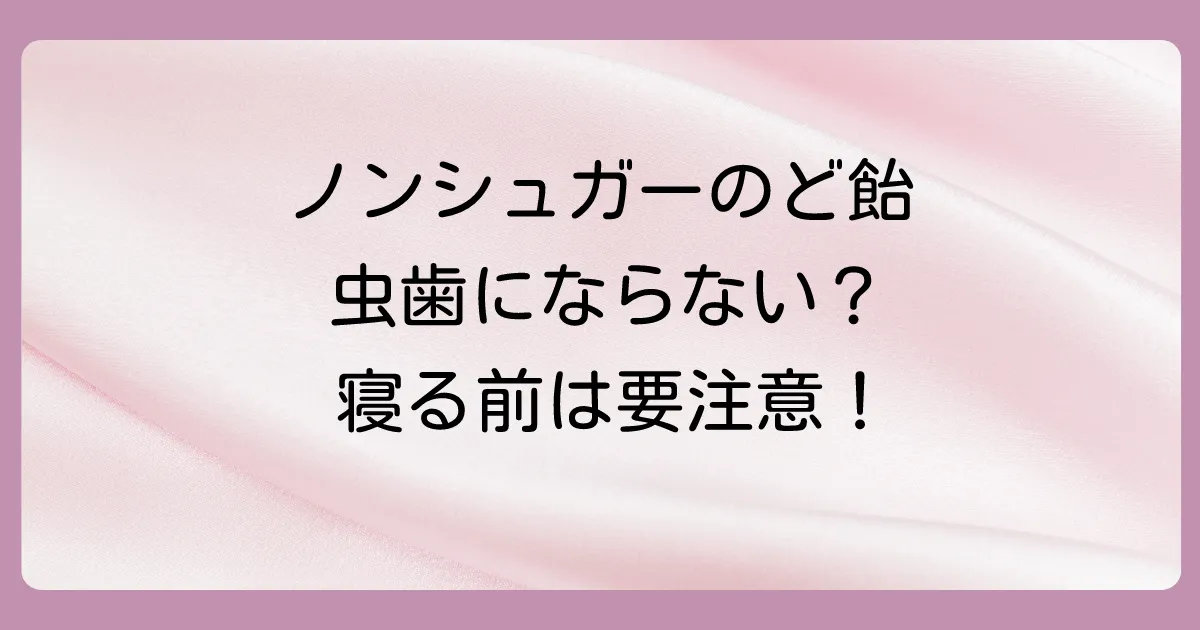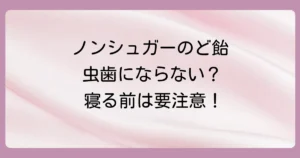のどの乾燥やイガイガを感じるとき、ついつい手が伸びてしまう「のど飴」。中でも「ノンシュガーなら虫歯にならない」と聞いて、積極的に選んでいる方も多いのではないでしょうか?でも、本当に虫歯の心配はないのでしょうか。寝る前に舐めても大丈夫?そんなあなたの素朴な疑問に、本記事が分かりやすくお答えします。ノンシュガーのど飴と虫歯の気になる関係をスッキリ解決しましょう。
【結論】ノンシュガーのど飴は虫歯になりにくい!でも100%安全とは限らない
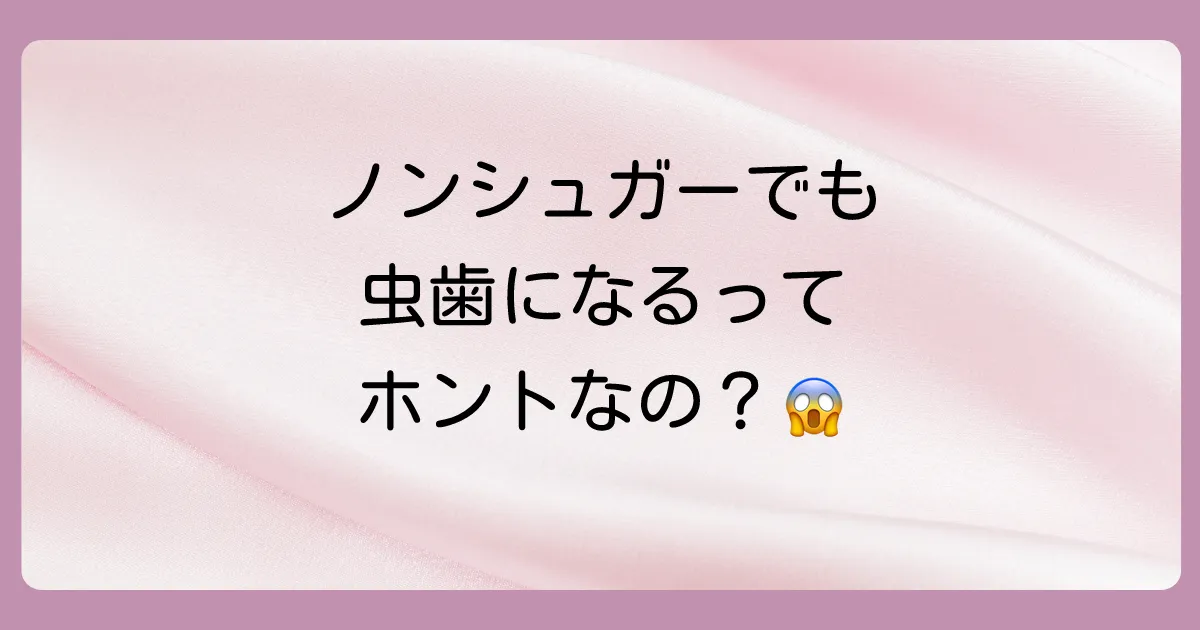
まず結論からお伝えすると、ノンシュガーのど飴は、砂糖を使った一般的な飴に比べて虫歯になるリスクは格段に低いです。これは紛れもない事実。しかし、「絶対に虫歯にならない」と断言できないのも、また事実なのです。一体どういうことなのでしょうか?
この章では、ノンシュガーのど飴がなぜ虫歯になりにくいのか、そして、それでも注意が必要な理由について解説します。
- なぜノンシュガーのど飴は虫歯になりにくいのか?その仕組みを解説
- 要注意!ノンシュガーのど飴でも虫歯リスクが高まるケース
- 虫歯を気にせず使える!ノンシュガーのど飴の選び方
「ノンシュガー」という言葉の本当の意味を理解し、安心してのど飴と付き合っていくための知識を身につけていきましょう。
なぜノンシュガーのど飴は虫歯になりにくいのか?その仕組みを解説
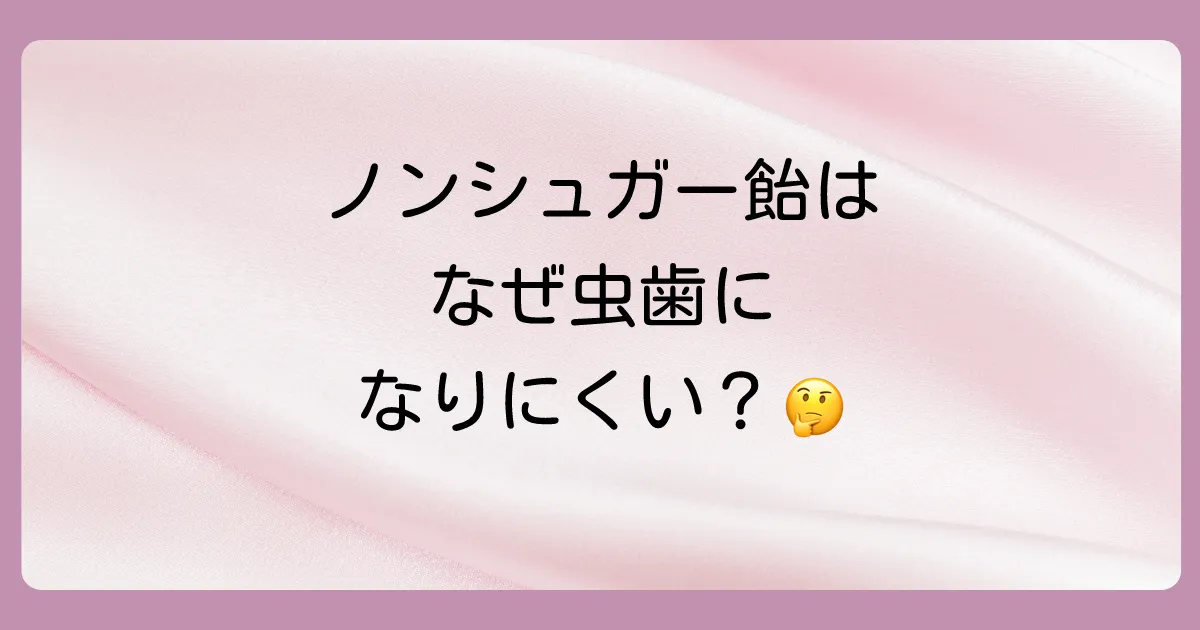
「ノンシュガー」と聞くと、単に「砂糖が入っていない」と思いがちですが、その甘さの秘密は「糖アルコール」という成分にあります。この糖アルコールこそが、ノンシュガーのど飴が虫歯になりにくい最大の理由です。ここでは、虫歯ができる基本的なメカニズムと、糖アルコールの働きについて詳しく見ていきましょう。
虫歯は、口の中にいるミュータンス菌などの虫歯菌が、食べ物に含まれる「糖」をエサにして酸を作り出すことから始まります。この酸が歯の表面のエナメル質を溶かしてしまうのです。しかし、ノンシュガーのど飴に使われる甘味料は、虫歯菌がうまく利用できないため、酸がほとんど作られません。だから、虫歯になりにくいというわけです。
虫歯菌が利用しにくい「糖アルコール」とは?
ノンシュガーのど飴の主成分として使われているのが、「糖アルコール」です。 商品の原材料表示を見ると、「還元水飴」「キシリトール」「ソルビトール」「マルチトール」「還元パラチノース」といった名前が見つかるはずです。これらが糖アルコールの仲間です。
糖アルコールは、名前に「糖」とついていますが、砂糖とは構造が少し異なります。そのため、虫歯菌がエサとして分解しにくく、歯を溶かすほどの強力な酸を産生することがほとんどありません。 これが、ノンシュガーのど飴が虫歯になりにくいと言われる最大の理由です。
さらに、糖アルコールは消化吸収されにくい性質を持つため、砂糖に比べてカロリーが低いという嬉しい特徴もあります。 ダイエット中の方や、血糖値が気になる方にも選びやすい甘味料と言えるでしょう。
キシリトールは虫歯予防効果も期待できる
糖アルコールの中でも、特に注目したいのが「キシリトール」です。キシリトールは、他の糖アルコールと同様に虫歯菌が酸を作りにくいだけでなく、虫歯菌(ミュータンス菌)そのものの活動を弱める働きがあることが研究で分かっています。
キシリトールを摂取すると、虫歯菌はそれを取り込もうとしますが、うまく代謝できずにエネルギーを消耗してしまいます。これを繰り返すことで、虫歯菌は徐々に弱っていくのです。さらに、キシリトールには、歯の再石灰化を促進する効果や、虫歯の原因となる歯垢(プラーク)を付きにくくする効果も報告されています。
多くの研究で、キシリトールの虫歯予防効果は科学的に証明されており、30~80%の確率で虫歯の発生を防ぐというデータもあります。 そのため、ノンシュガーのど飴を選ぶ際には、甘味料としてキシリトールが使われているかどうかを一つの基準にするのがおすすめです。
要注意!ノンシュガーのど飴でも虫歯リスクが高まるケース
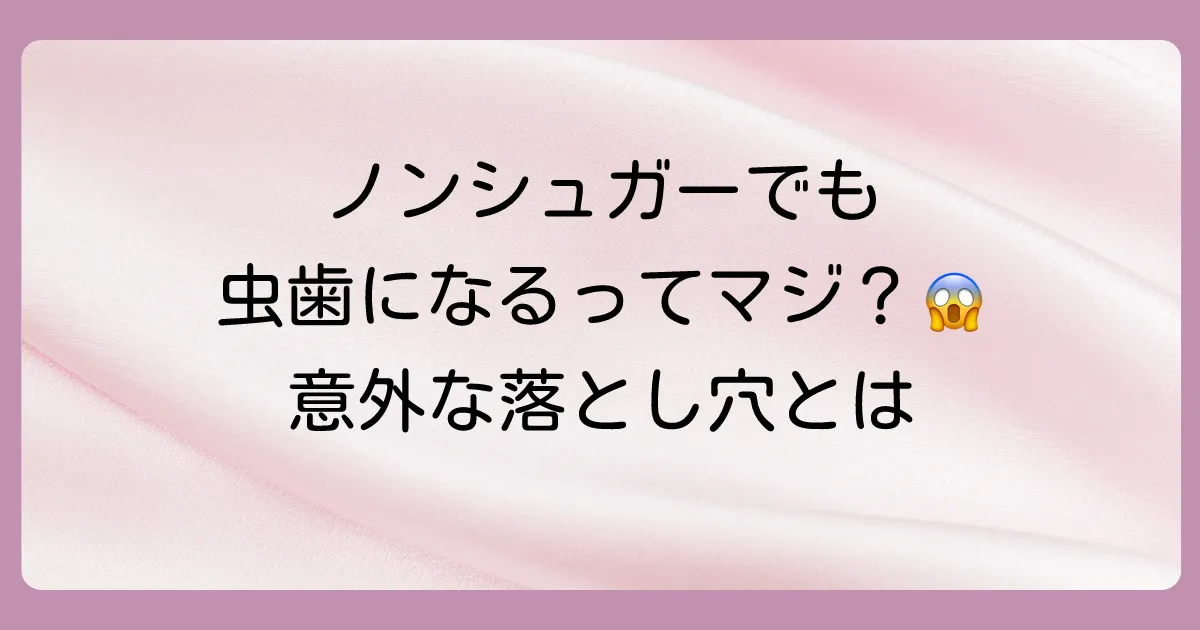
「ノンシュガーなら安心!」と油断してしまうのは少し早いかもしれません。実は、ノンシュガーのど飴でも、選び方や食べ方によっては歯にダメージを与えてしまう可能性があるのです。ここでは、特に注意したい3つのケースをご紹介します。これらのポイントを知っておくことで、より安全にのど飴を活用することができます。
甘味料自体は虫歯の原因になりにくくても、他の成分や食べるタイミングが口内環境に影響を与えることがあります。自分の習慣と照らし合わせながら、リスクがないかチェックしてみましょう。
酸性の成分(クエン酸など)が含まれている場合
ノンシュガーのど飴の多くは、フルーツ風味などの味付けのために「クエン酸」や「リンゴ酸」といった酸味料が添加されています。これらの「酸」そのものが、歯のエナメル質を溶かしてしまう「酸蝕症(さんしょくしょう)」というリスクになることをご存知でしょうか。
虫歯は「菌」が作り出す酸によって歯が溶ける病気ですが、酸蝕症は飲食物に含まれる「酸」によって直接歯が溶かされてしまう状態を指します。ノンシュガーのど飴を長時間口の中に入れておくと、この酸に歯が晒され続けることになり、歯の表面がもろくなってしまう可能性があるのです。
もちろん、すぐに歯が溶けてしまうわけではありませんが、習慣的に舐めている方は注意が必要です。商品を選ぶ際には、原材料表示を確認し、「酸味料」の記載がなるべく後ろの方にあるもの(含有量が少ないもの)を選ぶと良いでしょう。
寝る直前に舐めて歯磨きをしないのはNG
「歯磨きも済ませたし、あとは寝るだけ。のどが乾燥するからノンシュガーのど飴を舐めながら寝よう」…これは、実はとても危険な習慣です。
就寝中は、唾液の分泌量が大幅に減少します。唾液には、口の中の酸を洗い流したり、酸性に傾いた口内を中性に戻したりする「緩衝能」という大切な働きがあります。 しかし、唾液が少ない睡眠中は、この働きが弱まってしまうのです。
そんな無防備な状態でノンシュガーのど飴を口に含んでいると、たとえ虫歯菌が作る酸は少なくても、飴に含まれるわずかな糖類や酸味料の影響で、口の中が酸性の状態が長く続いてしまいます。 これでは、虫歯や酸蝕症のリスクを高めてしまうことになりかねません。寝る前にのど飴を舐めた場合は、必ずもう一度歯を磨くか、せめて水でしっかり口をゆすぐようにしましょう。
長時間ダラダラと舐め続ける
仕事中や勉強中に、口寂しさからノンシュガーのど飴を次から次へと舐めてしまうことはありませんか?この「ダラダラ食べ(舐め)」も、口内環境にとっては良くありません。
お口の中は、食事をするたびに酸性に傾き、唾液の力によって時間をかけて中性に戻ります。しかし、飴をずっと舐めていると、口の中が酸性に傾いている時間が長くなり、歯が溶けやすい状態が続いてしまうのです。 これは、砂糖入りの飴でもノンシュガーのど飴でも同じです。
のど飴はあくまでも一時的に喉を潤すためのもの。お菓子のようにダラダラと食べ続けるのは避け、必要な時に適量を舐めるように心がけましょう。1日の個数を決めておくのも良い方法です。
虫歯を気にせず使える!ノンシュガーのど飴の選び方
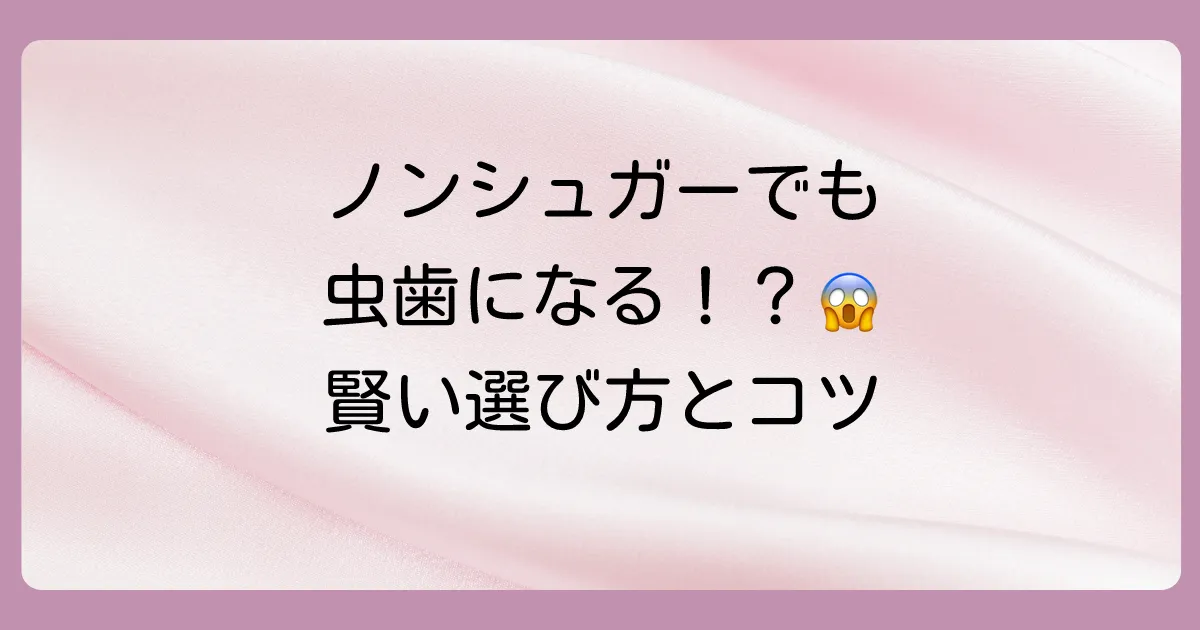
ここまで読んで、「じゃあ、どんなノンシュガーのど飴を選べばいいの?」と思った方も多いでしょう。虫歯のリスクをできるだけ抑え、安心して使えるノンシュガーのど飴を選ぶには、いくつかのポイントがあります。パッケージの表示をしっかりチェックして、自分の目的に合った賢い選択をしましょう。
この章では、具体的な選び方のコツを3つご紹介します。さらに、人気のメーカーの商品も比較しながら、あなたにぴったりの一品を見つけるお手伝いをします。
「シュガーレス」「糖類ゼロ」の表示を確認する
まず基本となるのが、パッケージの表示を確認することです。「ノンシュガー」や「シュガーレス」、「糖類ゼロ」といった表示がある商品を選びましょう。これらの表示は、食品100gあたりの糖類が0.5g未満である場合に許可されています。 糖類とは、砂糖やぶどう糖、果糖などの単糖類・二糖類のことで、これらが虫歯の直接的な原因となります。
この表示がある商品は、虫歯菌のエサとなる糖類がほとんど含まれていないため、虫歯リスクを大幅に低減できます。購入する際には、必ずこの表示があるかを確認する習慣をつけましょう。
甘味料に「キシリトール」が使われているものを選ぶ
前述の通り、糖アルコールの中でも「キシリトール」は虫歯予防効果が特に期待できる成分です。 虫歯菌の活動を弱らせる働きがあるため、より積極的に虫歯対策をしたい方にはキシリトール配合の製品がおすすめです。
商品を選ぶ際は、原材料表示をチェックし、甘味料として「キシリトール」が使われているか、そしてできれば原材料表示の最初の方に記載されているか(含有率が高いか)を確認しましょう。キシリトールガムなどでは「キシリトール含有率50%以上」が推奨されていますが、のど飴でも含有率が高いものを選ぶことで、より高い効果が期待できます。
人気のノンシュガーのど飴を比較
市場には様々なメーカーからノンシュガーのど飴が販売されています。ここでは、代表的な3社の人気商品を比較してみましょう。それぞれの特徴を知ることで、自分に合った商品が見つかるはずです。
| メーカー | 代表的な商品 | 主な甘味料 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| カンロ株式会社 | ノンシュガー果実のど飴 | 還元水飴 | ハーブエキス配合。様々なフルーツフレーバーが楽しめる。メントール不使用でスースーしないタイプもある。 |
| 株式会社龍角散 | 龍角散ののどすっきり飴(シュガーレス) | 還元水飴、還元麦芽糖水飴 | 独自のハーブパウダーを配合し、のどの専門メーカーならではのすっきり感が特徴。カシス&ブルーベリー味などもある。 |
| UHA味覚糖株式会社 | ノンシュガービタミンC&Dのど飴 | 還元水飴 | ビタミンCやビタミンDなどの栄養素を配合した機能性の高い商品が多い。ミント系やミルク系など多彩なラインナップ。 |
この他にも多くの商品がありますので、味の好みや求める機能性に合わせて、ぜひお気に入りを見つけてみてください。
よくある質問
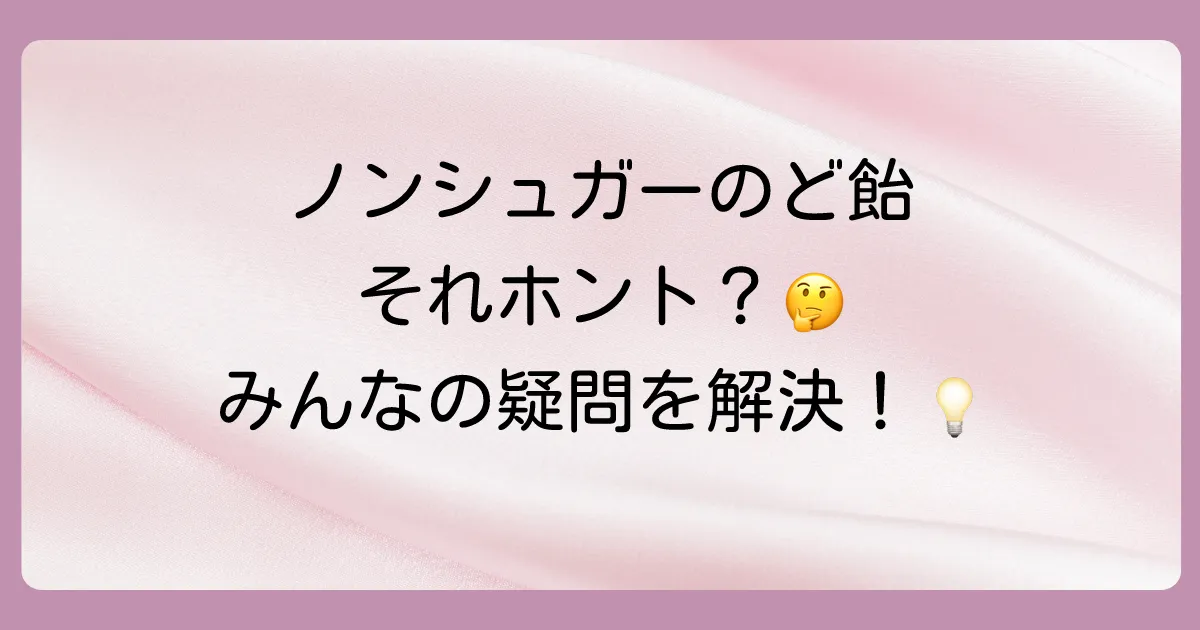
ノンシュガーのど飴は1日に何個まで食べていいですか?
ノンシュガーのど飴の1日の摂取量に明確な上限はありませんが、食べ過ぎには注意が必要です。主成分である糖アルコールは、一度に多量に摂取すると体質によってお腹がゆるくなることがあります。 これは、糖アルコールが小腸で消化・吸収されにくいためです。商品のパッケージに「一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります」といった注意書きがあるのはこのためです。まずは少量から試してみて、ご自身の体調に合わせて調整することをおすすめします。また、ダラダラと食べ続けることは虫歯や酸蝕症のリスクを高めるため、時間を決めて舐めるようにしましょう。
ノンシュガーのど飴を食べ過ぎると下痢になるって本当ですか?
はい、本当です。前述の通り、ノンシュガーのど飴の甘味料として使われるキシリトールやソルビトールなどの糖アルコールは、消化吸収されにくい性質を持っています。 そのため、一度にたくさん食べると、吸収されなかった糖アルコールが腸内に残り、腸内の水分量が増えることでお腹がゴロゴロしたり、下痢を引き起こしたりすることがあります。 これは一時的なもので、健康に害があるわけではありませんが、不快な症状を避けるためにも、適量を守ることが大切です。特に、お腹が敏感な方は少量ずつ試すようにしてください。
子供にノンシュガーのど飴を与えても大丈夫ですか?
固形の飴は、喉に詰まらせて窒息する危険性があるため、消費者庁などは5歳以下の子どもには与えないよう注意を呼びかけています。 これはノンシュガーのど飴も同様です。小さなお子さんには、誤って飲み込んでしまうリスクが非常に高いため、与えるべきではありません。市販されている子ども向けののど飴も、対象年齢が「5歳以上」などと定められていることが多いです。 どうしても喉のケアが必要な場合は、1歳頃から与えられる水飴タイプのものや、スプレータイプの製品などを検討し、必ず保護者の監督のもとで使用するようにしてください。
歯磨き後にノンシュガーのど飴を舐めてもいいですか?
歯磨き後にノンシュガーのど飴を舐めることは、基本的におすすめできません。 たとえノンシュガーであっても、製品によっては酸味料が含まれており、酸蝕症のリスクがあります。また、就寝中は唾液の分泌が減り、口の中が酸性に傾きやすくなるため、歯磨き後に何かを口にすることは避けるのが賢明です。もし歯磨き後に舐めてしまった場合は、再度軽く歯を磨くか、水で十分に口をすすぐようにしましょう。キシリトール100%のタブレットなど、歯科医院で推奨されているものであれば問題ない場合もありますが、一般的なのど飴は避けた方が無難です。
ノンシュガーとカロリーゼロは同じですか?
いいえ、ノンシュガーとカロリーゼロは異なります。「ノンシュガー(糖類ゼロ)」は、食品100gあたりの糖類が0.5g未満であることを示します。 一方、「カロリーゼロ(ノンカロリー)」は、食品100gあたりのエネルギーが5kcal未満の場合に表示できます。ノンシュガーのど飴に使われる還元水飴などの糖アルコールは、砂糖よりは低いもののカロリーはゼロではありません。 そのため、「ノンシュガー」であっても「カロリーゼロ」ではない商品がほとんどです。カロリーを厳密に制限している方は、栄養成分表示のエネルギー(カロリー)の項目もしっかり確認するようにしましょう。
まとめ
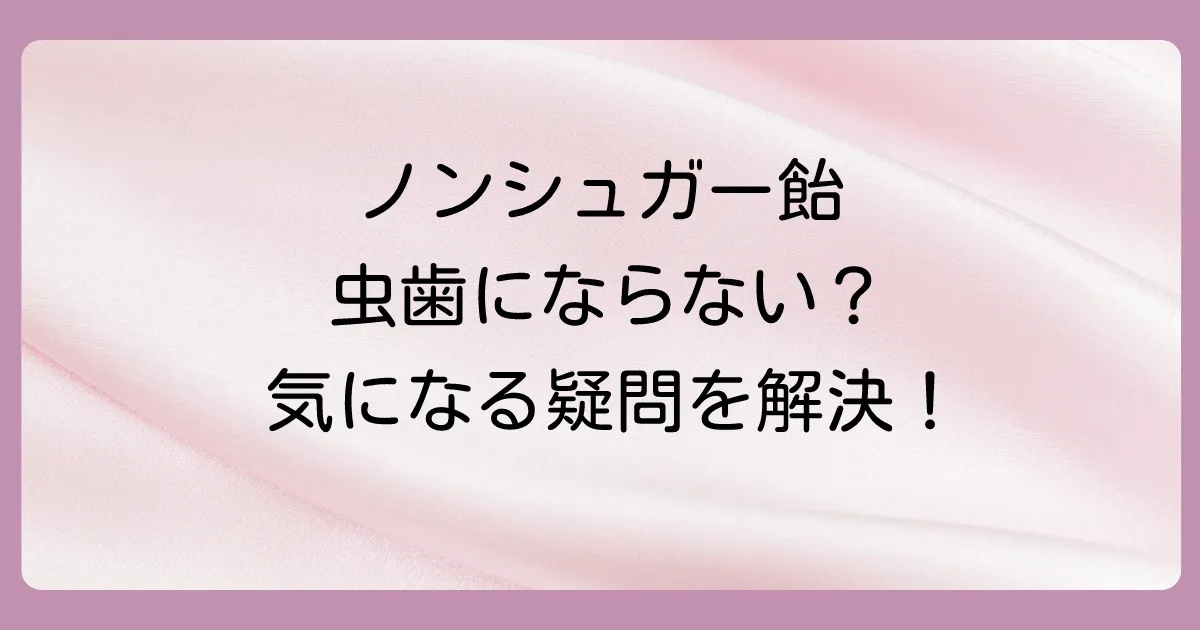
- ノンシュガーのど飴は虫歯菌のエサになりにくい。
- 主成分は酸を作りにくい「糖アルコール」。
- 砂糖の飴より虫歯リスクは格段に低い。
- しかし「絶対に虫歯にならない」わけではない。
- 酸味料による「酸蝕症」のリスクに注意。
- 長時間ダラダラ舐めるのは口内環境に悪い。
- 唾液が減る就寝前に舐めるのは避けるべき。
- 舐めた後は歯磨きか、水で口をゆすぐのが理想。
- 選び方の基本は「糖類ゼロ」表示の確認。
- 虫歯予防を意識するなら「キシリトール」配合がおすすめ。
- カンロや龍角散など各社から多様な商品が販売中。
- 食べ過ぎるとお腹がゆるくなることがある。
- 固形の飴は窒息リスクから幼児には与えない。
- 「ノンシュガー」と「カロリーゼロ」は意味が違う。
- 正しい知識で選び、安心して喉をケアしよう。
新着記事