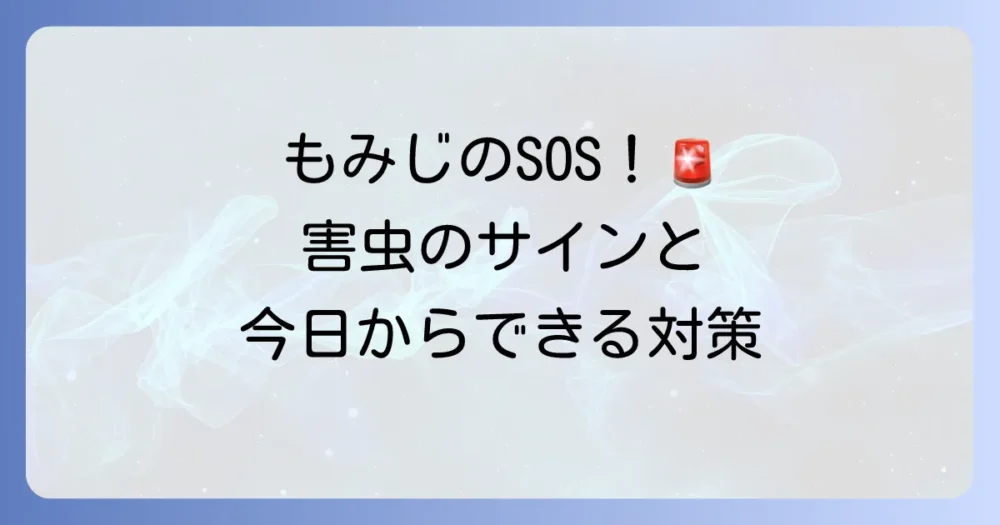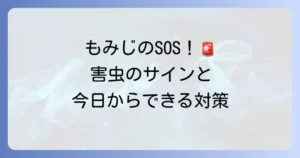大切に育てているもみじの葉が穴だらけになっていたり、白い粉のようなものが付着していたりすると、とても心配になりますよね。美しい紅葉を楽しみにしているのに、害虫のせいで台無しになってしまうのは避けたいものです。もみじは繊細なイメージがありますが、実はさまざまな害虫の被害に遭いやすい樹木の一つです。
本記事では、もみじに発生しやすい代表的な害虫の種類から、それぞれの特徴に合わせた駆除方法、そして何よりも大切な予防策まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたの大切なもみじを害虫から守るための具体的な方法がわかります。
【SOSサイン】もみじの害虫被害、こんな症状ありませんか?
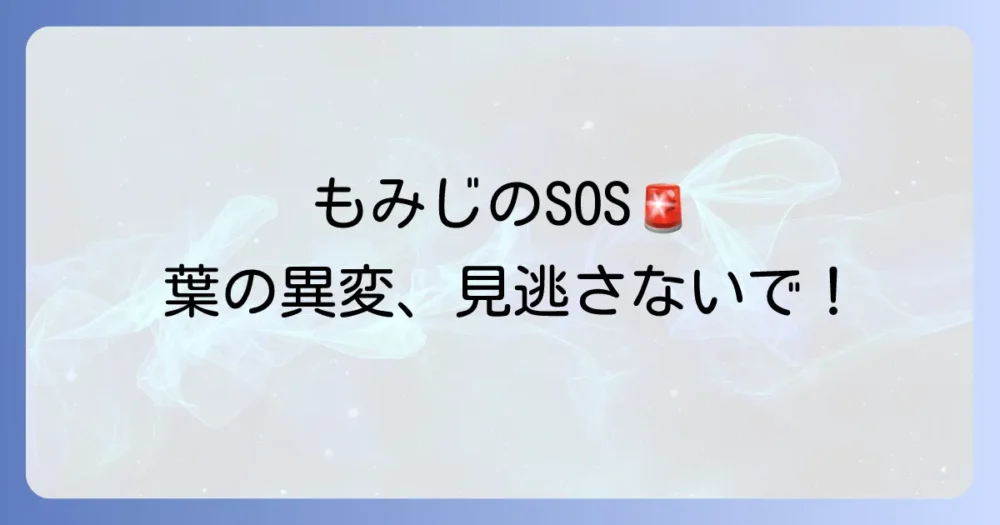
もみじが害虫の被害に遭っているとき、何らかのサインを出しています。早期発見が、被害を最小限に食い止めるための鍵となります。まずは、ご自宅のもみじに以下のような症状が出ていないかチェックしてみましょう。
- 葉に穴が開いている、ギザギザになっている
- 葉が変色している(黄色、白、茶色など)
- 葉の裏に小さな虫がたくさん付いている
- 葉や枝がベタベタしている
- 幹に穴が開いていたり、おがくずのようなものが出ていたりする
- 白い綿のようなものや、貝殻のようなものが付着している
- クモの巣のようなものが張っている
これらの症状は、害虫が発生している可能性が高いサインです。どの害虫が原因なのかを見極め、適切な対策を講じることが重要です。
【種類別】もみじの代表的な害虫と駆除・予防策
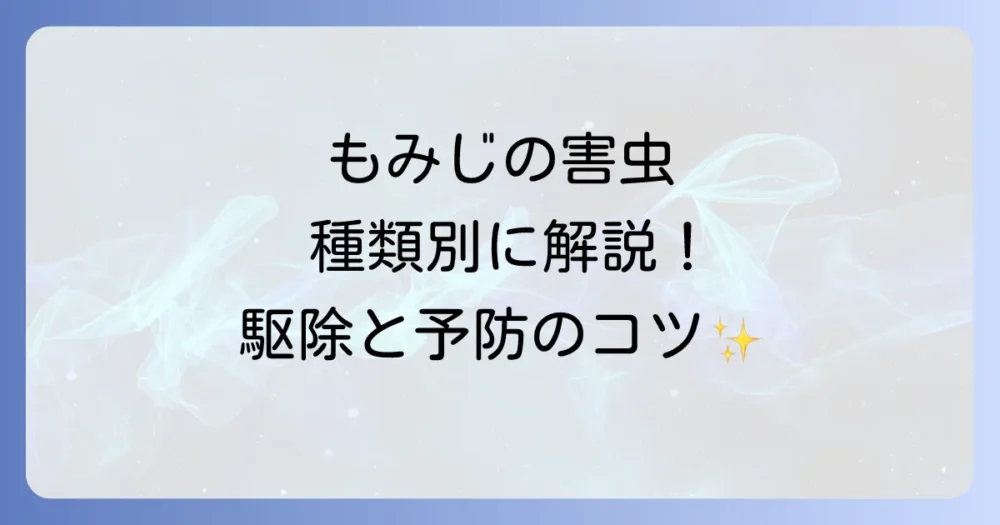
もみじに被害をもたらす害虫は数多く存在します。ここでは、特に発生しやすい代表的な害虫とその対策について詳しく見ていきましょう。
- アブラムシ|新芽や若葉にびっしり
- カイガラムシ|幹や枝に白い塊
- テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)|幹に穴を開ける最悪の敵
- イラガ(毛虫)|触ると危険!
- シャクトリムシ|葉を食い荒らす
- ハダニ|葉の養分を吸う小さなクモの仲間
アブラムシ|新芽や若葉にびっしり
アブラムシは、春先の新芽や若葉に集団で発生する、体長2~4mmほどの小さな虫です。 色は黒や緑など様々で、植物の汁を吸って生育を妨げます。繁殖力が非常に高く、あっという間に増えてしまうのが特徴です。
被害のサイン
アブラムシが発生すると、葉が縮れたり、成長が止まったりします。また、アブラムシの排泄物(甘露)によって葉や枝がベタベタになり、それを目当てにアリが集まってくることもあります。 この甘露は「すす病」という黒いカビが発生する原因にもなります。
駆除方法
発生初期であれば、ホースの水で勢いよく洗い流すだけでも効果があります。 しかし、数が多くなってしまった場合は、殺虫剤の使用がおすすめです。「オルトラン液剤」や「ベニカXファインスプレー」などがアブラムシに効果的です。 薬剤を使いたくない場合は、牛乳を水で薄めてスプレーする方法や、木酢液を散布する方法もあります。
予防策
アブラムシは光るものを嫌う性質があるため、木の根元にアルミホイルを敷いておくと、飛来を防ぐ効果が期待できます。 また、テントウムシはアブラムシの天敵なので、庭に放すのも有効な対策です。 風通しを良くすることも予防につながるため、適切な剪定を心がけましょう。
カイガラムシ|幹や枝に白い塊
カイガラムシは、その名の通り、硬い殻やロウ物質で体を覆っている害虫です。 幹や枝、葉に固着して吸汁し、もみじを弱らせます。大きさや色は種類によって様々で、白や茶色、紫褐色などが見られます。
被害のサイン
幹や枝に、貝殻のようなものや白い綿のような塊が付着していたら、カイガラムシの発生を疑いましょう。 被害が進むと、葉が黄色くなって落葉したり、枝が枯れたりします。 アブラムシ同様、排泄物が原因で「すす病」を引き起こすこともあります。
駆除方法
成虫は硬い殻に覆われているため、薬剤が効きにくいのが厄介な点です。 発生初期であれば、歯ブラシやヘラなどで物理的にこすり落とすのが最も確実な方法です。 幼虫が発生する5月~7月頃は薬剤が効きやすい時期なので、「スミチオン乳剤」などを散布すると効果的です。 冬の休眠期(12月~2月)に「マシン油乳剤」を散布すると、成虫を窒息させて駆除でき、翌春の発生を抑えることができます。
予防策
カイガラムシは風通しの悪い場所に発生しやすいです。 枝が混み合っている場所は剪定して、風通しと日当たりを良く保ちましょう。定期的に幹や枝を観察し、早期発見に努めることが重要です。
テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)|幹に穴を開ける最悪の敵
テッポウムシは、ゴマダラカミキリなどのカミキリムシの幼虫の通称です。 成虫がもみじの幹に卵を産み付け、孵化した幼虫が木の内部を食い荒らします。 被害に気づきにくく、気づいた時には手遅れになっていることも多い、非常に厄介な害虫です。
被害のサイン
幹の根元付近に、おがくずのような木くず(フラス)が落ちていたら要注意です。 これは、幼虫が内部を食い進みながら排出したものです。よく見ると、幹に小さな穴が開いているのが確認できます。 被害が進行すると、木の勢いがなくなり、最終的には枯れてしまいます。
駆除方法
木くずが出ている穴を見つけたら、針金を差し込んで幼虫を刺殺する方法があります。 しかし、内部で穴が曲がりくねっていると難しい場合も。その際は、専用の殺虫剤「園芸用キンチョールE」などが有効です。 この薬剤は、穴に直接ノズルを差し込んで噴射できるため、内部の幼虫を駆除できます。
予防策
カミキリムシの成虫を見つけたら、産卵される前に捕殺しましょう。 成虫は6月~8月頃に発生します。 木が弱っていると産卵されやすくなるため、日頃から適切な水やりや施肥を行い、もみじを健康に保つことが最大の予防策です。
イラガ(毛虫)|触ると危険!
イラガは、蛾の幼虫、いわゆる毛虫の一種です。葉の裏に集団で発生し、葉を食害します。 イラガの幼虫は毒針毛を持っており、触れると電気が走ったような激しい痛みに襲われるため、駆除作業には十分な注意が必要です。
被害のサイン
葉が、縁からレース状に食べられていたらイラガの仕業かもしれません。葉の裏をよく見ると、黄緑色の小さな毛虫が集団でいるのが見つかります。
駆除方法
絶対に素手で触らないでください。ゴム手袋や割り箸などを使い、葉ごと切り取って処分するのが安全です。数が多くて手に負えない場合は、「ベニカケムシエアゾール」などの殺虫剤を散布しましょう。
予防策
冬の間に、枝や幹に付いている繭(まゆ)を取り除いておくと、翌年の発生を減らすことができます。イラガの繭は、ウズラの卵のような形で固く、簡単に見つけられます。 また、剪定で風通しを良くしておくことも予防につながります。
シャクトリムシ|葉を食い荒らす
シャクトリムシも蛾の幼虫で、体を尺取り虫のように曲げながら移動するのが特徴です。 葉や新芽を食べてしまい、美観を損ねるだけでなく、生育にも影響を与えます。
被害のサイン
葉が不規則な形に食べられていたら、シャクトリムシがいる可能性があります。擬態が上手く、枝と見分けがつきにくいことがあるので注意深く観察しましょう。
駆除方法
見つけ次第、捕殺するのが最も手軽な方法です。数が多く発生した場合は、「GFオルトラン液剤」などの殺虫剤が効果的です。
予防策
成虫である蛾を寄せ付けないように、防虫ネットをかけるのも一つの方法です。また、鳥はシャクトリムシを捕食してくれるので、鳥が来やすい環境を作るのも良いでしょう。
ハダニ|葉の養分を吸う小さなクモの仲間
ハダニは、体長0.5mm程度の非常に小さな害虫で、クモの仲間に分類されます。葉の裏に寄生し、養分を吸います。高温で乾燥した環境を好み、特に梅雨明けから夏にかけて大量発生しやすいです。
被害のサイン
葉の表面に、針で刺したような白い小さな斑点が無数に現れます。これは「葉かすり」と呼ばれる症状です。被害が進むと葉全体が白っぽくなり、光合成ができなくなって枯れてしまいます。よく見ると、葉の裏にクモの巣のようなものが張られていることもあります。
駆除方法
ハダニは水に弱い性質があるため、定期的に葉の裏に勢いよく水をかける「葉水」が効果的です。発生してしまった場合は、ハダニ専用の殺ダニ剤を使用します。ハダニは薬剤への抵抗性がつきやすいため、同じ薬剤を連続して使用するのではなく、系統の異なる複数の薬剤をローテーションで使うと良いでしょう。
予防策
乾燥を防ぐために、こまめに葉水を行うことが最も効果的な予防策です。特に夏場の乾燥する時期は、朝夕の涼しい時間帯に葉の裏側までしっかりと水をかけてあげましょう。
【病気にも注意】害虫が引き起こすもみじの病気
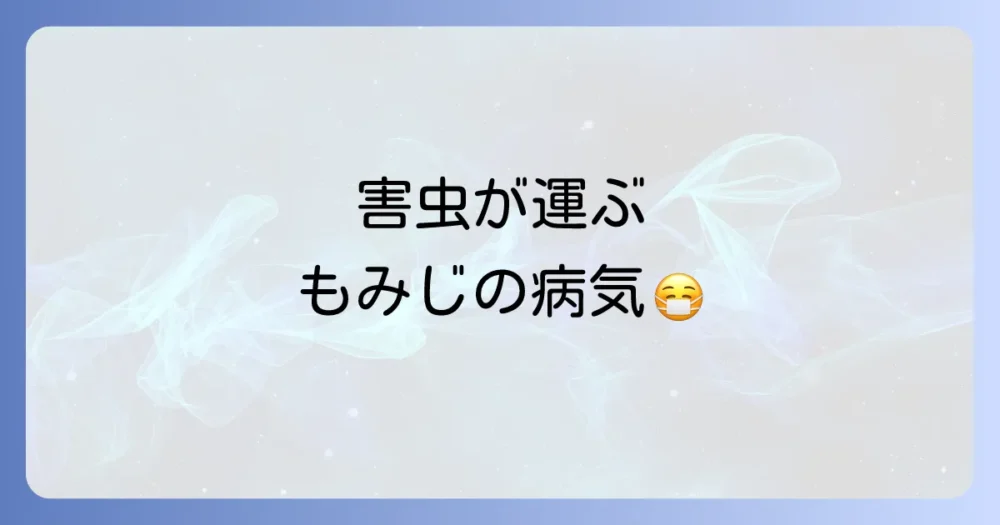
害虫は、もみじを直接食害するだけでなく、病気を引き起こす原因にもなります。ここでは、害虫が媒介する代表的な病気を2つ紹介します。
- うどんこ病
- すす病
うどんこ病
うどんこ病は、葉の表面にうどんの粉をまぶしたように、白いカビが生える病気です。 日当たりや風通しが悪いと発生しやすくなります。 この病気にかかると光合成が妨げられ、生育が悪くなるだけでなく、ひどい場合には葉が枯れてしまいます。
対策
アザミウマなどの害虫が、うどんこ病の菌を運ぶことがあります。 まずは害虫駆除を徹底しましょう。病気が発生してしまった場合は、症状が出ている葉を取り除き、「カリグリーン」や「ベニカXファインスプレー」などの殺菌剤を散布します。 予防としては、剪定で風通しを良くし、窒素肥料の与えすぎに注意することが大切です。
すす病
すす病は、葉や枝が黒いすすで覆われたようになる病気です。 これは、アブラムシやカイガラムシの排泄物(甘露)に黒いカビが繁殖することで発生します。 見た目が悪いだけでなく、光合成を妨げて生育を阻害します。
対策
すす病の原因となるアブラムシやカイガラムシを駆除することが最も重要です。 害虫を駆除すれば、すす病は自然と治まっていきます。黒くなった部分は、水で湿らせた布などで拭き取ることができます。
【予防が肝心】害虫を寄せ付けない!もみじの育て方
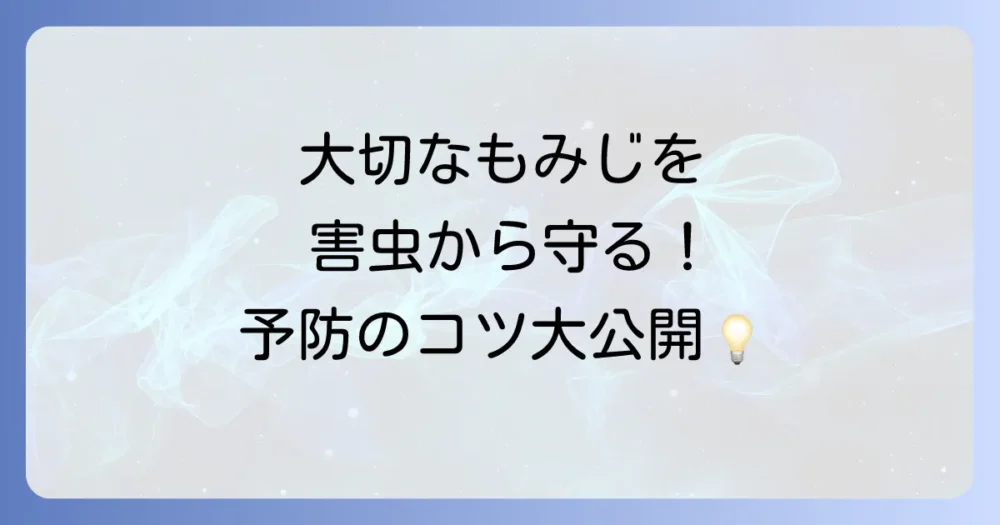
害虫が発生してから対処するのではなく、日頃から害虫を寄せ付けない環境を整えることが、もみじを健康に美しく保つための最も重要なポイントです。
- 剪定で風通しを良くする: 枝が混み合っていると湿気がこもり、病害虫の温床になります。 不要な枝や内側に向かって伸びる枝を切り、風と光が通り抜けるようにしましょう。
- 適切な水やりと施肥: 水切れや肥料の与えすぎは、木を弱らせる原因になります。 土の表面が乾いたらたっぷりと水を与え、肥料は規定量を守りましょう。健康な木は害虫の被害を受けにくくなります。
- 日々の観察を習慣に: 毎日少しでももみじの様子を見る習慣をつけましょう。葉の裏や幹などをチェックし、異変を早期に発見することが大切です。
- 天敵を味方につける: テントウムシやカマキリ、鳥などは害虫を食べてくれる益虫です。殺虫剤を使いすぎず、彼らが住みやすい環境を整えることも、長期的な害虫対策につながります。
【年間スケジュール】もみじの害虫対策カレンダー
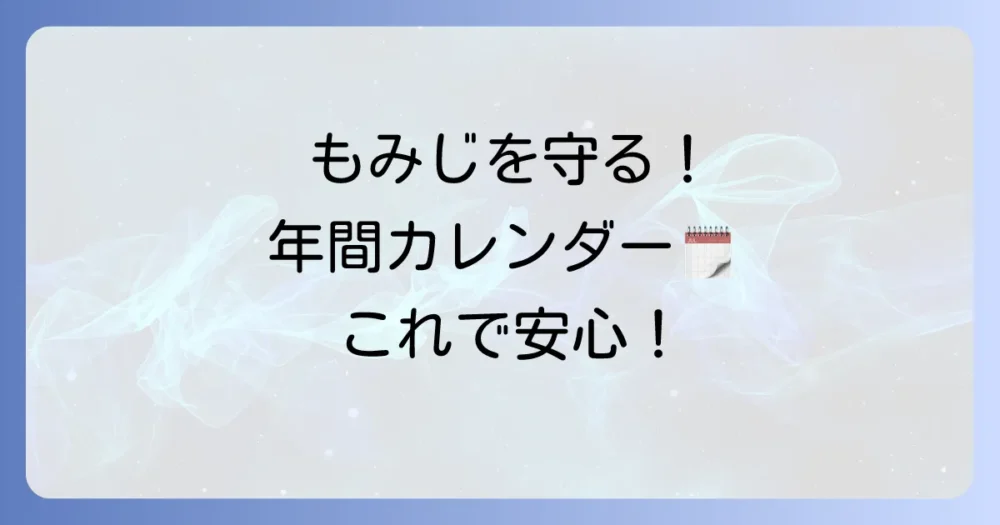
季節ごとに注意すべき害虫と対策を知っておくことで、より効果的な予防が可能です。
| 時期 | 注意すべき害虫・病気 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 冬(12月~2月) | カイガラムシ、イラガの繭 | マシン油乳剤の散布、繭の除去、剪定 |
| 春(3月~5月) | アブラムシ、うどんこ病 | 新芽の観察、薬剤散布(予防・駆除) |
| 夏(6月~8月) | テッポウムシ(カミキリムシ)、イラガ、ハダニ | 幹の観察(木くずチェック)、葉裏のチェック、葉水、薬剤散布 |
| 秋(9月~11月) | うどんこ病、カイガラムシ | 引き続き観察、枯れ葉の清掃 |
【自分でやる?業者に頼む?】害虫駆除の判断基準
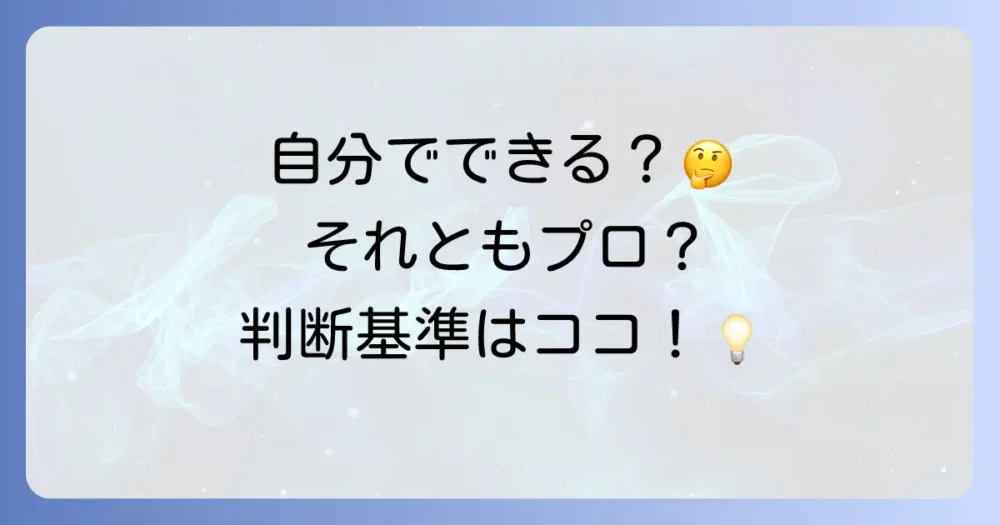
害虫駆除は自分で行うことも可能ですが、場合によっては専門の業者に依頼した方が良いケースもあります。
自分で対処できるケース
- 被害が限定的で、発生初期の場合
- 手の届く範囲での作業
- アブラムシやシャクトリムシなど、比較的駆除が容易な害虫
業者に依頼を検討するケース
- もみじが高木で、脚立を使っても作業が危険な場合
- 被害が広範囲に及んでいる、または何の害虫か特定できない場合
- テッポウムシなど、駆除が難しい害虫の場合
- イラガなど、毒を持つ危険な害虫が大量発生している場合
- 薬剤散布に不安がある、または時間がない場合
無理に自分で作業して、怪我をしたり、被害を拡大させてしまったりしては元も子もありません。状況に応じて、プロの力を借りることも検討しましょう。
よくある質問
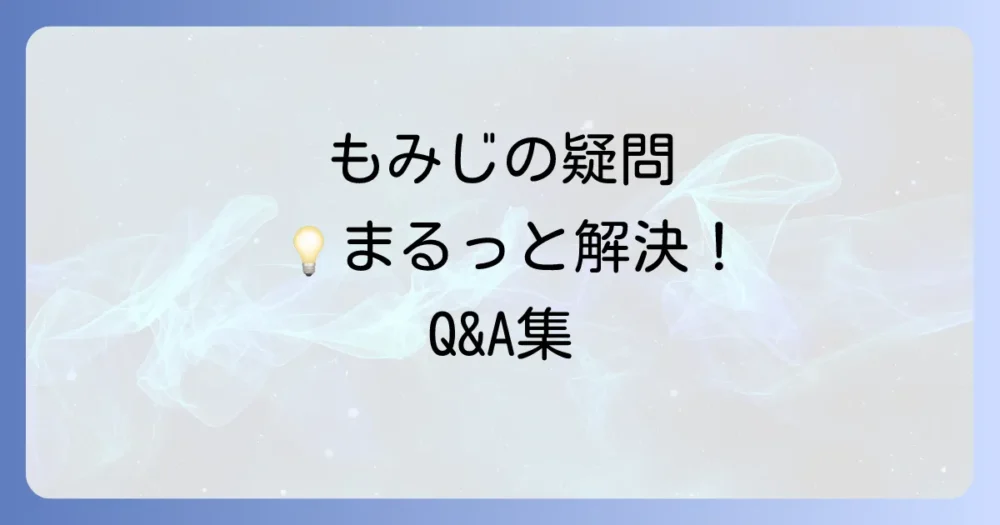
もみじに付きやすい虫は?
もみじには、アブラムシ、カイガラムシ、テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)、イラガ(毛虫)、シャクトリムシ、ハダニなどが付きやすいです。 特に春先のアブラムシと、幹に穴を開けるテッポウムシには注意が必要です。
もみじの葉が食べられる原因は?
もみじの葉が食べられる主な原因は、イラガやシャクトリムシといった蛾の幼虫による食害です。 葉の裏に集団でいる場合はイラガ、不規則に食べられている場合はシャクトリムシの可能性が高いでしょう。
もみじの消毒はいつすればいいですか?
害虫の種類によって効果的な時期は異なりますが、総合的な予防としては、害虫が活動を始める前の冬(12月~2月)にマシン油乳剤を散布するのがおすすめです。 また、アブラムシなどが発生しやすい春先(3月~4月)や、他の害虫の活動が活発になる夏前にも薬剤散布を行うとより効果的です。
もみじの葉が白くなる病気は何ですか?
もみじの葉が白い粉を吹いたようになる病気は「うどんこ病」の可能性が高いです。 これはカビの一種が原因で、日当たりや風通しが悪いと発生しやすくなります。
テッポウムシの駆除方法は?
テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)は、幹の穴から木くずが出ているのがサインです。 穴に針金を差し込んで刺殺するか、専用のノズルが付いた殺虫剤(園芸用キンチョールEなど)を穴に注入して駆除します。
カイガラムシの駆除方法は?
成虫は薬剤が効きにくいため、歯ブラシなどで物理的にこすり落とすのが効果的です。 幼虫が発生する5月~7月頃にスミチオン乳剤などを散布するか、冬の休眠期にマシン油乳剤を散布して駆除します。
アブラムシに効く薬は?
アブラムシには「オルトラン液剤」や「ベニカXファインスプレー」などの殺虫剤が効果的です。 根元に撒く粒剤タイプと、直接スプレーするタイプがあります。
木酢液はアブラムシに効きますか?
木酢液は、アブラムシに対する忌避効果(虫を寄せ付けにくくする効果)が期待できます。 殺虫効果は強くありませんが、予防として定期的に散布するのは有効な方法の一つです。
まとめ
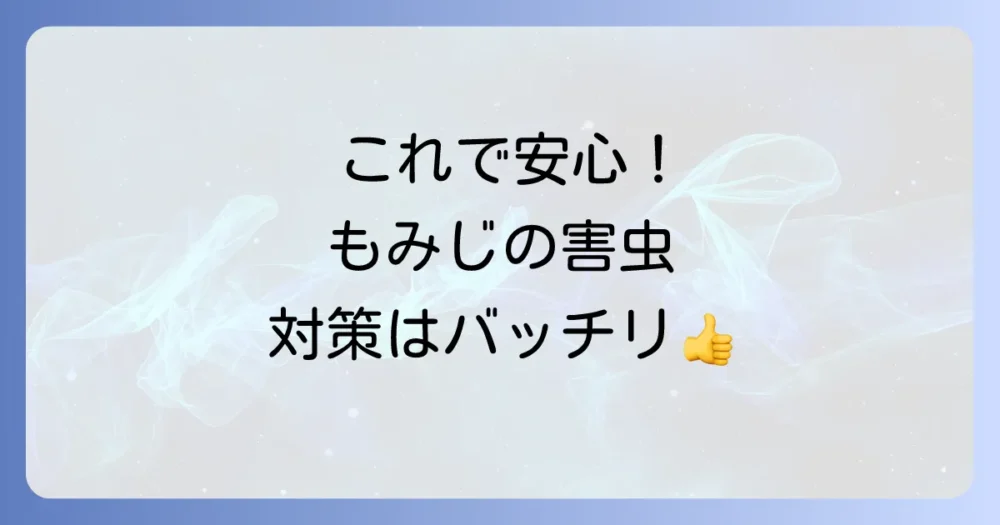
- もみじの害虫は早期発見・早期対策が重要です。
- 葉の穴や変色、ベタつきは害虫のサインです。
- 代表的な害虫はアブラムシ、カイガラムシ、テッポウムシです。
- アブラムシは新芽に付き、すす病の原因になります。
- カイガラムシは幹に固着し、薬剤が効きにくいです。
- テッポウムシは幹の内部を食害し、木を枯らすこともあります。
- イラガは毒針毛を持つため、駆除には注意が必要です。
- 害虫駆除は物理的除去と薬剤散布が基本です。
- 害虫が原因で「うどんこ病」や「すす病」になることがあります。
- 最大の予防策は、剪定で風通しを良くすることです。
- 適切な水やりと施肥で、木を健康に保ちましょう。
- 日々の観察で、害虫の発生をいち早く察知できます。
- 冬の薬剤散布(マシン油乳剤)は予防に効果的です。
- 高所作業や被害が甚大な場合は、専門業者への依頼も検討しましょう。
- 大切なもみじを守るために、年間を通した対策を心がけましょう。
新着記事