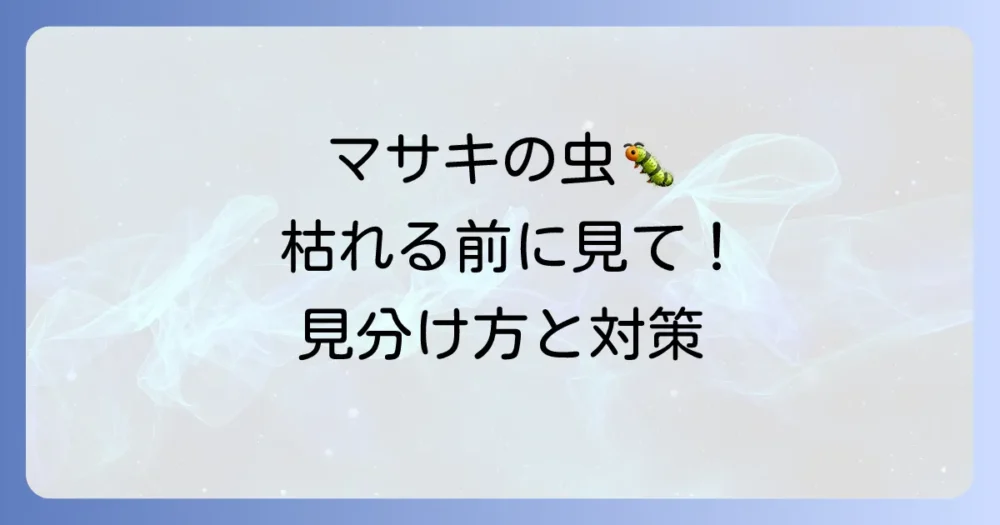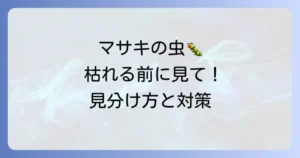大切に育てているマサキの葉に、いつの間にか虫がついていたり、葉が食べられていたりしてショックを受けた経験はありませんか?マサキは丈夫で育てやすい庭木ですが、実は害虫の被害に遭いやすい一面もあります。放置してしまうと、見た目が悪くなるだけでなく、最悪の場合枯れてしまうことも。本記事では、マサキに発生しやすい代表的な害虫の種類から、効果的な駆除方法、そして今日からできる予防策まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたの大切なマサキを害虫から守るための知識が身につきます。
マサキは害虫に注意!放置するリスクとは?

マサキは日本の気候にもよく合い、生垣などで人気の高い常緑樹です。しかし、そのみずみずしい葉は害虫にとってもご馳走。もし害虫を見つけても「少しだけだから大丈夫だろう」と油断していると、あっという間に被害が広がってしまう可能性があります。害虫を放置すると、見た目が損なわれるだけでなく、マサキの生育そのものに深刻な影響を与えかねません。
害虫による直接的な食害はもちろん、害虫の排泄物が原因ですす病などの病気を引き起こすこともあります。病気が広がると光合成が妨げられ、マサキはどんどん弱ってしまいます。最悪の場合、木全体が枯れてしまうことさえあるのです。そうなる前に、早期発見と適切な対策を講じることが、マサキを健康に保つための鍵となります。
この章では、まずマサキにどんな害虫が発生しやすいのか、その見分け方と対策について詳しく見ていきましょう。
- 【写真でチェック】マサキに発生しやすい代表的な害虫5選
- 害虫の種類別!効果的な駆除方法
- 害虫を寄せ付けない!今日からできる予防策
- 害虫が原因?マサキに起こる二次被害と病気
【写真でチェック】マサキに発生しやすい代表的な害虫5選
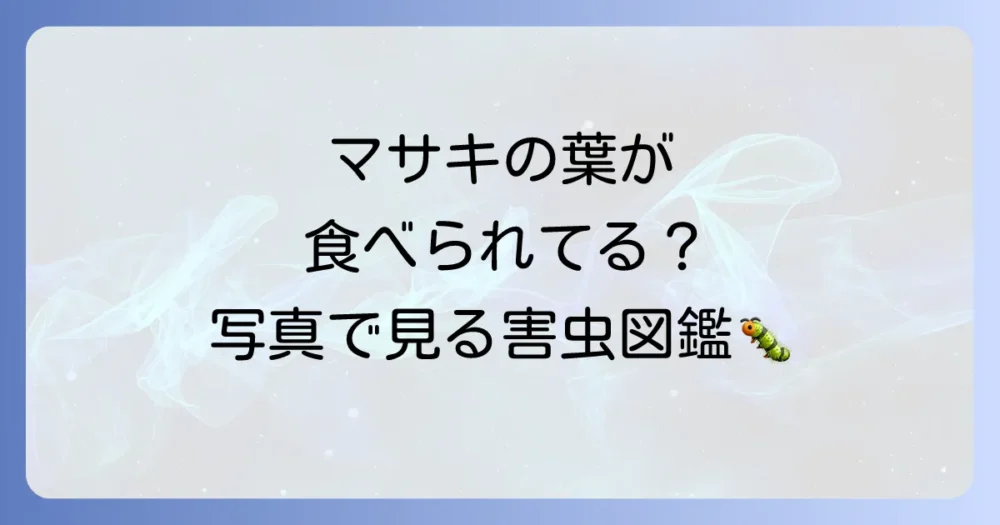
「マサキに虫がいるけど、なんていう名前の虫だろう?」と疑問に思ったことはありませんか。敵を知ることが、対策の第一歩です。ここでは、マサキに特に発生しやすい代表的な5種類の害虫について、その見た目の特徴、発生時期、そして被害の様子を解説します。ご自宅のマサキの状態と見比べながら、害虫の正体を突き止めましょう。
ミノウスバ
見た目の特徴と被害症状
ミノウスバはガの一種で、幼虫がマサキの葉を食害します。幼虫はクリーム色と黒色の縞模様が特徴的で、体長は最大で2cmほどになります。春先、新芽が出る頃に集団で発生することが多く、食欲が非常に旺盛。 放置すると、あっという間にマサキの葉を食べ尽くし、木を丸裸にされてしまうことも少なくありません。 葉の裏や枝にびっしりと群がっている姿は、見た目にも衝撃的です。また、肌に触れるとかぶれることがあるため、駆除の際は注意が必要です。
発生しやすい時期
ミノウスバの幼虫は、主に春(3月~5月頃)に発生します。 晩秋に成虫が枝先に卵を産み付け、卵の状態で冬を越します。 そして春、マサキの新芽が芽吹くタイミングで孵化し、活動を開始するのです。
効果的な駆除方法
発生初期であれば、木を揺らして落ちてきた幼虫を捕殺する方法もありますが、大量発生した場合は殺虫剤の使用が効果的です。 「スミチオン乳剤」や「オルトラン水和剤」などが有効とされています。 冬の間に枝先に産み付けられた白い卵塊を見つけたら、その枝ごと切り取って処分するのも有効な予防策です。
ユウマダラエダシャク
見た目の特徴と被害症状
ユウマダラエダシャクもガの幼虫で、いわゆる「シャクトリムシ」です。黒い体に黄色の斑点があるのが特徴で、集団で発生し、夜間に葉を猛烈な勢いで食害します。 昼間は株元に潜んでいることが多く、夜になると活動を始めます。被害が進むと、ミノウスバ同様に葉がほとんどなくなり、見るも無残な姿になってしまいます。
発生しやすい時期
年に2回、5月~6月と8月~9月頃に特に発生が多くなります。 幼虫の食害が目立つ時期です。冬は土の中で蛹の状態で越します。
効果的な駆除方法
幼虫を見つけ次第、割り箸などで捕殺するのが確実です。大量に発生してしまった場合は、ミノウスバと同様に「スミチオン乳剤」などの殺虫剤を散布するのが効果的です。 また、蛹の隠れ場所となる株元の落ち葉はこまめに掃除しておくことが、翌年の発生を抑える重要な予防策になります。
カイガラムシ類
見た目の特徴と被害症状
カイガラムシは、その名の通り貝殻のような硬い殻や、白い綿のようなものに覆われた害虫です。 枝や葉にびっしりと固着し、植物の汁を吸ってマサキを弱らせます。 マサキには特に「マサキナガカイガラムシ」や「ツノロウムシ」などが発生しやすいです。
被害が進むと、葉が黄色くなったり、生育が悪くなったりします。 さらに、カイガラムシの排泄物は「すす病」という病気の原因となり、葉や枝が黒いすすで覆われてしまいます。 このすす病は光合成を妨げるため、マサキの健康をさらに損なう原因となります。
発生しやすい時期
種類によって異なりますが、主に5月~7月頃に幼虫が発生し、活動が活発になります。 成虫は固着しているため、薬剤が効きにくいのが特徴です。
効果的な駆除方法
成虫は殻に覆われているため薬剤が効きにくいです。そのため、歯ブラシや竹べらなどで物理的にこすり落とすのが最も確実な方法です。 ただし、木を傷つけないように注意してください。幼虫が発生する6月~7月頃は、まだ殻が柔らかく移動するため、この時期に薬剤を散布するのが最も効果的です。 「オルトラン」やマシン油乳剤などが有効です。
アブラムシ類
見た目の特徴と被害症状
アブラムシは、体長2~4mm程度の小さな虫で、新芽や若い葉に群がって汁を吸います。繁殖力が非常に高く、あっという間に増殖します。汁を吸われると、新芽の成長が阻害されたり、葉が縮れたりします。
また、カイガラムシと同様に、アブラムシの甘い排泄物(甘露)はアリを誘い、「すす病」の原因にもなります。 葉がベタベタしていたら、アブラムシがいるサインかもしれません。
発生しやすい時期
春から秋にかけて、特に春(3月~5月)と秋(9月~10月)に多く発生します。
効果的な駆除方法
発生初期であれば、粘着テープで取り除いたり、牛乳や石鹸水をスプレーしたりする方法も有効です。数が増えてしまった場合は、専用の殺虫剤を散布しましょう。アブラムシは薬剤への抵抗性がつきやすいので、同じ薬剤を使い続けるのではなく、種類の違う薬剤をローテーションで使うとより効果的です。
ハマキムシ
見た目の特徴と被害症状
ハマキムシは、その名の通り、葉を糸で綴り合わせて巻いたり、折りたたんだりして、その中に隠れて葉を食べるガの幼虫です。 葉が不自然に巻かれていたり、くっついていたりしたら、ハマキムシの仕業を疑いましょう。中に潜んでいるため、外から見つけにくいのが厄介な点です。
食害された葉は、見た目が悪くなるだけでなく、光合成ができなくなり、マサキの生育に影響が出ます。
発生しやすい時期
春から秋にかけて、年に数回発生します。特に新芽が伸びる時期に被害が多く見られます。
効果的な駆除方法
巻かれた葉の中に幼虫がいるため、薬剤が直接かかりにくいです。そのため、巻かれた葉ごと摘み取って処分するのが最も確実な方法です。 被害が広範囲に及ぶ場合は、浸透移行性(薬剤が植物に吸収され、それを食べた害虫を駆除するタイプ)の殺虫剤、「オルトラン粒剤」などを株元に撒くのも有効です。
害虫の種類別!効果的な駆除方法
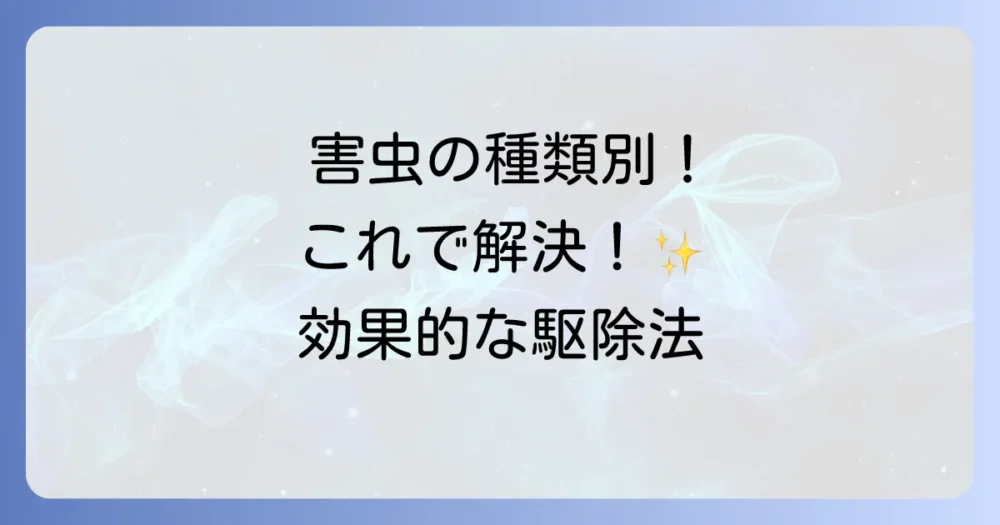
害虫の正体がわかったら、次はいよいよ駆除です。駆除方法には、手で取り除く物理的な方法から、薬剤を使う化学的な方法まで様々です。害虫の種類や発生状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。ここでは、具体的な駆除方法について、より詳しく解説していきます。
手で取り除く物理的駆除
害虫の数が少ない初期段階であれば、手で取り除く物理的な駆除が最も手軽で環境にも優しい方法です。
例えば、カイガラムシは成虫になると固着して動きません。古い歯ブラシや竹べらなどを使って、木の皮を傷つけないように優しくこすり落としましょう。 ポロポロと取れる感触は、少し快感かもしれません。
ミノウスバやユウマダラエダシャクなどの幼虫も、見つけ次第、割り箸でつまんで捕殺するのが効果的です。 特にミノウスバは集団でいることが多いので、一網打尽にできるチャンスもあります。ただし、ミノウスバの幼虫は触れるとかぶれることがあるので、必ず手袋を着用してください。
ハマキムシの場合は、中に幼虫が隠れている巻かれた葉ごと摘み取ってしまうのが一番です。これらの物理的駆除は、薬剤を使いたくない方や、被害が限定的な場合に特におすすめの方法です。
薬剤を使った化学的駆除
害虫が大量に発生してしまい、手作業では追いつかない場合は、薬剤を使った化学的駆除が必要になります。薬剤には様々な種類があるので、対象の害虫に効果のあるものを選びましょう。
おすすめの殺虫剤
マサキの害虫駆除によく使われる代表的な殺虫剤には以下のようなものがあります。
- スミチオン乳剤: 幅広い害虫に効果があり、特にミノウスバやユウマダラエダシャクなどの食害性害虫に有効です。 速効性があります。
- オルトラン粒剤・水和剤: 浸透移行性の殺虫剤で、根から吸収された成分が植物全体に行き渡り、葉を食べたり汁を吸ったりする害虫を駆除します。 効果が長持ちするのが特徴で、ハマキムシやカイガラムシにも有効です。
- マシン油乳剤: 冬の間に使用することで、カイガラムシなどの越冬している害虫や卵を油膜で覆って窒息死させます。
- ベニカXネクストスプレー: 殺虫成分と殺菌成分が両方入っているスプレータイプの薬剤です。 害虫と病気を同時に予防・治療したい場合に便利で、初心者でも手軽に使えます。
これらの薬剤は、ホームセンターや園芸店で入手できます。使用する際は、必ず製品のラベルをよく読み、記載されている使用方法、希釈倍率、使用回数を守ってください。
薬剤散布のコツと注意点
薬剤の効果を最大限に引き出し、安全に使用するためにはいくつかのコツがあります。
- 散布する時間帯: 早朝の風のない時間帯が最適です。日中の高温時に散布すると、薬害(薬剤によって植物が傷むこと)が出やすくなります。
- 散布する場所: 害虫は葉の裏に隠れていることが多いので、葉の裏までしっかりと薬剤がかかるように散布しましょう。
- 展着剤の活用: 展着剤(ダインなど)を薬剤に混ぜて使用すると、薬剤が葉に付きやすくなり、雨などで流れ落ちにくくなるため効果が高まります。
- 安全対策: 薬剤を吸い込んだり、皮膚に付着したりしないよう、マスク、ゴーグル、手袋を必ず着用しましょう。
害虫を寄せ付けない!今日からできる予防策
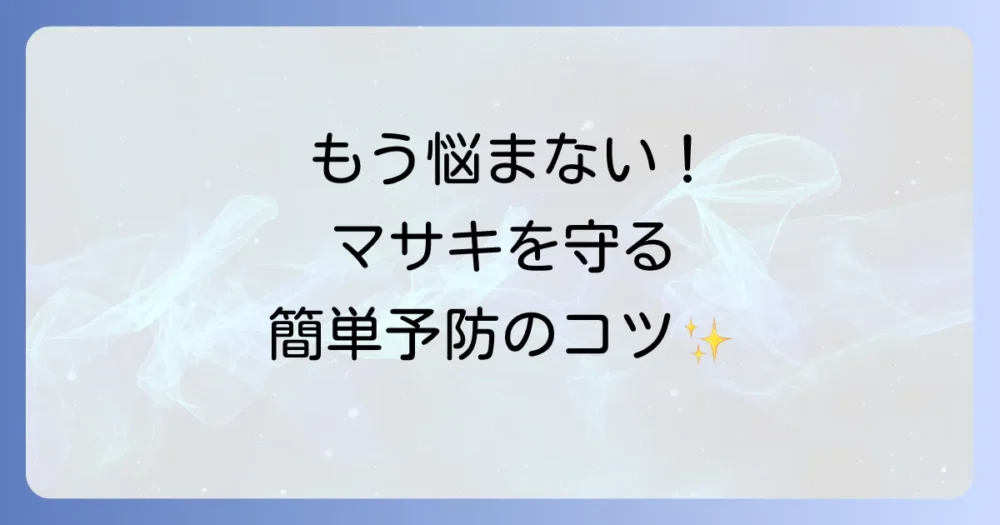
害虫が発生してから駆除するのは大変な作業です。最も理想的なのは、そもそも害虫を寄せ付けない環境を作ること。日頃のちょっとした手入れや工夫で、害虫の発生リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、誰でも今日から始められる効果的な予防策をご紹介します。
剪定で風通しを良くする
害虫予防の基本中の基本、それが剪定です。マサキは生育旺盛で、枝や葉が密集しやすい性質があります。 枝が混み合って風通しが悪くなると、湿気がこもり、害虫や病気にとって絶好の住処となってしまいます。
特に、カイガラムシやうどんこ病は、風通しの悪い環境で発生しやすくなります。 定期的に剪定を行い、内部まで日光が当たり、風が通り抜けるようにすることが非常に重要です。不要な枝や重なり合った枝を間引く「透かし剪定」を心がけましょう。
マサキの剪定に適した時期は、年に2回、新芽が落ち着いた6月頃と、秋の9月~10月頃です。 この時期に刈り込みを行うことで、密な生垣を維持しつつ、病害虫の予防にも繋がります。
日当たりを確保する
マサキは日陰にも比較的強い植物ですが、やはり健康に育てるためには日当たりの良い場所が理想です。 日光が十分に当たることで、植物自体が丈夫に育ち、病害虫に対する抵抗力も高まります。
逆に、完全な日陰では生育が悪くなり、ひょろひょろとした弱い株になってしまいます。 弱い株は、当然ながら害虫のターゲットになりやすくなります。もし鉢植えで育てている場合は、できるだけ日当たりの良い場所に移動させてあげましょう。地植えの場合は、周囲の植物を整理するなどして、少しでも日が当たるように工夫することが大切です。
落ち葉はこまめに掃除する
見落としがちですが、株元の落ち葉の掃除も重要な予防策の一つです。特に、ユウマダラエダシャクなどの害虫は、冬の間、土の中や落ち葉の下で蛹になって越冬します。
株元に落ち葉が積もったままだと、害虫にとって格好の隠れ家や越冬場所を提供してしまうことになります。こまめに落ち葉を拾い集めて処分することで、翌年の春に発生する害虫の数を減らすことができます。また、地面を清潔に保つことは、病原菌の発生を防ぐ上でも効果的です。
予防的に薬剤を散布する
毎年同じ害虫に悩まされている場合は、発生時期の少し前に予防的に薬剤を散布するのも有効な手段です。例えば、カイガラムシの幼虫が発生する5月~6月頃や、ミノウスバが孵化する春先など、害虫の活動が始まるタイミングを狙って薬剤を散布します。
また、冬の間にマシン油乳剤を散布しておくことで、越冬中のカイガラムシやその卵を駆除し、春の発生を抑えることができます。 害虫のライフサイクルを理解し、先手を打つことが、年間の防除を楽にするコツです。
害虫が原因?マサキに起こる二次被害と病気
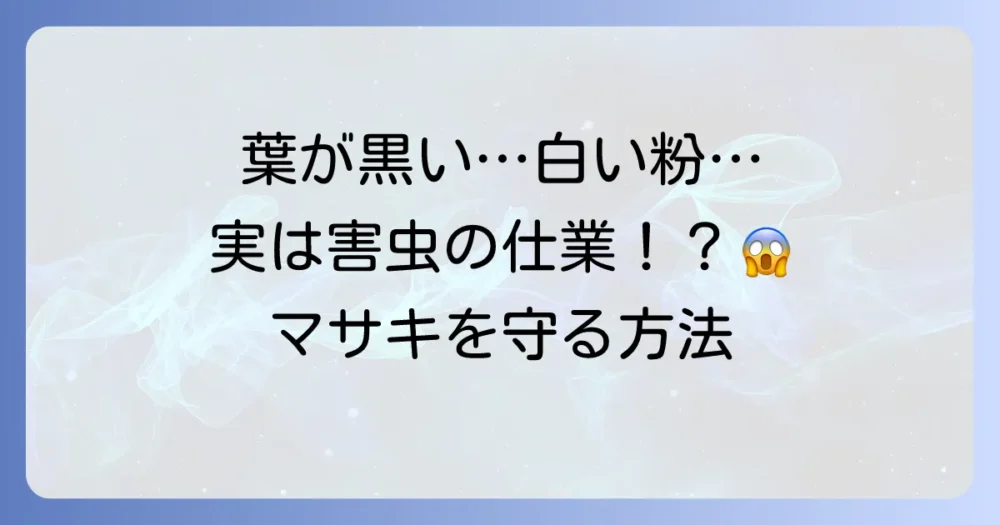
マサキの害虫被害は、葉を食べられるといった直接的なものだけではありません。害虫の存在が引き金となって、さらに厄介な病気を誘発することがあります。ここでは、害虫が原因で起こりやすい代表的な二次被害と病気について解説します。これらのサインに気づくことで、根本的な原因である害虫の存在を早期に発見できるかもしれません。
葉がベタベタ・黒くなる「すす病」
「マサキの葉がなんだかベタベタする」「葉や枝が黒いすすのようなもので覆われている」…そんな症状が見られたら、それはすす病かもしれません。
すす病は、カビの一種が原因で発生する病気ですが、このカビは植物自体から栄養を奪うわけではありません。カビが繁殖するのは、カイガラムシやアブラムシが出す甘い排泄物(甘露)の上なのです。 つまり、すす病が発生しているということは、その原因となるカイガラムシやアブラムシがマサキに寄生している証拠と言えます。
黒いすすは見た目が悪いだけでなく、葉の表面を覆って光合成を妨げるため、マサキの生育を阻害します。 すす病を根本的に解決するには、原因となっている害虫を駆除することが不可欠です。害虫を駆除すれば、すす病も自然と発生しなくなります。
白い粉が付く「うどんこ病」
葉の表面に、まるでうどんの粉をまぶしたように白いカビが生えるのが、うどんこ病です。 この病気もマサキでは非常によく見られます。 うどんこ病は、害虫の排泄物とは直接関係ありませんが、害虫が発生しやすい環境と共通点があります。
うどんこ病の菌は、日当たりや風通しが悪い、湿度の高い環境を好みます。 これは、カイガラムシなどの害虫が発生しやすい環境と全く同じです。そのため、害虫対策として剪定を行い、風通しを良くすることは、結果的にうどんこ病の予防にも繋がるのです。
うどんこ病にかかった葉は、光合成ができなくなり、やがて枯れてしまいます。 症状が軽い場合は、重曹を水で薄めたものをスプレーするなどの民間療法もありますが、広がってしまった場合は専用の殺菌剤(トップジンM水和剤、ベンレート水和剤など)で対処する必要があります。
よくある質問
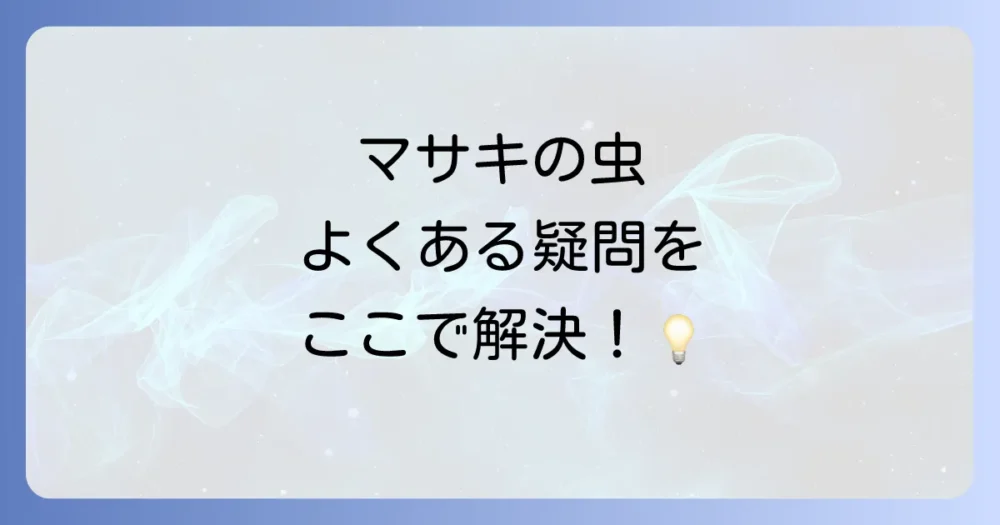
マサキに付く白い粒々は何ですか?
マサキの葉や枝に付いている白い粒々の正体は、多くの場合「マサキナガカイガラムシ」などのカイガラムシです。 この虫は植物の汁を吸って木を弱らせるだけでなく、すす病の原因にもなります。 見つけたら、歯ブラシなどでこすり落とすか、幼虫が発生する時期(6月~7月頃)に薬剤を散布して駆除しましょう。
害虫に強いマサキの品種はありますか?
基本的にどの品種のマサキでも害虫が付く可能性はありますが、一般的に原種に近い緑葉のマサキよりも、黄金マサキや銀マサキなどの斑入り品種の方が、やや害虫の被害を受けやすいと感じる方もいるようです。 しかし、最も重要なのは品種選びよりも、日当たりや風通しを良くするなど、植物が健康に育つ環境を整えてあげることです。 健康な株は病害虫への抵抗力も強くなります。
薬剤はいつ撒くのが効果的ですか?
薬剤を散布するのに最も効果的なタイミングは、害虫の種類によって異なります。食害性の幼虫(ミノウスバなど)に対しては、発生を見つけ次第、すぐに散布するのが効果的です。カイガラムシのように成虫が殻で覆われている害虫の場合は、殻を持たない幼虫が活動する時期(主に6月~7月)が薬剤散布のベストタイミングです。 また、予防として冬の間にマシン油乳剤を散布するのも非常に有効です。
ミノウスバに毒はありますか?
ミノウスバの幼虫には、ドクガのような強い毒はありません。 しかし、体毛に触れると人によってはかぶれたり、皮膚炎を起こしたりすることがあります。 駆除する際は、念のためゴム手袋などを着用し、直接肌に触れないように注意しましょう。
マサキの葉がベタベタするのはなぜですか?
マサキの葉がベタベタしている場合、その原因はアブラムシやカイガラムシの排泄物(甘露)である可能性が高いです。 これらの害虫は植物の汁を吸い、糖分を多く含んだ粘着性のある液体を排出します。この甘露は、アリを誘ったり、すす病の原因になったりします。葉のベタつきに気づいたら、アブラムシやカイガラムシがいないか、葉の裏や枝をよく観察してみてください。
まとめ
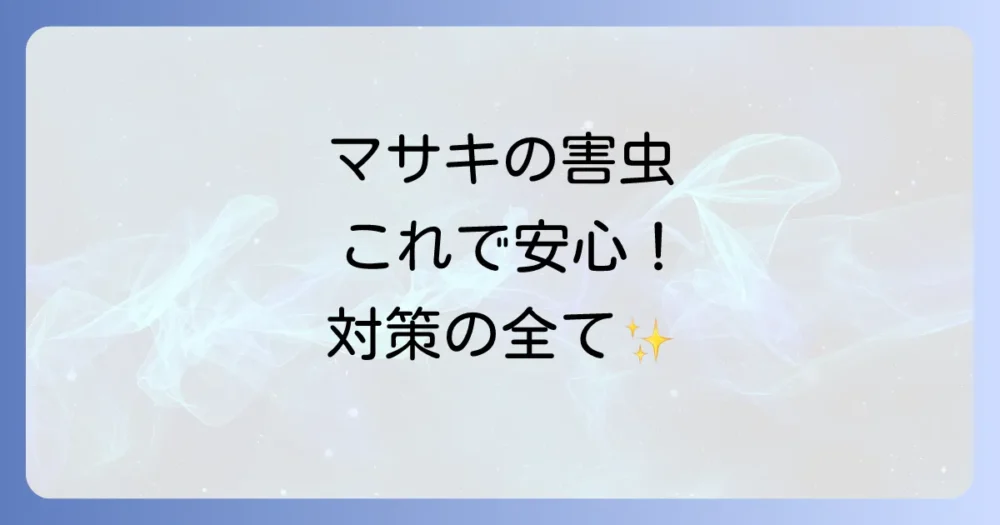
- マサキは丈夫だが害虫の被害に遭いやすい。
- 代表的な害虫はミノウスバ、ユウマダラエダシャク、カイガラムシなど。
- ミノウスバは春に発生し、葉を猛烈に食害する。
- ユウマダラエダシャクは黒いシャクトリムシで夜に活動する。
- カイガラムシは白い殻を被り、すす病の原因になる。
- アブラムシもすす病を引き起こし、新芽を弱らせる。
- ハマキムシは葉を巻いて中に隠れて食害する。
- 駆除は発生初期なら手作業、大量発生なら薬剤が有効。
- スミチオンやオルトランなどの薬剤が効果的。
- 予防の基本は剪定で風通しを良くすること。
- 剪定の適期は6月と9月~10月の年2回。
- 日当たりを確保し、株を健康に保つことが重要。
- 株元の落ち葉は害虫の越冬場所になるため掃除する。
- 害虫の排泄物は「すす病」の原因となる。
- 風通しの悪さは「うどんこ病」も誘発する。
- 害虫対策は病気の予防にも繋がる。
新着記事