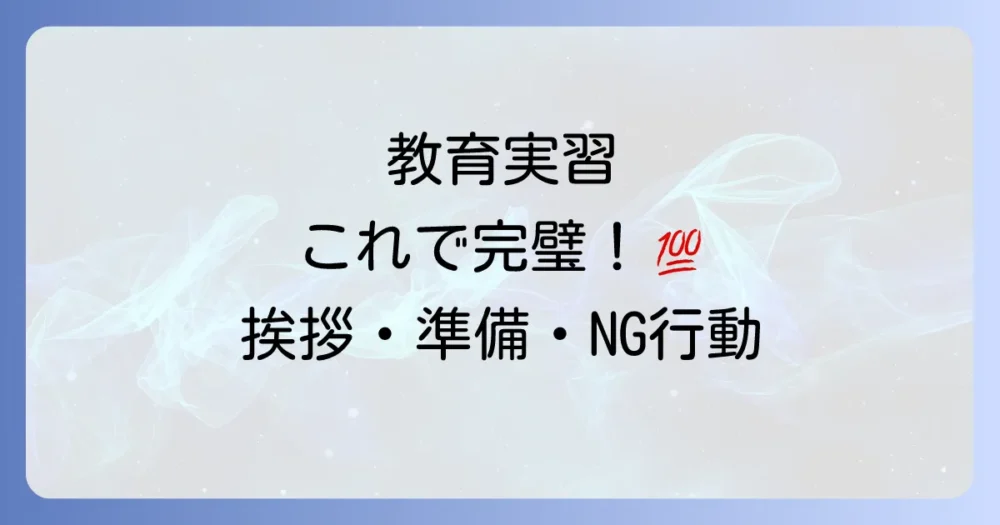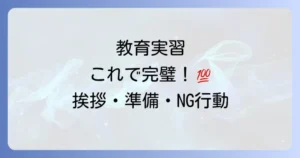「いよいよ教育実習が始まるけれど、何から準備すればいいんだろう…」「先生や生徒の前で、どんな挨拶をすれば良いか不安…」そんな悩みを抱えていませんか?教員になるための大きな一歩である教育実習。期待に胸を膨らませる一方で、未知の環境への不安や緊張を感じるのは当然のことです。本記事では、そんなあなたの不安を解消し、自信を持って実習に臨めるよう、具体的な心構えから、様々な場面で使える挨拶の例文までを徹底解説します。この記事を読めば、教育実習の準備は万全です!
【場面別】すぐに使える!教育実習の挨拶・自己紹介例文集
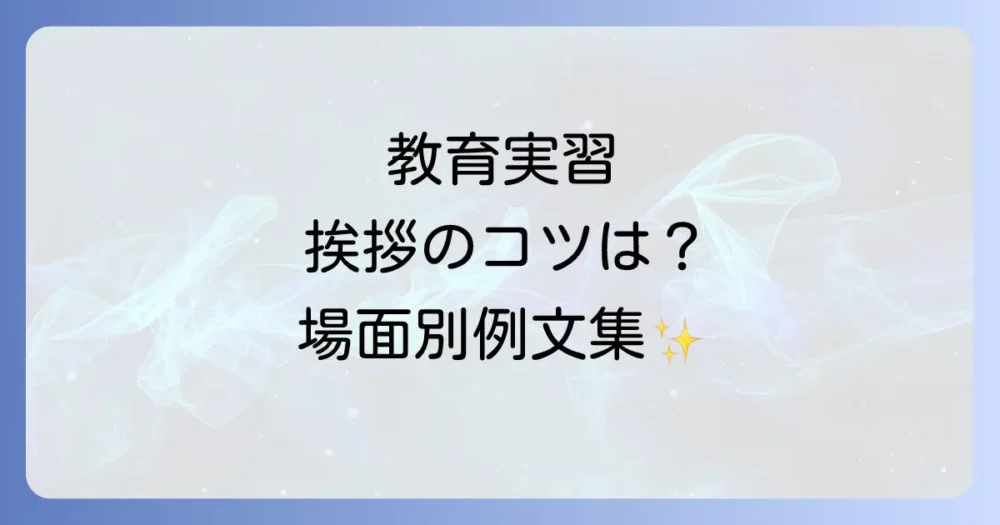
教育実習では、自己紹介や挨拶をする機会が数多くあります。 それぞれの場面に合わせた適切な挨拶は、先生方や生徒と良好な関係を築くための第一歩です。ここでは、様々なシチュエーションでそのまま使える、またはアレンジして使える例文を紹介します。
この章で紹介する内容は以下の通りです。
- 職員室での挨拶
- 生徒への最初の挨拶・自己紹介
- 研究授業での挨拶
- 実習最終日の挨拶
職員室での挨拶
実習初日、まず職員室で先生方に向けて挨拶をします。 先生方は忙しい朝の時間を割いてくれているため、簡潔かつ誠実に、ハキハキと話すことが重要です。 長々と話すのではなく、要点をまとめて30秒〜1分程度で終えるのが理想的です。
例文:
「おはようございます。本日より〇週間、教育実習をさせていただきます、〇〇大学〇〇学部の〇〇 〇〇と申します。担当教科は〇〇で、〇年〇組の〇〇先生のクラスでお世話になります。先生方の授業を見学させていただき、多くのことを学んでまいりたいと思っております。至らない点も多々あるかと存じますが、精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。」
ポイント:
- 所属と氏名、実習期間を明確に伝える。
- 担当教科とクラスを伝える。
- 学ぶ意欲と謙虚な姿勢を示す。
- 最後ははっきりと「よろしくお願いいたします」で締めくくる。
生徒への最初の挨拶・自己紹介
生徒たちとの最初の出会いは、その後の関係性を左右する大切な場面です。生徒たちは実習生に興味津々です。 先生としての威厳を保ちつつも、親しみやすさを感じてもらえるような自己紹介を心がけましょう。 ウケを狙いすぎると、逆になめられてしまう可能性もあるため注意が必要です。
例文:
「みなさん、おはようございます!今日から〇週間、皆さんと一緒に勉強することになりました、〇〇大学から来た〇〇 〇〇です。〇〇先生と呼んでください。担当教科は〇〇です。大学では〇〇部に所属していて、体を動かすことが大好きです。趣味は〇〇で、最近は〇〇にハマっています。皆さんの好きなことや、学校のことなど、たくさん教えてくれると嬉しいです。短い間ですが、一緒に楽しい時間にしましょう!どうぞよろしくお願いします!」
ポイント:
- 明るく、聞き取りやすい声で話す。
- 呼びやすいニックネームや名前を伝える。
- 趣味や特技など、自分の人柄が伝わるパーソナルな情報を少し加える。
- 生徒に興味があることを伝え、コミュニケーションを促す言葉を入れる。
研究授業での挨拶
研究授業は、実習の集大成とも言える重要な場面です。授業の冒頭で、参観してくださる先生方への感謝と、授業への意気込みを簡潔に伝えます。
例文:
「本日はお忙しい中、私の研究授業にご参観いただき、誠にありがとうございます。〇〇大学から参りました、教育実習生の〇〇 〇〇です。本日は、〇年生の〇〇という単元で、『〇〇』をねらいとした授業を行います。未熟な点も多いかと存じますが、生徒たちと一緒に精一杯頑張りますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。それでは、授業を始めます。」
ポイント:
- 参観への感謝を述べる。
- 授業の単元とねらいを簡潔に説明する。
- 謙虚な姿勢と意欲を示す。
実習最終日の挨拶
最終日には、お世話になった先生方と生徒たちへ感謝の気持ちを伝えます。 これまでの実習で学んだことや、心に残ったエピソードを交えながら、誠意を込めて挨拶しましょう。
先生方への挨拶(職員室):
「先生方、〇週間にわたる教育実習、本当にありがとうございました。初めは不安でいっぱいでしたが、先生方の温かいご指導と励ましのおかげで、無事に実習を終えることができました。特に、〇〇先生には授業づくりから生徒との関わり方まで、多くのことを学ばせていただきました。この貴重な経験を糧に、教員になるという夢に向かって、これからも精進してまいります。本当にお世話になりました。」
生徒への挨拶(クラス):
「みんな、〇週間本当にありがとう!みんなと毎日会えなくなるのは寂しいけど、このクラスで実習ができて本当に楽しかったです。授業で一生懸命発表してくれたこと、休み時間に色々な話をしてくれたこと、全部が良い思い出です。特に、〇〇の時間は、みんなの笑顔がとても印象に残っています。先生は、みんなからたくさんの元気と学びをもらいました。これからも、夢に向かって頑張ってください。ずっと応援しています!」
ポイント:
- 具体的なエピソードを交えて感謝の気持ちを伝える。
- 実習を通して得た学びや、今後の抱負を述べる。
- 生徒へのメッセージは、前向きで心に残る言葉を選ぶ。
これだけは押さえたい!教育実習に臨む3つの心構え
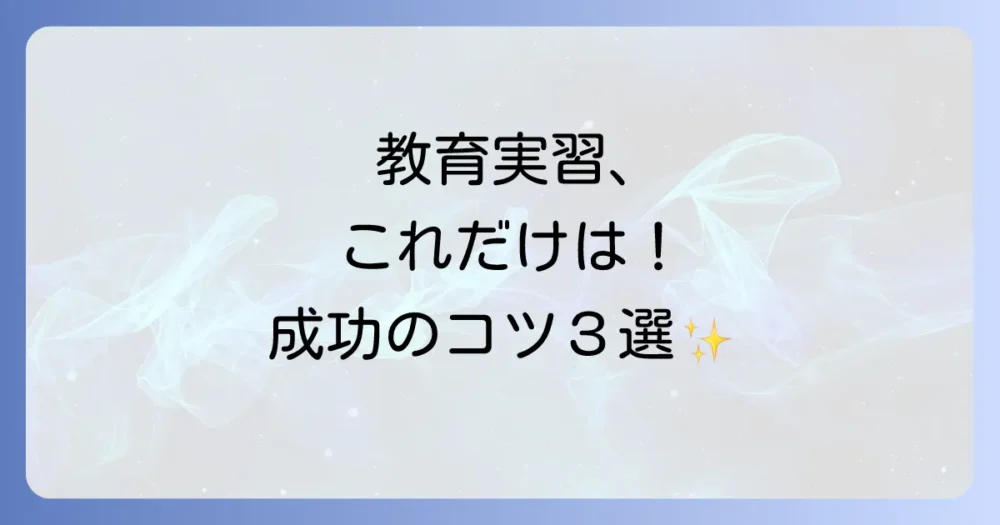
教育実習を成功させるためには、技術や知識だけでなく、しっかりとした心構えを持つことが不可欠です。 現場の先生方は、実習生の授業スキル以上に、その姿勢や人間性を見ています。ここでは、実習期間を通して持ち続けるべき、最も重要な3つの心構えについて解説します。
この章で解説する心構えは以下の通りです。
- 「教えてもらう」という謙虚な姿勢
- 常に「学ぶ」という探求心
- 子どもたちと真摯に向き合う誠実さ
「教えてもらう」という謙虚な姿勢
教育実習は、大学での学びを実践の場で検証し、深めるための機会です。しかし、忘れてはならないのが、自分は「実習生」であり、「学ぶ立場」であるという事実です。 実習校の先生方は、日々の多忙な業務の合間を縫って、あなたの指導にあたってくれています。 そのことへの感謝の気持ちを常に忘れないようにしましょう。
指導教官からのアドバイスや、時には厳しい指摘もあるかもしれません。それら全てを「自分の成長のための貴重な意見」として素直に受け止める謙虚さが求められます。たとえ自分の考えと違う指導を受けたとしても、まずは一度受け入れ、実践してみる姿勢が大切です。その上で、疑問点があれば「教えていただく」というスタンスで質問しましょう。「でも」「だって」という否定的な言葉から入るのは禁物です。
また、挨拶や時間厳守、礼儀正しい言葉遣いといった社会人としての基本的なマナーを徹底することも、謙虚な姿勢の表れです。 先生方だけでなく、事務職員の方や用務員の方など、学校に関わる全ての人への敬意を忘れないようにしましょう。
常に「学ぶ」という探求心
教育実習は、受け身の姿勢でいては得られるものが少なくなってしまいます。「何か一つでも多く吸収して帰るぞ」という強い探求心を持って、積極的に行動することが重要です。
具体的には、以下のような行動が挙げられます。
- 指導教官以外の先生の授業も積極的に見学させてもらう。
- 授業で分からなかったこと、疑問に思ったことは、必ずメモを取り、後で質問する。
- 朝の会や帰りの会、給食指導、清掃活動など、授業以外の場面からも教員の仕事を学ぼうとする。
- 生徒の様子をよく観察し、一人ひとりの個性やクラス全体の雰囲気を把握しようと努める。
「実習生だから」と遠慮せず、主体的に学ぶ姿勢を見せることで、先生方も「この実習生は意欲があるな」と感じ、より多くのことを教えてくれるはずです。もちろん、先生方の迷惑にならないよう、タイミングや状況をわきまえる配慮は必要です。
子どもたちと真摯に向き合う誠実さ
教育実習の主役は、言うまでもなく子どもたちです。実習生にとって、子どもたちは「評価の対象」ではなく、一人の人間として真摯に向き合うべき存在です。子どもたちは、大人が自分たちに本気で向き合ってくれているかどうかを敏感に感じ取ります。
休み時間や放課後など、授業以外の時間も積極的に子どもたちと関わり、コミュニケーションを図りましょう。 一人ひとりの名前を早く覚え、興味や関心があることを知ろうと努力する姿勢が、信頼関係の第一歩となります。時には、生徒指導の難しい場面に直面することもあるかもしれません。そんな時も、決して感情的にならず、一人の人間として誠実に対応することが求められます。
「先生」として見られる自覚を持ちつつも、子どもたちと同じ目線に立って物事を考え、共感しようとする姿勢が、子どもたちの心を開き、実りある実習へと繋がっていくでしょう。
差がつく!教育実習を成功させるための具体的な準備
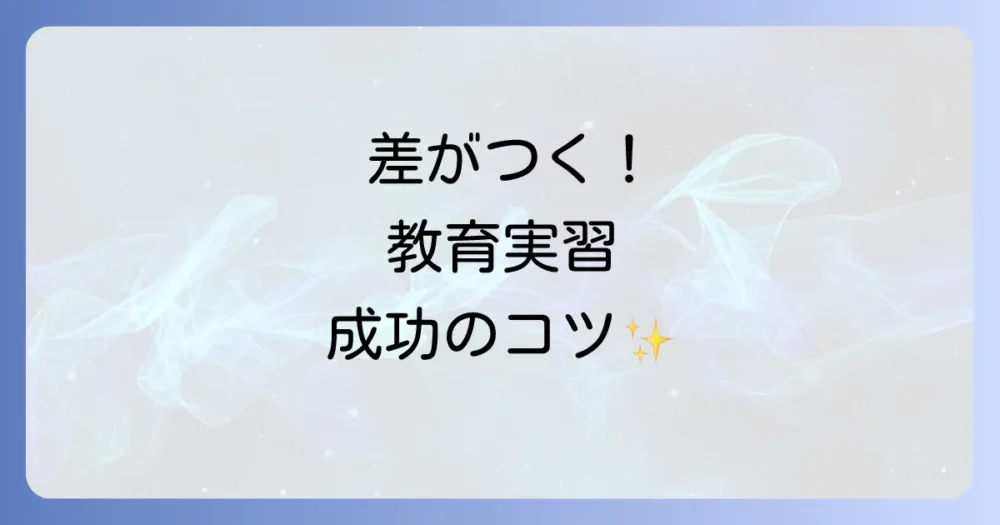
教育実習は、行き当たりばったりで臨むものではありません。 事前の準備をどれだけ入念に行うかが、実習の成否を大きく左右します。 ここでは、他の実習生と差をつけるための、具体的な準備について解説します。万全の準備で、自信を持って実習初日を迎えましょう。
この章で紹介する準備内容は以下の通りです。
- 実習校の情報収集と教材研究
- 指導案作成と模擬授業
- 持ち物の最終チェックリスト
- 服装と身だしなみの基本マナー
実習校の情報収集と教材研究
実習が始まる前に、実習校について深く理解しておくことは非常に重要です。まずは学校のホームページを隅々まで確認し、教育目標や方針、年間行事、生徒数、日課表などを把握しましょう。 学校がどのような教育を大切にしているかを知ることで、実習中の言動の指針になります。
次に、担当する学年や教科が分かったら、すぐに教材研究に取り掛かりましょう。 使用する教科書や指導書を手に入れ、単元の目標や内容を深く理解します。 自分が教える範囲だけでなく、その前後の単元にも目を通し、学習内容の繋がりを意識することが大切です。子どもたちから想定外の質問が飛んでくることも想定し、関連知識を広げておくと安心です。
指導案作成と模擬授業
指導案の作成は、教育実習で最も時間と労力がかかる作業の一つです。 しかし、これは授業の設計図であり、質の高い授業を行うためには不可欠です。 大学で学んだ指導案の書き方を復習し、指導教官に提出する前に、自分自身で何度も推敲を重ねましょう。
そして、指導案が完成したら、必ず模擬授業を行ってください。 友人や大学の先生に見てもらい、フィードバックをもらうのが理想ですが、一人でも構いません。実際に声に出して時間を計りながら行うことで、時間配分の感覚を掴んだり、説明が分かりにくい部分に気づいたりすることができます。 板書計画も具体的に立て、実際に書いてみる練習をしておくと、当日の授業がスムーズに進みます。
持ち物の最終チェックリスト
実習中は、毎日が忙しく、忘れ物をすると焦りの原因になります。事前に必要なものをリストアップし、前日までに完璧に準備しておきましょう。 学校から特に指示がない場合でも、一般的に必要とされるものを以下にまとめました。
- 書類関係: 教育実習日誌、大学からの書類、印鑑、学生証
- 筆記用具: 黒・赤ボールペン、鉛筆、消しゴム、採点用赤ペン、多色ボールペン、マーカー、定規など
- ノート・ファイル類: 授業見学用ノート、指導案や資料を挟むバインダーやクリアファイル
- 服装・身だしなみ: スーツ、上履き(体育館シューズ)、体育用の運動着・運動靴、ハンカチ、ティッシュ
- その他: 腕時計(スマホでの時間確認はNG)、給食用のエプロン・三角巾・マスク、水筒、雑巾
特に印鑑は出勤簿などで毎日使うことが多いので、忘れないように注意が必要です。
服装と身だしなみの基本マナー
実習生は「先生」として見られるため、服装や身だしなみには細心の注意を払う必要があります。清潔感が何よりも大切です。
服装:
- 基本はリクルートスーツです。 色は黒や紺、グレーなどの落ち着いたものを選びましょう。
- シャツやブラウスは白を基本とし、シワや汚れがないか毎日確認します。
- 体育の授業がある日は、学校指定のジャージか、それに準ずる動きやすい服装を準備します。
身だしなみ:
- 髪: 髪が長い場合は、授業の邪魔にならないようにまとめます。髪色は黒か、それに近い自然な色に戻しておきましょう。
- 爪: 短く切りそろえ、清潔に保ちます。ネイルアートは厳禁です。
- 化粧: ナチュラルメイクを心がけ、派手な印象にならないように注意します。
- アクセサリー: 結婚指輪以外は、基本的に外していくのが無難です。
子どもたちの手本となるような、清潔感のあるきちんとした身だしなみを常に意識してください。
【要注意】教育実習で避けるべきNG行動
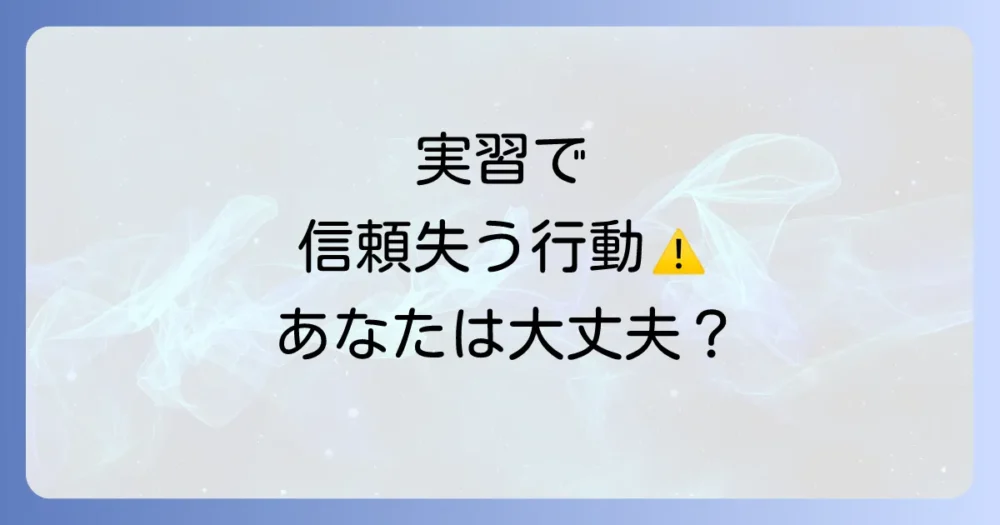
意欲的に実習に臨んでいても、些細な行動が原因で評価を下げてしまったり、学校に迷惑をかけてしまったりすることがあります。ここでは、教育実習中に絶対に避けるべきNG行動を具体的に解説します。知らず知らずのうちに信頼を失うことがないよう、しっかりと頭に入れておきましょう。
この章で解説するNG行動は以下の通りです。
- 遅刻・無断欠勤は厳禁
- 生徒との個人的な関わり
- 職員室内でのマナー違反
- SNSの取り扱いには細心の注意を
遅刻・無断欠勤は厳禁
社会人として当たり前のことですが、遅刻や無断欠勤は絶対に許されません。 教育実習においても、これは最も基本的なルールです。先生方は朝早くから打ち合わせや準備を行っています。 実習生は、指導教官よりも早く出勤するくらいの心構えでいましょう。交通機関の遅延なども考慮し、時間に余裕を持った行動を心がけてください。
やむを得ない事情で遅刻や欠席をする場合は、必ず実習が始まる前に、決められた手順に従って学校に直接電話で連絡を入れましょう。大学への連絡も忘れてはいけません。体調が悪い場合は無理をせず、正直に申し出ることが大切です。自己判断で行動せず、必ず指示を仰ぐようにしてください。
生徒との個人的な関わり
生徒と良好な関係を築くことは大切ですが、一線を越えた個人的な関わりは厳禁です。特に、以下の行動は大きな問題に発展する可能性があるため、絶対に避けてください。
- 個人的な連絡先の交換(LINE、Instagram、電話番号など)
- 学校外で二人きりで会うこと
- 特定の生徒だけを特別扱いする(えこひいき)
- 恋愛感情を抱かせるような言動
実習生は生徒にとって年齢が近く、親しみやすい存在です。 そのため、生徒から個人的な相談を受けたり、連絡先を聞かれたりすることもあるかもしれません。しかし、立場をわきまえ、常に「先生」と「生徒」という関係性を保つ必要があります。 もし対応に困るようなことがあれば、一人で抱え込まず、すぐに指導教官に相談してください。
職員室内でのマナー違反
職員室は、先生方にとって仕事場であり、プライベートな空間ではありません。実習生もその一員として、節度ある行動が求められます。
- 私語: 実習生同士でのおしゃべりは控えましょう。業務に関係のない話は、休憩時間などに場所をわきまえて行うべきです。
- スマートフォンの使用: 許可なくスマートフォンを操作するのはマナー違反です。緊急の連絡など、やむを得ない場合を除き、カバンの中にしまっておきましょう。
- 態度: 先生方が話している内容に聞き耳を立てたり、パソコンの画面を覗き込んだりするような行動は慎んでください。また、机に突っ伏したり、だらしない姿勢で座ったりすることも当然NGです。
常に周囲への配慮を忘れず、緊張感を持って過ごすことが大切です。空き時間は、ぼーっと過ごすのではなく、指導案の作成や教材研究、授業見学の記録整理など、やるべきことを見つけて主体的に動きましょう。
SNSの取り扱いには細心の注意を
現代において、SNSの取り扱いは非常にデリケートな問題です。 教育実習中の出来事や感想を気軽に投稿したくなる気持ちは分かりますが、それが大きなトラブルに繋がる危険性を常に認識しておく必要があります。
- 実習校や生徒、先生に関する情報の投稿は一切行わない。(学校名、個人名が特定できる写真や文章は厳禁)
- 「実習疲れた」「授業うまくいかなかった」といったネガティブな内容の投稿も避ける。(誰が見ているか分かりません)
- 生徒からSNSアカウントのフォロー申請があっても、絶対に許可しない。
実習生は、学校の内部情報を知る立場にあります。守秘義務を遵守し、実習に関する一切の内容をオンライン上で公開しないことを徹底してください。 一度の軽率な投稿が、実習校や大学、そして自分自身の将来に深刻な影響を及ぼす可能性があることを肝に銘じておきましょう。
感謝を伝える教育実習のお礼状【書き方と例文】
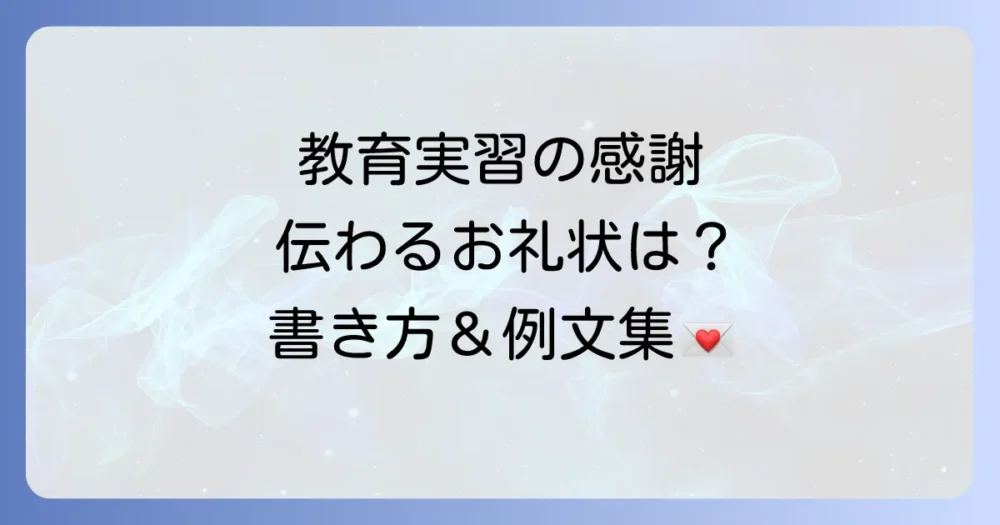
教育実習を終えたら、お世話になった実習校へ感謝の気持ちを伝えるお礼状を送りましょう。 これは社会人としての基本的なマナーであると同時に、自分の学びを振り返り、教員への志を新たにする良い機会にもなります。ここでは、お礼状の基本的な書き方と、すぐに使える例文を紹介します。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- お礼状を書くタイミングとマナー
- お礼状の基本構成
- 【宛先別】お礼状の例文
お礼状を書くタイミングとマナー
お礼状は、実習終了後、できるだけ早く、遅くとも1週間以内に投函するのが理想です。 感謝の気持ちが新鮮なうちに書くことで、より心のこもった内容になります。もし事情があって遅れてしまった場合でも、必ずお詫びの一文を添えて送るようにしましょう。
お礼状のマナー:
- 手書きで書く: 丁寧な字で、心を込めて書きましょう。パソコン作成は避け、黒または青の万年筆かボールペンを使用します。
- 便箋と封筒: 白無地の縦書きの便箋と、それに合った白い封筒を選びます。キャラクターものや色付きのものは避けましょう。
- 宛名: 基本的には「学校長」宛てに送ります。 宛名は「〇〇学校 校長 〇〇 〇〇 様」と正式名称で書きます。指導教官に特にお世話になった場合は、校長先生宛の手紙とは別に、指導教官個人宛ての手紙を添えても良いでしょう。
- 郵送方法: 普通郵便で送ります。速達にする必要はありません。
お礼状の基本構成
お礼状は、以下の構成で書くのが一般的です。
- 頭語: 「拝啓」など。
- 時候の挨拶: 季節に合った挨拶を書きます。「秋涼の候」「向寒の折」など。
- 安否を尋ねる挨拶: 先生方の健康や活躍を気遣う言葉を入れます。「先生方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」など。
- お礼の言葉: 教育実習を受け入れていただいたことへの感謝を述べます。
- 本文(実習の感想): 実習を通して学んだことや、心に残った具体的なエピソードなどを書きます。
- 今後の抱負: 実習での経験を今後どのように活かしていきたいかを述べます。
- 結びの挨拶: 学校の発展や先生方の健康を祈る言葉で締めくくります。「末筆ながら、貴校のますますのご発展と、先生方の今後のご健勝を心よりお祈り申し上げます。」など。
- 結語: 「敬具」など。頭語とセットで使います。
- 日付・署名・宛名: 投函する日付、自分の大学名・学部・氏名、宛名を最後に書きます。
【宛先別】お礼状の例文
ここでは、校長先生宛と指導教官宛の2パターンの例文を紹介します。
校長先生宛の例文:
拝啓
秋冷の候、貴校におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日は〇週間にわたる教育実習におきまして、大変お世話になり、誠にありがとうございました。お忙しい中、私たち実習生を温かく受け入れていただき、心より感謝申し上げます。
実習期間中は、指導教官の〇〇先生をはじめ、多くの先生方からご指導を賜り、授業の進め方はもちろんのこと、生徒一人ひとりと真摯に向き合うことの大切さなど、教育現場でしか得られない多くのことを学ばせていただきました。特に、全校生徒が一体となって取り組んでいた〇〇(学校行事など)での生徒たちの生き生きとした表情は、今も心に焼き付いております。
この度の貴重な経験を糧とし、生徒から信頼される教員になるという目標に向かって、一層精進してまいる所存です。
末筆ながら、貴校のますますのご発展と、先生方の今後のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇 〇〇
〇〇市立〇〇中学校
校長 〇〇 〇〇 様
指導教官宛の例文:
拝啓
朝夕はめっきり冷え込むようになりましたが、〇〇先生におかれましては、お変わりなくご活躍のことと存じます。
先日の教育実習では、大変お世話になり、誠にありがとうございました。先生には、お忙しい中、授業の準備から日誌の指導まで、懇切丁寧にご指導いただき、感謝の念に堪えません。
初めての授業で何から手をつけて良いか分からず、不安でいっぱいだった私に、先生が「失敗を恐れずに、まずは生徒と楽しむことが一番だよ」と声をかけてくださったおかげで、肩の力が抜け、自分らしく授業に臨むことができました。先生からいただいたアドバイスの一つひとつが、私の大きな財産です。
先生から学ばせていただいたことを胸に、私も先生のような、生徒の心に寄り添える温かい教員を目指して、努力を続けてまいります。
季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください。先生の今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇大学〇〇学部〇〇学科
〇〇 〇〇
〇〇先生
よくある質問
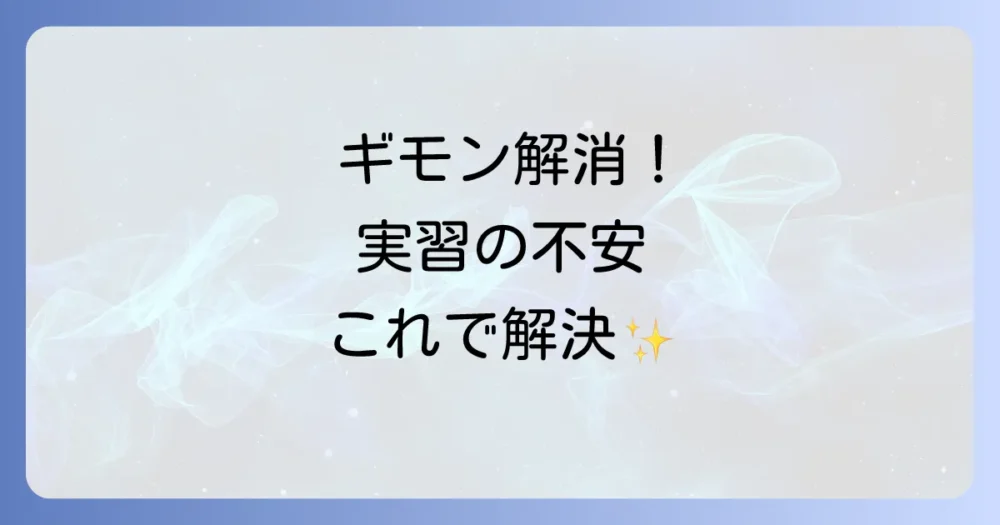
教育実習で一番大変なことは何ですか?
多くの実習生が挙げるのが、「指導案の作成」と「実習日誌の記入」です。 毎日、授業見学や自身の授業準備、生徒との関わりなどで一日があっという間に過ぎていく中で、放課後や帰宅後にこれらの書類作成に追われることになります。 質の高い授業を行うための指導案作成には多くの時間と労力が必要ですし、日々の学びや反省を記録する実習日誌も詳細に書くことが求められます。 時間管理を徹底し、効率的に作業を進める工夫が求められます。
生徒と上手くコミュニケーションをとるコツは?
まずは、一人ひとりの生徒の名前を早く覚えることが第一歩です。名前を呼んで話しかけることで、生徒は「自分を認めてくれている」と感じ、心を開きやすくなります。また、休み時間や掃除の時間などに積極的に生徒の輪に入り、生徒の好きなこと(ゲーム、アニメ、部活動など)に興味を持って質問してみましょう。 ただし、教師としての立場を忘れず、馴れ馴れしくなりすぎないよう、適度な距離感を保つことも大切です。
指導教官とうまくいかない場合はどうすればいいですか?
指導教官との関係に悩んだ場合は、一人で抱え込まず、まずは大学の担当教員に相談するのが最善です。 指導教官も人間ですから、相性が合わないと感じることもあるかもしれません。しかし、多くの場合、厳しい指導の裏には実習生を育てたいという思いがあります。まずは、指導内容を謙虚に受け止め、実践する努力をしてみましょう。その上で、どうしても納得できない点や、コミュニケーションが取れないと感じる場合は、大学の先生に間に入ってもらい、状況を客観的に見てもらうことが解決への近道です。
教育実習の自己紹介で何を話せばいいですか?
自己紹介では、基本的な情報に加えて、生徒があなたに興味を持つような要素を盛り込むと良いでしょう。
- 基本情報: 名前、大学名、実習期間、担当教科。
- 親しみやすさを出す要素: 呼んでほしいニックネーム、趣味や特技、好きな食べ物やアニメなど。
- 意気込み: 「皆さんとたくさん話したい」「一緒に勉強できるのが楽しみ」といった前向きなメッセージ。
長々と話すのではなく、1分程度で簡潔に、明るくハキハキと話すことを心がけましょう。 黒板に自分の名前や好きなものを書いて視覚的にアピールするのも効果的です。
教育実習で気をつけることは何ですか?
気をつけるべきことは多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の3点です。
- 時間厳守と挨拶の徹底: 社会人としての基本マナーです。常に時間に余裕を持って行動し、誰に対しても明るくハキハキと挨拶しましょう。
- 謙虚な姿勢と学ぶ意欲: 「実習生」として教えてもらう立場であることを忘れず、どんなことからも学ぼうとする姿勢が大切です。
- 生徒との適切な距離感: 生徒と親しくなることは重要ですが、教師としての立場をわきまえ、個人的な関係になりすぎないよう注意が必要です。
教育実習で生徒に言ってはいけないことは?
生徒の人格や家庭環境、プライバシーを傷つけるような発言は絶対に避けなければなりません。具体的には以下のような言葉です。
- 差別的な発言: 性別、国籍、容姿などに関する差別的な言葉。
- プライベートに踏み込みすぎる質問: 家庭の経済状況や、両親の職業、恋愛関係など。
- 他の生徒や先生の悪口・批判。
- 「どうせ無理」「あなたにはできない」といった、生徒の可能性を否定する言葉。
常に言葉の重みを意識し、一人の人間として尊重する姿勢で生徒に接してください。
まとめ
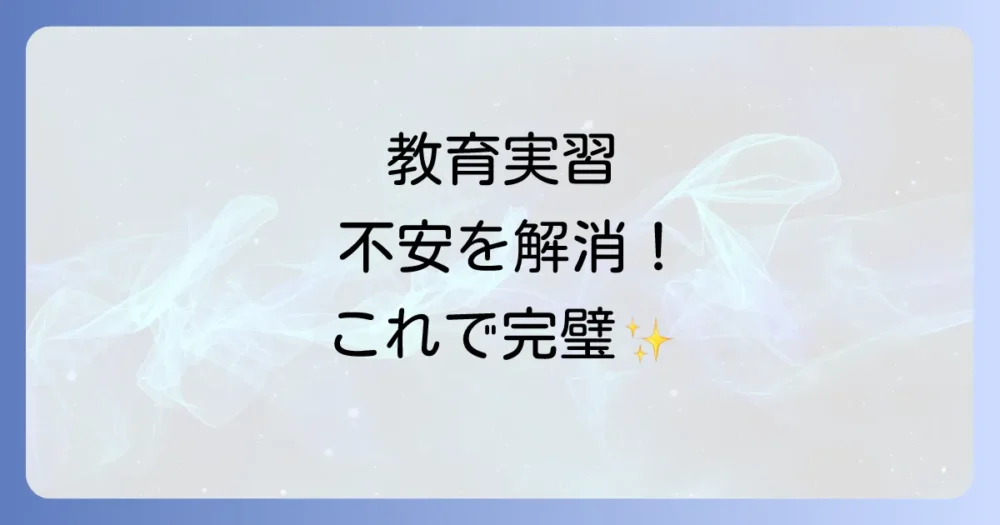
- 教育実習の挨拶は場面に応じて簡潔かつ誠実に行う。
- 心構えとして「謙虚さ」「学ぶ姿勢」「誠実さ」が重要。
- 事前の情報収集と教材研究が実習の質を左右する。
- 指導案作成後は必ず模擬授業で練習しておくこと。
- 持ち物はリスト化し、前日までに完璧に準備する。
- 服装と身だしなみは清潔感が第一、手本となるように。
- 遅刻・無断欠勤は社会人として絶対にNG。
- 生徒との個人的な連絡先の交換は厳禁である。
- 職員室では私語を慎み、節度ある行動を心がける。
- SNSへの実習に関する投稿は一切行わないこと。
- お礼状は実習後1週間以内に手書きで送るのがマナー。
- お礼状には具体的なエピソードを交え感謝を伝える。
- 困ったときは一人で抱えず大学の担当教員に相談する。
- 生徒とのコミュニケーションは名前を覚えることから。
- 常に言葉の重みを意識し、生徒の人格を尊重すること。
新着記事