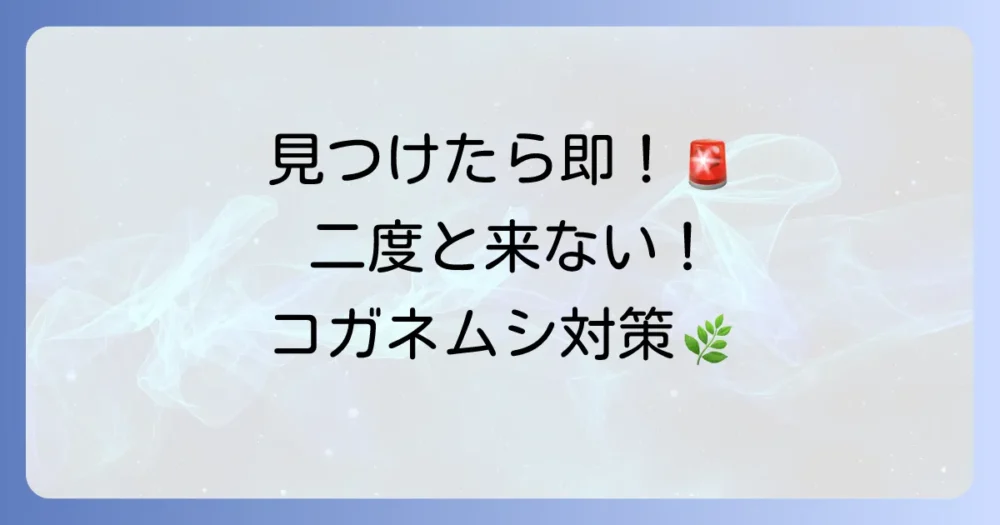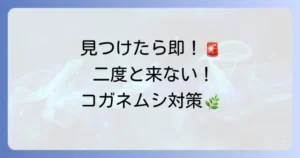大切に育てている植物の葉が、いつの間にか網目状にボロボロに…。「もしかして、あのキラキラした虫のせい?」そう、その犯人はコガネムシの成虫かもしれません。見た目は綺麗でも、ガーデニング愛好家にとっては厄介な害虫です。本記事では、そんなコガネムシ成虫の効果的な駆除方法から、おすすめの殺虫剤、二度と寄せ付けないための予防策まで、あなたの悩みを解決する方法を詳しく解説します。
コガネムシの成虫による被害とは?放置は危険!

コガネムシの成虫による被害は、見た目の悪さだけではありません。放置すると植物が枯れてしまうこともあるため、早期の対策が非常に重要です。まずは、どのような被害があるのかを正しく理解しましょう。
本章では、コガネムシの成虫が引き起こす具体的な被害について解説します。
- 葉や花がボロボロに!食害の特徴
- 被害を放置するとどうなる?
- コガネムシのフンが新たな被害を呼ぶ
葉や花がボロボロに!食害の特徴
コガネムシの成虫による最も分かりやすい被害は、葉や花の食害です。成虫は食欲旺盛で、様々な植物の葉を好んで食べます。 特に特徴的なのは、葉脈だけを残して、まるでレースのように網目状に食べてしまうことです。 このような食害跡を見つけたら、コガネムシの成虫がいる可能性が非常に高いでしょう。
また、葉だけでなく、バラやハイビスカスなどの美しい花びらも食べてしまいます。 せっかく咲いた花が虫食い状態になってしまうのは、とても悲しいことですよね。被害が広範囲に及ぶと、植物の光合成が妨げられ、生育不良の原因にもなります。
被害を放置するとどうなる?
「少し葉が食べられているだけだから」と油断してはいけません。コガネムシの被害を放置すると、植物全体が弱り、最悪の場合枯れてしまうことがあります。 成虫による葉の食害で光合成が十分にできなくなると、植物は成長するためのエネルギーを作れなくなります。
さらに深刻なのは、成虫が土の中に産み付ける卵です。孵化した幼虫は、土の中で植物の根を食べて成長します。 根が食害されると、植物は水分や養分を吸収できなくなり、地上部が元気なように見えても、突然枯れてしまうことがあるのです。 成虫を見つけたら、それは氷山の一角かもしれません。土の中には、さらに多くの幼虫が潜んでいる可能性があるのです。
コガネムシのフンが新たな被害を呼ぶ
あまり知られていませんが、コガネムシの成虫が葉に残すフンも厄介な存在です。コガネムシのフンには、仲間を呼び寄せるフェロモンのような働きがあると言われています。 つまり、フンを放置しておくと、次から次へと別のコガネムシが集まってきて、被害がさらに拡大してしまうのです。
葉の上に黒い小さな塊を見つけたら、それはコガネムシのフンかもしれません。見つけ次第、すぐに取り除くようにしましょう。 このように、成虫の食害、幼虫による根の被害、そしてフンによる誘引と、コガネムシは植物にとって三重苦をもたらす害虫なのです。
【即効性重視】見つけたらすぐ退治!コガネムシ成虫におすすめの殺虫剤(スプレータイプ)

植物に群がるコガネムシの成虫を見つけたら、一刻も早く駆除したいもの。そんな時に頼りになるのが、即効性に優れたスプレータイプの殺虫剤です。直接吹きかけるだけで、素早く退治できます。
ここでは、数あるスプレー剤の中から、特にコガネムシ成虫に効果的な商品を厳選してご紹介します。
- 住友化学園芸 ベニカXネクストスプレー
- アース製薬 アースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット
- フマキラー カダンA ケムシジェット
住友化学園芸 ベニカXネクストスプレー
「ベニカXネクストスプレー」は、多くのガーデナーから支持されている人気の殺虫殺菌剤です。この商品の大きな特徴は、5つの有効成分を配合している点。これにより、コガネムシはもちろん、アブラムシやハダニ、うどんこ病や黒星病といった病気まで、幅広い病害虫に効果を発揮します。
コガネムシに対しては、速効性と持続性を兼ね備えており、直接かければすぐに退治できるだけでなく、薬剤がかかった葉を食べた虫にも効果があります。また、植物の病気を予防する効果もあるため、害虫対策と病気予防を一度に行いたいという方には最適な1本と言えるでしょう。バラや多くの草花、野菜にも使える汎用性の高さも魅力です。
アース製薬 アースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット
「とにかく今いるコガネムシをすぐに何とかしたい!」という方には、「アースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット」がおすすめです。 その名の通り、強力なジェット噴射が特徴で、高い木にいるコガネムシにも薬剤が届きやすいのが利点です。
速効性に優れた殺虫成分「イミプロトリン」を配合しており、薬剤が直接かかったコガネムシを素早くノックダウンさせます。また、殺虫効果だけでなく忌避効果も期待できるため、散布しておくことでコガネムシが寄り付きにくくなる効果もあります。 屋外専用で、庭木や生垣などの広範囲に発生したコガネムシを手早く駆除したい場合に非常に役立ちます。
フマキラー カダンA ケムシジェット
「カダンA ケムシジェット」は、商品名に「ケムシ」とありますが、コガネムシの成虫にも優れた効果を発揮する殺虫スプレーです。この製品の強みは、殺虫成分に加えて、植物の栄養成分(窒素・リン酸・カリ)が配合されている点です。
コガネムシを駆除しながら、同時に植物に栄養を与えることができるため、食害で弱った植物の回復を助ける効果が期待できます。ジェット噴射で高い場所にも届きやすく、使い勝手も良好です。害虫駆除と植物のケアを同時に行いたいと考える、植物思いのあなたにぴったりの商品です。
【持続性で選ぶ】根こそぎ退治!コガネムシ成虫・幼虫におすすめの殺虫剤(粒剤・乳剤)

目の前の成虫を退治するだけでなく、土の中に潜む幼虫まで駆除し、長期的にコガネムシの発生を抑えたい場合は、持続性に優れた粒剤や乳剤タイプの殺虫剤が効果的です。これらは植物に成分が吸収され、全体に行き渡ることで効果を発揮します。
ここでは、根本的なコガネムシ対策におすすめの粒剤と乳剤をご紹介します。
- 【粒剤】住友化学園芸 オルトランDX粒剤
- 【粒剤】住友化学園芸 ダイアジノン粒剤3
- 【乳剤】住友化学園芸 スミチオン乳剤
【粒剤】住友化学園芸 オルトランDX粒剤
「オルトランDX粒剤」は、「浸透移行性」という特徴を持つ殺虫剤です。 これは、株元に撒くだけで有効成分が根から吸収され、植物全体に行き渡る仕組みのこと。 このため、薬剤が直接かからなかった葉を食べるコガネムシの成虫や、土の中にいる幼虫にも効果を発揮します。
効果の持続期間が長く、一度撒けば長期間にわたって植物を害虫から守ってくれるのが最大のメリットです。植え付け時や植え替え時に土に混ぜ込んでおけば、コガネムシの予防策として非常に有効です。 アブラムシなど他の害虫にも効果があるため、一つ持っておくと重宝する薬剤です。
【粒剤】住友化学園芸 ダイアジノン粒剤3
「ダイアジノン粒剤3」は、特に土の中にいるコガネムシの幼虫(ネキリムシ)退治に絶大な効果を発揮する土壌殺虫剤です。 多くの農家や園芸家から長年信頼されている定番商品でもあります。
この薬剤は、土に混ぜ込むことで効果を発揮します。 接触効果に加え、土の中でガス状に広がる「ベーパーアクション」により、広範囲の幼虫を効率的に駆除することができます。 成虫が飛来して産卵する前の春先や、植え付け前に土に混ぜておくことで、幼虫による根の被害を未然に防ぐことができます。 毎年コガネムシの幼虫に悩まされている方は、ぜひ試していただきたい殺虫剤です。
【乳剤】住友化学園芸 スミチオン乳剤
「スミチオン乳剤」は、水で薄めて使用するタイプの殺虫剤で、非常に幅広い害虫に効果がある家庭園芸の代表的な薬剤です。 コガネムシの成虫に対しては、散布することで直接駆除する効果があります。
この薬剤の優れた点は、植物の組織内に浸透する性質があるため、葉の裏に隠れている害虫や、食入した害虫にも効果が期待できることです。 また、芝生に発生したコガネムシの幼虫対策として、希釈液を土壌に染み込ませる(土壌灌注)という使い方もできます。 自分で希釈する手間はありますが、コストパフォーマンスが高く、様々な植物や害虫に柔軟に対応したい方におすすめです。
殺虫剤が効かない?コガネムシ駆除でよくある失敗と対策

「おすすめの殺虫剤を使ったのに、コガネムシが全然いなくならない…」そんな経験はありませんか?もしかしたら、殺虫剤の使い方やタイミングが間違っているのかもしれません。効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントがあります。
この章では、コガネムシ駆除で陥りがちな失敗例と、その対策について解説します。
- 散布する時間帯が間違っている
- 薬剤が虫や葉にしっかりかかっていない
- 同じ殺虫剤を使い続けている
散布する時間帯が間違っている
殺虫剤を散布する時間帯は、実は非常に重要です。特にスプレータイプの殺虫剤は、日中の高温時に散布すると、薬剤がすぐに蒸発してしまい効果が半減することがあります。また、植物にとっても負担が大きく、薬害(葉が焼けるなど)の原因になることも。
おすすめの散布時間は、比較的涼しい早朝か夕方です。特にコガネムシは早朝は動きが鈍いため、駆除の絶好のチャンスです。 雨が降る直前や強風時の散布も、薬剤が流れたり飛散したりしてしまうため避けましょう。天候と時間を見計らって、最も効果的なタイミングで散布することが大切です。
薬剤が虫や葉にしっかりかかっていない
基本的なことですが、意外と見落としがちなのが散布の仕方です。スプレー剤の場合、コガネムシの成虫に直接薬剤がかからなければ、十分な効果は得られません。また、葉の裏に隠れていることも多いため、葉の表だけでなく、裏側にもまんべんなく散布することを心がけましょう。
粒剤の場合も同様です。株元にパラパラと撒くだけでなく、土の表面に均一に広げ、軽く土と混ぜ合わせる(混和する)ことで、有効成分が土壌全体に行き渡りやすくなります。 薬剤のラベルに記載されている使用方法をよく読み、正しい使い方を実践することが、確実な駆除への近道です。
同じ殺虫剤を使い続けている
毎年同じ種類の殺虫剤を使い続けていると、「薬剤抵抗性」を持ったコガネムシが現れる可能性があります。薬剤抵抗性とは、同じ成分の薬剤に繰り返しさらされることで、その薬剤が効きにくくなる現象のことです。
もし、「去年は効いたのに今年は効果が薄い」と感じる場合は、この薬剤抵抗性を疑ってみる必要があります。対策としては、作用性の異なる複数の殺虫剤をローテーションで使用することが有効です。例えば、今年は有機リン系(スミチオンなど)を使ったら、来年はネオニコチノイド系(オルトランなど)を使ってみる、といった具合です。 殺虫剤のパッケージに記載されている有効成分名を確認し、系統の違うものをいくつか用意しておくと良いでしょう。
殺虫剤を使わない!コガネムシ成虫の駆除・対策方法

「小さな子供やペットがいるから、できるだけ殺虫剤は使いたくない」「無農薬で野菜を育てている」という方も多いでしょう。幸い、殺虫剤に頼らなくてもコガネムシの成虫を駆除・対策する方法はあります。
ここでは、薬剤を使わない自然にやさしいコガネムシ対策をご紹介します。
- 地道だけど確実!手で捕まえる
- ペットボトルで簡単!捕獲トラップを作る
- 自然の力で撃退!木酢液やニームオイルを活用する
地道だけど確実!手で捕まえる
最も原始的ですが、確実な方法が手で捕まえて駆除することです。コガネムシは危険を察知すると、ポトッと下に落ちて死んだふりをする習性があります。 この習性を利用し、植物の下に袋やバケツを構えて枝を揺すると、簡単に捕獲することができます。
活動が鈍くなる早朝に行うのが最も効率的です。 虫を直接触るのに抵抗がある方は、軍手や手袋を着用しましょう。 数は多いかもしれませんが、見つけ次第コツコツと捕殺することで、産卵される数を確実に減らすことができます。
ペットボトルで簡単!捕獲トラップを作る
コガネムシをおびき寄せて捕獲するトラップを自作することもできます。フェロモンを利用した市販のトラップもありますが、家庭にあるもので簡単に作れます。
作り方は簡単です。2Lのペットボトルの上部1/3あたりを切り、逆さにして本体に差し込み、漏斗(じょうご)のような形にします。中に、コガネムシが好む匂いのする液体(例えば、焼酎、砂糖、酢を混ぜたものなど)を数センチ入れておくだけ。匂いにつられて入ったコガネムシが、出られなくなるという仕組みです。これを庭木の枝などに吊るしておけば、自動でコガネムシを捕獲してくれます。
自然の力で撃退!木酢液やニームオイルを活用する
化学的な殺虫剤を使いたくない場合、自然由来の資材を活用する方法もあります。代表的なものが「木酢液(もくさくえき)」です。 木酢液は、木炭を作る際に出る煙を液体にしたもので、独特の燻製のような匂いがします。 この匂いを害虫が嫌うため、忌避効果が期待できます。 水で薄めて植物に散布して使います。ただし、殺虫効果そのものはないため、あくまで「寄せ付けにくくする」ためのものと考えましょう。
また、「ニームオイル」も人気の自然派資材です。ニームという樹木の種子から抽出したオイルで、害虫の食欲を減退させたり、成長を阻害したりする効果があると言われています。こちらも水で薄めて散布します。これらの自然資材は、化学農薬に比べて効果は穏やかですが、環境への負担が少なく、予防的に使いやすいのがメリットです。
もう発生させない!来年のためのコガネムシ予防策

コガネムシとの戦いは、駆除して終わりではありません。来年以降、再び大量発生させないためには、成虫が活動する時期だけでなく、年間を通した予防策が重要になります。
ここでは、将来の被害を減らすための効果的な予防策をいくつかご紹介します。
- 産卵場所をなくす!マルチングと防虫ネット
- 成虫を寄せ付けない!コンパニオンプランツとこまめな手入れ
- 幼虫が育ちにくい土壌環境を作る
産卵場所をなくす!マルチングと防虫ネット
コガネムシのメスは、植物の根元付近の土の中に潜り込んで産卵します。 そこで有効なのが、物理的に産卵させないようにすることです。
最も手軽な方法は「マルチング」です。ウッドチップやバークチップ、あるいは黒いビニール製のマルチシートなどで株元の土の表面を覆うことで、成虫が土に潜り込むのを防ぎます。 鉢植えの場合は、水苔や不織布で土の表面をカバーするのも良いでしょう。また、特に大切な植物は、目の細かい防虫ネットで全体を覆ってしまうのが最も確実な方法です。
成虫を寄せ付けない!コンパニオンプランツとこまめな手入れ
コガネムシが嫌う匂いを放つ植物を一緒に植える「コンパニオンプランツ」も、予防策の一つとして知られています。 例えば、マリーゴールド、ニンニク、スイセンなどは、コガネムシが嫌う成分を含んでいると言われ、忌避効果が期待できます。 バラなどのコガネムシが好む植物の近くに植えておくと良いでしょう。
また、日々のこまめな手入れも重要です。前述の通り、コガネムシのフンは仲間を呼び寄せます。 葉にフンを見つけたらすぐに取り除くこと。そして、成虫を見かけたら、産卵される前にすぐに捕殺すること。こうした地道な作業の積み重ねが、翌年の発生数を減らすことに繋がります。
幼虫が育ちにくい土壌環境を作る
コガネムシの幼虫は、未熟な堆肥や腐葉土などの有機物が豊富な土を好みます。 そのため、土作りをする際には、完熟した良質な堆肥を使うように心がけましょう。未熟な堆肥は、幼虫にとって格好のエサとなり、産卵場所として選ばれやすくなってしまいます。
また、植え替えや土を耕す際には、土の中に幼虫がいないかよく確認する習慣をつけましょう。 もし幼虫を見つけたら、その場で駆除します。 幼虫が育ちにくい土壌環境を整えることは、コガネムシ対策の根本的な解決策と言えるでしょう。
よくある質問

コガネムシの成虫や殺虫剤に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
コガネムシの成虫にキンチョールは効きますか?
家庭用の殺虫スプレーであるキンチョールも、コガネムシの成虫に直接かかれば効果は期待できます。 しかし、キンチョールは本来、ハエや蚊などの飛ぶ虫を対象とした製品であり、園芸用に作られたものではありません。植物に直接噴射すると、冷害などで植物を傷めてしまう可能性があります。 もし使用する場合は、植物から十分に距離を離し、短時間噴射に留めるなど注意が必要です。 基本的には、本記事で紹介したような園芸用の殺虫剤を使用することをおすすめします。
コガネムシの駆除に木酢液は効果がありますか?
木酢液には殺虫成分は含まれていないため、直接的な駆除効果は期待できません。 しかし、木酢液の独特の燻製のような匂いを害虫が嫌うため、忌避剤(虫よけ)としての効果は期待できます。 定期的に水で希釈したものを散布することで、コガネムシが寄り付きにくい環境を作る手助けになります。化学農薬を使いたくない場合の予防策の一つとして有効です。
コガネムシの成虫はどんな植物を好みますか?
コガネムシの成虫は非常に食欲旺盛で、多種多様な植物を食べます。 特に好むとされるのは、以下のような植物です。
- 花木:バラ、ハイビスカス、サルスベリ、ムクゲ
- 果樹:ブドウ、カキ、ブルーベリー、イチジク
- 野菜:ダイズ、インゲンなどのマメ科植物、ナス、イチゴ
- 庭木:サクラ、ケヤキ、クヌギ
これらの植物を育てている場合は、特に注意が必要です。
コガネムシとカナブンの見分け方は?
コガネムシとカナブンは見た目がよく似ていますが、簡単に見分けるポイントがあります。一番分かりやすいのは、体の形と羽の付け根です。
- コガネムシ:全体的に丸っこい体型。羽の付け根(小楯板)が半円形。植物の葉を食べる害虫。
- カナブン:やや四角張った体型。羽の付け根が逆三角形。樹液を吸う益虫(害はない)。
葉を食べているのがコガネムシ、木の幹で樹液を吸っているのがカナブンと覚えておくと良いでしょう。
コガネムシの成虫の活動時期はいつですか?
コガネムシの成虫が活発に活動するのは、主に初夏から夏にかけての6月~9月頃です。 種類によっては5月頃から現れるものもいます。 この時期に植物の葉が食べられていたら、コガネムシの仕業を疑いましょう。成虫は日中に活動することが多いですが、ドウガネブイブイのように夜行性の種類もいます。
まとめ

- コガネムシ成虫は葉や花を網目状に食害する。
- 放置すると幼虫が根を食害し植物が枯れる原因になる。
- フンは仲間を呼び寄せるため見つけたら除去する。
- 即効性を求めるならスプレータイプの殺虫剤がおすすめ。
- 根本対策には持続性のある粒剤や乳剤が効果的。
- 殺虫剤は早朝か夕方の涼しい時間帯に散布する。
- 葉の裏側にもしっかり薬剤がかかるように散布する。
- 同じ殺虫剤の連続使用は薬剤抵抗性を生む可能性がある。
- 殺虫剤を使わない場合は手で捕殺するのが確実。
- ペットボトルで簡単に捕獲トラップを作れる。
- 木酢液やニームオイルは忌避剤として有効。
- マルチングや防虫ネットで物理的に産卵を防ぐ。
- マリーゴールドなどのコンパニオンプランツも予防に役立つ。
- 幼虫は未熟な堆肥を好むため完熟堆肥を使用する。
- カナブンとは体の形と羽の付け根で見分けられる。
新着記事