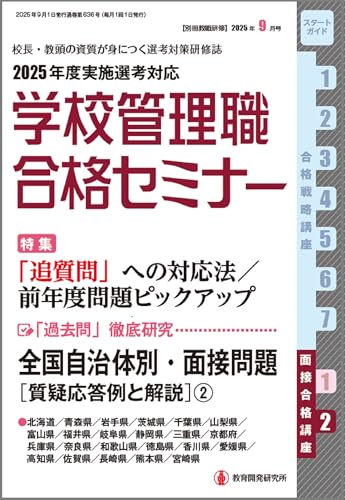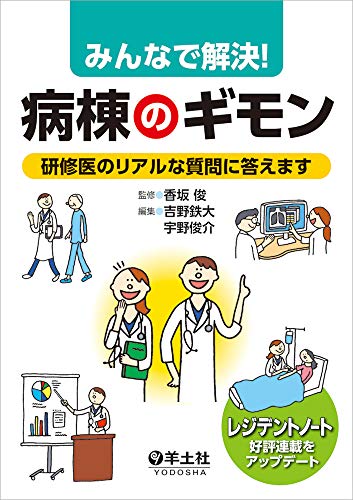「研修中に何か質問はありますか?」と聞かれても、なかなか質問が思いつかない…。そんな経験はありませんか?周りが積極的に質問しているのを見ると、余計に焦ってしまいますよね。でも、安心してください。研修で質問が思いつかないのは、あなただけではありません。本記事では、なぜ研修中に質問が出てこないのか、その原因を深掘りし、誰でも実践できる具体的な解決策や質問を見つけるコツを徹底解説します。この記事を読めば、次回の研修から積極的に質問できるようになるはずです。
なぜ研修で質問が思いつかないのか?主な5つの原因
研修で質問が思いつかない背景には、いくつかの心理的な要因や状況が隠されています。まずは、その主な原因を理解することから始めましょう。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
ここでは、研修で質問が思いつかない主な原因として、以下の5つを解説します。
- 内容を完璧に理解している(と思い込んでいる)
- 「何を聞けばいいか」が分からない
- 「こんなこと聞いてもいいのかな?」という不安
- 周りの目が気になってしまう
- 完璧な質問をしようとしすぎている
内容を完璧に理解している(と思い込んでいる)
研修内容が非常に分かりやすく、講師の説明も明快な場合、「すべて理解できた」と感じ、特に疑問点が浮かばないことがあります。これは素晴らしいことですが、本当に細部まで理解できているか、もう一度自問自答してみることも大切です。もしかしたら、分かったつもりになっているだけで、実際に業務で活用しようとすると「あれ?」となる部分が隠れているかもしれません。例えば、「この知識を自分の業務にどう活かせるだろうか?」や「例外的なケースではどう対応するのだろうか?」といった視点を持つと、新たな疑問が生まれることがあります。また、他の参加者がどのような点に疑問を持っているのかを聞くことで、自分では気づかなかった視点を発見できることもあります。
「何を聞けばいいか」が分からない
研修のテーマ自体が初めて触れる分野であったり、あまりにも専門的でどこから手をつけていいか分からない場合、「何を聞けばいいのかすら分からない」という状態に陥ることがあります。これは、知識の前提が不足しているか、あるいは情報量が多すぎて整理しきれていないサインかもしれません。このような時は、無理に高度な質問をしようとせず、まずは基本的な用語の確認や、研修内容の要点を自分なりに再確認するような質問から始めてみるのがおすすめです。「この〇〇という言葉の意味をもう少し詳しく教えていただけますか?」や「今の説明の△△という部分が、具体的にどのようなケースを指すのかイメージが湧きません」といった素直な疑問をぶつけてみましょう。講師は、参加者の理解度に合わせて丁寧に答えてくれるはずです。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」という不安
「こんな初歩的なことを聞いたら、他の参加者にどう思われるだろうか…」「講師に呆れられないだろうか…」といった不安から、質問をためらってしまうケースも少なくありません。特に、周りのレベルが高そうに見えると、余計に気後れしてしまいますよね。しかし、研修は学ぶ場であり、疑問を解消するための絶好の機会です。あなたが「初歩的だ」と感じる疑問も、実は他の多くの参加者が同じように感じている可能性があります。勇気を出して質問することで、自分だけでなく、他の人の理解を助けることにも繋がるのです。講師も、参加者が積極的に質問してくれることを歓迎している場合がほとんどです。「基本的なことかもしれませんが…」と前置きをして質問するのも一つの手です。
周りの目が気になってしまう
質問したい気持ちはあるものの、「的外れな質問をして笑われたらどうしよう」「発言することで注目を浴びるのが苦手」など、他者の評価を気にしすぎるあまり、結局何も言えずに終わってしまうことがあります。これは、特に大人数での研修や、社内の上下関係が気になるような場面で起こりがちです。しかし、研修の場では、あなたの発言内容そのものよりも、積極的に学ぼうとする姿勢が評価されることの方が多いでしょう。また、他の参加者も自分の学習に集中しており、あなたが思うほど他人の発言を一字一句気にしているわけではありません。まずは小さな一歩として、短い質問から試してみるのがおすすめです。
完璧な質問をしようとしすぎている
「どうせ質問するなら、鋭い指摘や本質を突くような、質の高い質問をしなければならない」と、無意識のうちにハードルを上げてしまっていることも、質問が思いつかない原因の一つです。完璧な質問を考えようとするあまり、結局タイミングを逃してしまったり、何も思いつかなくなったりするのです。しかし、研修の目的は、完璧な質問を披露することではなく、あなたの理解を深めることです。少しでも「あれ?」と思ったこと、「もっと知りたい」と感じたことを素直に言葉にするだけで十分なのです。「今の説明について、〇〇という理解で合っていますか?」といった確認の質問や、「△△について、もう少し具体例を教えていただけますか?」といった深掘りの質問でも、立派な質問と言えるでしょう。
大丈夫!研修で質問が思いつくようになる具体的な5つのステップ
研修で質問が思いつかない原因が分かったところで、次は具体的な解決策を見ていきましょう。少し意識を変えたり、準備をしたりするだけで、驚くほど質問がしやすくなるはずです。ここでは、誰でも実践できる5つのステップをご紹介します。
研修で質問が思いつくようになるための具体的なステップは以下の通りです。
- ステップ1:研修の目的とゴールを再確認する
- ステップ2:小さな「?」でもメモする習慣をつける
- ステップ3:「良い質問」のハードルを下げる
- ステップ4:質問の「型」を用意しておく
- ステップ5:他の参加者の質問に便乗してみる
ステップ1:研修の目的とゴールを再確認する
まず、研修が始まる前、あるいは研修の冒頭で、「この研修で何を得たいのか」「研修後、どんな状態になっていたいのか」という目的とゴールを明確にしましょう。目的意識を持つことで、研修内容のどの部分が自分にとって重要なのか、どこを重点的に聞くべきかが見えてきます。そして、そのゴールを達成するために「何が足りないのか」「何を確認すべきか」という視点が生まれ、自然と質問したいことが出てくるはずです。例えば、「今日の研修で学ぶ〇〇のスキルを、明日からの△△業務に活かせるようになりたい」というゴールを設定すれば、「このスキルを△△業務で使う際の注意点はありますか?」といった具体的な質問が考えられます。
ステップ2:小さな「?」でもメモする習慣をつける
研修中は、講師の説明を聞きながら、少しでも「ん?」「どういうこと?」「なぜ?」と感じたことや、気になったキーワードなどを、とにかくメモする習慣をつけましょう。「こんなこと質問するほどでもないかな」と思うような些細なことでも構いません。後から見返したときに、それが意外と重要な疑問点に繋がったり、他の疑問と結びついたりすることがあります。また、質問タイムになったときに、メモを見返すことで「そういえば、ここが気になっていたんだ」と質問を思い出すきっかけにもなります。スマートフォンやPCでのメモも良いですが、手書きのメモは記憶に残りやすいというメリットもあります。自分に合った方法で、積極的にメモを取りましょう。
ステップ3:「良い質問」のハードルを下げる
前述の「完璧な質問をしようとしすぎている」という原因とも関連しますが、「良い質問をしなければ」というプレッシャーは、質問の最大の敵です。「良い質問」の定義は人それぞれですし、研修の場では「分からないことを分かるようにする」ための質問であれば、どんなものでも価値があります。初歩的な質問、確認のための質問、感想に近いような疑問でも大丈夫。「こんなこと聞いてもいいのかな?」という気持ちは一旦脇に置いて、「自分が理解を深めるために聞くんだ」というスタンスで臨みましょう。講師は、どんな質問にも真摯に答えてくれるはずです。まずは「質問すること」自体に慣れることが大切です。
ステップ4:質問の「型」を用意しておく
いざ質問しようとしても、どう言葉にすれば良いか分からず、戸惑ってしまうこともありますよね。そんな時は、あらかじめいくつかの質問の「型」を準備しておくと便利です。例えば、以下のような型が考えられます。
- 確認のための質問:「〇〇という理解でよろしいでしょうか?」
- 具体例を求める質問:「△△について、もう少し具体的な例を教えていただけますか?」
- 理由や背景を尋ねる質問:「なぜ□□のような方法が推奨されるのですか?」
- 他のケースへの応用を考える質問:「この知識は、××のような場合にはどのように応用できますか?」
- 自分の意見を述べた上で問いかける質問:「私は〇〇と考えたのですが、この点について講師のご意見を伺えますか?」
これらの型に、研修内容や自分の疑問を当てはめるだけで、スムーズに質問を組み立てることができます。最初は型を意識するだけでも、徐々に自分なりの質問の仕方が身についていくでしょう。
ステップ5:他の参加者の質問に便乗してみる
どうしても自分から最初に質問するのが難しい場合は、他の参加者の質問に耳を傾け、そこから派生する形で質問を考えてみるのも有効な手段です。「〇〇さんの質問に関連してなのですが…」や「今の回答で△△というお話がありましたが、それについてもう少し詳しく…」といった形で切り出せば、自然な流れで質問に入りやすくなります。他の人の質問を聞くことで、自分では思いつかなかった視点に気づかされたり、自分の疑問点がより明確になったりすることもあります。また、誰かが質問を始めると、場の雰囲気が和らぎ、他の人も質問しやすくなるという効果も期待できます。
それでも質問が出てこない…そんな時の対処法
色々な対策を試してみても、研修中にどうしても質問が思いつかない、あるいは質問する勇気が出ないということもあるかもしれません。そんな時でも、学びを深めるチャンスを諦める必要はありません。ここでは、研修中以外での対処法や、少し視点を変えたアプローチをご紹介します。
どうしても質問が出てこない場合の対処法は以下の通りです。
- 研修後に個別に質問する
- 研修アンケートを活用する
- 「質問のための質問」を考えてみる
研修後に個別に質問する
研修時間内に質問できなかったとしても、それで終わりではありません。多くの研修では、終了後に講師が個別の質問に応じてくれる時間が設けられていることがあります。もしそのような時間がなさそうであれば、休憩時間や研修終了後に、直接講師に声をかけてみましょう。一対一の状況であれば、他の参加者の目を気にすることなく、落ち着いて質問できるはずです。事前に質問したい内容をメモにまとめておくと、スムーズに伝えることができます。「研修中は緊張してしまって…」と正直に伝えても良いでしょう。講師も、あなたの学びたいという意欲を理解し、丁寧に対応してくれるはずです。
研修アンケートを活用する
研修の最後には、多くの場合アンケートの記入が求められます。このアンケートは、研修内容のフィードバックだけでなく、疑問点を伝えたり、追加で知りたい情報をリクエストしたりする貴重な機会でもあります。「質問」という項目がなくても、自由記述欄などを活用して、研修中に聞けなかったことや、もっと詳しく知りたかった内容を具体的に書きましょう。研修の主催者や講師が目を通し、後日回答が得られたり、次回の研修内容に反映されたりする可能性があります。直接質問する勇気がない場合でも、この方法なら自分のペースで疑問を投げかけることができます。
「質問のための質問」を考えてみる
これは少し高度なテクニックかもしれませんが、「研修内容そのもの」に対する質問ではなく、「質問すること」自体について質問してみるというアプローチです。例えば、「今日のテーマについて、他の受講者の方がどのような点に疑問を持ちやすいか、代表的な例があれば教えていただけますか?」や「この分野をこれから深く学んでいく上で、どのような視点で疑問を持つと効果的でしょうか?」といった質問です。このような質問は、直接的な疑問解決には繋がらないかもしれませんが、他の参加者の疑問点を知ることで新たな気づきを得られたり、今後の学習のヒントになったりすることがあります。また、講師にとっても、参加者の関心度合いを探る良い機会となるでしょう。
実はメリットだらけ!研修で質問することの重要性
「質問が思いつかない…」と悩む一方で、そもそもなぜ研修で質問することがそんなに大切なのでしょうか?実は、質問をすることには、あなたが思っている以上に多くのメリットが隠されています。ここでは、研修で積極的に質問することの重要性について、改めて考えてみましょう。
研修で質問することの重要性・メリットは以下の通りです。
- 理解度が格段にアップする
- 講師や他の参加者との貴重なコミュニケーション機会
- 積極的な姿勢が評価につながることも
- 他の参加者の学びにも貢献できる
理解度が格段にアップする
研修で質問をする最大のメリットは、やはり研修内容に対する理解度が飛躍的に向上することです。疑問点をそのままにしてしまうと、その後の内容が頭に入ってこなかったり、誤った解釈のまま進んでしまったりする可能性があります。質問をして講師から的確な回答を得ることで、曖昧だった部分がクリアになり、知識がより深く定着します。また、自分の言葉で質問を組み立てる過程で、頭の中が整理され、何が分かっていて何が分かっていないのかを明確に意識することができます。これは、受け身で聞いているだけでは得られない、能動的な学習効果と言えるでしょう。
講師や他の参加者との貴重なコミュニケーション機会
質問は、単に疑問を解消するだけでなく、講師や他の参加者とのコミュニケーションを深める貴重な機会でもあります。講師に質問することで、一方的な講義形式から双方向のやり取りへと変わり、よりパーソナルなアドバイスやフィードバックを得られる可能性があります。また、他の参加者の前で質問をしたり、他の人の質問に耳を傾けたりすることで、お互いの考え方や視点を知ることができます。これがきっかけで、研修後も続くような有益なネットワークが生まれることだってあるのです。特に異業種交流研修などでは、多様なバックグラウンドを持つ人々と繋がるチャンスにもなります。
積極的な姿勢が評価につながることも
研修の場で積極的に質問する姿勢は、多くの場合、学習意欲の高さや主体性のアピールとして、講師や上司、人事担当者などから好意的に受け止められます。「この人は真剣に学ぼうとしているな」「積極的に業務改善に繋げようとしているな」といった印象を与えることができるでしょう。もちろん、評価のためだけに質問をするのは本末転倒ですが、結果としてポジティブな評価に繋がる可能性があることは、覚えておいても損はありません。特に昇進や昇格がかかった選抜研修などでは、発言内容も注目されていると考えた方が良いでしょう。
他の参加者の学びにも貢献できる
あなたがした質問は、あなた自身の学びになるだけでなく、実は他の参加者の学びにも貢献している可能性があります。「聞きたいけど聞けない」「そこが疑問だったけど、うまく言葉にできなかった」と思っていた他の参加者が、あなたの質問によって「そうそう、それが聞きたかったんだ!」と助けられるケースは少なくありません。また、一つの質問から議論が発展し、より多角的な視点や深い考察が生まれることもあります。あなたの勇気ある一言が、研修全体の質を高めることに繋がるかもしれないのです。そう考えると、質問することへのハードルも少し下がるのではないでしょうか。
研修講師・運営者の方へ:質問しやすい雰囲気作りのヒント
研修参加者が「質問が思いつかない」と感じる背景には、個人の特性だけでなく、研修の進め方や場の雰囲気も影響しています。ここでは、研修を企画・運営する講師や担当者の方々が、参加者にとってより質問しやすい環境を作るためのヒントをいくつかご紹介します。
質問しやすい雰囲気作りのためのヒントは以下の通りです。
- アイスブレイクで心理的安全性を高める
- 「どんな質問でも歓迎」というメッセージを明確に伝える
- グループワークで質問のハードルを下げる
- 匿名で質問できる仕組みを導入する
アイスブレイクで心理的安全性を高める
研修の冒頭で、参加者同士の緊張をほぐし、リラックスした雰囲気を作るためのアイスブレイクは非常に重要です。自己紹介や簡単なゲームなどを通じて、お互いの顔と名前を知り、少しでも話しやすい関係性を築くことができれば、その後の質疑応答のハードルもぐっと下がります。「何を言っても大丈夫だ」と感じられる心理的安全性の高い場を作ることを意識しましょう。特にオンライン研修では、意識的にコミュニケーションの機会を設けることが求められます。
「どんな質問でも歓迎」というメッセージを明確に伝える
講師から「どんな些細なことでも、初歩的なことでも、遠慮なく質問してください」「間違った質問なんてありません」といったメッセージを、研修の冒頭や質疑応答の前に繰り返し伝えることが大切です。言葉で伝えるだけでなく、講師自身が参加者の質問に対して、常に丁寧かつ肯定的に応答する姿勢を示すことで、参加者は安心して質問できるようになります。「良い質問ですね!」といったポジティブなフィードバックも効果的です。
グループワークで質問のハードルを下げる
いきなり大人数の前で質問するのが難しいと感じる参加者もいます。そこで、数人単位のグループワークを取り入れ、まずは小さなグループ内で質問や意見を出し合う時間を作るのも有効です。グループ内で出た質問を代表者が発表する形にすれば、個人が特定されるプレッシャーも軽減されます。また、他の人の意見を聞く中で、新たな疑問が生まれることも期待できます。
匿名で質問できる仕組みを導入する
特にオンライン研修の場合や、参加人数が多い場合には、匿名で質問を投稿できるツールやシステムを導入するのも一つの手です。チャット機能やQ&Aツール、オンラインの付箋ツールなどを活用すれば、名前を出さずに気軽に質問を投げかけることができます。これにより、「こんなことを聞いたら恥ずかしい」といった心理的な障壁を取り除く効果が期待できます。集まった質問の中から、講師がピックアップして回答する形式を取ると良いでしょう。
よくある質問
ここでは、研修での質問に関するよくある疑問にお答えします。
研修で全く質問しないのはまずいですか?
必ずしも「まずい」わけではありませんが、質問をすることで得られるメリット(理解度向上、積極性のPRなど)を逃してしまう可能性はあります。もし疑問点があるのに質問しないのであれば、それは非常にもったいないことです。ただし、本当に内容を完璧に理解しており、疑問点が全くないというケースも考えられます。大切なのは、疑問を放置しないことです。質問する・しないに関わらず、主体的に学ぶ姿勢が重要です。
研修で的外れな質問をしてしまったらどうしよう?
誰でも間違うことはありますし、研修の場では「的外れ」を恐れる必要はありません。講師はプロなので、質問の意図を汲み取り、適切に軌道修正してくれるはずです。むしろ、勇気を出して質問したこと自体が評価されることもあります。もし本当に的外れだったとしても、それを笑ったり非難したりするような雰囲気の研修であれば、そちらの方が問題です。気にせず、次の機会にまた質問してみましょう。
質問する時間がない場合はどうすればいいですか?
研修の進行上、質疑応答の時間が十分に取れないこともあります。そのような場合は、休憩時間や研修終了後に個別に講師に質問する、研修アンケートに記載する、後日メールなどで問い合わせる、といった方法を検討しましょう。事前に質問したいことをメモしておくと、限られた時間でもスムーズに質問できます。
新入社員研修で質問するときの注意点は?
新入社員研修では、特に積極的に質問することが推奨されます。ただし、質問の前に自分で少し調べてみる姿勢も大切です。調べても分からないこと、研修内容で初めて聞いたことなどを中心に質問すると良いでしょう。「基本的なことかもしれませんが」と前置きをしたり、何が分からなくて質問しているのかを明確に伝えたりすると、より丁寧な印象になります。他の同期の学びにも繋がるような質問を意識できるとさらに良いでしょう。
オンライン研修で質問するコツはありますか?
オンライン研修では、対面よりも質問のタイミングが掴みにくいことがあります。チャット機能を活用して質問をテキストで送る、挙手ボタンやリアクション機能で意思表示をする、講師が質問を促したタイミングを逃さない、などがコツです。カメラをオンにしておくと、講師もあなたの表情から理解度を察しやすくなります。簡潔に、分かりやすく質問内容を伝えることを心がけましょう。
研修で質問することで評価は変わりますか?
直接的な人事評価に直結するかは企業や研修の位置づけによりますが、多くの場合、積極的な学習姿勢は好意的に受け取られます。質問の内容や質によっては、問題解決能力や論理的思考力をアピールする機会にもなり得ます。ただし、評価を意識しすぎるあまり、不自然な質問を繰り返すのは逆効果になる可能性もあるので注意が必要です。あくまでも、自身の理解を深めるための質問を心がけましょう。
質問が思いつかないのは理解度が低いから?
一概には言えません。本当に理解度が低く、何が分からないのかすら分からない状態である可能性もあれば、逆に内容をよく理解しているために疑問が浮かばないという可能性もあります。また、緊張や遠慮から質問できないケースも考えられます。大切なのは、なぜ質問が思いつかないのか、その原因を自己分析してみることです。原因が分かれば、適切な対処法も見えてきます。
研修中に他の人が質問しているのを聞いて満足してしまうのはダメ?
他の人の質問とそれに対する回答を聞くことで、自分の疑問が解消されたり、新たな学びが得られたりすることはあります。それ自体は悪いことではありません。しかし、常に受け身で満足してしまうのは、主体的な学習機会を逃しているとも言えます。他の人の質問を参考にしつつも、「自分ならどう質問するか」「さらに深掘りするとしたらどこか」といった視点を持つことで、より能動的な学びに繋げることができるでしょう。
まとめ
- 研修で質問が思いつかないのは多くの人が経験する悩み。
- 原因は「理解しすぎ」「何を聞けばいいか不明」「不安」など様々。
- 完璧な質問を目指す必要はない。
- 研修の目的を明確にすると質問が見つかりやすい。
- 小さな疑問でもメモする習慣が大切。
- 質問の「型」を用意しておくとスムーズ。
- 他の人の質問に便乗するのも有効な手段。
- 研修後に個別質問やアンケート活用も可能。
- 質問は理解度向上に不可欠。
- 質問はコミュニケーションのきっかけになる。
- 積極的な姿勢は評価にも繋がる可能性がある。
- 自分の質問が他の参加者の助けになることも。
- 講師は質問しやすい雰囲気作りを心がけるべき。
- 心理的安全性の確保が重要。
- 匿名での質問も有効な場合がある。