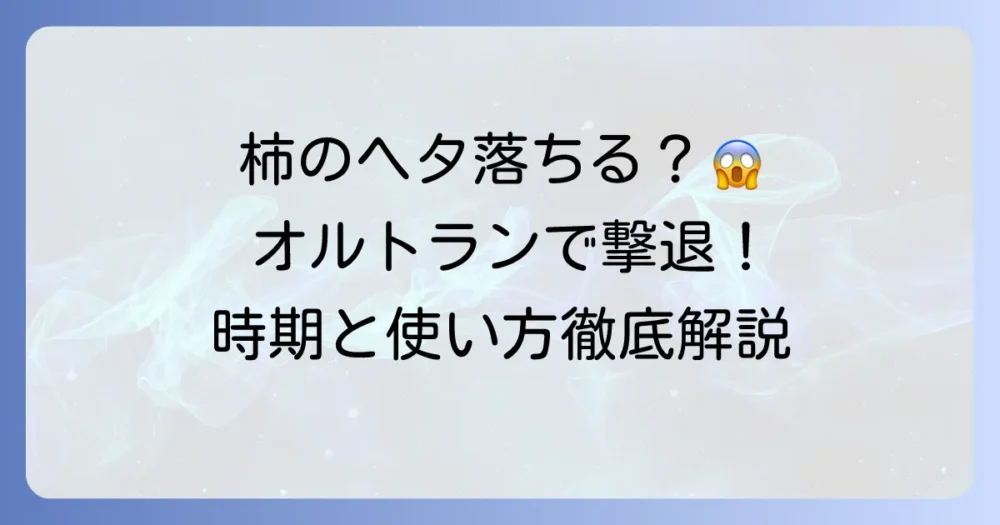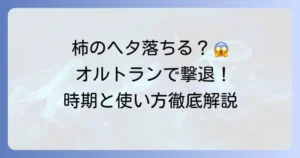大切に育てている柿の木が、害虫のせいで台無しに…なんて経験はありませんか?「実が大きくならずに落ちてしまう」「果実の表面が黒いススで汚れている」その悩み、もしかしたら害虫が原因かもしれません。特にカキノヘタムシガやカイガラムシは、柿の収穫に深刻なダメージを与える厄介な存在です。この記事では、そんな柿の害虫対策の切り札となる農薬「オルトラン」に焦点を当て、その効果的な使い方から散布時期、注意点までを詳しく解説します。正しい知識でしっかりと対策を行い、今年こそは美味しい柿をたくさん収穫しましょう!
柿栽培でオルトラン消毒が重要な理由とは?
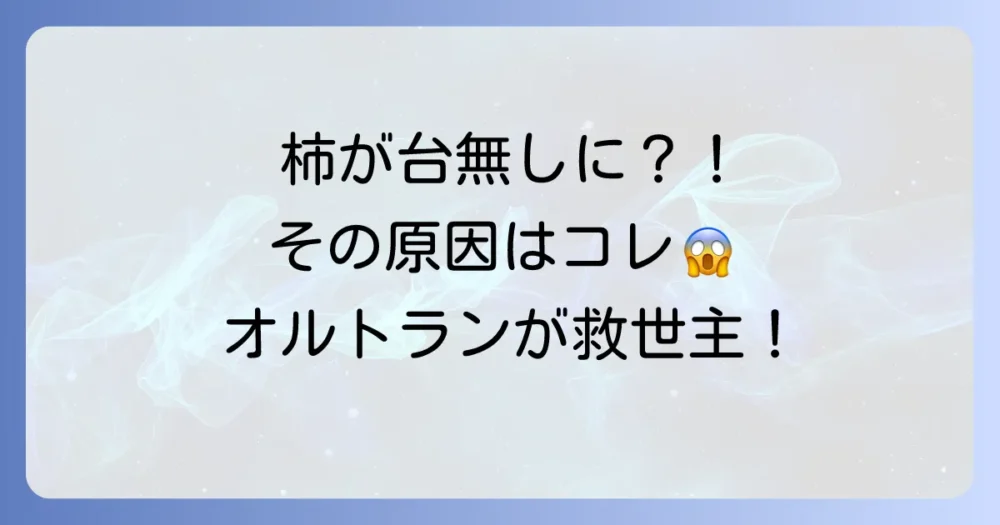
甘くて美味しい柿を収穫するためには、病害虫の防除が欠かせません。中でも殺虫剤であるオルトランを使った消毒は、多くの柿栽培農家や家庭菜園で取り入れられている重要な作業です。なぜなら、柿には収穫量や品質を著しく低下させる、手強い害虫が数多く発生するからです。ここでは、柿に発生しやすい主要な害虫と、それらが引き起こす被害について解説します。
- 放置は危険!柿に発生しやすい主要な害虫
- 害虫が引き起こす深刻な被害
放置は危険!柿に発生しやすい主要な害虫
柿の木には、年間を通してさまざまな害虫が発生します。特に注意が必要なのは以下の害虫たちです。
カキノヘタムシガ
「ヘタムシ」とも呼ばれ、柿栽培における最も厄介な害虫の一つです。 幼虫が柿のヘタから果実に侵入し、内部を食い荒らします。被害を受けた果実は、熟す前に変色し、ヘタを残してポトリと落ちてしまうのが特徴です。 年に2回発生し、特に第2世代の幼虫による被害は収穫量に大きな影響を与えます。
カイガラムシ類
樹の幹や枝、葉、果実などに寄生し、吸汁して柿の木を弱らせる害虫です。フジコナカイガラムシなどが代表的で、繁殖力が非常に高く、一度発生すると駆除が難しいのが特徴です。 びっしりと付着した姿は見た目も悪く、放置すると樹勢が衰える原因となります。
アブラムシ類
新芽や若い葉に群生し、吸汁します。大量に発生すると葉が縮れたり、生育が悪くなったりします。アブラムシの排泄物は、後述する「すす病」の原因にもなるため、早期の発見と駆除が重要です。
カメムシ類
果実が大きくなる夏から秋にかけて飛来し、口針を突き刺して果汁を吸います。 被害を受けた部分はスポンジ状になり、食味が著しく低下します。また、吸われた箇所から菌が入り、果実が腐ったり、早期に落果したりする原因にもなります。
害虫が引き起こす深刻な被害
これらの害虫を放置すると、単に虫が付くだけでは済まない、深刻な被害につながります。
実が落ちる・品質が低下する
カキノヘタムシガの食害による落果は、収穫を目前にした時期にも起こるため、栽培者の落胆は計り知れません。 また、カメムシに吸われた果実は、たとえ収穫できたとしても商品価値が大きく下がってしまいます。害虫の被害は、収穫量の減少に直結する重大な問題なのです。
すす病を誘発する
カイガラムシやアブラムシは、吸汁しながら「甘露」と呼ばれる甘い排泄物を出します。この甘露を栄養源にして繁殖するのが「すす病菌」という黒いカビです。 すす病が発生すると、果実や葉の表面が黒いススで覆われたようになり、見た目が非常に悪くなります。 光合成が妨げられて木の生育が悪くなるだけでなく、果実の商品価値も失われてしまいます。
柿の消毒に使うオルトラン|2つのタイプと特徴
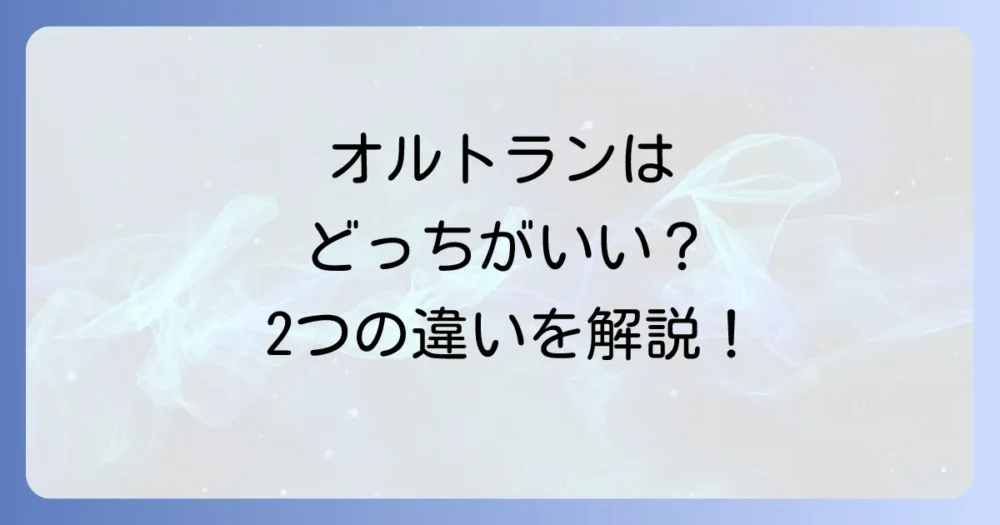
柿の害虫対策に効果的なオルトランですが、実は「水和剤」と「粒剤」という2つのタイプがあります。 それぞれに特徴があり、使用する場面や目的によって使い分けることが大切です。ここでは、それぞれのタイプの特徴と使い方を詳しく見ていきましょう。
- オルトラン水和剤の特徴と使い方
- オルトラン粒剤の特徴と使い方
オルトラン水和剤の特徴と使い方
オルトラン水和剤は、粉末状の農薬で、水に溶かして噴霧器などで散布するタイプです。
特徴
オルトランの有効成分「アセフェート」は、「浸透移行性」という優れた性質を持っています。 これは、薬剤が葉や茎から植物の内部に吸収され、その成分が植物全体に行き渡る仕組みのことです。 このため、薬剤が直接かからなかった葉の裏や、新しく出てきた葉を食べる害虫にも効果を発揮します。
また、アオムシやヨトウムシのような葉を食べる害虫(食害性害虫)から、アブラムシやアザミウマのような汁を吸う害虫(吸汁性害虫)まで、幅広い種類の害虫に効果があるのも大きな強みです。 効果の持続期間が長いのも特徴で、省力的な害虫防除が可能です。
使い方
柿に使用する場合、製品のラベルに記載されている希釈倍率を守って水で薄めます。例えば、柿のカキノヘタムシガやカイガラムシに使用する場合の希釈倍率は1500倍です。 計量スプーンなどを使って正確に測り、よくかき混ぜてから噴霧器に移して散布します。葉の表だけでなく、葉の裏や枝にもまんべんなくかかるように丁寧に散布するのがコツです。
オルトラン粒剤の特徴と使い方
オルトラン粒剤は、砂のような粒状の農薬で、植物の株元に直接まいて使用するタイプです。
特徴
粒剤の最大の特徴は、その手軽さです。水で薄める手間がなく、容器から直接パラパラとまくだけで済みます。 こちらも水和剤と同様に浸透移行性を持ち、根から吸収された有効成分が植物全体に行き渡り、効果を発揮します。
効果の持続期間が長く、一度まけば長期間害虫を防除できるため、特に家庭菜園などで手軽に害虫対策をしたい方におすすめです。 土の中にいる害虫にも効果が期待できます。
使い方
柿の木の場合、木の周囲の土に均一に散布します。製品によって使用量が定められているので、必ず確認しましょう。 散布後は、軽く土と混ぜ合わせるとより効果的です。薬剤が水に溶けて根から吸収されることで効果を発揮するため、散布後に水やりをすると良いでしょう。
ただし、農薬登録情報によると、柿の木自体に「オルトラン粒剤」の適用登録はありません(2025年7月現在)。 柿の木に使用する場合は、適用登録のある「オルトラン水和剤」を使用するのが正しい方法です。 粒剤は、野菜や花など、適用のある植物に使用しましょう。
【最重要】柿の消毒!オルトランを使う最適な時期と年間スケジュール
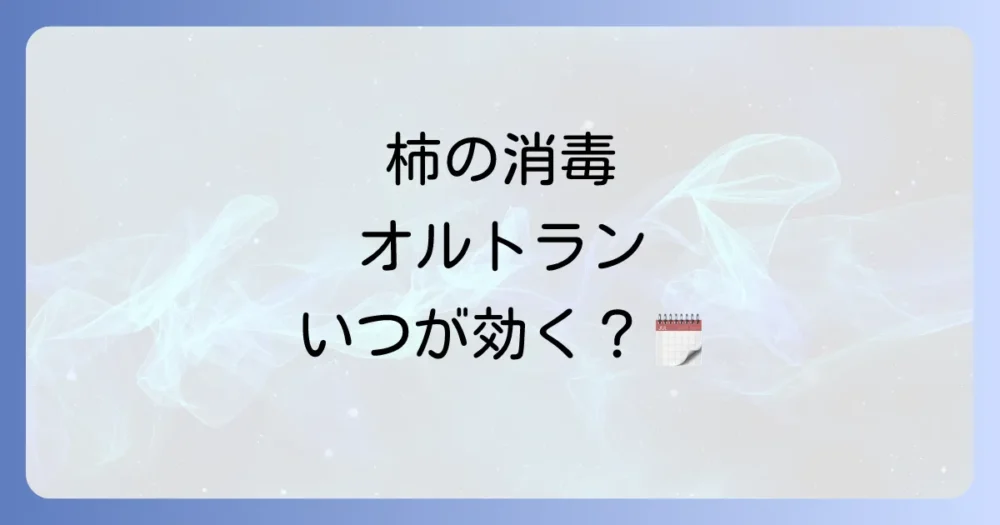
オルトランの効果を最大限に引き出すには、「いつ散布するか」というタイミングが非常に重要です。害虫が活動を始める前や、薬剤が効きやすい時期を狙って散布することで、効率的に防除できます。ここでは、害虫の種類ごとの散布タイミングと、年間の消毒スケジュールについて解説します。
- 害虫の種類別!オルトラン散布のタイミング
- ひと目でわかる!柿の年間消毒カレンダー
害虫の種類別!オルトラン散布のタイミング
防除したい害虫によって、最適な散布時期は異なります。
カキノヘタムシガ対策
カキノヘタムシガは年に2回発生します。防除の重要なタイミングもこの2回です。
- 1回目:5月下旬~6月上旬
第1世代の成虫が発生し、産卵する時期です。幼虫が果実に侵入する前に駆除することが重要です。 - 2回目:7月下旬~8月上旬
第2世代の発生時期で、この時期の被害は収穫量に大きく影響します。被害を最小限に抑えるため、この時期の防除は必須です。
幼虫がヘタに潜り込んでしまうと薬剤が届きにくくなるため、発生初期の散布が成功のコツです。
カイガラムシ対策
カイガラムシは、硬い殻で覆われた成虫には薬剤が効きにくいという特徴があります。そのため、殻を持たない幼虫が発生する時期を狙って散布するのが最も効果的です。
- 幼虫発生期:6月中旬~下旬
この時期にオルトラン水和剤を散布することで、効率よく駆除できます。カイガラムシは繁殖力が旺盛なので、このタイミングを逃さないようにしましょう。
アブラムシ対策
アブラムシは春から秋にかけて断続的に発生します。発生を見つけ次第、すぐに散布するのが基本です。特に新芽が伸びる時期は注意深く観察しましょう。
ひと目でわかる!柿の年間消毒カレンダー
柿の栽培では、オルトランだけでなく、他の殺菌剤なども含めて年間を通した防除計画を立てることが、安定した収穫への近道です。以下に、一般的な消毒スケジュールの例を表にまとめました。
| 時期 | 主な対象病害虫 | 主な使用薬剤(例) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 冬(12月~2月) | カイガラムシ類、炭疽病 | マシン油乳剤 | 粗皮削りを実施後、マシン油乳剤を散布すると越冬するカイガラムシに非常に効果的です。 |
| 発芽前(3月下旬~4月上旬) | 黒星病、カイガラムシ類 | 石灰硫黄合剤 | 越冬した病原菌や害虫の密度を減らす重要な消毒です。 |
| 5月上旬~中旬 | アザミウマ類、ケムシ類 | オルトラン水和剤など | 展葉期から開花前にかけて、吸汁性害虫の防除を行います。 |
| 5月下旬~6月上旬 | カキノヘタムシガ(第1世代)、炭疽病、落葉病 | オルトラン水和剤、殺菌剤 | 最重要防除時期の一つ。ヘタムシガの発生初期を逃さず散布します。 |
| 6月中旬~下旬 | カイガラムシ類(幼虫)、炭疽病、落葉病 | オルトラン水和剤、殺菌剤 | 薬剤の効きやすいカイガラムシの幼虫発生期がターゲットです。 |
| 7月下旬~8月上旬 | カキノヘタムシガ(第2世代)、カメムシ類 | オルトラン水和剤、他殺虫剤 | 2度目の最重要防除時期。被害が大きくなる時期なので徹底防除します。 |
| 8月中旬以降 | カメムシ類、炭疽病 | 各種殺虫剤、殺菌剤 | 収穫時期が近づくため、農薬の使用時期制限(収穫前日数)を厳守します。 |
※この表はあくまで一例です。お住まいの地域の気候や病害虫の発生状況に合わせて、JAや農業指導機関の情報を参考に調整してください。
柿の消毒でオルトランを使う際の注意点
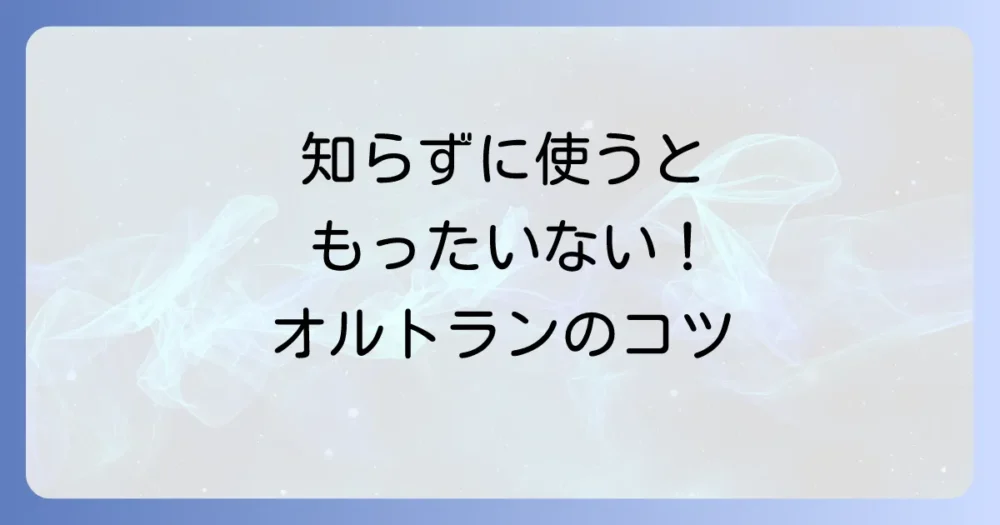
オルトランは正しく使えば非常に有効な農薬ですが、いくつかの注意点があります。安全に、そして効果的に使用するために、以下の点を必ず守ってください。
- 使用回数と収穫前日数を必ず守る
- 散布時の服装と周辺への配慮
- 他の農薬との混用について
- ミツバチなど益虫への影響
使用回数と収穫前日数を必ず守る
農薬には、作物ごとに「総使用回数」と「使用時期(収穫〇日前まで)」が定められています。これは、収穫される作物に農薬が残留しないようにするための大切なルールです。
柿の場合、オルトラン水和剤(有効成分アセフェートを含む農薬)の総使用回数は2回以内、使用時期は収穫45日前までと定められています。 これを超えて使用することはできません。例えば、カキノヘタムシガ対策で6月と8月に1回ずつ使用したら、その年のオルトラン水和剤の使用はそれで終わりです。安全な柿を収穫するために、このルールは絶対に守りましょう。
散布時の服装と周辺への配慮
農薬を散布する際は、薬剤を吸い込んだり、皮膚に付着したりしないように、適切な服装を心がけましょう。
- マスク:農薬用のマスクを着用します。
- ゴーグル:薬剤が目に入るのを防ぎます。
- 長袖・長ズボン:皮膚の露出を避けます。
- 帽子、手袋:農薬散布用のものを用意しましょう。
また、風の強い日には散布を避け、風下の人や作物、洗濯物などに薬剤がかからないように十分注意してください。近隣に家がある場合は、事前に声をかけておくとトラブルを防げます。
他の農薬との混用について
病気と害虫を同時に防除するために、殺菌剤と殺虫剤を混ぜて散布することがあります。これを「混用」といいます。オルトラン水和剤も他の農薬と混用できる場合がありますが、混ぜ合わせると化学反応を起こして効果がなくなったり、薬害が出たりする組み合わせもあります。
混用する際は、必ず使用する農薬のラベルを確認し、「混用事例表」などを参考に問題ない組み合わせかを確認してください。不明な場合は、農薬を購入した販売店やJAに問い合わせるのが確実です。
ミツバチなど益虫への影響
オルトランは、ミツバチなどの花粉交配を手伝ってくれる益虫にも影響を与える可能性があります。柿の開花時期など、ミツバチが活発に活動している時期の散布は避けるようにしましょう。
また、近くで養蜂が行われている場合は、事前に散布する旨を連絡するなど、十分な配慮が必要です。地域のルールに従い、益虫を守りながら害虫対策を行うことが大切です。
オルトランだけじゃない!柿の消毒におすすめの農薬
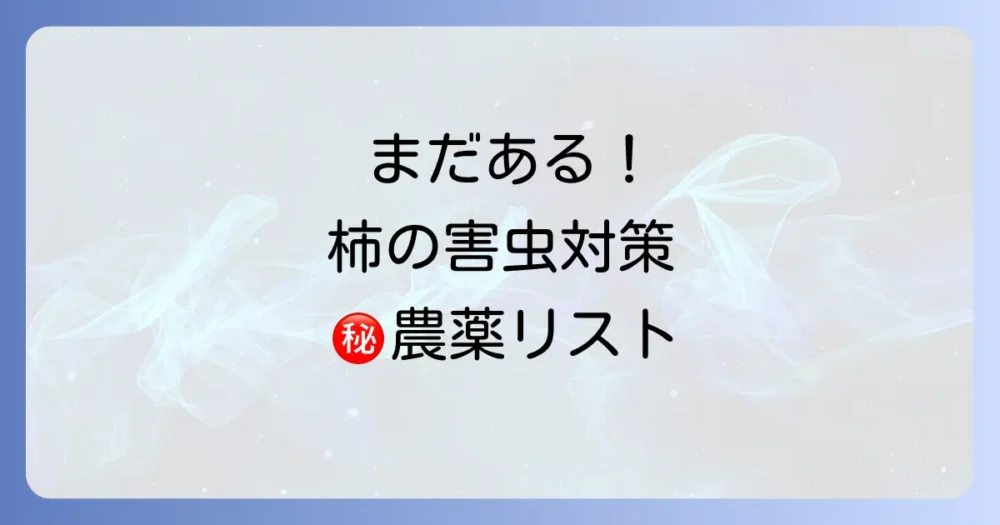
柿の害虫対策にはオルトランが非常に有効ですが、同じ薬ばかりを使い続けると、害虫がその薬に対して抵抗性を持ち、効きにくくなることがあります。 これを「薬剤抵抗性」といいます。抵抗性の発達を防ぐためには、作用性の異なる複数の薬剤をローテーションして使用することが重要です。ここでは、オルトラン以外で柿の消毒によく使われる代表的な農薬を紹介します。
- スミチオン乳剤
- モスピラン顆粒水溶剤
- マシン油乳剤 (カイガラムシ対策)
スミチオン乳剤
スミチオン乳剤は、オルトランと同じ「有機リン系」に分類される殺虫剤ですが、家庭園芸でも古くから使われている代表的な農薬の一つです。 カキノヘタムシガをはじめ、アブラムシ、ケムシ類など、非常に幅広い害虫に効果があります。
速効性があり、害虫に直接かかると高い効果を発揮します。柿では、カキノヘタムシガやハマキムシ類などに登録があり、収穫30日前まで使用可能です。 オルトランとは異なる害虫に効果を示す場合もあるため、発生している害虫の種類によって使い分けるのが良いでしょう。
モスピラン顆粒水溶剤
モスピランは「ネオニコチノイド系」という、オルトランやスミチオンとは異なる系統の殺虫剤です。 オルトランと同様に優れた浸透移行性を持ち、植物全体に効果が行き渡ります。
特にカメムシ類やアブラムシ類、カイガラムシ類に高い効果を示します。 収穫前日まで使用できるというメリットがあり、収穫期が近い時期に発生した害虫にも対応しやすいのが大きな特徴です。 作用性の異なる薬剤として、ローテーション散布の重要な選択肢となります。
マシン油乳剤 (カイガラムシ対策)
マシン油乳剤は、主に冬の休眠期に使用する特殊な薬剤です。これは殺虫成分で害虫を殺すのではなく、油の膜で越冬中のカイガラムシやハダニなどを物理的に窒息させて駆除するものです。
薬剤抵抗性が発達する心配がないため、カイガラムシの密度を効果的に下げるための基本となる防除方法です。 12月から2月頃、柿の葉が完全に落ちた後、粗皮(古い樹皮)を剥いでから散布すると、樹皮の隙間で越冬している害虫に直接作用し、非常に高い効果が期待できます。 春先の害虫発生を大きく抑制することができるため、手間はかかりますがぜひ実施したい対策です。
農薬を減らしたい方へ|無農薬・減農薬での害虫対策
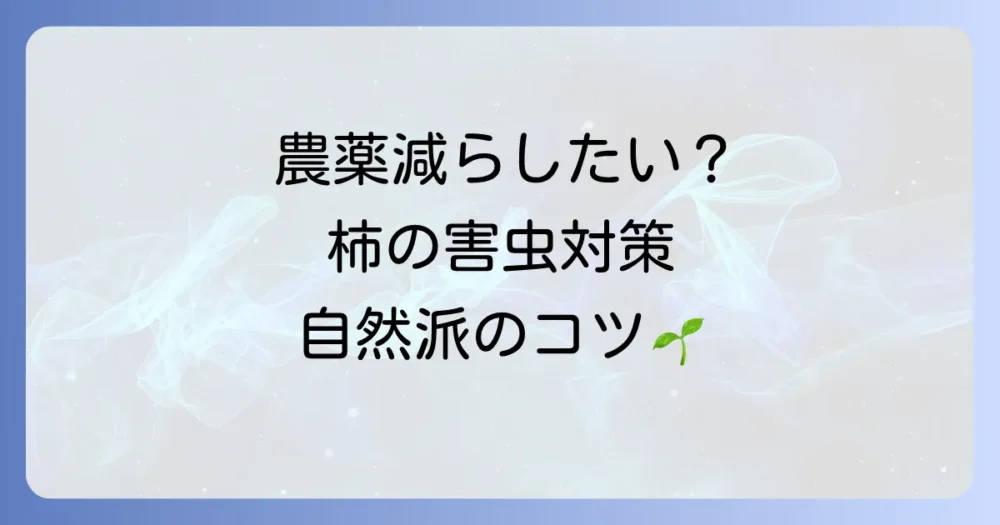
「できるだけ農薬は使いたくない」と考える方も多いでしょう。完全に無農薬で柿を栽培するのは難しい面もありますが、農薬の使用を減らすための「耕種的防除」と呼ばれる方法があります。 これらは薬剤散布と組み合わせることで、より高い防除効果を発揮します。
- 冬の作業がカギ!粗皮削りの効果
- 風通しを良くする剪定
- 益虫を活用する
冬の作業がカギ!粗皮削りの効果
冬に行う「粗皮削り」は、非常に効果的な害虫対策です。 柿の木の幹は、古くなると表面の皮がゴツゴツとめくれ上がってきます。この樹皮の隙間は、カキノヘタムシガの幼虫やカイガラムシ類、その他の病害虫にとって絶好の越冬場所となっています。
専用のヘラや鎌などを使って、この古い樹皮(粗皮)を削り落とすことで、越冬中の害虫を物理的に駆除することができます。 これにより、春先の害虫の発生源を大幅に減らすことが可能です。削り取った樹皮は、そのままにせず、集めて焼却するか、土に埋めて処分しましょう。地味な作業ですが、春以降の農薬散布の回数を減らすことにも繋がる、とても重要な作業です。
風通しを良くする剪定
柿の木の枝が混み合っていると、風通しや日当たりが悪くなります。湿気がこもりやすい環境は、炭疽病などの病気が発生しやすくなるだけでなく、害虫にとっても隠れやすい快適な住処となってしまいます。
冬に行う剪定で、不要な枝や内側に向かって伸びる枝などを切り、樹の内部まで日光と風がよく通るようにしてあげましょう。 これにより、病害虫が発生しにくい健康な木になります。また、風通しが良くなることで、農薬を散布した際に薬剤が木の隅々まで行き渡りやすくなり、消毒の効果を高めるというメリットもあります。
益虫を活用する
畑や庭には、害虫を食べてくれる「天敵」となる益虫もたくさんいます。例えば、テントウムシはアブラムシを食べてくれますし、寄生蜂は特定の害虫の卵に自分の卵を産み付けます。
農薬の中には、害虫だけでなくこれらの益虫にも影響を与えてしまうものがあります。薬剤を選ぶ際には、できるだけ天敵への影響が少ないものを選択することも、減農薬につながる一つの方法です。 また、多様な植物を植えることで、天敵が住みやすい環境を作ることも有効です。
よくある質問
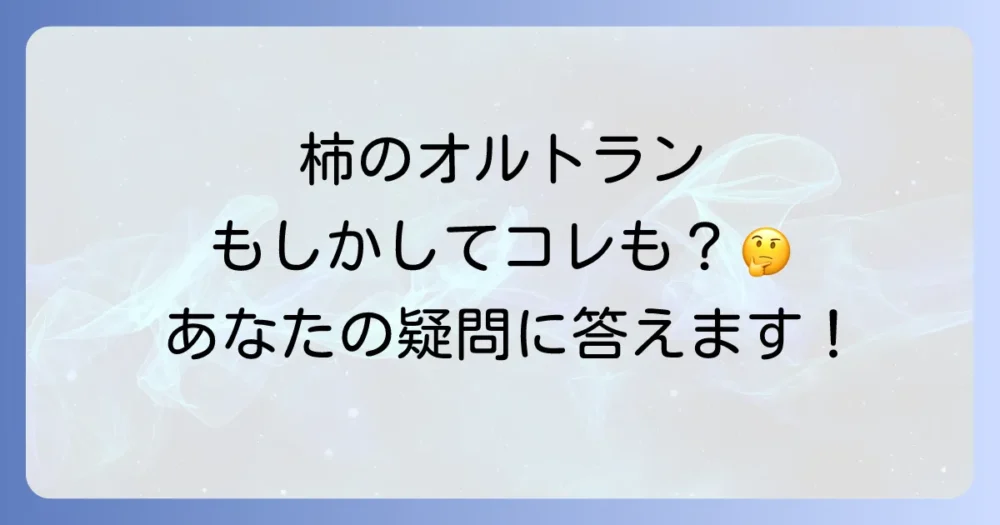
柿の実に付いた黒いすす(すす病)は食べられますか?
はい、食べても問題ありません。すす病の黒い正体はカビですが、人体に害を及ぼすものではありません。 また、すす病は果実の表面に付着しているだけなので、果実の内部まで影響することはほとんどありません。 見た目が気になる場合は、布などで拭き取ればきれいに落ちます。ただ、すす病の原因となるカイガラムシなどが付着している可能性はあるので、しっかりと洗い流してから食べるようにしましょう。
オルトランを散布した後に雨が降ったらどうなりますか?
オルトラン水和剤のような浸透移行性の薬剤は、散布後、有効成分が植物に吸収されるまでにある程度の時間が必要です。一般的に、散布後4~6時間程度は雨が降らない日を選ぶのが理想です。散布直後に強い雨が降ってしまうと、薬剤が流されてしまい、効果が十分に発揮されない可能性があります。天気予報をよく確認し、晴れ間が続く日を選んで散布しましょう。
オルトランはどこで購入できますか?
オルトラン水和剤やオルトラン粒剤は、全国のホームセンター、園芸店、農協(JA)、またはインターネット通販などで購入することができます。 使用方法や適用作物について不明な点があれば、購入時に専門の店員さんに相談することをおすすめします。
柿の消毒をしないとどうなりますか?
消毒を全くしない場合、カキノヘタムシガやカイガラムシなどの害虫の被害が深刻になる可能性が非常に高いです。 多くの実が収穫前に落果したり、すす病で果実が真っ黒になったりして、収穫量が大幅に減少、あるいは全く収穫できなくなることも考えられます。 また、害虫の多発は樹の勢いを弱らせ、翌年以降の収穫にも悪影響を及ぼします。
オルトランの毒性は大丈夫ですか?
オルトランは農薬取締法に基づき登録された農薬であり、ラベルに記載された使用方法、使用回数、使用時期を守って正しく使用すれば、安全性は確保されています。 オルトランの毒性区分は「普通物」に分類されており、これは農薬の中では比較的毒性が低いことを示しています。 しかし、農薬であることに変わりはないため、散布時の防護装備の着用や、保管場所の管理など、取り扱いには十分注意が必要です。
まとめ
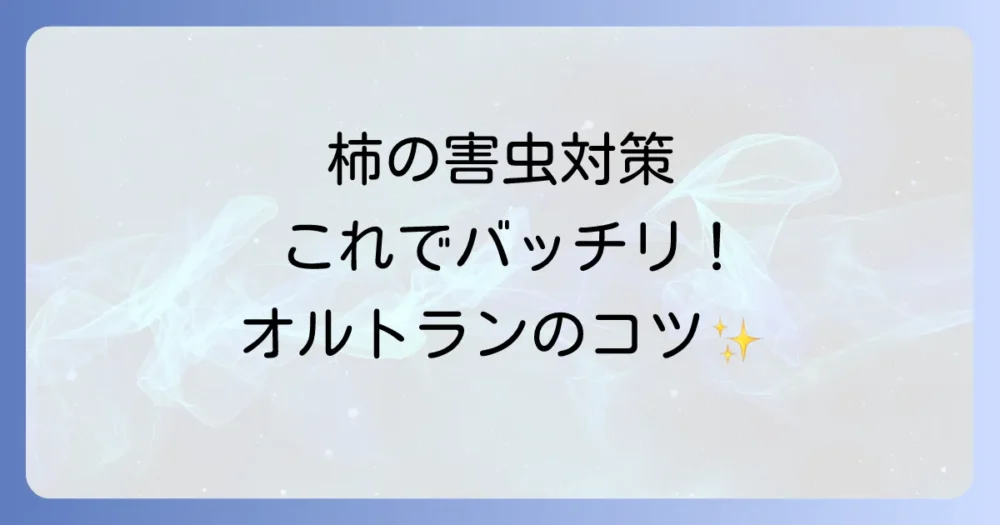
- 柿の重要害虫はカキノヘタムシガとカイガラムシ。
- 害虫被害は落果やすす病の原因となる。
- オルトランは浸透移行性で幅広い害虫に効く。
- 柿には適用のある「オルトラン水和剤」を使用する。
- カキノヘタムシガ対策は5月下旬と7月下旬が重要。
- カイガラムシ対策は幼虫が発生する6月頃が最適。
- 使用回数(年2回)と収穫前日数(45日前)を厳守する。
- 散布時はマスクやゴーグルなど防護装備を着用する。
- 薬剤抵抗性対策に他系統の農薬とローテーションする。
- スミチオンやモスピランも柿の害虫に有効な農薬。
- 冬の休眠期にはマシン油乳剤がカイガラムシに効果的。
- 無農薬・減農薬対策として冬の「粗皮削り」は必須。
- 剪定で風通しを良くすることも病害虫予防になる。
- すす病の実は拭けばきれになり食べても問題ない。
- 正しい知識で消毒し、美味しい柿の収穫を目指す。
新着記事