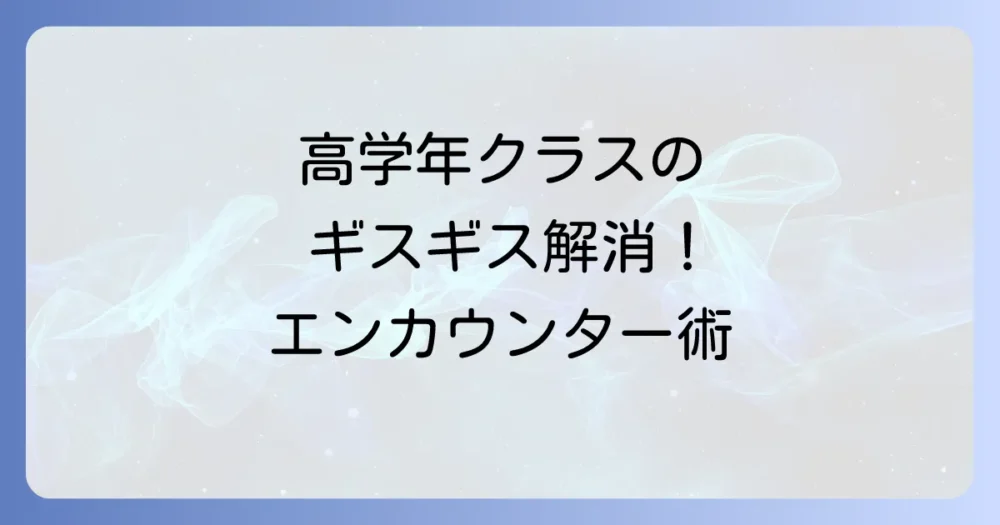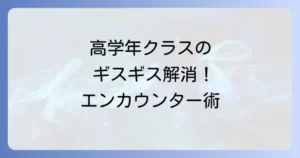小学校高学年のクラス運営、子どもたちの人間関係に悩んでいませんか?「最近クラスの雰囲気がギスギスしている…」「特定の子が孤立しがち…」そんな悩みを抱える先生は少なくないでしょう。思春期に差し掛かり、心も体も大きく変化するこの時期は、友人関係が複雑になりがちです。本記事では、そんな高学年のクラスに温かい人間関係を育む「グループエンカウンター」について、基本から具体的な実践方法までを徹底解説します。明日からの学級経営にすぐに活かせるヒントが満載です。
小学校高学年こそグループエンカウンターが重要!その理由とねらい
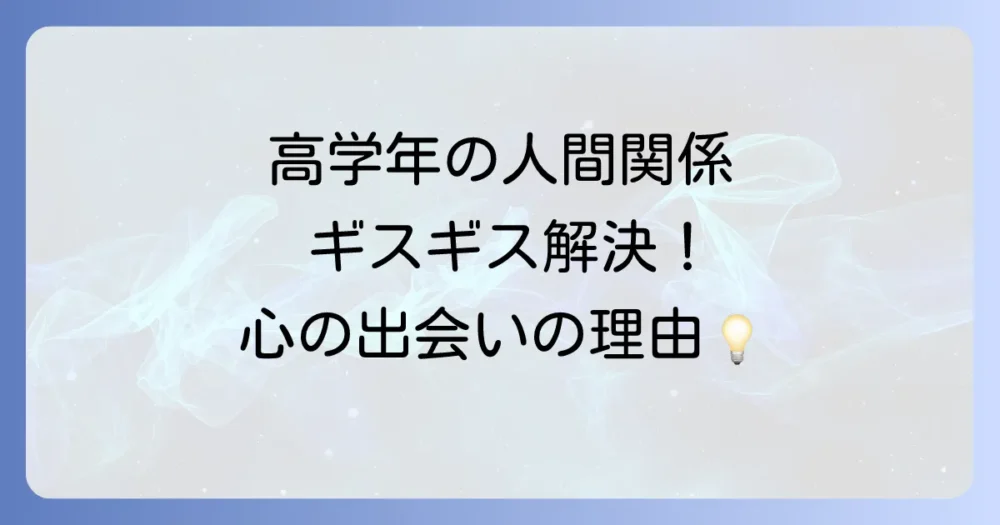
多感な時期である小学校高学年にとって、グループエンカウンターは非常に重要な活動です。仲間との関わりの中で、自分自身や他者への理解を深める貴重な機会となります。この章では、なぜ高学年にグループエンカウンターが必要なのか、その理由と具体的なねらいについて掘り下げていきます。
- そもそもグループエンカウンターとは?
- なぜ高学年に必要なのか?思春期特有の課題
- グループエンカウンターで目指す3つのねらい
そもそもグループエンカウンターとは?
グループエンカウンターとは、日本語で「出会い」を意味する言葉です。 ここでの出会いとは、単に顔を合わせるだけでなく、本音と本音で関わり合う「心と心の出会い」を指します。 参加者は、リーダー(ファシリテーター)から与えられた課題(エクササイズ)にグループで取り組み、その中で感じたことや考えたことを正直に分かち合います(シェアリング)。
この一連の体験を通して、普段は見せない自分の一面を表現したり(自己開示)、他者の意外な一面を知ったりすることで、自分自身や他者への理解を深めていくことを目的としています。 もともとはカウンセリングの技法として開発されましたが、現在では教育現場、特に学級経営や人間関係づくりのための予防的なアプローチとして広く活用されています。
特に、あらかじめエクササイズやルールが決められている「構成的グループエンカウンター(SGE)」は、学校現場でも取り入れやすく、短時間で効果的に実施できるのが特徴です。
なぜ高学年に必要なのか?思春期特有の課題
小学校高学年(9歳〜12歳頃)は、心身ともに子どもから大人へと移行する「思春期」の入り口にあたる非常にデリケートな時期です。この時期の子どもたちには、特有の課題が見られます。
まず、抽象的な思考ができるようになり、他者の視点を意識し始める一方で、自己中心的な考え方から抜け出せない部分も残っています。 そのため、友人関係において「自分はどう見られているか」を過剰に気にするようになります。 また、仲間意識が強まり、特定のグループを形成するようになりますが、その反面、閉鎖的で排他的な集団になりやすいという側面も持っています。 これがいわゆる「ギャングエイジ」と呼ばれる特徴です。
このような発達段階にある高学年の子どもたちは、友人との些細なすれ違いや思い込みから、仲間外れや陰口といったトラブルに発展しやすく、人間関係に悩みやすい傾向があります。 グループエンカウンターは、こうした思春期特有の課題を乗り越え、健全な人間関係を築くためのスキルを体験的に学ぶ絶好の機会となるのです。
グループエンカウンターで目指す3つのねらい
小学校高学年でグループエンカウンターを実施する際には、主に以下の3つのねらいが設定されます。これらは相互に関連し合っており、子どもたちの心の成長を多角的に支えます。
- 自己理解と他者理解の深化
エクササイズを通して自分の気持ちや考えを表現し、また友人のそれを受け止める体験は、「自分はこんなことを感じるんだ」「あの子はこんなことを考えていたんだ」という新たな発見につながります。 これは、自分自身を客観的に見つめる「自己理解」と、他者の多様な価値観を認める「他者理解」を深める上で非常に重要です。 - コミュニケーション能力の育成
グループエンカウンターでは、「話す」ことだけでなく、「聴く」ことも重視されます。友人の話を最後まで真剣に聴き、その気持ちを受け止めるという体験は、円滑なコミュニケーションの基礎となります。自分の意見を適切に主張する力(自己主張)と、相手の意見を尊重する力の両方をバランスよく育むことができます。 - 自己肯定感と所属感の向上
グループの中で自分の意見が受け入れられたり、ありのままの自分を認めてもらえたりする体験は、子どもたちの自己肯定感を高めます。 「このクラスにいていいんだ」「自分は大切な存在なんだ」という安心感や所属感は、いじめや不登校の未然防止にもつながり、子どもたちが安心して学校生活を送るための土台となります。
【明日からできる】小学校高学年向けグループエンカウンターの進め方
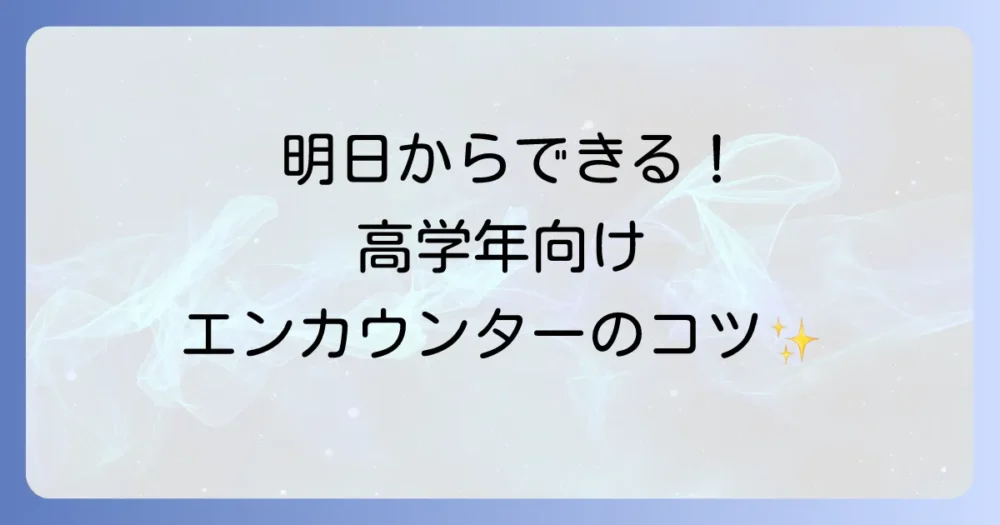
グループエンカウンターの重要性は分かったけれど、実際にどう進めればいいのか不安に思う先生もいるかもしれません。しかし、ポイントさえ押さえれば、誰でも効果的に実施することができます。この章では、具体的な進め方のステップや、進行役の心構えについて解説します。
- 失敗しないための3つのステップ
- ファシリテーター(進行役)の重要な役割と心構え
- 子どもたちが安心できる「3つの約束」
失敗しないための3つのステップ
構成的グループエンカウンターは、基本的に「ウォーミングアップ」「エクササイズ(本活動)」「シェアリング(分かち合い)」という3つのステップで構成されています。 この流れを意識することで、子どもたちの心の扉を自然に開き、深い学びに繋げることができます。
- ウォーミングアップ(導入)
まずは、心と体の緊張をほぐすための準備運動です。簡単なゲームやアイスブレイクを取り入れ、クラス全体の雰囲気を和ませることを目的とします。 例えば、簡単なジャンケンゲームや、後ほど紹介する「聖徳太子ゲーム」のような、誰もが楽しめる活動がおすすめです。 この段階で、子どもたちが「なんだか楽しそう」と感じられるような雰囲気を作ることが、その後の活動をスムーズに進めるコツです。 - エクササイズ(本活動)
ウォーミングアップで場が温まったら、いよいよ本日のメイン活動であるエクササイズに移ります。エクササイズは、「自己理解」「他者理解」「信頼体験」など、その日のねらいに沿ったものを選びます。 リーダーは、活動のルールや目的を、明確かつ簡潔に説明することが非常に重要です(インストラクション)。 必要であれば、教師自身が手本を見せる(モデリング)ことで、子どもたちは安心して活動に取り組むことができます。 - シェアリング(分かち合い)
エクササイズが終わったら、活動を通して感じたことや気づいたことをグループや全体で共有する「シェアリング」の時間を設けます。 ここでの目的は、感想を発表させることではなく、本音の気持ちを交流させることにあります。 「〇〇さんの意見を聞いて、自分はこう感じたよ」といったように、互いの気持ちを伝え合うことで、体験がより深い学びに変わります。この時間が、グループエンカウンターの最も重要な部分と言っても過言ではありません。
ファシリテーター(進行役)の重要な役割と心構え
グループエンカウンターの成否は、リーダーであるファシリテーターの役割にかかっていると言っても良いでしょう。しかし、特別なカウンセリングの技術が必要なわけではありません。大切なのは、子どもたち一人ひとりに寄り添う心構えです。
まず、教師自身が「一人の参加者」として楽しむ姿勢を見せることが大切です。 教師が心を開き、自己開示をすることで、子どもたちも安心して自分を表現しやすくなります。 例えば、エクササイズの説明をする際に、教師自身の体験談を少し話すだけでも、場の雰囲気は大きく変わります。
また、子どもたちの発言を評価したり、結論を急いだりしないことも重要です。たとえ沈黙が流れても、それは子どもたちが自分の内面と向き合っている大切な時間かもしれません。「どんな意見も、どんな気持ちも、ここでは受け入れられる」という安全な場を保障することが、ファシリテーターの最も重要な役割です。 子どもたちの自由な発想や感情の表出を温かく見守り、時にはそっと背中を押してあげるような存在を目指しましょう。
子どもたちが安心できる「3つの約束」
グループエンカウンターを始める前には、子どもたちが安心して活動に取り組めるように、いくつかの基本的なルールを全員で確認することが不可欠です。特に以下の「3つの約束」は、本音の交流を守るための土台となります。
- 人の話を最後まで聴く
友だちが話している途中で、茶化したり、否定したり、自分の話をかぶせたりしないことを約束します。 相手の話に真剣に耳を傾ける姿勢が、信頼関係の第一歩です。 - ここで聴いた話は、他の場所で言わない(守秘義務)
この場で話された個人的な内容や本音は、このグループだけの秘密にします。 「ここでなら安心して話せる」という信頼感が、正直な自己開示を促します。 - 話したくないことは話さなくてもいい(パスする権利)
どうしても言いたくないことや、参加したくない活動がある場合は、無理に参加する必要はありません。 自分の気持ちを大切にすることも、重要な学びの一つです。
これらの約束事を、活動の最初に全員で声に出して確認することで、クラス全体に心理的な安全性が生まれ、より質の高いエンカウンター体験へとつながっていきます。
【場面別】すぐに使える!小学校高学年向けグループエンカウンターゲーム・活動例10選
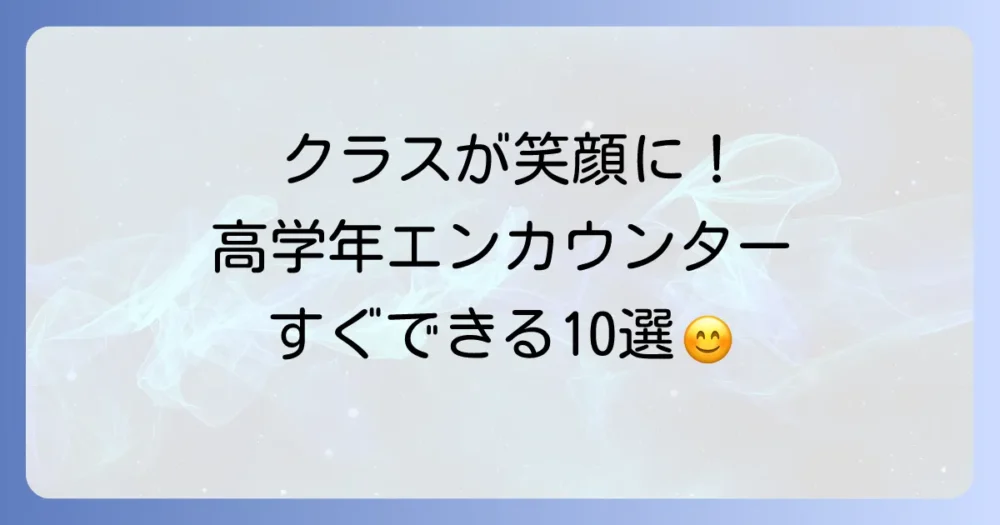
理論や進め方がわかったところで、次は具体的な活動例を見ていきましょう。ここでは、小学校高学年の子どもたちが楽しみながら取り組めるゲームやエクササイズを、「アイスブレイク」「相互理解」「協力」の3つの場面に分けて10個紹介します。準備物も少なく、明日からの学級活動で気軽に取り入れられるものばかりです。
- アイスブレイクに最適!簡単なゲーム
- 互いを深く知るための活動
- 協力して課題解決するゲーム
アイスブレイクに最適!簡単なゲーム
まずは、活動の導入や、少し雰囲気が硬い時に使える簡単なゲームです。心と体をほぐし、自然な笑顔を引き出すことを目的とします。
- 聖徳太子ゲーム
数人のグループで、お題の単語を一文字ずつ同時に発声し、他のグループがそれを当てるゲームです。 例えば「ランドセル」なら、「ラ」「ン」「ド」「セ」「ル」と5人が同時に言います。聴き取る側は集中力が必要で、言う側は協力が不可欠。一体感が生まれやすく、盛り上がること間違いなしです。 - ひたすらジャンケン
教室を自由に歩き回り、出会った人とひたすらジャンケンをします。 勝っても負けてもOK。あいこになったら自己紹介をして握手(またはハイタッチ)をして別れ、また新しい相手を探します。たくさんの友達と短時間で関わることができ、クラス全体の壁を取り払うのに効果的です。 - この指とまれ
リーダーが出すお題(例:「朝ごはんがパンだった人」「好きな教科が同じ人」)に当てはまる人が集まるゲームです。 自分と同じ仲間を見つけることで親近感が湧き、自然なグループ作りができます。お題を工夫することで、子どもたちの意外な共通点が見つかるかもしれません。
互いを深く知るための活動
次に、お互いの内面や価値観に少しだけ触れる活動です。自己開示と他者理解を促し、関係を深めることを目指します。
- 探偵ごっこ(サイン集め)
「飛行機に乗ったことがある」「ペットを飼っている」といった質問が書かれた紙を持ち、該当する友達を探してサインをもらいます。 ルールは、一人からは一つのサインしかもらえないこと。ゲーム感覚で、普段あまり話さない友達とも話すきっかけが生まれます。 - 私はわたしが好きです、なぜならば
グループで輪になり、「私はわたしが好きです。なぜならば、〇〇だからです」と順番に発表していくエクササイズです。 自分の長所や好きなところを言葉にすることで、自己肯定感を高めます。友人の発表を聞くことで、他者の良いところを見つける視点も養われます。 - 四つの部屋
「もし旅行に行くなら? A:海 B:山 C:都会 D:温泉」といった四択のお題を出し、子どもたちは自分の答えに最も近いと思う部屋(教室の四隅)に移動します。 同じ部屋に集まったメンバーで、なぜそれを選んだのか理由を話し合います。価値観の違いや共通点に気づくことができます。 - ブラインドウォーク
二人一組になり、一人が目隠しをし、もう一人が言葉の指示だけで誘導して歩きます。目隠しをする側は相手を信頼する気持ちが、誘導する側は相手への責任感や思いやりが育ちます。言葉を使わない信頼体験ができる、少し高度なエクササイズです。
協力して課題解決するゲーム
最後に、グループで力を合わせなければ達成できない課題に挑戦する活動です。協力することの大切さや、集団で成し遂げる喜びを体験します。
- 伝言リレーゲーム
グループで一列になり、先頭の人から最後の人まで、お題の文章を伝言していきます。 簡単なようで意外と難しく、正確に伝えようとする責任感や、チームワークが試されます。最後には、元の文章とどれだけ違ってしまったかで大いに盛り上がります。 - ペーパータワー
限られた枚数の紙(例:A4用紙20枚)だけを使って、グループで協力し、できるだけ高いタワーを作るゲームです。作戦会議や役割分担が成功の鍵。試行錯誤する中で、自然とコミュニケーションが活発になります。 - 人間知恵の輪
グループ全員で輪になって手をつなぎ、そこから一度も手を離さずに、絡まった腕をほどいて全員が外側を向いたきれいな一つの輪に戻すゲームです。全員の協力が不可欠で、達成感は格別です。身体的な接触を通して、心の距離もぐっと縮まります。
グループエンカウンターを成功させるための注意点とコツ
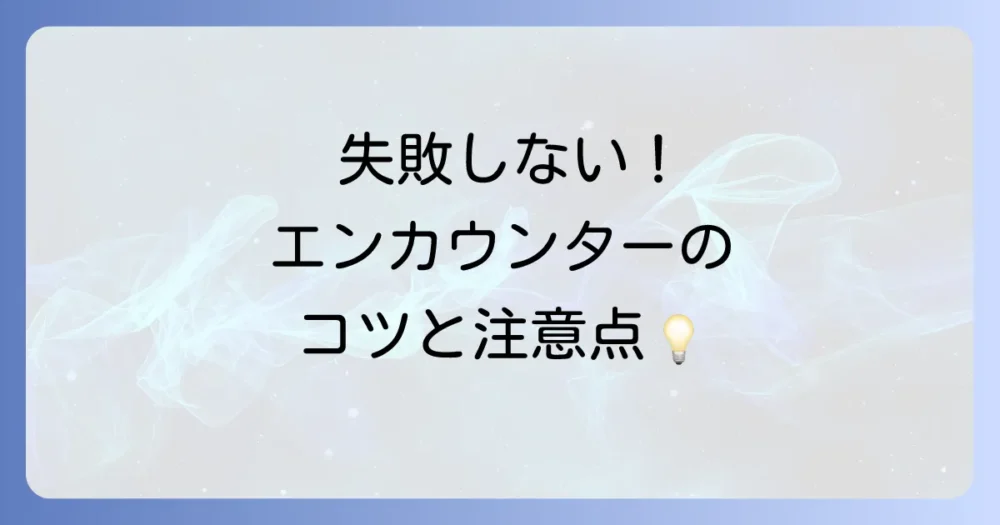
グループエンカウンターは、子どもたちの心を育む強力なツールですが、その一方で、やり方を間違えると逆効果になってしまう可能性も秘めています。子どもたち一人ひとりが安心して参加し、実りある体験にするためには、いくつかの注意点とコツがあります。ここでは、特に重要なポイントを解説します。
- 無理強いは絶対にNG!参加しない子への配慮
- 「沈黙」も大切な時間
- ネガティブな意見が出たときの対応
- 時間配分と場所の確保
無理強いは絶対にNG!参加しない子への配慮
最も重要なことは、いかなる活動も無理強いしないということです。 グループエンカウンターの基本ルールの一つに「パスする権利」があるように、話したくないこと、参加したくない活動がある子どもには、その気持ちを尊重し、見学することを認めましょう。
特に、自己肯定感が低かったり、人前で話すのが苦手だったりする子どもにとって、無理に参加させられることは大きな苦痛となり、かえって心を閉ざす原因になりかねません。 大切なのは、「参加しない」という選択も認めることで、その子にとっての「安全」を保障することです。見学しているだけでも、場の雰囲気を感じたり、友人の様子を見たりすることで、その子なりに何かを感じ取っているかもしれません。教師は、「どうして参加しないの?」と問い詰めるのではなく、「いつでも参加していいんだよ」という温かい眼差しで見守る姿勢が求められます。
「沈黙」も大切な時間
シェアリングの時間などで、誰も発言せずにシーンと静まり返ってしまう「沈黙」。進行役の教師にとっては、焦りや不安を感じる瞬間かもしれません。しかし、この沈黙を恐れる必要はありません。
子どもたちにとって沈黙は、エクササイズでの体験を振り返り、自分の気持ちを整理している大切な時間です。また、誰かが勇気を出して話し出すのを待っている時間でもあります。教師が焦って「誰か意見はありませんか?」と何度も促したり、特定の生徒を指名したりすると、子どもたちは「何か言わなければいけない」というプレッシャーを感じ、本音を話しにくくなってしまいます。
沈黙が訪れたら、教師も一緒にその時間を味わうくらいの余裕を持ちましょう。「沈黙も、大切なコミュニケーションの一つ」と捉え、子どもたちが自分の内面と向き合う時間をじっくりと待ってあげることが、結果的に深い気づきにつながるのです。
ネガティブな意見が出たときの対応
シェアリングでは、時には「つまらなかった」「〇〇さんの意見はよく分からなかった」といったネガティブな意見や、他者への批判的な意見が出てくることもあります。このような発言が出ると、場の雰囲気が悪くなるのではないかと心配になるかもしれません。
しかし、こうしたネガティブな意見も、その子が感じた正直な「本音」です。これを否定したり、無理にポジティブな意見に言い換えさせたりしてはいけません。大切なのは、まずその意見を「一つの正直な気持ち」として受け止めることです。「そう感じたんだね。どうしてそう思ったのか、もう少し教えてくれる?」と、その気持ちの背景にあるものを丁寧に尋ねてみましょう。
また、他の子どもたちにも「今の意見を聞いて、どう感じたかな?」と問いかけることで、多様な視点からの対話が生まれます。ネガティブな意見をタブー視せず、クラス全体で考えるきっかけとして活かすことができれば、それは人間関係をより成熟させるための貴重な学びとなるでしょう。
時間配分と場所の確保
グループエンカウンターを効果的に行うためには、物理的な環境設定も重要です。まず、時間配分ですが、通常の45分(または50分)授業の中で行う場合、各ステップの時間をあらかじめ計画しておくことが大切です。 特に、最も重要なシェアリングの時間が尻切れトンボにならないよう、十分な時間を確保しましょう。 目安として、ウォーミングアップ5分、エクササイズ20分、シェアリング15分、まとめ5分といった形が考えられます。
場所については、机や椅子を動かして、子どもたちが自由に動き回れるスペースを確保できるのが理想です。 教室が狭い場合は、体育館や多目的室などを活用するのも良いでしょう。また、子どもたちが輪になって座れるようにするなど、全員の顔が見えるレイアウトを工夫することも、コミュニケーションを促進する上で効果的です。
よくある質問
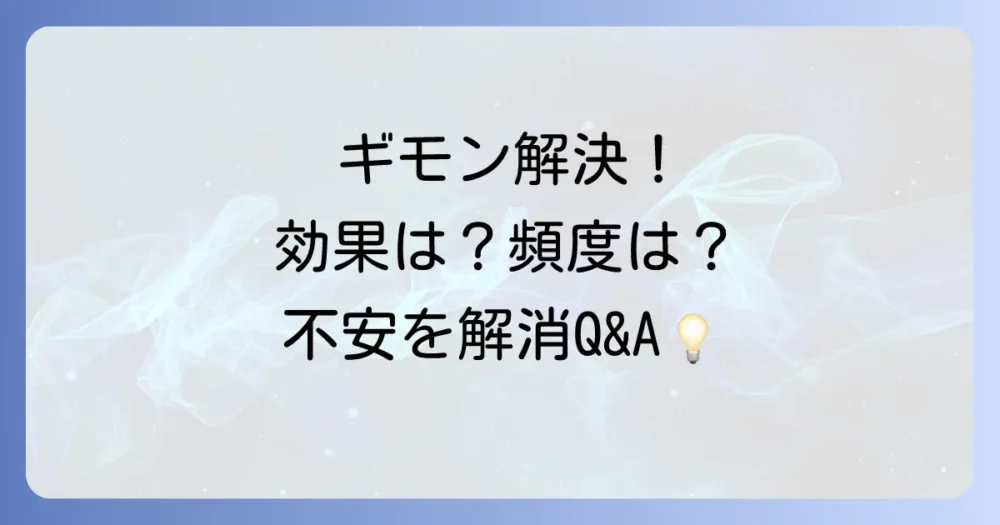
ここでは、グループエンカウンターに関して、先生方からよく寄せられる質問にお答えします。効果やネガティブな反応への対処法など、実践する上での疑問や不安を解消していきましょう。
グループエンカウンターに効果はあるの?
はい、多くの研究や実践報告でその効果が示されています。 継続的に実施することで、子どもたちの自己肯定感や他者への受容的な態度が高まることが報告されています。 また、クラスの雰囲気が温かくなり、いじめや不登校といった問題の予防・改善にもつながるとされています。 具体的には、以下のような効果が期待できます。
- 人間関係の円滑化: 互いを理解し、尊重する態度が育ち、友人関係のトラブルが減少します。
- 自己肯定感の向上: ありのままの自分を受け入れてもらえる体験を通して、自分に自信が持てるようになります。
- 学級の雰囲気の改善: 安心・安全な雰囲気が生まれ、誰もが居心地の良さを感じるクラスになります。
- 学習意欲の向上: 良好な人間関係は、協力して学ぶ活動(協働学習)の土台となり、学習効果を高めることにもつながります。
ただし、一度や二度実施しただけで劇的な変化が起こるわけではありません。大切なのは、継続的に、そして学級経営全体の中に位置づけて取り組むことです。
「気持ち悪い」「意味ない」と感じる子がいる場合はどうすればいい?
グループエンカウンターに対して、一部の子どもが「気持ち悪い」「わざとらしい」「意味ない」といった否定的な感情を抱くことは、残念ながらあり得ます。 特に、思春期に入り、他者の目を意識し始める高学年の子どもたちにとっては、本音を話すことへの抵抗感や羞恥心が強い場合があります。
このような反応があった場合、まず大切なのは、その子の気持ちを否定せずに受け止めることです。「そう感じるんだね」と一度受け入れた上で、なぜそう感じるのかを個別にじっくり聴いてみることが重要です。もしかしたら、過去の経験からくる不信感や、自己開示への強い不安があるのかもしれません。
対処法としては、以下のような点が考えられます。
- 無理強いしない: 前述の通り、参加しない権利を保障し、見学を認めます。
- 活動のレベルを下げる: 最初はゲーム性の高い、身体を動かす活動から始めるなど、抵抗感の少ないエクササイズを選びます。
- 教師の自己開示: 教師自身が自分の弱さや失敗談を話すことで、子どもたちが心を開くきっかけを作ります。
エンカウンターは、全員が同じように楽しむことを強制するものではありません。一人ひとりの心の状態に寄り添い、その子なりのペースを尊重することが、結果的にクラス全体の信頼関係を築くことにつながります。
どのくらいの頻度で行うのが効果的?
効果的な実施頻度に絶対的な正解はありませんが、単発で終わらせるのではなく、計画的・継続的に行うことが重要です。
例えば、学期始めや長期休暇明けなど、クラスの雰囲気をリフレッシュしたいタイミングで集中的に行うのも一つの方法です。また、週に1回、朝の会や帰りの会の短い時間を使って「ミニ・エクササイズ」を継続的に行うことも非常に効果的です。
大切なのは、「特別なイベント」としてではなく、「日常的な活動」として学級経営の中に位置づけることです。例えば、道徳の授業や特別活動の時間と関連付けて実施することで、より自然な形で取り入れることができます。 クラスの実態や子どもたちの様子を見ながら、無理のない範囲で継続できる計画を立てましょう。
準備するものはありますか?
紹介したゲームの多くは、特別な準備物なしで実施できます。しかし、活動によっては以下のようなものがあると、よりスムーズで効果的な運営ができます。
- ワークシート: 「探偵ごっこ」の質問リストや、シェアリングの前に自分の気持ちを整理するための振り返りシートなど。
- 筆記用具: ワークシートに記入するために必要です。
- タイマーやストップウォッチ: 時間管理に役立ちます。
- 小道具: 「ペーパータワー」で使う紙や、「ブラインドウォーク」で使う目隠しなど、エクササイズに応じたもの。
最も大切な準備物は、子どもたちが安心して活動できる「安全な場」と、教師自身の「開かれた心」と言えるでしょう。
オンラインでも実施できますか?
はい、工夫次第でオンラインでも実施可能です。 臨時休校やICTの活用が進む中で、オンラインでのグループエンカウンターの需要も高まっています。
オンラインで実施する場合のポイントは以下の通りです。
- ツールの活用: ビデオ会議システムのブレイクアウトルーム機能を使えば、小グループでの活動が可能です。チャット機能やホワイトボード機能も有効活用できます。
- 非言語的コミュニケーションの工夫: 表情が伝わりにくい分、リアクションボタンやジェスチャーを積極的に使うよう促します。
- 活動内容の選定: 「四つの部屋」は投票機能で代用できますし、「私はわたしが好きです」のような言語的なエクササイズはオンラインに向いています。
対面での活動とは異なる難しさもありますが、物理的に離れていても心のつながりを作る上で、オンラインでのエンカウンターは有効な手段の一つです。
まとめ
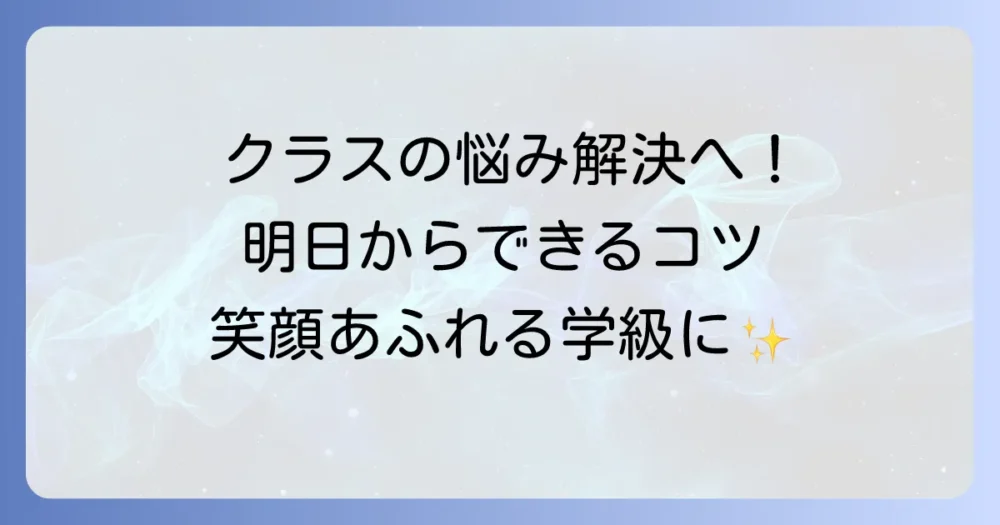
- グループエンカウンターは本音で関わり合う「心と心の出会い」です。
- 思春期特有の課題を抱える小学校高学年に特に重要です。
- 自己理解、他者理解、コミュニケーション能力の育成が主なねらいです。
- 進め方は「ウォーミングアップ」「エクササイズ」「シェアリング」の3ステップです。
- 進行役は子どもが安心できる場作りを心がけることが大切です。
- 活動前には「話を聴く」「秘密を守る」「パスする権利」の約束を確認します。
- 「聖徳太子ゲーム」は協力と一体感を育むのにおすすめです。
- 「探偵ごっこ」は普段話さない友達と関わるきっかけになります。
- 「私はわたしが好きです」は自己肯定感を高めるエクササイズです。
- 活動を無理強いせず、参加しない子の気持ちも尊重することが重要です。
- シェアリングでの「沈黙」は、子どもが考えるための大切な時間です。
- ネガティブな意見も正直な気持ちとして受け止め、対話のきっかけにします。
- 継続的に実施することで、より高い効果が期待できます。
- 一部の子が否定的な反応を示しても、その気持ちを受け止め個別に対応します。
- 工夫次第でオンラインでも実施可能で、心のつながりを育めます。
新着記事