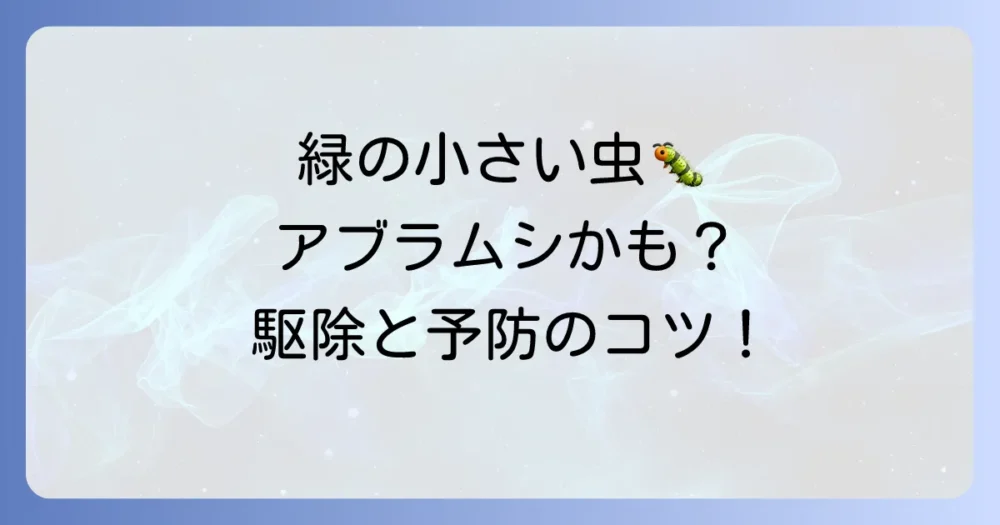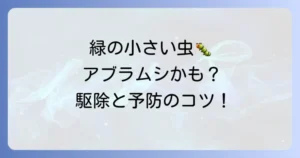大切に育てている家庭菜園の野菜や、ベランダの美しい花々に、いつの間にかびっしりと付いている緑色の小さい虫…。その光景に、思わずゾッとしてしまった経験はありませんか?その虫の正体、もしかしたら「アブラムシ」かもしれません。アブラムシは非常に繁殖力が高く、放置しておくとあっという間に増えて、植物を弱らせてしまう厄介な害虫です。でも、ご安心ください。本記事では、アブラムシの正体から、なぜ大量発生するのかという原因、そして誰でも簡単にできる駆除方法と今後の発生を防ぐための予防策まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、もう緑の小さい虫に悩まされることはありません。
その緑の小さい虫、アブラムシかもしれません
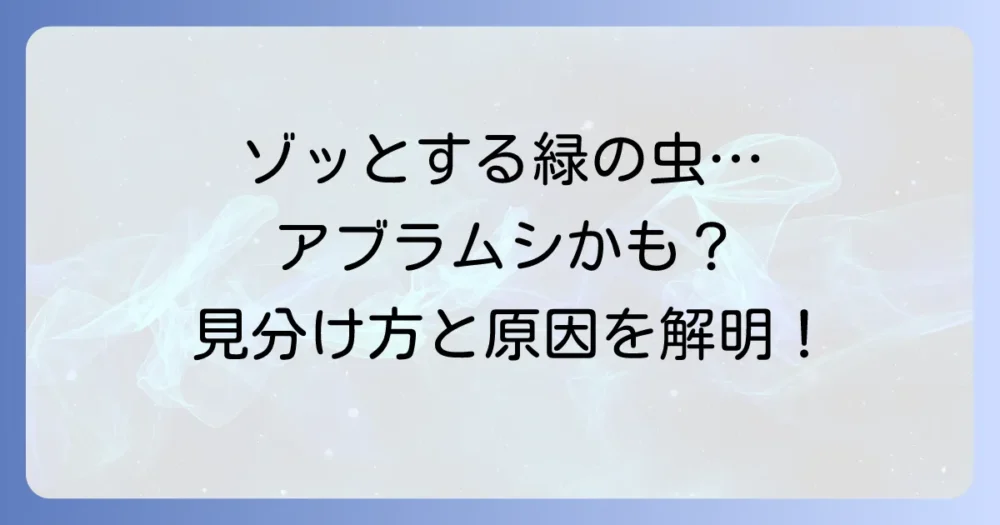
植物に群がる小さな緑色の虫を見つけたら、それはアブラムシである可能性が非常に高いです。まずは敵の正体を知ることから始めましょう。ここでは、アブラムシの基本的な情報について解説します。
- アブラムシの見た目の特徴と種類
- アブラムシが発生しやすい時期と場所
- なぜ?アブラムシが大量発生する原因
これらの情報を知ることで、より効果的な対策を立てることができます。
アブラムシの見た目の特徴と種類
アブラムシは、カメムシ目に属する昆虫で、体長は2mmから4mm程度の非常に小さな虫です。 体の色は一般的に緑色をイメージする方が多いですが、実は黒色、黄色、赤色、茶色など様々な種類が存在します。 日本国内だけでも700種類以上が確認されており、多くの種類は特定の植物に寄生する性質を持っています。 体は柔らかく、植物の汁を吸うための針のような口を持っています。 ほとんどのアブラムシには翅がありませんが、密集してきたり、環境が悪化したりすると、翅の生えた「有翅型(ゆうしがた)」が現れ、他の植物へと飛んで移動し、被害を拡大させます。
代表的なアブラムシには、多くの植物に寄生するモモアカアブラムシやワタアブラムシなどがいます。 自分の家の植物についている虫が何の種類かまで特定する必要はありませんが、「緑色以外のアブラムシもいる」ということを覚えておくと、早期発見に繋がります。
アブラムシが発生しやすい時期と場所
アブラムシは、春(4月~6月)と秋(9月~10月)の過ごしやすい気候の時期に特に活発に活動し、大量発生しやすくなります。 真夏や真冬は活動が鈍りますが、暖かい地域や温室などの室内では一年中発生する可能性があるので油断は禁物です。
発生しやすい場所は、植物の柔らかい部分です。特に、新芽、若葉の裏、茎、つぼみなどは、アブラムシにとって格好の餌場となります。 これらの場所は栄養が豊富で、アブラムシの口も刺しやすいため、好んで集まってきます。日当たりが悪く風通しの悪い場所も、アブラムシが好む環境なので注意が必要です。
なぜ?アブラムシが大量発生する原因
アブラムシがなぜあれほど大量に発生するのか、不思議に思ったことはありませんか?その理由は、彼らの驚異的な繁殖力と、発生を助長するいくつかの環境要因にあります。
最大の原因は、その驚異的な繁殖力です。春から秋にかけての暖かい時期、アブラムシはオスを必要としない「単為生殖(たんいせいしょく)」で増えることができます。 メスだけで子どもを産むことができ、しかも卵ではなく直接幼虫を産むため、爆発的に数が増えるのです。 わずか10日ほどで成虫になり、また子どもを産むというサイクルを繰り返すため、1匹見つけたらあっという間に大群になってしまいます。
また、窒素成分の多い肥料の与えすぎも原因の一つです。 窒素は植物の葉を茂らせるために必要な栄養素ですが、多すぎると植物内でアミノ酸が過剰に作られます。アブラムシはこのアミノ酸が大好きなので、窒素過多の植物に引き寄せられてしまうのです。
さらに、風通しの悪さもアブラムシの発生を助長します。 葉が密集していると、湿気がこもりやすくなり、アブラムシにとって快適な環境になります。また、天敵に見つかりにくいというメリットもあります。
【放置は危険!】アブラムシが植物に与える深刻な被害
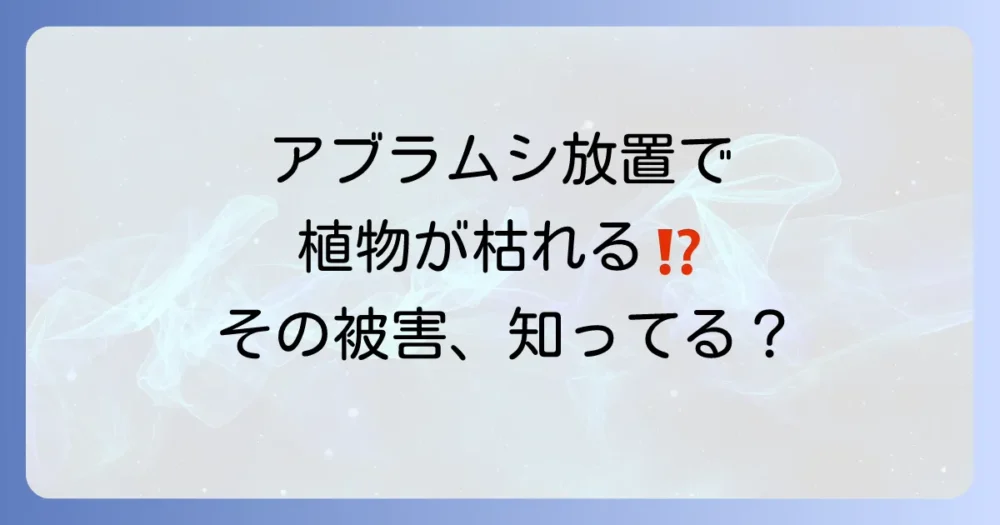
「小さい虫だから、少しぐらい大丈夫だろう」とアブラムシを放置するのは非常に危険です。アブラムシは植物に様々な悪影響を及ぼし、最悪の場合、枯らしてしまうこともあります。ここでは、アブラムシがもたらす深刻な被害について解説します。
- 栄養を吸い取られ生育不良に
- ウイルス病を媒介する
- すす病を誘発し光合成を妨げる
- アリを呼び寄せ、天敵から守られてしまう
これらの被害を知れば、早期駆除の重要性がお分かりいただけるはずです。
栄養を吸い取られ生育不良に
アブラムシの最も直接的な被害は、植物の栄養を吸い取ってしまうことです。 アブラムシは、植物の体内に流れる栄養分(師管液)を口針を突き刺して吸います。 1匹が吸う量はわずかでも、大群で一斉に吸汁するため、植物は深刻な栄養不足に陥ります。その結果、新芽や葉が縮れたり、変形したり、生育が著しく悪くなったりします。 ひどい場合には、植物全体が弱って枯れてしまうこともあります。
ウイルス病を媒介する
アブラムシは、植物の病気を媒介する運び屋でもあります。特に問題となるのが「モザイク病」などのウイルス病です。 ウイルスに感染した植物の汁を吸ったアブラムシが、次に健康な植物の汁を吸う際に、口針についたウイルスを伝染させてしまいます。 一度ウイルス病に感染してしまうと、農薬などを使っても治療することはできません。 被害が広がらないように、感染した株を抜き取って処分するしかなくなってしまいます。
すす病を誘発し光合成を妨げる
アブラムシがたくさんいる葉や茎が、黒いススのようなもので覆われてベタベタしているのを見たことはありませんか?これは「すす病」という病気です。 アブラムシは、吸った汁の中から必要なアミノ酸だけを吸収し、余分な糖分を「甘露(かんろ)」と呼ばれる甘い排泄物として体外に出します。 この甘露が付着した部分に、空気中のカビが繁殖して黒くなったものがすす病の正体です。 すす病自体が植物を直接枯らすわけではありませんが、葉の表面を覆ってしまうことで光合成を妨げ、植物の生育を阻害します。
アリを呼び寄せ、天敵から守られてしまう
アブラムシがいる場所には、よくアリが集まってきています。これは、アリがアブラムシの出す甘い排泄物「甘露」をエサにしているためです。 この関係は、ただアリが蜜をもらっているだけではありません。アリは甘露をもらう代わりに、アブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブなどを追い払い、アブラムシを守るという「共生関係」にあるのです。 アリがいることでアブラムシは天敵に襲われることなく、安心して繁殖を続けることができてしまいます。 アブラムシの別名が「アリマキ(蟻牧)」と呼ばれるのは、この関係性に由来しています。
今すぐできる!アブラムシの駆除方法7選
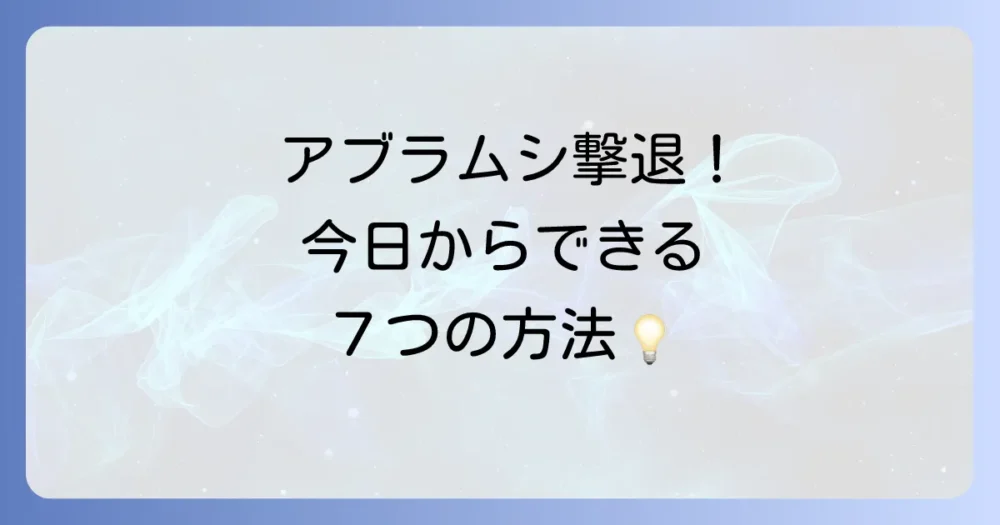
アブラムシの被害の深刻さがお分かりいただけたところで、いよいよ具体的な駆除方法について解説します。発生状況や植物の種類に合わせて、最適な方法を選んでください。手軽に試せるものから、効果の高い薬剤まで、幅広くご紹介します。
- 【初期段階に】手や歯ブラシで取り除く
- 【広範囲に】勢いよく水で洗い流す
- 【地道に】粘着テープで貼り付ける
- 【農薬を使いたくない方に】牛乳スプレー
- 【予防にも】木酢液・竹酢液スプレー
- 【天敵に頼る】テントウムシを味方につける
- 【効果てきめん】市販の殺虫剤を使う
【初期段階に】手や歯ブラシで取り除く
アブラムシの数がまだ少ない初期段階であれば、手で直接取り除くのが最も手軽で確実な方法です。少し気持ち悪いかもしれませんが、ゴム手袋などをはめて、指でつまんだり、こすり落としたりして駆除しましょう。植物を傷つけないように優しく行うのがコツです。
また、使い古しの歯ブラシを使うのもおすすめです。歯ブラシで軽くこすれば、葉の裏や茎の隙間など、指が届きにくい場所にいるアブラムシも効率的に除去できます。 この方法は、薬剤を使いたくない野菜やハーブなどに特に適しています。
【広範囲に】勢いよく水で洗い流す
アブラムシが広範囲に発生してしまった場合は、ホースや霧吹きなどを使って勢いよく水をかけて洗い流す方法が有効です。 アブラムシは水に弱く、強い水圧で簡単に植物から剥がれ落ちます。特に葉の裏に集まっていることが多いので、下から上に向かって水をかけると効果的です。
ただし、この方法だけでは地面に落ちたアブラムシが再び植物に登ってくる可能性があります。また、水の勢いが強すぎると、植物の新芽や花を傷つけてしまう恐れもあるため、力加減には注意が必要です。 水で洗い流した後に、後述する薬剤散布などを組み合わせると、より確実な駆除が期待できます。
【地道に】粘着テープで貼り付ける
セロハンテープやガムテープなどの粘着テープを使って、アブラムシをペタペタと貼り付けて取り除く方法もあります。 この方法は、薬剤を使わずに物理的に駆除できるのがメリットです。テープの粘着面をアブラムシに軽く押し当てるだけで、簡単に捕殺できます。
ただし、粘着力が強すぎるテープを使うと、植物の葉や茎を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。 また、アブラムシの数が多い場合は、非常に根気のいる作業になります。あくまでも、発生初期の補助的な駆除方法として捉えると良いでしょう。
【農薬を使いたくない方に】牛乳スプレー
小さなお子様やペットがいるご家庭で、できるだけ農薬を使いたくないという方におすすめなのが牛乳スプレーです。 牛乳をスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接吹きかけます。牛乳が乾く過程で膜を作り、アブラムシの気門(呼吸するための穴)を塞いで窒息死させるという仕組みです。
作り方は簡単で、牛乳と水を1:1で割る、あるいは牛乳を原液のままスプレーボトルに入れるだけです。 散布する際は、晴れた日の午前中に行い、牛乳がしっかりと乾くようにするのがポイントです。 ただし、散布後に牛乳をそのままにしておくと、腐敗して悪臭やカビの原因になるため、乾いた後は必ず水で洗い流すようにしてください。
【予防にも】木酢液・竹酢液スプレー
木酢液(もくさくえき)や竹酢液(ちくさくえき)も、アブラムシ対策に有効なアイテムです。これらは木炭や竹炭を焼くときに出る煙を冷却して液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。 この香りをアブラムシが嫌うため、忌避効果(虫を寄せ付けなくする効果)が期待できます。
使用する際は、製品のパッケージに記載されている希釈倍率を守り、水で薄めてからスプレーボトルで散布します。 木酢液には殺虫効果はあまり期待できませんが、定期的に散布することでアブラムシを予防する効果があります。 また、土壌改良効果も期待できるため、植物の生育を助ける副次的な効果も得られます。
【天敵に頼る】テントウムシを味方につける
自然の力を借りてアブラムシを駆除する方法もあります。アブラムシの天敵であるテントウムシを畑や庭に放すのです。テントウムシは成虫も幼虫もアブラムシを大好物としており、1匹のナナホシテントウの成虫は1日に100匹以上のアブラムシを食べるとも言われています。
他にも、ヒラタアブの幼虫やクサカゲロウの幼虫、アブラバチなども強力な天敵です。 これらの益虫(えきちゅう)が活動しやすい環境を整えることで、アブラムシの発生を自然に抑制することができます。殺虫剤をむやみに使うと、これらの天敵まで殺してしまう可能性があるので、薬剤の使用は慎重に行いましょう。
【効果てきめん】市販の殺虫剤を使う
アブラムシが大量に発生してしまい、手作業や自然由来の方法では追いつかない場合は、市販の殺虫剤を使用するのが最も効果的です。殺虫剤には、大きく分けてスプレータイプと粒剤タイプがあります。
スプレータイプは、アブラムシに直接吹きかけて駆除するもので、速効性が高いのが特徴です。「ベニカXネクストスプレー」などは、アブラムシに対して約1ヶ月の効果持続が期待できる製品もあります。
粒剤タイプは、植物の株元に撒くことで、有効成分が根から吸収され、植物全体に行き渡ります。 これにより、葉の裏などに隠れているアブラムシも駆除することができます。「GFオルトラン粒剤」などが有名で、効果の持続期間が長いのがメリットです。
野菜などに使用する場合は、その作物に登録があるか、収穫前日数がどのくらいかなどを必ず確認し、使用方法を守って正しく使いましょう。
もう悩まない!アブラムシを寄せ付けないための予防策
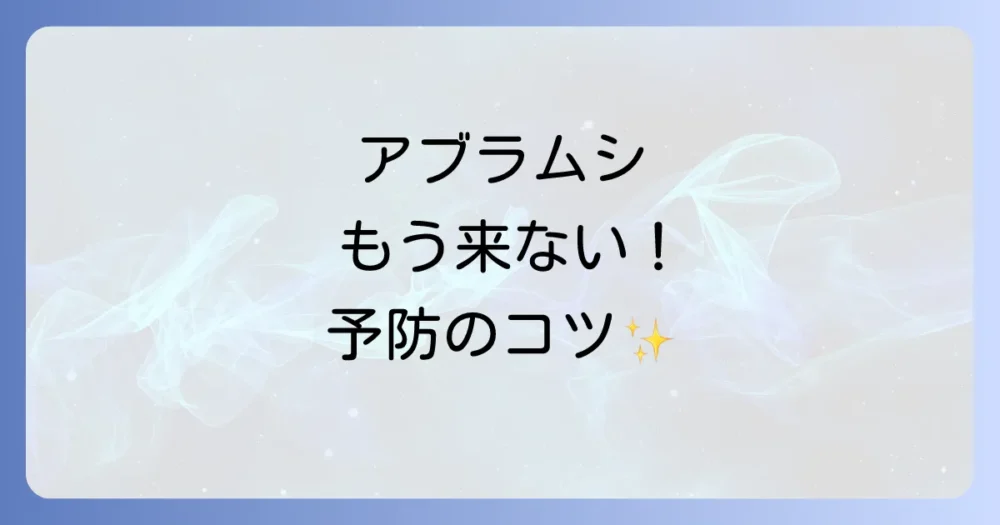
アブラムシは一度駆除しても、環境が変わらなければ再び発生する可能性があります。大切なのは、アブラムシが寄り付きにくい環境を作ることです。ここでは、今日から実践できる効果的な予防策をご紹介します。
- 肥料の与え方を見直す(窒素分を控える)
- 風通しと日当たりを良くする
- 防虫ネットや反射テープを活用する
- コンパニオンプランツを植える
これらの対策を組み合わせることで、アブラムシの発生を大幅に減らすことができます。
肥料の与え方を見直す(窒素分を控える)
アブラムシの発生原因でも触れましたが、窒素(チッソ)成分の多い肥料の与えすぎは、アブラムシを引き寄せる大きな原因となります。 窒素は葉や茎の成長を促す「葉肥(はごえ)」とも呼ばれますが、過剰になると植物体内のアミノ酸が増え、それを好むアブラムシが集まってきてしまいます。
肥料を与える際は、パッケージに記載されている規定量を守ることが大切です。特に、野菜の栽培などで有機肥料を使う場合、油かすなどは窒素分が多いので、与えすぎに注意しましょう。リン酸やカリウムとのバランスが取れた肥料を選ぶことも、植物を健康に育て、病害虫に強くする上で重要です。
風通しと日当たりを良くする
アブラムシは、日当たりが悪く、ジメジメとした風通しの悪い場所を好みます。 植物の葉が茂りすぎていると、株元まで日光が届かず、空気がよどんでアブラムシにとって絶好の隠れ家となってしまいます。
定期的に剪定を行い、混み合った枝や葉を間引いて、株全体に日光が当たり、風が通り抜けるようにしましょう。 これにより、アブラムシが住み着きにくい環境になるだけでなく、植物自体の健康も促進され、病気の予防にも繋がります。
防虫ネットや反射テープを活用する
物理的にアブラムシの侵入を防ぐ方法も非常に効果的です。特に、野菜などを育てる際には、目の細かい防虫ネットでトンネルがけをすることで、翅のある有翅アブラムシの飛来を防ぐことができます。
また、アブラムシはキラキラと光るものを嫌う性質があります。 この性質を利用して、植物の株元にアルミホイルを敷いたり、銀色の反射テープを張ったりするのも有効な予防策です。太陽の光が乱反射することで、アブラムシが方向感覚を失い、植物に近づきにくくなります。
コンパニオンプランツを植える
コンパニオンプランツ(共栄作物)を一緒に植えることで、アブラムシを遠ざける方法もあります。コンパニオンプランツとは、近くに植えることでお互いによい影響を与え合う植物のことです。
アブラムシ対策として有名なのは、マリーゴールド、ミント、カモミール、ニンニク、ネギ類など、特定の香りを持つ植物です。これらの植物の香りをアブラムシが嫌うため、寄せ付けにくくする効果が期待できます。 逆に、ナスタチウムのようにアブラムシを引き寄せる「おとり植物」として利用し、メインで育てたい植物からアブラムシを遠ざけるという方法もあります。
よくある質問
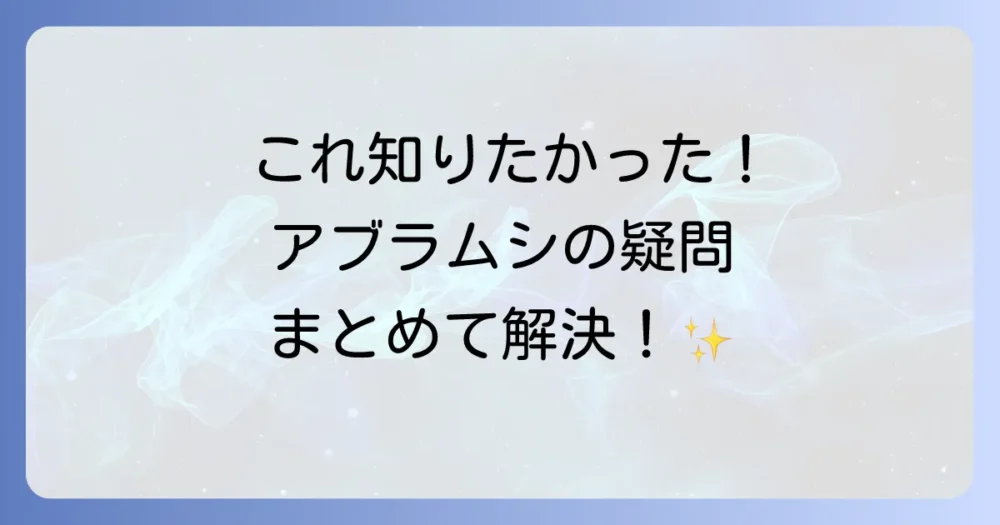
室内で発生したアブラムシの対策は?
室内で観葉植物などを育てている場合でも、アブラムシが発生することがあります。 窓やドアの開閉時や、人の衣服について侵入することが主な原因です。室内では天敵がいないため、一度発生すると増えやすい環境にあります。対策としては、まず発見次第、濡らしたティッシュや綿棒で拭き取るのが手軽です。数が多い場合は、屋外に出して水で洗い流すか、牛乳スプレーなどを試してみましょう。薬剤を使用する場合は、室内でも使えると明記された製品を選び、使用方法をよく読んで換気をしながら行ってください。 「evo 虫を寄せ付けない水」のような天然由来成分のスプレーもおすすめです。
アブラムシとアリはなぜ一緒にいるの?
アブラムシがいる植物にアリが集まっているのは、両者が「共生関係」にあるためです。 アブラムシは植物の汁を吸い、余分な糖分を「甘露」という甘い排泄物として出します。アリはこの甘露が大好物で、エサとして利用しています。 その見返りとして、アリはアブラムシの天敵であるテントウムシなどを追い払い、アブラムシを外敵から守ってあげます。 まるで牧場で家畜を育てるようにアリがアブラムシを世話することから、アブラムシは「アリマキ(蟻牧)」とも呼ばれています。
アブラムシに似た虫はいますか?
植物に付く小さい虫はアブラムシ以外にもいくつか存在します。例えば、「コナジラミ」は白い小さな虫で、植物を揺らすと白い粉のように飛び立ちます。「ハダニ」は0.5mm程度と非常に小さく、葉の裏に寄生して汁を吸い、葉にかすり状の白い斑点をつけます。被害が進むとクモの巣のような網を張ることもあります。これらの虫もアブラムシと同様に植物に害を与えるため、見つけ次第、適切な方法で駆除する必要があります。
おすすめの殺虫剤はありますか?
アブラムシに効果のある殺虫剤は数多く販売されています。手軽に使えるスプレータイプでは、住友化学園芸の「ベニカXネクストスプレー」が速効性と持続性に優れておりおすすめです。 食品成分由来の薬剤を希望する方には、同社の「ピュアベニカ」も良いでしょう。 根元に撒く粒剤タイプでは、長期間効果が持続する住友化学園芸の「家庭園芸用GFオルトラン粒剤」が定番商品として人気があります。 使用する植物(野菜、花、庭木など)や、周辺環境(ペットや子供の有無)に合わせて、適切な薬剤を選ぶことが重要です。必ず商品のラベルを確認し、用法・用量を守って使用してください。
まとめ
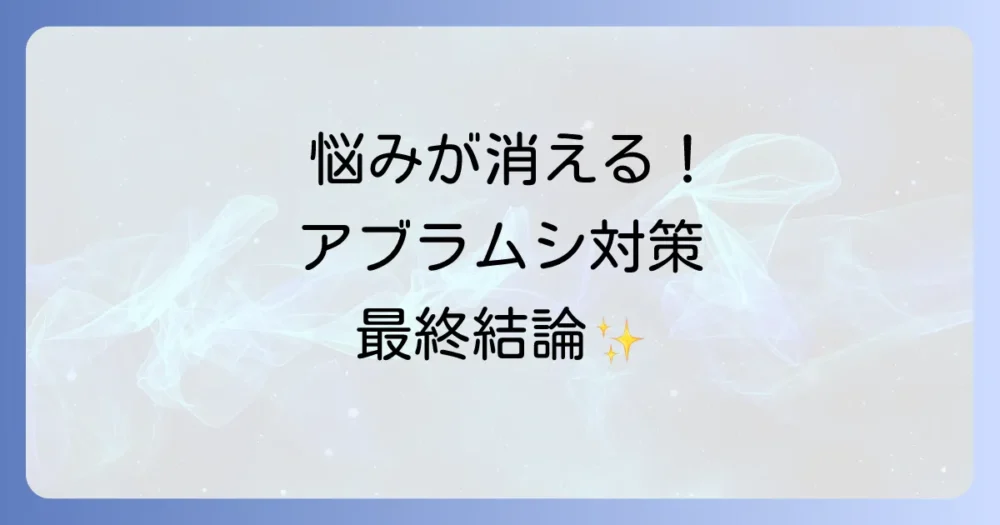
- 緑の小さい虫の多くはアブラムシである可能性が高い。
- アブラムシは緑色だけでなく、黒や黄色など様々な色がいる。
- 春と秋に特に発生しやすく、驚異的な繁殖力で増える。
- 窒素肥料の与えすぎや風通しの悪さが大量発生の原因になる。
- 植物の栄養を吸い、ウイルス病や、すす病を媒介する。
- アリと共生関係にあり、天敵から守られている。
- 初期段階なら手やテープ、水で物理的に駆除できる。
- 農薬を使いたくない場合は牛乳スプレーが有効。
- 木酢液スプレーは予防効果が期待できる。
- 天敵のテントウムシはアブラムシを食べてくれる益虫。
- 大量発生時は市販の殺虫剤が最も効果的。
- 予防には肥料管理、剪定による風通しの確保が重要。
- 防虫ネットや反射テープで物理的に侵入を防ぐ。
- コンパニオンプランツを植えるのも効果的な予防策。
- 駆除と予防を組み合わせて、大切な植物を守ることが大切。