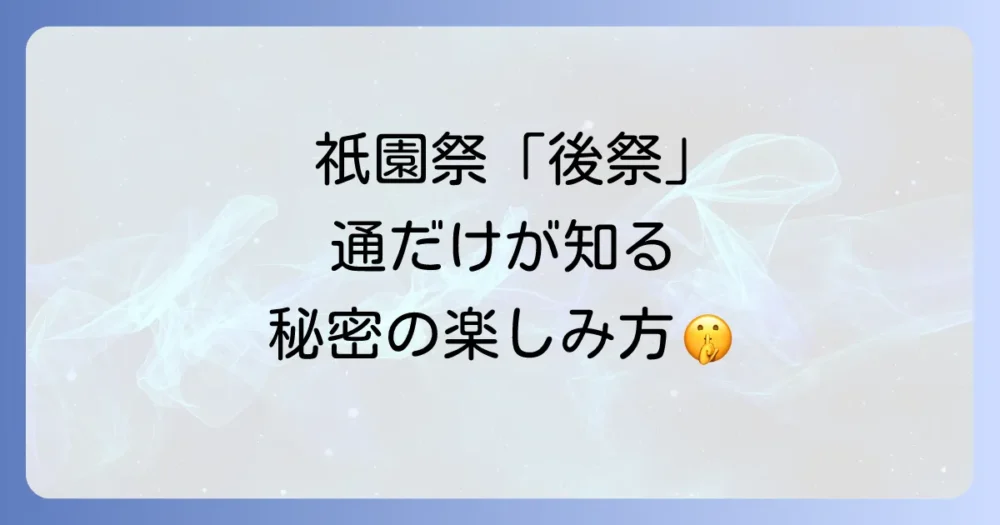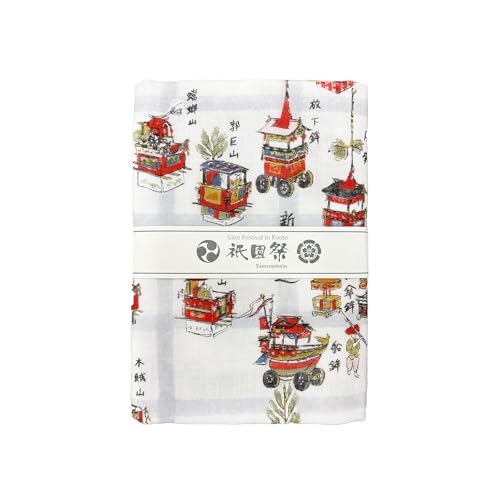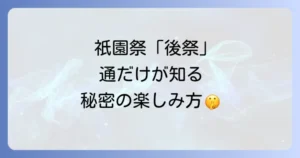京都の夏を彩る日本三大祭の一つ、祇園祭。そのクライマックスの一つである「後祭(あとまつり)」について、あなたはどれくらいご存知でしょうか。「前祭(さきまつり)には行ったことがあるけど、後祭はよく知らない」「なんだか地味なイメージがある」なんて思っていたら、もったいない!実は後祭には、前祭とはひと味違う、通好みで奥深い魅力が満載なのです。
本記事では、祇園祭の後祭を心ゆくまで満喫するための楽しみ方を、プロの視点から徹底的に解説します。2025年の最新日程から、山鉾巡行の見どころ、静かな宵山の過ごし方、そして還幸祭や花傘巡行といった関連神事まで、これを読めば後祭の全てがわかります。あなたもきっと、後祭の虜になるはずです。
祇園祭の「後祭」は通好み!前祭との違いを知って10倍楽しむ
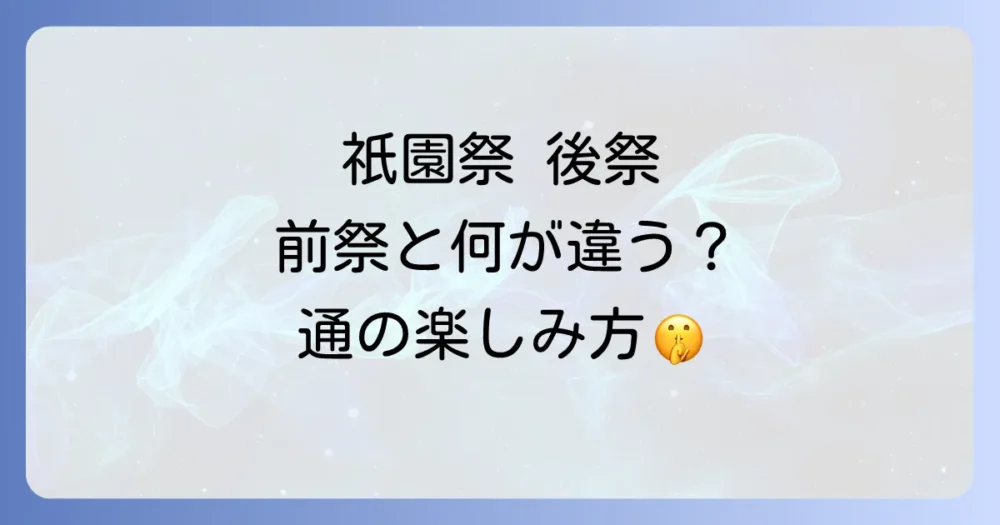
祇園祭の後祭の魅力を知るには、まず前祭との違いを理解することが大切です。なぜ後祭が「通好み」と言われるのか、その歴史的背景や日程、そして後祭ならではの魅力に迫ります。
この章では、以下の点について詳しく解説していきます。
- そもそも後祭とは?2014年に復活した歴史的背景
- 後祭の開催日程はいつ?【2025年版】
- 前祭とはここが違う!後祭ならではの3つの魅力
そもそも後祭とは?2014年に復活した歴史的背景
祇園祭の山鉾巡行は、もともと7月17日の「前祭」と24日の「後祭」の2回に分けて行われていました。 これは、八坂神社の神様を神輿(みこし)に乗せて四条御旅所(おたびしょ)へお迎えする「神幸祭(しんこうさい)」(17日)と、再び八坂神社へお還りいただく「還幸祭(かんこうさい)」(24日)という、祭りの最も重要な神事に合わせて、それぞれの日に市中を清めるために行われていたものです。
しかし、交通事情など時代の変化に伴い、1966年(昭和41年)から2013年(平成25年)までの48年間は、前祭と後祭が統合され、7月17日に一度だけ山鉾巡行が行われる形となっていました。 この間、後祭の巡行に代わるものとして「花傘巡行」が始まりました。
その後、祇園祭本来の姿を取り戻そうという機運が高まり、2014年(平成26年)に49年ぶりに後祭の山鉾巡行が復活したのです。 この復活は、歴史と伝統を重んじる京都の心意気の表れであり、祇園祭の奥深さを物語る出来事でした。同時に、幕末の戦火で焼失して以来休み鉾となっていた「大船鉾」が150年ぶりに巡行に復帰し、大きな話題となりました。
後祭の開催日程はいつ?【2025年版】
祇園祭の後祭は、毎年7月21日から24日にかけて行われます。2025年(令和7年)の主な日程は以下の通りです。お出かけの計画を立てる際の参考にしてください。
- 後祭 宵山(よいやま): 7月21日(月・祝)~23日(水)
- 後祭 山鉾巡行(やまほこじゅんこう): 7月24日(木)
- 花傘巡行(はながさじゅんこう): 7月24日(木)
- 還幸祭(かんこうさい): 7月24日(木)
このように、後祭のクライマックスは7月24日に集中しています。山鉾巡行だけでなく、華やかな花傘巡行、そして勇壮な神輿渡御である還幸祭と、一日を通して祇園祭の神髄に触れることができるのが特徴です。
前祭とはここが違う!後祭ならではの3つの魅力
多くの観光客でごった返す前祭と比べ、後祭には落ち着いた雰囲気の中で祭りをじっくりと味わえる魅力があります。ここでは、後祭ならではの特筆すべき3つの魅力をご紹介します。
- 比較的、混雑が少なくゆったり楽しめる
後祭の最大の魅力は、前祭に比べて人出が少ないことです。 前祭の宵山期間中(特に15日・16日)は、四条通や烏丸通が歩行者天国となり、多くの露店が軒を連ね、身動きが取れないほどの混雑となります。 一方、後祭の宵山では歩行者天国や露店の出店がありません。 そのため、自分のペースで山鉾をじっくりと鑑賞したり、駒形提灯が揺れる幻想的な夜の風情を楽しんだりすることができます。 - 山鉾巡行と神輿渡御(還幸祭)を同日に見られる
7月24日は、午前中に山鉾巡行、午後から夕方にかけては還幸祭の神輿渡御が行われます。 山鉾巡行が「動く美術館」と称される静かな美の祭典であるのに対し、還幸祭は「ホイット、ホイット!」という威勢の良い掛け声とともに神輿が練り歩く、動的で熱気あふれる神事です。 この静と動、二つの異なる魅力を持つ行列を一日で堪能できるのは、後祭ならではの醍醐味と言えるでしょう。 - 復活した山鉾など、通好みの見どころが満載
後祭には、歴史の物語を感じさせる見どころが多くあります。2014年に150年ぶりに復活した「大船鉾」は、後祭の最後尾(殿)を進むくじ取らずの鉾で、その荘厳な姿は必見です。 さらに2022年には、196年ぶりに「鷹山」が巡行に本格復帰し、大きな注目を集めました。 こうした長い時を経て復活を遂げた山鉾の姿を間近に見られるのは、歴史の証人になるような特別な体験です。
【後祭のハイライト】山鉾巡行の楽しみ方完全ガイド
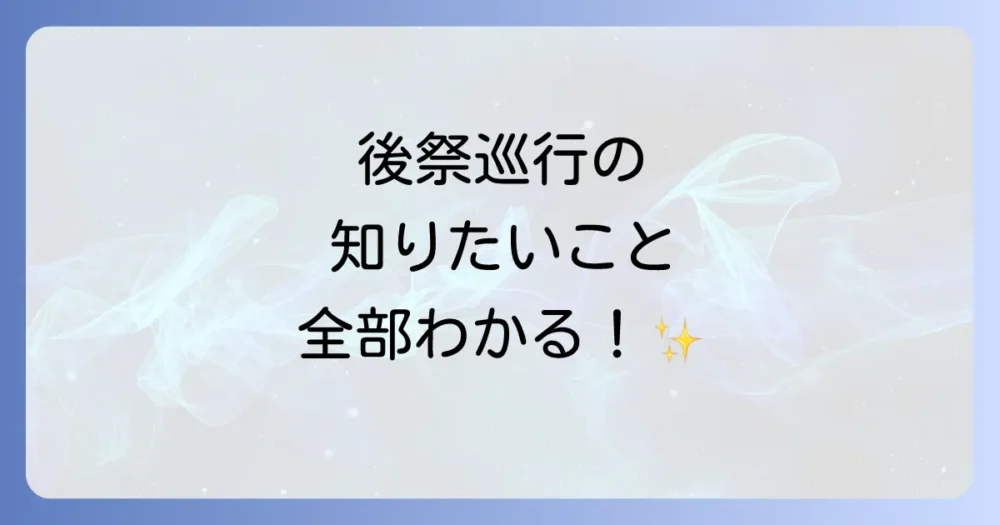
7月24日の午前中に行われる山鉾巡行は、後祭のハイライトです。前祭とは異なるルートや見どころを知っておくことで、その魅力を余すところなく楽しむことができます。ここでは、巡行ルートから注目の山鉾、おすすめの観覧スポットまでを詳しく解説します。
この章のポイントはこちらです。
- 2025年の巡行日時とルートをチェック!前祭との違いも
- 必見!後祭のスター山鉾「大船鉾」と「鷹山」
- ここで見るのがおすすめ!観覧スポットと穴場情報
- 有料観覧席は買うべき?メリット・デメリットを解説
2025年の巡行日時とルートをチェック!前祭との違いも
後祭の山鉾巡行は、前祭とは出発時間とルートが異なります。間違えないように、しっかりと確認しておきましょう。
- 日時: 2025年7月24日(木) 午前9時30分 出発
- 巡行ルート: 烏丸御池 → 河原町御池 → 四条河原町 → 四条烏丸
前祭が四条烏丸から東へ出発するのに対し、後祭は烏丸御池を東へ出発し、前祭とは逆のコースをたどります。 巡行する山鉾は、橋弁慶山を先頭に11基です。 前祭の23基に比べると規模は小さいですが、その分、一つひとつの山鉾を丁寧に見ることができます。
巡行の最大の見どころの一つが、交差点で巨大な鉾の向きを90度変える「辻回し」です。 後祭では、河原町御池と四条河原町の2か所で行われます。 水をかけた竹を車輪の下に敷き、「エンヤラヤー」の掛け声とともに力強く方向転換する様子は圧巻の一言。ぜひ見ておきたいポイントです。
必見!後祭のスター山鉾「大船鉾」と「鷹山」
後祭には11基の個性豊かな山鉾が巡行しますが、中でも特に注目したいのが、近年復活を遂げた2基の山鉾です。
大船鉾(おおふねほこ)
後祭の巡行の最後尾、「殿(しんがり)」を務めるのが大船鉾です。 その名の通り巨大な船の形をしており、神功皇后の朝鮮出兵の物語に基づいています。前祭の「船鉾」が出陣を表すのに対し、後祭の大船鉾は戦いを終えて帰還する「凱旋」の姿を表しているのが特徴です。 幕末の「蛤御門の変」(1864年)で焼失して以来、長らく休み鉾となっていましたが、町衆の熱意により2014年に150年ぶりに巡行へ復帰しました。 豪華絢爛な装飾と、凱旋の船にふさわしい堂々とした姿は、後祭の象徴ともいえる存在です。
鷹山(たかやま)
2022年に196年ぶりに巡行へ復帰し、大きな話題となったのが鷹山です。 応仁の乱以前から存在したとされる歴史ある山で、鷹狩りをテーマにしています。 御神体として鷹匠(鷹遣)、犬遣、樽負という3体の人形が飾られています。 江戸時代後期に大きな曳山(ひきやま)として巡行していましたが、1826年の巡行中に大雨で被災し、その後巡行が途絶えていました。 約200年の時を経て蘇った勇壮な姿は、祇園祭の歴史の重みと、伝統を未来へ繋ぐ人々の情熱を感じさせてくれます。
ここで見るのがおすすめ!観覧スポットと穴場情報
山鉾巡行をどこで見るかは、満足度を大きく左右する重要なポイントです。人気のスポットから、比較的ゆったり見られる穴場までご紹介します。
- 河原町御池(京都市役所前)
巡行が出発して最初の辻回しが行われるポイントです。 全ての山鉾の辻回しを見ることができ、京都市長による「くじ改め」の儀式も行われるため、見どころが満載です。 当然ながら大変な人気スポットなので、良い場所で見るには早朝から場所取りをする必要があります。 - 四条河原町
2回目の辻回しが行われる、こちらも人気の観覧スポットです。 多くの人が集まりますが、交差点の四隅が広いため、比較的見やすい場所を見つけやすいかもしれません。 - 四条通(河原町通~烏丸通)
巡行の最終盤にあたるこの区間は、比較的混雑が緩和される穴場と言えます。 特に四条烏丸のゴール地点に近づくほど、ゆったりと見物できる可能性が高まります。辻回しのような派手な見せ場はありませんが、まっすぐ進む山鉾の美しい姿や、奏でられる祇園囃子を落ち着いて楽しみたい方におすすめです。
有料観覧席は買うべき?メリット・デメリットを解説
山鉾巡行には、京都市観光協会などが販売する有料観覧席が設けられます。購入を迷っている方のために、メリットとデメリットをまとめました。
メリット
- 場所取りの必要がない: 長時間待つことなく、確実に座って観覧できます。特に体力に自信のない方や、小さなお子様連れには大きな利点です。
- 見やすいロケーション: 観覧席は御池通沿いなど、巡行が見やすい場所に設置されます。解説パンフレットが付いていることも多く、より深く巡行を楽しめます。
デメリット
- 費用がかかる: 当然ですが、観覧には料金が必要です。
- 人気が高く入手困難な場合も: 席数には限りがあり、発売後すぐに売り切れてしまうことも少なくありません。
- 自由な移動ができない: 一度席に着くと、辻回しだけを見に移動するといった自由な動きは難しくなります。
じっくりと快適に観覧したい、場所取りのストレスを避けたいという方には有料観覧席はおすすめです。一方で、自分の見たいポイントを自由に移動しながら楽しみたいという方は、早めに場所取りをして一般の沿道から観覧するのが良いでしょう。
後祭の宵山(よいやま)は静かな夜の散策が魅力
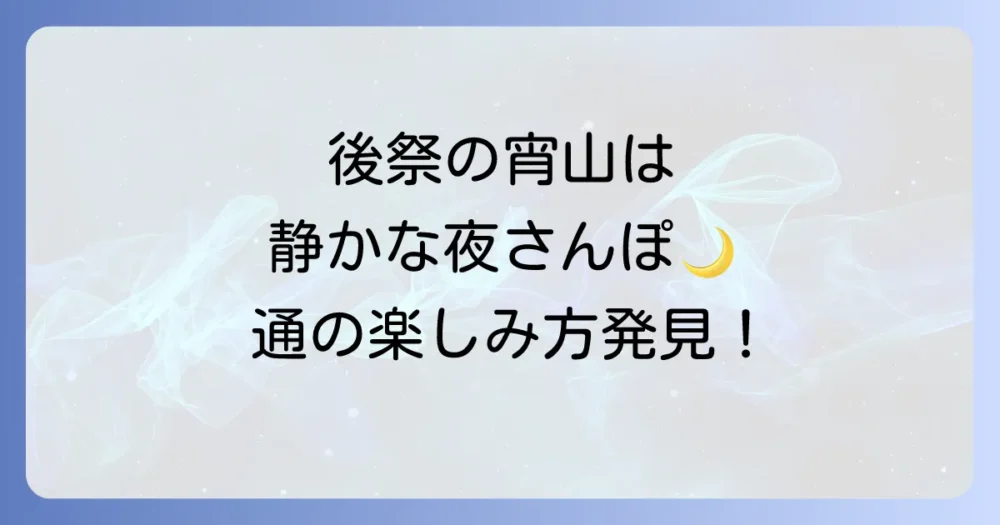
7月21日から23日にかけての3日間は「後祭の宵山」と呼ばれます。前祭の喧騒とは対照的に、しっとりとした情緒あふれる時間を過ごせるのが後祭宵山の大きな魅力です。ここでは、その楽しみ方をご紹介します。
この章のポイントは以下の通りです。
- 宵山の日程と落ち着いた雰囲気
- 屋台は出ない?後祭宵山のグルメ事情
- 屏風祭で各家に伝わる家宝を鑑賞
宵山の日程と落ち着いた雰囲気
後祭の宵山は、山鉾巡行の前々々日、前々日、前日、つまり7月21日、22日、23日に行われます。 夕刻になると、各山鉾町に建てられた山鉾に駒形提灯が灯され、幻想的な光景が広がります。そして、どこからともなく聞こえてくるのが「コンチキチン」という祇園囃子の音色。
前祭と大きく違うのは、歩行者天国にならず、露店も出ないことです。 そのため、人混みにもまれながら歩くというよりは、普段の京都の街並みの中に山鉾が溶け込んでいるような、落ち着いた雰囲気を楽しむことができます。 提灯の灯りに照らされた懸装品(けそうひん)と呼ばれる豪華な飾りを間近でじっくりと眺めたり、それぞれの山鉾の由来に思いを馳せたりと、ゆったりとした大人の時間を過ごすのに最適です。
屋台は出ない?後祭宵山のグルメ事情
前述の通り、後祭の宵山では前祭のように通りにずらりと屋台が並ぶことはありません。 あの賑やかな雰囲気が好きだという方には少し物足りなく感じるかもしれませんが、がっかりする必要はありません。
山鉾が建つ四条烏丸周辺には、魅力的な飲食店がたくさんあります。宵山の散策の合間に、京料理の老舗で本格的な和食を味わうのも良いですし、町家を改装したおしゃれなカフェで一休みするのも素敵です。また、この時期限定のメニューを提供しているお店もあります。屋台の食べ歩きとは違った、落ち着いた空間で京都の食を堪能するのも、後祭ならではの楽しみ方と言えるでしょう。
事前に気になるお店をリサーチして予約しておくと、スムーズに食事を楽しむことができますよ。
屏風祭で各家に伝わる家宝を鑑賞
宵山の期間中、山鉾町の旧家や老舗では、所蔵している屏風や美術品などを通りから見えるように飾り、一般に公開する「屏風祭(びょうぶまつり)」が行われます。 これは、山鉾を飾るのと同じように、家に伝わる宝物を披露することで祭りを盛り上げるという、町衆の心意気から始まった習わしです。
普段は決して見ることのできない個人所蔵の貴重な屏風や掛け軸、調度品などを、格子戸越しに鑑賞することができます。まさに街全体が美術館になるような、風情あふれる催しです。すべての家で行われているわけではありませんが、提灯の灯りに照らされた町家を散策しながら、美しい家宝を探して歩くのも宵山の大きな楽しみの一つです。近年は実施する家が減ってきているとも言われており、見ることができたら幸運かもしれません。
まだまだある!後祭期間中の見逃せない神事・イベント
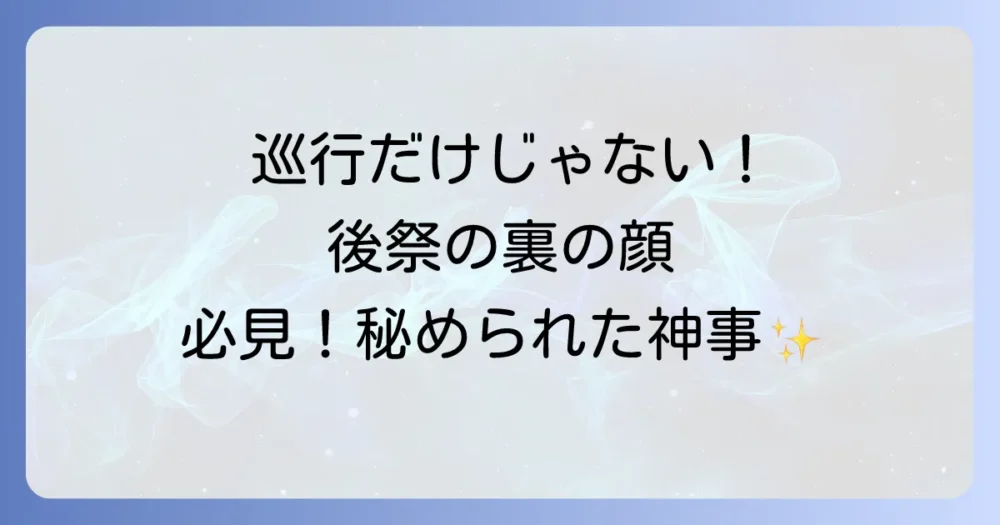
7月24日は山鉾巡行だけではありません。祭りの本来の主役である神様をお乗せした神輿が還る「還幸祭」や、華やかな「花傘巡行」など、見逃せない神事やイベントが目白押しです。これらを見ることで、祇園祭への理解がさらに深まるはずです。
この章では、以下の神事・イベントをご紹介します。
- 勇壮な神輿渡御!祭りのクライマックス「還幸祭(かんこうさい)」
- 山鉾巡行とは別の華やかさ「花傘巡行」
- 南観音山の「あばれ観音」など各山鉾の独自神事
勇壮な神輿渡御!祭りのクライマックス「還幸祭(かんこうさい)」
還幸祭は、7月17日の神幸祭で四条御旅所にお迎えしていた八坂神社の三基の御神輿(ごしんよ)が、再び氏子町内を巡り、八坂神社へお還りになる神事です。 「おかえり」とも呼ばれ、祇園祭のクライマックスの一つとされています。
7月24日の夕方5時頃、三基の神輿が次々と御旅所を出発します。 「ホイット、ホイット!」という担ぎ手たちの威勢の良い掛け声とともに、重さ約2トンにもなる神輿が練り歩く様は圧巻です。 神輿を高く持ち上げる「差し上げ」や、回転させる「差し回し」など、力強いパフォーマンスも見どころです。
山鉾巡行の静かで厳かな雰囲気とは対照的な、熱気とエネルギーに満ちた渡御は、祭りの神聖さと町衆の情熱を肌で感じさせてくれます。深夜、八坂神社に神輿が還り、境内の明かりがすべて消された中で行われる「御霊遷し」の神事で、一か月にわたる祭りは静かに終わりへと向かいます。
山鉾巡行とは別の華やかさ「花傘巡行」
山鉾巡行が後祭で復活する以前、7月24日の巡行の代わりとして始まったのが花傘巡行です。 現在も後祭の山鉾巡行と同日に行われ、祭りに華を添えています。
午前10時に八坂神社を出発し、市役所などを巡って再び八坂神社へ戻ります。 その名の通り、美しい花で飾られた傘鉾を中心に、馬に乗ったお稚児さん、武者行列、獅子舞、そして祇園の芸舞妓さんを乗せた曳き車など、総勢1000人近くにもなる華やかな行列が続きます。 山鉾巡行が伝統的な様式美を誇るのに対し、花傘巡行はより賑やかで芸能的な色彩が濃いのが特徴です。
八坂神社に戻った後は、舞殿で舞踊などが奉納され、こちらも見ごたえがあります。 山鉾巡行とはまた違った、雅で美しい行列を楽しんでみてはいかがでしょうか。
南観音山の「あばれ観音」など各山鉾の独自神事
後祭の期間中、各山鉾町では独自の神事や行事が行われます。これらは観光客向けというよりは、町内の人々が祭りの無事を祈願するためのものですが、その一部を垣間見ることで、より深く祇園祭の文化に触れることができます。
特に有名なのが、後祭宵山の最終日、7月23日の夜に行われる南観音山の「あばれ観音」です。 日和神楽(ひよりかぐら)を終えて町内に戻ってきた南観音山の御神体・楊柳観音像を蓮台に固定し、白布でぐるぐる巻きにした状態で、「ワッショイ、ワッショイ」と担ぎながら町内を駆け巡ります。 観音様を揺さぶることでご利益を発揮させるといわれるこの奇祭は、一見の価値ありです。
また、同じく23日には役行者山で聖護院の山伏による護摩焚きが行われるなど、それぞれの山鉾が持つ歴史や信仰に根差した行事が行われています。 宵山散策の際に、こうした場面に出会えたらラッキーですね。
【目的別】あなたに合った後祭の楽しみ方プラン
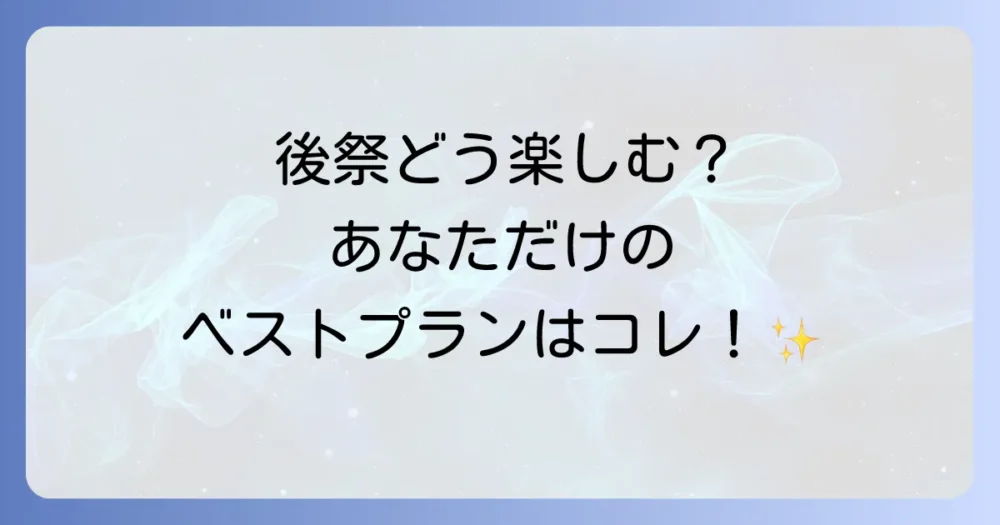
後祭の魅力を知ったところで、具体的にどう楽しめばいいか、目的別のモデルプランをご提案します。初めての方も、一人旅の方も、ご家族連れの方も、このプランを参考に自分だけの後祭の楽しみ方を見つけてください。
ここでは、3つのプランをご紹介します。
- 初めてでも安心!後祭の魅力を満喫する王道プラン
- じっくり深く味わう!お一人様向け満喫プラン
- 子連れで楽しむための注意点とおすすめポイント
初めてでも安心!後祭の魅力を満喫する王道プラン
後祭が初めてという方は、まずハイライトを効率よく巡るのがおすすめです。7月24日に的を絞ったプランはいかがでしょうか。
- 午前中:山鉾巡行を観覧
まずはメインイベントの山鉾巡行へ。少し早起きして、巡行ルートの中でも比較的空いている四条通(河原町~烏丸)で場所を確保しましょう。11基の山鉾がゆっくりと進む様子や、美しい懸装品、祇園囃子の音色を楽しみます。 - 昼食:四条烏丸周辺でランチ
巡行が終わったら、周辺でランチタイム。混雑が予想されるので、少し時間をずらすか、事前に予約しておくとスムーズです。 - 午後:花傘巡行を少しだけ鑑賞
時間に余裕があれば、八坂神社方面へ移動し、華やかな花傘巡行の雰囲気を味わうのも良いでしょう。 - 夕方~夜:還幸祭でクライマックスを体感
夕方からは、祭りのクライマックス「還幸祭」へ。四条御旅所から出発する神輿の熱気を間近で感じてみましょう。勇壮な神輿渡御は、きっと忘れられない思い出になるはずです。
じっくり深く味わう!お一人様向け満喫プラン
一人旅なら、自分の興味の赴くままに、より深く後祭の世界に浸るプランがおすすめです。
- 7月23日(宵山):静かな夜の散策と屏風祭
宵山の最終日、夕暮れ時から四条烏丸界隈へ。駒形提灯に照らされた山鉾を一つひとつじっくりと鑑賞します。お目当ての山鉾(大船鉾や鷹山など)の会所で授与品(ちまきや手ぬぐい)をいただくのも良い記念になります。格子戸越しに見える屏風祭を探しながら、風情ある路地を気ままに歩いてみましょう。夜には南観音山の「あばれ観音」を見に行くのも一興です。 - 7月24日(巡行日):辻回しと還幸祭に集中
早朝から河原町御池の交差点へ向かい、迫力満点の「辻回し」を最前列で狙います。巡行が終わった後は一度休憩し、夕方からの還幸祭に備えましょう。神輿が通るルートを先回りしながら、様々な表情を見せる神輿渡御を追いかけるのも面白いかもしれません。
子連れで楽しむための注意点とおすすめポイント
お子様連れの場合は、無理のないスケジュールと安全への配慮が第一です。後祭は前祭より空いているとはいえ、混雑する場所はあります。
- 山鉾巡行は短時間で
長時間の場所取りや観覧は子供にとって負担です。巡行ルートの終盤、四条烏丸に近い場所で、通り過ぎる山鉾をいくつか見るだけでも十分楽しめます。ベビーカーは混雑時には危険なため、抱っこ紐などを用意すると安心です。 - 宵山は明るい時間帯に
夜の宵山も魅力的ですが、お子様連れなら昼間や夕方の明るい時間帯に訪れるのがおすすめです。人も少なく、ゆっくりと山鉾を見ることができます。 - 花傘巡行がおすすめ
山鉾巡行よりも、芸舞妓さんや子供神輿が登場する花傘巡行の方が、小さなお子様には分かりやすく楽しめるかもしれません。華やかな行列にきっと喜ぶはずです。 - こまめな休憩と水分補給を
夏の京都は大変暑いです。熱中症対策として、帽子や日傘、飲み物は必須です。無理せず、カフェなどでこまめに休憩を取り入れましょう。
祇園祭「後祭」のアクセスと混雑を避けるコツ
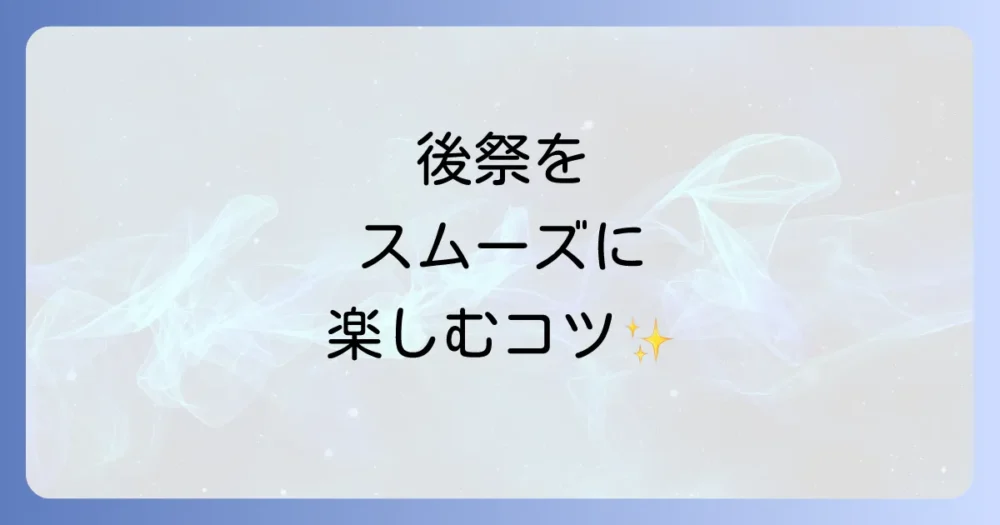
後祭を快適に楽しむためには、事前の準備が欠かせません。会場へのアクセス方法や混雑を避けるためのポイント、そしてあると便利な持ち物についてまとめました。
この章のポイントはこちらです。
- 会場周辺へのアクセス方法一覧
- 混雑を避けて快適に楽しむためのポイント
- これだけは準備したい!持ち物リスト
会場周辺へのアクセス方法一覧
後祭の主な舞台となる四条烏丸周辺は、公共交通機関の利用が非常に便利です。期間中は交通規制が敷かれることもあるため、車でのアクセスは避けましょう。
- 電車でのアクセス
- 阪急京都線「烏丸駅」下車すぐ
- 京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車すぐ
- 京都市営地下鉄東西線「烏丸御池駅」下車 徒歩約5分
- バスでのアクセス
- 京都市バス「四条烏丸」バス停下車すぐ
山鉾巡行や還幸祭の当日は、一部バスの運行ルートが変更になる場合があります。事前に京都市交通局のウェブサイトなどで最新情報を確認しておくと安心です。
混雑を避けて快適に楽しむためのポイント
前祭よりは空いているとはいえ、後祭でも混雑は発生します。少しでも快適に過ごすためのコツをご紹介します。
- 時間をずらして行動する
山鉾巡行であれば、スタート地点や辻回しといった人気スポットを避け、巡行の後半のルートで観覧するのがおすすめです。 宵山も、提灯が灯り始める夕方や、多くの人が帰路につく遅めの時間を狙うと、比較的ゆっくり見ることができます。 - 平日の宵山を狙う
後祭の宵山は7月21日~23日です。もし日程が合うなら、週末や祝日よりも平日の方が人出は少ない傾向にあります。 - メインストリートから一本入る
宵山の際、山鉾が建つ新町通や室町通は多くの人で賑わいます。しかし、そこから一本路地に入るだけで、驚くほど静かになることがあります。祇園囃子の音色をBGMに、静かな路地を散策するのも乙なものです。
これだけは準備したい!持ち物リスト
夏の京都、そして祭りの人混みを快適に過ごすために、以下の持ち物を準備しておくことをおすすめします。
- 飲み物: 熱中症対策は万全に。ペットボトルや水筒を持参しましょう。
- 帽子・日傘: 日中の山鉾巡行観覧では日差しを遮るものが必須です。
- 扇子・うちわ: 手軽に涼をとれるアイテムは重宝します。
- 汗拭きシート・タオル: 汗をかいたときにさっぱりできます。
- 歩きやすい靴: 長時間歩き回ることが多いので、スニーカーなどが最適です。
- 小さなレジャーシート: 山鉾巡行を待つ間、地面に座る際に便利です。
- モバイルバッテリー: 写真撮影や情報検索でスマートフォンの電池は消耗しがちです。
- 現金: ちまきなどの授与品は現金のみの場合が多いです。少額の現金を用意しておきましょう。
祇園祭「後祭」の楽しみ方に関するよくある質問
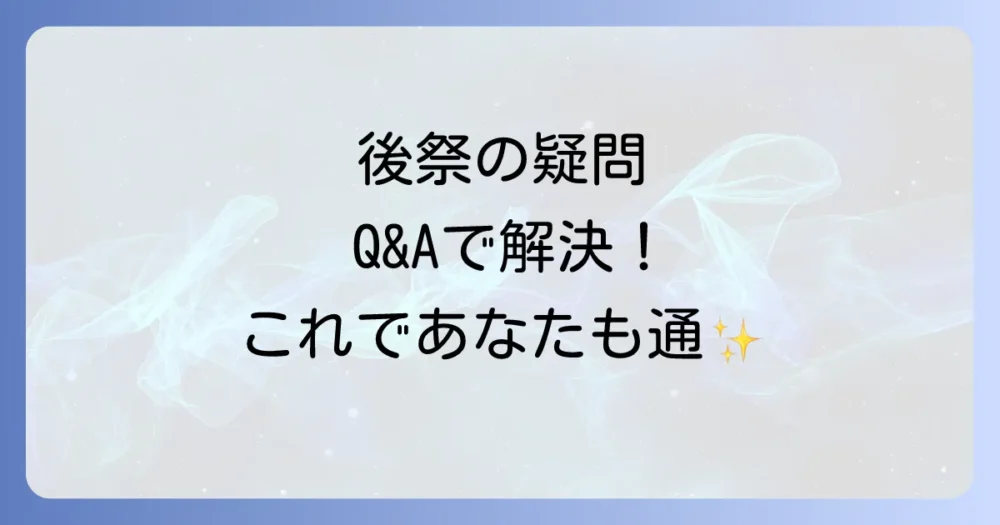
祇園祭の後祭に屋台は出ますか?
いいえ、後祭の宵山(7月21日~23日)では、前祭の宵山(15日・16日)のように通りに屋台がずらりと並ぶことはありません。 また、大規模な交通規制である歩行者天国も実施されません。 そのため、比較的落ち着いた雰囲気の中で宵山を楽しむことができます。
後祭の山鉾巡行は何時からですか?
後祭の山鉾巡行は、例年7月24日の午前9時30分に烏丸御池を出発します。 前祭が午前9時に四条烏丸を出発するのと時間も場所も異なるので注意が必要です。巡行は午前11時半頃に四条烏丸で終了する予定です。
祇園祭の前祭と後祭はどちらがおすすめですか?
どちらも魅力的なので一概には言えませんが、目的によっておすすめは異なります。
前祭がおすすめな方: 祭りの熱気や賑わいを存分に味わいたい方。屋台や歩行者天国を楽しみたい方。23基の豪華な山鉾が見たい方。
後祭がおすすめな方: 人混みを避けて、落ち着いて祭りを楽しみたい方。 山鉾や屏風祭などをじっくり鑑賞したい方。山鉾巡行と神輿渡御(還幸祭)の両方を見たい方。歴史や通な見どころに興味がある方。
後祭の山鉾は何基ですか?
後祭で巡行する山鉾は全部で11基です。 内訳は、くじ取らずの山鉾が5基(橋弁慶山、北観音山、南観音山、大船鉾、鷹山)、くじ取りで順番を決める山鉾が6基(黒主山、役行者山、鯉山、八幡山、浄妙山、鈴鹿山)です。 ちなみに前祭は23基の山鉾が巡行します。
花傘巡行とは何ですか?
花傘巡行は、かつて後祭の山鉾巡行が中断されていた時代に、その代わりとして始まった華やかな行列です。 山鉾の古い形態とされる花傘を中心に、芸舞妓さんを乗せた曳き車、子供神輿、鷺踊、獅子舞など、総勢1000人近くが練り歩きます。 山鉾巡行とは異なり、芸能的な色彩が濃いのが特徴で、後祭の山鉾巡行と同日の7月24日に行われます。
まとめ
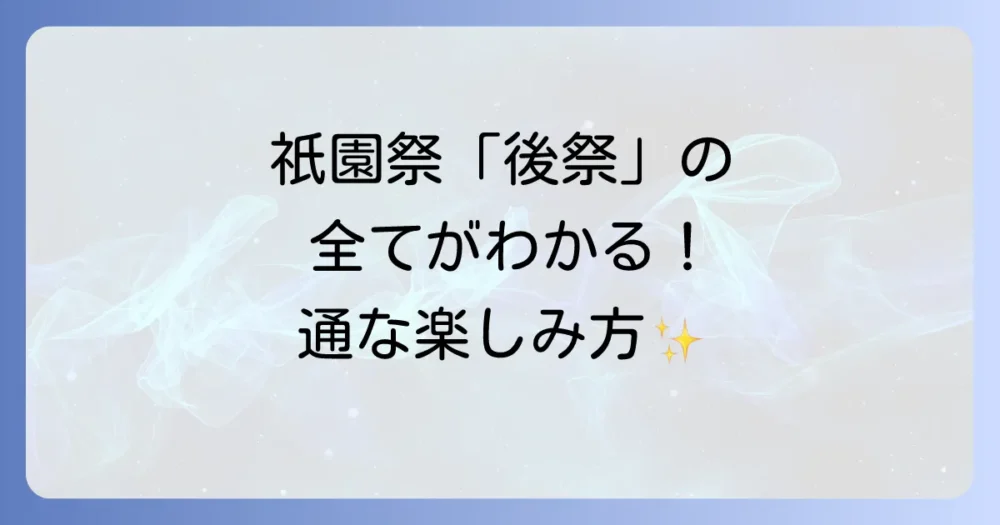
- 後祭は7月21日~24日、前祭より落ち着いた雰囲気。
- 2014年に49年ぶりに復活した歴史ある祭り。
- 後祭宵山は屋台や歩行者天国がなく、静かに楽しめる。
- 山鉾巡行は7月24日9時半に烏丸御池を出発。
- 巡行ルートは前祭とは逆回りで、山鉾は11基。
- 見どころは150年ぶり復活の「大船鉾」。
- 196年ぶり復活の「鷹山」も大きな注目株。
- 辻回しは河原町御池と四条河原町で行われる。
- 巡行ルートの後半、四条通は観覧の穴場。
- 宵山では「屏風祭」で旧家の家宝が見られる。
- 7月24日午後は勇壮な神輿渡御「還幸祭」がある。
- 同日午前には華やかな「花傘巡行」も開催。
- 南観音山の「あばれ観音」など独自神事も。
- 人混みを避けてじっくり楽しみたい「通」におすすめ。
- アクセスは公共交通機関を利用するのが賢明。