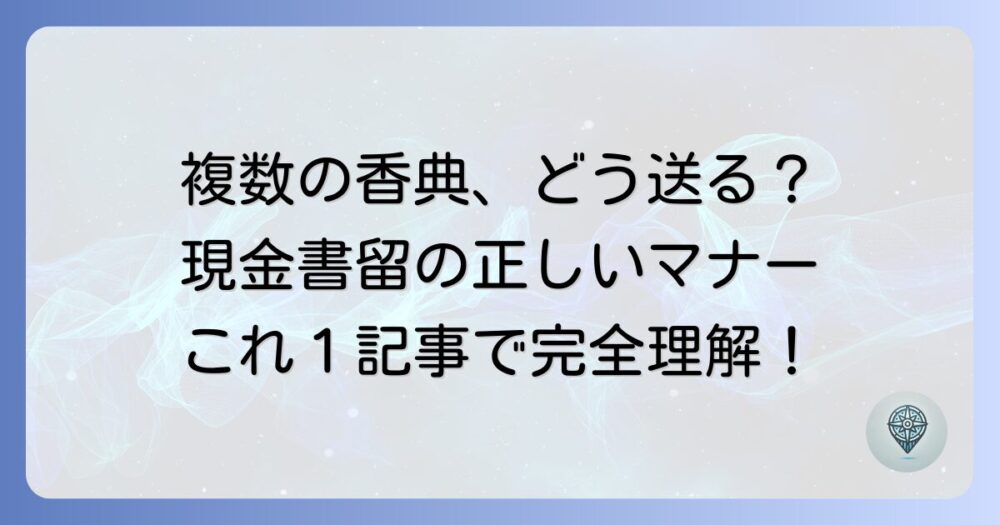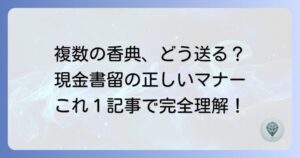葬儀に参列できない場合、香典を現金書留で送ることを検討される方もいらっしゃるでしょう。特に、複数の方の香典をまとめて送る場合や、ご自身が複数の方の代理で香典を送る場合など、どのようにすれば失礼なく、かつ確実に届けられるのか悩むことも多いのではないでしょうか。本記事では、現金書留で香典を複数送る際の具体的な方法やマナー、注意点について詳しく解説します。いざという時に慌てないためにも、ぜひ参考にしてください。
現金書留で香典を送る基本
まず、現金書留で香典を送る際の基本的なルールとマナーを確認しましょう。これらを理解しておくことで、複数送る場合にも応用が利きます。
本章では、以下の項目について解説します。
- 現金書留とは?
- 香典を現金書留で送るケース
- 現金書留の送り方
- 現金書留の料金
- 香典袋の選び方と書き方
- お悔やみの手紙を添える
現金書留とは?
現金書留とは、現金を送るための日本郵便の専用サービスです。 普通郵便や宅配便で現金を送ることは郵便法で禁止されているため、香典を送る際は必ず現金書留を利用する必要があります。 現金書留は、万が一の事故の際に損害額が補償されるのが特徴です。 また、引受けから配達までの送達過程が記録されるため、安心して送ることができます。
香典を現金書留で送るケース
本来、香典は通夜や葬儀に参列し、受付で直接手渡すのがマナーです。しかし、遠方に住んでいる、仕事の都合がつかない、体調が優れないなどの理由で参列できない場合もあるでしょう。そのような場合に、現金書留で香典を送ることはマナー違反にはあたりません。 むしろ、何もしないよりも弔意を伝えることができます。
現金書留の送り方
現金書留で香典を送る手順は以下の通りです。
- 現金書留専用封筒を用意する
郵便局の窓口で現金書留専用封筒を購入します。 香典袋が入る大きめのサイズも用意されています。 - 香典袋を準備する
現金を香典袋に入れます。香典袋の表書きや中袋の書き方は、手渡しする場合と同様です。 - お悔やみの手紙を準備する
参列できないお詫びと弔意を伝える手紙を添えるのがマナーです。 便箋は白無地のものを選び、1枚に簡潔にまとめましょう。 - 現金書留封筒に封入する
香典袋とお悔やみの手紙を現金書留封筒に入れます。 現金を直接封筒に入れるのはマナー違反です。 - 郵便局の窓口で手続きをする
現金書留封筒に必要事項を記入し、郵便局の窓口で発送手続きを行います。 ポスト投函はできません。
現金書留の料金
現金書留の料金は、基本料金(郵便物の重さによって変動)に加えて、現金書留の料金がかかります。 損害要償額(補償額)によって料金が異なり、1万円までは480円(2024年10月1日改定料金)です。 それ以上の金額を送る場合は、5,000円ごとに11円が加算されます(上限50万円)。 現金書留専用封筒の料金は別途21円かかります。
香典袋の選び方と書き方
香典袋は、故人の宗教・宗派に合わせて選びます。 仏式では「御霊前」(四十九日前)や「御仏前」(四十九日後)、神式では「御玉串料」などが一般的です。 宗教が不明な場合は「御香典」とするとよいでしょう。 香典袋の表書きや中袋の金額、氏名、住所は薄墨で書くのが正式なマナーとされていますが、現代では黒いインクのペンでも問題ないとされることもあります。 金額は旧字体の漢数字(例:金伍阡圓也)で書くのがより丁寧です。
お悔やみの手紙を添える
現金書留で香典を送る際には、お悔やみの手紙を添えるのがマナーです。 手紙には、葬儀に参列できないお詫び、故人への弔いの言葉、遺族へのいたわりの言葉などを簡潔に記します。 便箋は白無地で、封筒も白無地の一重のものを選びましょう。 手紙は、香典袋と一緒に現金書留封筒に入れます。
現金書留で香典を複数入れる場合のマナーと注意点
複数の香典を一つの現金書留で送る場合、いくつかの注意点があります。誰から誰への香典なのかが明確にわかるように、そして受け取る側に失礼がないように配慮することが大切です。
本章では、以下の項目について解説します。
- 誰の香典か分かるようにする
- 香典袋のまとめ方
- 現金書留封筒への入れ方
- お悔やみの手紙の書き方
- 送るタイミングと宛先
誰の香典か分かるようにする
複数の香典をまとめて送る場合、最も重要なのは、それぞれの香典が誰からのものなのかを明確にすることです。 受け取った遺族が混乱しないように、それぞれの香典袋に差出人の氏名、住所、金額を正確に記載しましょう。 連名で出す場合は、代表者の氏名と「外一同」と記載し、別紙に全員の氏名、住所、金額を明記して同封するのが一般的です。
例えば、会社の部署一同で出す場合は、香典袋の表書きに「〇〇部一同」と書き、中袋に代表者の連絡先と、別紙に個々の氏名と金額を記載します。 友人同士で出す場合も同様に、代表者を立てるか、全員の名前を記載した別紙を用意すると良いでしょう。
香典袋のまとめ方
複数の香典袋を現金書留封筒に入れる際は、それぞれの香典袋が汚れたり、折れ曲がったりしないように丁寧に扱いましょう。 香典袋は、現金書留封筒の大きさに合わせて選び、無理に詰め込まないように注意が必要です。 もし、香典袋のサイズが大きく、現金書留封筒に入りきらない場合は、郵便局で大きめの現金書留封筒を購入しましょう。 複数の香典袋を重ねる場合は、表書きが見えるように、向きを揃えて入れると丁寧です。
また、お札の入れ方にもマナーがあります。新札は避け、使用感のあるお札を準備するのが一般的です。 お札の向きは、肖像画が描かれている面を下にし、香典袋の裏側(封をする側)から見て人物の顔が下になるように入れます。 複数枚入れる場合は、お札の向きを揃えましょう。
現金書留封筒への入れ方
現金書留封筒には、送る現金の総額を記入する欄があります。複数の香典を同封する場合、それぞれの香典の金額を合計した総額を正確に記入してください。また、差出人の住所、氏名、電話番号も忘れずに記入します。 封筒の表面には、宛先の住所、氏名を正確に記載しましょう。 喪主宛に送るのが一般的です。
現金書留封筒に香典袋を入れる際は、封筒の表側に対して、香典袋も表向きになるように入れます。 お悔やみの手紙も同封する場合は、香典袋と一緒に入れます。 封をしたら、所定の場所に割印または署名をします。
お悔やみの手紙の書き方
複数の香典をまとめて送る場合でも、お悔やみの手紙を添えるのが望ましいです。 手紙の内容は、それぞれの香典の差出人に共通する内容で構いません。例えば、代表して送る場合は、「〇〇(代表者名)です。この度は心よりお悔やみ申し上げます。〇〇様、△△様からもお預かりいたしましたご香典を同封させていただきます。」のように、誰からの香典を同封しているのかを明記すると丁寧です。
手紙の文面では、時候の挨拶は不要です。 故人を悼む言葉、遺族へのいたわりの言葉、参列できないお詫びなどを簡潔に述べましょう。 忌み言葉(「重ね重ね」「たびたび」など)や、生死に関する直接的な表現は避けるのがマナーです。
送るタイミングと宛先
香典を送るタイミングは、訃報を受けたらなるべく早く、通夜や葬儀に間に合うように送るのが理想的です。 しかし、葬儀後に知った場合は、葬儀後1週間から1ヶ月以内を目安に送るとよいでしょう。 あまり早すぎても、また遅すぎても遺族の負担になる可能性があるため配慮が必要です。
宛先は、基本的には喪主の自宅宛てに送ります。 葬儀会場に送る場合は、事前に会場が現金書留の受け取りに対応しているか、また誰宛に送ればよいかを確認しておきましょう。 会場によっては受け取りができない場合もあります。
現金書留で香典を複数送る際のQ&A
現金書留で香典を複数送る際に疑問に思いがちな点をQ&A形式でまとめました。
Q1. 現金書留の封筒はどこで買えますか?
現金書留専用封筒は、全国の郵便局の窓口で購入できます。 サイズは通常サイズと、香典袋などが入る大きめのサイズがあります。 料金は1枚21円です(2024年5月現在)。
Q2. 香典袋はどんなものを選べばいいですか?
香典袋は、故人の宗教・宗派に合わせて選びます。 仏式であれば白黒または双銀の結び切りの水引がついたもの、神式であれば双白の結び切りの水引がついたものなどが一般的です。 宗教が不明な場合は、白無地の封筒に「御香典」と表書きするものでも構いません。 金額に見合った格の香典袋を選びましょう。
Q3. お悔やみの手紙は必ず必要ですか?
必須ではありませんが、香典を送る際にはお悔やみの手紙を添えるのが丁寧なマナーとされています。 特に遠方で参列できない場合など、弔意を伝える大切な手段となります。 短い文章でも構いませんので、心を込めて書きましょう。
Q4. 連名で香典を送る場合、表書きはどうすればいいですか?
3名程度までであれば、全員の氏名を右から目上の人順に記載します。 4名以上の場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左下に「外一同」と書くか、会社や団体名であれば「〇〇部一同」などと記載します。 そして、別紙に全員の氏名、住所、金額を明記して中袋に同封します。
Q5. 現金書留で送る場合、香典袋の中のお金の入れ方に決まりはありますか?
はい、あります。お札は新札を避け、使用感のあるものを用意するのが一般的です。 新札しかない場合は、一度折り目を付けてから入れるとよいでしょう。 お札の向きは、肖像画が描かれている面を下にし、香典袋の裏側(封をする側)から見て人物の顔が下になるように入れます。 複数枚入れる場合は、お札の向きを揃えましょう。
Q6. 複数の香典を1つの現金書留封筒に入れても大丈夫ですか?
はい、問題ありません。ただし、それぞれの香典が誰からのものか、金額はいくらかが明確にわかるように、各香典袋に必要事項をきちんと記載することが重要です。 受け取る側が混乱しないよう、配慮しましょう。
Q7. 現金書留の料金はいくらですか?
現金書留の料金は、基本料金(郵便物の重さで決まります)と現金書留の加算料金の合計です。 加算料金は、送る現金の額(損害要償額)によって異なり、1万円までは480円(2024年10月1日改定料金)です。 1万円を超え50万円までは、5千円ごとに11円が加算されます。 これに現金書留用封筒代21円が別途かかります。
Q8. 香典を送るタイミングはいつがいいですか?
訃報を受けたら、できるだけ早く送るのが望ましいです。 通夜や葬儀に間に合うように手配しましょう。 間に合わない場合は、葬儀後1週間から1ヶ月以内を目安に、喪主の自宅へ送ります。 あまり遅くなると香典返しなどの手配で遺族に二度手間をかけてしまう可能性があるため注意が必要です。
まとめ
- 現金書留で香典を送ることはマナー違反ではない。
- 現金を送る際は必ず現金書留を利用する。
- 現金書留専用封筒と香典袋、お悔やみの手紙を用意する。
- 複数の香典を送る際は、誰からの香典か明確にする。
- 香典袋には差出人情報と金額を正確に記載する。
- 連名の場合は代表者名を書き、別紙に全員の情報を記載する。
- 現金書留封筒には送る現金の総額を記入する。
- お悔やみの手紙を添えて弔意を伝える。
- 送るタイミングは訃報を受けたら早めに、または葬儀後1週間~1ヶ月以内。
- 宛先は基本的に喪主の自宅宛てにする。
- 葬儀会場へ送る場合は事前に受け取り可能か確認する。
- 現金書留の料金は基本料金+加算料金+封筒代。
- お札は新札を避け、向きを揃えて入れる。
- 香典袋は故人の宗教に合わせて選ぶ。
- 不明な場合は「御香典」が無難。
新着記事