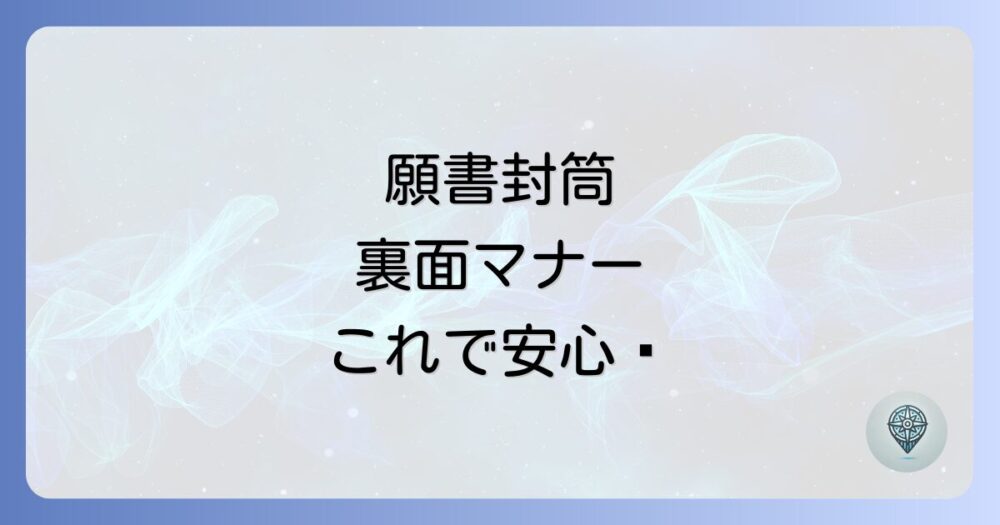受験や資格試験の際に提出する願書。その願書を入れる封筒の裏面の書き方について、詳しく知りたいと思っていませんか?「自分の住所や名前はどこに書けばいいの?」「日付は必要?」「〆(しめ)マークは書くべき?」など、細かい疑問がたくさんあるかもしれません。
本記事では、願書用封筒の裏面の正しい書き方を、縦書き・横書きのパターン別に分かりやすく解説します。また、封筒の選び方や、書き損じた場合の対処法、郵送時の注意点など、願書提出に関するあらゆる疑問を解消できるよう、情報を網羅しました。この記事を読めば、自信を持って願書を提出できるようになるでしょう。
願書用封筒の裏面に記載する基本情報
願書用封筒の裏面には、主に以下の情報を記載します。これらの情報は、万が一、宛先不明で返送される場合や、学校側が差出人を確認する際に必要となります。正確かつ丁寧に記入しましょう。
- 差出人の郵便番号
- 差出人の住所
- 差出人の氏名
- 投函日(日付) (必須ではないが、記載しておくと丁寧な印象に)
- 封締め(「〆」や「封」など) (必須ではないが、マナーとして記載することが多い)
差出人の郵便番号・住所・氏名の書き方
差出人の情報は、封筒の裏面左下に記載するのが一般的です。都道府県名から省略せずに、建物名や部屋番号まで正確に記入しましょう。 氏名は、住所の左側に、住所よりも少し大きめの文字で書くとバランスが良いです。保護者名も併記するよう指示がある場合は、住所の左側に保護者氏名、その下に「方」と書き、封筒の中央寄りに受験者本人の氏名を記載します。
特に重要なのは、住所を「〇-〇-〇」のようにハイフンで省略せず、「〇丁目〇番地〇号」と正式な表記で書くことです。 これは、公的な書類を送付する際のマナーとして覚えておきましょう。
また、使用するペンは、黒色の油性ボールペンやサインペンが推奨されます。 水性ペンは雨などでにじむ可能性があり、油性マジックは裏写りする可能性があるため避けた方が無難です。 ペン先の太さも、細すぎると読みにくいため、1.0mm以上のものが好ましいでしょう。
投函日(日付)の書き方
投函日は、封筒の裏面の左上に記載するのが一般的です。 縦書きの場合は漢数字(例:令和六年五月十四日)、横書きの場合はアラビア数字(例:2024.5.14)で記入します。 必須ではありませんが、いつ投函したのかを明確にするために記載しておくと、より丁寧な印象を与えることができます。
封締め(「〆」「封」「緘」)の書き方
封締めは、封筒を糊付けした後に、フラップ(フタ)と本体が重なる部分に書く印のことです。 「〆」の他に「封」や「緘」といった文字も使われます。 これは、「確かに封をしました」「途中で誰にも開封されていません」という意思表示になります。 願書の封筒に必ず記載しなければならないというルールはありませんが、書いておく方が一般的です。 「〆」マークは、「締」という字を簡略化したものであり、「×(バツ)」ではないので注意しましょう。
封締めは、必ず封をしてから書きましょう。 封をする前に書くと、印がずれてしまう可能性があります。
【パターン別】願書用封筒裏面の書き方
封筒の裏面の書き方は、縦書きか横書きかによってレイアウトが異なります。どちらの書き方が正しいということはありませんが、表面の宛名書きの形式に合わせるのが一般的です。つまり、表面が縦書きなら裏面も縦書き、表面が横書きなら裏面も横書きにします。
ここでは、それぞれのパターンについて詳しく解説します。
- 縦書きの場合
- 横書きの場合
縦書きの場合
縦書きで裏面を書く場合、差出人の住所と氏名は封筒の中央、または左下に配置します。
中央に書く場合:
- 郵便番号は、封筒の継ぎ目の右側に横書きで記載するか、算用数字で縦書きします。
- 住所は、郵便番号の下に、右から左へ縦書きで記入します。番地などの数字は漢数字を用います(例:一丁目二番地三号)。
- 氏名は、住所の左隣に、住所よりも少し大きめの文字で縦書きします。
- 投函日は、封筒の左上に縦書きで漢数字で記入します。
- 封締めは、フラップの中央に書きます。
左下に書く場合:
- 郵便番号は、封筒の左下に横書きで記載するか、算用数字で縦書きします。
- 住所は、郵便番号の下に、右から左へ縦書きで記入します。
- 氏名は、住所の左隣に、住所よりも少し大きめの文字で縦書きします。
- 投函日は、封筒の左上に縦書きで漢数字で記入します。
- 封締めは、フラップの中央に書きます。
一般的には、左下に書く方がスペースを有効活用でき、バランスも取りやすいでしょう。
横書きの場合
表面の宛名が横書きの場合や、学校から横書きの指定がある場合は、裏面も横書きで記入します。
- 郵便番号は、封筒の左下、または右下に横書きで記載します。
- 住所は、郵便番号の下に横書きで記入します。番地などの数字はアラビア数字を用います(例:1-2-3)。
- 氏名は、住所の下、または住所の右隣に横書きします。
- 投函日は、封筒の左上にアラビア数字で横書きします。
- 封締めは、フラップの中央に書きます。
横書きの場合、差出人の情報は封筒の下半分、中央よりやや右下にまとめて記載することが多いです。 郵便番号、住所、氏名の順で上から下に書きます。住所の書き始めと氏名の書き始めを揃え、住所の書き終わりと氏名の書き終わりを揃えると、美しく見えます。
願書用封筒の選び方と注意点
願書を入れる封筒は、学校から指定がある場合は必ずその封筒を使用しましょう。 指定がない場合は、自分で用意する必要があります。その際の選び方と注意点について解説します。
- 封筒のサイズ
- 封筒の色
- 封筒の材質
- 書き損じの対処法
封筒のサイズ
願書はA4サイズ(210mm × 297mm)が一般的です。そのため、願書を折らずに入れられる「角形2号(角2)」サイズ(240mm × 332mm)の封筒を選びましょう。 角形A4号(角A4)も使用可能ですが、書類に厚みがあると入らない可能性があるため、角2が無難です。 長形3号など、願書を折らなければ入らないサイズの封筒は避けましょう。
封筒の色
封筒の色については、特に指定がない限り、白色または茶色の無地のものを選びましょう。 一般的に、白色の封筒の方がよりフォーマルな印象を与えるとされていますが、茶色の封筒でも問題ありません。 学校によっては、白を推奨している場合もあるため、募集要項などを確認しましょう。 迷った場合は、白色を選んでおけば間違いありません。
封筒の材質
封筒の材質は、中身が透けない程度の厚みのあるものを選びましょう。 あまりにも薄いと、中の書類が透けて見えたり、郵送中に破損したりする可能性があります。
書き損じの対処法
万が一、封筒の宛名や差出人情報を書き損じてしまった場合は、修正テープや修正液、二重線での訂正は避け、新しい封筒に書き直すのがマナーです。 特に願書のような重要な書類を送る場合は、相手に失礼な印象を与えかねません。 学校指定の封筒の場合は、書き損じに備えて複数枚用意しておくと安心です。 どうしても修正が必要な場合は、修正箇所が目立たないように最小限に留めるべきですが、原則は書き直しと考えましょう。
願書提出時のその他のマナー
封筒の裏面の書き方以外にも、願書提出時にはいくつか注意しておきたいマナーがあります。スムーズな手続きのために、以下の点も確認しておきましょう。
- 「願書在中」の記載
- 封の仕方
- 郵送方法
- 提出期限の確認
「願書在中」の記載
封筒の表面の左下(縦書きの場合)または左側(横書きの場合)には、赤色のペンで「願書在中」または「入学願書在中」と記載し、四角で囲みましょう。 これは、他の郵便物と区別し、重要な書類であることを示すためのものです。
封の仕方
願書を入れた封筒は、のりを使ってしっかりと封をしましょう。 スティックのりや両面テープが、シワになりにくく綺麗に仕上がるためおすすめです。 セロハンテープは剥がれやすく、見た目もあまり良くないため避けましょう。 のり付けした後は、前述の通り「〆」などの封締めを記載します。
郵送方法
願書は非常に重要な書類ですので、普通郵便ではなく、「簡易書留」で郵送するのが一般的です。 簡易書留は、郵便物の引受けと配達を記録し、万が一の事故の場合には実損額の賠償も行われるため、安心して送ることができます。学校によっては郵送方法が指定されている場合もあるので、募集要項を必ず確認しましょう。
提出期限の確認
願書の提出には、「必着」と「当日消印有効」の2つのケースがあります。
- 必着:指定された期日までに、学校に願書が到着している必要があります。
- 当日消印有効:指定された期日の郵便局の消印が押されていれば、期日後に学校に到着しても受理されます。
どちらのケースかしっかりと確認し、余裕を持って提出するようにしましょう。
よくある質問
願書の封筒の裏面に日付は必ず書くべきですか?
必須ではありませんが、投函日を記載しておくと、いつ送付されたものかが明確になり、より丁寧な印象になります。 縦書きの場合は漢数字、横書きの場合はアラビア数字で、封筒の裏面の左上に記載するのが一般的です。
封筒の裏面に書く差出人の名前は親の名前でも良いですか?
原則として、差出人は受験者本人の氏名を書きます。 ただし、学校からの指示で保護者名を併記するよう求められている場合は、その指示に従ってください。 その場合、住所の左側に保護者氏名、その下に「方」と書き、封筒の中央寄りに受験者本人の氏名を記載するなどの方法があります。
願書の封筒を書き損じた場合、修正テープを使っても良いですか?
修正テープや修正液の使用は避け、新しい封筒に書き直すのがマナーです。 特に願書のような重要な書類では、訂正跡があると相手に良い印象を与えません。学校指定の封筒の場合は、予備を多めに用意しておくと安心です。
封筒の「〆」マークは必ず必要ですか?
必ずしも必要というわけではありませんが、「確かに封をしました」という意思表示として書くのが一般的です。 「〆」の他に「封」や「緘」といった文字も使われます。 書く場合は、封筒を糊付けした後に、フラップと本体が重なる中央部分に記載します。
願書を入れる封筒の色は茶色でも大丈夫ですか?
特に指定がない限り、茶色の封筒でも問題ありません。 ただし、白色の封筒の方がよりフォーマルな印象を与えるとされています。 迷った場合や、より丁寧な印象を与えたい場合は、白色の封筒を選ぶと良いでしょう。 学校から色の指定がある場合は、必ずその指示に従ってください。
願書はクリアファイルに入れて送った方が良いですか?
願書が折れ曲がるのを防ぐためにクリアファイルに入れたくなるかもしれませんが、基本的には不要です。 学校側で大量の願書を処理する際に、クリアファイルがかえって手間になることがあります。 クリップ留めも同様の理由で避けた方が良いでしょう。 学校から特に指示がない限り、願書はそのまま封筒に入れて問題ありません。
願書を郵送する際、普通郵便でも大丈夫ですか?
願書は非常に重要な書類ですので、普通郵便ではなく「簡易書留」で郵送することを強くおすすめします。 簡易書留は、配達状況の追跡ができ、万が一の際の補償もあるため安心です。学校から郵送方法の指定がある場合は、その指示に従ってください。
まとめ
- 願書封筒裏面には差出人の郵便番号・住所・氏名・日付・封締めを記載。
- 住所は都道府県から省略せず、正式な番地表記で。
- 氏名は受験者本人。保護者名は指示がある場合のみ。
- 日付は任意だが、書くと丁寧。左上に漢数字かアラビア数字で。
- 封締め「〆」は任意だが、書くのが一般的。封をしてから書く。
- 縦書きの場合、差出人情報は中央か左下に。数字は漢数字。
- 横書きの場合、差出人情報は下半分右寄りに。数字はアラビア数字。
- 封筒サイズはA4を折らずに入れられる角2号が基本。
- 封筒の色は白か茶色。迷ったら白が無難。
- 書き損じは修正せず、新しい封筒に書き直すのがマナー。
- 表面左下に赤字で「願書在中」と記載し四角で囲む。
- 封はのり付けし、セロハンテープは避ける。
- 郵送は「簡易書留」が推奨される。
- 提出期限は「必着」か「当日消印有効」かを確認。
- クリアファイルやクリップは基本的に不要。
新着記事