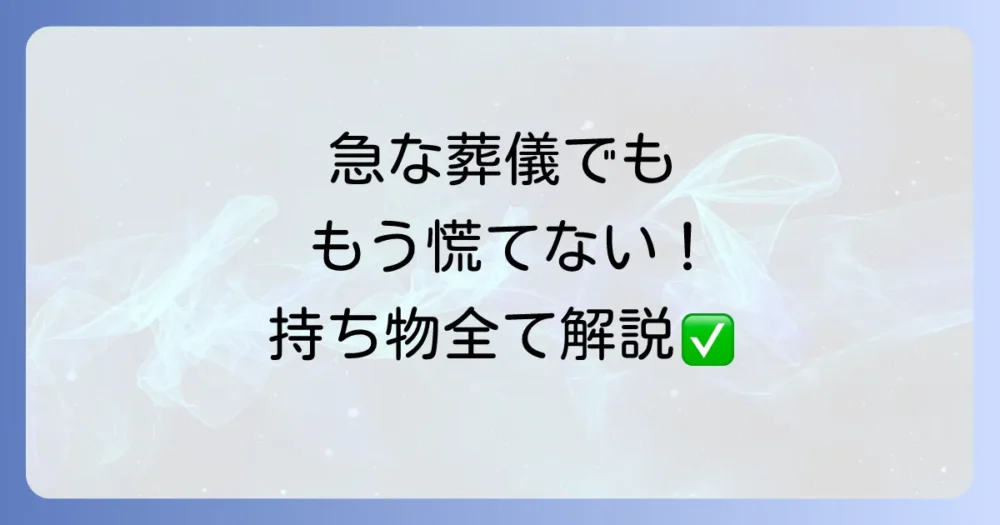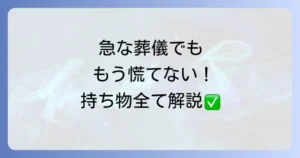突然の訃報に、何を持っていけば良いか分からず戸惑っていませんか?故人を偲ぶ大切な場であるお葬式では、失礼のないようにマナーを守った持ち物を準備することが重要です。しかし、いざという時に何が必要なのか、すべてを思い出すのは難しいものです。
本記事では、葬儀に参列する際の持ち物を網羅したチェックリストを、男性・女性・子供別に詳しくご紹介します。香典の準備や服装のマナー、急な参列で準備が間に合わない場合の対処法まで、これさえ読めば誰でも安心して葬儀に臨めるよう、分かりやすく解説します。ぜひ、最後までお読みいただき、万全の準備を整えてください。
【葬式持ち物チェックリスト】まずはこれだけ!絶対に忘れてはいけない必須アイテム
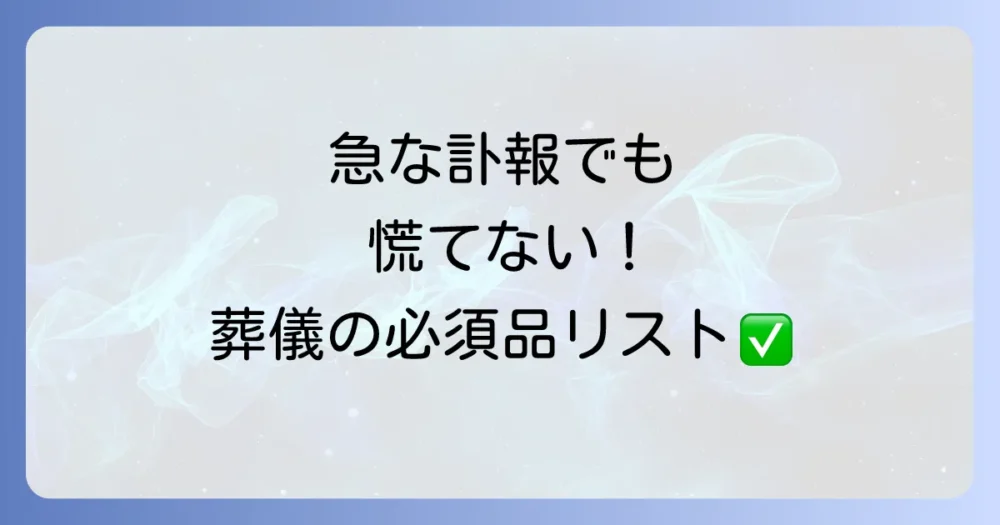
お葬式に参列する際、まず最低限これだけは揃えておきたいという必須アイテムがあります。急な知らせで時間がない場合でも、これらの持ち物さえあれば、ひとまずマナー違反になることはありません。落ち着いて準備ができるよう、一つひとつ確認していきましょう。
この章では、以下の絶対に忘れてはいけない持ち物について解説します。
- 香典(不祝儀袋)
- 袱紗(ふくさ)
- 数珠(じゅず)
- 黒いバッグ
- ハンカチ・ティッシュ
- スマートフォン・携帯電話
- 財布
香典(不祝儀袋)
香典は、故人への供養の気持ちと、遺族の金銭的な負担を助ける意味合いで渡すお金です。 香典を辞退されている場合を除き、持参するのがマナーです。 香典袋は「不祝儀袋」と呼ばれ、白黒または双銀の水引が結ばれているものを選びましょう。 表書きは、宗教や宗派によって異なりますが、わからない場合は「御霊前」と書かれたものを選ぶのが一般的です。 ただし、浄土真宗では亡くなるとすぐに仏になると考えられているため、「御仏前」を使用します。 新札を包むのは「不幸を予期していた」とされマナー違反なので、手元に新札しかない場合は一度折り目を付けてから入れましょう。
袱紗(ふくさ)
香典袋をそのままバッグやポケットに入れて持ち運ぶのはマナー違反です。必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。 袱紗には、香典袋が汚れたり水引が崩れたりするのを防ぐ役割と、相手への弔意を示す意味合いがあります。 弔事では、紺、深緑、グレーなどの寒色系の色の袱紗を選びます。 紫色の袱紗は慶弔両用で使えるため、一つ持っておくと便利です。 包み方は、袱紗をひし形に広げ、中央よりやや右に香典袋を置き、右、下、上、左の順でたたみます。 渡す直前に袱紗から取り出し、相手から見て正面になるように向きを変えて両手で渡します。
数珠(じゅず)
数珠は、仏式の葬儀に参列する際の必需品です。 本来はお経を読む回数を数えるための仏具ですが、現在では故人への敬意や冥福を祈る気持ちを表すものとして、参列者も持つのが一般的になっています。 数珠には宗派ごとに正式な「本式数珠」と、宗派を問わず使える「略式数珠」があります。 自分の宗派と違う葬儀に参列する場合でも、自身の数珠を持参して問題ありません。 数珠の貸し借りはマナー違反とされているため、持っていない場合はこの機会に用意しておくことをおすすめします。 葬儀中は左手で持つのが基本です。
黒いバッグ
葬儀に持っていくバッグは、光沢のない黒無地の布製のものが最も望ましいとされています。 革製品は殺生を連想させるため避けるのが無難ですが、光沢のないものであれば許容される場合もあります。 金具が目立つものや、ブランドのロゴが大きく入っているデザインは避け、シンプルで小ぶりなハンドバッグを選びましょう。 男性は基本的にバッグを持たず、必要なものはスーツのポケットに入れますが、荷物が多い場合は黒のクラッチバッグやセカンドバッグを使用します。
ハンカチ・ティッシュ
涙を拭ったり、手を清めたりする際にハンカチは欠かせません。色は白か黒の無地を選びましょう。 柄物やタオル地のハンカチはカジュアルな印象を与えるため避けた方が無難です。 ティッシュも同様に、ケースに入っている場合は白か黒のシンプルなものを選びましょう。予期せぬ場面で必要になることもあるため、忘れずに持参してください。
スマートフォン・携帯電話
会場までの地図を確認したり、連絡を取ったりするためにスマートフォンは必要ですが、葬儀中は必ずマナーモードに設定するか、電源を切っておきましょう。着信音やバイブレーションの音が鳴り響くのは、厳粛な雰囲気を壊す大変失礼な行為です。アラーム設定なども事前に確認し、音が鳴らないように注意が必要です。
財布
香典とは別に、交通費や急な出費に備えて財布も必要です。ただし、派手な色やデザインの長財布などは避け、バッグと同様に黒や紺などの落ち着いた色のシンプルなものを選ぶのが望ましいです。普段使いの財布でも問題ありませんが、あまりにカジュアルなものや装飾が多いものは、サブバッグなどに入れて見えないように配慮すると良いでしょう。
【男女別】葬式の持ち物チェックリスト|身だしなみも忘れずに
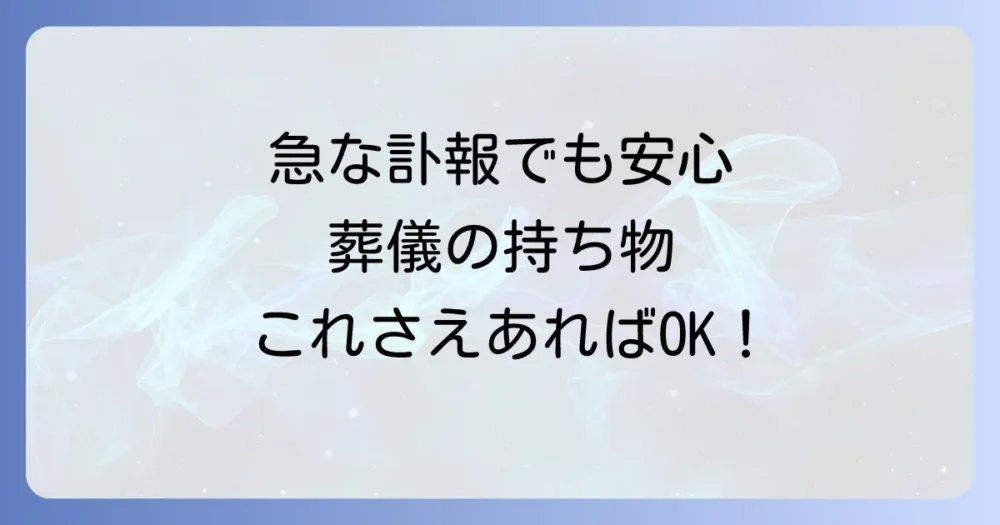
葬儀に参列する際の持ち物は、基本的な必須アイテムに加えて、性別によって少し異なります。特に女性は、メイク道具やストッキングの予備など、細やかな配慮が必要です。男性も、普段はあまり意識しない小物選びに注意が必要です。この章では、男女それぞれの持ち物と、服装や身だしなみのポイントをチェックリスト形式で詳しく解説します。故人やご遺族に失礼のないよう、しっかりと確認しておきましょう。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 男性の持ち物と服装のポイント
- 女性の持ち物と服装・メイクのポイント
男性の持ち物と服装のポイント
男性の場合、持ち物は比較的シンプルですが、服装や小物のマナーには注意が必要です。基本的にはバッグを持たず、必要なものはスーツのポケットに収めるのが一般的です。 遠方からの参列などで荷物が多くなる場合は、黒無地のシンプルなセカンドバッグやクラッチバッグを用意しましょう。
服装は、光沢のないブラックスーツ(喪服)が基本です。 ワイシャツは白無地、ネクタイ、ベルト、靴下、革靴はすべて黒で統一します。 ネクタイピンやカフスボタンなどの光るアクセサリーは、結婚指輪以外は外すのがマナーです。 腕時計も、派手なデザインやゴールドのものは避け、シンプルなものを選ぶか、外しておきましょう。 髪型は清潔感を第一に整え、香りの強い整髪料や香水の使用は控えます。
以下に男性の持ち物チェックリストをまとめました。
- 必須アイテム:
- 香典(袱紗に包む)
- 数珠
- 白いハンカチ
- ティッシュ
- 財布
- スマートフォン
- 服装・小物:
- ブラックスーツ(喪服)
- 白無地のワイシャツ
- 黒無地のネクタイ
- 黒いベルト
- 黒い靴下
- 黒い革靴(光沢のないもの)
- あると便利なもの:
- 黒いセカンドバッグやクラッチバッグ
- 黒いコート(冬場)
- 折りたたみ傘(黒や紺など地味な色)
女性の持ち物と服装・メイクのポイント
女性は男性に比べて持ち物が多くなる傾向があります。メイク道具や予備のストッキングなど、女性ならではのアイテムも準備しておくと安心です。バッグは、光沢のない黒無地の布製ハンドバッグが基本です。 荷物が入りきらない場合は、同じく黒無地のサブバッグを用意しましょう。
服装は、黒のアンサンブルやワンピース、スーツなどのブラックフォーマルを着用します。 肌の露出は控え、スカート丈は膝が隠れる長さを選びましょう。 ストッキングは、30デニール以下の薄手の黒が基本です。 伝線したときのために、予備を1足持っていくと安心です。 靴は、光沢のない黒のシンプルなパンプスを選び、ヒールの高さは3~5cm程度のものが望ましいです。
アクセサリーは、結婚指輪以外は基本的に外しますが、つける場合は一連のパールネックレスや一粒パールのイヤリング(ピアス)のみとされています。 二連以上のネックレスは「不幸が重なる」ことを連想させるためNGです。 メイクは、派手な色を使わない「片化粧」を心がけ、ナチュラルに仕上げます。髪が長い場合は、黒のゴムやバレッタでシンプルにまとめましょう。 香水はつけません。
以下に女性の持ち物チェックリストをまとめました。
- 必須アイテム:
- 香典(袱紗に包む)
- 数珠
- 白または黒のハンカチ
- ティッシュ
- 財布
- スマートフォン
- 黒いフォーマルバッグ
- あると便利なもの:
- 予備の黒いストッキング
- メイク直し用のポーチ(口紅、ファンデーションなど)
- 黒いサブバッグ
- 黒いコート(冬場)
- 折りたたみ傘(黒や紺など地味な色)
- 髪をまとめる黒いゴムやヘアピン
【子供・赤ちゃん連れ】葬式の持ち物チェックリスト
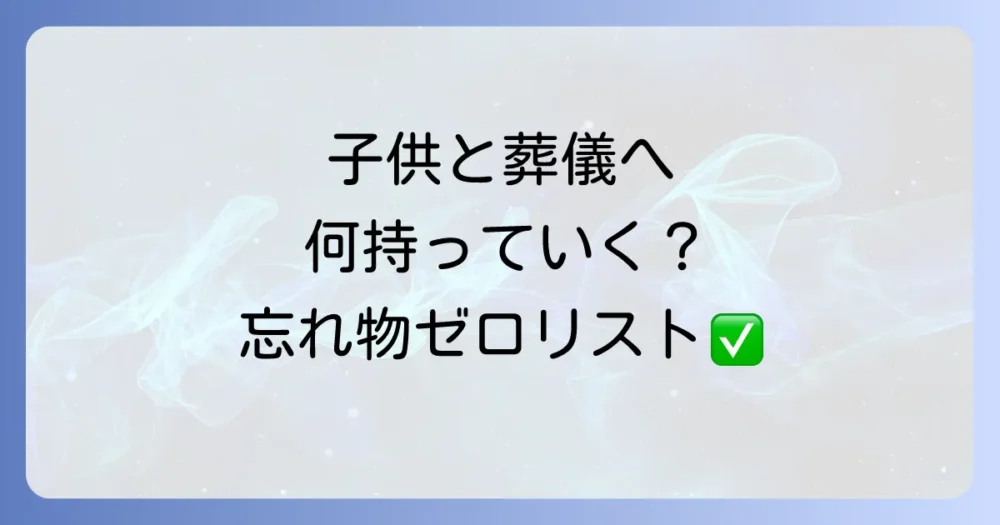
子供や赤ちゃんを連れて葬儀に参列する場合、大人の持ち物に加えて、子供用の準備も必要になります。特に赤ちゃん連れの場合は、おむつやミルクなど、荷物が多くなりがちです。また、子供が静かに過ごせるような工夫も大切です。この章では、子供や赤ちゃん連れで参列する際の持ち物と服装について、年齢別に詳しく解説します。事前にしっかりと準備をして、落ち着いて故人とお別れができるようにしましょう。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 子供の持ち物と服装
- 赤ちゃん連れの場合の持ち物
子供の持ち物と服装
子供の服装は、学校の制服があればそれが正装となります。 制服がない場合は、黒や紺、グレーなどのダークカラーを基調とした、シンプルな服装を選びましょう。 男の子なら白いシャツに黒や紺のズボン、女の子なら黒や紺のワンピースや、白いブラウスに黒いスカートなどが適しています。キャラクターものや派手なデザインの服は避けましょう。 靴や靴下も、黒や白、紺などの落ち着いた色で揃えます。
持ち物としては、子供が長時間静かに待っていられるような工夫が必要です。音の出ない絵本や塗り絵、折り紙などを持参すると良いでしょう。 ただし、ゲーム機や漫画など、周りの方の迷惑になる可能性のあるものは避けるのが無難です。 また、子供用の飲み物やおやつも、必要に応じて準備しておくと安心です。ただし、会場内で飲食が可能かどうかは事前に確認しておきましょう。
以下に子供の持ち物チェックリストをまとめました。
- 服装:
- 学校の制服(ある場合)
- ない場合:黒・紺・グレーなどの地味な色の服(ワンピース、シャツ、ズボンなど)
- 黒・白・紺などの靴下
- 黒い靴(スニーカーでも可)
- 持ち物:
- ハンカチ、ティッシュ
- 音の出ないおもちゃ(絵本、塗り絵、折り紙など)
- 飲み物、おやつ(必要に応じて)
- 汚れた時用の着替え
赤ちゃん連れの場合の持ち物
赤ちゃんを連れての参列は、特に準備が大変です。授乳やおむつ替えなど、必要なものがたくさんあります。荷物が多くなるため、大きめの黒いマザーズバッグなどをサブバッグとして用意しましょう。
服装は、白やベージュ、グレーなどの淡い色のベビー服であれば問題ありません。 赤やピンクなどのお祝いを連想させる派手な色は避けましょう。 母親の服装は、授乳しやすい前開きの黒いワンピースなどが便利です。授乳ケープも忘れずに持参しましょう。
持ち物は、普段のお出かけセットに加えて、万が一に備えて多めに準備しておくと安心です。おむつや着替えは、汚れたものを入れるビニール袋とセットで用意します。ミルクの場合は、お湯や哺乳瓶も必要です。また、ぐずった時にすぐにあやせるよう、音の出ないお気に入りのおもちゃや、抱っこ紐があると便利です。
以下に赤ちゃん連れの持ち物チェックリストをまとめました。
- 服装(赤ちゃん):
- 白、ベージュ、グレーなどの淡い色のベビー服
- 靴下
- 持ち物:
- おむつセット(おむつ、おしりふき、ビニール袋)
- ミルクセット(粉ミルク、哺乳瓶、お湯)または授乳ケープ
- 着替え(2~3セット)
- ガーゼ、タオル
- 抱っこ紐
- 音の出ないおもちゃ
- 離乳食(必要な場合)
- 大きめのサブバッグ(黒など地味な色)
【立場別】葬式の持ち物で気をつけること
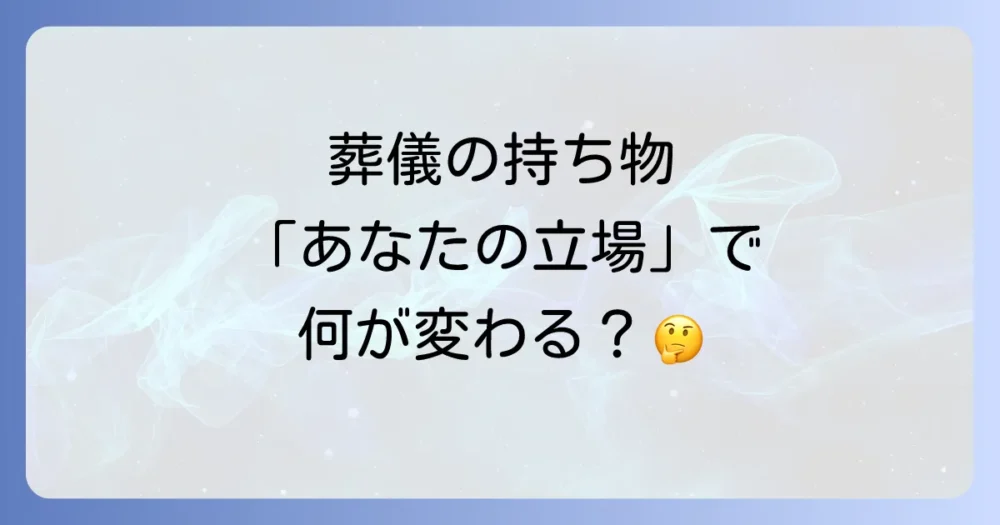
葬儀に参列する際の持ち物は、故人との関係性や自身の立場によっても少しずつ異なります。親族として参列する場合と、一般の会葬者として参列する場合では、準備しておくと良いものが変わってきます。また、受付係を頼まれた際には、さらに特別な持ち物が必要になることも。この章では、それぞれの立場に応じた持ち物のポイントを解説します。自分の立場を把握し、それに合わせた準備をすることで、よりスムーズに、そして心を込めて葬儀に臨むことができるでしょう。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 親族として参列する場合
- 一般の会葬者として参列する場合
- 受付係を頼まれた場合
親族として参列する場合
親族として参列する場合、一般の会葬者よりも斎場にいる時間が長くなることが多く、また、遺族の手伝いをする場面も考えられます。 そのため、基本的な持ち物に加えて、長時間滞在することや、お手伝いをすることを想定した準備が必要です。
例えば、着替えやエプロンなどがあると、食事の準備や片付けを手伝う際に便利です。 また、スマートフォンの充電が切れないように、モバイルバッテリーを持参すると安心でしょう。 遠方から駆けつける場合は、宿泊の準備も必要になるかもしれません。遺族は非常に忙しく、細かな気配りが難しい状況にあるため、自分のことは自分で管理できるよう、準備を万全にしておくことが大切です。また、親族間で香典の金額を合わせることもあるため、事前に相談しておくと良いでしょう。
一般の会葬者として参列する場合
一般の会葬者として参列する場合は、基本的な持ち物リストに沿って準備すれば問題ありません。 故人や遺族への弔意を示すことが最も重要ですので、マナーを守った服装と持ち物を心がけましょう。特に、香典、袱紗、数珠は忘れずに持参してください。
仕事関係で参列する場合は、名刺を持っていくと受付でスムーズです。 受付で記帳する際に、会社名や所属部署を正確に伝えることができます。ただし、名刺を渡す際は、あくまで記帳の補助として使用し、名刺交換のように渡すのは控えましょう。受付で「こちらに会社名と名前をお願いします」と差し出すのがスマートです。
受付係を頼まれた場合
遺族から受付係を頼まれた場合は、他の参列者とは異なる特別な準備が必要です。受付係は、遺族に代わって弔問客をお迎えし、香典を預かるという重要な役割を担います。そのため、スムーズに業務をこなせるような道具を揃えておくと良いでしょう。
具体的には、筆記用具(ボールペン、筆ペンなど)、香典を整理するためのノートやファイル、電卓などがあると便利です。 筆ペンは、会葬者名簿に名前を代筆する際に役立ちます。また、香典を預かる際には、誰からいくら預かったのかを正確に記録する必要があります。そのためのノートや、金額を計算するための電卓は必須と言えるでしょう。その他、細かいお金を扱うこともあるため、小銭を分けておけるケースや、手を清潔に保つためのウェットティッシュなどもあると重宝します。
【季節別】あると便利な葬式の持ち物チェックリスト
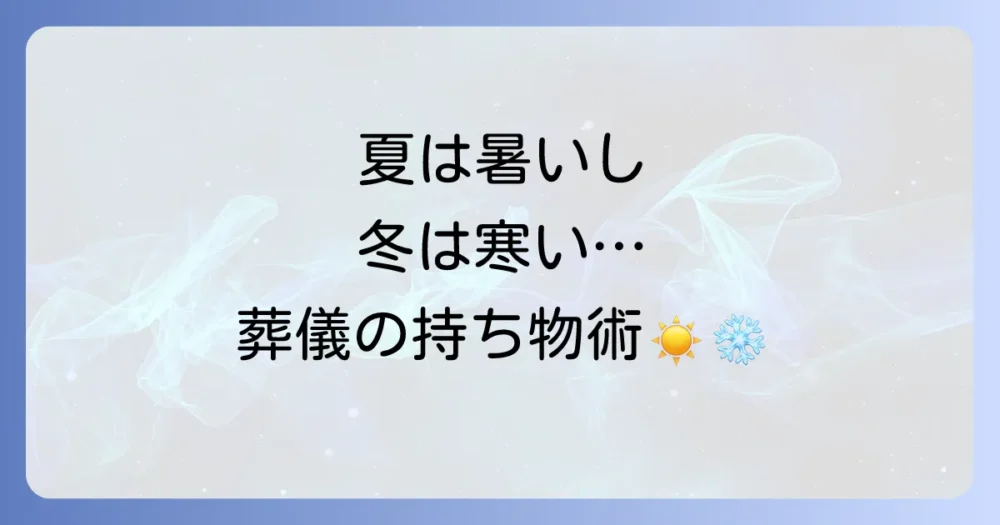
葬儀に参列する際の持ち物は、基本的なアイテムに加えて、季節に応じた準備をしておくと、より快適に過ごすことができます。特に、夏の暑さや冬の寒さは体力を消耗させるため、対策を怠らないようにしたいものです。この章では、夏と冬、それぞれの季節にあると便利な持ち物をリストアップしてご紹介します。必須ではありませんが、持っていると自分自身だけでなく、周りの方への配慮にも繋がるアイテムです。ぜひ参考にしてみてください。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 夏(暑い時期)にあると便利なもの
- 冬(寒い時期)にあると便利なもの
夏(暑い時期)にあると便利なもの
夏の葬儀は、暑さとの戦いでもあります。喪服は熱を吸収しやすい黒色であるため、熱中症対策は欠かせません。斎場内は冷房が効いていますが、屋外での待ち時間や移動中は非常に暑くなります。汗をかいても身だしなみを保てるよう、また体調を崩さないよう、以下のアイテムを準備しておくと安心です。
- 扇子やうちわ: 黒や紺など地味な色の無地のものを選びましょう。 仰々しくならないよう、静かに使うのがマナーです。
- 制汗シート: 汗のべたつきを抑え、さっぱりとさせることができます。無香料タイプを選ぶのがポイントです。
- 予備のハンカチ: 汗を拭く機会が多いため、替えのハンカチがあると清潔感を保てます。
- 日傘: 屋外で待つ時間が長い場合に役立ちます。黒や紺の無地で、シンプルなデザインのものを選びましょう。
- 塩分補給ができる飴やタブレット: 熱中症対策として、手軽に塩分を補給できるものがあると便利です。
- 冷たい飲み物: 水筒やペットボトルで持参しておくと、いつでも水分補給ができます。
冬(寒い時期)にあると便利なもの
冬の葬儀では、寒さ対策が重要になります。斎場内は暖房が効いていますが、換気のために窓が開いていたり、足元が冷えたりすることもあります。また、火葬場への移動や屋外での待ち時間は非常に寒く、体調を崩す原因にもなりかねません。体を冷やさないように、防寒対策をしっかりとして臨みましょう。
- 黒いコートや上着: ウールやカシミヤ素材の黒無地のコートが適しています。 ダウンジャケットや毛皮、革製品は殺生を連想させるため避けましょう。
- カイロ: 貼るタイプや手持ちタイプなど、複数あると便利です。 特に足元は冷えやすいので、靴用のカイロもおすすめです。
- ひざ掛け: 斎場内で足元が冷える際に役立ちます。黒や紺などの地味な色で、コンパクトにたためるものを選びましょう。
- 手袋: 屋外での移動時に重宝します。黒無地で、革製以外のものを選びましょう。
- 厚手のストッキングやタイツ(女性): 通常は薄手のストッキングがマナーですが、寒さが厳しい場合は、無地の厚手のタイツでも許容されることがあります。
- 温かい飲み物: 保温性の高い水筒に入れて持参すると、体を内側から温めることができます。
葬式の持ち物に関するマナー|香典・数珠・袱紗の正しい扱い方
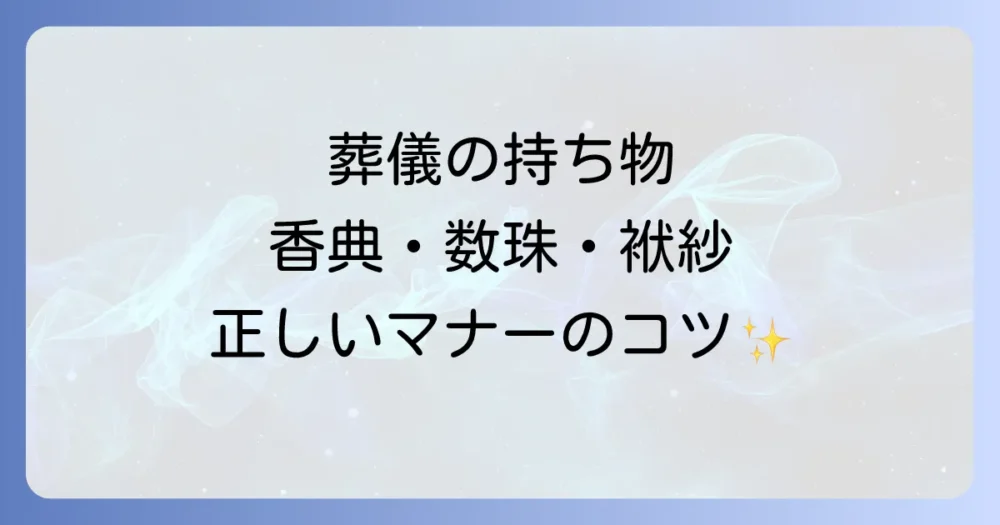
葬儀に参列する際、持ち物を揃えるだけでなく、その扱い方にもマナーがあります。特に、香典、数珠、袱紗は、故人や遺族への弔意を示す上で非常に重要な役割を担うため、正しい知識を身につけておくことが大切です。誤った使い方をしてしまうと、せっかくの気持ちが伝わらないばかりか、失礼にあたってしまう可能性も。この章では、これら3つのアイテムの正しい扱い方について、具体的な手順を交えながら詳しく解説します。自信を持って振る舞えるよう、しっかりと確認しておきましょう。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 香典の準備と渡し方のマナー
- 数珠の正しい持ち方と使い方
- 袱紗の選び方と包み方
香典の準備と渡し方のマナー
香典は、故人への最後の贈り物であり、遺族へのいたわりの気持ちを表すものです。準備から渡し方まで、一連の流れに細やかなマナーがあります。
まず、不祝儀袋の表書きは薄墨で書くのが基本です。これは「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」という気持ちを表すためです。中袋には、包んだ金額、住所、氏名を楷書で丁寧に記入します。金額は「壱、弐、参」などの大字(旧漢字)で書くとより丁寧です。
お札は、新札を避けるのがマナーです。 新札しかない場合は、一度折り目をつけてから入れましょう。お札の向きは、肖像画が描かれている面を裏側(下向き)にして揃えて入れます。これは、顔を伏せて悲しみを表すという意味合いがあります。
渡すタイミングは、受付がある場合は記帳を済ませた後です。 袱紗から香典袋を取り出し、相手から見て表書きが読めるように向きを変え、「この度はご愁傷様でございます」などのお悔やみの言葉を述べながら、両手で丁寧に渡します。
数珠の正しい持ち方と使い方
数珠は、仏様と心を通わせるための大切な仏具です。 葬儀中は、常に敬意を持って扱いましょう。
移動する時や着席している時は、左手で持ちます。 房が下になるように、輪を親指と人差し指の間にかけたり、手首にかけたりします。直接畳や椅子の上に置くのはマナー違反です。
合掌する際は、宗派によって持ち方が異なりますが、一般的には両手の親指と人差し指の間に輪をかけるようにして持ちます。 略式の数珠の場合は、左手にかけたまま右手を添えて合掌しても構いません。
焼香の際は、左手に数珠を持ち、右手で焼香を行います。 自分の宗派の数珠を持参するのが基本ですが、持っていない場合は宗派を問わない略式数珠を用意しましょう。家族間であっても貸し借りはしないのがルールです。
袱紗の選び方と包み方
袱紗は、香典を大切に扱う気持ちを表すためのものです。色や包み方にも慶事と弔事で違いがあります。
弔事用の袱紗の色は、紫、紺、深緑、グレーなどの寒色系です。 紫色は慶弔両用で使えるため、一つ持っていると非常に便利です。 慶事用の赤やオレンジなどの暖色系の袱紗は使わないように注意しましょう。
包み方は、弔事の場合「左開き」になるように包みます。 具体的な手順は以下の通りです。
- 袱紗をひし形に広げ、爪がある場合は右側にくるように置きます。
- 中央よりやや右側に香典袋を置きます。
- 右、下、上の順に角を内側に折りたたみます。
- 最後に左側を折り、右側の下に差し込むか、爪で留めます。
この包み方は「悲しみを流す」という意味合いがあり、慶事の「右開き」とは逆になります。 渡す直前に袱紗から取り出し、たたんだ袱紗の上に香典袋を乗せて渡すと、より丁寧な印象になります。
急な葬式で準備が間に合わない!持ち物の代用方法と入手場所
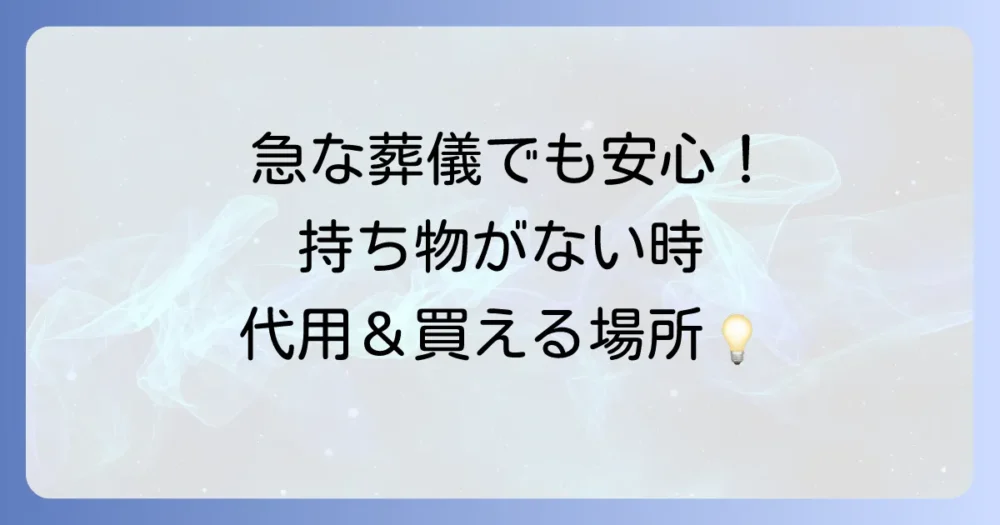
突然の訃報は、いつ訪れるかわかりません。「喪服や必要な小物を準備する時間がない!」と焦ってしまうこともあるでしょう。しかし、諦める必要はありません。急な場合でも、マナーを守りつつ参列するための代用方法や、すぐに手に入れられる場所を知っておけば、落ち着いて対応できます。この章では、いざという時に役立つ、葬儀の持ち物の代用策と、コンビニや100円ショップなど身近な場所での入手方法について解説します。慌てずに、故人を偲ぶ気持ちを最優先できるよう、ぜひ参考にしてください。
この章で解説する内容は以下の通りです。
- 数珠がない場合はどうする?
- 袱紗がない場合の代用品
- 喪服や黒いネクタイはどこで買う?
数珠がない場合はどうする?
仏式の葬儀において数珠は大切な持ち物ですが、急なことで手元にない場合もあるでしょう。しかし、数珠の貸し借りはマナー違反とされています。 これは、数珠が持ち主のお守りであり、分身のようなものと考えられているためです。
もし数珠がない場合は、無理に用意せず、数珠を持たずに参列しても問題ありません。 最も大切なのは故人を悼む気持ちです。数珠がないからといって、手を合わせる気持ちが損なわれるわけではありません。合掌する際は、数珠を持っている人と同じように、心を込めて手を合わせましょう。
どうしても気になる場合や、今後も使う機会がある場合は、葬儀場の売店や、最近ではコンビニエンスストア、100円ショップでも略式の数珠を取り扱っていることがあります。また、仏具店やデパートのフォーマルウェア売り場、オンラインストアでも購入可能です。
袱紗がない場合の代用品
香典をむき出しで持参するのは避けたいもの。しかし、専用の袱紗が手元にない場合もあるでしょう。その際は、地味な色のハンカチで代用することができます。
代用するハンカチは、黒、紺、グレー、紫などの寒色系で、無地のものを選びましょう。白でも構いません。シルクのような光沢のある素材や、柄物は避けてください。包み方は袱紗と同じで、香典袋を中央に置き、ひし形になるようにたたんでいきます。受付で渡す際は、ハンカチから取り出して、ハンカチをたたんだ上に香典袋を乗せて渡すと丁寧です。
香典袋と袱紗がセットになったものが、コンビニエンスストアや文房具店、スーパーマーケットなどで販売されていることも多いので、探してみるのも一つの手です。
喪服や黒いネクタイはどこで買う?
急な訃報で最も困るのが服装かもしれません。喪服が手元にない、またはサイズが合わないといった場合、どうすればよいのでしょうか。
男性の場合、ダークスーツ(濃紺やチャコールグレーの無地)で代用することも可能です。その際は、ワイシャツは白無地、ネクタイと靴下、靴は必ず黒で統一しましょう。黒いネクタイは、コンビニエンスストアや駅の売店、スーパーの衣料品コーナーなどで手に入ることが多いです。
女性の場合も、黒や濃紺の無地のワンピースやアンサンブルであれば、略喪服として着用できます。肌の露出を抑え、シンプルなデザインのものを選びましょう。
本格的な喪服が必要な場合は、紳士服店やデパートのフォーマルコーナー、大型スーパーの衣料品売り場などで購入できます。最近では、即日仕上げてくれる店舗も増えています。また、葬儀社や貸衣装店でレンタルするという選択肢もあります。サイズも豊富に揃っているため、急な場合でも体に合ったものを見つけやすいでしょう。
よくある質問
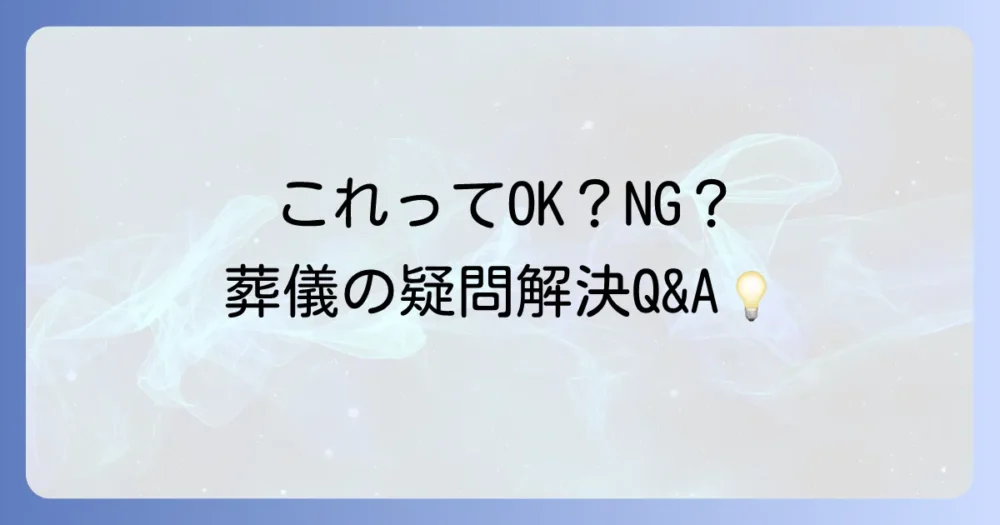
葬儀の持ち物やマナーに関しては、細かな疑問が尽きないものです。ここでは、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。いざという時に迷わないよう、事前に確認しておきましょう。
葬式にアクセサリーはつけてもいいですか?
A. 基本的に、結婚指輪以外のアクセサリーは外すのがマナーです。 ただし、洋装の場合は、一連のパール(真珠)のネックレスや、一粒タイプのパールのイヤリング(ピアス)であれば着用しても良いとされています。 パールは「涙の象徴」とされ、お悔やみの席にふさわしい宝石と考えられています。二連や三連のネックレスは「不幸が重なる」ことを連想させるため、必ず一連のものを選びましょう。 ゴールドや光り輝く宝石、派手なデザインのものは厳禁です。
結婚指輪はつけていても大丈夫ですか?
A. はい、結婚指輪はつけていても問題ありません。 葬儀の場で唯一許されているアクセサリーとも言えます。ただし、ダイヤモンドが大きくあしらわれているなど、あまりに華美なデザインの場合は、石の部分を手のひら側に回すなどの配慮をすると良いでしょう。婚約指輪も、シンプルなデザインであれば問題ないとされることもありますが、基本的には結婚指輪のみと考えておくのが無難です。
髪型や髪色で気をつけることはありますか?
A. 髪型は、清潔感を第一に、顔周りをすっきりとまとめるのが基本です。長い髪は、耳より下の位置で一つに束ねます。その際、黒のゴムやシュシュ、バレッタなど、地味でシンプルな髪留めを使用しましょう。 派手な飾りはNGです。髪色は、明るすぎる場合は、一時的に黒くするヘアカラースプレーなどを利用するのも一つの方法ですが、無理に染め直す必要はありません。大切なのは、故人を偲ぶ気持ちと、清潔感のある身だしなみです。
予備のストッキングは必要ですか?
A. はい、女性の場合は予備のストッキングを準備しておくことを強くおすすめします。 葬儀では、椅子のささくれや、移動中の些細なことでストッキングが伝線してしまうことがよくあります。伝線したまま参列するのは見苦しく、マナー違反と見なされることも。いざという時に慌てないよう、バッグに予備を1足入れておくと安心です。
傘の色に決まりはありますか?
A. はい、傘の色にも配慮が必要です。黒や紺、グレーなどの地味な色の傘が望ましいです。 派手な色や柄物の傘は、お悔やみの場にふさわしくありません。ビニール傘でも問題ありませんが、できれば色のついていない透明なものか、骨組みが黒いものを選ぶと良いでしょう。葬儀社で貸し出し用の傘を用意している場合もあります。
葬式に持っていくバッグの大きさは?
A. 葬儀に持っていくバッグは、小さいほどフォーマルとされています。 必要最低限のもの(香典、数珠、ハンカチ、財布、スマートフォンなど)が入る程度の、小ぶりなハンドバッグが基本です。 荷物が多くて入りきらない場合は、メインのバッグとは別に、黒無地のシンプルなサブバッグを用意しましょう。 サブバッグはA4サイズ程度でマチのないものが一般的です。
香典の金額の相場はいくらですか?
A. 香典の金額は、故人との関係性やご自身の年齢、社会的立場、地域の慣習などによって大きく異なります。 あくまで一般的な目安ですが、以下を参考にしてください。
- 親: 5万円~10万円
- 兄弟姉妹: 3万円~5万円
- 祖父母: 1万円~3万円
- その他の親族: 1万円~3万円
- 友人・知人: 5千円~1万円
- 会社関係者(上司・同僚・部下): 5千円~1万円
- 隣近所の方: 3千円~5千円
「4」や「9」など、死や苦を連想させる忌み数は避けるのがマナーです。 金額に迷った場合は、同じ立場の友人や同僚と相談して金額を合わせるのも良いでしょう。
まとめ
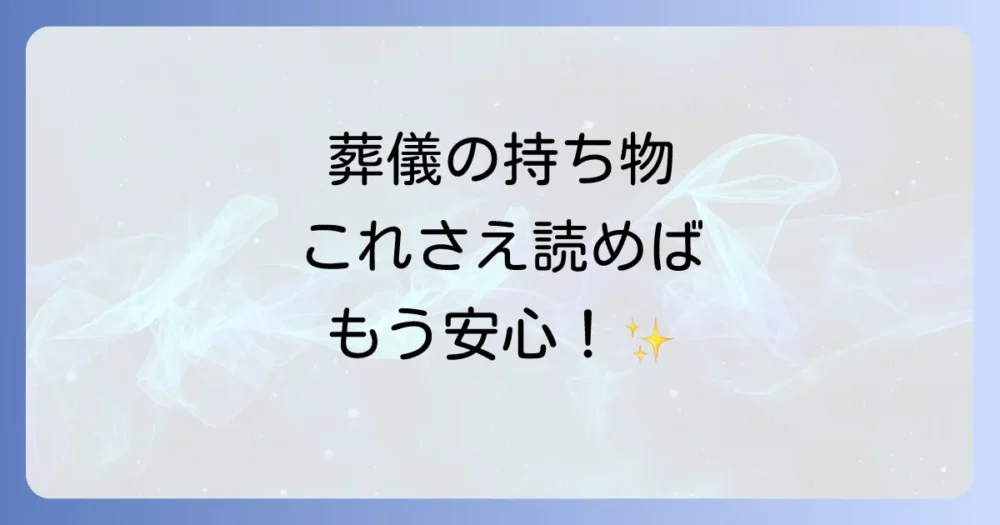
- 葬儀の必須持ち物は香典、袱紗、数珠、黒いバッグ、ハンカチです。
- 香典は袱紗に包み、数珠の貸し借りはマナー違反です。
- 男性は黒のスーツ、女性は黒のフォーマルウェアが基本服装です。
- 女性は予備のストッキングやメイク直しポーチがあると安心です。
- 子供連れは音の出ないおもちゃや着替えを準備しましょう。
- 赤ちゃん連れはおむつやミルク、抱っこ紐が必須です。
- 立場によって持ち物は異なり、親族は手伝いの準備も必要です。
- 受付係は筆記用具やノートなど、別途準備が必要です。
- 夏は扇子や制汗シート、冬はカイロやコートで季節対策をします。
- 香典の表書きは薄墨で、新札は避けるのがマナーです。
- 数珠は左手で持ち、直接床に置かないようにしましょう。
- 袱紗は弔事用の色を選び、左開きになるように包みます。
- 急な場合は、ダークスーツや地味な色のハンカチで代用可能です。
- アクセサリーは結婚指輪と一連のパールのみが基本です。
- 香典の金額は故人との関係性や年齢によって変わります。
新着記事