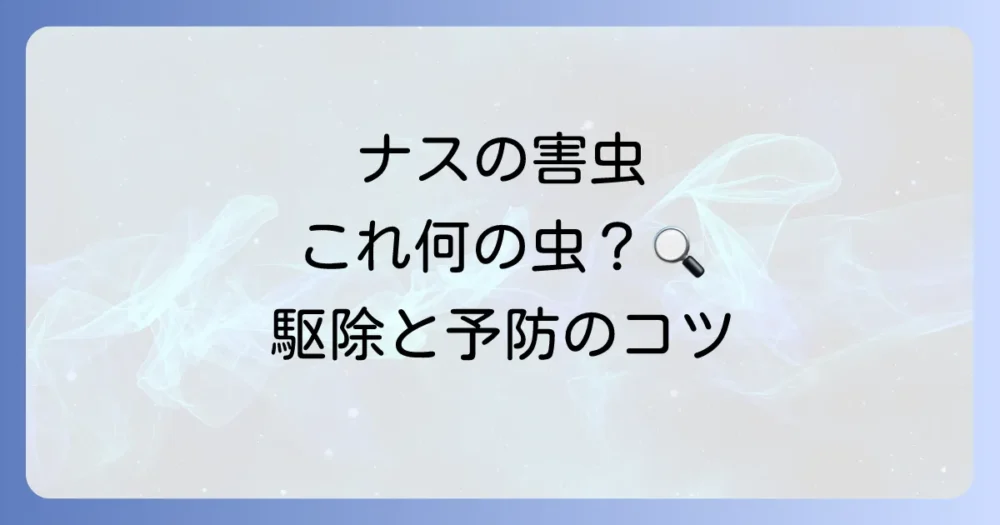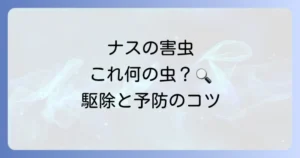家庭菜園で人気のナス。みずみずしい実が育っていく様子は、毎日の楽しみですよね。しかし、そんな大切なナスを狙う厄介な存在が「害虫」です。気づいたときには葉がボロボロに…なんて経験はありませんか?本記事では、ナスに発生しやすい害虫の種類から、被害症状による見分け方、そして農薬に頼らない駆使・予防法まで、プロの視点で徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたも害虫に負けないナス栽培の達人になれるはずです。
被害症状でチェック!これって何の害虫?
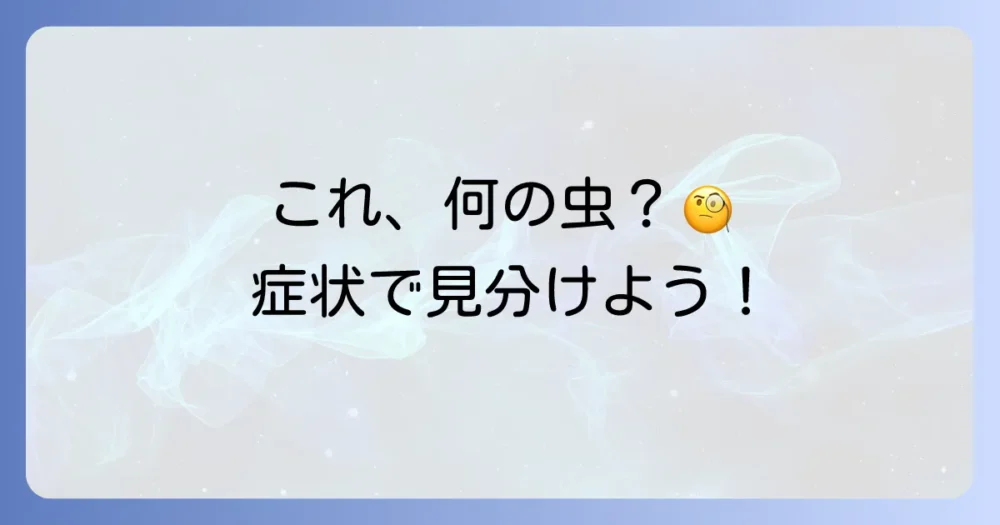
「葉に穴が…」「なんだかベタベタする…」そんなナスの異変は、害虫からのSOSサインかもしれません。まずは、被害の状況から原因となっている害虫を突き止めることが対策の第一歩です。ここでは、代表的な被害症状と、その原因と考えられる害虫について解説します。
- 葉が縮れたり、新芽がベタベタしている
- 葉に白い斑点やかすり傷、クモの巣のような糸がある
- テントウムシみたいな虫がいるのに、葉が網目状にスカスカ
- 株に触れると白い小さな虫がワッと舞う
- 夜の間に葉や実に大きな穴が開けられている
- 葉に白いペンで落書きしたような筋がある
- 花が変色したり、実の表面がザラザラになる
【症状別】なすを襲う主要な害虫7選!特徴と見分け方
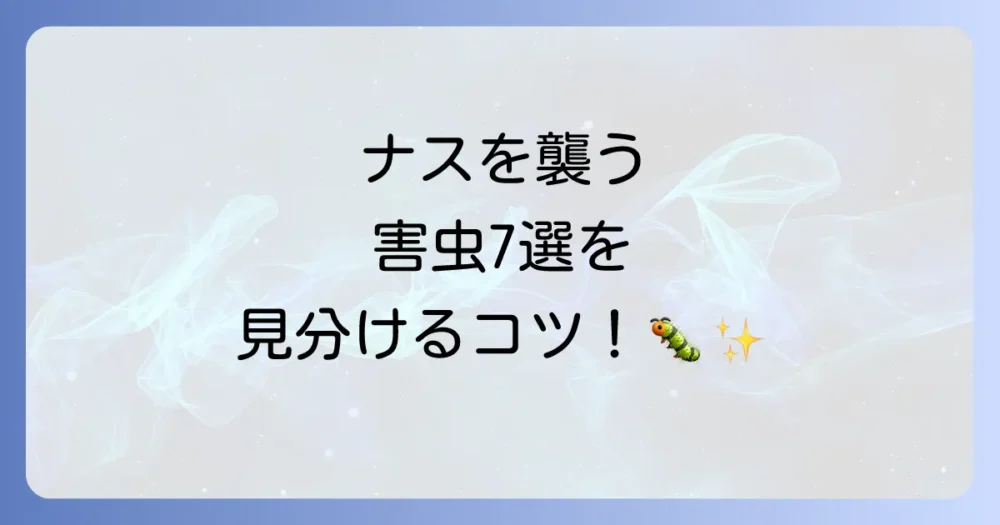
ここでは、ナスに特に発生しやすい7種類の害虫について、その特徴、発生時期、具体的な被害を写真付きで詳しく解説します。正しい知識を身につけて、早期発見・早期対策につなげましょう。
アブラムシ|新芽や葉裏にびっしり
体長1~4mmほどの小さな虫で、緑色や黒色など種類によって体色が異なります。 ナスでは特にワタアブラムシやモモアカアブラムシがよく見られます。 春から秋にかけて、特に5月~6月と9月~10月に発生しやすく、風通しの悪い環境や窒素過多の肥料で増殖します。
新芽や葉の裏に群生し、汁を吸って株を弱らせるのが特徴です。吸汁されると葉が縮れたり、生育が悪くなったりします。 また、アブラムシの排泄物(甘露)が原因で、葉が黒いすすで覆われたようになる「すす病」を誘発することもあります。 さらに、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第すぐに対処が必要です。
ハダニ|葉が白っぽくなりクモの巣のような糸
体長0.5mm前後と非常に小さく、肉眼での確認が難しい害虫です。 クモの仲間に分類され、高温で乾燥した環境を好むため、特に梅雨明け後の6月~9月頃に爆発的に増えることがあります。
葉の裏に寄生して汁を吸い、吸われた部分は葉緑素が抜けて白い小さな斑点ができます。 被害が広がると葉全体が白っぽくカスリ状になり、光合成ができなくなって枯れてしまいます。 発生が進むと、葉の裏にクモの巣のような細かい糸を張るのが大きな特徴です。
テントウムシダマシ(ニジュウヤホシテントウ)|葉が網目状にスカスカ
益虫であるナナホシテントウとよく似ていますが、こちらはナス科の植物を食害する害虫です。 見分け方は、背中の星の数が28個と多いことや、ナナホシテントウのような光沢がなく、細かい毛に覆われている点です。
成虫も幼虫も、葉の裏側から表皮を残して食べるため、被害部分は白っぽく、レースのように網目状になるのが特徴的な食害痕です。 被害が進むと葉は褐色に枯れてしまいます。成虫は実を食べることもあり、ナスの商品価値を大きく損ないます。
コナジラミ|触ると白い小さな虫がワッと舞う
体長1~2mmほどの白い小さな虫で、カメムシの仲間です。 名前の通り、株を揺らすと白い粉のようにワッと飛び立つのが特徴です。高温多湿を好み、春から秋、特に6月~9月頃に多く発生します。
幼虫・成虫ともに葉の裏に寄生して汁を吸い、株を弱らせます。 大量に発生すると生育が著しく悪くなり、アブラムシと同様に排泄物が原因で「すす病」を引き起こすこともあります。 また、ウイルス病を媒介することもある厄介な害虫です。
ヨトウムシ(夜盗虫)|夜の間に葉や実に大きな穴が開けられている
ヨトウガ(夜盗蛾)の幼虫で、その名の通り、昼間は土の中や株元に隠れ、夜になると活動して葉や実を食い荒らします。 若い幼虫は緑色ですが、成長すると褐色や黒っぽい色になります。
発生時期は4月~6月頃と8月~11月頃です。 葉を食べて大きな穴を開け、成長すると実にも侵入して穴を開けてしまいます。 被害がひどい場合は、収穫が皆無になることもあるため、早期の発見と駆除が重要です。
ハモグリバエ(絵描き虫)|葉に白いペンで落書きしたような筋がある
体長3mm以下の小さなハエの仲間で、幼虫が葉の内部に潜り込んで食害します。 幼虫が葉の中を食べ進んだ跡が、白いペンで絵を描いたような筋状の模様として残るため、「絵描き虫」とも呼ばれます。
春から秋にかけて発生し、特に5月~10月に被害が多く見られます。 食害された葉は光合成能力が低下し、ひどい場合には枯れてしまいます。被害を受けた葉を見つけたら、葉ごと摘み取って処分するのが確実な対策です。
アザミウマ(スリップス)|花が変色したり、実の表面がザラザラになる
体長0.5~2mmほどの非常に小さく細長い虫で、花の内部や葉の付け根など、見つけにくい場所に潜んでいます。 黄色や黒っぽい色をしており、5月~10月頃に発生します。
花を吸汁されると、花びらが変色したり、つぼみが開かなくなったりします。 実が被害を受けると、表面がザラザラしたコルク状になったり、灰褐色に変色したりして品質が大きく低下します。 また、ウイルス病を媒介することもあるため注意が必要です。
【初心者でも安心】農薬に頼らない!なすの害虫対策10選
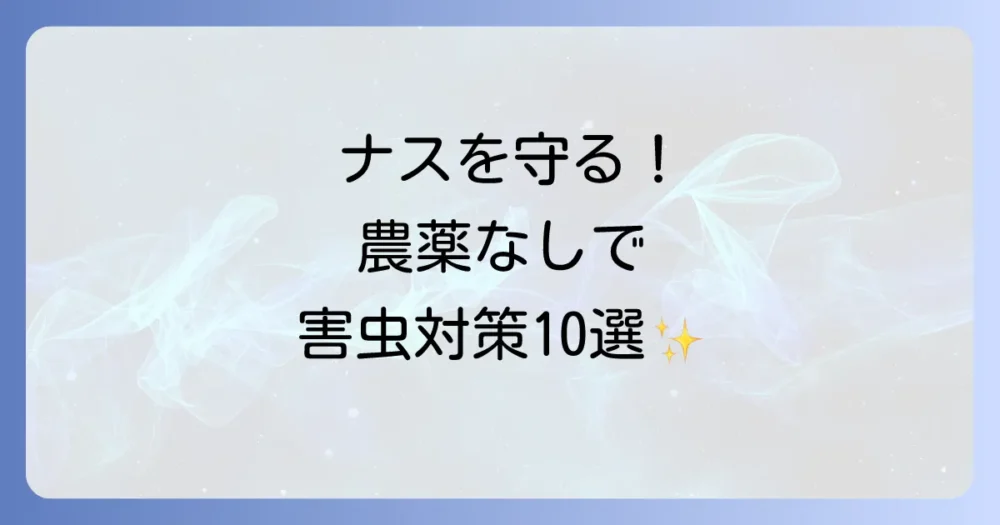
「家庭菜園だから、できるだけ農薬は使いたくない…」そう考える方は多いはずです。ここでは、体や環境に優しい、農薬を使わない害虫対策を10個厳選してご紹介します。簡単なものから始められるので、ぜひ試してみてください。
- 見つけ次第、手やテープで取り除く(物理的駆除)
- 水や牛乳スプレーで洗い流す
- 酢や木酢液で作る手作りスプレー
- ニームオイルを活用する
- 天敵のテントウムシを味方につける
- キラキラ光るシルバーマルチを敷く
- 防虫ネットで物理的にガードする
- コンパニオンプランツを一緒に植える
- 風通しを良くして多湿を防ぐ
- 雑草をこまめに抜く
見つけ次第、手やテープで取り除く(物理的駆除)
アブラムシやテントウムシダマシなど、目に見える害虫の数が少ない初期段階では、最もシンプルで効果的な方法です。手で直接取り除くか、ガムテープやセロハンテープなどの粘着部分を使ってペタペタと貼り付けて駆除します。 特に葉の裏は害虫の隠れ家になりやすいので、念入りにチェックしましょう。歯ブラシを使ってこすり落とすのも有効です。
水や牛乳スプレーで洗い流す
アブラムシやハダニは水に弱い性質があります。 ホースのシャワーなどで勢いよく水をかけて洗い流すだけでも、数を減らすことができます。特に乾燥を好むハダニには、定期的な葉水(葉に水をかけること)が予防にもつながります。
また、牛乳を水で1:1に薄めたスプレーも効果的です。 牛乳が乾くときに膜を作り、アブラムシやコナジラミを窒息させる効果が期待できます。 ただし、散布後に牛乳が腐敗して臭いやカビの原因になることがあるため、乾いた後に水で洗い流すのがおすすめです。
酢や木酢液で作る手作りスプレー
食用の酢を水で薄めたスプレーも、害虫対策として手軽に試せます。酢の匂いを嫌って害虫が寄り付きにくくなる効果や、殺菌効果が期待できます。目安として、水500mlに対して酢を50ml(10倍希釈)ほど混ぜてスプレーします。
木酢液も同様に、独特の燻製のような香りで害虫を遠ざける効果があります。 製品によって濃度が異なるため、記載されている希釈倍率を守って使用してください。どちらも、植物に直接かける際は、まず一部で試してから全体に散布すると安心です。
ニームオイルを活用する
ニームオイルは、インド原産の「ニーム」という木の種子から抽出される天然成分のオイルです。害虫の食欲を減退させたり、成長を阻害したりする効果があり、アブラムシをはじめとする多くの害虫に効果が期待できます。 忌避効果もあるため、予防的に散布するのも良いでしょう。製品の指示に従って水で希釈して使用します。
天敵のテントウムシを味方につける
アブラムシには、強力な天敵がいます。それがナナホシテントウです。成虫も幼虫もアブラムシを大量に食べてくれる、とても頼もしい益虫です。 畑でテントウムシを見かけたら、害虫のテントウムシダマシと間違えずに、大切にしましょう。アブラムシが発生している場所に放してあげると、効果的に駆除してくれます。
キラキラ光るシルバーマルチを敷く
アブラムシやアザミウマなどの害虫は、キラキラと乱反射する光を嫌う習性があります。 そこで、株元にシルバーマルチ(銀色のポリフィルム)を敷くことで、害虫が飛来するのを防ぐ効果が期待できます。 さらに、地温の上昇を抑えたり、雑草の発生を防いだりする効果もあるため、一石二鳥の対策です。
防虫ネットで物理的にガードする
害虫の侵入を物理的に防ぐ最も確実な方法の一つが、防虫ネットです。苗を植え付けた早い段階からトンネル状にネットをかけておくことで、外から飛んでくる成虫の侵入や産卵を防ぎます。
ポイントは、ネットの目の細かさです。アブラムシは比較的大きいので1mm目合いでも防げますが、コナジラミやアザミウマといったさらに小さい害虫を防ぐには、0.4mm以下の細かい目合いのネットを選ぶ必要があります。 ネットの裾に隙間ができないように、しっかりと土で埋めることも忘れないでください。
コンパニオンプランツを一緒に植える
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることでお互いによい影響を与え合う植物のことです。ナスの近くに特定の植物を植えることで、害虫を遠ざける効果が期待できます。
- マリーゴールド:根にいるセンチュウを防ぐ効果が有名ですが、その独特の香りがコナジラミなどの害虫を遠ざけるとも言われています。
- ネギ類(長ネギ、ニラなど):独特の匂いがアブラムシなどの害虫を寄せ付けにくくします。
- バジル:香りが良く、アブラムシなどを防ぐ効果が期待できます。
風通しを良くして多湿を防ぐ
害虫や病気の多くは、風通しが悪く湿度の高い環境を好みます。 ナスの葉が茂りすぎて混み合ってきたら、適度に枝や葉を剪定(せんてい)して、株全体の風通しと日当たりを良くしてあげましょう。これは、害虫の発生を抑えるだけでなく、ナスの健全な生育にもつながります。
雑草をこまめに抜く
畑やプランターの周りの雑草は、害虫の隠れ家や発生源になります。 特にハダニなどは雑草で繁殖し、そこからナスに移動してくることがあります。 こまめに除草を行い、畑を清潔に保つことが、害虫予防の基本です。
どうしても退治できない…そんな時のための農薬(殺虫剤)ガイド
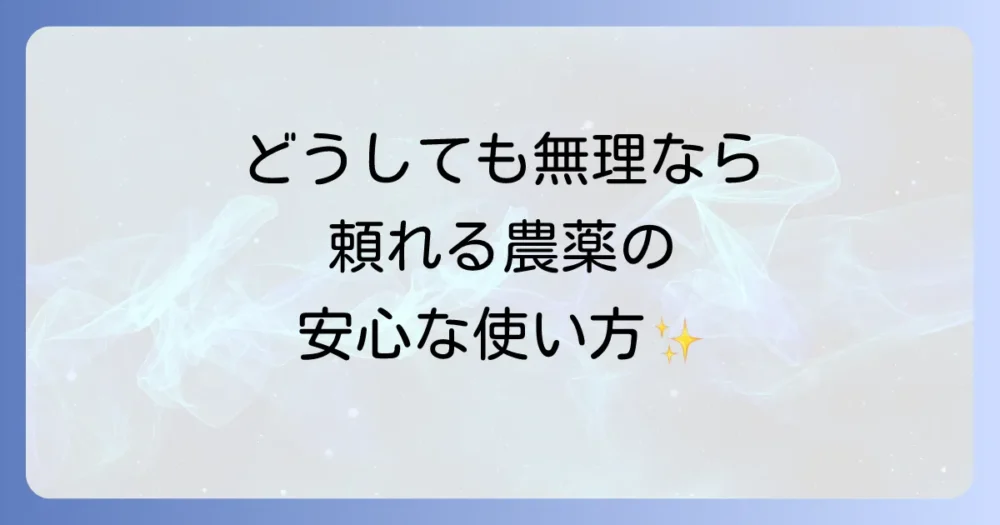
いろいろな対策を試しても害虫の勢いが止まらない、大量発生してしまった…。そんな時には、最終手段として農薬(殺虫剤)の使用も検討しましょう。正しく使えば、効果的に被害を抑えることができます。
農薬を使う前に確認したいこと
農薬を使用する際は、必ず製品のラベルをよく読んでください。対象となる作物(この場合はナス)と害虫、そして希釈倍率や使用回数、収穫前の使用禁止期間(収穫前日数)などの記載事項を厳守することが非常に重要です。 安全に使うためのルールを守り、効果的な防除を行いましょう。
【有機JAS適合】初心者にもおすすめの薬剤
「農薬は使いたいけど、化学合成されたものはちょっと…」という方には、有機JAS規格(オーガニック栽培)でも使用が認められている天然成分由来の薬剤がおすすめです。
- コロマイト乳剤:ハダニやコナジラミに効果的な薬剤で、有機JAS適合です。
- アーリーセーフ:ヤシ油由来の成分で、アブラムシやハダニなどを油膜で覆って窒息させます。
- ボタニガードES:ハダニの天敵となる微生物を利用した殺虫剤です。
害虫別・おすすめの市販薬
特定の害虫に高い効果を発揮する薬剤もあります。代表的なものとして、住友化学園芸の「ベニカベジフルスプレー」は、アブラムシやコナジラミ、ハダニなど幅広い害虫に効果があり、初心者にも使いやすいスプレータイプです。 また、「ダニ太郎」はハダニ類に特化した薬剤です。
害虫は同じ系統の薬剤を使い続けると抵抗性を持ってしまうことがあるため、異なる系統の薬剤をローテーションで散布するのが効果的です。
農薬を安全に使うための注意点
農薬を散布する際は、マスクや手袋、保護メガネなどを着用し、薬剤が直接体にかからないように注意しましょう。風の強い日を避け、早朝や夕方の涼しい時間帯に散布するのが基本です。また、ハチなどの益虫に影響が少ない薬剤を選ぶ配慮も大切です。
よくある質問
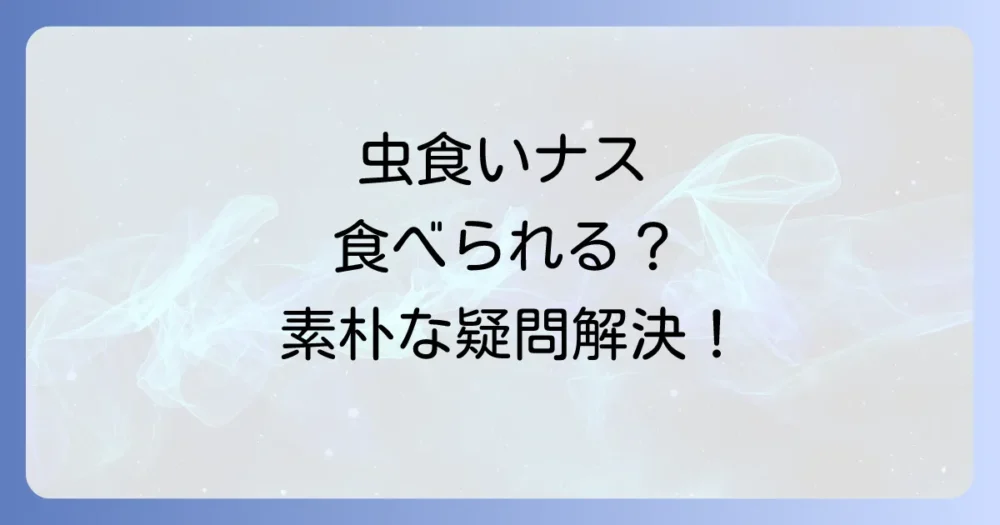
ここでは、なすの害虫に関する、よくある質問にお答えします。
ナスの実に虫食いの穴が…食べられますか?
ヨトウムシなどに食べられて穴が開いてしまったナスでも、穴の周りや傷んだ部分を大きく取り除けば、残りの部分は食べることができます。ただし、穴から雑菌が入っている可能性も考えられるため、加熱調理して食べるのが安心です。虫が中に残っていないか、よく確認してから調理しましょう。
テントウムシは益虫?害虫?見分け方は?
テントウムシには、アブラムシを食べてくれる益虫の「ナナホシテントウ」と、ナスの葉を食べる害虫の「テントウムシダマシ(ニジュウヤホシテントウ)」がいます。
- 益虫(ナナホシテントウ):背中の星が7つ。体がツヤツヤと光沢がある。
- 害虫(テントウムシダマシ):背中の星が28個と多い。光沢がなく、細かい毛で覆われているように見える。
この違いを覚えて、益虫は大切にし、害虫は見つけ次第駆除しましょう。
薬剤散布のベストな時間帯はいつですか?
薬剤散布は、日中の暑い時間帯を避け、風のない早朝か夕方に行うのが最適です。日中に行うと、気温が高いことで薬液がすぐに蒸発してしまったり、薬害(植物がダメージを受けること)が出やすくなったりします。また、ミツバチなどの活動が活発な時間帯を避ける意味もあります。
コーヒーやみかんの皮は害虫対策に効果がありますか?
コーヒーの香りや、乾燥させたみかんの皮の匂いを害虫が嫌うと言われ、忌避効果を期待して株元に撒くといった方法が紹介されることがあります。 科学的に証明された確実な効果があるとは言えませんが、農薬を使わない対策の一つとして試してみる価値はあるかもしれません。コーヒーかすを撒く場合は、カビの原因にならないよう、よく乾燥させてから少量ずつ使うようにしましょう。
まとめ
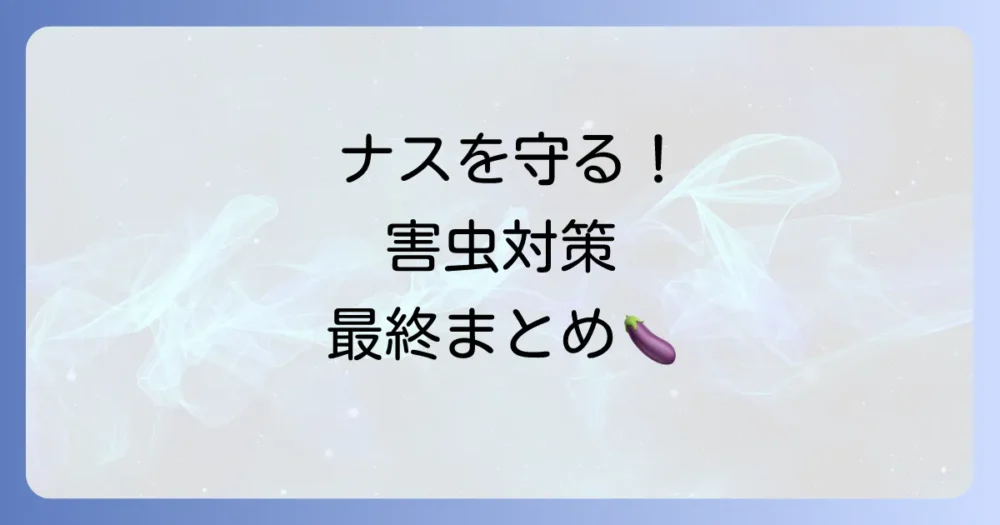
- ナスにはアブラムシやハダニなど多くの害虫がつく。
- 被害症状から原因の害虫を特定することが対策の第一歩。
- 葉の縮れやベタつきはアブラムシのサイン。
- 葉の白い斑点やクモの巣状の糸はハダニの仕業。
- 葉が網目状に食べられていたらテントウムシダマシを疑う。
- 白い小さな虫が舞うならコナジラミが発生している。
- 夜間の食害や大きな穴はヨトウムシが原因。
- 農薬を使わない対策も豊富にある。
- 手で取る、水で流すなど物理的駆除は初期に有効。
- 牛乳や酢、木酢液のスプレーも手軽に試せる。
- 防虫ネットやシルバーマルチで物理的に侵入を防ぐ。
- 風通しを良くし、雑草をなくすなど環境整備も重要。
- 大量発生時は農薬の使用も検討する。
- 農薬はラベルをよく読み、正しく安全に使うこと。
- 益虫のテントウムシと害虫の見分けも大切。