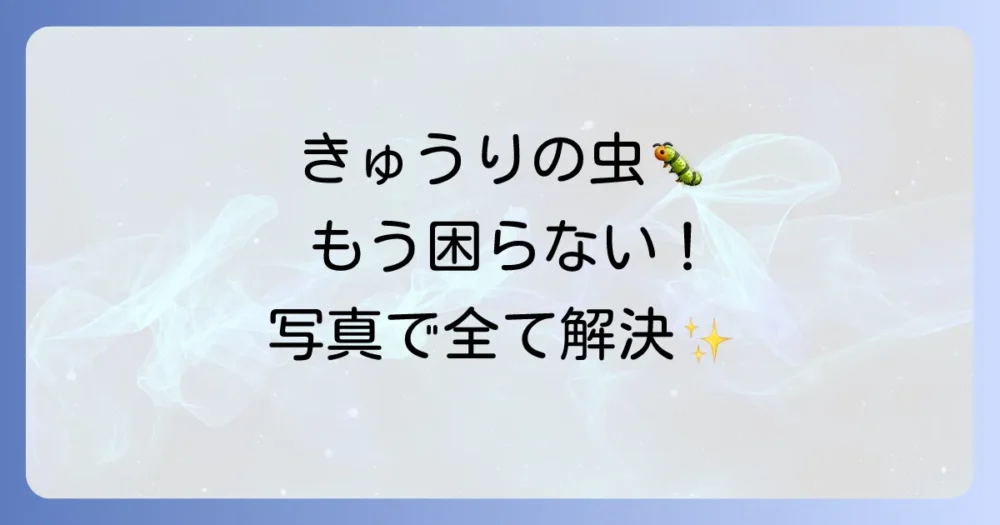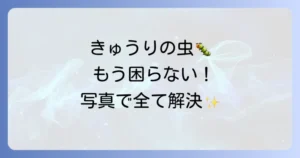家庭菜園で人気のきゅうり。みずみずしい実の収穫を楽しみに育てているのに、気づけば葉が穴だらけになっていたり、白い虫がびっしりついていたり…そんな経験はありませんか?大切に育てたきゅうりが虫の被害にあうのは、とてもショックですよね。でも、安心してください。この記事を読めば、きゅうりにつく厄介な虫の種類から、誰でも簡単にできる駆除方法、そして今後の被害を防ぐための予防策まで、全てを理解することができます。
【緊急】きゅうりに虫を発見!まずやるべきこと
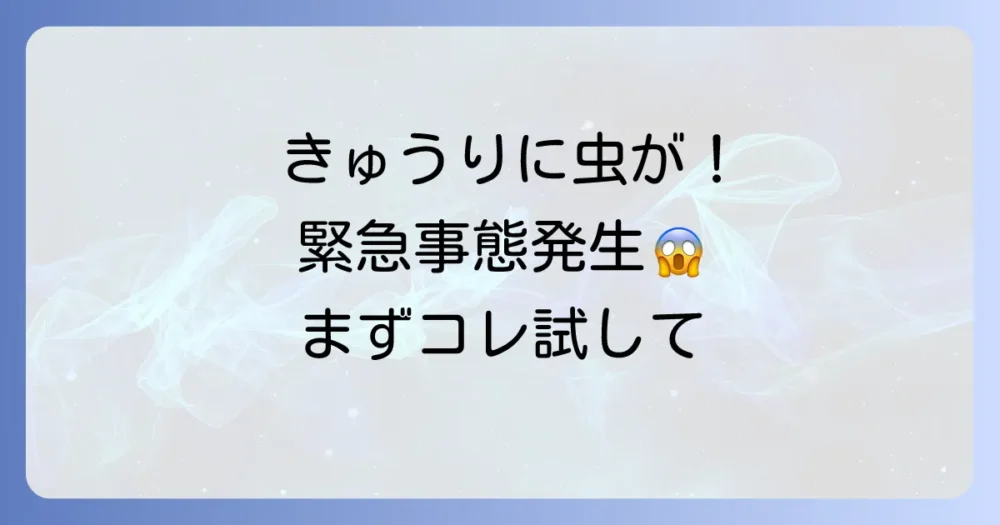
きゅうりに虫を見つけたら、被害が広がる前に迅速な対応が重要です。パニックにならず、まずは落ち着いて以下のことを試してみてください。
まず、目に見える虫は、手で取り除くか、粘着テープなどで捕獲しましょう。特に、ウリハムシのような比較的大きな虫には効果的です。アブラムシのように小さい虫が大量に発生している場合は、古い歯ブラシなどで優しくこすり落とすのも一つの手です。
次に、牛乳や木酢液を水で薄めたスプレーを散布するのもおすすめです。これらは、多くの害虫が嫌うため、手軽にできる対策として知られています。農薬を使いたくない方でも安心して試せる方法なので、ぜひ覚えておいてください。初期段階であれば、これらの対策で十分に被害を抑えることが可能です。
きゅうりの害虫図鑑!症状別に見分けるポイント
きゅうりを加害する害虫は一種類ではありません。敵を知ることが、効果的な対策への第一歩です。ここでは、きゅうりに発生しやすい代表的な害虫とその被害症状を、詳しく解説します。あなたのきゅうりを困らせている虫の正体を突き止めましょう。
- ウリハムシ
- アブラムシ
- ハダニ
- コナジラミ
- アザミウマ
- タバコガ
- ネキリムシ
ウリハムシ
体長7~8mmほどのオレンジ色の甲虫で、きゅうりをはじめとするウリ科の植物を好んで食べます。 成虫は葉を円を描くように食害し、葉が網目状になったり、円形の穴が開いたりするのが特徴です。 幼虫は土の中で根を食べるため、被害が深刻になると株全体が枯れてしまうこともあります。 特に5月~8月頃に活発に活動するため、この時期は注意が必要です。
アブラムシ
体長1~2mm程度の非常に小さな虫で、緑色や黒色など様々な色をしています。 新芽や葉の裏にびっしりと群生し、植物の汁を吸って弱らせます。アブラムシの被害にあうと、葉が縮れたり、生育が悪くなったりします。また、アブラムシの排泄物は「すす病」という黒いカビが発生する原因にもなり、光合成を妨げてしまいます。繁殖力が非常に高く、あっという間に増えてしまうため、早期発見・早期駆除が重要です。
ハダニ
葉の裏に寄生し、汁を吸う非常に小さな害虫です。肉眼では確認しにくいほど小さいですが、被害が進むと葉緑素が抜けて、葉にかすり状の白い斑点が現れます。 さらに被害が拡大すると、葉全体が白っぽくなり、光合成ができなくなって最終的には枯れてしまいます。 高温で乾燥した環境を好むため、梅雨明けから夏にかけて特に発生しやすくなります。
コナジラミ
体長1~2mmほどの白い羽を持つ虫で、植物を揺らすと白い粉のように一斉に飛び立つのが特徴です。 葉の裏に寄生して汁を吸い、アブラムシと同様に「すす病」を誘発します。 また、ウイルス病を媒介することもあるため、非常に厄介な害虫です。
アザミウマ
体長1mmほどの非常に細長い虫で、葉の汁を吸います。被害を受けると、葉脈に沿って白い斑点ができたり、葉が縮れたりする症状が現れます。 アザミウマもウイルス病を媒介することが知られており、被害が広がる前に駆除することが大切です。
タバコガ
蛾の幼虫(イモムシ)が、きゅうりの実に穴を開けて中に侵入し、食い荒らします。 被害を受けた実は商品価値がなくなるだけでなく、そこから腐敗してしまうこともあります。成虫である蛾が飛来して卵を産み付けるため、防虫ネットなどで成虫の侵入を防ぐことが予防につながります。
ネキリムシ
夜行性の蛾の幼虫で、その名の通り、夜の間に地際に出てきて、苗の根元を食いちぎってしまいます。 朝、畑を見に行ったら苗が根元からポッキリと倒れていた、という場合はネキリムシの仕業である可能性が高いです。日中は土の中に隠れているため、見つけるのが難しい害虫です。
【農薬を使わない】きゅうりの害虫駆除・対策7選
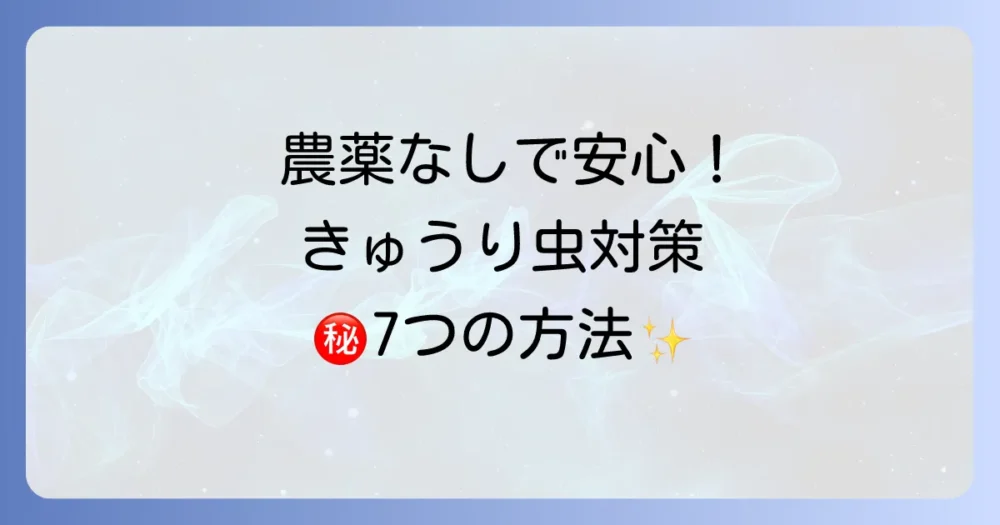
「できるだけ農薬は使いたくない」と考える方は多いでしょう。ここでは、化学農薬に頼らずにきゅうりを害虫から守る、環境にも優しい7つの方法をご紹介します。手軽に試せるものから、少し手間をかけるものまで、状況に合わせて組み合わせてみてください。
- 手やテープで捕殺する
- 牛乳スプレー
- 木酢液・竹酢液スプレー
- ニンニク・唐辛子スプレー
- コンパニオンプランツの活用
- シルバーマルチやキラキラテープ
- 天敵(テントウムシなど)の活用
手やテープで捕殺する
最も原始的ですが、確実な方法です。ウリハムシのように比較的大きな虫は、見つけ次第、手で捕まえるか、ガムテープなどの粘着面に貼り付けて捕殺します。 アブラムシのように小さな虫が密集している場合は、セロハンテープで貼り付けて取ることもできます。毎日の観察を習慣にし、虫が増える前にこまめに取り除くことが、被害を最小限に抑えるコツです。
牛乳スプレー
牛乳を水で薄めてスプレーすると、アブラムシやハダニに効果があります。 スプレーした牛乳が乾く際に膜を作り、害虫を窒息させる仕組みです。作り方は、牛乳と水を1:1の割合で混ぜるだけ。散布後は、牛乳が腐敗して臭いの原因にならないよう、乾いたら水で洗い流すのがおすすめです。
木酢液・竹酢液スプレー
木酢液や竹酢液は、木炭や竹炭を作る際に出る煙を冷却して液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。この香りを害虫が嫌うため、忌避効果が期待できます。 また、植物の成長を助ける効果もあるとされています。製品に記載されている希釈倍率を守って水で薄め、葉の表裏にまんべんなく散布しましょう。
ニンニク・唐辛子スプレー
ニンニクや唐辛子の刺激的な臭いや辛み成分を利用した手作りスプレーも、害虫対策に有効です。 ニンニク数片と唐辛子数本を細かく刻み、水に入れて煮出した後、冷ましてから布で濾してスプレーボトルに入れます。展着剤として、石鹸水を少量加えると、より効果が高まります。
コンパニオンプランツの活用
きゅうりの近くに特定の植物を植えることで、害虫を遠ざけたり、天敵を呼び寄せたりする効果が期待できます。これをコンパニオンプランツと呼びます。 きゅうりの害虫対策には、ネギ類(長ネギ、ニラなど)が特に有効です。ネギの強い香りをウリハムシが嫌うため、混植することで被害を減らすことができます。 また、マリーゴールドは土の中のセンチュウを、パセリやパクチーはその香りで害虫を遠ざける効果があるとされています。
シルバーマルチやキラキラテープ
アブラムシやアザミウマなどの害虫は、キラキラと光るものを嫌う習性があります。この性質を利用して、株元にシルバーマルチを敷いたり、支柱にキラキラ光るテープを吊るしたりすることで、害虫の飛来を防ぐ効果が期待できます。 これは、農薬を使わない物理的な防除方法として非常に有効です。
天敵(テントウムシなど)の活用
テントウムシは、アブラムシを食べてくれる益虫です。畑でテントウムシを見かけたら、むやみに駆除せず、大切にしましょう。天敵が住みやすい環境を整えることも、長期的な害虫管理につながります。ただし、テントウムシに似た「ニジュウヤホシテントウ(テントウムシダマシ)」は、ナス科の植物の葉を食べる害虫なので間違えないように注意が必要です。
【効果てきめん】農薬(殺虫剤)を使った駆除方法
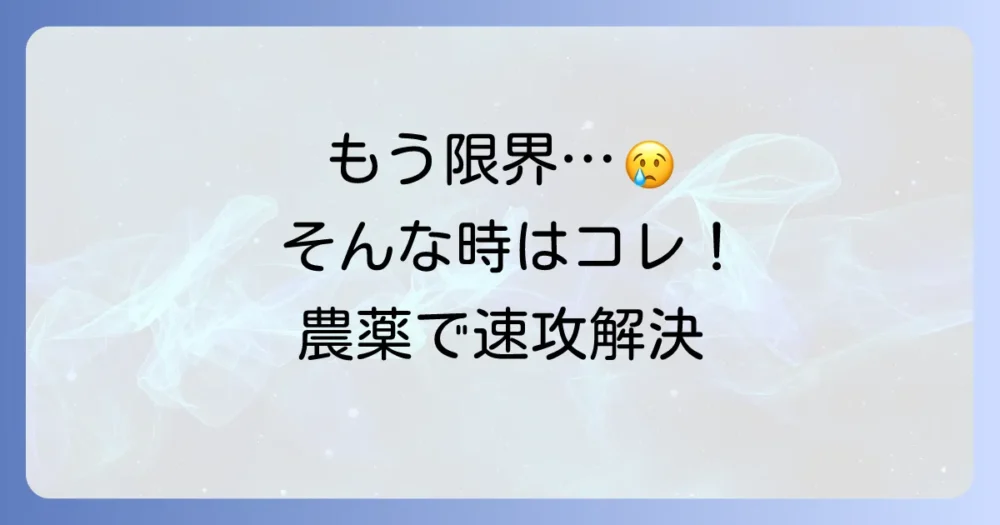
いろいろな対策を試しても害虫の勢いが止まらない、あるいは被害が甚大で手遅れになりそうな場合は、農薬(殺虫剤)の使用も検討しましょう。正しく使えば、非常に高い効果を発揮します。ここでは、農薬を選ぶ際のポイントと、安全な使い方について解説します。
農薬には様々な種類がありますが、きゅうりに使用できる登録があるか、そして対象の害虫に効果があるかを必ず確認してください。例えば、ウリハムシにはマラソン乳剤やオルトラン粒剤などが有効です。 アブラムシには浸透移行性(薬の成分が植物に吸収され、植物全体に効果が行き渡るタイプ)のモベントフロアブルなどが効果的です。
農薬を使用する際は、製品ラベルに記載されている使用方法、希釈倍率、使用回数、収穫前日数などを必ず守ってください。また、同じ農薬を使い続けると、害虫が抵抗性を持ってしまい効かなくなることがあります。 作用性の異なる複数の農薬を順番に使う「ローテーション散布」を心がけることで、長く効果的に害虫を防除できます。 散布する際は、風のない早朝や夕方に行い、マスクや手袋を着用するなど、自身の安全にも十分配慮しましょう。
【予防が肝心】きゅうりの害虫を寄せ付けないための予防策
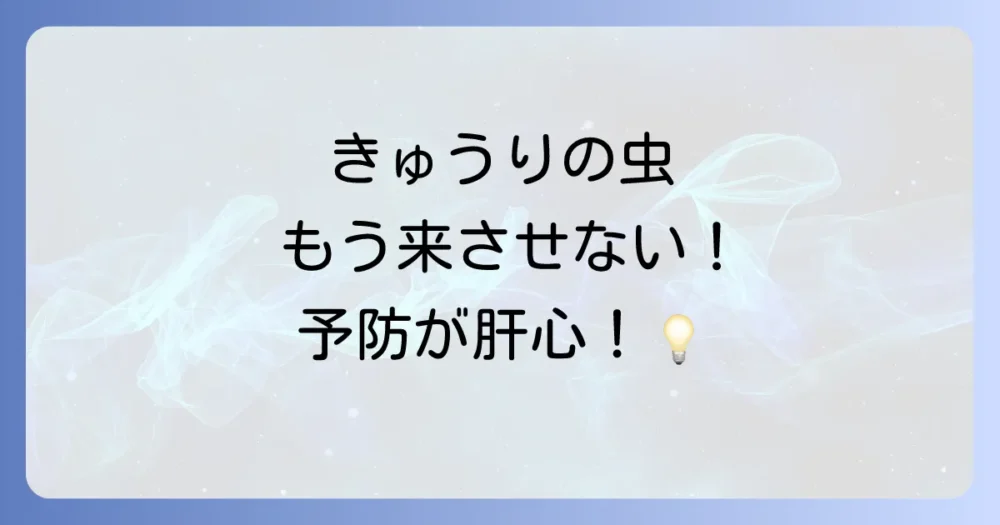
害虫対策で最も重要なのは、そもそも虫を寄せ付けない環境を作ることです。日頃のちょっとした心がけで、害虫の発生リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、誰でも実践できる効果的な予防策をご紹介します。
- 防虫ネット・あんどんの設置
- コンパニオンプランツを植える
- 風通しを良くする(適切な剪定)
- 土作りと施肥管理
- 雑草をこまめに抜く
防虫ネット・あんどんの設置
物理的に害虫の侵入を防ぐ防虫ネットは、最も効果的な予防策の一つです。 特に、苗を植え付けた直後の若い時期は害虫の被害を受けやすいため、トンネル状に支柱を立てて防虫ネットで覆うと安心です。また、植え付けたばかりの苗をペットボトルやポリ袋などで囲う「あんどん仕立て」も、ウリハムシなどの飛来を防ぐのに有効です。
コンパニオンプランツを植える
駆除の項目でも触れましたが、コンパニオンプランツは予防にも大きな効果を発揮します。きゅうりの株間にネギやニラを植えることでウリハムシを、マリーゴールドを植えることでセンチュウを遠ざけることができます。 見た目も華やかになり、一石二鳥の効果が期待できます。
風通しを良くする(適切な剪定)
葉が茂りすぎて風通しが悪くなると、湿気がこもり、病害虫が発生しやすい環境になります。特に、ハダニやうどんこ病は多湿な環境を好みます。下の方の古い葉や、混み合っている部分の葉を定期的に取り除く「整枝(せいし)・剪定(せんてい)」を行い、株全体の風通しと日当たりを良く保ちましょう。
土作りと施肥管理
健康な株は病害虫に対する抵抗力が強くなります。堆肥などをすき込んで水はけと水持ちの良いふかふかの土を作ることが、健康なきゅうりを育てる基本です。また、肥料の与えすぎ、特に窒素成分が過多になると、株が軟弱に育ち、アブラムシなどの害虫がつきやすくなると言われています。 適切な量を適切なタイミングで与えるように心がけましょう。
雑草をこまめに抜く
畑の周りの雑草は、害虫の隠れ家や発生源になります。 特に、ハダニは雑草で発生してから野菜に移動してくることがあります。きゅうりの株周りだけでなく、畑全体の雑草をこまめに抜くことで、害虫が住み着きにくいクリーンな環境を保つことができます。
よくある質問
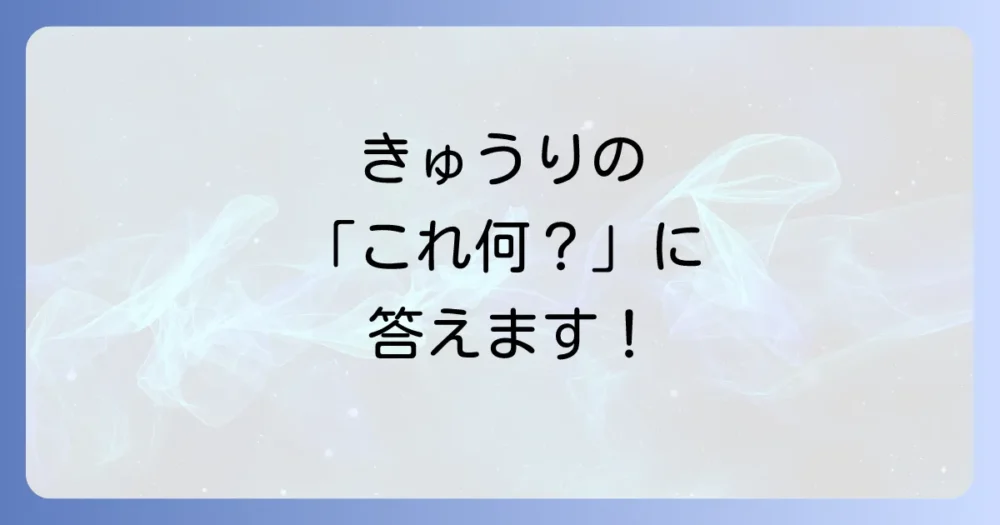
きゅうりの葉に白い筋のような模様があるのは何?
葉に白い筋で絵を描いたような模様ができるのは、「ハモグリバエ(エカキムシ)」の幼虫が葉の内部を食害した跡です。 被害が広がると光合成を妨げますが、生育初期の被害でなければ、大きな問題になることは少ないです。被害を受けた葉を見つけたら、筋の先端にいる幼虫を指で潰すか、葉ごと取り除きましょう。
きゅうりの実に虫がつくことはある?
はい、つきます。代表的なのは「タバコガ」や「オオタバコガ」の幼虫です。 これらの幼虫はきゅうりの実に穴を開けて中に侵入し、内部を食い荒らします。成虫(蛾)の飛来を防ぐために、防虫ネットをかけるのが効果的な予防策です。
黒い小さい虫の正体は?
きゅうりにつく黒くて小さい虫は、いくつかの可能性が考えられます。オレンジ色が混じっていれば「ウリハムシ」の仲間かもしれません。 新芽や葉裏にびっしりついていれば「アブラムシ」の可能性があります。 虫のいる場所や被害の状況をよく観察して、正体を特定しましょう。
白いふわふわした虫は何?
植物を揺らすと白い粉のように飛び立つ小さな虫は「コナジラミ」です。 葉の裏にびっしりと寄生し、植物の汁を吸います。繁殖力が強く、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第、牛乳スプレーや薬剤などで早めに駆除することが重要です。
コンパニオンプランツで相性が悪いものはある?
はい、あります。きゅうりのコンパニオンプランツとして相性が悪いとされる代表的な植物は「ジャガイモ」です。 ジャガイモはきゅうりと同じように多くの養分を必要とするため、養分や水分を奪い合ってしまう可能性があります。また、ジャガイモがかかりやすい病気がきゅうりにうつるリスクも考えられます。
まとめ
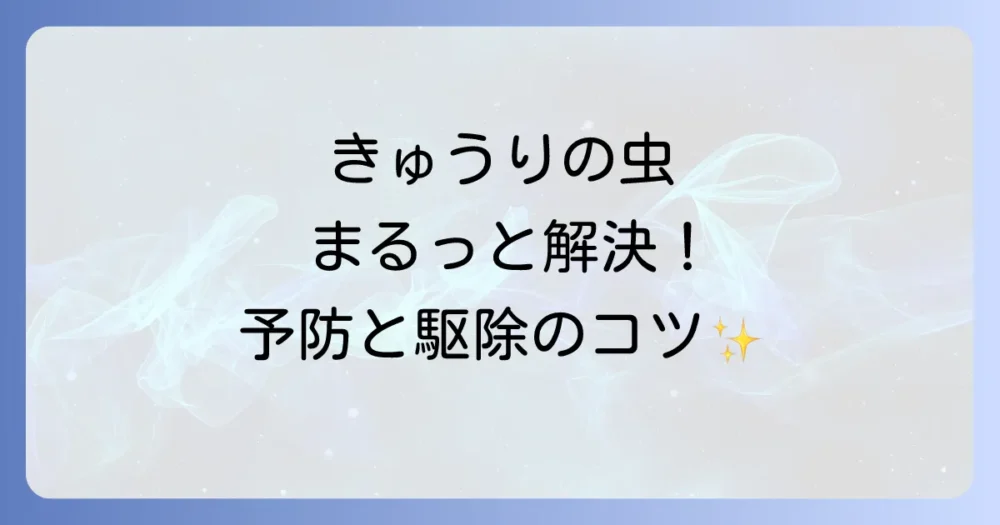
- きゅうりの害虫は早期発見・早期駆除が重要。
- 代表的な害虫はウリハムシ、アブラムシ、ハダニなど。
- 被害症状から害虫の種類を特定することが対策の第一歩。
- 農薬を使わない対策として手での捕殺や手作りスプレーがある。
- 牛乳スプレーはアブラムシやハダニに効果的。
- 木酢液やニンニクスプレーは害虫の忌避効果が期待できる。
- コンパニオンプランツ(ネギ、マリーゴールド)は予防に有効。
- シルバーマルチはアブラムシなどの飛来を防ぐ。
- 被害がひどい場合は適切な農薬の使用を検討する。
- 農薬は使用方法を守り、ローテーション散布を心がける。
- 最も重要なのは予防策。
- 防虫ネットは物理的な侵入を防ぐのに最も効果的。
- 適切な剪定で風通しを良く保つ。
- 窒素肥料の与えすぎは害虫を呼び寄せる原因になる。
- 畑の周りの除草を徹底し、害虫の隠れ家をなくす。