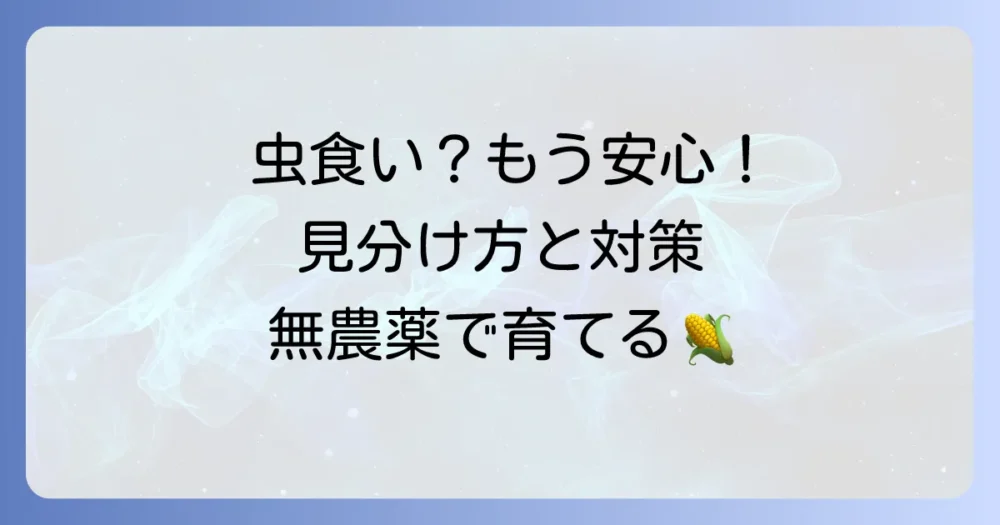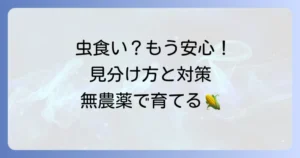家庭菜園で人気のとうもろこし。甘くて美味しい実が育つのを心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。しかし、せっかく育てたとうもろこしが虫に食べられてしまい、がっかりした経験はありませんか?とうもろこしは甘くて栄養豊富なため、残念ながら多くの虫が寄ってきやすい野菜です。でも、安心してください。虫の種類と生態を知り、適切な対策をすれば、被害を最小限に抑えることができます。本記事では、とうもろこしにつく代表的な虫、その見分け方、そして農薬に頼らない予防・駆除方法まで、詳しく解説していきます。
とうもろこしを襲う!知っておきたい代表的な害虫
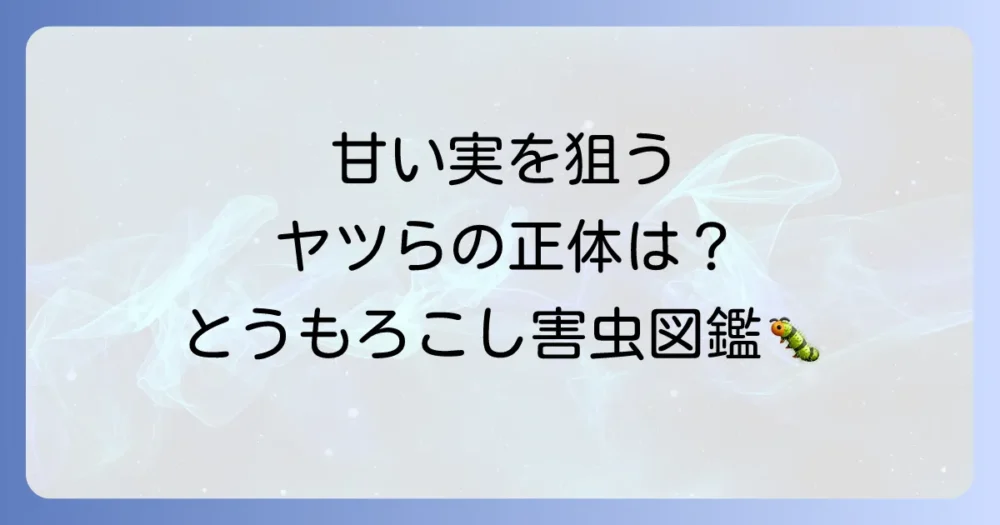
まず、あなたのとうもろこしを狙っている犯人を知ることから始めましょう。とうもろこしに被害を与える主な害虫は、その食べ方や発生時期に特徴があります。ここでは、特に注意すべき害虫の種類と、その被害の見分け方について解説します。
最大の敵!アワノメイガ
とうもろこし栽培で最も警戒すべき害虫がアワノメイガです。 この虫は蛾の幼虫で、トウモロコシの実に穴を開けて中に侵入し、内部から食い荒らしてしまいます。 皮をむいたら虫がいた、という経験の多くは、このアワノメイガの仕業です。被害が進むと、フンで汚れたり、そこから病気が発生したりすることもあります。
被害の見分け方
アワノメイガの被害を見つけるポイントは、とうもろこしの穂先や茎に「おがくず」のようなフン(食入糞)が出ていないかを確認することです。 幼虫が内部に侵入したサインであり、このフンを見つけたら要注意。また、茎に侵入されると生育が悪くなることもあります。 発生時期は6月から8月頃で、特に雄穂(とうもろこしの先端にあるススキのような花)が出る時期に成虫が飛来し、卵を産み付けます。
実を食い荒らすオオタバコガ
オオタバコガもアワノメイガと同様に、幼虫がとうもろこしの実を食害する厄介な害虫です。 アワノメイガが穂の途中から侵入することがあるのに対し、オオタバコガは主に穂の先端、絹糸(ひげ)の部分から侵入する傾向があります。幼虫は非常に食欲旺盛で、一つの実だけでなく、次々と移動して被害を広げることもあります。
被害の見分け方
被害は穂の先端に集中することが多いのが特徴です。 皮をむくと、先端部分の実が食べられ、フンがたまっているのを確認できます。オオタバコガの幼虫は緑色や褐色のイモムシで、体長は4cmほどにまで成長します。 葉や茎にも卵を産み付けるため、定期的な観察が重要です。
汁を吸うカメムシ
カメムシは、とうもろこしの実に細い口を突き刺し、汁を吸ってしまいます。 吸われた部分は栄養が抜け、粒が茶色く変色したり、しぼんでしまったりするため、見た目も味も悪くなります。 特に収穫間近の甘くなったとうもろこしは狙われやすいので注意が必要です。
被害の見分け方
皮の上からでも、粒がまだらに変色していたり、へこんでいたりすることで被害に気づくことがあります。カメムシは独特の臭いを放つため、畑でその臭いを感じたら、株をよく観察してみましょう。周辺の雑草に隠れていることも多いので、畑の周りの草刈りも予防につながります。
葉を食べるヨトウムシ
ヨトウムシは「夜盗虫」という名前の通り、夜間に活動して葉を食い荒らす害虫です。 昼間は土の中に隠れているため、見つけにくいのが特徴。 葉が食べられると光合成が妨げられ、とうもろこし全体の生育が悪くなってしまいます。特に若い苗の時期に被害にあうと、大きなダメージを受けることがあります。
被害の見分け方
朝、畑を見回ったときに、葉に虫食いの穴がたくさん空いていたり、葉の縁から食べられていたりしたらヨトウムシの被害を疑いましょう。株の根元の土を少し掘ってみると、丸まった幼虫が見つかることがあります。葉の裏に卵が産み付けられていることもあるので、葉の裏側もチェックする習慣をつけましょう。
集団で発生するアブラムシ
アブラムシは非常に小さな虫で、葉や茎にびっしりと集団で発生し、汁を吸います。 大量に発生すると、生育が阻害されるだけでなく、アブラムシの排泄物(甘露)が原因で「すす病」という黒いカビが発生し、光合成を妨げることもあります。さらに、ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第早めに対処することが重要です。
被害の見分け方
葉の裏や茎、雄穂などに小さな虫が群がっているのを見つけたら、それがアブラムシです。アブラムシの排泄物で葉がベタベタしていたり、黒いすすのようなものが付着していたりする場合も発生のサインです。
苗の天敵ネキリムシ
ネキリムシはヨトウムシと同じくヤガ科の幼虫で、その名の通り、植え付けたばかりの若い苗の地際部分を食いちぎってしまう恐ろしい害虫です。 被害にあうと苗が倒れてしまい、そのまま枯れてしまいます。せっかく植えた苗が一夜にしてダメにされることもあるため、特に植え付け直後は注意が必要です。
被害の見分け方
朝、畑を見に行くと、苗が根元からポッキリと折れて倒れているのが被害のサインです。ネキリムシも夜行性で、昼間は被害株の根元の土の中に隠れています。 被害を見つけたら、すぐに周りの土を掘って幼虫を探し出し、捕殺しましょう。
今日からできる!害虫対策の基本と予防法
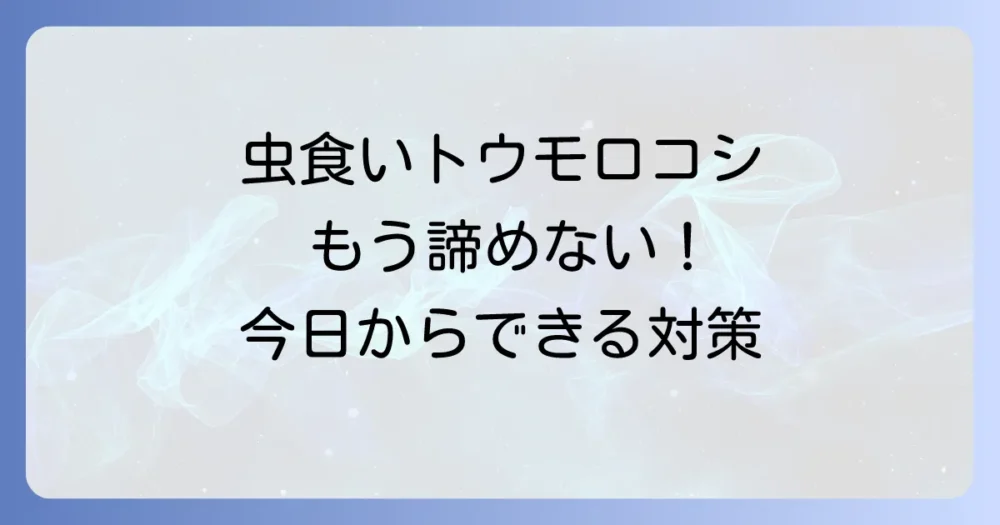
害虫の被害を防ぐためには、虫が発生してから対処するだけでなく、そもそも虫を寄せ付けない環境を作ることが非常に重要です。ここでは、農薬に頼る前にできる、基本的な害虫対策と予防法をご紹介します。少しの手間で大きな効果が期待できますので、ぜひ実践してみてください。
物理的にガード!防虫ネットの活用
最も確実で効果的な予防法の一つが、防虫ネットでとうもろこし全体を覆うことです。 アワノメイガやオオタバコガ、カメムシなどの成虫が飛んできて卵を産み付けるのを物理的に防ぎます。特に、アワノメイガは雄穂の匂いに引き寄せられるため、雄穂が出始めるタイミングでネットをかけるのが効果的です。
ネットをかける際は、支柱を立てて、とうもろこしの葉や実にネットが直接触れないように空間を作るのがポイントです。 ネットが実に触れていると、その上からカメムシが汁を吸ったり、鳥につつかれたりする可能性があるからです。 また、地面との間に隙間ができないように、裾を土で埋めるか、ピンでしっかりと固定しましょう。 畑全体を覆うのが難しい場合は、雌穂(とうもろこしの実になる部分)一つ一つにストッキングタイプの水切りネットなどをかける方法も有効です。
アワノメイガ対策の切り札!雄穂の処理
アワノメイガは、とうもろこしの先端から出る雄穂の匂いに強く引き寄せられます。 この習性を利用した対策が、受粉が終わった後の雄穂を切り取ってしまうという方法です。 受粉は、雄穂から出た花粉が、雌穂の絹糸(ひげ)に付くことで行われます。絹糸が茶色く枯れ始めたら受粉完了のサインです。
受粉が終わったのを確認したら、不要になった雄穂を切り取って畑の外に持ち出し、処分しましょう。 これにより、アワノメイガの成虫が寄ってくるのを大幅に減らすことができます。ただし、受粉が不十分だと実入りが悪くなるため、全ての株の雄穂を一度に切り取るのではなく、受粉の進み具合を見ながら順番に行うのがおすすめです。家庭菜園など、栽培本数が少ない場合は、雄穂を切り取って雌穂のひげに直接ポンポンと花粉をつけてあげる人工授粉を行うと、より確実です。
畑を清潔に保つ
害虫の多くは、雑草が生い茂っている場所を隠れ家や産卵場所とします。 特にカメムシやヨトウムシは雑草地で増える傾向があるため、畑の中だけでなく、周囲の雑草もこまめに刈り取り、清潔な環境を保つことが重要です。
また、収穫後の残渣(茎や葉)にも害虫の蛹などが残っている可能性があります。 収穫が終わった株は畑に残さず、速やかに片付けましょう。 これにより、翌年の発生源を減らすことができます。
天敵を味方につける
畑の生態系を豊かにすることも、害虫対策につながります。アブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブ、アワノメイガの卵に寄生するタマゴバチなど、害虫を食べてくれる益虫が活動しやすい環境を整えましょう。
天敵を呼び込むためには、多様な植物を植えることが有効です。例えば、マメ科の植物(インゲンや枝豆など)はアワノメイガを遠ざける効果があると言われています。 様々な花を咲かせることで、益虫たちの餌場や隠れ家を提供することもできます。
虫がついてしまった!見つけた時の駆除方法
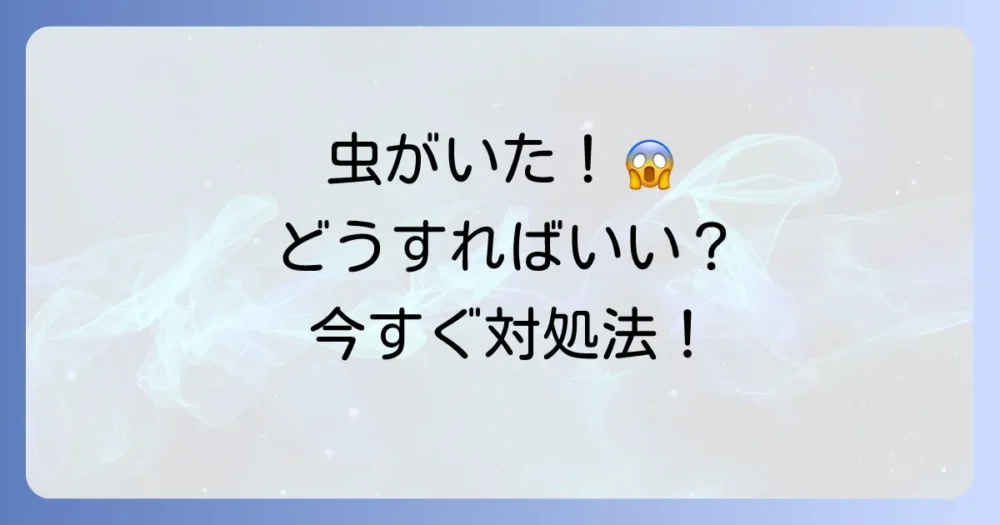
予防策を講じていても、虫がついてしまうことはあります。被害を広げないためには、早期発見と迅速な対応が鍵となります。ここでは、虫を見つけた時の具体的な駆除方法について解説します。
基本は手で取り除く「捕殺」
家庭菜園など、栽培規模が小さい場合に最も確実で環境に優しい方法が、見つけた虫を手で取り除く「捕殺」です。アワノメイガやオオタバコガの幼虫は、穂先や茎のフンを手がかりに見つけ出し、中にいる幼虫を捕まえましょう。 カメムシやヨトウムシなども、見つけ次第捕殺します。
特に、アワノメイガやオオタバコガは、実に深く潜り込んでしまうと農薬も効きにくくなるため、被害の初期段階でフンを見つけ、手で取り除くことが非常に効果的です。 毎日畑を観察し、虫のサインを見逃さないようにしましょう。
天然由来の成分で追い払う
農薬を使いたくない場合、天然由来の成分を利用したスプレーを試してみるのも一つの手です。例えば、木酢液や竹酢液を薄めたものを散布すると、その独特の匂いで虫を寄せ付けにくくする効果が期待できます。 ただし、これらの効果は一時的なものが多く、雨が降ると流れてしまうため、こまめな散布が必要です。
また、アブラムシに対しては、牛乳を水で薄めたものや、石鹸水をスプレーすると、アブラムシの気門を塞いで窒息させる効果があります。ただし、散布後に植物を傷めないよう、水で洗い流すなどのケアが必要な場合もあります。使用する際は、まず一部の葉で試してから全体に散布するようにしましょう。
最終手段としての農薬使用
どうしても被害が抑えられない、大量発生してしまったという場合には、農薬の使用も検討する必要があります。とうもろこし用の農薬には様々な種類があり、害虫の種類によって効果的なものが異なります。
例えば、アワノメイガには「デナポン粒剤5」のような粒状の薬剤を雄穂が出始める時期に散布する方法があります。 オオタバコガやヨトウムシには「トレボン乳剤」などが有効です。 農薬を使用する際は、必ず製品ラベルに記載されている使用方法、使用時期、使用回数などを厳守してください。 特に収穫前の使用制限期間には十分注意し、安全なとうもろこしを収穫しましょう。
虫食いのとうもろこしは食べられる?
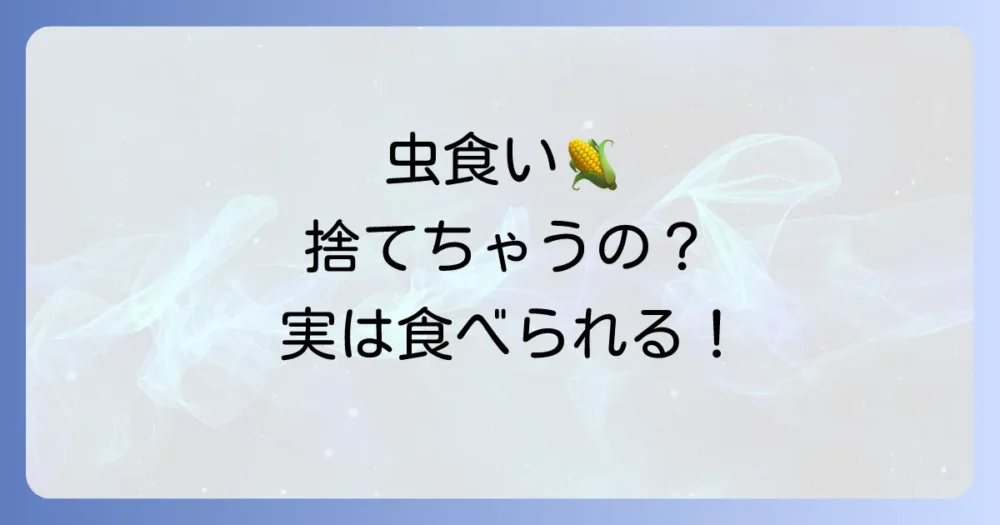
皮をむいて虫が出てくると、食欲が失せてしまうかもしれませんが、多くの人が疑問に思うのが「このとうもろこし、食べても大丈夫?」ということでしょう。
結論から言うと、虫がいた部分と、その周りのフンなどで汚れた部分をきれいに取り除けば、残りの部分は問題なく食べられます。 虫自体に毒があるわけではなく、虫も美味しいとうもろこしを食べて育っているだけです。 実際に、とうもろこしを食べるアワノメイガの幼虫は、加熱するとコーンのような香りがして美味しいという話もあります。
ただし、虫が食べた跡からカビが生えたり、腐敗が進んだりしている場合は、その部分は食べないようにしましょう。見た目や臭いを確認し、明らかに傷んでいる部分は潔く諦めることが大切です。虫食いの跡を包丁で削り取り、よく洗ってから加熱調理すれば、美味しくいただくことができます。
よくある質問
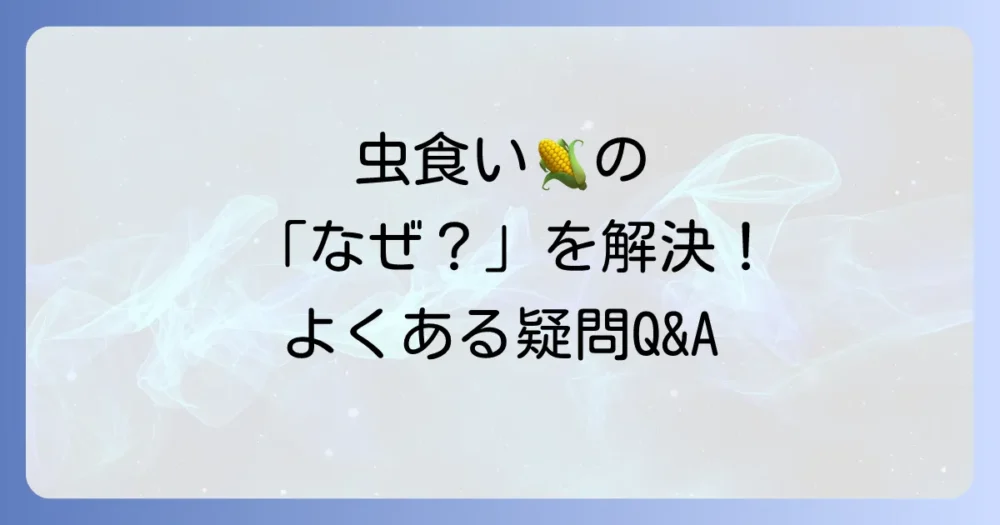
Q1. とうもろこしにつく白い虫は何ですか?
A1. とうもろこしにつく白い虫は、いくつかの可能性が考えられます。葉や茎にびっしりついている小さな虫であれば「アブラムシ」の可能性があります。また、穂の中にいるイモムシ状の虫であれば「アワノメイガ」の幼虫が黄白色をしているため、白っぽく見えることがあります。 状況をよく観察し、どの害虫か特定することが対策の第一歩です。
Q2. とうもろこしの先端にいる虫はどうすればいいですか?
A2. とうもろこしの先端(穂先)にいる虫は、「オオタバコガ」や「アワノメイガ」の幼虫である可能性が高いです。 見つけ次第、手で取り除いて捕殺するのが最も確実な方法です。被害が先端部分だけであれば、その部分を切り落としてしまえば、残りの部分は食べられることが多いです。
Q3. とうもろこしの虫除けにネットはいつからかけるのが効果的ですか?
A3. 防虫ネットをかける最も効果的なタイミングは、害虫が卵を産み付けに来る前です。特にアワノメイガは雄穂の匂いに引き寄せられるため、雄穂が出始めたらすぐにネットをかけるのがおすすめです。 受粉のためにネットを一時的に外すか、ネットをかけたまま人工授粉を行うと良いでしょう。
Q4. 無農薬でとうもろこしの虫を防ぐ方法はありますか?
A4. はい、無農薬でも虫を防ぐ方法はあります。最も効果的なのは防虫ネットで物理的に虫の侵入を防ぐことです。 それに加えて、受粉後に雄穂を切り取ってアワノメイガを寄せ付けないようにしたり、畑の周りの除草を徹底したり、天敵の力を借りるなどの方法を組み合わせることで、農薬を使わなくても被害を減らすことは可能です。
Q5. 虫食いのとうもろこしの見分け方はありますか?
A5. 皮をむく前に虫食いを見分けるには、いくつかのポイントがあります。まず、穂先の絹糸(ひげ)の付け根あたりや、皮の表面に穴が開いていたり、茶色いフンが付着していたりしないかを確認します。 これらはアワノメイガやオオタバコガが侵入した跡である可能性が高いです。また、皮の上から触ってみて、一部分だけ実がへこんでいたり、柔らかくなっていたりする場合も、中で虫に食われている可能性があります。
まとめ
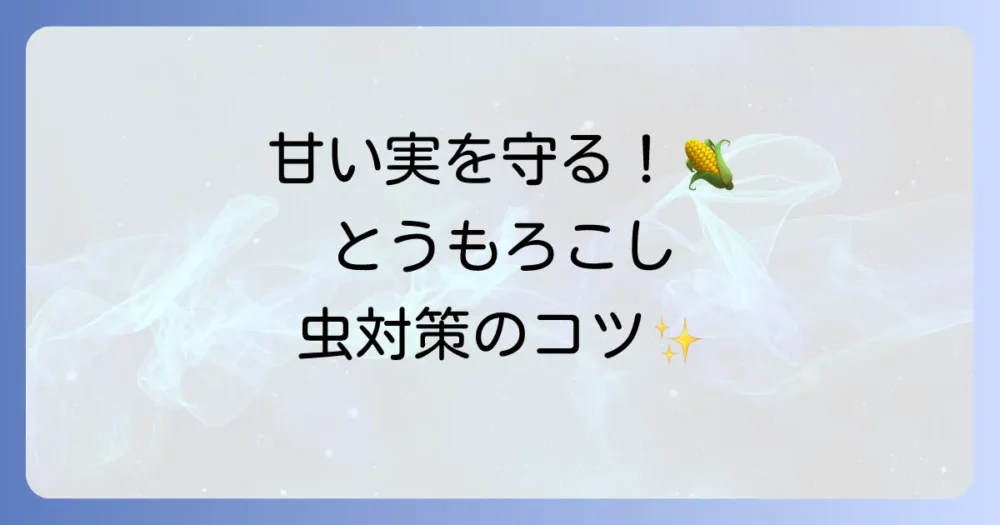
- とうもろこしの主な害虫はアワノメイガとオオタバコガ。
- アワノメイガは茎や穂の途中から、オオタバコガは穂先から侵入する。
- カメムシは実の汁を吸い、ヨトウムシやネキリムシは葉や苗を食べる。
- アブラムシは集団で発生し、生育を阻害する。
- 最も効果的な予防は、雄穂が出る頃からの防虫ネット。
- アワノメイガ対策には、受粉後の雄穂の除去が有効。
- 畑の周りの除草を徹底し、害虫の隠れ家をなくす。
- 虫を見つけたら、基本は手で取り除く「捕殺」が確実。
- 木酢液や石鹸水など、天然由来の資材も補助的に使える。
- 被害がひどい場合は、適切な農薬を正しく使用する。
- 虫食いの実は、虫と汚れを取り除けば食べられることが多い。
- カビや腐敗がある場合は、その部分は食べないようにする。
- 日々の観察が早期発見につながり、被害を最小限に抑える鍵。
- 複数の予防策を組み合わせることで、無農薬栽培も可能になる。
- 美味しいとうもろこし収穫のために、諦めずに害虫対策をしよう。