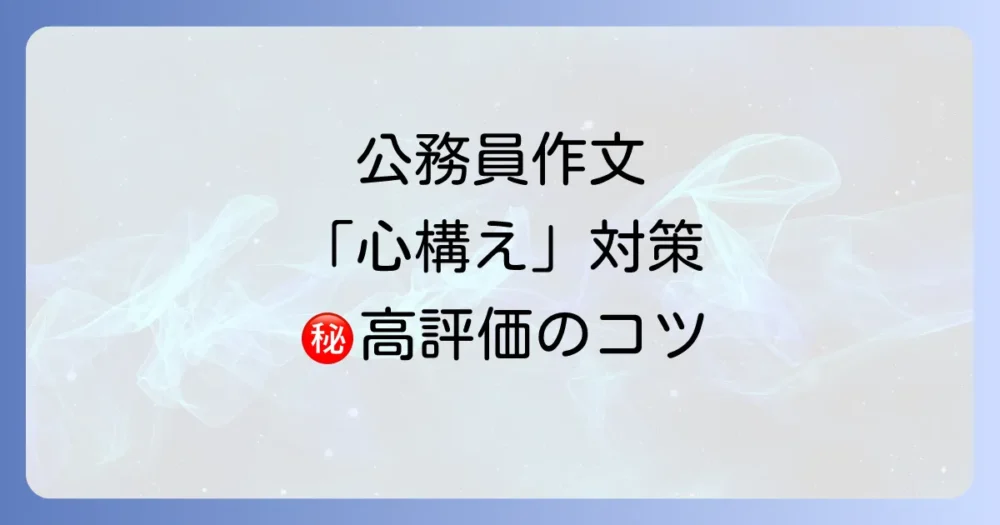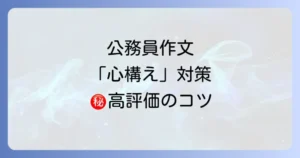公務員試験の作文、「公務員としての心構え」というテーマで手が止まっていませんか?「何を書けば評価されるんだろう…」「ありきたりな内容になってしまいそう…」そんな不安を抱えている受験生は少なくありません。実は、このテーマはあなたの人間性や公務員としての適性をアピールできる絶好のチャンスなのです。本記事では、評価される心構えの要素から、具体的な構成、すぐに使える例文10選、そしてライバルと差をつけるコツまで、あなたの作文対策を全面的にサポートします。
公務員の作文で「心構え」が問われる理由とは?
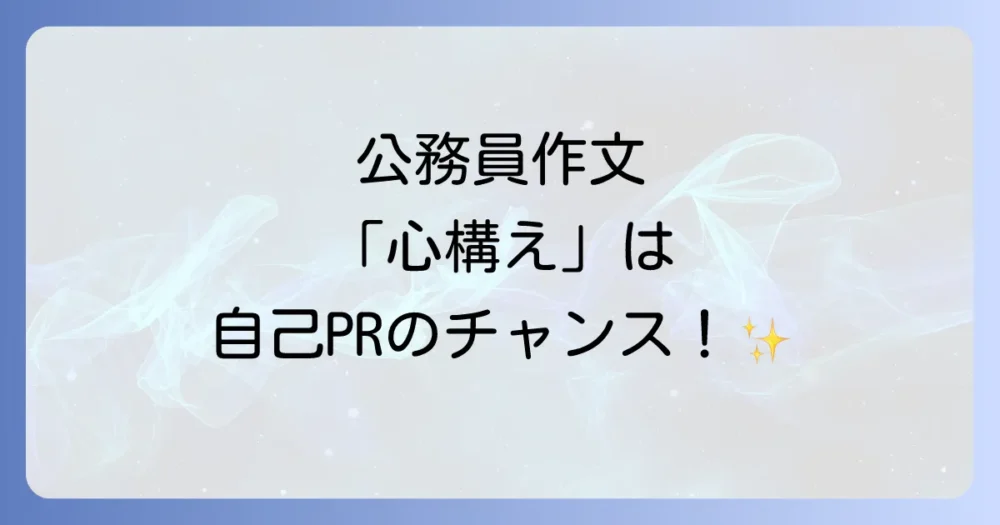
公務員試験の筆記試験において、なぜ「公務員としての心構え」といった一見すると漠然としたテーマが出題されるのでしょうか。それは、学力試験だけでは測れない、あなたの「人となり」や「公務員としての適性」を深く知るためです。採用側は、あなたがどのような価値観を持ち、どのように仕事に向き合おうとしているのか、その本質を見極めようとしています。
このテーマを通じて、採用担当者は以下の点を確認しています。
- 人物像や価値観の把握: あなたがこれまでの人生で何を大切にし、どのような経験から何を学んできたのかを知ることで、あなたの人間性を理解しようとしています。
- 公務員としての適性の見極め: 公務員に求められる「全体の奉仕者」としての意識や、公正さ、責任感といった資質を持っているかを確認しています。
つまり、この作文は単なる文章能力テストではありません。あなたという人間を伝えるための、重要な自己PRの機会なのです。だからこそ、表面的な言葉を並べるのではなく、あなた自身の言葉で、熱意をもって語ることが求められます。
【最重要】評価される「公務員としての心構え」7つの要素
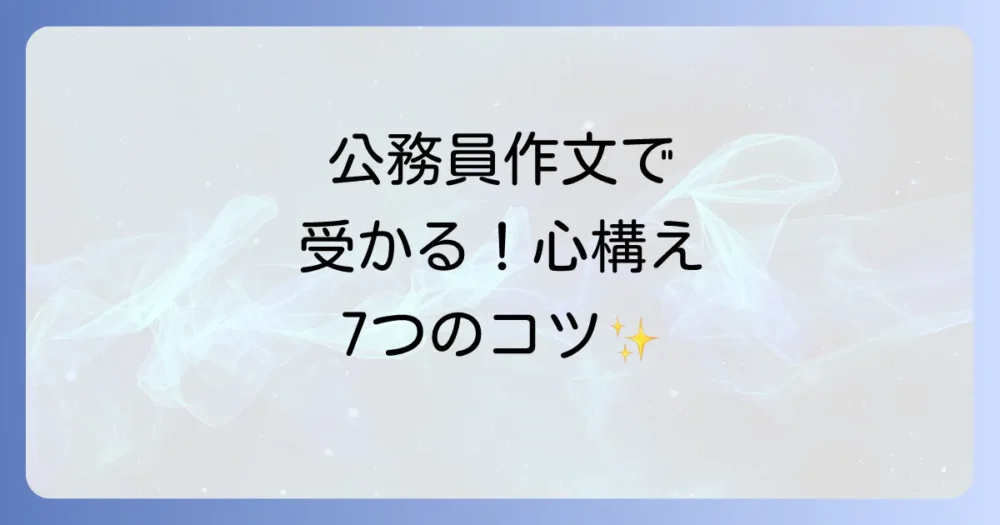
「公務員としての心構え」と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。高評価を得るためには、公務員に特に求められる資質を理解し、それを自分の言葉で表現することが不可欠です。ここでは、作文でアピールすべき7つの重要な心構えを解説します。これらの要素を意識して、あなたの経験と結びつけてみましょう。
具体的には、以下の7つの要素が挙げられます。
- ① 全体の奉仕者としての使命感
- ② 公正・中立な姿勢
- ③ 強い責任感
- ④ 高い倫理観とコンプライアンス意識
- ⑤ 住民に寄り添うコミュニケーション能力
- ⑥ チームで成果を出す協調性
- ⑦ 常に学び続ける向上心
① 全体の奉仕者としての使命感
公務員の最も基本的な心構えは、「全体の奉仕者」であることです。 これは、特定の個人や団体の利益のためではなく、国民や住民全体の幸福と利益のために働くという強い意識を指します。 作文では、なぜあなたが一部の人のためでなく、社会全体に貢献したいと考えるようになったのか、その背景にある経験や想いを具体的に記述することが重要です。例えば、ボランティア活動で感じた社会課題や、地域の人々とのふれあいを通して芽生えた公共への意識など、あなた自身の物語を語ることで、説得力が増します。
② 公正・中立な姿勢
公務員の仕事は、許認可や補助金の交付など、住民の権利や利益に深く関わるものが多くあります。そのため、どのような状況においても、感情や私的な関係に流されることなく、法令や規則に基づいて公平に判断し、行動する姿勢が厳しく求められます。 例えば、部活動やアルバイトでルールを守り、全員に平等に接した経験や、意見が対立する場面で中立的な立場から調整役を担った経験などを盛り込むと、あなたの公正さをアピールできるでしょう。特定の誰かを贔屓するのではなく、常に全体の利益を考えて行動できる人材であることを示してください。
③ 強い責任感
公務員の仕事は、一つひとつが国民や住民の生活に直結しています。 そのため、どんな小さな業務であっても、最後までやり遂げる強い責任感は不可欠な資質です。学業やサークル活動、アルバイトなどで、困難な課題に直面しながらも、粘り強く取り組んで成果を出した経験はありませんか。その経験を通して、あなたがどのように責任を果たしたのか、そしてその経験から何を学んだのかを具体的に述べることで、あなたの責任感の強さを効果的に伝えることができます。「自分に任された仕事は、必ず最後までやり遂げる」という信頼感をアピールしましょう。
④ 高い倫理観とコンプライアンス意識
公務員には、一般の会社員以上に高い倫理観と法令遵守(コンプライアンス)の意識が求められます。 地方公務員法や国家公務員倫理規程などには、信用失墜行為の禁止や守秘義務などが厳格に定められています。 作文では、ルールや決まり事を守ることの重要性を理解していることを示すエピソードを盛り込むことが有効です。例えば、誰も見ていない場所でもルールを守った経験や、不正や間違いに対して誠実に対応した経験などを通して、あなたの高い倫理観をアピールしてください。公務員という立場の重さを理解していることを示すことが重要です。
⑤ 住民に寄り添うコミュニケーション能力
公務員の仕事は、デスクワークだけではありません。窓口業務や地域での活動など、多様な住民と直接対話する機会が数多くあります。 相手の意見や要望を丁寧に聴く「傾聴力」と、行政の制度や方針などを分かりやすく伝える「説明力」、この両方を兼ね備えた双方向のコミュニケーション能力が不可欠です。アルバイトでの接客経験や、異なる世代の人と交流した経験など、あなたが他者とどのように良好な関係を築いてきたかを具体的に示しましょう。相手の立場や気持ちを想像し、寄り添う姿勢をアピールすることがポイントです。
⑥ チームで成果を出す協調性
行政の仕事は、一人で完結するものはほとんどなく、多くの場合、同僚や上司、関係部署など、多くの人々と協力しながら進めていきます。 そのため、自分の意見を主張するだけでなく、周囲の意見を尊重し、チーム全体として最善の成果を目指す協調性が求められます。文化祭や体育祭、グループ研究などで、意見の対立を乗り越えて目標を達成した経験は、協調性をアピールする絶好の材料です。その中であなたがどのような役割を果たし、チームの成功にどう貢献したのかを具体的に記述することで、組織の一員として円滑に業務を遂行できる人材であることを示すことができます。
⑦ 常に学び続ける向上心
社会は常に変化しており、行政が対応すべき課題も多様化・複雑化しています。 そのため、公務員には、一度身につけた知識やスキルに安住するのではなく、常に新しい知識を吸収し、自己の能力を高めようと努力し続ける向上心が求められます。 資格取得のために勉強した経験や、苦手なことに挑戦して克服した経験など、あなたが自己成長のために努力したエピソードを盛り込みましょう。変化に対応し、自ら進んで学び続ける姿勢を示すことで、将来にわたって成長し、組織に貢献してくれる人材であるという期待感を抱かせることができます。
【基本構成】公務員の心構えを作文で書くならPREP法!
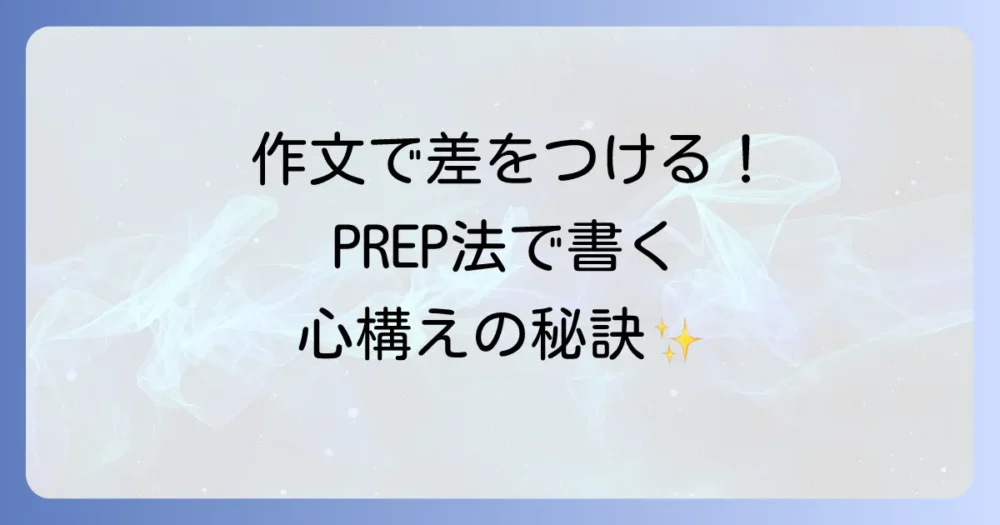
「伝えたいことはたくさんあるのに、文章にするとまとまらない…」そんな悩みを持つ方におすすめなのが、「PREP(プレップ)法」という文章構成術です。 これは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)の頭文字を取ったもので、論理的で分かりやすい文章を誰でも簡単に作成できるフレームワークです。この型に沿って書くことで、採点者にあなたの主張が明確に伝わり、高評価に繋がりやすくなります。
序論(Point):結論を最初に提示する
まず、文章の冒頭で「私が公務員として最も大切にしたい心構えは〇〇です」というように、あなたの一番伝えたい結論(Point)を明確に述べます。最初に結論を示すことで、読み手(採点者)は「この作文は何について書かれているのか」をすぐに理解でき、その後の文章をスムーズに読み進めることができます。ここで提示する「心構え」は、前章で解説した7つの要素などを参考に、あなた自身の経験と最も強く結びつくものを選びましょう。この部分が作文全体の方向性を決める、いわば羅針盤の役割を果たします。
本論(Reason & Example):具体的な経験を交えて理由を述べる
次に、序論で述べた結論の「なぜそう思うのか」という理由(Reason)と、それを裏付ける具体的なエピソード(Example)を展開します。 ここが作文の核となる部分であり、あなたのオリジナリティが最も発揮される場所です。 なぜその心構えが重要だと考えるようになったのか、そのきっかけとなった出来事を具体的に描写しましょう。例えば、「責任感が重要だ」と主張するなら、部活動で困難な役割を最後までやり遂げた経験などを挙げ、「いつ、どこで、誰が、何をしたか」が情景として浮かぶように書くことがコツです。 抽象的な精神論で終わらせず、あなた自身の血の通った体験談を語ることで、主張に説得力が生まれます。
結論(Point):再度結論を述べ、将来の抱負に繋げる
最後に、本論の内容を簡潔にまとめ、序論で述べた結論(Point)を改めて強調します。 そして、「この経験から学んだ〇〇という心構えを、公務員として△△といった業務で活かし、地域社会に貢献したい」というように、将来の抱負や仕事への意欲に繋げて締めくくります。 これにより、あなたの心構えが単なる過去の思い出ではなく、未来に向けた強い意志に基づいていることをアピールできます。採用担当者に「この受験生と一緒に働きたい」と思わせるような、前向きで力強いメッセージを伝えましょう。
【テーマ別】公務員としての心構え 作文例10選
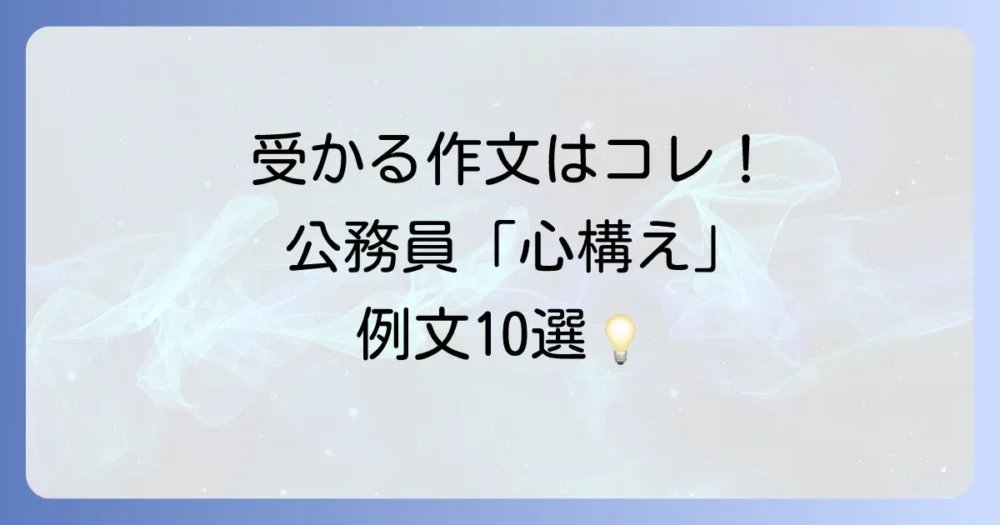
ここでは、「公務員としての心構え」に関連する様々なテーマに基づいた作文の例文を10個紹介します。これらの例文はあくまで一例です。 丸暗記するのではなく、構成の仕方や表現方法、エピソードの盛り込み方などを参考に、あなた自身の経験に基づいたオリジナルの作文を作成するためのヒントとして活用してください。 自分ならどんな経験を当てはめることができるか、考えながら読んでみましょう。
例文1:全体の奉仕者として
私が公務員として最も大切にしたい心構えは、全体の奉仕者として、常に公共の利益を追求する姿勢です。
大学時代に所属していた地域活性化を目的とするボランティアサークルでの活動が、この考えを強く意識するきっかけとなりました。当初、私たちは若者向けのイベント企画に力を入れていましたが、活動を続ける中で、地域の高齢者の方々から「昼間に集える場所が少ない」という切実な声を聞く機会がありました。一部のメンバーからは「活動の趣旨と違う」という意見も出ましたが、私は地域の全ての世代が笑顔で暮らせる町こそが真の活性化だと考え、メンバーと何度も対話を重ねました。そして、高齢者向けの茶話会と、子どもたちが昔の遊びを教わる世代間交流イベントを新たに企画・実行しました。イベント当日、参加された高齢者の方々の笑顔と、子どもたちの楽しそうな声に触れた時、特定の誰かのためではなく、地域全体の幸福を考えることの重要性とやりがいを肌で感じました。
この経験から学んだ、多様な立場の人々の声に耳を傾け、全体の利益のために行動することの尊さを、公務員の仕事においても貫き通したいです。住民一人ひとりの声に真摯に向き合い、一部の意見に偏ることなく、市全体の発展に貢献できる職員を目指します。
例文2:住民との信頼関係
私が公務員として働く上で最も重要だと考えるのは、住民一人ひとりとの信頼関係を築くことです。
学生時代、私は市役所の窓口で短期のアルバ侶イトを経験しました。ある日、複雑な手続きに戸惑い、強い口調で質問をされる高齢の女性がいらっしゃいました。最初は私も緊張しましたが、まずは女性の話を遮らずに最後まで丁寧にお聴きすることを心掛けました。お話を伺うと、何度も市役所に足を運んでいるにもかかわらず、その都度説明が異なり、不安な気持ちを抱えていらっしゃることが分かりました。私は、ただ手続きの説明をするだけでなく、女性の不安な気持ちに寄り添い、一つひとつの項目をゆっくりと、専門用語を使わずに説明しました。最終的に手続きを終えた際、女性から「あなたに話を聞いてもらえて本当に良かった。ありがとう」という言葉をいただき、胸が熱くなりました。
この経験を通じて、行政サービスは単なる手続きの処理ではなく、住民の心に寄り添い、信頼を得ることで初めて成り立つものだと学びました。公務員として、常に相手の立場に立って考え、誠実な対話を重ねることで、住民の方々から「この人になら安心して相談できる」と思っていただけるような、信頼される職員になりたいと考えています。
例文3:困難な課題への挑戦
私が公務員として大切にしたい心構えは、前例のない困難な課題に対しても、諦めずに挑戦し続ける粘り強さです。
私は大学のゼミで、地域の耕作放棄地問題に関する研究に取り組みました。当初は文献調査が中心でしたが、机上の空論で終わらせたくないという思いから、実際に地権者の方々へヒアリング調査を行うことにしました。しかし、多くの地権者は高齢であり、「今さら何かを始めても…」と消極的な反応がほとんどで、何度も心が折れそうになりました。そこで私たちは、まず自分たちが汗を流す姿を見せることが重要だと考え、地権者の一人から許可を得て、小さな畑を借りて野菜作りを始めました。その姿を見た他の地権者の方々が少しずつ心を開いてくださり、最終的には地域のNPOや企業を巻き込んだ市民農園プロジェクトへと発展させることができました。
この経験から、困難な状況でも、粘り強く誠実に行動し続けることで、人の心を動かし、道を切り拓くことができると確信しました。公務員として、今後ますます複雑化・多様化する行政課題に直面した際にも、決して諦めることなく、関係者と協力しながら解決策を探し続ける職員になりたいです。
例文4:チームワークと協調性
私が公務員として働く上で不可欠だと考えるのは、多様な意見を尊重し、チームとして成果を最大化する協調性です。
私は学生時代、文化祭実行委員としてクラスの出し物を担当しました。企画段階でクラスの意見が真っ二つに割れ、一時は険悪な雰囲気が漂いました。私はリーダーではありませんでしたが、このままでは最高の文化祭にできないと感じ、双方の意見の代表者を集めて話し合いの場を設けました。それぞれの意見の良い点、懸念点を客観的に整理し、全員が納得できる妥協点を探ることに徹しました。その結果、両方の案の良いところを取り入れた新しい企画が生まれ、クラスは再び一つにまとまりました。準備は大変でしたが、本番で来場者から大きな拍手をもらった時の達成感は、一人では決して味わえないものでした。
この経験から、異なる意見の対立は、より良いものを生み出すためのチャンスであり、そのためには個々の意見を尊重し、対話を重ねる協調性が不可欠だと学びました。公務員の仕事は、様々な部署や関係機関との連携が必須です。この協調性を活かし、円滑な人間関係を築きながら、チームの一員として組織全体の目標達成に貢献していきたいです。
例文5:誠実さと倫理観
私が公務員として常に心に刻みたいのは、いかなる時も住民の信頼を裏切らない、高い倫理観に基づいた誠実な行動です。
私はスーパーマーケットのレジでアルバイトをしていた際、会計を終えたお客様が商品を一つ忘れて帰られたことに気づきました。高価なものではなかったため、一瞬、自分の判断で処理してしまおうかという考えが頭をよぎりました。しかし、お客様にとっては大切な商品であり、店の信用にも関わる問題だと考え直し、すぐに店長の指示を仰ぎました。そして、防犯カメラの映像からお客様を特定し、連絡を取って無事にお渡しすることができました。後日、そのお客様から丁寧なお礼の手紙をいただき、誠実な行動が人の信頼に繋がることを実感しました。
公務員は、全体の奉仕者として、その一つひとつの行動が住民からの信頼の礎となります。このアルバイトの経験で培った、ルールを遵守し、たとえ小さなことであっても誠実に対応する姿勢を、公務員としての職務においても徹底したいです。常に公正明大であることを自らに課し、住民の皆様から寄せられる信頼と期待に応え続けられる職員でありたいと考えています。
例文6:自己成長と向上心
私が公務員として持ち続けたい心構えは、社会の変化に対応し、常に自己の知識や能力を高めようと努力する向上心です。
私は大学で情報学を専攻していましたが、行政サービスのデジタル化が進む中で、技術的な知識だけでなく、法律や福祉といった幅広い分野の知識の必要性を痛感しました。そこで、専門分野の学習に加え、自主的に行政法の勉強会に参加したり、地域の福祉施設でボランティア活動を行ったりと、積極的に視野を広げる努力をしました。最初は慣れない分野の学習に苦労しましたが、多様な知識が結びついた時に、より多角的な視点から物事を考えられるようになる面白さを知りました。
この経験から、現状に満足せず、常に新しいことを学び続ける姿勢が、自身の成長だけでなく、より質の高いサービス提供に繋がることを学びました。公務員になった後も、担当する業務に関する専門知識を深めることはもちろん、関連する法令や社会情勢の変化にも常にアンテナを張り、自己研鑽を怠らない職員になりたいです。そして、培った知識と能力を住民サービス向上のために最大限に活かしていきたいと考えています。
例文7:多様な意見の尊重
私が公務員として大切にしたいのは、自分とは異なる価値観や意見を尊重し、多様性を受け入れる姿勢です。
私は大学の国際交流サークルに所属しており、様々な国籍や文化背景を持つ留学生と活動を共にしてきました。活動当初は、文化的な違いから生じる意見の対立や誤解も少なくありませんでした。例えば、会議の時間に対する考え方の違いから、計画がうまく進まないことがありました。しかし、一方的に日本の常識を押し付けるのではなく、相手の文化を理解しようと努め、お互いにとって心地よい運営方法を粘り強く話し合いました。その結果、以前よりも深く互いを理解し合え、サークルとしての一体感も高まりました。
この経験を通じて、多様な意見の中にこそ、新たな発見や創造のヒントがあることを学びました。住民のニーズが多様化する現代において、公務員には画一的な視点ではなく、様々な立場の人々の声に耳を傾け、それぞれの状況に配慮した柔軟な対応が求められます。サークル活動で培った多様性を受け入れる姿勢を活かし、どのような立場の人にも寄り添い、誰もが暮らしやすい社会の実現に貢献したいです。
例文8:法令遵守の重要性
私が公務員として職務を遂行する上で、根幹に置きたい心構えは、法令や規則を正しく理解し、厳格に遵守することの重要性です。
私は大学の法学部で学んでおり、ゼミでは行政法の判例研究に取り組んできました。研究を進める中で、行政の裁量権の範囲や、法律に基づいた適正な手続きの重要性を深く学びました。特に印象に残っているのは、些細な手続きの瑕疵が、住民の権利を大きく侵害する結果に繋がった判例です。この判例は、私に法律が人々の生活を守るための最後の砦であることを教え、それを運用する公務員の責任の重さを痛感させました。
法律や条例は、住民全体の公平性を保ち、社会の秩序を維持するために存在します。個人の感情やその場の状況で判断を曲げることは、行政への信頼を根底から揺るがす行為です。法学部で培った知識とリーガルマインドを活かし、常に法令に基づいた公正な職務執行を徹底します。そして、住民の方々に対しては、なぜそのようなルールになっているのかを丁寧に説明する責任も果たし、納得感のある行政サービスの提供に努めたいと考えています。
例文9:志望自治体への貢献
私が〇〇市の職員として最も大切にしたい心構えは、市の現状と課題を深く理解し、その発展に貢献したいという強い当事者意識です。
私は幼い頃からこの〇〇市で育ち、豊かな自然と温かい地域コミュニティの中で成長しました。しかし、近年は若者の市外流出による活力の低下が課題となっていることを肌で感じています。大学進学で一度市を離れたことで、改めて〇〇市の魅力と課題を客観的に見つめ直すことができました。帰省するたびに、商店街のシャッターが増えている光景を見るのは寂しく、この愛する故郷のために何かしたいという思いが強くなりました。そこで、大学の卒業論文では「地方都市における関係人口創出」をテーマに、〇〇市をモデルケースとして具体的な活性化策を研究・提言しました。
この研究活動を通じて培った知識と、故郷への深い愛情こそが、私の強みです。公務員として、机上の空論で終わらせるのではなく、実際に地域に入り、住民の方々と対話を重ねながら、〇〇市の活性化に向けた施策の実現に尽力したいです。常に「自分たちの街を良くする」という当事者意識を持ち、情熱を持って職務に邁進することをお約束します。
例文10:失敗から学んだこと
私が公務員として大切にしたい心構えは、失敗を恐れず挑戦し、その経験から真摯に学び、次に活かす姿勢です。
私は高校時代、サッカー部の副部長として、チームの練習メニュー作成を担当していました。全国大会出場という高い目標を掲げ、私は強豪校の練習方法をそのまま導入するという大きな改革を行いました。しかし、チームのレベルに合わない厳しい練習についていけない部員が続出し、チームの雰囲気は悪化、結果として地区大会の初戦で敗退するという悔しい結果に終わりました。試合後、私は自分の独りよがりな判断が敗因であったことを全部員に謝罪し、一人ひとりと面談して意見を聞きました。その結果、目標設定の重要性だけでなく、仲間との対話を通じて現状を正しく把握することの大切さを痛感しました。
この大きな失敗経験は、私に独善的な判断の危うさと、他者の意見に耳を傾けることの重要性を教えてくれました。公務員の仕事においても、前例のない課題や困難な決断を迫られる場面があると思います。その際にも、この失敗から得た教訓を忘れず、常に謙虚な姿勢で周囲と対話し、たとえ失敗したとしても、その経験を糧として成長し続けられる職員になりたいと考えています。
ライバルと差をつける!作文の評価を上げる3つのコツ
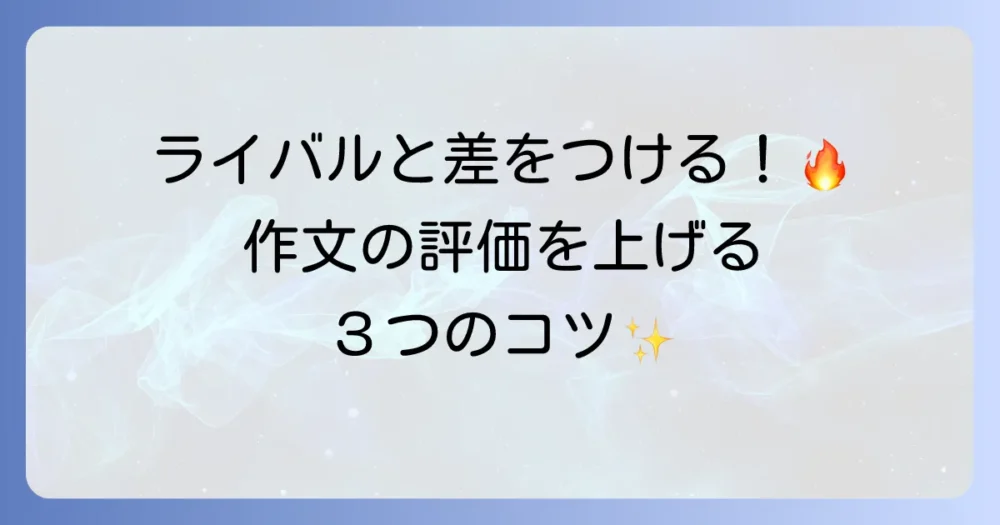
多くの受験生が対策してくる「公務員としての心構え」というテーマ。ありきたりな内容で終わらせず、採用担当者の記憶に残る作文にするためには、もう一歩踏み込んだ工夫が必要です。ここでは、あなたの作文をワンランクアップさせ、ライバルと差をつけるための3つの具体的なコツを紹介します。これらの点を意識するだけで、あなたの熱意と個性がより一層伝わるはずです。
ライバルと差をつけるコツは以下の3つです。
- コツ1:抽象論で終わらせず「自分だけのエピソード」を語る
- コツ2:志望する自治体の「課題」と「取り組み」を絡める
- コツ3:「将来、どんな職員になりたいか」を具体的に描く
コツ1:抽象論で終わらせず「自分だけのエピソード」を語る
「責任感が大切です」「協調性を活かしたいです」といった言葉だけでは、他の受験生との差別化は図れません。重要なのは、その心構えを裏付ける「あなただけの具体的なエピソード」です。 例えば、「責任感」をアピールするなら、ただ「責任感があります」と書くのではなく、「文化祭で誰もやりたがらなかった会計係を引き受け、予算内で全ての買い物を終え、一円の誤差もなく報告書を完成させた」というように、情景が目に浮かぶほど具体的に書きましょう。あなたが直面した課題、その時の感情、そしてどのように乗り越えたのかをリアルに語ることで、あなたの言葉に血が通い、人間的な魅力として伝わります。
コツ2:志望する自治体の「課題」と「取り組み」を絡める
あなたの作文に深みと説得力を持たせるためには、志望する自治体への理解度を示すことが非常に効果的です。 その自治体のホームページや広報誌を読み込み、「人口減少」「防災対策」「子育て支援」といった具体的な課題を把握しましょう。そして、その課題に対して、あなたの心構えや経験をどのように活かせるのかを具体的に結びつけます。例えば、「私の強みである粘り強さを活かし、〇〇市が取り組んでいる高齢者の見守り活動において、一人暮らしの高齢者宅を一軒一軒訪問し、信頼関係を築くことから始めたい」といったように記述すれば、単なる憧れではなく、即戦力として貢献したいという強い意欲を示すことができます。
コツ3:「将来、どんな職員になりたいか」を具体的に描く
作文の締めくくりは、あなたの将来性をアピールする絶好の機会です。「住民のために頑張ります」といった漠然とした抱負ではなく、「どのような公務員になりたいか」というビジョンを具体的に示しましょう。 例えば、「窓口業務において、手続きに不安を抱える住民の方に『あなたに相談してよかった』と言ってもらえるような、傾聴力と分かりやすい説明力を兼ね備えた職員になりたい」あるいは「将来的には、〇〇(関心のある分野)の専門知識を深め、政策立案にも携われる職員を目指したい」など、あなたの目指す職員像を鮮明に描くことで、採用担当者はあなたの成長意欲と将来性を高く評価するでしょう。入庁後の姿を具体的にイメージできていることを伝えることが重要です。
よくある質問
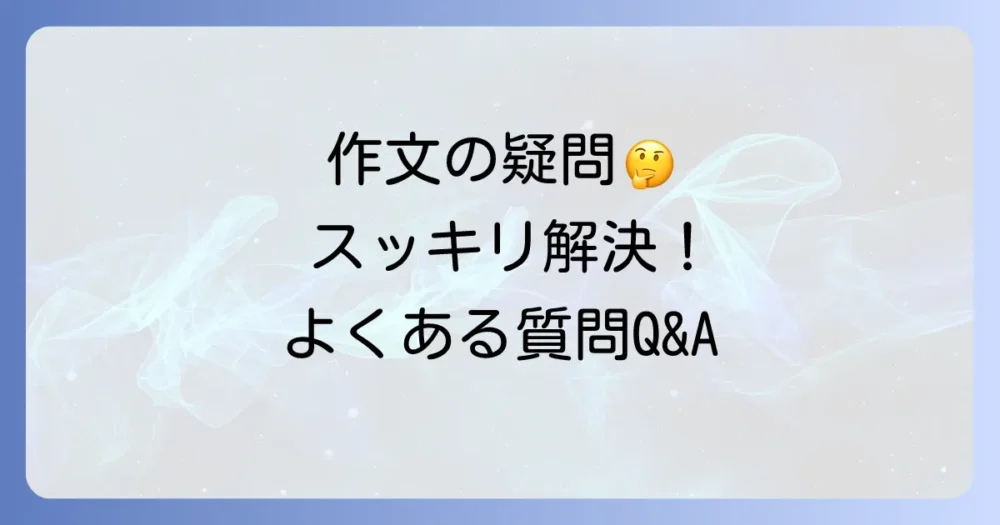
作文の文字数はどのくらいですか?
公務員試験の作文で指定される文字数は、自治体や試験区分によって異なりますが、一般的には600字から1,200字程度が多いです。 重要なのは、指定された文字数の8割から9割以上は必ず書くことです。 文字数が少なすぎると、熱意や意欲が低いと判断されてしまう可能性があります。逆に文字数を超過するのは論外です。練習の段階から、時間を計りながら指定文字数内に文章をまとめる訓練をしておきましょう。
作文で書いてはいけないNGな内容はありますか?
はい、いくつか注意すべき点があります。まず、政治的・宗教的に偏った思想や、特定の団体を批判するような内容は避けるべきです。 また、公務員の仕事に対して「安定しているから」「楽そうだから」といった待遇面のみを志望理由にするような、意欲を疑われる内容は絶対に書いてはいけません。 さらに、嘘の経験談や、誰かの受け売りのような具体性のない抽象的な話も評価されません。あくまで、あなた自身の経験に基づいた、誠実で前向きな内容を心掛けてください。
作文の練習はどのようにすれば良いですか?
効果的な練習方法は、まず過去問や頻出テーマ(「志望動機」「自己PR」「最近関心を持ったニュース」など)で、実際に時間を計って書いてみることです。 書き終えたら、必ず学校の先生や予備校の講師、信頼できる社会人など、第三者に読んでもらい、添削してもらうことが非常に重要です。 自分では気づかない誤字脱字や、分かりにくい表現、論理の矛盾などを指摘してもらうことで、文章は格段に良くなります。また、良い評価を受けた例文を書き写してみるのも、文章構成や表現方法を学ぶ上で効果的です。
「心構え」以外に、どのようなテーマが出題されますか?
「公務員としての心構え」以外にも、様々なテーマが出題されます。大きく分けると、①自己PR系(「あなたの長所・短所」「学生時代に最も力を入れたこと」など)、②時事問題・社会課題系(「少子高齢化」「防災対策」「DXの推進」など)、③志望自治体系(「〇〇市の課題と解決策」「〇〇市の魅力を高めるために」など)があります。 日頃から自己分析を深めるとともに、新聞やニュースで社会の動きに関心を持ち、志望自治体の情報収集を怠らないことが、どのようなテーマにも対応できる力に繋がります。
まとめ
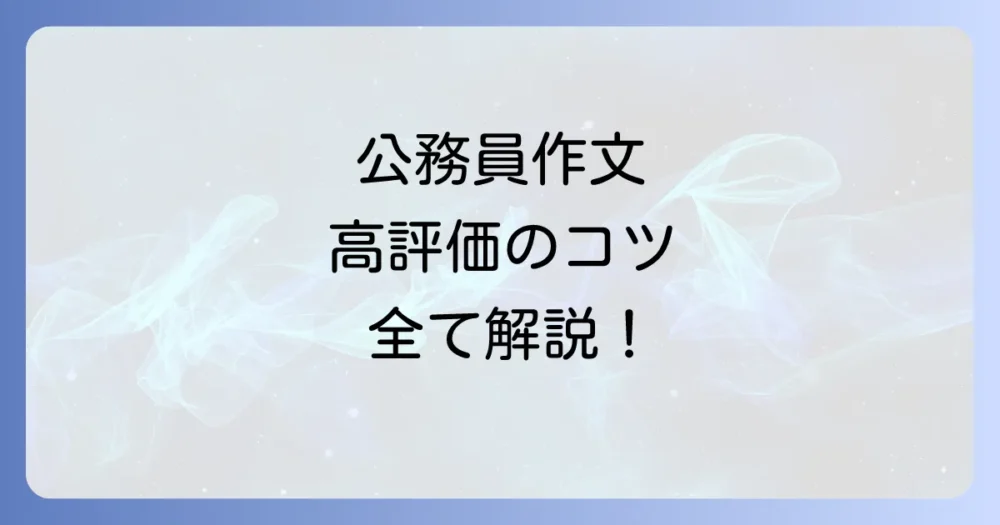
- 公務員の作文で「心構え」が問われるのは人物像や適性を知るためです。
- 評価される心構えは「全体の奉仕者」「公正さ」「責任感」など7つです。
- 文章構成は結論から述べる「PREP法」が効果的です。
- 抽象論ではなく、あなただけの具体的なエピソードを語ることが重要です。
- 「全体の奉仕者」としての経験をボランティア活動などで示しましょう。
- 「信頼関係」を築いた経験はアルバイトの接客などでアピールできます。
- 「困難な課題への挑戦」はゼミや研究での粘り強さで表現可能です。
- 「チームワーク」は部活動やサークルでの協調性で示せます。
- 「誠実さ・倫理観」はアルバイトでの真摯な対応でアピールできます。
- 「向上心」は資格取得など自己研鑽の経験で示しましょう。
- 志望自治体の課題と自身の経験を結びつけると説得力が増します。
- 将来どのような職員になりたいか、具体的なビジョンを描くことが大切です。
- 文字数は指定の8割以上を目指し、時間内に書く練習をしましょう。
- 政治的な偏りや待遇面のみを理由にするのはNGです。
- 書いた作文は必ず第三者に添削してもらうことが上達の近道です。
新着記事