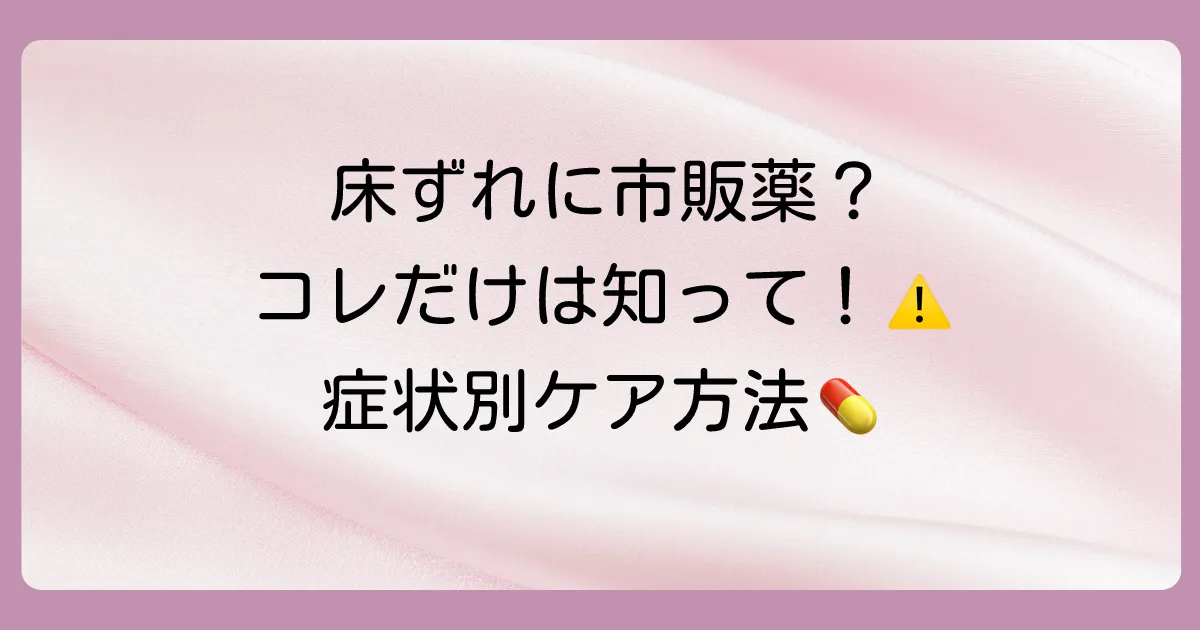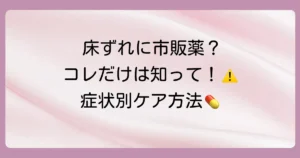「もしかして、これって床ずれ…?」「病院に行く前に、市販の薬でどうにかできないかな…」
ご自身や大切なご家族に床ずれの兆候を見つけた時、まず頭に浮かぶのは市販薬のことではないでしょうか。この記事では、床ずれに市販の塗り薬が使えるのか、使える場合はどのような薬を選べば良いのかを詳しく解説します。症状レベルに合わせた薬の選び方から、悪化させないための自宅でのケア方法、そしてすぐに病院へ行くべきサインまで、あなたの不安に寄り添いながら丁寧にご紹介します。
まず確認!その床ずれ、市販薬でケアできる?
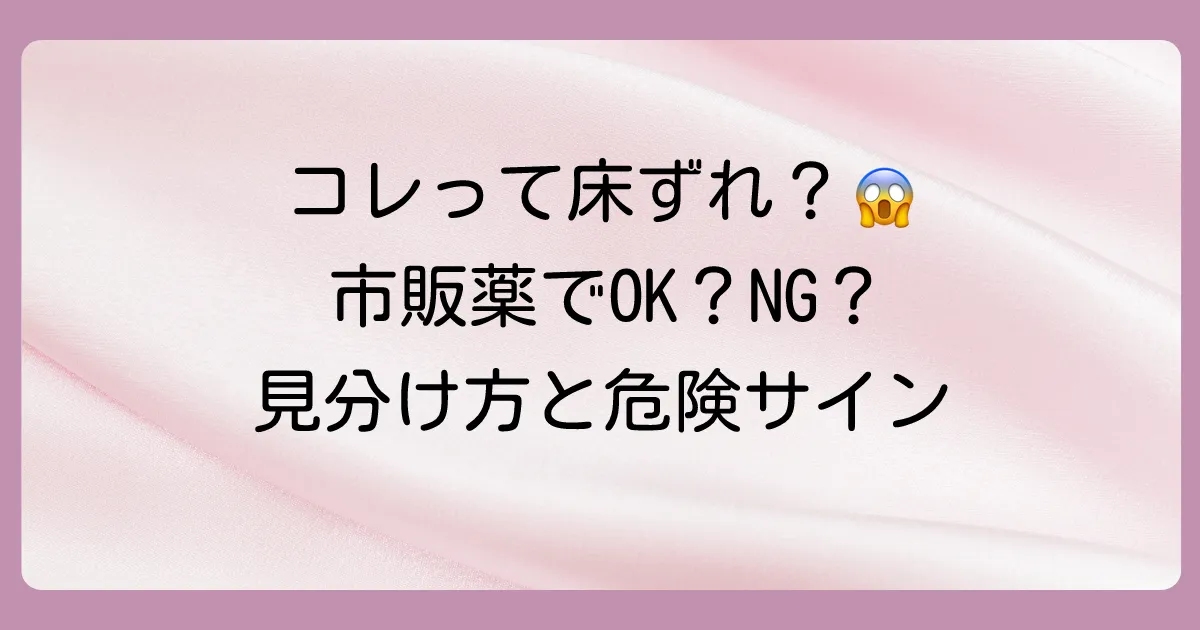
床ずれ(褥瘡)ができてしまった時、すぐに市販薬に頼りたくなる気持ちはよく分かります。しかし、すべての床ずれに市販薬が使えるわけではありません。自己判断で誤ったケアをすると、かえって症状を悪化させてしまう危険性もあります。まずは、ご自身の床ずれの状態を正しく把握することが何よりも大切です。
この章では、以下の点について解説していきます。
- 床ずれ(褥瘡)の基本
- 市販薬で対応できる症状のレベル
- 自分でできる症状レベルのチェック方法
- すぐに病院を受診すべき危険なサイン
床ずれ(褥瘡)とは?
床ずれは、医学的には「褥瘡(じょくそう)」と呼ばれます。 長時間、ベッドや布団、車椅子などで同じ姿勢をとり続けることで、体重で圧迫された部分の血流が悪くなり、皮膚やその下の組織がダメージを受けてしまう状態のことです。
特に、自分で寝返りをうつことが難しい方や、骨が突出している部分(お尻の仙骨部、かかと、肩甲骨など)は、圧力が集中しやすいため床ずれができやすい場所として知られています。
床ずれは、単なる皮膚の傷ではありません。放置すると皮膚の奥深く、時には筋肉や骨にまで達する深刻な状態になり、強い痛みを伴ったり、感染症を引き起こして命に関わるケースもある怖い病気なのです。
市販薬で対応できるのは「ごく初期」の床ずれだけ
結論から言うと、市販薬で対応できるのは、皮膚に赤みが出ているだけの「ごく初期段階」の床ずれに限られます。 この段階であれば、皮膚を保護する市販の塗り薬を使いながら、こまめな体位変換などで圧迫を取り除くことで、改善が期待できる場合があります。
しかし、水ぶくれや皮むけ、じゅくじゅくした傷ができてしまった場合は、市販薬での対応は困難です。この段階になると、感染のリスクが高まり、専門的な治療が必要となるため、自己判断でのケアは絶対に避けるべきです。 薬の選択を間違えると、治りが遅くなるだけでなく、症状を悪化させる可能性も十分に考えられます。
【セルフチェック】あなたの床ずれのステージは?
床ずれの重症度は、その深さによってステージ(病期)分けされています。市販薬を使って良いかどうかの判断基準として、ご自身の症状がどのステージに当てはまるか確認してみましょう。
| ステージ | 症状 | 市販薬での対応 |
|---|---|---|
| ステージⅠ | 皮膚に赤みがある。 指で押しても赤みが消えない。 | 〇 (保護クリームなどで対応可能な場合がある) |
| ステージⅡ | 水ぶくれ、びらん(皮むけ)、浅い傷ができている。 | ✕ (速やかに医療機関を受診) |
| ステージⅢ | 皮膚の下の脂肪組織まで傷が達している。 | ✕ (速やかに医療機関を受診) |
| ステージⅣ | 筋肉や骨が見えるほど、傷が深くなっている。 | ✕ (速やかに医療機関を受診) |
ポイントは「指で押して赤みが消えるかどうか」です。 赤くなっている部分を3秒ほど指で押し、白く変化して離すとまた赤くなる場合は、まだ血流が保たれているため床ずれの一歩手前です。しかし、押しても赤みが消えない場合は、ステージⅠの床ずれの可能性が高いサインです。
こんな症状はすぐに病院へ!受診の目安
以下の症状が見られる場合は、市販薬で様子を見ずに、できるだけ早く皮膚科や形成外科などの医療機関を受診してください。在宅で療養されている場合は、かかりつけ医や訪問看護師にすぐに相談しましょう。
- 水ぶくれ、皮むけ、ただれがある
- 傷がじゅくじゅくしている、または出血している
- 傷口から膿が出ている、嫌な臭いがする
- 傷の周りが熱を持っている、腫れている
- 皮膚が黒っぽく硬くなっている(壊死している可能性)
- 強い痛みがある
- 市販薬を2~3日使っても改善しない、または悪化している
これらのサインは、床ずれが進行している、あるいは感染を起こしている可能性を示しています。早期に適切な治療を受けることが、重症化を防ぎ、早く治すための鍵となります。
【症状レベル別】床ずれに使える市販の塗り薬の選び方
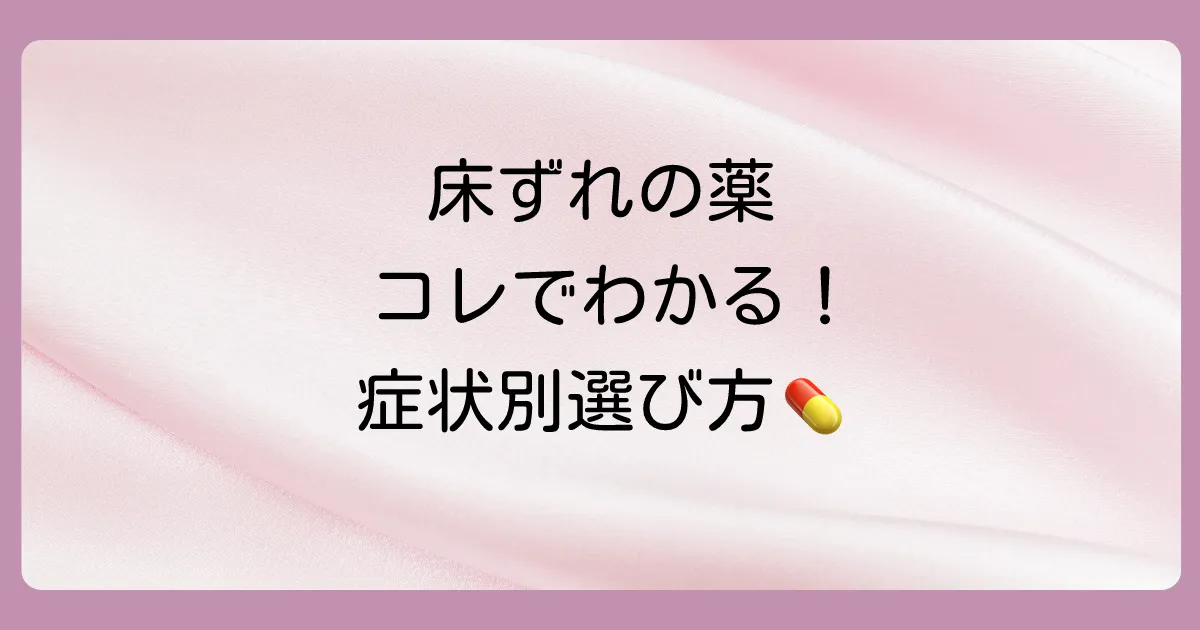
「ステージⅠの赤みだけなら、市販薬でケアできるかもしれない」と判断できた方のために、ここでは具体的な薬の選び方を解説します。大切なのは、症状に合った成分の薬を選ぶことです。間違った薬は、かえって皮膚のトラブルを招くこともあります。
この章では、以下の点について解説していきます。
- 【ステージⅠ:皮膚に赤みがある段階】におすすめの保護・保湿剤
- 【ステージⅡ以降】はなぜ市販薬がNGなのか
- 薬局・ドラッグストアでの相談のコツ
【ステージⅠ:赤み】におすすめの保護・保湿を目的とした塗り薬
皮膚に赤みが出ているだけのステージⅠの床ずれは、これ以上悪化させないための「保護」と「保湿」がケアの中心となります。外部からの摩擦や乾燥、汚れなどの刺激から皮膚を守り、皮膚が本来持つバリア機能をサポートしてくれる塗り薬を選びましょう。
具体的には、以下のような成分を含むものがおすすめです。
- 白色ワセリン
皮膚の表面に油分の膜を作り、水分の蒸発を防ぎながら外部の刺激から肌を保護します。 成分がシンプルで刺激が少なく、赤ちゃんからお年寄りまで幅広く使えるのが特徴です。褥瘡予防・管理ガイドラインでも推奨されています。 - 亜鉛華(酸化亜鉛)軟膏
皮膚を保護し、炎症を和らげる作用があります。 また、患部を乾燥させる働きもあるため、少しじゅくっとした感じがある場合にも使われることがあります。
これらの薬は、治療を目的とするよりは、皮膚を保護して悪化を防ぐ「お守り」のような役割と考えるのが良いでしょう。 塗る前には、皮膚を清潔にすることが大切です。ぬるま湯で優しく洗い流すか、刺激の少ない洗浄剤で清潔にした後、水分を優しく拭き取ってから塗りましょう。
なぜ水ぶくれや傷があると市販薬はNG?
水ぶくれや傷ができてしまったステージⅡ以降の床ずれに、なぜ市販薬が使えないのでしょうか。それには、主に2つの理由があります。
- 感染のリスクが非常に高いから
皮膚のバリア機能が壊れた状態の傷口は、細菌が侵入しやすく、感染の温床となります。 市販の殺菌・消毒薬を自己判断で使うと、傷の治癒に必要な細胞まで傷つけてしまったり、薬剤耐性菌を生み出す原因になったりすることがあります。医療機関では、傷の状態に合わせて適切な抗菌薬を選択し、感染をコントロールします。 - 傷の状態に合わせた専門的な処置が必要だから
床ずれの傷は、乾燥させれば良いというものではありません。傷口から出る「滲出液(しんしゅつえき)」には、傷を治すための成分が多く含まれています。 医療現場では、この滲出液の量を適切にコントロールし、傷口を最適な湿潤環境に保つための「ドレッシング材」という特殊な保護シートや、傷の治癒を促進する専門的な塗り薬(例:フィブラストスプレー®など)を使い分けます。 これらは医師の診断がなければ使用できません。
このように、ステージⅡ以降の床ずれ治療は、専門的な知識と判断が不可欠です。 安易な自己判断は、治癒を遅らせるだけでなく、より深刻な事態を招きかねないことを覚えておいてください。
薬局・ドラッグストアで薬剤師に相談する際のポイント
市販薬を購入する際は、自己判断で選ばず、必ず薬剤師や登録販売者に相談しましょう。その際、以下の情報をできるだけ詳しく伝えると、より的確なアドバイスがもらえます。
- 誰が使うのか(本人、家族など)
- 床ずれができている場所(お尻、かかとなど)
- いつから症状があるか
- 具体的な症状(赤みだけか、水ぶくれや傷はあるか、痛みはあるかなど)
- 現在、治療中の病気や使用中の薬はあるか
- アレルギー歴はあるか
可能であれば、スマートフォンのカメラで患部の写真を撮って見せるのが最も確実です。 専門家である薬剤師は、症状によっては市販薬での対応の限界を伝え、医療機関の受診を勧めてくれます。そのアドバイスには、素直に従うことが大切です。
ドラッグストアで買える!床ずれ初期ケアにおすすめの市販薬
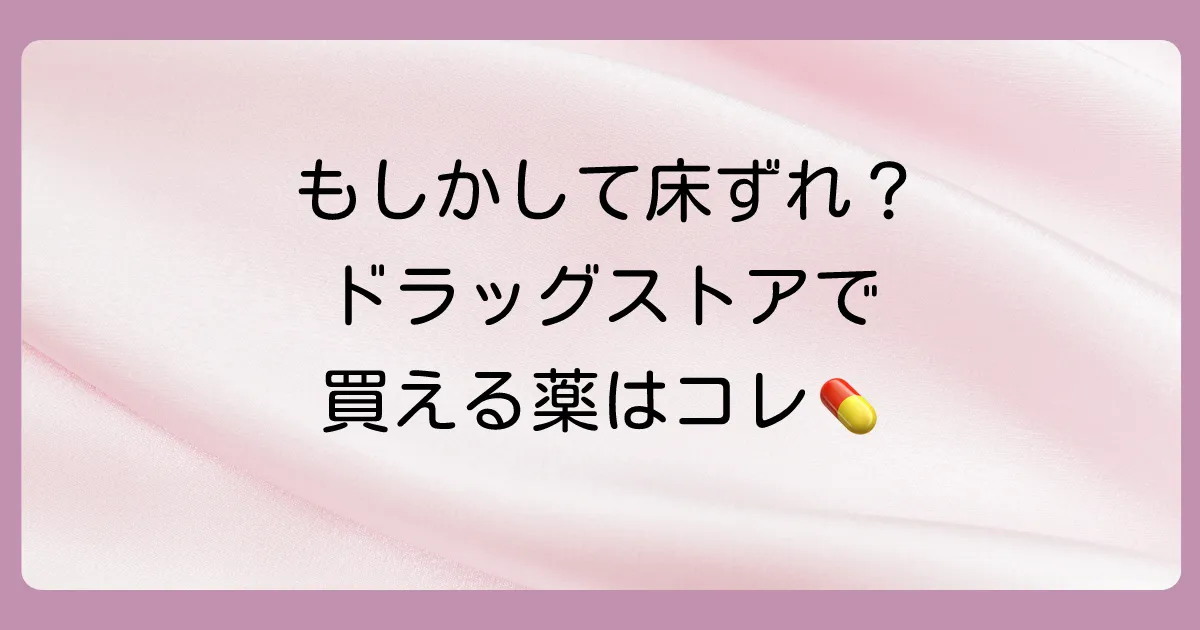
ここでは、ドラッグストアなどで購入可能で、ステージⅠの「赤み」段階の床ずれの保護・保湿ケアに使える可能性のある市販薬をいくつかご紹介します。ただし、これらはあくまで悪化を防ぐための「保護」が目的であり、「治療」するものではないことをご理解ください。使用前には必ず薬剤師に相談し、数日使用しても改善しない場合は速やかに医療機関を受診してください。
この章では、以下の具体的な商品について解説します。
- サンホワイトP-1(白色ワセリン)
- ポリベビー(酸化亜鉛配合)
- コーフルS(殺菌成分+保護成分)
保護・保湿の基本「白色ワセリン」
サンホワイトP-1などの高品質な白色ワセリンは、床ずれ初期のスキンケアの基本となるアイテムです。不純物が少なく、非常に低刺激なため、デリケートな患部にも安心して使用できます。
皮膚の表面に薄い膜を作ることで、水分の蒸発を防ぎ、乾燥から肌を守ります。 それと同時に、衣類との摩擦や、尿・便などの外的刺激から皮膚を保護するバリアの役割も果たしてくれます。特別な薬効成分は含まれていませんが、この「保護する」というシンプルな働きが、床ずれの悪化予防には非常に重要なのです。
清潔にした患部に、薄く優しく塗り広げます。入浴後や体を拭いた後など、皮膚を清潔にしたタイミングで塗るのが効果的です。
保護と軽い炎症緩和に「ポリベビー」
「ポリベビー」は、酸化亜鉛にビタミンA、D2、そして痒みを抑えるジフェンヒドラミンなどを配合した軟膏です。元々は赤ちゃんのおむつかぶれやあせもに使われる薬ですが、その成分は床ずれ初期のケアにも応用できる場合があります。
主成分の酸化亜鉛が皮膚を保護し、軽い炎症を抑える働きをします。また、軟膏が皮膚のすべりを良くし、摩擦を軽減する効果も期待できます。さらっとした使用感も特徴です。
ただし、痒み止め成分も含まれているため、漫然と使用するのではなく、赤みや軽い炎症が見られる場合に短期的に使用するのが良いでしょう。
殺菌と保護を兼ね備えた「コーフルS」
「コーフルS」は、効能・効果に「床ずれ」が記載されている数少ない第3類医薬品です。 殺菌・消毒作用のあるアクリノールと、皮膚を保護し炎症を抑える酸化亜鉛が主成分です。
この薬は、ステージⅠの赤みの段階で、特に失禁などにより皮膚が不潔になりやすく、感染のリスクが少し気になるような場合に選択肢となります。殺菌成分が細菌の増殖を抑えつつ、酸化亜鉛が皮膚を保護してくれます。
ただし、殺菌成分は時に皮膚への刺激となる可能性もゼロではありません。また、黄色い色素が衣服に付着しやすいという注意点もあります。 あくまで「浅い床ずれ」が対象であり、傷が深い場合や悪化が見られる場合は、すぐに使用を中止し医師に相談することが重要です。
塗り薬だけじゃない!床ずれの悪化を防ぐ自宅でのセルフケア
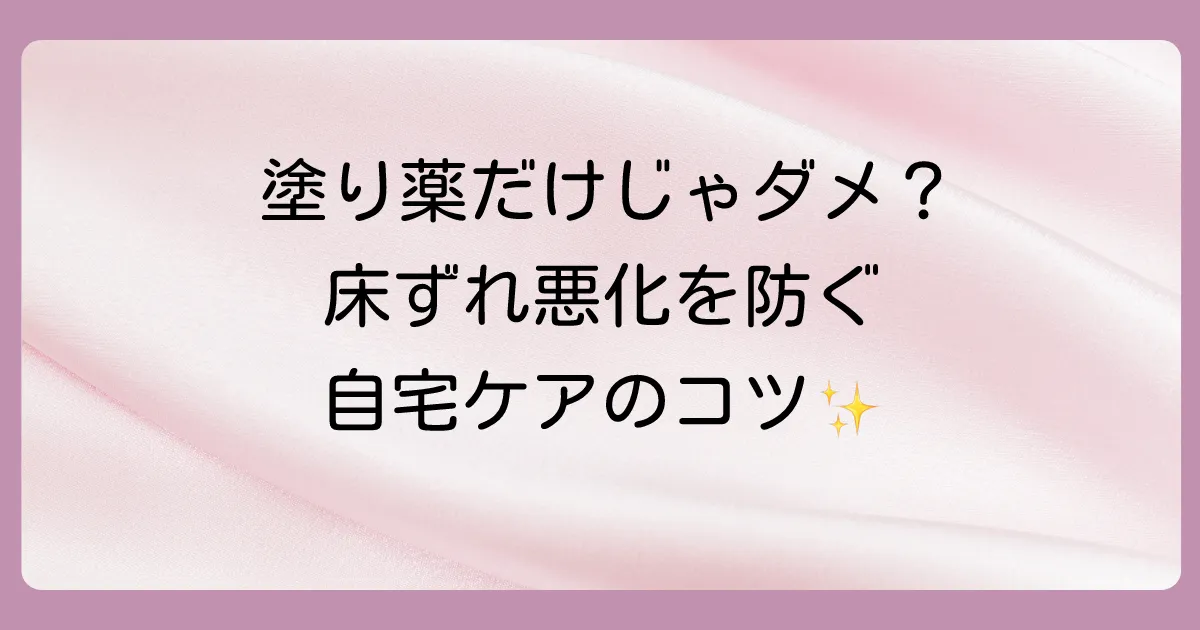
床ずれのケアは、塗り薬を塗るだけで終わりではありません。むしろ、薬以上に大切なのが、床ずれの根本原因である「圧迫」を取り除き、皮膚を健康な状態に保つ日々のケアです。市販薬を使いながら、これから紹介するセルフケアを徹底することが、悪化を防ぎ、改善への近道となります。
この章では、以下の重要なセルフケアについて解説します。
- 最も重要!圧力を分散させる工夫
- 皮膚を清潔に保つスキンケア
- 内側から治す力を高める栄養管理
- 傷を優しく保護するドレッシング材の活用
最も重要!圧力を分散させる工夫(体圧分散)
床ずれの最大の原因は、同じ場所に継続して圧力がかかることです。 この圧力を取り除く「体圧分散」こそが、床ずれケアの基本中の基本であり、最も重要なポイントです。
- こまめな体位変換
寝たきりの場合は、少なくとも2時間ごとに体の向きを変えるのが理想です。 「仰向け→右向き→左向き」といったように、圧力がかかる場所を変えてあげましょう。体を動かす際は、皮膚をこすって「ずれ」が生じないよう、優しく持ち上げるように動かすのがコツです。 - 体圧分散寝具の活用
体圧を効果的に分散させるための専用マットレス(エアマットレスなど)やクッションの活用は非常に有効です。 体全体を面で支えることで、骨の突出部にかかる圧力を軽減できます。介護保険を利用してレンタルすることも可能なので、ケアマネジャーに相談してみましょう。 - ポジショニングの工夫
クッションやタオルを使い、体の下に隙間を作ってあげるだけでも圧力を逃がすことができます。例えば、仰向けの時はかかとの下にタオルを丸めて入れる、横向きの時は背中や膝の間にクッションを挟むなどの工夫が有効です。
皮膚を清潔に保つスキンケア
皮膚が不潔な状態、特に汗や尿・便などで湿った状態(湿潤)が続くと、皮膚がふやけて傷つきやすくなり、床ずれの大きな原因となります。 清潔と保湿を心がけ、皮膚のバリア機能を正常に保ちましょう。
- 優しい洗浄
体を洗う際は、石鹸をよく泡立て、ナイロンタオルなどでゴシゴシこするのは厳禁です。 泡でなでるように優しく洗い、ぬるま湯でしっかりと洗い流しましょう。 - 保湿ケア
洗浄後は、皮膚が乾燥しないうちに保湿剤(ワセリンや保湿クリームなど)を塗って、皮膚の潤いを保ちましょう。 乾燥もまた、皮膚のバリア機能を低下させる原因になります。 - 撥水クリームの活用
失禁がある場合は、尿や便が直接皮膚に触れないように、お尻周りに撥水性のあるクリーム(水をはじくクリーム)を塗っておくと、刺激から皮膚を保護できます。
内側から治す力を高める栄養管理
皮膚や筋肉の材料となる栄養が不足していると、いくら外からケアをしても、傷を治す力が湧いてきません。 特に、低栄養状態は床ずれの大きなリスク因子です。 バランスの取れた食事で、内側から治癒力を高めましょう。
- たんぱく質
皮膚や筋肉を作る主成分です。肉、魚、卵、大豆製品などを毎食取り入れましょう。 - 亜鉛
皮膚の再生に不可欠なミネラルです。牡蠣、レバー、牛肉などに多く含まれます。 - ビタミンC
コラーゲンの生成を助け、傷の治りをサポートします。野菜や果物に豊富です。
食事が十分に摂れない場合は、栄養補助食品などを活用するのも一つの方法です。 かかりつけ医や管理栄養士に相談してみましょう。
傷を優しく保護するドレッシング材の活用
ドレッシング材とは、傷を保護するためのシート状の医療材料のことです。ステージⅠの赤みの段階で、衣類との摩擦が気になる場合などに、フィルムタイプのドレッシング材を貼って保護する方法があります。
透明なフィルムタイプは、貼ったまま皮膚の状態を観察できるメリットがあります。ただし、粘着剤で皮膚がかぶれてしまうこともあるため、長時間の使用は避け、剥がす際は皮膚を傷つけないようにゆっくりと剥がしましょう。
注意点として、ハイドロコロイドタイプ(キズパワーパッド™など)は、自己判断で床ずれに使うのは避けるべきです。 これらは滲出液を吸収して湿潤環境を作るものですが、感染のある傷に使うと細菌を閉じ込めてしまい、症状を悪化させる危険があります。使用については必ず医師の指示に従ってください。
床ずれの市販薬に関するよくある質問
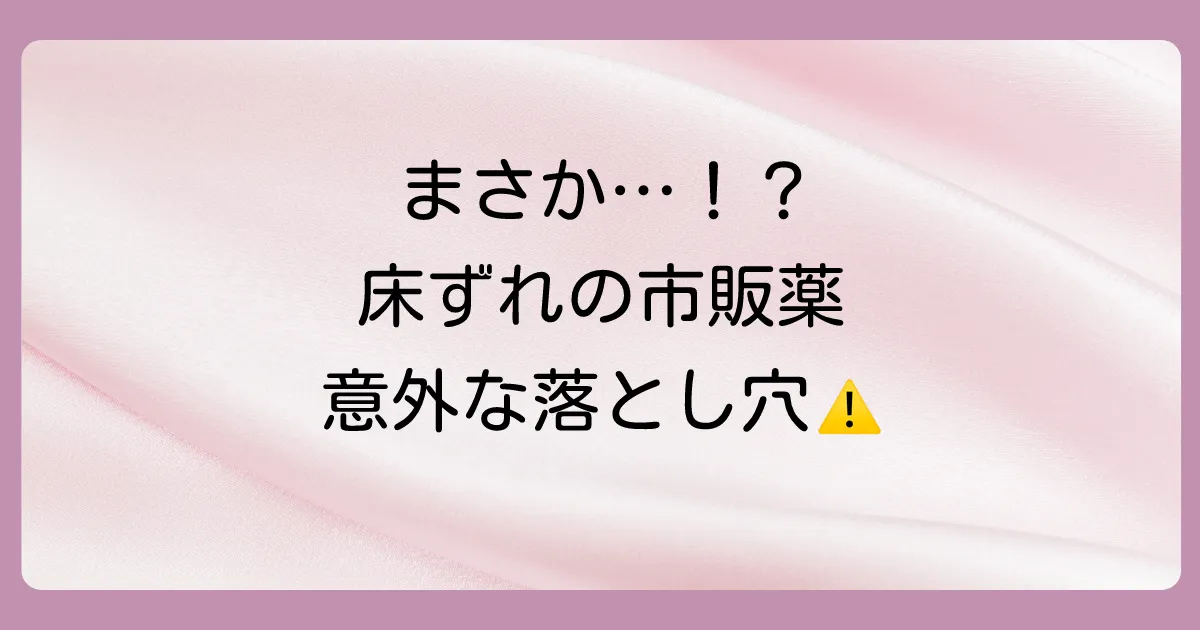
ここでは、床ずれの市販薬に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。自己判断で薬を使い、後悔することのないように、正しい知識を身につけておきましょう。
オロナインH軟膏は床ずれに使えますか?
オロナインH軟膏の主な有効成分は、殺菌・消毒作用のあるクロルヘキシジングルコン酸塩液です。効能・効果には「きりきず、すりきず、にきび」などは記載されていますが、「床ずれ(褥瘡)」の記載はありません。
理論上、ごく浅い傷の感染予防として使える可能性はゼロではありませんが、床ずれの傷は非常にデリケートです。消毒薬の刺激が、かえって傷の治りを妨げてしまう可能性も指摘されています。自己判断での使用は避け、床ずれの保護を目的とするならば、より刺激の少ないワセリンなどを使用する方が安全です。どうしても使いたい場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。
傷パワーパッドのようなものは使ってもいいですか?
いいえ、自己判断で使用するのは非常に危険です。傷パワーパッド™に代表されるハイドロコロイドタイプのドレッシング材は、傷口から出る滲出液を吸収・保持して湿潤環境を作り、治癒を促進するものです。
しかし、これは感染のない清潔な傷に使うことが大前提です。床ずれの傷は、見た目では分からなくても細菌が存在している可能性があります。そのような傷を密閉してしまうと、中で細菌が繁殖し、感染を悪化させる重大なリスクがあります。ハイドロコロイド材は、必ず医師の診断と指示のもとで使用するようにしてください。
薬はどのくらいの頻度で塗ればいいですか?
使用する薬の種類や、皮膚の状態によって異なります。一般的に、ワセリンなどの保護剤は、入浴後や体を拭いた後など、1日に1~2回程度、皮膚を清潔にしたタイミングで塗るのが基本です。
ただし、排泄物で汚れてしまった場合などは、その都度きれいに拭き取ってから塗り直す必要があります。大切なのは、回数よりも「清潔な状態を保った上で塗る」ということです。詳しくは、購入した薬の説明書を確認するか、薬剤師に指示を仰いでください。
薬を塗っても良くならない場合はどうすればいいですか?
市販の保護クリームなどを2~3日使用しても赤みが引かない、あるいは赤みが濃くなる、範囲が広がる、痛みが出てくる、水ぶくれができるなどの変化が見られた場合は、すぐに使用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。
市販薬で対応できる範囲は非常に限られています。良くならないということは、その症状が市販薬のレベルを超えているというサインです。放置すればするほど、治癒までの道のりは長く、険しいものになってしまいます。ためらわずに専門家の助けを借りましょう。
予防のために使える市販のクリームはありますか?
はい、あります。床ずれの「予防」を目的とするならば、保湿と保護に特化したクリームが有効です。
- 保湿クリーム・ローション:乾燥は皮膚のバリア機能を低下させるため、日常的に全身の保湿を心がけることが予防につながります。
- 撥水性クリーム:失禁のある方の場合、お尻周りにあらかじめ撥水性のクリームを塗っておくことで、尿や便の刺激から皮膚を守り、床ずれの発生リスクを低減できます。
これらの予防的スキンケアと、本記事で紹介した体圧分散や栄養管理を組み合わせることが、床ずれを未然に防ぐための最も効果的な方法です。
まとめ
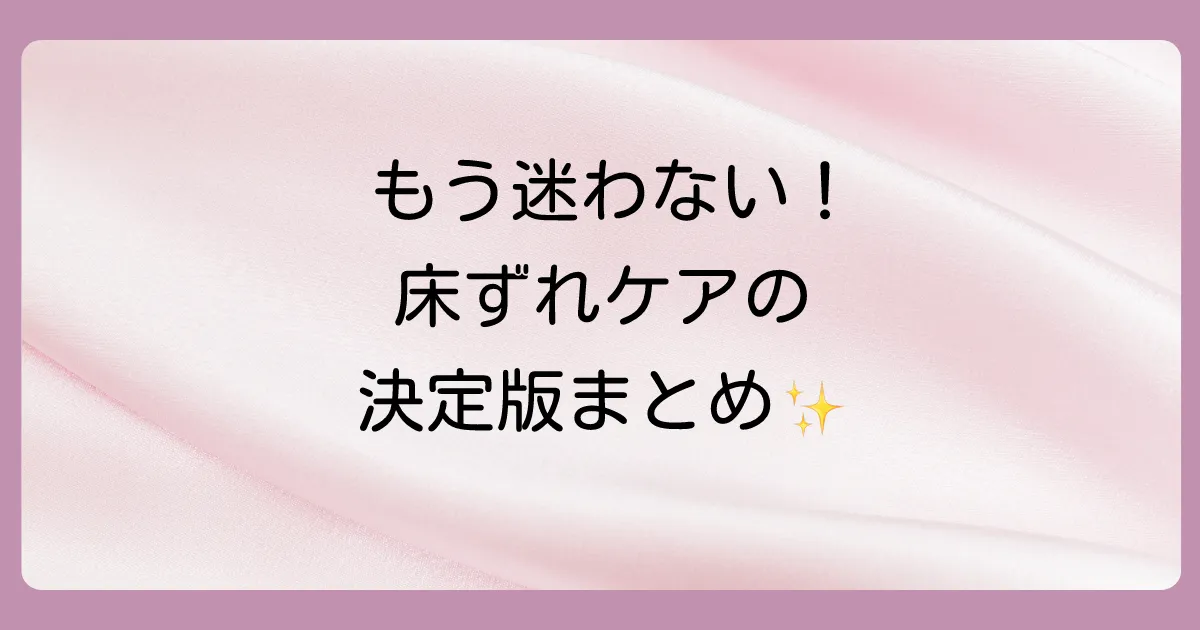
- 市販の塗り薬で対応できるのは、皮膚に赤みがあるだけの「ごく初期」の床ずれのみです。
- 水ぶくれや傷がある場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診してください。
- 初期の赤みには、ワセリンなどの「保護・保湿剤」で皮膚を刺激から守ることが基本です。
- 効能に「床ずれ」と記載のある市販薬もありますが、対象は浅いものに限られます。
- 市販薬を選ぶ際は、必ず薬剤師に症状を詳しく伝えて相談しましょう。
- オロナインや傷パワーパッド™の自己判断での使用はリスクが伴います。
- 床ずれケアで最も重要なのは、薬よりも「体圧分散」です。
- 2時間ごとの体位変換や体圧分散寝具の活用が不可欠です。
- 皮膚を清潔に保ち、乾燥させないスキンケアを徹底しましょう。
- ゴシゴシ洗いはせず、優しく洗浄し、保湿を心がけてください。
- 内側からのケアとして、たんぱく質などを十分に摂る栄養管理も重要です。
- 市販薬を数日使っても改善しない、または悪化する場合はすぐに受診が必要です。
- 床ずれの「予防」には、日常的な保湿ケアや撥水クリームの活用が有効です。
- 床ずれは放置すると重症化し、治療が困難になるため早期対応が鍵となります。
- 不安な点があれば、ためらわずに医師や訪問看護師などの専門家に相談しましょう。
新着記事