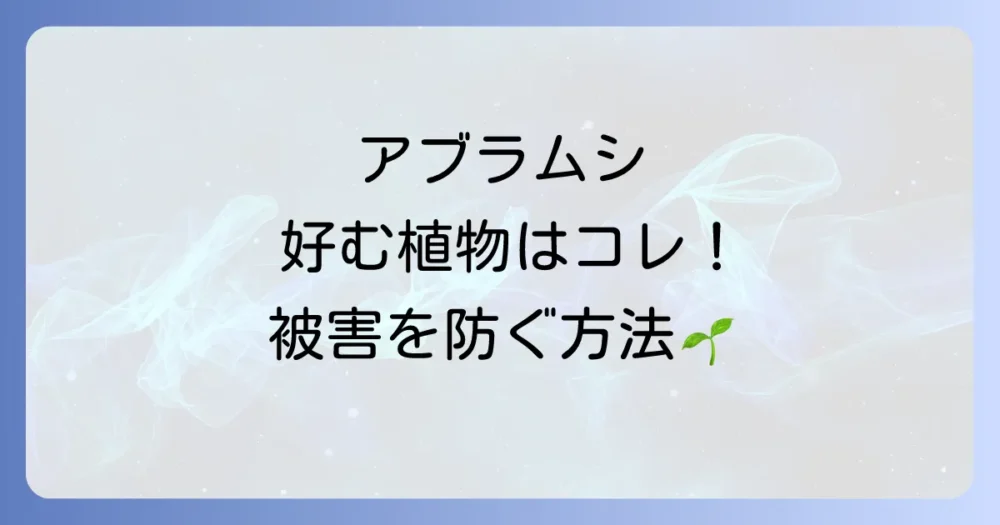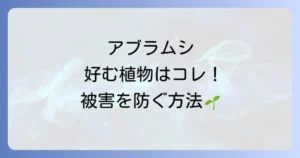大切に育てている野菜や花に、いつの間にかびっしりとついている緑色や黒色の小さな虫…その正体はアブラムシかもしれません。アブラムシは繁殖力が非常に強く、あっという間に増えて植物を弱らせてしまう厄介な害虫です。この記事では、なぜか特定のお花や野菜にばかりアブラムシが発生することに悩んでいるあなたのために、アブラムシが好む植物の種類から、その原因、そして今日からできる具体的な予防・駆除方法まで、詳しく解説していきます。
アブラムシが特に好む植物リスト
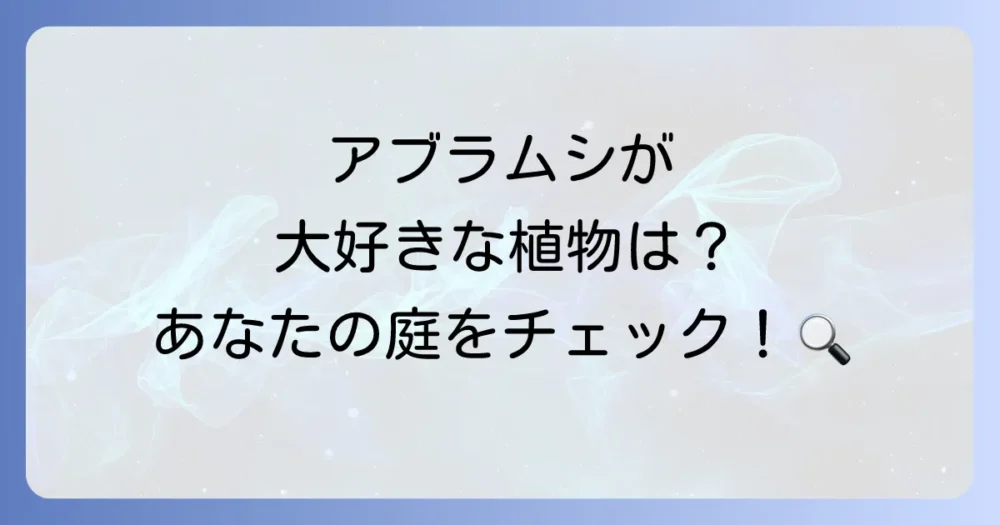
ガーデニングや家庭菜園をしていると、なぜか毎年同じ植物にアブラムシが発生する、と感じたことはありませんか?実はアブラムシには特に好みやすい植物の傾向があります。ここでは、アブラムシの被害に遭いやすい植物をカテゴリー別に紹介します。ご自身の育てている植物が当てはまるか、チェックしてみてください。
- 野菜類
- 花・草花類
- 果樹類
- 観葉植物
野菜類
家庭菜園で人気の野菜の多くは、残念ながらアブラムシの好物です。特に、柔らかい葉を持つ野菜や、生育初期の新芽は狙われやすい傾向にあります。
代表的なものとしては、ナス、トマト、ピーマン、ジャガイモなどのナス科の野菜が挙げられます。 また、キャベツ、ハクサイ、ダイコン、カブなどのアブラナ科の野菜も被害に遭いやすいです。 その他、キュウリやスイカといったウリ科、エダマメやソラマメなどのマメ科、ホウレンソウなどもアブラムシが好んで集まります。 これらの野菜は、葉が柔らかく栄養分が豊富なため、アブラムシにとって格好の餌場となってしまうのです。
花・草花類
お庭を彩る美しい花々も、アブラムシの被害から逃れることはできません。特に多くの人に愛されているバラは、アブラムシの被害が非常に多いことで知られています。 新芽や蕾にびっしりとアブラムシがついているのを見て、がっかりした経験がある方も多いのではないでしょうか。
その他にも、春のガーデニングの主役であるチューリップやユリ、夏の花壇を彩るペチュニアやサルビア、水辺に咲くスイレンなどもアブラムシが好む花として知られています。 これらの花は、見た目が美しいだけでなく、アブラムシにとっても魅力的な栄養源となっているのです。
果樹類
庭木として果樹を育てている場合も注意が必要です。アブラムシは果樹にも発生し、生育に影響を与えることがあります。特に、ウメ、モモ、リンゴ、ナシといったバラ科の果樹は、アブラムシがつきやすい代表格です。
また、レモンなどの柑橘類や、クリ、ブルーベリーなども被害報告が多く見られます。 果樹の場合、葉だけでなく、新梢や若い果実にまで被害が及ぶことがあるため、定期的な観察が欠かせません。
観葉植物
「室内で育てているから大丈夫」と安心はできません。アブラムシは観葉植物にも発生します。特に、葉が柔らかくみずみずしい種類の観葉植物は注意が必要です。
例えば、人気の観葉植物であるパキラやガジュマル、コーヒーの木などは、アブラムシが好む植物として挙げられます。 室内は屋外に比べて天敵が少なく、一度発生すると一気に増殖してしまう可能性があります。窓からの侵入や、購入した苗に付着していた、などのケースも考えられるため、油断は禁物です。
なぜ?アブラムシが特定の植物に集まる3つの原因
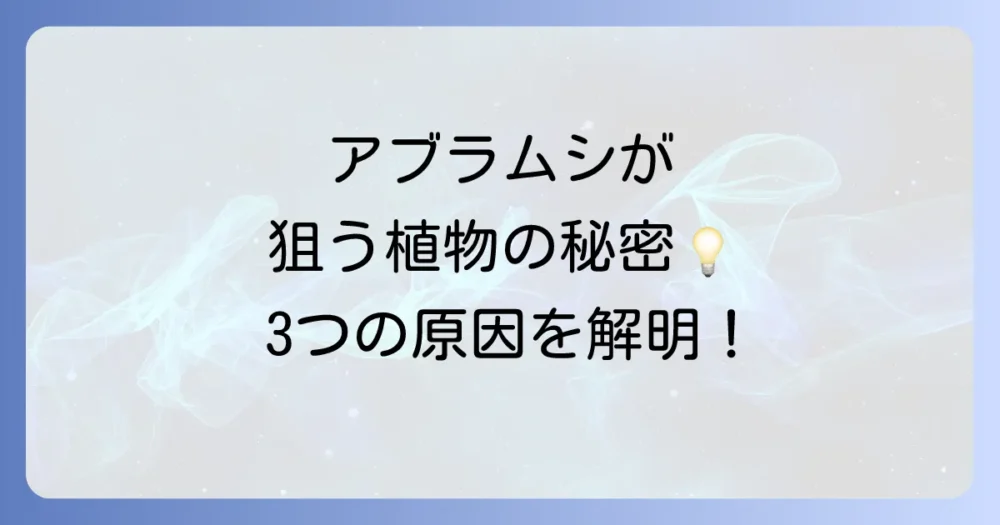
なぜアブラムシは、特定の植物を選んで集まってくるのでしょうか。その理由は、アブラムシの生態と植物の状態に隠されています。ここでは、アブラムシが植物に引き寄せられる主な3つの原因について解説します。この原因を知ることで、効果的な予防策へと繋がります。
- 原因1:柔らかい新芽や葉
- 原因2:窒素(チッソ)肥料の与えすぎ
- 原因3:日当たり・風通しの悪い環境
原因1:柔らかい新芽や葉
アブラムシは、硬い葉よりも柔らかくて瑞々しい部分を好みます。 なぜなら、彼らの口は植物に突き刺して汁を吸う「吸汁性」という特徴を持っているからです。 そのため、植物の中でも特に成長が盛んな新芽や若葉、つぼみといった部分は、組織が柔らかく、アブラムシにとって非常に吸汁しやすい場所なのです。
春先にアブラムシの発生が多くなるのは、多くの植物が一斉に新芽を出し始める時期と重なるためです。 植物が元気に成長している証でもある新芽が、皮肉にもアブラムシを呼び寄せる原因の一つになっているのです。
原因2:窒素(チッソ)肥料の与えすぎ
植物の成長を促すために与える肥料が、逆にアブラムシを呼び寄せる原因になることがあります。特に、窒素(チッソ)成分の多い肥料の与えすぎには注意が必要です。
窒素は葉や茎の成長を促進する「葉肥(はごえ)」とも呼ばれる重要な成分ですが、これが過剰になると植物体内のアミノ酸が増加します。 実は、このアミノ酸はアブラムシの大好物なのです。 良かれと思って与えた肥料が、アブラムシにとってのごちそうを作り出し、結果的に大量発生を招いてしまうケースは少なくありません。肥料は規定量を守り、バランスの取れたものを選ぶことが大切です。
原因3:日当たり・風通しの悪い環境
アブラムシは、日当たりが悪く、風通しの悪いジメジメした環境を好みます。 植物が密集して植えられていたり、剪定不足で葉が茂りすぎていたりすると、株元の日当たりや風通しが悪化します。
このような環境は、アブラムシが天敵から身を隠しやすく、安心して繁殖できる絶好の場所となります。 また、日照不足や風通しの悪さは植物自体の生育を弱らせ、病害虫への抵抗力を低下させる原因にもなります。 植物を健康に保ち、アブラムシを寄せ付けないためには、適切な株間を保ち、定期的な剪定で風通しと日当たりを確保することが非常に重要です。
アブラムシを放置するとどうなる?知っておきたい被害
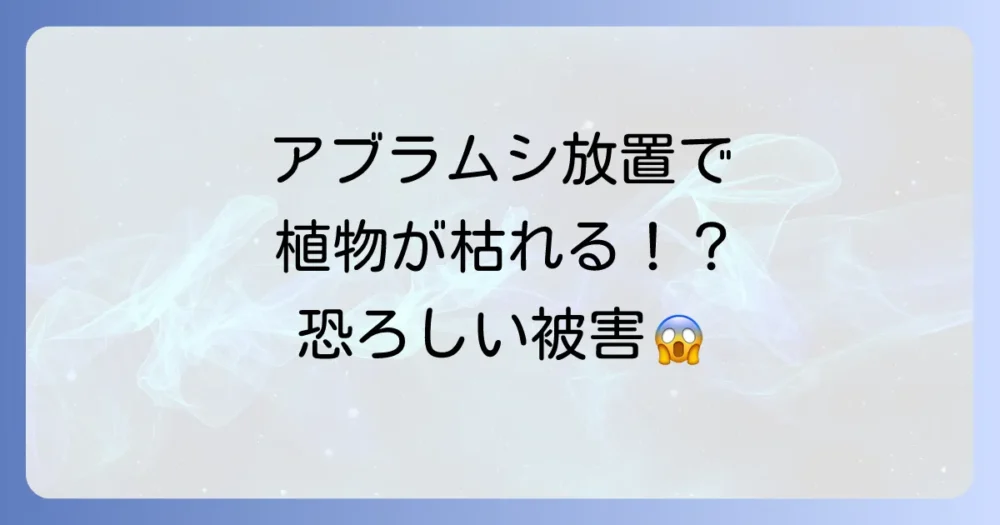
「小さな虫だから」とアブラムシを侮ってはいけません。その驚異的な繁殖力であっという間に増え、植物に深刻なダメージを与えます。ここでは、アブラムシを放置した場合に起こる、恐ろしい被害について具体的に解説します。
- 直接的な被害:吸汁による生育阻害
- 間接的な被害1:ウイルス病(モザイク病など)の媒介
- 間接的な被害2:「すす病」の誘発
- 間接的な被害3:アリを呼び寄せる
直接的な被害:吸汁による生育阻害
アブラムシによる最も直接的な被害は、植物の汁を吸われることによる生育阻害です。 アブラムシは、植物の葉や茎、新芽などに口針を突き刺し、栄養分が詰まった師管液を吸い取ります。
一匹一匹の吸汁量はわずかでも、群れで一斉に加害するため、植物は深刻な栄養不足に陥ります。 その結果、葉が縮れたり、変形したり、成長が著しく悪くなったりします。最悪の場合、株全体が弱って枯れてしまうこともあります。特に、まだ成長段階にある若い苗や新芽が被害に遭うと、その後の生育に大きな影響が出てしまいます。
間接的な被害1:ウイルス病(モザイク病など)の媒介
アブラムシの被害で最も厄介なのが、ウイルス病を媒介することです。 アブラムシは、ウイルスに感染した植物の汁を吸った後、健康な植物に移動して吸汁することで、ウイルスを次々と広げてしまいます。
代表的な病気に「モザイク病」があります。 この病気にかかると、葉にモザイクのような濃淡のまだら模様が現れ、縮れたり奇形になったりして、やがて株全体の生育が悪くなります。 ウイルス病には治療薬がなく、一度かかってしまうと回復させることは困難です。 被害が広がらないように、病気にかかった株を抜き取って処分するしかありません。
間接的な被害2:「すす病」の誘発
アブラムシがたくさんいる葉や茎が、黒いすすで覆われたように汚れているのを見たことはありませんか?これは「すす病」という病気です。
この病気は、アブラムシの排泄物である「甘露(かんろ)」が原因で発生します。 甘露は糖分を多く含んでいてベタベタしており、これを栄養源として黒いカビが繁殖します。 このカビが植物の表面を覆うことで、すす病となります。すす病自体が直接植物を枯らすことは少ないですが、葉の表面を覆ってしまうことで光合成を妨げ、植物の生育を阻害してしまいます。 また、見た目も非常に悪くなります。
間接的な被害3:アリを呼び寄せる
アブラムシが発生している植物の周りで、アリが行列を作っているのを見かけることがあります。これは、アリがアブラムシの出す甘い排泄物「甘露」を好んで集めているためです。
アリとアブラムシは、実は「共生関係」にあります。アリは甘露をもらう代わりに、アブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブの幼虫などを追い払い、アブラムシを外敵から守るボディーガードの役割を果たします。 そのため、アリがいるとアブラムシは安心して繁殖を続けることができ、被害がさらに拡大してしまうという悪循環に陥るのです。
アブラムシを寄せ付けない!今日からできる予防策5選
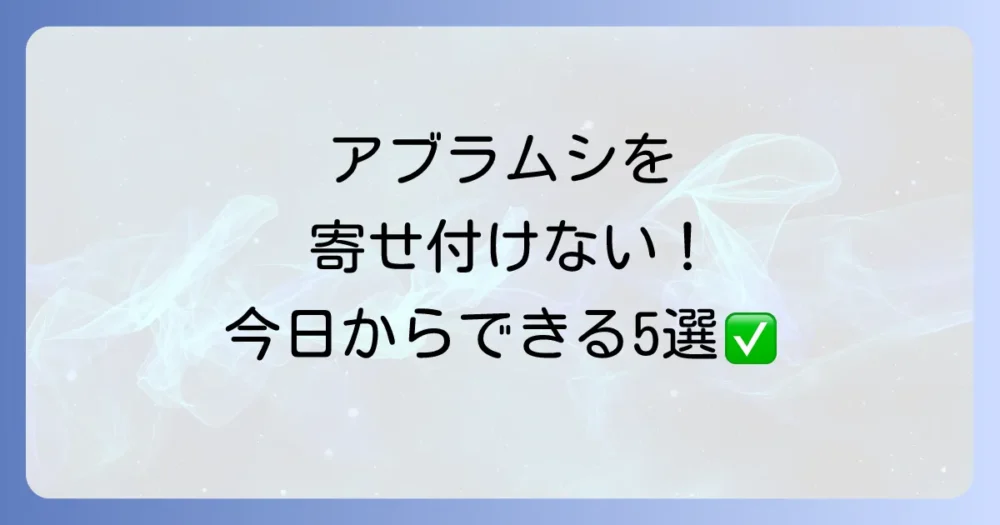
アブラムシの被害を防ぐには、何よりも予防が大切です。発生してから駆除するのは大変ですが、あらかじめアブラムシが嫌う環境を作っておくことで、被害を最小限に抑えることができます。ここでは、誰でも簡単に始められる5つの予防策をご紹介します。
- 対策1:コンパニオンプランツを活用する
- 対策2:キラキラ光るものを設置する
- 対策3:適切な肥料管理
- 対策4:風通しと日当たりを確保する
- 対策5:防虫ネットを活用する
対策1:コンパニオンプランツを活用する
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いによい影響を与え合う植物のことです。アブラムシ対策として、特定の香りを放つハーブなどを一緒に植える方法が効果的です。
アブラムシが嫌う香りの代表格は、ミント、セージ、バジル、ローズマリーなどのシソ科のハーブや、カモミール、マリーゴールドといったキク科の植物です。 これらの植物を、アブラムシを避けたい野菜や花の近くに植えることで、アブラムシが寄り付きにくくなります。逆に、チャイブのようにアブラムシを引き寄せる植物を「おとり」として使い、守りたい植物から遠ざけるという方法もあります。
対策2:キラキラ光るものを設置する
アブラムシは、キラキラと乱反射する光を非常に嫌う性質があります。 この習性を利用して、アブラムシを物理的に遠ざける方法があります。
プロの農家では、畝を覆う「シルバーマルチ」という銀色のシートを使ってアブラムシの飛来を防いでいます。 家庭菜園では、そこまで大掛かりでなくても、植物の株元にアルミホイルを敷いたり、短冊状に切ったアルミホイルを支柱に吊るしたりするだけでも効果が期待できます。 光が乱反射することでアブラムシの方向感覚を狂わせ、植物に近づきにくくさせるのです。
対策3:適切な肥料管理
前の章でも触れましたが、窒素(チッソ)肥料の与えすぎはアブラムシを呼び寄せる大きな原因となります。 植物を元気に育てたい一心で肥料をたくさん与えてしまうと、植物体内のアミノ酸濃度が高まり、アブラムシにとって魅力的な環境を作り出してしまいます。
大切なのは、肥料のパッケージに記載されている規定量を守り、与えすぎないことです。 また、窒素・リン酸・カリがバランスよく配合された肥料を選ぶようにしましょう。特に、植物の成長が旺盛になる春先は、肥料の量に注意が必要です。適切な肥料管理は、植物を健康に育て、結果的に病害虫に強い株を作ることにも繋がります。
対策4:風通しと日当たりを確保する
アブラムシは、日当たりが悪く、湿気がこもる場所を好みます。 そのため、植物の植え付け間隔(株間)を適切にとり、風通しを良くすることが基本的な予防策となります。
また、葉が茂りすぎて内部が蒸れている場合は、適度に剪定や葉かきを行い、株の中心部まで光と風が通るようにしてあげましょう。 これにより、アブラムシが好むジメジメした環境を改善できるだけでなく、植物自体が健康に育ち、病害虫への抵抗力も高まります。 定期的なお手入れが、アブラムシを遠ざける第一歩です。
対策5:防虫ネットを活用する
特にアブラナ科の野菜など、アブラムシの被害を絶対に避けたい場合には、防虫ネットで物理的にトンネルを作って覆うのが最も確実な方法です。
アブラムシは非常に小さいため、目の細かいネットを選ぶ必要があります。防虫ネットでしっかりと覆うことで、羽の生えたアブラムシが飛んできて卵を産み付けるのを防ぐことができます。 ネットをかける際は、裾に隙間ができないように土でしっかり埋めるなど、アブラムシが侵入できないように工夫することが大切です。
もし発生してしまったら?アブラムシの効果的な駆除方法
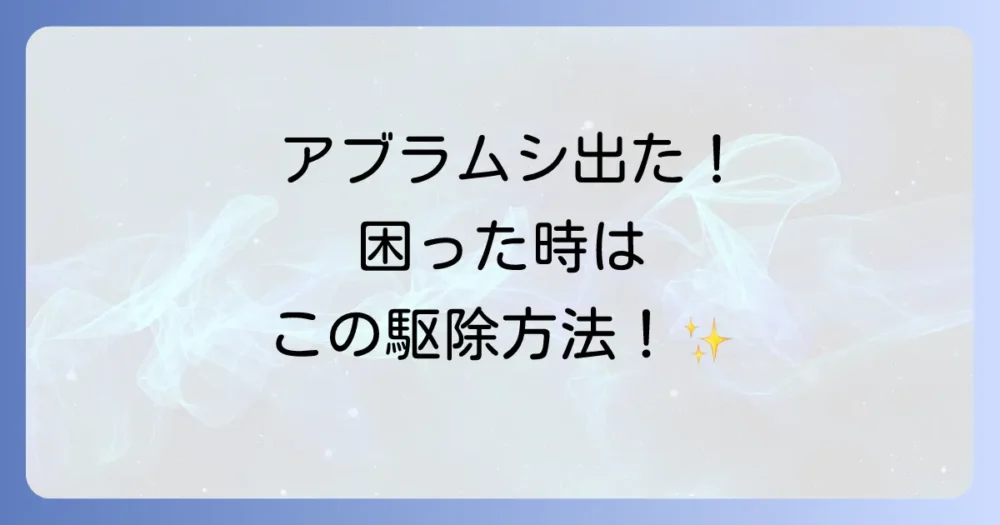
予防策を講じていても、アブラムシが発生してしまうことはあります。発見したら、数が少ないうちに早めに対処することが重要です。ここでは、無農薬でできる手軽な方法から、天敵の力を借りる方法、最終手段としての薬剤まで、効果的な駆除方法を紹介します。
- 無農薬でできる駆除方法
- 天敵の力を借りる
- どうしてもダメな場合は薬剤(殺虫剤)を使う
無農薬でできる駆除方法
家庭菜園や、小さなお子様やペットがいるご家庭では、できるだけ農薬を使わずに駆除したいものです。アブラムシは、薬剤を使わなくても対処できる方法がいくつかあります。
テープや歯ブラシで取り除く
アブラムシの数がまだ少ない初期段階であれば、物理的に取り除くのが最も手軽で確実です。セロハンテープやガムテープなどの粘着テープを、アブラムシがいる部分にペタペタと貼り付けて捕殺します。 粘着力が強すぎると植物を傷つけてしまう可能性があるので、粘着力の弱いテープを使うか、一度手の甲などで粘着力を弱めてから使うと良いでしょう。また、使い古しの歯ブラシなどで優しくこすり落とす方法も有効です。
水で洗い流す
ホースのシャワーやスプレーボトルを使って、勢いよく水をかけて洗い流す方法も効果的です。 アブラムシは水に弱く、強い水流で簡単に植物から剥がれ落ちます。特に葉の裏に潜んでいることが多いので、葉をめくりながら下からも水をかけるのがポイントです。ただし、この方法ではアブラムシが地面に落ちるだけで死滅はしないため、再付着を防ぐためにも定期的に行う必要があります。
牛乳スプレー
昔から知られている民間療法ですが、牛乳スプレーもアブラムシ駆除に利用できます。 牛乳を水で薄めず原液のままスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接吹きかけます。 吹き付けた牛乳が乾く際に膜を作り、アブラムシの気門(呼吸するための穴)を塞いで窒息させるという仕組みです。 散布後は、牛乳が腐敗して悪臭やカビの原因になるため、乾いたら必ず水でしっかりと洗い流すようにしてください。
木酢液・竹酢液スプレー
木酢液や竹酢液は、木炭や竹炭を作る際に出る煙を冷却して液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。 アブラムシはこの香りを嫌うため、忌避効果が期待できます。 木酢液や竹酢液を規定の倍率(製品の指示に従ってください)に水で薄め、スプレーで植物全体に散布します。 殺虫効果はありませんが、定期的に散布することでアブラムシを寄せ付けにくくする予防効果が見込めます。
天敵の力を借りる
自然の生態系を利用して、アブラムシの天敵に食べてもらうという方法もあります。これは「生物的防除」と呼ばれ、環境に優しい方法です。
アブラムシの天敵として最も有名なのがテントウムシです。 特にナナホシテントウやナミテントウは、幼虫も成虫もアブラムシを大好物とし、1日に何十匹、多いものでは100匹以上も捕食してくれます。 庭でテントウムシを見かけたら、むやみに駆除せず、アブラムシがいる植物の近くにそっと放してあげましょう。その他にも、ヒラタアブの幼虫やクサカゲロウの幼虫、アブラムシの体内に卵を産み付けるアブラバチなども強力な天敵です。 殺虫剤を使うとこれらの益虫も死んでしまうため、天敵の力を借りたい場合は薬剤の使用を控えることが大切です。
どうしてもダメな場合は薬剤(殺虫剤)を使う
アブラムシが大量発生してしまい、手作業での駆除や天敵の力だけでは追いつかない場合は、最終手段として園芸用の殺虫剤を使用することも検討しましょう。
殺虫剤には、直接虫にかけて駆除するスプレータイプや、土に混ぜて根から成分を吸収させ、植物全体に効果を行き渡らせる粒剤タイプなど、様々な種類があります。 野菜に使用する場合は、収穫前日まで使えるものなど、食品への安全性が配慮された製品を選びましょう。 使用する際は、必ず製品のラベルに記載されている使用方法、対象植物、希釈倍率などをよく読み、正しく使用することが重要です。
よくある質問
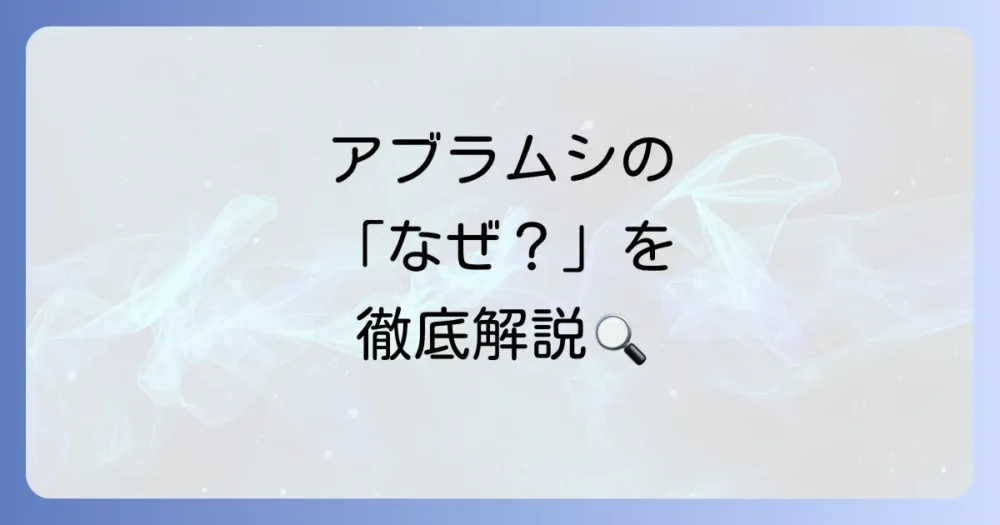
アブラムシはどこからやってくるのですか?
アブラムシは、主に2つの方法でやってきます。一つは、羽の生えた成虫(有翅型)が風に乗って飛んでくるケースです。 特に春や秋に、他の場所で増えたアブラムシが新しい餌場を求めて飛来し、植物に住み着いて繁殖を始めます。もう一つは、購入した苗や土に卵や幼虫が付着しているケースです。 また、人の衣服やペットにくっついて屋内に持ち込まれることもあります。
アブラムシに天敵はいますか?
はい、アブラムシには多くの天敵がいます。最も有名なのはテントウムシで、幼虫・成虫ともにアブラムシを捕食します。 その他にも、ウジ虫のような見た目のヒラタアブの幼虫、クサカゲロウの幼虫、アブラムシの体内に卵を産み付けて内部から食べてしまう寄生バチ(アブラバチなど)も有力な天敵です。 これらの天敵を味方につけることで、薬剤に頼らずにアブラムシの数をコントロールすることが可能です。
牛乳スプレーはなぜ効くのですか?
牛乳スプレーがアブラムシに効く理由は、牛乳が乾燥する際にできる膜が、アブラムシの体表にある呼吸するための穴(気門)を塞いでしまうためです。 これにより、アブラムシは呼吸ができなくなり窒息して死んでしまいます。殺虫成分で駆除するわけではないので、薬剤に抵抗性を持つアブラムシにも効果が期待できます。ただし、使用後は悪臭やカビの原因になるため、水で洗い流すことが必須です。
室内(観葉植物)でもアブラムシは発生しますか?
はい、発生します。室内は天敵がいないため、一度侵入を許すとアブラムシにとって安全な繁殖場所となります。侵入経路としては、窓や網戸の隙間から羽のあるタイプが飛んでくる、外から帰宅した人の衣服や持ち物に付着して持ち込まれる、新しく購入した観葉植物の苗に元々ついていた、などが考えられます。 室内でも油断せず、定期的に植物をチェックすることが大切です。
アブラムシが好きな色や匂いはありますか?
アブラムシは黄色に引き寄せられる性質があると言われています。 この習性を利用して、黄色の粘着シートで捕獲する方法があります。 匂いに関しては、アブラムシは植物が出すアミノ酸などの匂いに誘引されると考えられています。 逆に、ミントやマリーゴールドなどのハーブが出す強い香りは嫌う傾向があるため、コンパニオンプランツとして利用されています。
まとめ
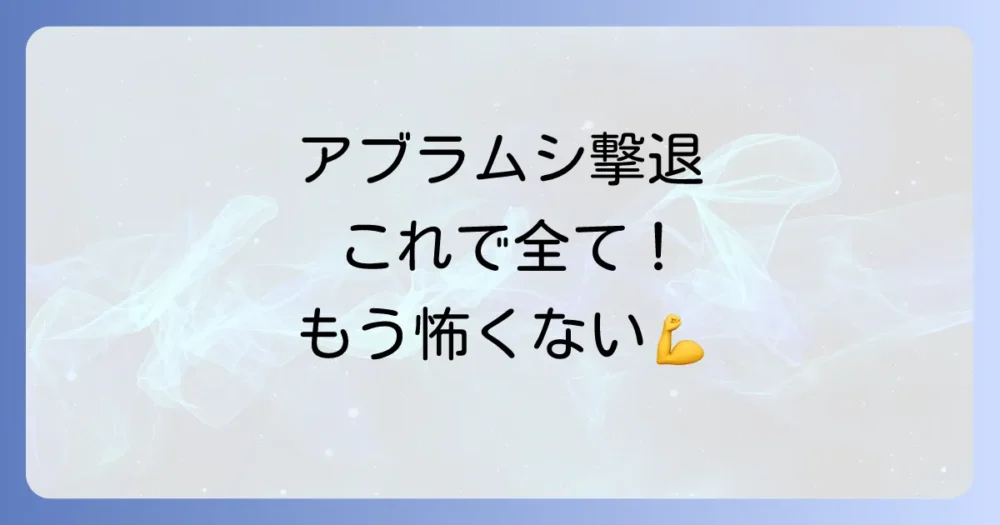
- アブラムシは柔らかい新芽や若葉を好む。
- ナス科、アブラナ科、バラ科の植物は特に注意が必要。
- 窒素肥料の与えすぎはアブラムシを呼び寄せる。
- 日当たりや風通しの悪い環境で発生しやすい。
- 吸汁被害のほか、ウイルス病やすす病の原因になる。
- アリがいるとアブラムシの繁殖を助長してしまう。
- 予防にはコンパニオンプランツや光るものが有効。
- 適切な肥料管理と風通しの確保が基本対策。
- 発生初期はテープや水流で物理的に駆除できる。
- 牛乳スプレーや木酢液は無農薬での対策に使える。
- 天敵のテントウムシはアブラムシの強力な捕食者。
- 大量発生時は園芸用の殺虫剤の使用も検討する。
- 薬剤使用時は用法・用量を必ず守ることが重要。
- 室内でも観葉植物に発生する可能性がある。
- アブラムシ対策は早期発見・早期対応が鍵となる。