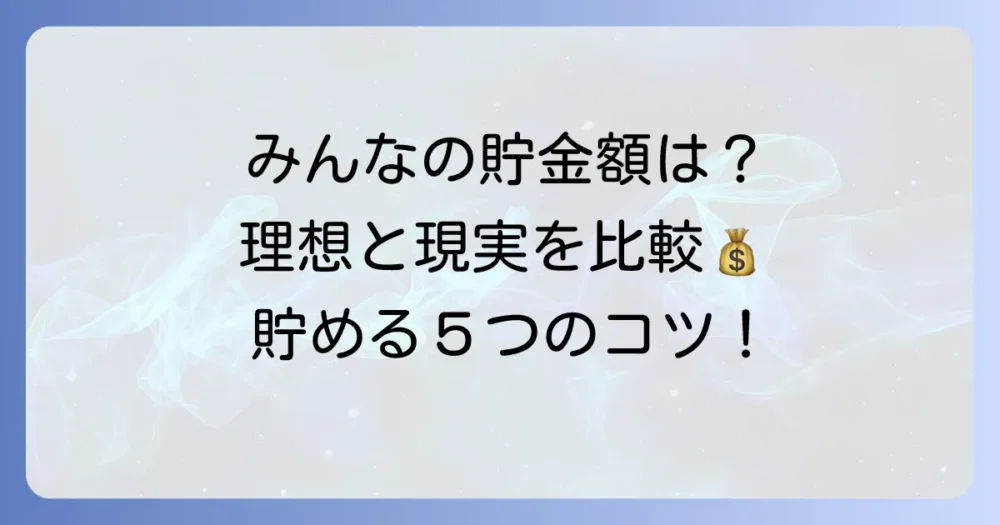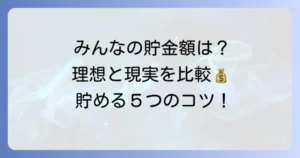「周りの人はどれくらい貯金しているんだろう?」「自分のこの貯金額で、将来大丈夫かな…」そんな漠然とした不安を抱えていませんか?本記事では、年代別の理想の貯金額と、リアルな平均値・中央値を徹底比較。あなたの現在地を確認し、無理なく理想に近づくための具体的な5つのコツを分かりやすく解説します。この記事を読めば、お金の不安が解消され、未来に向けた具体的な一歩を踏み出せるはずです。
【年代別】貯金額の理想と現実|平均・中央値データを徹底比較
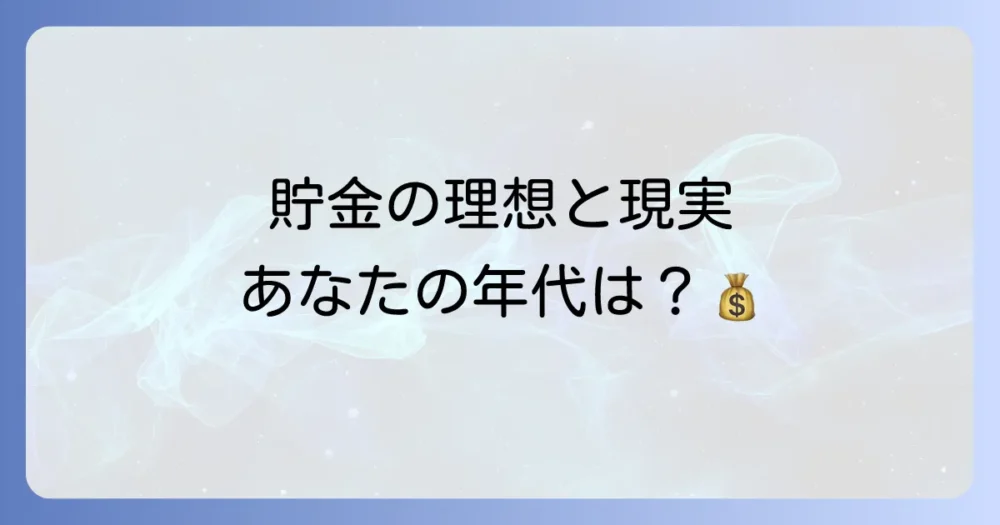
将来のために貯金が大切なのは分かっていても、具体的にいくらを目指せば良いのか、そして自分の貯金額が他の人と比べて多いのか少ないのか、気になりますよね。ここでは、信頼できる公的なデータをもとに、年代別の貯金額のリアルな実態と、目指すべき理想の金額について詳しく見ていきましょう。
本章でご紹介する主な内容はこちらです。
- データをみる上での注意点:「平均値」と「中央値」の違い
- 【20代】貯金額の理想と現実
- 【30代】貯金額の理想と現実
- 【40代】貯金額の理想と現実
- 【50代】貯金額の理想と現実
- 【60代以降】貯金額の理想と現実
データをみる上での注意点:「平均値」と「中央値」の違い
貯金額のデータを見る際に、「平均値」と「中央値」という2つの指標がよく使われます。この2つの違いを理解しておくことは、現状を正しく把握するために非常に重要です。なぜなら、より実態に近い数値を知ることができるからです。
平均値は、調査対象者全員の貯金額を合計し、その人数で割った数値です。計算が簡単な一方で、一部の極端に貯金額が多い富裕層の数値に大きく引き上げられてしまう傾向があります。 例えば、5人中4人の貯金額が100万円で、1人だけ1億円の人がいると、平均値は約2080万円となり、多くの人の実感とはかけ離れた金額になってしまいます。
一方、中央値は、調査対象者の貯金額を少ない順に並べたときに、ちょうど真ん中にくる人の数値です。 先ほどの例で言えば、中央値は100万円となり、より多くの人の実態に近い数値を示します。そのため、自分の貯金額を周りと比較する際は、平均値よりも中央値を参考にするのがおすすめです。
【20代】貯金額の理想と現実
社会人としてのキャリアがスタートする20代。収入もまだ多くはなく、奨学金の返済などがある一方で、自己投資や趣味にもお金を使いたい時期でしょう。そんな20代の貯金額の現実はどうなっているのでしょうか。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、20代の金融資産保有額は以下の通りです。
| 世帯 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 161万円 | 15万円 |
| 二人以上世帯 | 382万円 | 84万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
中央値を見ると、単身世帯で15万円、二人以上世帯でも84万円と、まだまとまった貯金ができていない人が多いのが実情です。しかし、20代はこれからの資産形成の土台を作る非常に重要な時期。理想としては、まず生活費の3ヶ月~半年分を緊急用の資金として貯めることを目指しましょう。 例えば、月々の生活費が15万円なら、45万円~90万円が目標です。さらに、年収の10%~15%を毎年貯蓄に回す習慣をつけられると、30代以降の資産形成がぐっと楽になります。
【30代】貯金額の理想と現実
30代は、キャリアアップによる収入増が期待できる一方で、結婚、出産、住宅購入など、人生の大きなライフイベントが集中する時期でもあります。 支出が増え、貯金が難しくなる人も多い年代です。
金融広報中央委員会の同調査によると、30代の金融資産保有額は以下のようになっています。
| 世帯 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 459万円 | 90万円 |
| 二人以上世帯 | 677万円 | 180万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
中央値は単身世帯で90万円、二人以上世帯で180万円と、20代から着実に増えているものの、平均値との乖離は依然として大きいままです。これは、貯蓄ができている人とそうでない人の差が開き始めていることを示唆しています。
30代の理想の貯金額は、年収の半分から1年分が一つの目安とされています。 例えば年収400万円なら、200万円~400万円です。ライフイベントに備えつつ、老後資金の準備も意識し始める時期であり、iDeCoやNISAといった制度の活用も視野に入れたいところです。
【40代】貯金額の理想と現実
40代は、仕事では管理職に就くなど収入がピークに近づく一方、子どもの教育費や住宅ローンの返済など、支出も最大になることが多い年代です。 まさに、家計の正念場と言えるでしょう。
金融広報中央委員会の調査による40代の金融資産保有額はこちらです。
| 世帯 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 883万円 | 85万円 |
| 二人以上世帯 | 944万円 | 250万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
二人以上世帯の中央値は250万円と、30代から増加しているものの、単身世帯では中央値が85万円と微減しています。これは、ライフスタイルの多様化などが影響していると考えられます。平均値は1000万円近くに達しており、格差がさらに広がっている様子がうかがえます。
40代の理想の貯金額は、老後資金を本格的に意識し、年収の2倍以上を目指したいところです。特に、退職金があまり期待できない場合や、自営業の場合は、より多くの準備が必要になります。50代までに2,000万円~3,000万円を目標に設定するなど、具体的な計画を立てて実行していくことが求められます。
【50代】貯金額の理想と現実
50代は、子育てが一段落し、教育費の負担が軽くなる家庭も増えてくる時期です。 定年退職が見えてくる中で、老後資金準備のラストスパートをかける重要な10年間となります。
金融広報中央委員会の調査から、50代の金融資産保有額を見てみましょう。
| 世帯 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 1,087万円 | 30万円 |
| 二人以上世帯 | 1,168万円 | 250万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
二人以上世帯の中央値は40代から横ばいの250万円ですが、単身世帯では30万円と大きく減少しており、厳しい状況がうかがえます。一方で、平均値は単身・二人以上世帯ともに1,000万円を超えており、しっかりと準備を進めている層がいることも事実です。
50代の理想の貯金額は、退職までに3,000万円が一つの大きな目標となります。 これは、いわゆる「老後2000万円問題」に、病気や介護などの予備費を加味した金額です。退職金や年金の受給見込額を確認し、不足分をこの10年間でいかに準備するか、具体的なシミュレーションと実行計画が不可欠です。
【60代以降】貯金額の理想と現実
60代は、定年退職を迎え、多くの人が年金生活に入る年代です。これまでに蓄えた資産をどのように活用し、豊かで安心なセカンドライフを送るかがテーマとなります。
金融広報中央委員会の調査による60代の金融資産保有額は以下の通りです。
| 世帯 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 1,555万円 | 300万円 |
| 二人以上世帯 | 1,897万円 | 550万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
退職金などにより、中央値も単身世帯で300万円、二人以上世帯で550万円と大きく増加しています。しかし、平均値との差は依然として大きく、準備状況には個人差が大きいことがわかります。
60代以降の理想は、貯蓄を取り崩しながら生活するだけでなく、資産寿命を延ばす工夫をすることです。 全てを安全資産である預貯金にするのではなく、一部はリスクを抑えた投資信託などで運用を続けることで、資産の目減りを緩やかにすることが可能です。また、健康なうちは働き続けるなど、収入源を確保することも、安心な老後生活につながります。
なぜ理想の貯金額を目指す必要があるの?主なライフイベントと費用
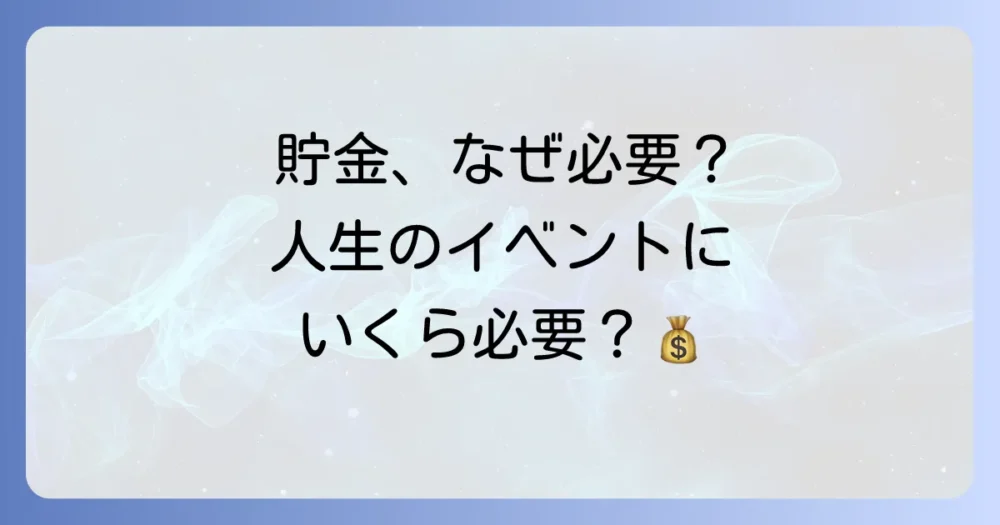
「なぜそんなに貯金が必要なの?」と疑問に思うかもしれません。貯金の目的は人それぞれですが、多くの人に共通するのが、人生の節目で起こる「ライフイベント」への備えです。ここでは、主なライフイベントと、それぞれにかかる費用の目安を見ていきましょう。これを知ることで、貯金のモチベーションがきっと上がるはずです。
この章で解説する主なライフイベントはこちらです。
- 結婚費用
- 住宅購入費用
- 子どもの教育費用
- 老後資金
結婚費用
人生の大きな門出である結婚。幸せな瞬間ですが、まとまった費用がかかるイベントでもあります。婚約から新婚旅行までにかかる費用の総額は、平均で300万円前後と言われています。
主な内訳は以下の通りです。
- 結納・顔合わせ:約10万円~20万円
- 婚約・結婚指輪:約50万円~60万円
- 結婚式・披露宴:約200万円~300万円(ご祝儀で一部まかなえる場合も)
- 新婚旅行:約30万円~50万円
- 新生活準備(家具・家電など):約50万円~70万円
もちろん、挙式のスタイルや新婚旅行の行き先によって費用は大きく変動します。しかし、二人で協力して計画的に準備を進めることが、幸せな新生活の第一歩と言えるでしょう。親からの援助が期待できる場合もありますが、まずは自分たちで準備する意識が大切です。
住宅購入費用
「いつかはマイホームを」と考える人は多いでしょう。住宅は人生で最も大きな買い物と言われ、数千万円単位の資金が必要になります。多くの人が住宅ローンを利用しますが、その際に必要となるのが頭金です。
頭金の目安は、物件価格の10%~20%程度とされています。例えば、4,000万円の物件であれば、400万円~800万円の頭金があると、その後のローン返済が楽になります。頭金が多いほど、借入額が減り、月々の返済額や総支払額を抑えることができるからです。
また、物件価格以外にも、登記費用や不動産取得税、仲介手数料といった諸費用が物件価格の5%~10%程度かかります。これらの費用も現金で用意する必要があるため、計画的な資金準備が欠かせません。
子どもの教育費用
子どもの成長は喜ばしいものですが、同時に教育費という長期的な支出が始まります。子ども一人を育てるのにかかる教育費は、幼稚園から大学卒業まで、すべて国公立でも約1,000万円、すべて私立の場合は約2,500万円以上かかると言われています。
特に負担が大きくなるのが大学の費用です。国公立大学でも4年間で約250万円、私立大学理系の場合は500万円以上かかることも珍しくありません。これらの費用を、家計に大きな負担をかけずに支払うためには、子どもが小さいうちから学資保険やNISAなどを活用して、コツコツと準備しておくことが非常に重要です。
老後資金
近年、「老後2000万円問題」という言葉をよく耳にするようになりました。 これは、高齢夫婦無職世帯が、年金収入だけでは毎月約5万円の赤字となり、30年間で約2,000万円の貯蓄が必要になるという試算から来ています。
しかし、これはあくまで平均的なモデルケースです。ゆとりのある老後を送りたい場合、例えば夫婦で旅行に行ったり、趣味を楽しんだりするためには、さらに多くの資金が必要になります。生命保険文化センターの調査では、ゆとりある老後生活費として月々約38万円が必要というデータもあり、この場合、不足額はさらに大きくなります。
持ち家の有無、健康状態、どのような生活を送りたいかによって必要な金額は変わりますが、公的年金だけに頼るのではなく、自分自身で資産を準備しておく「じぶん年金」の考え方が不可欠です。 早めに準備を始めるほど、月々の負担は軽くなります。30代、40代からの計画的な準備が、安心で豊かな老後につながるのです。
理想の貯金額を達成するための5つのコツ
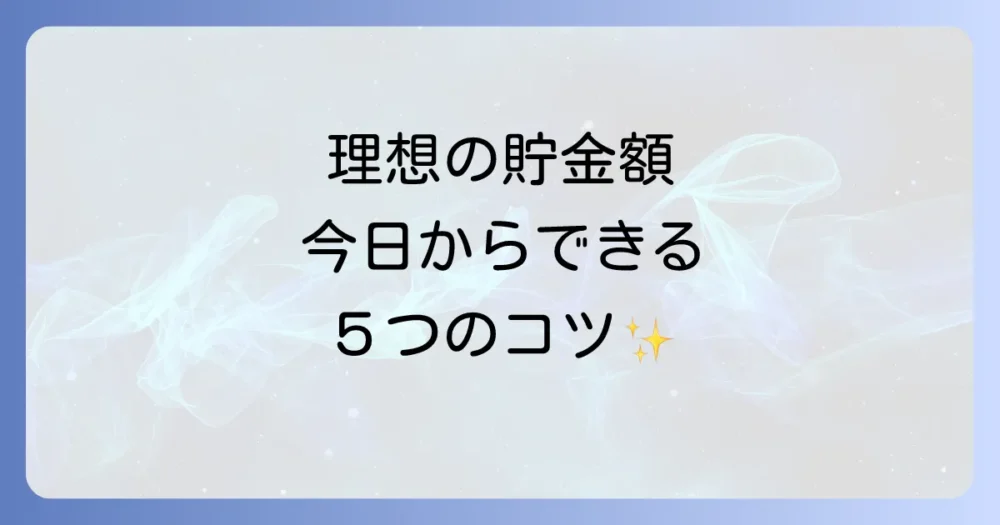
年代別の理想と現実、そして貯金の目的が明確になったところで、いよいよ実践編です。「でも、どうやって貯めたらいいの?」という方のために、今日から始められる具体的な5つのコツをご紹介します。難しいことはありません。一つずつ着実に実行すれば、あなたの貯金は確実に増えていきます。
ここで紹介する5つのコツはこちらです。
- コツ1:家計の収支を「見える化」する
- コツ2:「先取り貯金」を仕組み化する
- コツ3:大きな固定費から見直す
- コツ4:収入を増やす努力も始める
- コツ5:NISAなどを活用して「お金にも働いてもらう」
コツ1:家計の収支を「見える化」する
貯金の第一歩は、自分のお金が「何に」「いくら」使われているのかを正確に把握することです。 これができていないと、どこを節約すれば良いのか分からず、闇雲な節約は長続きしません。まずは1ヶ月、家計簿をつけてみましょう。
最近は、レシートを撮影するだけで自動で記録してくれる便利な家計簿アプリがたくさんあります。クレジットカードや銀行口座と連携すれば、入力の手間も省けてさらに簡単です。家計簿をつけることで、「思ったよりコンビニで無駄遣いしているな」「サブスクの料金が意外と高い…」といった、お金の使い方のクセや問題点が見えてきます。この「気づき」こそが、貯金体質への改善のスタートラインです。
コツ2:「先取り貯金」を仕組み化する
「給料が余ったら貯金しよう」という考え方では、お金はなかなか貯まりません。なぜなら、手元にお金があると、ついつい使ってしまうのが人間の心理だからです。そこでおすすめなのが、「収入-貯金=生活費」という考え方。 つまり、給料が入ったら、使う前に一定額を貯金用の口座に移してしまう「先取り貯金」です。
これを成功させるコツは、「仕組み化」すること。会社の財形貯蓄制度や、銀行の自動積立定期預金サービスを利用すれば、毎月決まった日に自動で給与振込口座から貯金用口座にお金を移動してくれます。 一度設定してしまえば、あとは意識しなくても勝手にお金が貯まっていく。この「強制力」が、貯金を成功させるための強力な味方になります。
コツ3:大きな固定費から見直す
家計の支出には、毎月変動する「変動費(食費、交際費など)」と、毎月ほぼ一定額が出ていく「固定費(家賃、通信費、保険料など)」があります。節約というと食費を切り詰めるイメージがありますが、効果が大きく、一度見直せば効果がずっと続くのが固定費の見直しです。
例えば、以下のような項目を見直してみましょう。
- スマートフォン:大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月々数千円の節約になることも。
- 保険:加入したままになっていませんか?ライフステージの変化に合わせて保障内容を見直すことで、保険料を安くできる可能性があります。
- サブスクリプション:利用頻度の低い動画配信サービスや音楽アプリはありませんか?一つひとつは少額でも、複数契約していると大きな金額になります。
- 家賃:更新のタイミングで、より家賃の安い物件への引っ越しを検討するのも一つの手です。
固定費を月5,000円削減できれば、年間で6万円の貯金につながります。無理な節約でストレスを溜めるよりも、まずは固定費にメスを入れるのが賢い方法です。
コツ4:収入を増やす努力も始める
支出を減らす「節約」と同時に考えたいのが、収入を増やすことです。 節約には限界がありますが、収入が増えれば、その分貯金に回せるお金も増え、目標達成のスピードが格段に上がります。
収入を増やす方法は様々です。
- 今の会社で昇進・昇給を目指す:資格取得やスキルアップで自身の市場価値を高める。
- 副業を始める:クラウドソーシングサイトなどを活用し、週末や空き時間を使って収入源を増やす。
- 転職する:より条件の良い会社に転職し、年収アップを目指す。
もちろん簡単なことではありませんが、将来の自分のために、今のうちから自己投資を行い、収入を増やすための行動を起こしておくことが、理想の貯金額を達成するための大きな力となります。
コツ5:NISAなどを活用して「お金にも働いてもらう」
超低金利時代の今、銀行にお金を預けているだけでは、資産はほとんど増えません。そこで重要になるのが、貯金と並行して「投資」を行い、お金にも働いてもらうという考え方です。
「投資」と聞くと、「怖い」「難しそう」というイメージを持つかもしれませんが、国が用意してくれている初心者向けの非課税制度「NISA(ニーサ)」を活用すれば、少額からでも安心して始めることができます。 NISAは、投資で得た利益(配当金、分配金、譲渡益)が非課税になるお得な制度です。
例えば、毎月3万円を年利5%で30年間積み立て投資した場合、元本1,080万円に対し、運用益は約1,470万円にもなり、合計で2,500万円を超える資産を築ける可能性があります。これが預貯金であれば、利息はほとんどつきません。もちろん投資にはリスクがありますが、長期・積立・分散を心がけることで、リスクを抑えながら安定的なリターンを目指すことが可能です。理想の貯金額、特に老後資金を効率的に準備するためには、NISAの活用は必須と言えるでしょう。
どうしても貯金ができない…そんなあなたが陥りがちな落とし穴と対策
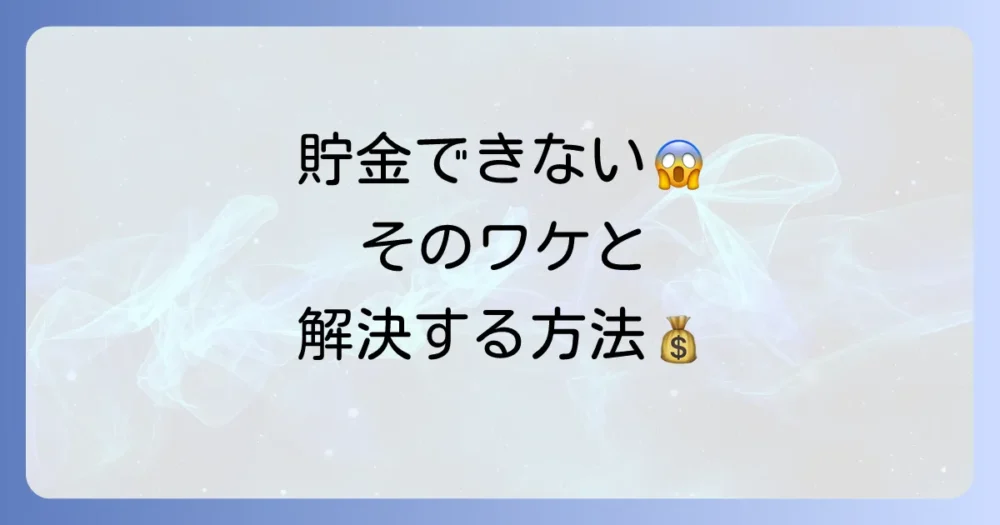
「コツは分かったけど、それでも貯金ができない…」そんな風に悩んでいませんか?貯金が苦手な人には、実は共通するいくつかの「落とし穴」があります。自分でも気づかないうちに、その穴にハマってしまっているのかもしれません。ここでは、よくある3つの落とし穴とその対策をご紹介します。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
この章で解説する主な落とし穴はこちらです。
- 落とし穴1:目標が漠然としている
- 落とし穴2:「残ったら貯金しよう」と考えている
- 落とし穴3:自分へのご褒美が多すぎる
落とし穴1:目標が漠然としている
「とにかくお金を貯めたい」というように、目標が漠然としていると、モチベーションを維持するのは難しいものです。 ゴールのないマラソンを走っているようなもので、途中で息切れしてしまうのも無理はありません。
対策:目標を具体的に設定する
大切なのは、「何のために」「いつまでに」「いくら」貯めるのかを具体的にすることです。 例えば、「3年後の海外旅行のために50万円貯める」「10年後に住宅購入の頭金として500万円貯める」といった具合です。目標が具体的になれば、そこから逆算して「毎月いくら貯めれば良いか」が明確になります。 小さな目標でも構いません。まずは達成できそうな目標を立て、成功体験を積み重ねることが、貯金を習慣化する近道です。
落とし穴2:「残ったら貯金しよう」と考えている
これは貯金ができない人に最も多いパターンです。給料日に「今月は少し贅沢しようかな」と考え、月末になって「あれ、今月もお金が残らなかった…」と後悔する。この繰り返しでは、いつまでたっても貯金は増えません。
対策:「先取り貯金」を徹底する
解決策は、前の章でもご紹介した「先取り貯金」です。 給料が入ったら、まず貯金額を別の口座に移し、残ったお金で生活する習慣をつけましょう。「このお金は最初からなかったもの」と考えるのがコツです。銀行の自動積立サービスなどを利用して、強制的に貯金する仕組みを作ってしまえば、意志の力に頼ることなく、着実にお金を貯めることができます。
落とし穴3:自分へのご褒美が多すぎる
「仕事を頑張ったから」「ストレスが溜まったから」と、何かと理由をつけて自分にご褒美をあげていませんか?適度なご褒美はモチベーション維持に繋がりますが、その頻度が多すぎたり、金額が大きすぎたりすると、貯金の妨げになります。
対策:ご褒美にルールを設ける
ご褒美を完全に無くす必要はありません。大切なのは、ルールを決めることです。「月に1回まで」「予算は5,000円以内」「〇〇を達成したら」など、自分なりのルールを設定しましょう。また、お金をかけないご褒美を見つけるのも良い方法です。例えば、好きな映画を観る、ゆっくりお風呂に入る、公園を散歩するなど、お金をかけなくても心を満たす方法はたくさんあります。計画的なご褒美で、賢くモチベーションをコントロールしましょう。
よくある質問
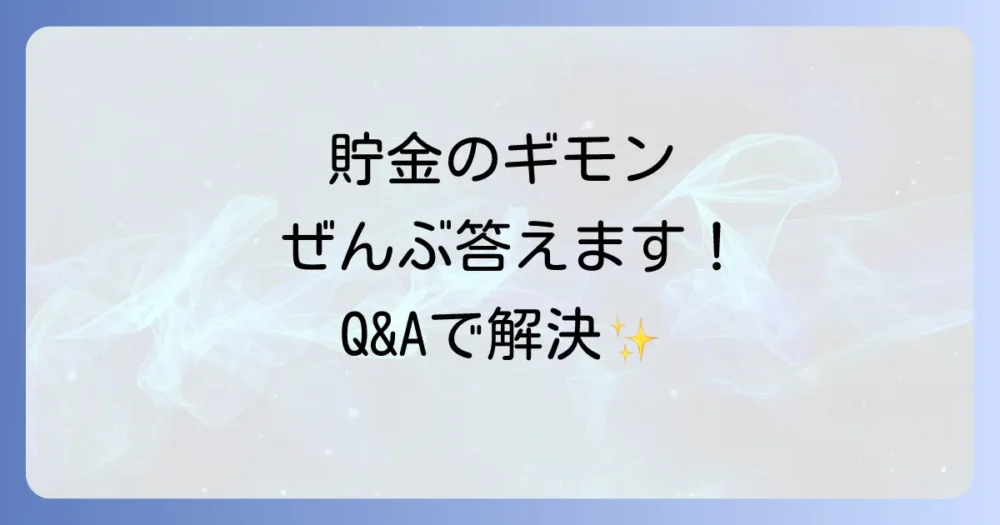
ここでは、年代別の理想の貯金額に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
手取り収入のうち、何割を貯金するのが理想ですか?
一般的に、手取り収入の10%~20%を貯金に回すのが一つの目安とされています。 収入が多い場合や、貯め時である独身時代などは30%前後を目指すのも良いでしょう。 例えば、手取り25万円なら、2.5万円~5万円が目標です。ただし、これはあくまで目安です。家族構成やライフステージによって家計の状況は大きく異なるため、無理のない範囲で自分に合った割合を見つけることが大切です。まずは5%からでも良いので、継続することを最優先に考えましょう。
貯金がゼロの人はどのくらいいますか?
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、金融資産を保有していない、つまり貯金がゼロの世帯の割合は、単身世帯で23.3%、二人以上世帯で19.7%となっています。年代別に見ると、特に若い世代でその割合が高くなる傾向があります。決して珍しいことではありませんが、病気や失業など、いざという時に備えるためにも、少額からでも貯金を始めることが重要です。
理想の貯金額は、独身と夫婦でどう変わりますか?
理想の貯金額は、独身か夫婦(二人以上世帯)かによって大きく変わります。一般的に、夫婦世帯の方が住宅購入や子どもの教育費など、将来必要となる資金が大きくなるため、独身世帯よりも多くの貯金が必要になります。実際に、各年代の貯蓄額データを見ても、二人以上世帯の方が単身世帯よりも平均値・中央値ともに高い傾向にあります。 夫婦で将来のライフプランを共有し、協力して貯蓄計画を立てることが大切です。
借金がある場合、貯金と返済どちらを優先すべきですか?
借金がある場合は、基本的には返済を優先するべきです。特に、消費者金融のカードローンなど金利が高い借金は、放置しておくと利息がどんどん膨らんでしまいます。貯金で得られる利息よりも、借金の利息の方がはるかに高いため、一日でも早く返済することが結果的に家計の助けになります。ただし、返済に全額を充ててしまい、手元に全くお金がない状態も危険です。急な出費に対応できず、新たな借金をしてしまう可能性があるからです。生活費の1ヶ月分程度の緊急用資金は確保しつつ、残りの余剰資金を全力で返済に回すのが現実的な方法と言えるでしょう。
まとめ
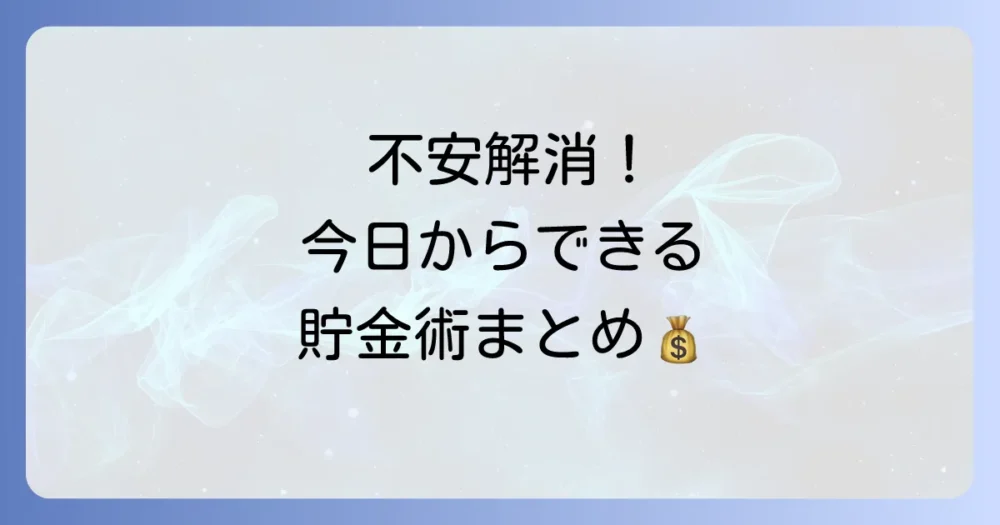
- 年代別の理想貯金額は、現実の平均・中央値と差がある
- 自分の状況を把握するには「中央値」を参考にすると良い
- 20代はまず生活防衛資金、30代は年収の1年分が目標
- 40代は老後を見据え年収の2倍以上、50代は3000万円を目指す
- 60代は資産寿命を延ばす運用を心がけることが重要
- 貯金の大きな目的は結婚・住宅・教育・老後などのライフイベント
- 貯金成功の第一歩は家計の「見える化」から
- 「先取り貯金」を仕組み化するのが最も効果的な方法
- 節約は効果の大きい「固定費」の見直しから着手する
- 支出削減と同時に「収入を増やす」努力も大切
- 低金利時代にはNISAなどを活用した「資産運用」が必須
- 貯金できない人は「目標の具体化」から始める
- 「残ったら貯金」ではなく「貯めてから使う」習慣をつける
- ご褒美は計画的に、ルールを決めて行うことが大切
- 借金がある場合は、緊急資金を確保しつつ返済を最優先する