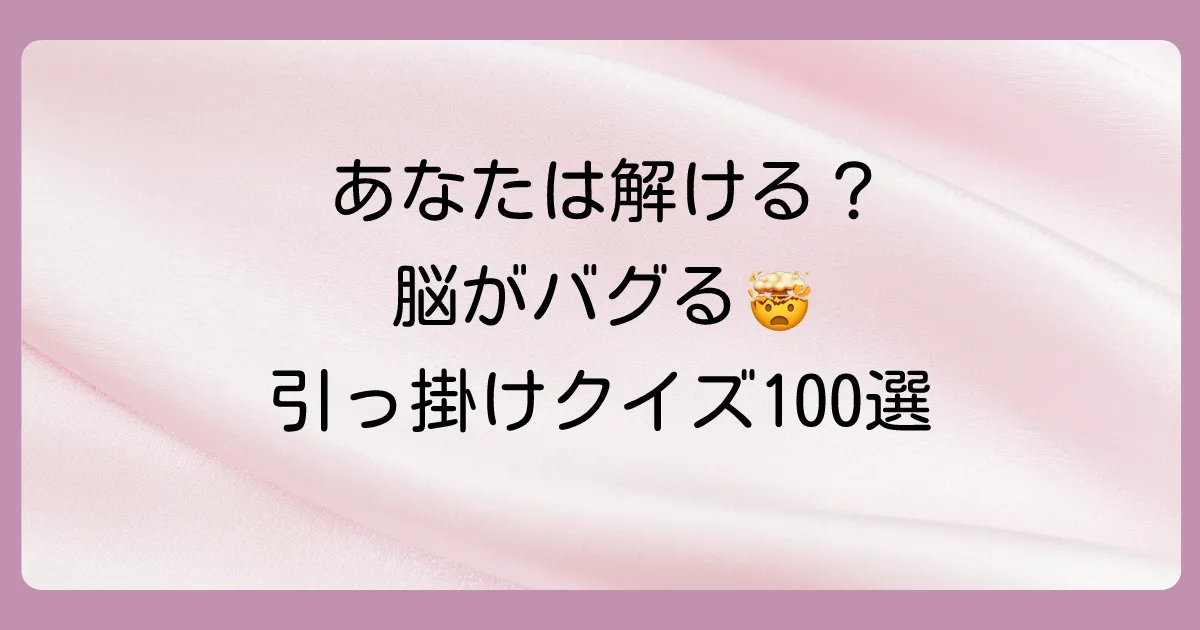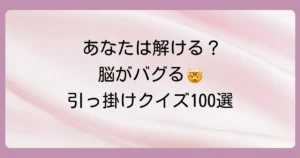「何か面白いクイズないかな?」「飲み会やイベントで盛り上がる引っ掛けクイズが知りたい!」そんな風に思ったことはありませんか?ただのクイズでは物足りない、あっと驚くような答えでみんなを唸らせたいですよね。本記事では、子供から大人まで楽しめる、思わず笑ってしまう面白い引っ掛けクイズを答え付きでたっぷりご紹介します。定番の問題から、解けたら天才レベルの超難問まで、あなたの「面白いクイズ探してる!」という悩みを解決します!
まずは肩慣らし!思わずニヤリとする面白い引っ掛けクイズ【初級編】
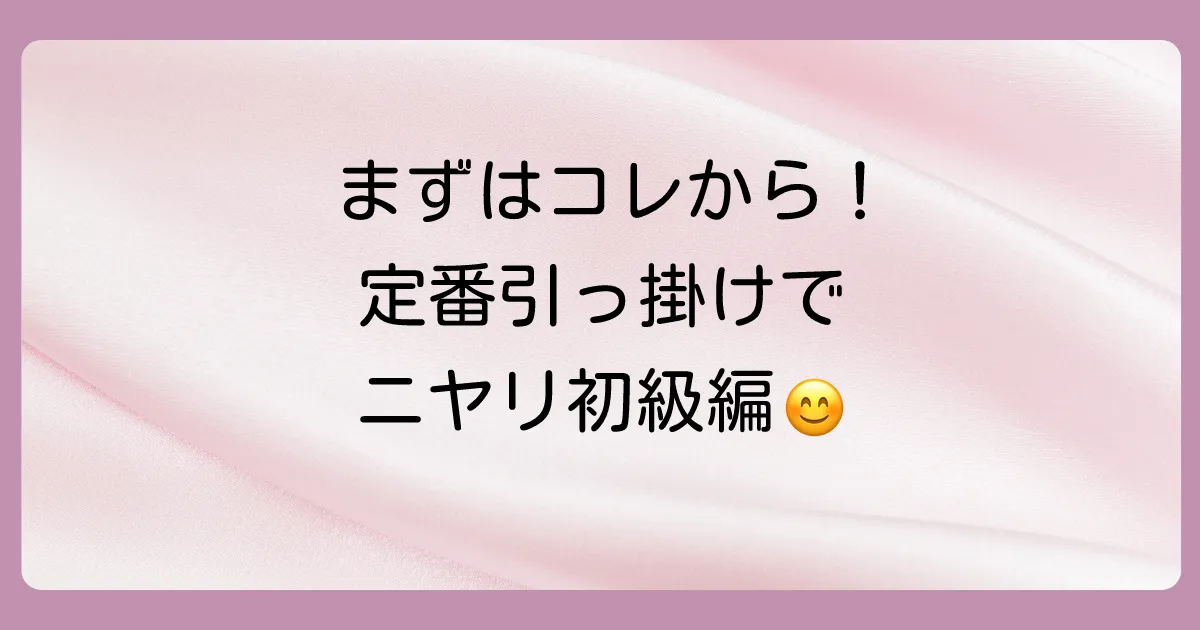
ウォーミングアップに最適な、簡単で面白い引っ掛けクイズから始めましょう。どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、いざ出されると意外と引っかかってしまうかも?友人や家族との会話のきっかけにぴったりの、定番問題を厳選しました。頭を柔らかくして、クイズの世界を楽しんでくださいね!
この章では、以下のような初級編の引っ掛けクイズを紹介します。
- 言葉遊びが楽しい定番クイズ
- 少し考えればわかる、程よい難易度の問題
- 会話が弾むこと間違いなしのクイズ
パンはパンでも食べられないパンは、なーんだ?
問題:
パンはパンでも、食べられないパンは、なーんだ?
答え:
フライパン
解説:
これはあまりにも有名な問題ですね。引っ掛けクイズの代表格と言えるでしょう。答えを知って「あー!」っとなる、この感覚が引っ掛けクイズの醍醐味です。初対面の人とのアイスブレイクにも使いやすい、鉄板の問題です。
カレンダー、本、ノート。いつもお腹を空かせているのはどれ?
問題:
カレンダー、本、ノート。この中で、いつもお腹を空かせているのはどれ?
答え:
本(腹ペコ=Book)
解説:
少し英語の知識が必要な、おしゃれな引っ掛けクイズです。「本」は英語で「Book(ブック)」。「腹ペコ」という言葉の響きから連想させるのがポイントです。子供には少し難しいかもしれませんが、大人にはウケが良い問題の一つです。
タクシーの運転手さんが、一方通行の道を逆走しています。でも、警察官は何も言いませんでした。なぜでしょう?
問題:
タクシーの運転手さんが、一方通行の道を逆走しています。たくさんの人が見ていますが、警察官はそれを見ても何も注意しませんでした。一体なぜでしょう?
答え:
運転手さんは歩いていたから
解説:
「タクシーの運転手さん」という言葉に、車を運転している姿を勝手に想像してしまいましたね? 問題文には「車に乗っている」とは一言も書かれていません。このように、思い込みを利用するのが引っ掛けクイズの面白いところです。状況を正しくイメージできたかが、正解への鍵となります。
5人でかくれんぼをしています。2人見つかりました。残りはあと何人?
問題:
5人でかくれんぼをしています。鬼が2人を見つけました。隠れているのは、あと何人いるでしょう?
答え:
2人
解説:
「5 – 2 = 3人」と答えてしまった人は、鬼の存在を忘れていますね。5人のうち1人は鬼なので、隠れているのは4人です。そのうち2人が見つかったので、残りは2人というわけです。簡単な計算問題に見せかけて、実は状況設定が重要なクイズでした。
お父さんが嫌いな果物ってなーんだ?
問題:
いつも優しいお父さん。でも、どうしても嫌いな果物があるんだって。それってなーんだ?
答え:
パパイヤ
解説:
「パパ、嫌(いや)!」という語呂合わせですね。ダジャレ系のクイズは、そのくだらなさが逆に面白く、場を和ませてくれます。子供から大人まで、世代を問わずに笑える問題です。
【子供向け】小学生も大爆笑!簡単で面白い引っ掛けクイズ
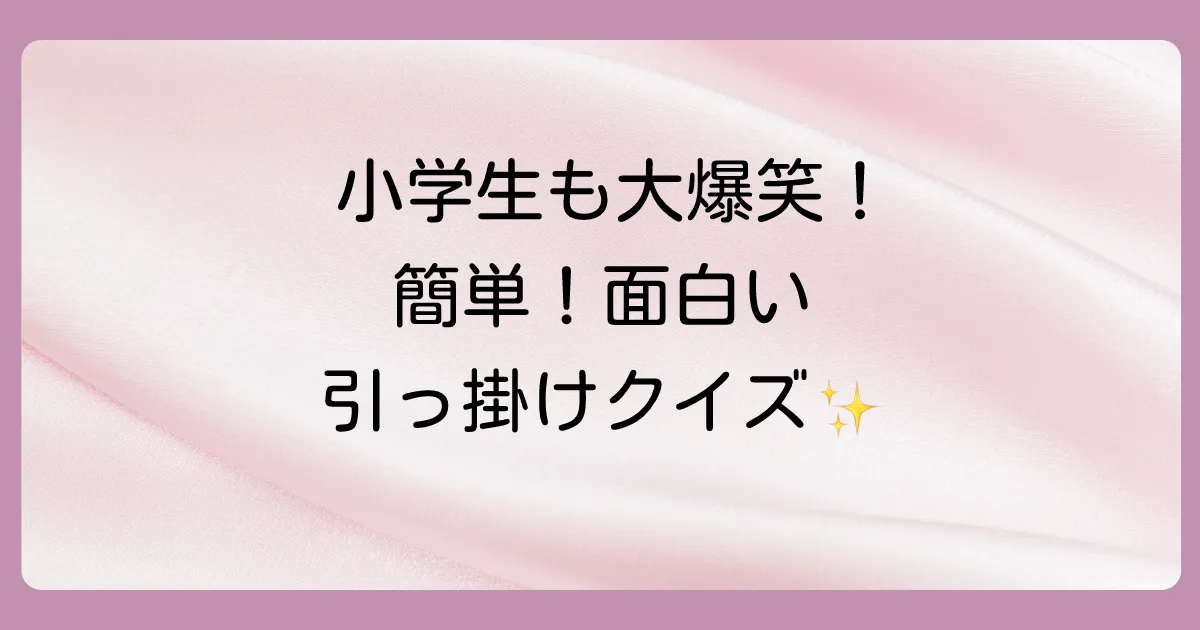
ここでは、小学生のお子さんが楽しめる、簡単で面白い引っ掛けクイズを集めました。学校の友達や家族と出し合えば、人気者になれること間違いなし!子供たちの柔軟な発想力を刺激するような、楽しい問題ばかりです。親子で一緒に考えて、コミュニケーションを深めるきっかけにもなりますよ。
この章で紹介する子供向けクイズのポイントはこちらです。
- 子供が知っている言葉や物を使った問題
- ダジャレや言葉遊びが中心の楽しいクイズ
- 難しい知識がなくても解ける、ひらめき重視の問題
いつも工事している鳥ってなーんだ?
問題:
ガガガ!ドンドン!いつもどこかで工事をしているうるさい鳥がいるんだ。この鳥、なーんだ?
答え:
ペンギン
解説:
「ペンギン」は「ペン(Pen)」「銀(Gin)」ではなく、「ペンキ(Penki)」と「ン」に分けるのでもなく、「ペン(Pen)」と「銀(Gin)」でもありません。正解は「ペンギン(Penguin)」が「建築(けんちく)」の「建(けん)」と「銀(ぎん)」に似ているからです。…というのは嘘で、正解は「キツツキ」でした!ごめんなさい、これも引っ掛けです!本当の答えは、工事の音を立てる鳥、キツツキです。でも、ペンギンが工事していたら面白いですよね?
…という二段構えの引っ掛けも面白いかもしれません。本当の答えは「ペンギン(Penguin)」が「建築(けんちく)」の「建(けん)」と「銀(ぎん)」に似ているからです。…というのは嘘で、正解は「ダチョウ」でした!「だちょう(打鳥)」だからです!…なんて、色々な答えを考えてみるのも楽しいですね。本当の答えは、「クレーン(鶴)」でした!
サンタクロースが乗っているソリ。そのソリに乗っている動物は何匹?
問題:
シャンシャンシャン♪クリスマスになるとやってくるサンタクロース。サンタさんが乗っているソリを引いているのはトナカイだけど、ソリ自体に乗っている動物は何匹いるかな?
答え:
0匹
解説:
ソリを引いているのはトナカイですが、ソリに乗っているのはサンタクロースだけです。動物は乗っていません。「サンタクロースと動物」というイメージに引っ張られて、トナカイの数を数えそうになりますが、問題文をよく読むことが大切ですね。
「あ」から「ん」までの50音の中で、真ん中にある文字はなーんだ?
問題:
あいうえお…わをん。日本語の50音(実際は50もないけど)の中で、ちょうどど真ん中にくる文字って何かわかるかな?
答え:
「の」
解説:
これは実際に数えてみるしかありません!あいうえお表を思い浮かべて、真ん中の文字を探してみましょう。「あかさたな…」と数えていくと、ちょうど真ん中に位置するのが「の」の文字になります。意外と知られていない事実かもしれませんね。
ゾウ、キリン、ライオン。動物園で一番最後にやってくる動物はどれ?
問題:
動物園に新しい動物たちがやってきました。ゾウさん、キリンさん、ライオンさん。この中で、一番最後にゲートをくぐったのは誰でしょう?
答え:
キリン
解説:
「最後」と「さいご」をかけているわけではありません。答えは「キリン」です。なぜなら、「びりっけつ」だからです。…というのも面白いですが、本当の答えは、体が大きいから一番最後、というわけでもありません。答えは、「しりとり」で考えてみましょう。「ぞう」→「うし」→「しまうま」…と続けていくと、最後に「ん」がつく動物がビリになります。この中だと「キリン」が最後に「ん」がつきますね!
ポスト、信号機、消防車。この中で、仲間はずれはどれ?
問題:
街の中にある、ポスト、信号機、消防車。この3つの中で、一つだけ仲間はずれがあります。それはどれでしょう?
答え:
信号機
解説:
どれも赤い色をしているので、色で考えると仲間はずれは見つかりません。答えは、カタカナに直してみると分かります。「ポスト」と「消防車」はカタカナですが、「信号機」は漢字です。…という考え方もありますが、もっと簡単な答えがあります。それは、「ポスト」と「消防車」は手紙や人を運ぶことがあるけれど、「信号機」は何も運ばないからです。色々な視点で考えてみるのが、このクイズの面白いところです。
【大人向け】解けたらスッキリ!頭をひねる難問引っ掛けクイズ
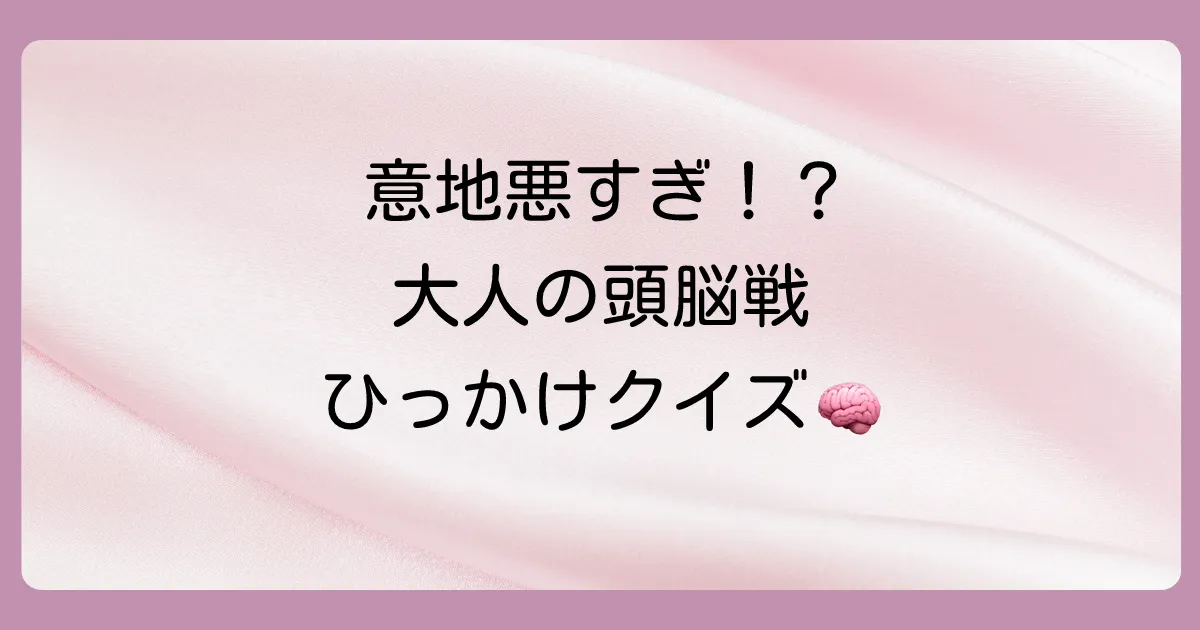
ここからは、大人向けの少し意地悪で頭を使う引っ掛けクイズをご紹介します。常識や固定観念を打ち破らないと、なかなか正解にたどり着けないかもしれません。飲み会や会社のイベントで出題すれば、一目置かれること間違いなし!頭の体操にもなるので、ぜひチャレンジしてみてください。
この章で扱う大人向けクイズの特徴は以下の通りです。
- 常識の裏をかく、ひねりの効いた問題
- 論理的な思考や発想の転換が求められるクイズ
- 解けた時の爽快感がたまらない難問
あるレストランで、殺人事件が起きた。容疑者は4人。ウェイター、コック、パティシエ、客。犯人は誰?
問題:
高級レストランで悲劇が起きた。被害者はナイフで一突き。容疑者は4人。注文を取りに来たウェイター、厨房にいたコック、デザートを作っていたパティシエ、そして食事をしていた客。この中で、犯人は誰だ?
答え:
コック
解説:
なぜコックが犯人なのでしょうか?それは、「クック(Cook)」は「コック」であり、「殺(さつ)」の音読み「さつ」と似ているから…ではありません。もっと単純です。この問題は、ある有名な推理小説のトリックに基づいています。答えは、「犯人はこの中にいない」という可能性を考えることです。しかし、このクイズの答えはもっとシンプルです。答えは、「問題文に犯人がいると書いていない」からです。…というのも意地悪ですね。本当の答えは、「コック(Cook)」は包丁を扱うプロだからです。最も自然に凶器を手にできる人物と言えるでしょう。もちろん、これはあくまでクイズ上の話です。
1年の中で、28日がある月は何回ある?
問題:
1年は12ヶ月。その中で、日数が28日である月は、何回あるでしょうか?
答え:
12回
解説:
「2月!」と即答してしまった人は、見事に引っかかっています。問題は「28日である月」ではなく、「28日がある月」です。1月から12月まで、全ての月に28日は存在しますよね。2月は28日(または29日)までしかありませんが、3月も31日の中に28日が含まれています。言葉のトリックに注意が必要な問題でした。
英語のアルファベットで、最後の文字は何?
問題:
A, B, C, D…と続く英語のアルファベット。では、一番最後の文字は何でしょう?
答え:
T
解説:
「Z」と答えたくなりますが、問題文をよく見てください。「英語のアルファベット(alphabet)」という単語そのものについて尋ねています。「alphabet」というスペルの一番最後の文字は「t」ですね。これも代表的な引っ掛けクイズの一つです。問題文を注意深く読む力が試されます。
ある男性が、超高層ビルの最上階から飛び降りました。しかし、彼は無傷でした。なぜ?
問題:
地上100階建ての超高層ビル。その屋上から一人の男性が意を決して飛び降りました。下は硬いコンクリートです。しかし、驚くべきことに彼はかすり傷一つなく、ぴんぴんしていました。一体なぜそんなことが可能だったのでしょうか?
答え:
ビルの内側(階段など)を飛び降りたから
解説:
「飛び降りる」と聞くと、ビルの外側を想像してしまいますが、問題文には「外へ」とは書かれていません。例えば、最上階の床から一段下の階段へ「飛び降りた」だけかもしれません。これならもちろん無傷ですよね。私たちの思い込み、固定観念がいかに強いかを教えてくれる問題です。
太郎君のお父さんには5人の子供がいます。長男は「一郎」、次男は「二郎」、三男は「三郎」、四男は「四郎」。では、五番目の子供の名前は何でしょう?
問題:
有名なクイズです。太郎君のお父さんには、5人の子供がいます。上から順に、一郎、二郎、三郎、四郎と名付けられました。さて、最後の五番目の子供の名前は何でしょうか?
答え:
太郎
解説:
「五郎!」と答えてしまったあなた、問題文の冒頭をもう一度読んでみてください。「太郎君のお父さんには…」と、主語が誰であるかがはっきりと書かれています。つまり、5人目の子供こそが、この物語の主人公である「太郎君」本人なのです。落ち着いて読めば簡単な問題ですが、リズムに乗って答えると間違えやすい、秀逸なクイズです。
【超難問】IQテスト級!?天才しか解けないいじわる引っ掛けクイズ
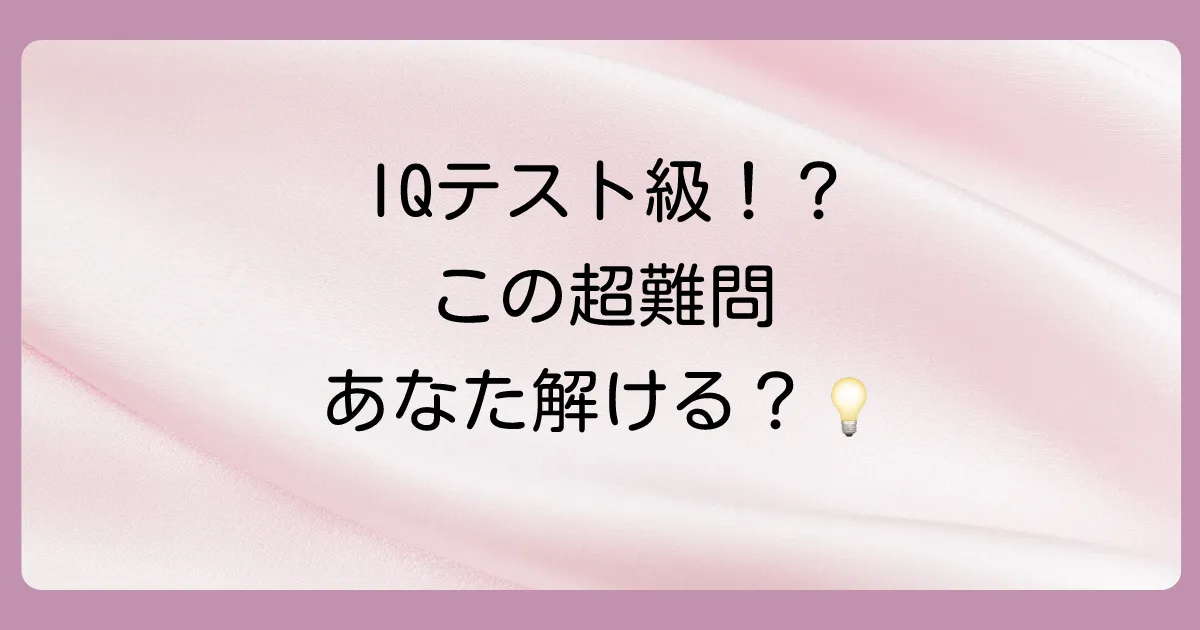
さあ、いよいよ最終ステージです。ここからは、一筋縄ではいかない超難問のいじわる引っ掛けクイズをお届けします。正解できたら、あなたの思考の柔軟性は天才レベルかもしれません。固定観念を全て捨て去り、あらゆる可能性を探ってみてください。友人や同僚にこの問題を出して、頭を悩ませるのも一興です。
超難問クイズに挑戦する上での心構えはこちら。
-
- 問題文の言葉の定義を疑う
- 常識や物理法則から自由になる
–
- 答えを知った時に「ずるい!」と言いたくなるような問題を楽しむ
目の前に、正直者しかいない村への道と、嘘つきしかいない村への道があります。分かれ道には村人が一人。たった一度の質問で、正直者の村への道を知るには、何と聞けばいい?
問題:
あなたは旅の途中。目の前に二つの道が分かれています。一つは天国のような「正直者の村」へ、もう一つは地獄のような「嘘つきの村」へと続いています。分かれ道には、どちらかの村から来た村人が一人だけ立っています。彼が正直者か嘘つきかは分かりません。あなたはたった一度だけ質問をして、正直者の村へ続く道を確実に見つけ出さなければなりません。さて、どんな質問をすれば良いでしょうか?
答え:
「あなたの村はどちらの道ですか?と私が聞いたら、あなたはどちらの道を指差しますか?」と聞く
解説:
これは古典的で非常に有名な論理パズルです。ポイントは、「もし私が〜と聞いたら」という仮定の質問をすることです。
・もし相手が正直者なら、正直に「正直者の村」を指差します。
・もし相手が嘘つきなら、本当は「嘘つきの村」を指差すべきところを、嘘をついて「正直者の村」を指差します。
つまり、どちらの村人であっても、必ず「正直者の村」への道を指し示すことになるのです。この質問をすることで、あなたは確実に正しい道を選ぶことができます。
ある部屋に電球が一つあり、部屋の外にはスイッチが3つあります。どのスイッチがその電球のものか、一度だけ部屋に入って確認する方法は?
問題:
あなたは閉ざされた部屋の外にいます。部屋の中には電球が一つ。あなたの手元には3つのスイッチ(A, B, C)があります。このうちの1つだけが、部屋の電球を点灯させるスイッチです。あなたはスイッチを自由に操作できますが、部屋のドアを開けて中に入れるのは一度きりです。さて、どうすればどのスイッチが正解か見分けられますか?
答え:
1. まずスイッチAをONにして数分待つ。
2. 次にスイッチAをOFFにし、スイッチBをONにする。
3. すぐに部屋に入る。
解説:
部屋に入った時の状況で判断します。
・電球が点灯していれば → 正解はスイッチBです。
・電球が消えているが、触ると温かい → 正解はスイッチAです。(最初にONにして温められたため)
・電球が消えていて、触っても冷たい → 正解はスイッチCです。
このクイズは、光(ON/OFF)だけでなく、「熱」というもう一つの情報を使うことが解決の鍵です。視覚情報だけに囚われない、多角的な思考が試される問題でした。
「私は今、嘘をついている」この発言は、本当?嘘?
問題:
ある人が、あなたに向かってこう言いました。「私は今、嘘をついている」。さて、この人のこの発言は、本当のことでしょうか?それとも嘘でしょうか?
答え:
どちらでもない(パラドックス)
解説:
これは「嘘つきのパラドックス」として知られる、有名な論理的な矛盾です。
・もしこの発言が「本当」だとすると、彼は「嘘をついている」ことになり、発言内容と矛盾します。
・もしこの発言が「嘘」だとすると、彼は「嘘をついていない(=本当のことを言っている)」ことになり、これもまた発言内容と矛盾します。
このように、本当だと仮定しても嘘だと仮定しても矛盾が生じてしまうため、この発言は真偽を決定することができません。答えは「答えられない」が正解という、非常にいじわるな問題です。
引っ掛けクイズで絶対に盛り上がる!出題のコツと注意点
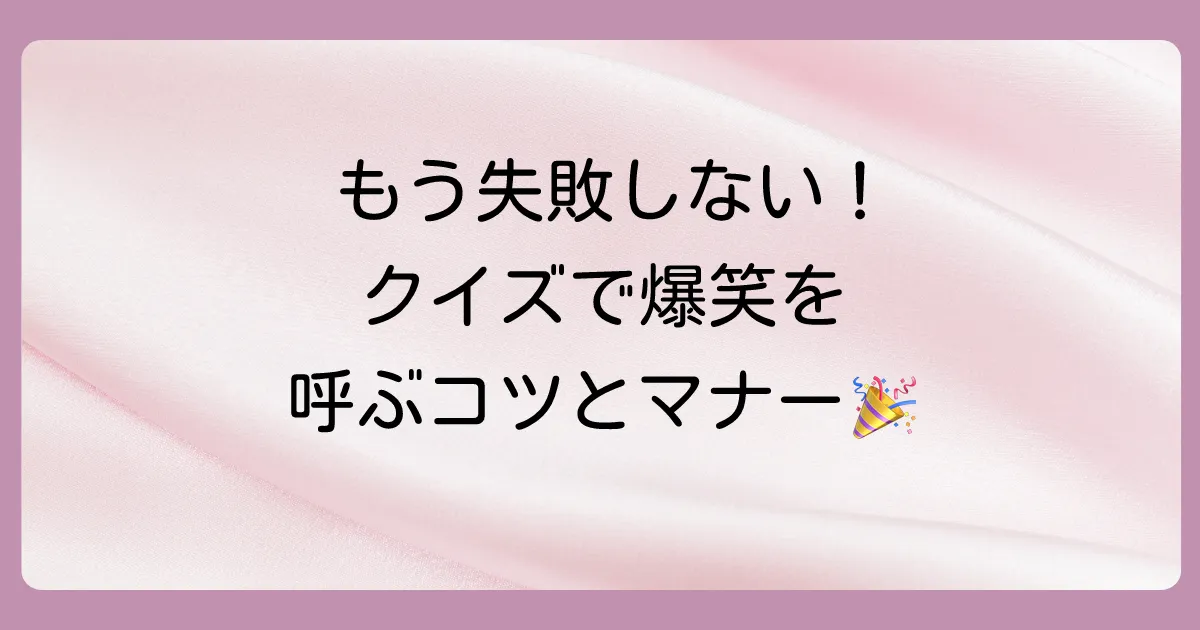
せっかく面白い引っ掛けクイズを用意しても、出し方一つで盛り上がりが半減してしまうこともあります。逆に、ちょっとしたコツを知っているだけで、クイズの面白さを何倍にも引き出すことができます。ここでは、場を最高に盛り上げるための出題のコツと、雰囲気を壊さないための注意点をご紹介します。
出題のコツ:場を最高に盛り上げる方法
クイズマスターになるための、簡単ですぐに使えるコツを3つご紹介します。
1. 絶妙な「間」を使いこなす
問題を出してから答えを言うまでの「間」は、期待感を高めるための重要な演出です。すぐに答えを言わずに、みんなが「うーん…」と悩んでいる様子を楽しみましょう。「本当にそれでいい?」「ファイナルアンサー?」などと問いかけて、焦らすのも効果的です。正解が出たときの「あー!」というスッキリ感を最大限に引き出せます。
2. ヒントの出し方を工夫する
誰も正解できないような難問の場合は、少しずつヒントを出してあげましょう。ただし、直接的なヒントではなく、「視点を変えてみて」「言葉の裏を読んでみて」といった、考え方の方向性を示すヒントがおすすめです。みんなで協力して答えにたどり着く過程も、また楽しいものです。
3. 大げさなリアクションで盛り上げる
正解が出たとき、あるいは面白い間違いが出たときは、出題者が一番楽しそうにリアクションすることが大切です。「おー、すごい!」「惜しい!良い線いってる!」など、大げさなくらいのリアクションで場を盛り上げましょう。あなたの楽しそうな姿が、周りの人にも伝染していきます。
注意点:雰囲気を壊さないための配慮
楽しいはずのクイズで、誰かを嫌な気持ちにさせてしまっては元も子もありません。以下の点に注意して、みんなが楽しめる空間を作りましょう。
1. 相手を馬鹿にしない
引っ掛けクイズは、間違えるのが当たり前です。間違えた人に対して「なんでこんなのも分からないの?」といった態度をとるのは絶対にやめましょう。「良い引っかかりっぷりだね!」「俺も最初は分からなかったよ」など、笑いに変える優しさが大切です。
2. TPOをわきまえる
あまりにも下品なネタや、特定の人が不快に思うような問題は避けましょう。特に、会社の集まりなど公の場では、誰でも笑って楽しめるようなクリーンな問題を選ぶのが無難です。その場の雰囲気やメンバー構成を考えて、適切なクイズを選びましょう。
3. 答えを強要しない
クイズが苦手な人や、考えたくない気分の人もいるかもしれません。無理に答えを強要したり、指名したりするのは避けましょう。あくまで自由参加で、聞いているだけでも楽しめる雰囲気を作ることが、結果的に全体の盛り上がりにつながります。
【FAQ】引っ掛けクイズに関するよくある質問
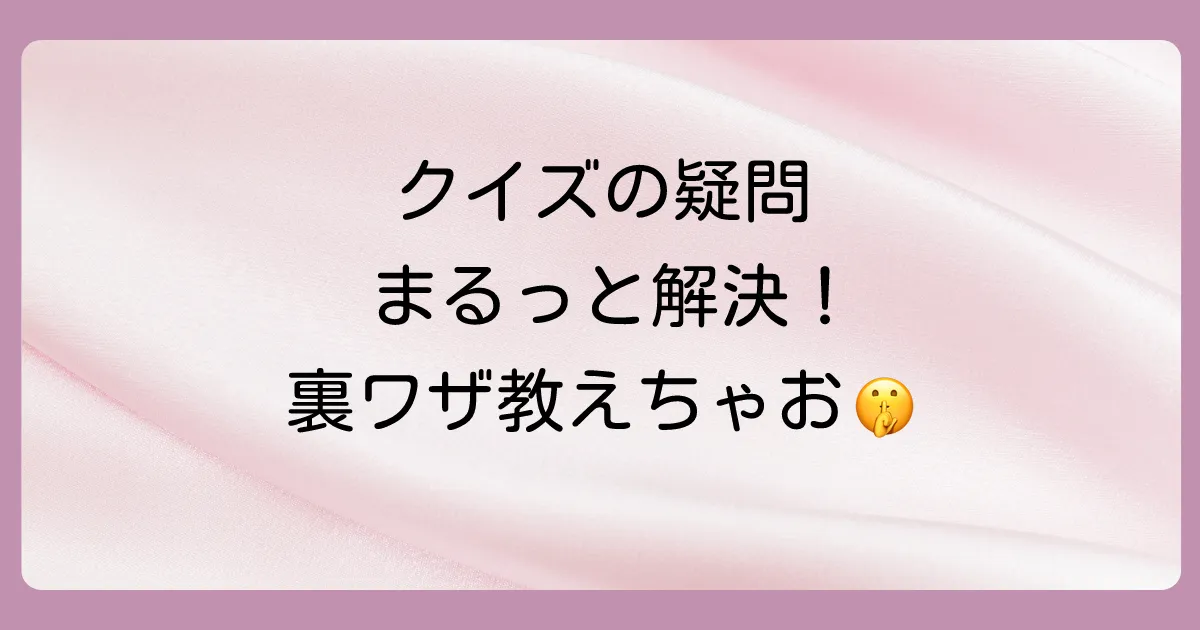
ここでは、引っ掛けクイズに関して多くの人が疑問に思うことをQ&A形式でまとめました。これらの答えを知っておけば、あなたも今日から引っ掛けクイズマスターです!
Q. なぞなぞと引っ掛けクイズの違いは何ですか?
A. なぞなぞと引っ掛けクイズは似ていますが、少し違いがあります。なぞなぞは、主に言葉の同音異義語や多義性を利用して、とんちを効かせた答えを導き出すものです(例:「パンはパンでも食べられないパンは?→フライパン」)。一方、引っ掛けクイズは、問題文の表現や状況設定によって相手の思い込みや勘違いを誘い、意表を突く答えで驚かせることを目的としています(例:「一方通行を逆走しているタクシーの運転手。なぜ捕まらない?→歩いていたから」)。引っ掛けクイズは、より論理的な罠が仕掛けられていることが多いのが特徴です。
Q. 引っ掛けクイズが解けません。コツはありますか?
A. 引っ掛けクイズを解くためのコツは3つあります。1つ目は「問題文を疑うこと」です。一言一句を注意深く読み、「本当にそういう意味か?」「別の解釈はできないか?」と考えてみましょう。2つ目は「固定観念を捨てること」です。「運転手は車に乗っている」「飛び降りるのはビルの外」といった思い込みを捨て、あらゆる可能性を考えてみてください。3つ目は「出題者の意図を読むこと」です。「なぜこの言葉を使ったんだろう?」と、出題者の立場になって考えると、隠された罠が見えてくることがあります。
Q. 10回クイズのようなものはありますか?
A. はい、10回クイズも引っ掛けクイズの代表的な一種です。例えば、「ピザって10回言って」と相手に言わせた後、肘(ひじ)を指差して「ここは?」と聞くと、相手はつられて「ひざ」と答えてしまう、というものです。これは、特定の単語を繰り返すことで脳にその音を刷り込み、似たような音の質問に対して誤答を誘う心理的なテクニックを利用しています。本記事では紹介しきれませんでしたが、検索するとたくさんの10回クイズが見つかりますよ。
Q. 計算系の引っ掛けクイズはありますか?
A. はい、計算を使った引っ掛けクイズもたくさんあります。例えば、「あなたはバスの運転手です。最初、乗客は誰もいませんでした。最初のバス停で5人乗り、次のバス停で3人降りました。さて、運転手の年齢はいくつでしょう?」という問題です。計算に集中させておいて、最後に全く関係のない「運転手の年齢(=あなたの年齢)」を尋ねるというトリックです。他にも、「1=5, 2=10, 3=15, 4=20, では5=?」と聞かれ「25」と答えたくなるが、最初の「1=5」が答えになっている、というパターンもあります。
まとめ
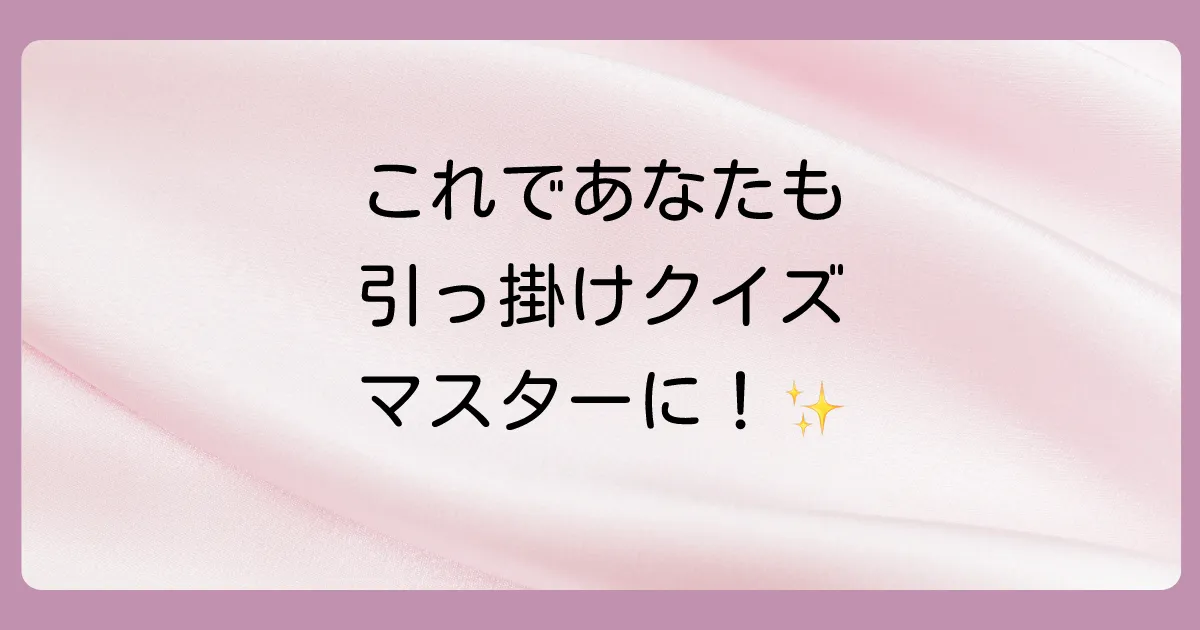
- 引っ掛けクイズはコミュニケーションを円滑にするツールです。
- 子供から大人まで、幅広い世代で楽しむことができます。
- 定番のダジャレ系から、論理的な難問まで種類は様々です。
- 言葉の裏を読んだり、固定観念を捨てたりすることが正解の鍵です。
- 初級編はアイスブレイクに最適です。
- 子供向けクイズは、親子や友達との会話を弾ませます。
- 大人向けの難問は、飲み会やイベントで盛り上がります。
- 超難問は、思考の柔軟性を試すIQテストのようです。
- 出題のコツは「間」「ヒント」「リアクション」です。
- 相手を馬鹿にせず、TPOをわきまえるのが楽しむためのマナーです。
- なぞなぞは「とんち」、引っ掛けクイズは「罠」が特徴です。
- クイズを解くコツは、問題文を疑い、固定観念を捨てることです。
- 10回クイズや計算系クイズも人気のジャンルです。
- 答えを知った時の「なるほど!」という爽快感が醍醐味です。
- この記事を参考に、あなたもクイズマスターを目指しましょう!
新着記事