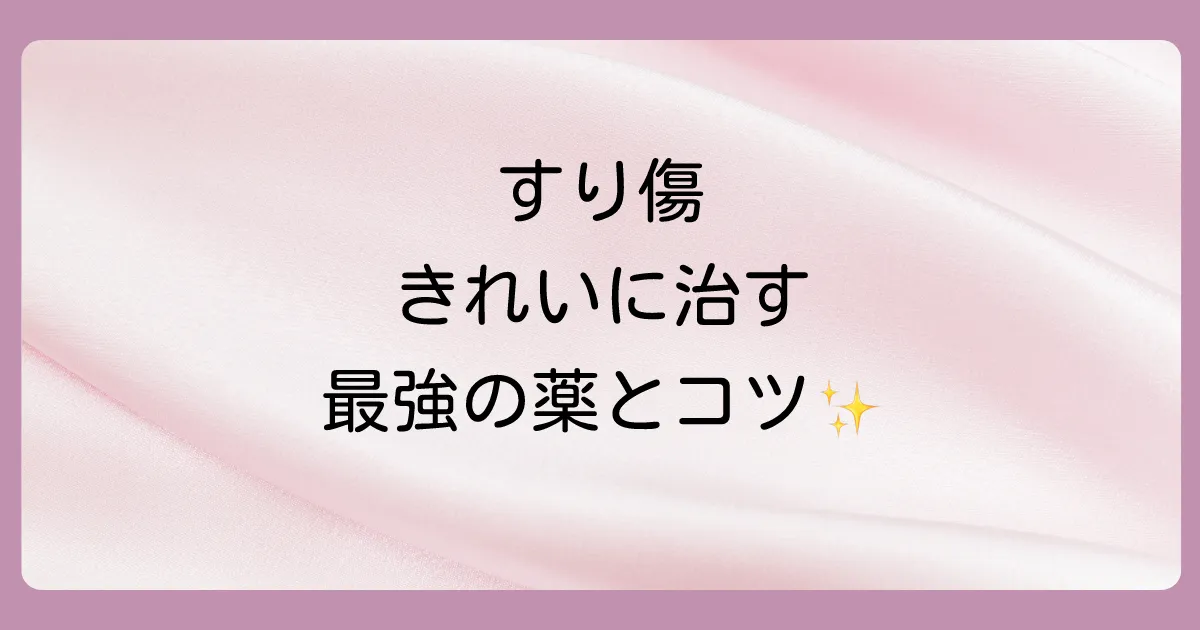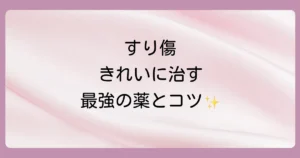うっかり転んでしまったり、何かに擦ってしまったり…日常生活でできてしまう「すり傷」。たいしたことないと思っても、ジンジン痛んだり、跡が残らないか心配になったりしますよね。「どの塗り薬を使えばいいの?」「早くきれいに治すにはどうしたら?」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、すり傷ができたときの正しい処置方法から、症状に合わせた市販の塗り薬の選び方、そして傷跡を残さず治すためのコツまで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、もう薬局の棚の前で迷うことはありません。あなたにぴったりのケア方法を見つけて、すり傷の悩みを解決しましょう。
すり傷の処置、間違ってない?まずやるべき3つのステップ
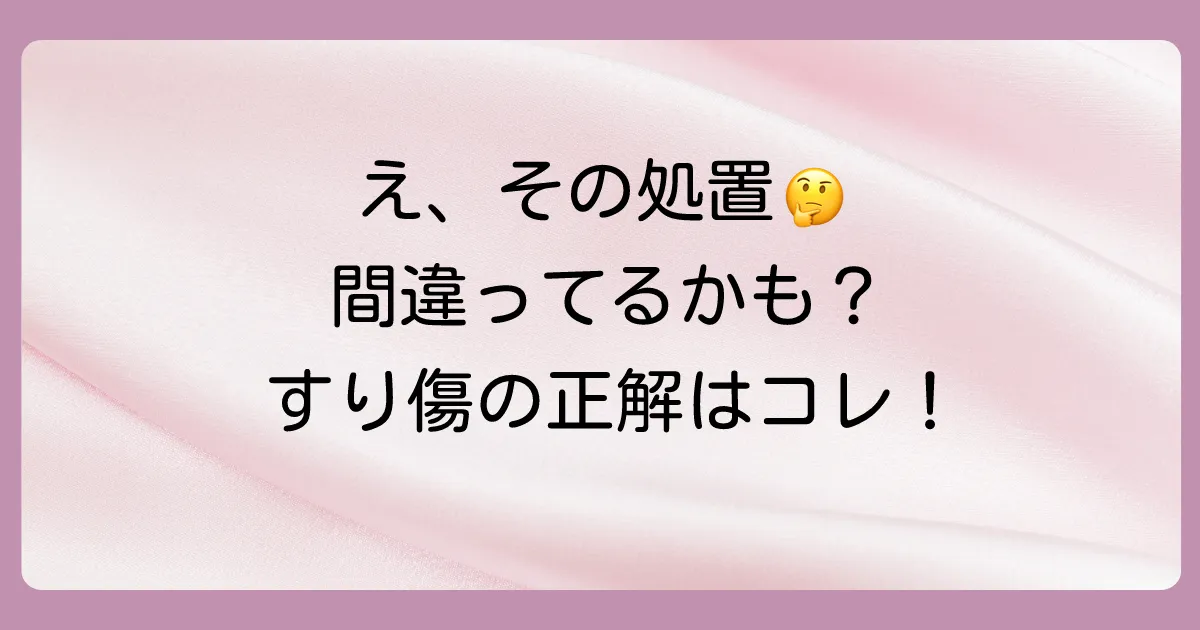
すり傷ができてしまったとき、慌てて塗り薬を探す前に、まずやるべき大切なことがあります。それは、傷口を清潔にすることです。正しい初期対応が、後の治り方や傷跡に大きく影響します。まずは以下の3つのステップを落ち着いて行いましょう。
- ステップ1:まずは流水でしっかり洗浄
- ステップ2:異物を取り除く
- ステップ3:清潔なガーゼで止血・保護
ステップ1:まずは流水でしっかり洗浄
すり傷の処置で最も重要なのが「洗浄」です。転んだときには、目に見えない砂や泥、雑菌などが傷口に付着しています。これらを洗い流さないまま薬を塗ったり絆創膏を貼ったりすると、感染症を引き起こし、化膿する原因になってしまいます。
特別な消毒液は必要ありません。水道の流水で十分です。 傷口に直接水を当て、最低でも1〜2分、できれば3〜5分ほど、しっかりと汚れを洗い流してください。 しみるかもしれませんが、ここで手を抜かないことが、きれいに治すための第一歩です。石鹸をよく泡立てて、傷の周りを優しく洗うのも効果的です。
ステップ2:異物を取り除く
洗浄しても、砂利やガラスの破片、木のとげなどが傷口に残っている場合があります。これらは「外傷性刺青(がいしょうせいしせい)」といって、傷が治った後も黒っぽいシミとして残ってしまう原因になります。 また、感染のリスクも高まります。
ピンセットなどで取り除けるものは丁寧に取り除きましょう。しかし、自分で取り除くのが難しい場合や、深く入り込んでいる場合は、無理をせず医療機関を受診してください。 病院では、麻酔をしてブラシでこするなど、専門的な方法で異物を除去してくれます。
ステップ3:清潔なガーゼで止血・保護
洗浄が終わったら、清潔なガーゼやタオルで傷口を優しく押さえて、じわじわと続く出血を止めます。 ほとんどのすり傷は、数分から十数分圧迫すれば止血できます。 もし、5分以上圧迫しても出血が止まらない場合や、血が勢いよく噴き出すような場合は、速やかに医療機関を受診してください。
血が止まったら、傷口を保護します。このとき、傷口を乾燥させないことがポイントです。かつては「傷は乾かして治す」のが常識でしたが、現在では傷口から出る「滲出液(しんしゅつえき)」という液体を保つ「湿潤療法(モイストヒーリング)」の方が、痛みが少なく、早くきれいに治ることが分かっています。 傷口を保護する絆創膏や被覆材を選びましょう。
【症状で選ぶ】あなたのすり傷に合う塗り薬はこれ!
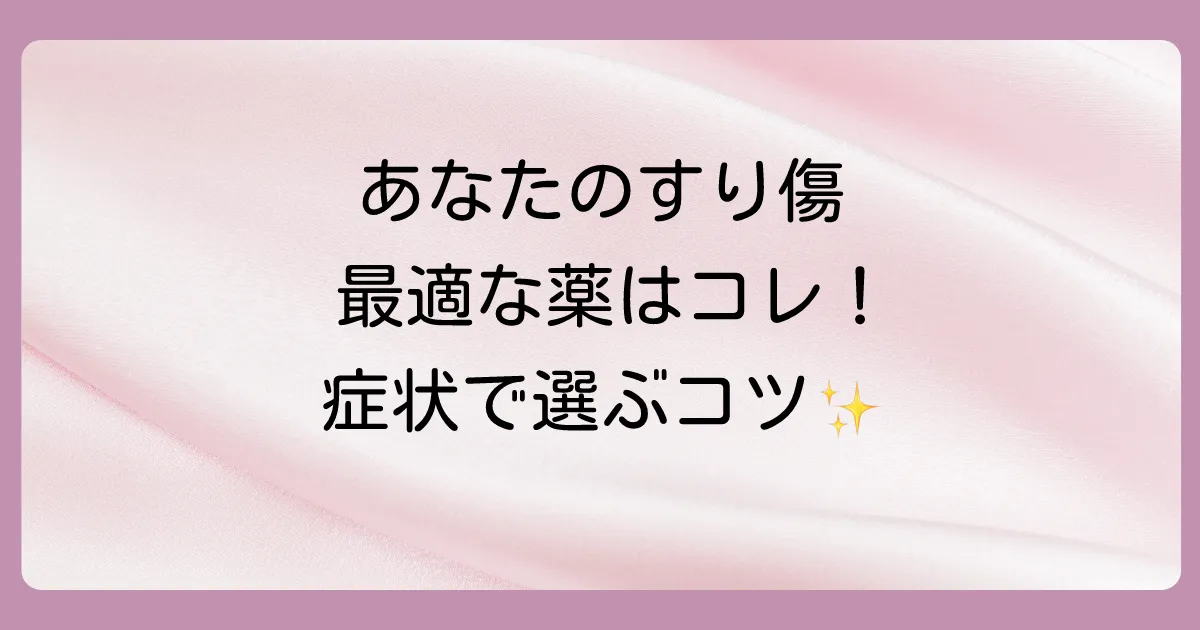
すり傷の初期処置が終わったら、いよいよ塗り薬の出番です。しかし、薬局にはたくさんの種類の塗り薬が並んでいて、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。大切なのは、今のあなたのすり傷の状態に合った薬を選ぶことです。ここでは、症状別に最適な塗り薬の選び方を解説します。
- 【基本】化膿していない軽いすり傷
- 【化膿・じゅくじゅく】感染が心配なすり傷
- 【痛みが強い】ズキズキするすり傷
- 【傷跡を残したくない】きれいに治したい場合
【基本】化膿していない軽いすり傷
傷口が赤くなっている程度で、膿んだり、じゅくじゅくしたりしていない軽いすり傷の場合。この段階では、細菌の感染を防ぐことが最も重要です。選ぶべきは、殺菌・消毒成分が配合された塗り薬です。
代表的な成分には「クロルヘキシジングルコン酸塩」や「ベンゼトニウム塩化物」などがあります。 これらの成分は、傷口の細菌の増殖を抑え、化膿を防ぐ働きをします。 家庭の常備薬としておなじみの「オロナインH軟膏」もこのタイプに含まれます。 まずは基本の殺菌・消毒薬で、傷を清潔に保ちましょう。
【化膿・じゅくじゅく】感染が心配なすり傷
傷の周りが赤く腫れて熱を持っていたり、黄色や緑色の膿が出ていたり、じゅくじゅくとした液体が止まらない場合。これは細菌に感染し、化膿してしまっているサインです。 このような状態には、殺菌・消毒成分だけでは不十分なことがあります。
選ぶべきは、「抗生物質」が配合された塗り薬です。 抗生物質は、細菌そのものを殺したり、増殖を強力に抑えたりする働きがあります。 「コリスチン硫酸塩」「バシトラシン」「フラジオマイシン硫酸塩」などが代表的な成分です。 2種類以上の抗生物質を配合し、より多くの種類の菌に対応できる製品もあります。 化膿してしまった傷には、抗生物質入りの薬でしっかり対応することが大切です。
【痛みが強い】ズキズキするすり傷
すり傷は皮膚の表面にある神経がむき出しになるため、ヒリヒリ、ズキズキとした痛みを伴うことが多いです。 特に、傷ができた直後や、服がこすれるときの痛みはつらいもの。その痛みを少しでも和らげたい場合には、痛み止め成分(局所麻酔成分)が配合された塗り薬がおすすめです。
「ジブカイン塩酸塩」や「リドカイン」といった成分が、傷口の感覚を一時的に麻痺させ、つらい痛みを和らげてくれます。 これらの成分は、殺菌成分や組織修復成分と一緒に配合されていることが多いので、痛みも抑えつつ、傷の治りを助けることができます。痛みに弱い方やお子様には、痛み止め成分入りの薬を選ぶと良いでしょう。
【傷跡を残したくない】きれいに治したい場合
「すり傷の痛みは治まったけど、この跡、残らないかな…」と心配になる方も多いでしょう。傷跡をできるだけ残さずにきれいに治すためには、皮膚の修復を助ける成分に注目しましょう。
「アラントイン」という成分は、新しい皮膚組織の生成を促し、傷の治りを早める効果があります。 また、傷が治った後の色素沈着やケロイド状の盛り上がりを防ぐためには、「ヘパリン類似物質」が配合された製品が有効です。 これは血行を促進し、皮膚のターンオーバーを助けることで、傷跡を目立ちにくくする働きがあります。 傷跡ケアは、傷が完全にふさがってから始めるのが一般的です。焦らず、適切なタイミングでケアを始めましょう。
【目的別】すり傷におすすめの市販塗り薬8選
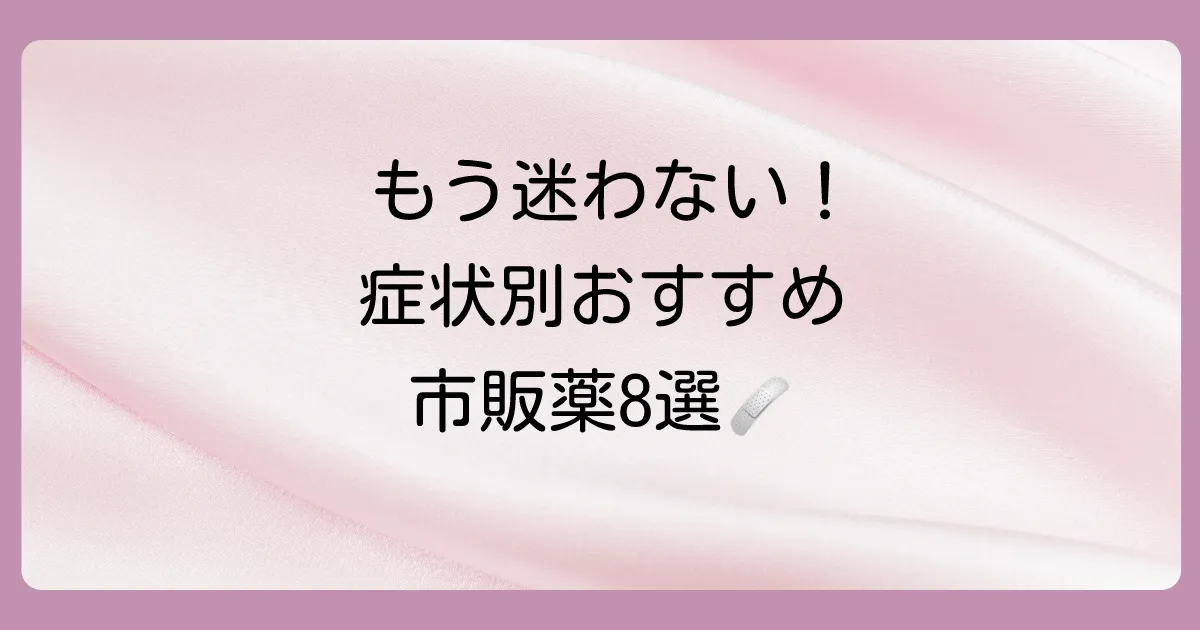
ここからは、ドラッグストアなどで購入できる具体的な市販薬を、目的別に8種類ご紹介します。それぞれの特徴を理解して、ご自身の症状や用途に合ったものを選んでみてください。迷ったときは、薬剤師さんに相談するのも良い方法です。
- 幅広く使える定番薬|オロナインH軟膏
- 化膿した傷に|ドルマイシン軟膏
- 化膿も炎症も抑えたい|クロマイ-P軟膏AS
- 殺菌力が持続する|マキロンs キズ軟膏
- 痛みを和らげたい|メモA
- しみにくく子供にも|キズカイン
- 傷跡ケアに|アットノン
- スプレータイプで手軽に|マキロンs ジェット&スプレー
幅広く使える定番薬|オロナインH軟膏
「オロナインH軟膏」は、多くの家庭で常備されている定番の皮膚疾患・外傷治療薬です。 主成分のクロルヘキシジングルコン酸塩が優れた殺菌効果を発揮し、すり傷や切り傷の化膿を防ぎます。
すり傷だけでなく、にきびや吹出物、軽いやけど、ひび、あかぎれなど、幅広い皮膚トラブルに使えるのが大きな特徴です。 軟膏タイプで患部をしっかり保護します。まずは一つ持っておくと安心な、まさに「家庭の万能薬」と言えるでしょう。ただし、湿疹やかぶれ、化粧下地、虫さされには使用できないので注意が必要です。
化膿した傷に|ドルマイシン軟膏
「ドルマイシン軟膏」は、化膿してしまった傷や、化膿が心配な傷に特に力を発揮する塗り薬です。その秘密は、2種類の抗生物質にあります。グラム陽性菌に有効な「コリスチン硫酸塩」と、グラム陰性・陽性菌に幅広く効く「バシトラシン」を配合。 これにより、多くの細菌による感染を防ぎ、治療します。
じゅくじゅくしてしまった傷や、膿んでしまったおでき(せつ・めんちょう)などにも効果的です。 傷口をしっかり洗浄した後、1日に1〜3回、適量を塗布するか、ガーゼに伸ばして貼ります。 細菌感染が疑われるすり傷には、頼りになる選択肢です。
化膿も炎症も抑えたい|クロマイ-P軟膏AS
「クロマイ-P軟膏AS」は、化膿した患部に使える抗生物質配合の軟膏です。特徴は、2種類の抗生物質(クロラムフェニコール、フラジオマイシン硫酸塩)に加えて、炎症を抑えるステロイド成分(プレドニゾロン)が配合されている点です。
これにより、細菌の増殖を抑えるだけでなく、化膿に伴う赤みや腫れ、痛みといったつらい炎症症状もしっかりと鎮めてくれます。じゅくじゅくしたり、ただれたりして、炎症が強い患部に特に適しています。ただし、ステロイドが含まれているため、漫然と長期間使用することは避け、5〜6日使用しても改善しない場合は医療機関を受診しましょう。
殺菌力が持続する|マキロンs キズ軟膏
液体消毒薬でおなじみの「マキロン」シリーズの軟膏タイプです。「マキロンs キズ軟膏」は、殺菌消毒成分のベンゼトニウム塩化物に加え、組織修復を助けるアラントイン、炎症を抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合しています。
軟膏が傷口を保護し、殺菌効果が持続するのが特徴です。ベタつかず、透明で目立ちにくい軟膏なので、顔や手など人目につきやすい場所のすり傷にも使いやすいでしょう。さわやかなマキロンフレグランスも特徴の一つです。
痛みを和らげたい|メモA
「メモA」は、すり傷のつらい痛みを和らげることに着目した塗り薬です。殺菌成分のクロルヘキシジングルコン酸塩液に加え、局所麻酔成分のジブカイン塩酸塩が配合されており、傷の痛みを素早く鎮めてくれます。
さらに、組織修復成分のアラントインやビタミンEも含まれており、傷の治りを助ける効果も期待できます。 なめらかで伸びの良い軟膏で、すり傷のほか、切り傷や軽いやけどにも使用できます。 痛みに敏感な方や、お子様のすり傷におすすめです。
しみにくく子供にも|キズカイン
「キズカイン」は、デリケートな子どもの肌にも使いやすいように工夫された塗り薬です。殺菌成分のセトリミドに加え、痛みとかゆみをダブルで抑える局所麻酔成分リドカインと抗ヒスタミン成分ジフェンヒドラミンを配合しています。
油性の基剤を使用しているため刺激が少なく、傷口にしみにくいのが特徴です。 傷口を優しく保護しながら、殺菌し、痛みやかゆみを抑えてくれるので、薬を塗るのを嫌がるお子様にも安心して使いやすいでしょう。親子で使える常備薬として便利です。
傷跡ケアに|アットノン
「アットノン」は、すり傷そのものを治す薬ではなく、傷が治った後に残る「傷あと」を目立たなくするための薬です。主成分の「ヘパリン類似物質」が、血行を促進し、皮膚のターンオーバーを促すことで、色素沈着や皮膚のしこりを改善します。
ジェルタイプやクリームタイプ、コンシーラータイプなど、様々な種類があり、部位や傷あとの状態に合わせて選べます。使用するタイミングは、傷が完全に治り、かさぶたなどが取れた後です。傷が治りかけの段階では使用できないので注意しましょう。 きれいな肌を取り戻すための、アフターケアの強い味方です。
スプレータイプで手軽に|マキロンs ジェット&スプレー
「マキロンs ジェット&スプレー」は、軟膏を塗るのが苦手な方や、手を汚さずにケアしたいという場合に便利なスプレータイプの消毒薬です。殺菌消毒成分に加え、組織修復成分と抗炎症成分が配合されています。
この製品のユニークな点は、2つの噴射方法が選べること。傷が砂や泥で汚れている場合は「ジェット」で勢いよく洗浄・消毒し、比較的きれいな傷には「スプレー」で広範囲にやさしく消毒できます。アウトドアなど、すぐに手が洗えない場面でも重宝します。
塗り薬だけじゃない!すり傷を早くきれいに治す「湿潤療法」とは?
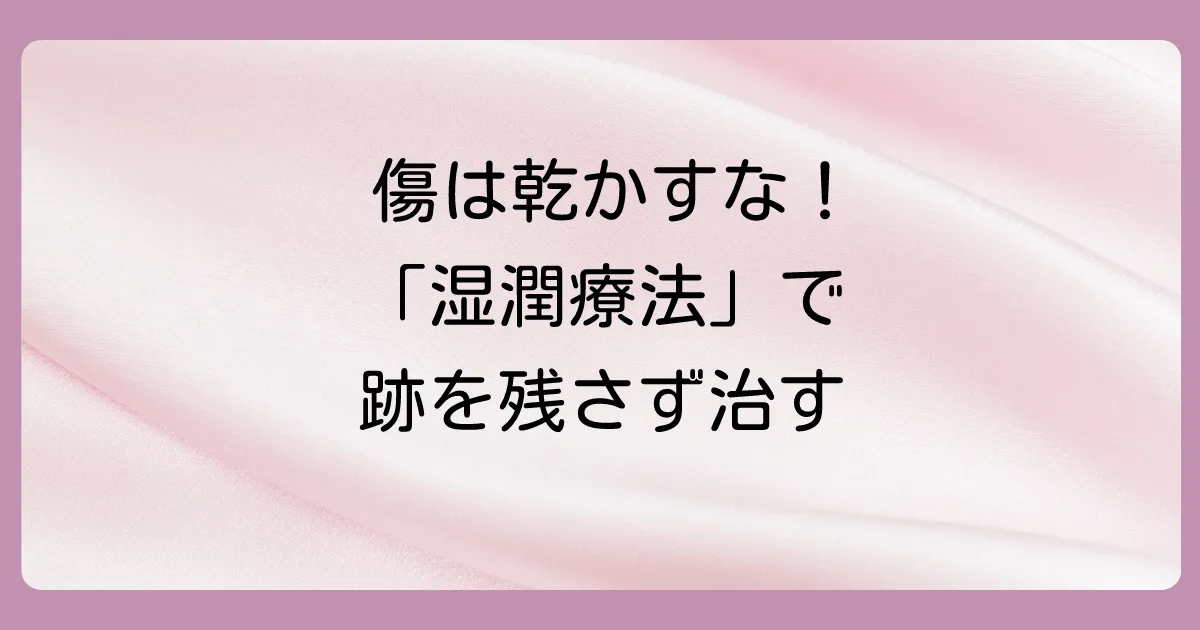
最近、すり傷の治療法として主流になっているのが「湿潤療法(モイストヒーリング)」です。これは、従来の「消毒して乾かす」という方法とは全く逆の発想で、傷口を潤った状態に保つことで、人間が本来持っている自己治癒力を最大限に引き出す治療法です。 ここでは、湿潤療法の仕組みと、塗り薬との使い分けについて解説します。
- 湿潤療法のメリット・デメリット
- 塗り薬と湿潤療法(キズパワーパッドなど)の使い分け
- 湿潤療法を行う際の注意点
湿潤療法のメリット・デメリット
湿潤療法の最大のメリットは、「早く、きれいに、痛みが少なく」治せる点です。 傷口から出る滲出液には、皮膚の細胞を再生させるための成長因子がたくさん含まれています。 この滲出液を乾燥させずに保つことで、細胞の活動が活発になり、治癒が早まります。また、かさぶたを作らないため、傷跡が残りにくく、神経が空気に触れないため痛みも軽減されます。
一方、デメリットとしては、正しい方法で行わないと細菌が繁殖しやすくなる点が挙げられます。 傷口の洗浄が不十分だったり、感染を起こしている傷に使用したりすると、かえって症状を悪化させる可能性があります。また、毎日傷の状態を観察し、適切に被覆材を交換する必要があります。
塗り薬と湿潤療法(キズパワーパッドなど)の使い分け
では、塗り薬と湿潤療法(キズパワーパッド™に代表されるハイドロコロイド素材の絆創膏など)は、どのように使い分ければよいのでしょうか。
まず、キズパワーパッド™などのハイドロコロイド絆創膏を使用する場合、塗り薬や消毒液との併用は基本的にNGです。 軟膏やクリームを塗ると、絆創膏の粘着力が弱まって剥がれやすくなり、湿潤環境をうまく保てなくなってしまいます。
使い分けのポイントは「傷の状態」です。
湿潤療法が向いている傷
- 洗浄してきれいになった、感染の兆候がない軽いすり傷、切り傷
- 滲出液(透明〜少し黄色い液体)が出ている傷
塗り薬が向いている傷
- 砂や泥などで汚れており、感染のリスクが高い傷
- すでに赤く腫れたり、膿が出たりして感染を起こしている傷
- 滲出液がほとんど出ていない、乾き気味の傷
迷った場合は、まず塗り薬で感染を防ぎ、傷の状態が落ち着いてから湿潤療法に切り替えるという方法もあります。
湿潤療法を行う際の注意点
家庭で湿潤療法を行う際には、いくつか重要な注意点があります。まず、傷口の洗浄を徹底すること。これが最も重要です。 異物や細菌が残ったまま密閉すると、中で菌が繁殖し、大変なことになります。
次に、毎日必ず傷を観察すること。 絆創膏を貼りっぱなしにするのではなく、1日に1回は剥がして、傷の周りが赤く腫れていないか、嫌な臭いがしないか、痛みが強くなっていないかなどをチェックしましょう。 もし感染のサインが見られたら、すぐに湿潤療法を中止し、医療機関を受診してください。 また、糖尿病の方や免疫力が低下している方は、感染症のリスクが高いため、自己判断で湿潤療法を行う前に医師に相談することをおすすめします。
こんなすり傷は病院へ!受診の目安
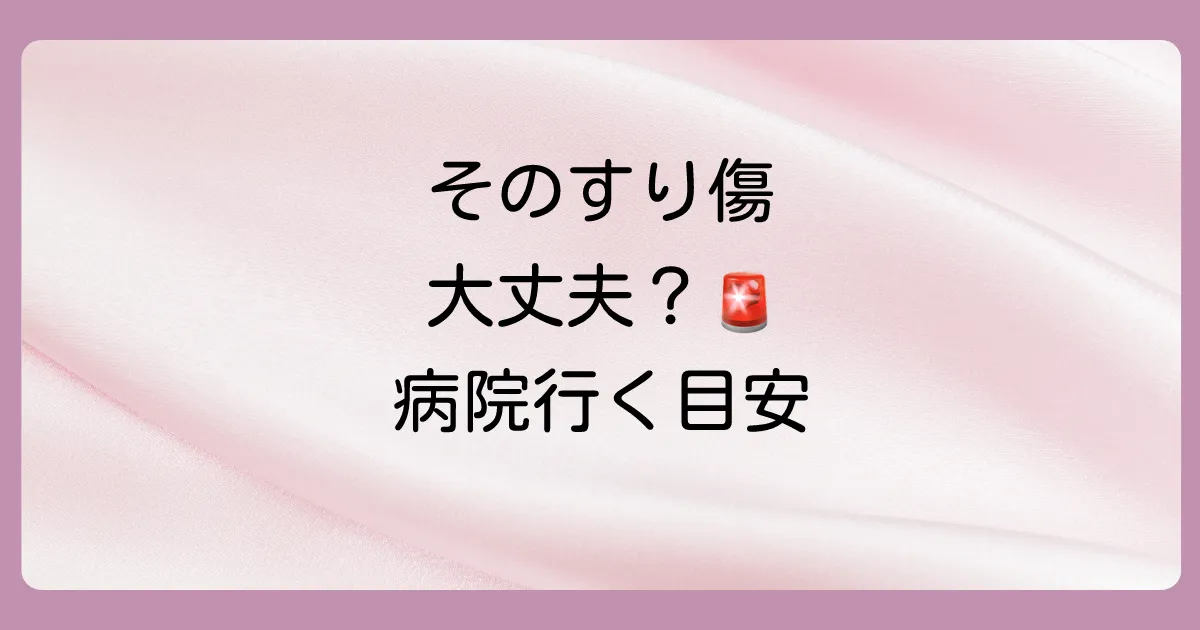
ほとんどのすり傷は家庭でのセルフケアで対応できますが、中には専門的な治療が必要なケースもあります。放置すると、傷跡がひどく残ったり、重い感染症につながったりする危険性も。以下のような場合は、自己判断せずに速やかに医療機関を受診しましょう。 診療科は、皮膚科、形成外科、外科などが適しています。
- 傷が深い・広い・汚い場合
- 出血が止まらない場合
- 動物に噛まれた、錆びたものでケガをした場合
- 数日経っても改善しない、悪化する場合
傷が深い・広い・汚い場合
すり傷といっても、皮膚がえぐれるように深かったり、手のひらサイズ以上に広範囲に及んでいたりする場合は、病院での処置が必要です。 深い傷は真皮や皮下組織まで達している可能性があり、縫合が必要になることもあります。 また、砂やアスファルトなどが傷の奥深くまで入り込んでしまっている場合も、家庭での洗浄だけでは取り除けません。 放置すると感染や「外傷性刺青」の原因になるため、病院でしっかり洗浄してもらう必要があります。
出血が止まらない場合
通常、すり傷からの出血は、清潔なガーゼなどで傷口を5分から10分ほど圧迫すれば止まります。 しかし、圧迫を続けても出血が止まらない場合や、血がにじみ出るのではなく、脈打つように噴き出してくる場合は、太い血管が傷ついている可能性があります。 このような場合は、傷口を圧迫し続けたまま、すぐに救急外来などを受診してください。
動物に噛まれた、錆びたものでケガをした場合
犬や猫などの動物に噛まれたり、引っかかれたりしてできた傷は、見た目は小さくても動物の口の中にいる特殊な細菌に感染するリスクが非常に高いです。また、土の中にいる破傷風菌は、古釘や錆びた金属などでできた傷から体内に侵入します。 破傷風は命に関わることもある恐ろしい感染症です。これらの場合は、傷の深さに関わらず、必ず病院を受診し、適切な洗浄や抗生物質の投与、必要であれば破傷風ワクチンの接種を受けてください。
数日経っても改善しない、悪化する場合
適切な手当てをしているにもかかわらず、2〜3日経っても痛みが引かない、むしろ痛みが強くなる、傷の周りの赤みや腫れが広がる、膿が出る、発熱するといった症状が見られる場合は、傷口で感染が広がっている証拠です。 セルフケアを続けずに、すぐに医療機関を受診してください。適切な抗生物質の内服や点滴が必要になる場合があります。
よくある質問
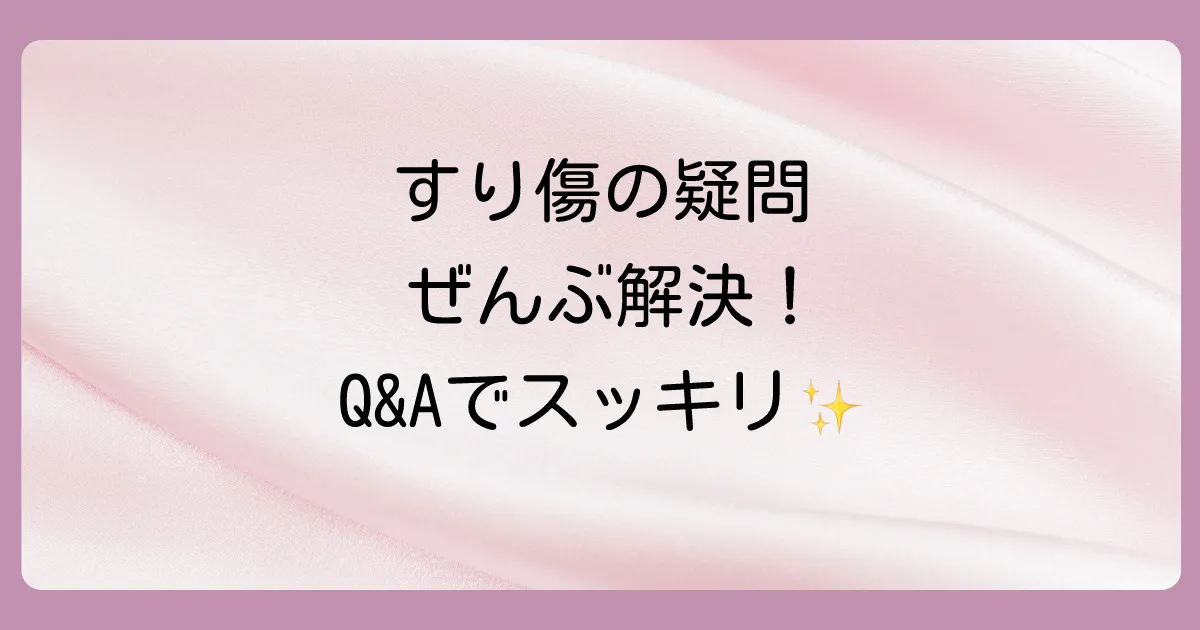
Q. すり傷にオロナインは使ってもいいですか?
はい、使用できます。オロナインH軟膏の主成分は殺菌・消毒作用のあるクロルヘキシジングルコン酸塩で、すり傷や切り傷の化膿を防ぐ効果があります。 ただし、じゅくじゅくと化膿がひどい傷や、深い傷、やけどには適さない場合もあります。 また、湿潤療法を行うためのハイドロコロイド絆創膏(キズパワーパッド™など)との併用は、絆創膏が剥がれやすくなるためできません。
Q. すり傷に塗ってはいけないものはありますか?
基本的に、用途が異なる薬は塗るべきではありません。例えば、虫さされ用の薬や、湿疹用のステロイド軟膏などを自己判断で塗るのはやめましょう。また、アロエや味噌、油といった民間療法も、科学的根拠がなく、かえって傷口を汚して感染のリスクを高めるだけなので絶対にしないでください。傷口はまず清潔な水で洗い、用途に合った塗り薬か被覆材で保護するのが基本です。
Q. 子供や赤ちゃんに使える塗り薬はありますか?
はい、あります。ただし、大人と同じ薬が使えるとは限りません。子供の皮膚は大人よりデリケートなため、刺激の少ない製品を選ぶことが大切です。 例えば、しみにくい油性基剤の軟膏や、痛み止め成分が配合されたものがおすすめです。 製品の添付文書に「小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください」といった記載があるか確認しましょう。年齢制限が設けられている薬もあるため、不明な場合は薬剤師や小児科医に相談するのが最も安全です。
Q. 顔のすり傷には何を使えばいいですか?
顔は特に傷跡が残りやすい場所なので、より慎重なケアが必要です。まず、傷口を丁寧に洗浄することが非常に重要です。塗り薬は、ベタつきが少なく透明で目立ちにくいタイプのものが使いやすいでしょう。抗生物質入りの軟膏で感染をしっかり防ぐことが大切です。また、傷が治った後は、紫外線対策を徹底してください。紫外線は色素沈着の原因となり、傷跡がシミのように残ってしまいます。日焼け止めを塗ったり、UVカット効果のあるテープを貼ったりして保護しましょう。傷の程度によっては、形成外科の受診をおすすめします。
Q. 塗り薬はいつまで、1日に何回塗ればいいですか?
塗る回数や期間は、薬の種類や傷の状態によって異なります。一般的には、1日に1〜数回、傷口を洗浄して清潔にした後に塗布します。 薬の添付文書に記載されている用法・用量を必ず確認してください。 塗るのをやめるタイミングは、傷が乾いて薄い皮が張り、滲出液が出なくなったら一つの目安です。だらだらと長期間塗り続けるのはよくありません。5〜6日使用しても症状が改善しない、または悪化するようであれば、使用を中止して医師や薬剤師に相談しましょう。
Q. すり傷は何日くらいで治りますか?
すり傷の治る期間は、傷の深さや大きさ、処置の方法、年齢、健康状態などによって大きく異なります。浅いすり傷であれば、適切な処置をすれば数日から1週間程度で上皮化(薄い皮が張る状態)します。湿潤療法を行った場合は、乾燥させるよりも治りが早い傾向にあります。 しかし、傷が深かったり、感染を起こしたりすると、治癒までに数週間かかることもあります。傷が治る過程で赤みや盛り上がりが続くこともありますが、これは正常な反応で、半年から1年かけて徐々に白く平らな傷跡に変化していきます。
まとめ
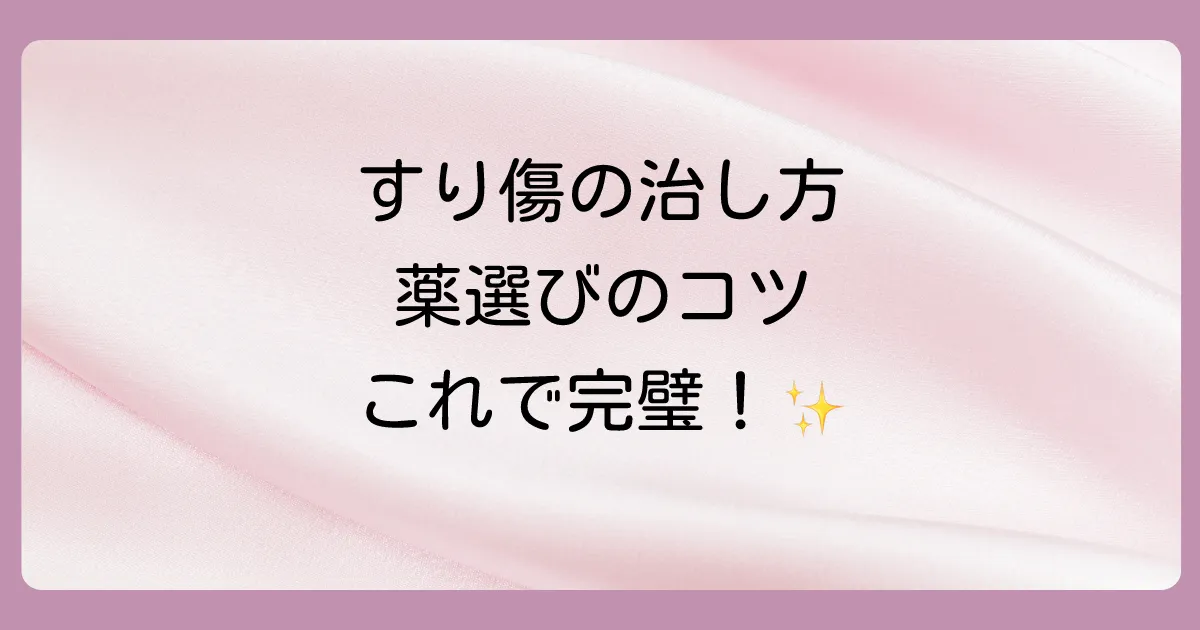
- すり傷ができたらまず流水でしっかり洗浄する。
- 消毒よりも洗浄が重要で、異物を取り除く。
- 軽いすり傷には殺菌・消毒成分入りの薬を選ぶ。
- 化膿した傷には抗生物質入りの塗り薬が効果的。
- 痛みが強い場合は局所麻酔成分入りの薬を選ぶ。
- 傷跡ケアにはヘパリン類似物質などが有効。
- オロナインH軟膏は幅広い用途に使える定番薬。
- ドルマイシン軟膏は化膿した傷に強い。
- 湿潤療法は早くきれいに治すが正しい知識が必要。
- キズパワーパッド™と塗り薬の併用は基本的にNG。
- 傷口の洗浄が不十分だと湿潤療法は逆効果。
- 傷が深い、出血が止まらない場合は病院へ。
- 動物咬傷や錆びたものでの怪我は必ず受診する。
- 数日経っても悪化する場合は感染のサイン。
- 顔の傷は特に丁寧にケアし、紫外線対策を徹底する。
新着記事