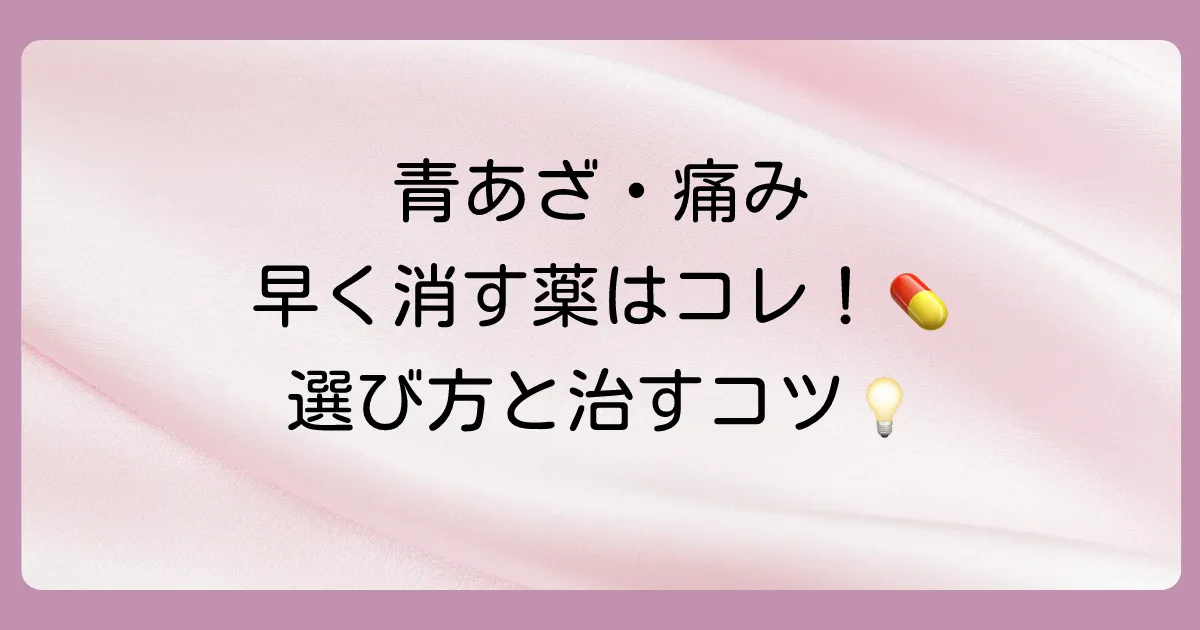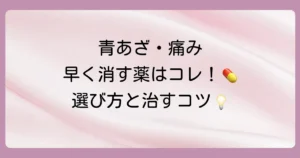「机の角に足をぶつけて、ひどい青あざが…」「転んでできた打ち身が痛くてつらい…」そんな経験はありませんか?日常生活で起こりやすい打ち身は、見た目も気になりますし、ズキズキとした痛みが続くと憂鬱になりますよね。一刻も早く治したいけれど、どの薬を選べばいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、つらい打ち身の症状を和らげるため、症状に合わせた市販の塗り薬の選び方を詳しく解説します。早く治すための応急処置や、病院を受診すべきケースについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
まずはコレ!打ち身におすすめの市販塗り薬【症状別】
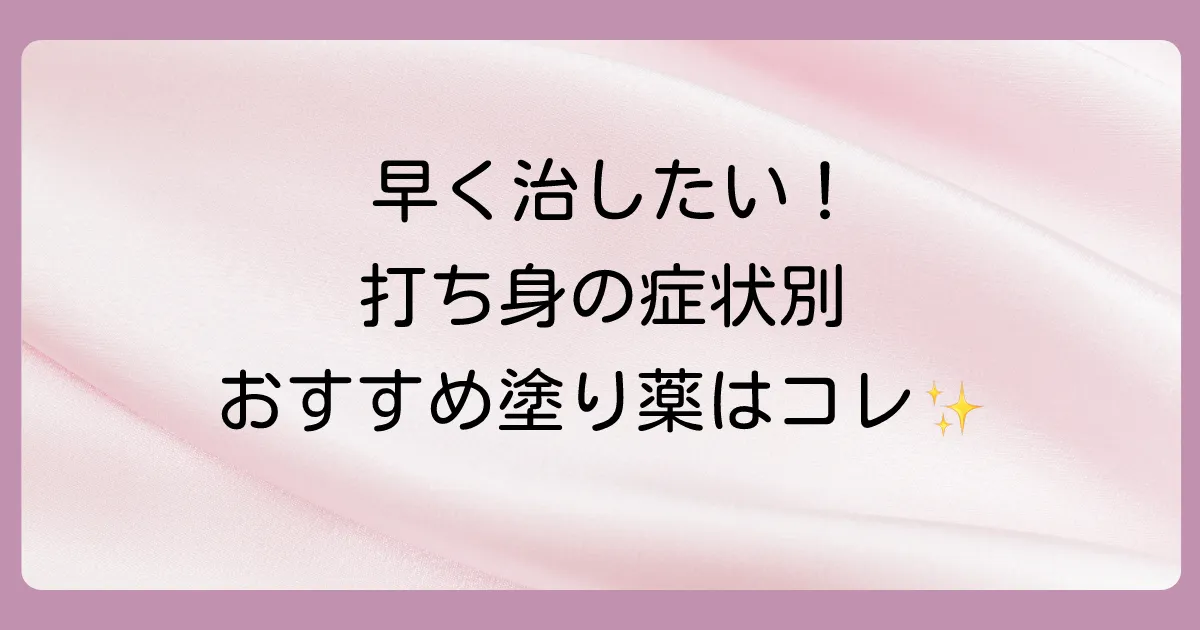
「とにかく早くこの青あざを消したい!」「この痛みをなんとかしたい!」そんなお悩みに合わせて、まずは症状別におすすめの市販塗り薬を紹介します。ドラッグストアなどで手軽に購入できるものを中心に選びましたので、薬選びの参考にしてください。
この章では、以下の3つの症状に合わせた塗り薬を紹介します。
- 【内出血・青あざを早く消したい方へ】ヘパリン類似物質配合の塗り薬
- 【ズキズキする痛みが強い方へ】非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)配合の塗り薬
- 【植物由来成分で優しくケアしたい方へ】アルニカチンキ配合の塗り薬
【内出血・青あざを早く消したい方へ】ヘパリン類似物質配合の塗り薬
打ち身によってできた内出血や青あざを早く治したい方には、「ヘパリン類似物質」が配合された塗り薬がおすすめです。ヘパリン類似物質には、血液が固まるのを防ぎ、血行を促進する作用があります。 これにより、皮膚の下に溜まってしまった血液(内出血)の排出を促し、気になる青あざを早く薄くする効果が期待できます。
また、保湿効果も高いため、乾燥による肌トラブルを防ぎながらケアできるのも嬉しいポイントです。 医療用医薬品としても長年使用されている成分で、小さなお子様からご高齢の方まで、比較的安心して使用できる製品が多いのも特徴です。 代表的な市販薬としては、小林製薬の「アットノン」シリーズや、健栄製薬の「ヒルマイルド」などがあります。 クリームタイプやジェルタイプ、ローションタイプなど様々な剤形があるので、使用する部位や好みの使用感に合わせて選ぶことができます。
【ズキズキする痛みが強い方へ】非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)配合の塗り薬
打ち身の直後で、ズキズキとした強い痛みや熱感を伴う腫れがある場合には、「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」が配合された塗り薬が効果的です。 この成分は、痛みの原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑えることで、優れた鎮痛・抗炎症作用を発揮します。
代表的な成分には、「フェルビナク」「インドメタシン」「ロキソプロフェン」「ジクロフェナクナトリウム」などがあります。これらが配合された市販薬は、「バンテリンコーワ」シリーズや「フェイタス」シリーズ、「ボルタレン」シリーズなど、数多く販売されています。 痛みが特に強い急性期(受傷後2〜3日)に使用するのがおすすめです。ただし、副作用として皮膚のかぶれなどが起こる可能性もあるため、使用上の注意をよく読んでから使用しましょう。
【植物由来成分で優しくケアしたい方へ】アルニカチンキ配合の塗り薬
「化学成分は少し心配…」「肌が弱いから、なるべく優しいものを使いたい」という方には、植物由来の成分である「アルニカチンキ」を配合した塗り薬が選択肢の一つになります。アルニカは、ヨーロッパの山岳地帯に生息するキク科の植物で、古くから打ち身や捻挫の治療に用いられてきました。
アルニカチンキには、炎症を抑え、血行を促進する作用があるとされ、打ち身による痛みや腫れ、内出血を和らげる効果が期待できます。 刺激が少なく、肌に優しい使い心地の製品が多いのが特徴です。市販薬では、サロメチールシリーズなどに配合されていることがあります。 強い痛みや腫れには非ステロイド性抗炎症薬の方が効果は高いですが、軽度の打ち身や、慢性期のケア、肌への優しさを重視したい方におすすめの成分です。
打ち身の塗り薬、どう選ぶ?3つのポイント
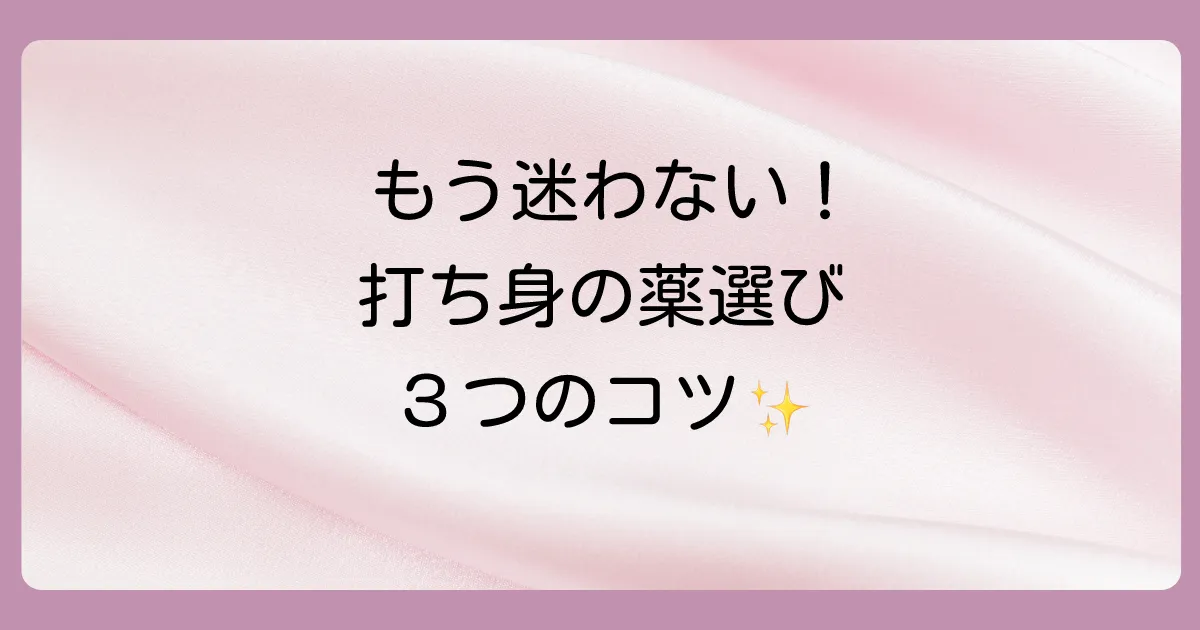
ドラッグストアには様々な種類の打ち身の薬が並んでいて、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。そこで、自分に合った塗り薬を見つけるための3つのポイントを解説します。症状や成分、使い心地に注目して、最適な一品を選びましょう。
この章では、以下の3つのポイントについて詳しく見ていきます。
- ポイント1:症状で選ぶ(痛み、腫れ、内出血)
- ポイント2:成分で選ぶ(ヘパリン、NSAIDsなど)
- ポイント3:剤形で選ぶ(クリーム、ゲル、ローション)
ポイント1:症状で選ぶ(痛み、腫れ、内出血)
まず最も大切なのは、「今のあなたの症状」に合わせて薬を選ぶことです。打ち身の症状は、時間の経過とともに変化していきます。
受傷直後の「急性期」(〜3日程度)は、ズキズキとした強い痛み、熱を伴う腫れが主な症状です。この時期は、炎症を抑えることが最優先。そのため、鎮痛・抗炎症作用に優れた「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」配合の塗り薬が適しています。
少し時間が経った「慢性期」になると、痛みや腫れは和らぎ、青あざ(内出血)が目立つようになります。この段階では、血行を促進して内出血の吸収を早めることが回復への近道です。血行促進作用のある「ヘパリン類似物質」や「アルニカチンキ」などが配合された薬に切り替えるのがおすすめです。 このように、症状のステージに合わせて薬を使い分けることが、効果的なケアのコツです。
ポイント2:成分で選ぶ(ヘパリン、NSAIDsなど)
症状に合わせた薬を選ぶためには、パッケージに記載されている「有効成分」をチェックすることが重要です。前の章でも触れましたが、打ち身の薬の主な有効成分は以下の通りです。
- ヘパリン類似物質: 血行を促進し、内出血(青あざ)を早く治す効果が期待できます。保湿作用もあります。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs): フェルビナク、インドメタシン、ロキソプロフェンなど。強い痛みや腫れを抑える効果が高いです。
- アルニカチンキ: 植物由来の成分で、穏やかな抗炎症作用と血行促進作用があります。肌への刺激が少ないのが特徴です。
- サリチル酸グリコールなど: 湿布薬などにもよく使われる消炎鎮痛成分です。比較的マイルドな作用で、子供でも使える製品があります。
これらの成分の特徴を理解し、自分の症状や体質(肌の弱さなど)に合ったものを選びましょう。迷ったときは、薬剤師さんに相談するのも良い方法です。
ポイント3:剤形で選ぶ(クリーム、ゲル、ローション)
塗り薬には、様々な「剤形(テクスチャー)」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。使用する部位やシーン、好みの使用感に合わせて選ぶと、より快適にケアを続けることができます。
- クリーム: しっとりとした使用感で、保湿力が高いのが特徴です。皮膚を保護する効果も期待でき、乾燥しやすい部位に適しています。ただし、少しべたつきを感じることもあります。
- ゲル(ジェル): 透明で速乾性があり、サラッとした使用感が特徴です。 べたつきが少ないため、服に付きにくく、日中の使用にも向いています。広範囲に塗り広げやすいのもメリットです。
- ローション: 液体状で伸びが良く、毛が生えている部位や広範囲にも塗りやすいです。清涼感のある使い心地のものが多いですが、クリームやゲルに比べて保湿力はやや劣る傾向があります。
- スプレー: 手を汚さずに広範囲に塗布できる手軽さが魅力です。背中など、手の届きにくい部位にも使いやすいでしょう。
例えば、関節などのよく動かす部位には密着しやすいクリーム、夏場や日中の使用にはサラッとしたゲル、といったように使い分けるのがおすすめです。
打ち身を1日でも早く治す!塗り薬の効果的な使い方と応急処置
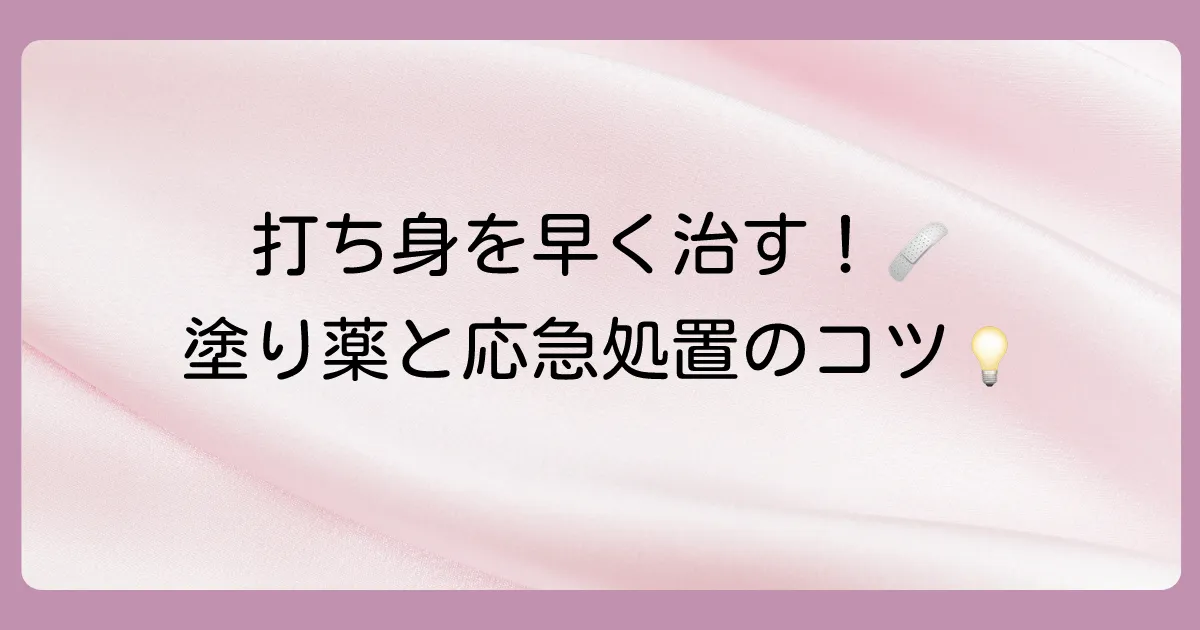
せっかく良い薬を選んでも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。ここでは、塗り薬の効果を最大限に引き出すための使い方と、打ち身を悪化させずに早く治すための応急処置「RICE処置」について解説します。正しい知識で、つらい打ち身を1日でも早く回復させましょう。
この章では、以下のポイントを詳しく解説します。
- 塗り薬を塗るタイミングと回数
- 塗る前に実践!RICE処置で悪化を防ぐ
- 慢性期(温める時期)のケア
塗り薬を塗るタイミングと回数
塗り薬の効果をしっかり得るためには、用法・用量を守ることが基本です。製品のパッケージや説明書に記載されている回数と量を必ず確認しましょう。一般的には、1日数回、患部に適量を塗擦(すりこむ)または塗布(のばしてつける)します。
塗るタイミングとしておすすめなのは、入浴後です。皮膚が清潔で温まっているため、血行が良くなり、薬の成分が浸透しやすくなります。塗る際は、ゴシゴシと強くこすりつけるのではなく、優しくマッサージするように塗り込むのがコツです。特に内出血がひどい場合は、強く刺激するとかえって悪化させてしまう可能性があるので注意しましょう。清潔な手で、患部とその周辺に少し広めに塗るのが効果的です。
塗る前に実践!RICE処置で悪化を防ぐ
打ち身をした直後は、塗り薬を塗る前に「RICE(ライス)処置」という応急処置を行うことが非常に重要です。 これを行うかどうかで、その後の治りの速さが大きく変わってきます。RICEとは、4つの処置の頭文字をとったものです。
- Rest(安静): 患部を動かさず、安静にします。無理に動かすと内出血や腫れが悪化します。
- Ice(冷却): 氷のうや保冷剤などをタオルで包み、患部を冷やします。1回15〜20分程度を目安に、感覚がなくなったら一度中断し、また冷やすというのを繰り返します。冷やすことで血管が収縮し、内出血や腫れ、痛みを抑えることができます。
- Compression(圧迫): 弾性包帯やテーピングなどで患部を軽く圧迫し、固定します。これにより、内出血や腫れが広がるのを防ぎます。 きつく締めすぎると血行障害を起こすので注意が必要です。
- Elevation(挙上): 患部を心臓より高い位置に保ちます。腕や足の打ち身の場合、クッションや台の上に置くと良いでしょう。重力を利用して、腫れを軽減させる効果があります。
このRICE処置は、受傷後すぐに行い、24〜72時間程度続けるのが理想的です。
慢性期(温める時期)のケア
受傷後2〜3日が過ぎ、痛みや熱感、腫れが引いてきたら、ケアの方法を「冷やす」から「温める」に切り替えます。この時期を「慢性期」と呼びます。慢性期には、患部を温めて血行を促進することで、残った内出血の吸収を促し、硬くなった筋肉をほぐして回復を早めることができます。
具体的な方法としては、蒸しタオルやカイロを当てたり、ぬるめのお湯でゆっくり入浴したりするのが効果的です。このタイミングで、ヘパリン類似物質など血行促進作用のある塗り薬を使い、優しくマッサージするのも良いでしょう。ただし、まだ痛みが強い場合や、温めてみて痛みがぶり返すような場合は、まだ炎症が残っている可能性があるので、温めるのは中止し、もう少し冷却を続けてください。自分の体の反応を見ながら、慎重に進めることが大切です。
【注意】こんな打ち身は病院へ!受診の目安
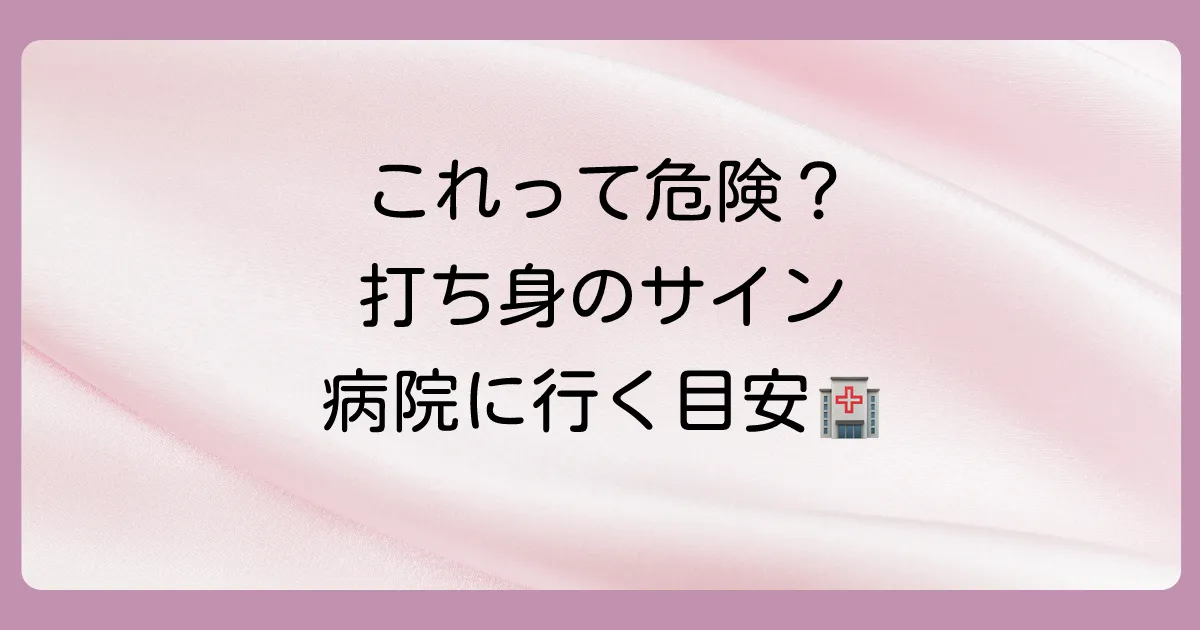
ほとんどの打ち身は市販薬やセルフケアで自然に治りますが、中には骨折など、より深刻な怪我を伴っている場合もあります。 放置すると後遺症が残る可能性もあるため、注意が必要です。ここでは、セルフケアで様子を見ずに、すぐに病院を受診すべき症状の目安と、何科に行けばよいのかを解説します。
この章では、以下の2つのポイントを解説します。
- 病院に行くべき症状リスト
- 何科を受診すればいい?
病院に行くべき症状リスト
「ただの打ち身」と自己判断せず、以下のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- 激しい痛みや腫れが続く: 時間が経っても痛みが全く引かない、またはどんどん強くなる。
- 患部が変形している: 明らかに形がおかしい、関節が普段曲がらない方向に曲がっている。
- 全く動かせない、体重をかけられない: 激痛で腕や足を動かせない、または足に体重をかけると激痛が走る。
- しびれや麻痺がある: 患部やその先の感覚がない、ピリピリとしたしびれが続く。
- 頭部や腹部を強く打った: 意識がもうろうとする、吐き気や嘔吐がある、記憶が曖昧などの症状がある場合は特に危険です。
- 数週間経っても症状が改善しない: 適切なケアをしても、腫れや痛みが全く引かない。
これらの症状は、骨折や脱臼、靭帯損傷、あるいは内臓損傷など、重篤な状態が隠れているサインかもしれません。 迷ったら、まずは専門医に相談することが大切です。
何科を受診すればいい?
打ち身で病院に行く場合、どの診療科を受診すればよいか迷うかもしれません。症状や打った場所によって適切な診療科は異なります。
- 腕、足、肩、腰などの打ち身: 基本的には「整形外科」を受診します。 骨や関節、筋肉の専門家が、レントゲン検査などで骨折の有無などを正確に診断してくれます。
- 頭を強く打った場合: 意識障害、めまい、吐き気などがある場合は、「脳神経外科」を受診してください。 見た目に異常がなくても、頭蓋内で出血している可能性があります。
- 顔面の打ち身: 目や鼻、歯などを強く打った場合は、それぞれの専門科(眼科、耳鼻咽喉科、歯科・口腔外科)の受診も検討しましょう。まずは整形外科で骨の異常がないか診てもらうのが一般的です。
- 胸やお腹を強く打った場合: 呼吸が苦しい、腹痛がひどいなどの症状があれば、内臓損傷の可能性があるため、救急外来や「外科」を受診する必要があります。
どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけ医に相談するか、総合病院の受付で症状を伝えて案内してもらうとよいでしょう。
打ち身の塗り薬に関するよくある質問
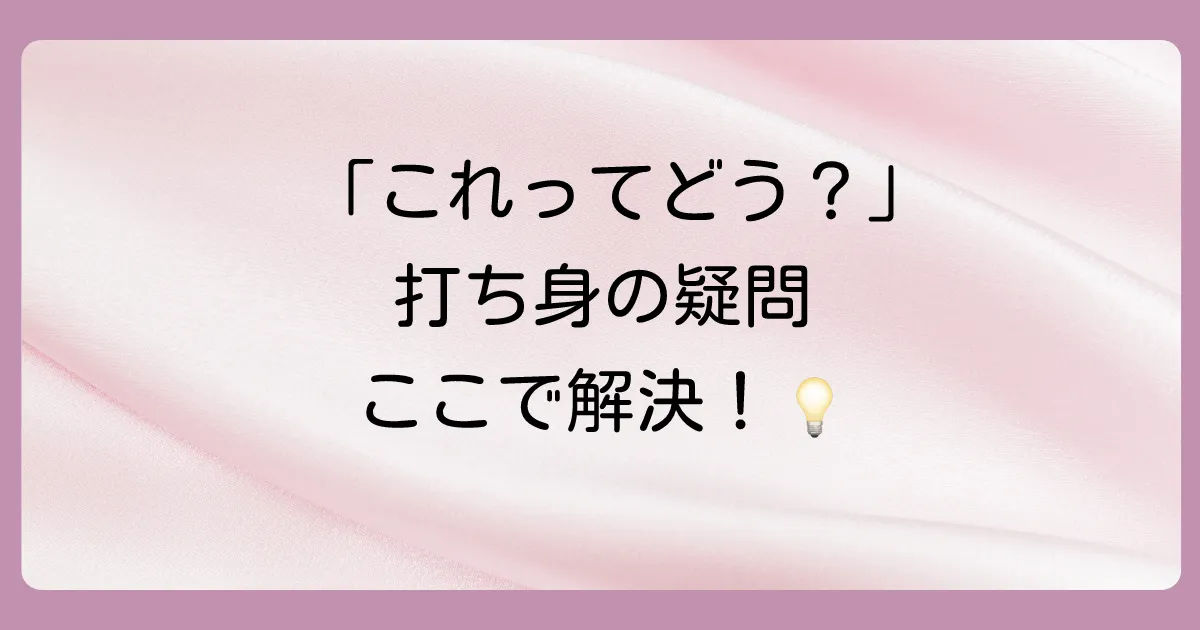
子供に使える打ち身の塗り薬はありますか?
はい、子供に使える打ち身の塗り薬もあります。ただし、大人用の薬を自己判断で使うのは避けるべきです。特に、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の中には、子供への使用が推奨されていない成分や年齢制限があるものがあります。
子供のデリケートな肌には、ヘパリン類似物質や、アルニカチンキ、サリチル酸グリコールなどが配合された、比較的刺激の少ない製品がおすすめです。 製品によっては年齢制限がないものもありますが、使用前には必ずパッケージの注意書きを確認し、対象年齢を守って使用してください。 心配な場合は、購入前に薬剤師や登録販売者に相談するか、小児科を受診して適切な薬を処方してもらうのが最も安全です。
顔にできた打ち身に薬を塗っても大丈夫ですか?
顔の皮膚は他の部位に比べて薄くデリケートなため、薬の使用には注意が必要です。特に目の周りや粘膜への使用は避けるべきとされている薬が多いです。
顔への使用を考える場合は、まず製品の添付文書で「顔面への使用」が可能かどうかを確認してください。「顔面を除く」と記載されている製品は使用できません。 比較的、ヘパリン類似物質を主成分とする製品は顔にも使えるものが多いですが、こちらも必ず確認が必要です。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は刺激が強い場合があるため、顔への使用は慎重になるべきです。自己判断が難しい場合は、皮膚科や整形外科を受診して相談することをおすすめします。
塗り薬と湿布、どちらが良いですか?
塗り薬と湿布は、どちらも打ち身の痛みを和らげるのに有効ですが、それぞれに特徴があります。どちらが良いかは、症状や使用する部位、生活スタイルによって異なります。
塗り薬は、関節などの凹凸があって湿布が貼りにくい場所や、広範囲に塗りたい場合に便利です。 また、肌がかぶれやすい人にとっては、湿布よりも刺激が少ない場合があります。剤形(クリーム、ゲルなど)を選べるのもメリットです。
一方、湿布は、有効成分が長時間にわたって皮膚から吸収され続けるため、持続的な効果が期待できます。 また、患部を保護し、衣類などで薬が擦れて落ちてしまうのを防ぐ効果もあります。急性期には冷湿布、慢性期には温湿布と、温度によるケアを同時に行えるのも特徴です。
結論として、動きの多い関節には塗り薬、平らな面で持続的な効果を期待したい場合は湿布など、状況に応じて使い分けるのが賢い方法と言えるでしょう。
打ち身の跡を残さないためにはどうすればいいですか?
打ち身の跡、特に色素沈着を残さないためには、初期対応と根気強いケアが重要です。
- 初期の徹底した冷却: 受傷直後にRICE処置をしっかり行い、内出血を最小限に抑えることが最も重要です。
- 血行促進ケア: 炎症が治まったら、ヘパリン類似物質配合の薬などで血行を促進し、内出血の吸収を早めましょう。 温めたり、優しくマッサージしたりするのも効果的です。
- 紫外線対策: 打ち身の跡は、紫外線によって色素沈着を起こしやすくなります。患部が治りかけの時期は、衣服で覆ったり、日焼け止めを塗ったりして、紫外線から肌を守りましょう。
- バランスの取れた食事: 皮膚のターンオーバーを助けるビタミンCやビタミンE、タンパク質などを意識的に摂取することも、きれいな肌の再生につながります。
これらのケアを続けることで、跡が残るリスクを減らすことができます。
まとめ
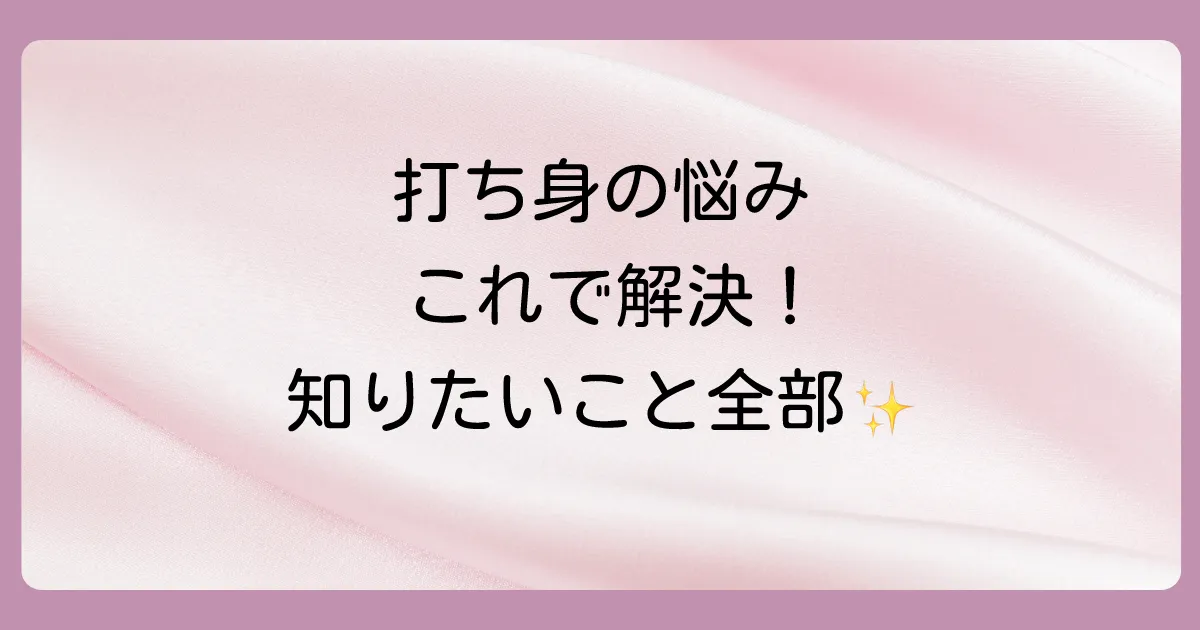
- 打ち身の薬は症状に合わせて選ぶことが重要です。
- 内出血には「ヘパリン類似物質」がおすすめです。
- 強い痛みには「非ステロイド性抗炎症薬」が効果的です。
- 肌が弱い方は「アルニカチンキ」配合も選択肢になります。
- 薬選びは「症状」「成分」「剤形」の3点がポイントです。
- 急性期は冷やし、慢性期は温めるのが基本のケアです。
- 受傷直後の「RICE処置」が治りを早くします。
- 塗り薬は入浴後に塗ると浸透しやすくなります。
- 激しい痛みや変形がある場合はすぐに病院へ行きましょう。
- 頭や腹部を打った際は特に注意が必要です。
- 受診する科は整形外科が基本ですが、部位によります。
- 子供や顔への使用は、専用の薬か医師の指示に従いましょう。
- 塗り薬と湿布は部位や状況で使い分けるのがおすすめです。
- 打ち身の跡を防ぐには、初期対応と紫外線対策が大切です。
- 迷ったときは薬剤師や医師に相談しましょう。